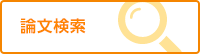論文記事
|
第65巻第4号 2018年4月 静岡県が設定する健康づくりの新三要素(運動・栄養・社会参加)
久保田 晃生(クボタ アキオ) 岡本 尚己(オカモト ナオキ) 野中 佑紀(ノナカ ユウキ) |
目的 運動と栄養の指導に加え,社会参加の指導および実践の場面を意図的に取り入れた教室を考案し,健康づくり,介護予防関連の評価指標への効果を介入研究で検証した。
方法 非無作為割付による並行群間比較試験である。静岡県下田市の65歳以上の高齢者で,地域包括支援センターの協力で研究参加者を募り,介入群21人(76.2±4.7歳),対照群24人(78.0±4.7歳)で実施した。介入群には運動,栄養,社会参加を取り入れた教室(以下,教室)を実施した。全14回で1・14回目は,効果を評価する測定会を行った。測定会では運動面(5m最大歩行時間,開眼片足立ち,握力,下肢筋力,Timed Up & Go,運動自己チェック),栄養面(食生活自己チェック),社会参加面(社会関連性指標,社会参加自己チェック)を測定した。2回目から13回目は,運動は毎回,栄養と社会参加は隔週で指導および実践を取り入れた。なお,運動は,自体重を用いた筋力トレーニングや体操を実施した。栄養は,塩分摂取に重点を置き指導した。社会参加は,社会参加活動の情報提供と,グループ活動を行った。グループは,3~4人程度で3つの課題(ウォーキングマップの作成,健康づくり・介護予防のチラシづくり,グループ体操の作成)に取り組んだ。対照群は,介入群の測定会のみ同様に行った。介入効果の検証は,時点と群の2要因による反復測定の分散分析を実施し,2要因間の交互作用を検討した。また,対応のあるt検定で群内比較を施した。
結果 介入群では運動面の開眼片足立ち,Timed Up & Go,栄養面の食生活自己チェック,社会参加面の社会参加自己チェックで,群内の有意差(p<0.05)が認められた。一方,対照群では,運動面の開眼片足立ち,Timed Up & Goで,群内の有意差(p<0.05)が認められた。いずれも好ましい変化を示した。2要因による反復測定の分散分析を実施したが有意な交互作用は認められなかった。
結論 本研究は社会参加を強調した新たな健康づくり教室であったが,実施上の課題も多く,交互作用は認められず介入効果を強く支持できないこともあり,評価指標や内容の改善が必要である。
キーワード 運動,栄養,社会参加,健康づくり教室
|
第65巻第4号 2018年4月 ホームヘルパーの自己成長感に関連する要因-個別ケアの実践度に焦点をあてて-広瀬 美千代(ヒロセ ミチヨ) |
目的 在宅介護においてホームヘルパーは,非常にストレスフルな状況にあるといえるが,ネガティブな状況下においても学びや成長を感じる等の肯定的な側面を見いだせているかといった価値的側面を探求することが求められる。本研究においては,ホームヘルパーの自己成長感に関する要因を適切なアセスメントと突発的な支援ができるという個別ケアに焦点をあてて検討することを目的とした。
方法 A県内の訪問介護事業所から無作為抽出した,600名を対象とする自記式郵送調査を行った。調査票の有効回収数は149通,有効回収率は24.8%となった。質問項目は「自己成長感」,性別,年齢,ヘルパー経験年数,仕事継続意識,および「新たな気づきと突発的支援」であった。統計分析においては「自己成長感」について,「新たな気づきと突発的支援」を潜在変数とする1因子モデルを設定し,確証的因子分析を行った。また,構造方程式モデルを用いて適合度と各変数間の関連性を確認した。
結果 欠損値のない131人のデータを用いて,「自己成長感」3項目および「新たな気づきと突発的支援」7項目による1因子モデルを設定し,構造方程式モデリングを用いて確証的因子分析を実施した結果,統計学的な水準を満たし,構成概念妥当性が支持された。また,「新たな気づきと突発的支援」が「自己成長感」を規定するとした因果関係モデルのデータに対する適合度は,χ2(df)=73.863(72),RMSEA=0.014,CFI=0.999と統計学的な許容水準を満たしていた。また,尺度のCronbachのα係数は,すべての因子において0.870以上を示した。さらにヘルパーの経験年数と「新たな気づきと突発的支援」,仕事継続意識と「自己成長感」の間には,有意な関連が確認された。
結論 本研究におけるホームヘルパーの「自己成長感」は,信頼性と構成概念妥当性が得られたことから尺度として使用可能であると判断した。また,「新たな気づきと突発的支援」は「自己成長感」と関連がみられた。本研究結果から,ヘルパーとしての経験を積み,様々な気づきを通じて突発的な対処能力が高まることで個別ケアが可能となると,学びや成長を自覚していく可能性があることが示唆された。今後の課題としては因果関係の明瞭さを高めるため,質問項目を吟味し,調査対象者を拡大して実施することが求められる。
キーワード ホームヘルパー,自己成長感,個別ケア,ヘルパー経験年数,仕事継続意識,構造方程式モデリング
|
第65巻第3号 2018年3月 障害福祉制度へのつながりにくさに関する一考察-北海道内ホームレス支援施設利用者調査結果の分析から-山口 大輔(ヤマグチ ダイスケ) |
目的 本研究の目的は,北海道内のホームレス支援施設利用者の障害者手帳の取得状況と支援課題の関連について検討し,利用者の障害福祉制度へのつながりにくさについて考察することである。
方法 調査は,北海道内の7カ所のホームレス支援施設を対象として,ホームレス支援施設で利用者支援に従事している支援者に利用者個々の情報を記載する転記票調査を実施した。転記の範囲は「2015年6月30日」に施設を利用していた利用者全員とした。調査項目は,基本属性,入所直前の生活場所,入所につなげた人や機関,障害者手帳の取得状況(手帳の取得時期と障害の疑いの有無),支援課題などである。
結果 分析の視点として,利用者の障害者手帳の取得状況に着目し,①「入所前」に障害者手帳を取得した事例,②「入所後」に障害者手帳を取得した事例,③障害の「疑いあり」の事例の三つに区分した上で,支援課題との関連について検討した。その結果,上記の三つのタイプに共通しているのは,支援課題として「日常生活支援」の必要性と同時に,「障害福祉の支援拒否への対応」という要因が見いだされた。そのなかで,障害者手帳の取得にまでつながっていかない事例と手帳取得につながり,制度につながったとしても,一時的なものであり,制度利用をして支援を受け続けるという状態が「長続きしない」という事例が明らかとなった。さらに,その背景には,利用者の「精神的な不安定さ」「対人関係の困難さ」という要因が影響していたと考えられる。
結論 障害のある人に対して障害者手帳の取得,つまり障害認定の申請につなげて,障害福祉制度・サービスを利用するという支援が一般的な考え方ではあるが,困難や不利が複雑化している利用者にとっては,制度がうまくつながっていかない現状が示されたといえる。障害があるため,フォーマルな制度である障害福祉制度へつなげるという支援の方法では,背景が複雑である生活困窮者に対する支援の方法としては狭い捉え方であり,インフォーマルな支援の構築という視点に基づいたきめ細かい支援対応が必要になると考えられる。
キーワード ホームレス支援施設利用者,障害者手帳,障害福祉制度,支援課題,生活困窮者
|
第65巻第3号 2018年3月 介護福祉施設への介護ロボット導入効果と
佐野 千尋(サノ チヒロ) 渡邊 久実(ワタナベ クミ) 酒寄 学(サカヨリ マナブ) |
目的 本研究は,介護ロボットを導入した社会福祉法人の職員を対象にフォーカスグループインタビューを実施し,介護ロボット導入による効果と今後の課題および可能性を明らかにすることを目的とした。
方法 茨城県の社会福祉法人Hにおいて介護ロボットを使用する職員6名(理学療法士1名,作業療法士1名,介護福祉士1名,介護支援員1名,生活支援員2名)を対象に,フォーカスグループインタビューを実施した。分析は逐語記録より重要アイテムの抽出,類型化を行い,重要カテゴリーを抽出した。
結果 対象者全員が介護ロボット導入によるポジティブな変化や効果について述べていた。セラピー用アザラシ型ロボット導入の主な効果は,職員のストレス軽減やコミュニケーションの促進,利用者の言動の活発化や認知症の周辺症状の緩和等であった。介護支援ロボットスーツ導入の主な効果は,職員の身体的負担の軽減やリクルート活動への影響であった。また,介護ロボットの使用に際する今後の課題および可能性では,介護ロボットを使いこなすための技術の習得の重要性や新たな使用法の検討,使用についてアドバイスし合える環境づくりなど多様な意見が聞かれた。
結論 介護ロボット導入による効果として利用者や職員,環境でのポジティブな変化が聞かれた一方で,さらなる有効活用に向けた使用体制の構築や新たな活用の検討等の工夫展開が必要であると考えられる。本研究の成果をもとに,実践における介護ロボットの有効活用が期待される。
キーワード 介護ロボット,フォーカスグループインタビュー,質的研究
|
第65巻第3号 2018年3月 血液透析患者を対象とした心理状態の類型化とその特徴竹本 与志人(タケモト ヨシヒト) 杉山 京(スギヤマ ケイ) 仲井 達哉(ナカイ タツヤ) |
目的 血液透析患者の抑うつ状態の早期発見に有用な資料を得るために,血液透析患者の視点から心理状態を類型化し,抑うつ状態のリスクの高い心理状態を探索することとした。
方法 A県内の透析施設に通院する血液透析患者2,000名を対象に,無記名自記式の質問紙調査を実施した。調査内容は属性,心理状態,抑うつ状態などで構成した。統計解析は,心理状態について潜在クラス分析を用いて類型化を行い,次いで各クラスの特徴を確認するため,属性,抑うつ状態(K6)などについて有意差検定を行った。
結果 解析には,回収された1,137名の調査票のうち当該項目に欠損値のない862名の資料を用いた。血液透析患者は心理状態により6つのクラスに類型化され,年齢や透析歴,抑うつ状態においてクラス間に有意差が確認された。なかでもK6に関しては,クラス3の平均得点が最も低く,多重比較の結果,クラス3はクラス1,クラス2,クラス4,クラス6との間に有意差が確認された。
結論 クラス3以外の5つのクラスが抑うつ状態の可能性のある患者の割合が高い集団であると考えられた。本調査研究は単県の透析患者を対象としたものであることから,今後は他の地域での追試が課題である。また,透析患者の抑うつ状態の評価に関してはK6を用いた研究が僅少であり,後続研究との比較が課題である。
キーワード 血液透析,心理状態,類型化,潜在クラス分析
|
第65巻第3号 2018年3月 3歳児歯科健診からみたう蝕の地域格差について藤山 友紀(フジヤマ ユキ) 田代 敦志(タシロ アツシ) |
目的 3歳児におけるう蝕の地域格差について,地理情報システム(GIS)を用いて国勢調査の小地域統計データを活用した分析を行い,背景にある個人要因と環境要因を可視化し,う蝕との関係を明らかにすることを目的とした。
方法 新潟市A区における平成23年度の3歳児の歯科健診受診者613人を対象に,「う蝕の有無」を目的変数,「性別」「おやつの回数」「甘味飲料摂取の有無」「歯磨剤使用の有無」「フッ化物歯面塗布の有無」を説明変数としたロジスティック回帰分析を行った。次に同区の平成21~23年度の健診受診者1,835名を対象に,う蝕を有する者の割合と統計解析で有意な影響を認めた個人要因の分布状況をGIS上で可視化し,両者の関連について地理空間上で比較を行った。さらに,環境要因として,居住地の「人口密度」「産業別人口比率」「歯科医院から居住地までの直線距離」および「地域住民の学歴割合」を取り上げ,小地域統計データを用いてう蝕有病率との関係を分析した。
結果 ロジスティック回帰分析の結果,甘味飲料摂取の有無とフッ化物歯面塗布の有無にう蝕との関連が認められ,それぞれのオッズ比は1.66(95%信頼区間(CI)1.08-2.56),0.55(95%CI 0.35-0.88)であった。GISを用いた可視化により,行政区域に関わらないう蝕の有病状況と個人要因の分布が捉えられた。環境要因との比較において,人口密度では密集地区と過疎地区に比較して中間地区でう蝕有病率が低い傾向が認められ,産業人口比率では2次産業の割合が30%以下の地域でう触有病率の低い傾向が認められ,歯科医院から居住地までの直線距離についても,距離に依存してう触有病率が高くなる傾向にあったが,χ2検定において有意差は認めなかった。さらに,地域住民の大学卒業割合が高い地域では,有意にう蝕が少ない結果が得られたが,う蝕に関連する変数について級内相関係数を求めた結果,地域差の多くは個人レベルで説明されると考えられた。
結論 3歳児におけるう蝕とその要因の広がりをGISにより地理空間上で初めて可視化し,う蝕の背景にある地域性を分析し,居住する地域の環境要因とう蝕有病率の関係を明らかにした。今後は,分析結果をもとにう蝕有病率の低下に向けて,地域の実情に合った取り組みが必要と考えている。
キーワード う蝕,地域格差,小地域統計,GIS,個人要因,環境要因
|
第65巻第3号 2018年3月 訪問・通所リハビリテーション利用者の
曽根 稔雅(ソネ トシマサ) 中谷 直樹(ナカヤ ナオキ) 遠又 靖丈(トオマタ ヤスタケ) |
目的 本研究の目的は,訪問リハビリテーション(以下,訪問リハ)利用者と通所リハビリテーション(以下,通所リハ)利用者における特性や課題の違いを明らかにすることに加え,それぞれの利用者が抱えている課題を要介護度別に分析することである。
方法 本研究の対象者として,各事業所に勤務するリハビリテーション(以下,リハ)担当者1名当たり1名の利用者の抽出を依頼し,訪問リハは2016年1月1日時点,通所リハは2015年10月1日時点での調査を実施した。調査項目は,利用者の特性,ケアマネジャーが考える解決すべき課題,リハ計画書の作成者が設定した日常生活上の課題であった。利用者の特性と課題について,訪問リハ利用者と通所リハ利用者との差を検討するため対応のないt検定およびχ2検定を実施した。また,要介護度別の傾向性を検討するためCochran-Armitage検定を実施した。
結果 訪問リハでは1,266事業所の利用者3,989名,通所リハでは467事業所の利用者1,840名から回答を得た。利用者の特性として,訪問リハ利用者は,通所リハ利用者より要介護度が重度の者,日常生活自立度の低い者が多かった。課題として,訪問リハ利用者は,起居動作やADLにおける身辺動作,介護負担軽減,買い物,余暇活動の課題が多く,通所リハ利用者は,歩行・移動,閉じこもり予防,社会的参加支援の課題が多かった。要介護度別に検討した結果,訪問リハ利用者と通所リハ利用者共通の課題として,要介護度が重度になるほど,ADLや介護負担軽減の課題が多く,IADL維持・向上,社会的参加支援の課題が少ないことが示された。また,筋力向上,筋持久力向上,歩行・移動,階段昇降,閉じこもり予防の課題は,訪問リハ利用者で要介護度が重度になるほど少なくなるのに対し,通所リハ利用者では要介護度における違いは示されなかった。さらに,身体機能に関する課題は,活動や社会参加に関する課題より多いことが示された。
結論 訪問リハは利用者の生活環境で実施されること,通所リハは機器が整備され,他の利用者との関わりを通じた支援ができる環境にあることから,それぞれの特性が活かされた形で課題が挙げられていた。また,身体機能に関する課題は依然として多いことが示され,高齢者個々人のQOLの向上を目指すためには,さらに活動や社会参加に関する課題に目を向けていく必要があると考える。これら課題の特徴を踏まえることは,利用者の居宅サービスにおけるリハの均てん化に向けた重要な視点になるものと思われる。
キーワード 訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,実態調査
|
第65巻第2号 2018年2月 医療・福祉関係統計調査の現状と体系的整備に関する研究増田 雅暢(マスダ マサノブ) |
目的 本研究は,厚生労働省が実施している医療・福祉関係の基礎的な統計調査について,その現状を体系的に整理するとともに,行政担当者や地方自治体の関係者に対するヒアリング等を行うことにより,その課題を抽出し,今後の改善方策を提案することをねらいとした。研究対象としては,国民生活基礎調査や21世紀出生児縦断調査等の縦断調査,社会福祉施設等調査,医療施設調査,患者調査,社会医療診療行為別統計等,厚生労働省の旧統計情報部が所管している10本の統計調査を選択した。
方法 研究方法としては,学識経験者による委員会を組織し,定期的に意見交換を行う会議を開催したほか,委員の間で分担を決めて,各統計調査の現状と課題等を整理した。また,厚生労働省の統計調査の担当者に意見聴取を行ったほか,地方自治体へのヒアリングを行った。
結果・結論 10本の統計調査に関する現状と課題について,それぞれ個別に指摘した。例えば,国民生活基礎調査の課題として,回収率の低下とその対応策,行政記録の利用とその可能性,外国人の増加への対応,介護・医療に関する調査項目の追加等について言及した。10本の統計調査の現状と課題を踏まえた統計調査全体の今後の課題として,①予算上の制約に対応するために,統計調査の担当部局が,統計調査に関連する省内の関係部局と密接な連携を図り,関係部局の援護も受けながら予算確保に努める必要があることや,調査内容・項目の変更・追加等について,統計調査の担当部局がイニシアチブをとってもよいこと,②調査内容や調査結果の集計・公表方法について,統計調査に協力している地方自治体や統計調査のユーザーである研究者等の意見を反映する必要があること,③地域包括ケアシステムの構築や福祉人材の確保問題,在宅医療と介護の連携強化など,こうした新しい政策の流れや,オンライン調査やビッグデータの活用など,新たな調査方法に対応していく必要があることを指摘した。
キーワード 基幹統計,一般統計,縦断調査
|
第65巻第2号 2018年2月 中山間地域住民の食事・買い物の状況からみた
長谷 亮佑(ハセ リョウスケ) 山口 奈津(ヤマグチ ナツ) ホセイン マハブブ(ホセイン マハブブ) |
目的 わが国では急速な高齢化が進み,社会保障費の増大も続く中,できるだけ長く住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう地域包括ケアシステムの構築が目指されている。地域での生活を継続するためには,必要な条件が様々あるが,生活の中での日々の食事摂取は最も重要なものの一つで,そのための買い物も欠かせない。本研究の目的は,高齢化が進み,地区内に商店もない中山間地域住民の食事摂取と買い物の状況などを分析し,自宅生活継続のための方策を検討することである。
方法 山口県岩国市錦地域で,行政と関係機関などで構成される錦地域住民支援連携会議が主体となって,2012年11月から2015年3月までの間に3つの地区の計194人の住民に住民生活・健康調査が行われた。調査員の全戸訪問による聞き取りアンケート調査で,質問項目は,性別,年齢,職業,世帯構成といった基本的属性,食事の頻度や内容,買い物や交通手段といった日常生活の実態等であった。
結果 回答者の年齢の中央値は78(範囲29-101)歳で,高齢化率は87%であった。食事摂取状況は「毎日規則正しく食事を摂っている」が190人(98%),「困らない程度に食べている」が3人(2%),「食事が摂れずに困っている」が1人(1%)であった。13人の独居男性も含めた191人(98%)は自炊もしくは同居の家族が作る食事であった。主な買い物手段は自家用車・バイクが120人(62%)と最も多く,家族に依頼27人(14%),宅配サービス21人(11%),移動販売車10人(5%),路線バス8人(4%)であった。
結論 中山間地域の住民は,野菜を自給し,独居の高齢男性でも自炊するなど個々の生活能力が高いため,近くに商店や飲食店がなくても生活を継続できている。しかし,今以上に高齢化し,新たに要介護状態になる者も出てくる中で,中山間地域の住民の多くが他の地域に移転せざるを得なくなる可能性も考えられる。移動販売車や宅配サービス,配食サービスなどにより自宅生活が継続しやすくなるかもしれないが,今後もさらに人口減,高齢化が進む中山間地域では今ある民間サービスの継続さえ厳しいと思われる。一方で,地域調査や住民説明会をきっかけに,住民ボランティアの助け合い組織が活性化したり,解散していた老人会が復活したりしており,地域住民が自ら地域課題に取り組む動きが出てきている。その中で,車の乗り合わせを地域内でさらに促進するなど,住民の互助を促進するような取り組みが活発になることを期待したい。
キーワード 地域包括ケアシステム,中山間地域,食事摂取,買い物,互助
|
第65巻第2号 2018年2月 高校におけるヤングケアラーの割合とケアの状況-大阪府下の公立高校の生徒を対象とした質問紙調査の結果より-濱島 淑恵(ハマシマ ヨシエ) 宮川 雅充(ミヤカワ マサミツ) |
目的 日本におけるヤングケアラーの実態把握は,諸外国と比較して,遅れているのが現状である。本研究では,高校におけるヤングケアラーの実態を,高校生自身の主訴,認識に基づいて把握することを目的とした。
方法 2016年1~12月に,大阪府下の公立高校において,生徒を対象とした質問紙調査を実施した。
結果 10校の協力を得ることができ,合計で5,671票の調査票が回収された。そのうち,本研究の分析対象は,5,246票となった。別居している家族も含め,家族にケアを必要としている人がいるかを尋ねた結果,5,246名のうち664名(12.7%)がいると回答していた。さらに,325名(6.2%)が,回答者自身がケアをしていると回答していた。なお,そのうち,53名は,幼いきょうだいがいるためという理由のみでケアをしていた。325名から,この53名を除外した結果,272名がヤングケアラーと考えられ,その割合は5.2%であった。ケアの内容に関する回答結果からは,高校生のヤングケアラーは,ケアを要する家族に,直接,身体的なケアを行っている場合もあるが,家事を担う,年下のきょうだいの世話をする,感情面でのサポートをする,特定の場面で力仕事や外出時の介助・付き添いをするといったケア役割が回ってきやすいことが示唆された。また,ケアの期間については,中央値が3年0カ月,75パーセンタイルが6年5カ月であり,ケア役割が常態化,長期化しつつあるケースが一定数存在することが示唆された。ケアの頻度,1日のケア時間に注目して,負担がより大きいと考えられるヤングケアラーの割合を求めた結果,週4,5日以上ケアをしている者は2.3%,学校がある日に1日2時間以上のケアをしている者は1.2%,学校がない日に1日4時間以上のケアをしている者は1.2%,学校がある日に1日2時間以上,かつ,学校がない日に1日4時間以上のケアをしている者は1.0%存在すると考えられた。
結論 日本の高校においても,ヤングケアラーは存在し,負担が大きいと考えられるケースもそこには含まれていることが示された。また,彼らの担うケアの特徴から,その存在は潜在化しやすいことが示唆された。家庭内でのケア役割を担うことが彼らに過度な負担を強い,将来の可能性を狭める経験とならないように,ヤングケアラーの支援体制を社会的に構築する必要があると考えられる。
キーワード ヤングケアラー,若年介護者,介護者支援,家族支援,高校生,質問紙調査
|
第65巻第2号 2018年2月 身体活動とレジリエンスの関連-自衛隊員における検討-小島 令嗣(コジマ レイジ) |
目的 うつ病の有病率は増加傾向にあり,大きな社会問題である。ストレス回復力であるレジリエンスの向上は,うつ病対策の一つとして挙げられる。また身体活動は,レジリエンスとの関連が示唆されているがその検討は少ない。本研究は身体活動とレジリエンスの関連に用量反応関係があるかを明らかにするため,自衛隊員を対象に横断研究を行った。
方法 2015年度生活習慣病検診を受けた,35歳以上の男性自衛隊員16,358名を解析対象とした。身体活動量は,国際標準化身体活動質問票(IPAQ),レジリエンスは,Tachikawa Resilience Scale(TRS;範囲10-70)にて評価した。身体活動量をIPAQの値で四分位群(Q1~Q4)に分け,4群間におけるTRSの値を共分散分析にて,婚姻,睡眠時間,喫煙,飲酒,BMI,最終学歴,年齢,階級で調整し比較した。
結果 対象者の年齢は44.2±5.9歳(平均値±標準偏差),IPAQ区分ごとのTRS(平均値(95%信頼区間))は,Q1;46.6(46.3-46.9),Q2;47.5(47.2-47.8),Q3;47.9(47.6-48.2),Q4;48.2(47.9-48.5)であり,IPAQが高値であるほどTRSが高かった(傾向性検定p<0.01)。
結論 身体活動量とレジリエンスの間には,正の用量反応関係がみられた。習慣的な身体活動量を多くすることで,レジリエンスを高められる可能性が示唆された。
キーワード 身体活動,レジリエンス,自衛隊員
|
第65巻第2号 2018年2月 高槻市におけるゲートキーパー養成研修の効果について田渕 紗也香(タブチ サヤカ) 谷本 芳美(タニモト ヨシミ) 加藤 美幸(カトウ ミユキ)的場 輝世(マトバ カヨ) 木村 直也(キムラ ナオヤ) 森定 一稔(モリサダ カズトシ) 髙野 正子(タカノ マサコ) |
目的 自殺対策における人材養成(ゲートキーパー養成)はわが国が掲げる重点施策の1つである。本研究では高槻市職員を対象として,ゲートキーパー養成研修の自殺対策の取り組みに対する効果について検討することを目的とした。
方法 市職員3,717人(正規職員2,687人,非常勤職員1,030人)を対象者に,無記名自記式アンケート調査を行い,回答が得られた2,653人のうち性別・年齢が不明な者を除いた2,633人を解析対象者とした。質問項目は仕事や職場での生活や,自殺対策の取り組みに関する項目とした。自殺対策の取り組みについてはゲートキーパー養成研修受講の有無との関連を,χ2検定を用いて比較検討した。
結果 仕事や職場での生活に関することについての相談相手は上司・同僚が1,132人(43.0%),家族・友人が1,249人(47.4%)と多かった。さらに,上司・同僚に相談した者の85.4%,家族・友人の86.5%が相談後にメンタルヘルスケア効果有りであった。ゲートキーパー養成研修受講者は403人(15.3%)であった。ゲートキーパー養成研修受講有りの方が93.1%と有意に高い割合で自殺対策の必要性を理解していた。またセルフケア実施の割合や,職場の上司・同僚・部下等,家族・友人等,市民,それぞれに対する周囲へのケアを実施している割合も受講有りの方が有意に高い割合を示した。
結論 高槻市職員における研究からゲートキーパー養成研修受講は自殺対策の取り組みに関連することが示された。とりわけ,市民対応時に自殺対策の取り組みを有意に高い割合で実施していることが明らかとなり,ゲートキーパー養成研修の意義が示された。しかし,本研究は,市職員対象に行ったものであり,本結果の外的妥当性については今後さらに検討が必要である。
キーワード 自殺対策,ゲートキーパー養成,研修,市職員,メンタルヘルスケア
|
第65巻第2号 2018年2月 EPA送り手国の看護師と受け入れ国である
|
目的 EPA外国人看護師と日本における彼らの指導者の看取り観の差異および看取り観に関連する要因を探り,異文化間ケアの在り方を考える一助とする。
方法 2008~2014年に派遣されたEPA外国人看護師を受け入れた411施設(全数)に対して,EPA外国人看護師全員とその指導者を施設ごとに1人の合計3,258人に郵送調査を実施した。看取り観の測定にはFATCOD-Form B-Jを用いて,看取り観を従属変数として,国籍,個人の属性,社会文化的特性,死生観(死生観の測定には臨老式死生観尺度を使用)を独立変数として,重回帰分析を実施した。調査期間は2015年10月~12月である。
結果 回答施設は121施設(29.4%)で,有効回答者は503人(15.4%)であった。EPA送り手国(フィリピン,インドネシア,ベトナム)と日本とで看取り観の比較を行った。国ごとの看取り観の比較を行った結果,「ケアの前向きさ」に関しては,日本が有意に高く,「ケアの認識」に関しては,フィリピンの得点が他の3カ国に比べて有意に高く(p<0.001),日本の得点が他の3カ国に比べて有意に低い。「総得点」に関しては,フィリピンの得点が他の3カ国に比べて有意に高い(p<0.05)。死にゆく患者に対するケアの前向きさは,「国」による差はなく,「経験年数」「職種」「看取り経験」「死からの回避」「人生の目的意識」に関連がみられた。ケアの認識に関しては,「国籍」「経験年数」「人生の目的意識」「死への関心」が関連要因となっていた。
結論 看取り観に関連する要因は,死にゆく患者への「ケアの前向きさ」に関しては,国籍による差はなく,経験を積み重ね,死を回避せず,人生の目的意識を持つ死生観を育むことで,看取りケアができるようになっていく。しかし,「ケアの認識」に関しては,日本が他の3カ国に比較して有意に低く,国籍による差がみられた。これに関連する要因については,今後も引き続き異文化間ケアへの検討が必要である。
キーワード EPA,外国人看護師,看取り観,死生観,異文化間ケア,エンドオブライフ・ケア
|
第65巻第1号 2018年1月 認知症対応型共同生活介護事業所の平成26年度
渡辺 康文(ワタナベ ヤスフミ) |
目的 福祉や介護のサービスの質の確保が必要である。本研究は認知症対応型共同生活介護事業所(GH)がサービスを改善するため,平成26年度の地域密着型外部評価で公表した目標達成計画を調査して,問題点・課題のあった項目と,その改善計画をとりまとめ,以前のデータと合わせて4年間のデータとし,その推移を検証してGH全体の「見える化」を推し進め,サービスの質の向上に資することを目的とした。
方法 ワムネットと2県の情報提供から,平成26年度に外部評価を実施した,東京都と山梨県を除く45道府県のGHの目標達成計画を参照し,自己評価68項目において問題点・課題があった項目の数と割合および問題点・課題が多かった項目の改善計画内容の分類と区分を算出し,平成23~25年度の過去の調査データを利用して平成23~26年度の4年間のデータとした。
結果 平成26年度の外部評価で以下が明らかになった。実施したGHは8,328ヵ所で,問題点・課題があった項目は17,068件であった。問題点・課題が多い項目は,1位「災害対策」,2位「運営推進会議」,3位「地域つきあい」,4位「介護計画とモニタリング」,5位「重度化や終末期」であった。改善計画内容の区分で割合が大きかったのは「災害対策」では「地域へのはたらきかけ」,「運営推進会議」では「多様な参加者」,「重度化や終末期」では「職員の資質向上」であった。
結論 問題点・課題があった項目の4年間の推移から,「災害対策」「運営推進会議」「重度化や終末期」「地域つきあい」「介護計画とモニタリング」等への集中が続いていることがわかった。問題点・課題が多かった項目の改善計画の推移からは「災害対策」と「運営推進会議」でGHと地域との関係づくりが続いていることが示され,「重度化や終末期」では職員教育の必要性が継続していると考えられた。今後は「地域つきあい」「介護計画とモニタリング」「運営に関する利用者,家族等意見の反映」「日常的な外出支援」等の項目も改善計画を内容分析して可視化を広げることが望ましい。また,目標達成計画に68項目の番号表記がないものがある,介護業界の用語が散見される等の情報開示のうえでの課題がある。今後のGHのサービスの質とホスピタリティの向上のため,外部評価調査員の質の担保や人数の確保が期待される。
キーワード サービスの質,認知症対応型共同生活介護事業所(GH),地域密着型外部評価,問題点・課題,改善計画
|
第65巻第1号 2018年1月 日本における小児患者数の推移と疾病構造の変化内山 有子(ウチヤマ ユウコ) 田中 哲郎(タナカ テツロウ) |
目的 近年の日本では,少子化にともなう15歳未満の小児患者数の減少や医療の進歩により,小児が受診する疾病構造に変化が見られている。そこで,小児の患者数や疾病構造の変化,傷病別医療費などの年次推移より小児医療の現状を分析し,小児医療の課題について検討を行った。
方法 厚生労働省が公表している国民医療費,患者調査,人口動態統計を用いて,年齢階級別の推計患者数,受療率,医療費と小児の傷病別入院患者数を算出した。
結果 0~14歳の1日あたりの推計入院患者数は,1984年~2014年の30年間で約4割に減少した。また,入院受療率,外来患者数ともに約7割に減少したが,外来受療率は1.2倍に増加していた。1人あたりの年間入院医療費は1986年から2014年の30年間で約3倍に,入院1件あたりの医療費は約4倍に,入院1日あたりの医療費は約5倍に増加していた。また,2014年の0~14歳の1人あたりの年間外来医療費は15~44歳よりは高いが,45~64歳,65歳以上よりは低く,受診1回あたりの外来医療費は他の年齢階級の中で最も低かった。0~14歳の1人あたりの年間外来医療費は1986年から2014年の30年間で約2.5倍に,受診1回あたりの外来医療費は約2倍に増加しており,傷病別入院患者数は1996年から2014年の20年間で周産期における病態が増加し,呼吸器系の疾患が減少していた。
結論 この30年間で小児の1日あたりの推計入院患者数,入院受療率,1日あたりの推計外来患者数は減少したが,外来受療率は増加し,小児科の診療が外来を中心としたものとなり入院と外来のバランスに変化が生じている傾向がみられた。また,2016(平成28)年に行われた診療報酬の改定によりNICUなどの設備があり周産期および先天奇形の診療を行っている病院の診療報酬は高くなるが,新生児の診療を積極的に行っていない小児科や呼吸器・感染症等を中心に診ている小児科にとってはこの改定による利益は少ないことがわかった。今後,安定した小児科診療を継続していくためには,一般の小児科病院にも目を向けた診療報酬の改定等が望まれる。また,近年の行われている小児入院施設の集約化は,病院の体制強化や専門能力の向上により重症患者の治療成績を向上させることにつながるが,極端な集約化が進められると,地域によっては近くに小児医療施設がなくなる可能性があるため,少子化対策,育児支援という観点からも国民的議論として再考していく必要があると思われた。
キーワード 推計入院患者数,推計外来患者数,受療率,入院医療費,外来医療費,疾病構造
|
第65巻第1号 2018年1月 インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動発症例における
中村 裕樹(ナカムラ ユウキ) 大日 康史(オオクサ ヤスシ) 菅原 民枝(スガワラ タミエ) |
目的 インフルエンザ罹患時における異常行動の発症について,過去の研究では,調査対象薬剤のいずれかの使用状況が不明であった症例が多数存在した。本研究では,調査対象薬剤のいずれの使用状況も明らかになるように調査を行い,それらの割合を用いて,過去の症例数を割り戻すことで改めて薬剤ごとの異常行動発症に関する検討を行った。
方法 オセルタミビル,アマンタジン,ザナミビル,アセトアミノフェン,ペラミビル,ラニナミビル,テオフィリンを調査対象薬剤とし,2012/2013シーズンから2014/2015シーズンの3シーズンでの,いずれかの使用状況が不明であった症例数を,いずれの使用状況も明らかになるように調査を行った2015/2016シーズンの症例数を元に割り戻し,それぞれの使用例での異常行動症例数を正確確率検定(厳密検定)によって比較した。
結果 異常行動発症例において使用が認められたオセルタミビル,ザナミビル,ペラミビル,ラニナミビル,アセトアミノフェンにおいて,シーズン間で使用した患者の割合に有意差はなかった。また,それらの使用薬剤の組み合わせが不明であった症例を割り戻しても同様の結果となった。
結論 使用薬剤の組み合わせが不明であった症例数を考慮に入れても,異常行動の発症と使用薬剤との特定の関連がある,とは言えないことが示された。ただし,本研究での症例数は2015/2016シーズンのみの結果を反映したものであるため,今後も引き続き検証が必要であると考えられる。
キーワード インフルエンザ,異常行動,ノイラミニダーゼ阻害剤,オセルタミビル
|
第65巻第1号 2018年1月 回復期リハビリテーション病院に入院した脳卒中患者の
梅原 拓也(ウメハラ タクヤ) 田中 亮(タナカ リョウ) 恒松 美輪子(ツネマツ ミワコ) |
目的 本研究は,入院時の認知機能の程度を基に脳卒中患者を分類し,理学療法,作業療法,言語聴覚療法の提供単位数に着目して,療法の効果の有無を区別するカットオフ値を算出してその精度を評価することを目的とした。
方法 対象者は,脳卒中患者とした。入院中に実施された理学療法,作業療法,言語聴覚療法の単位数を調べた。認知機能の評価にはFIMを使用した。入院時の認知機能の障害の程度により患者を低群,中群,高群の3群に分類した。認知機能のより大きな回復に関連する単位数を検討し,カットオフ値や確率を明らかにするために,ロジスティック回帰分析とROC分析を行い,変数ごとに事後確率を求めた。
結果 3群に共通して抽出された因子は,言語聴覚療法の総単位数であった。この変数のカットオフ値・陽性尤度比・陰性尤度比・事後確率は,低群で208単位以上・2.33・0.56・64.0%であり,中群で123単位以上・1.16・0.22・51.0%であり,高群で98単位以上・1.83・0.81・61.0%であった。
結論 本研究の結果から,FIM認知項目合計点の回復に言語聴覚療法が関連することと,その介入量が示唆された。ただ,予測精度は高くないので,さらに検討が必要である。
キーワード 回復期リハビリテーション,脳卒中,認知機能,介入量,ロジスティック回帰分析
|
第65巻第1号 2018年1月 自治体における母子健康手帳と綴込型松井式便色カードの
顧 艶紅(コ エンコウ) 大森 豊緑(オオモリ トヨノリ) 松井 陽(マツイ アキラ) |
目的 2012年度から松井式便色カード(以下,便色カード)が母子健康手帳に綴じ込まれており,各自治体からの交付により,胆道閉鎖症のスクリーニングとして活用されている。便色カードによるスクリーニングは先天性代謝異常症等のマススクリーニング検査と異なり,行政による保護者・医療関係者への周知とカードの色調精度管理がその効果を大きく左右するため,厚生労働省通知で使用法・交付と説明や色調精度管理に関する技術的助言等が示されている。今回,母子健康手帳と便色カードの印刷および交付・説明の状況を把握するため,導入後初めての全国調査を行った。
方法 都道府県を通して,2015年10月末現在で全国の1,741自治体へ調査票を送付し,横断調査を行った。
結果 調査票の回収率は80.6%(1,404),母子健康手帳見本の回収率は65.9%(1,148)であった。現在使用している母子健康手帳について1,303自治体は計21の業者から購入し,97自治体は計23の印刷業者で独自に印刷していた。便色カード印刷可能業者リストに掲載されている業者が印刷した手帳を購入または印刷を依頼した自治体は1,016であった。また,35の自治体が競争入札によって毎年購入先や印刷業者を替えていた。一つの自治体を除き,母子健康手帳と便色カードの購入先や印刷業者は同一であった。また,母子健康手帳の省令様式内に綴じ込まれていない,あるいは規格外の用紙に印刷されている便色カードもあった。なお,上述の厚生労働省通知について,「知っている」と答えた自治体は80.5%(1,098/1,364)であった。718の自治体が市町村役場の窓口で母子健康手帳を交付しており,交付時に母子健康手帳と便色カードについて説明していたのはそれぞれ85.2%と42.1%であった。支所・出張所で母子健康手帳を交付していたのは358自治体で,交付時に説明していたのはそれぞれ61.5%と27.9%であった。保健所・保健センターで母子健康手帳を交付していたのは877自治体で,交付時に説明していたのはそれぞれ97.3%と57.8%であった。また児童館や公民館などその他の施設で交付していたのは70自治体で,交付時(新生児・乳児訪問時を含む)に説明していたのはそれぞれ82.9%と78.6%であった。
結論 便色カードによる胆道閉鎖症のスクリーニングの効果を上げるため,印刷可能業者リストに掲載されていない業者で印刷されたカードの精度管理を図るとともに,母子健康手帳の交付時に便色カード使用法についての説明を行うことを周知徹底する必要がある。
キーワード 母子健康手帳,自治体,松井式便色カード,精度管理,マススクリーニング
|
第65巻第1号 2018年1月 母親の年齢と職業の妊娠の結果への影響-人口動態職業・産業別調査を用いて-仙田 幸子(センダ ユキコ) |
目的 人口動態職業・産業別調査の出生票データおよび死産票データと,人口動態調査の死亡票データのうち乳児死亡のデータを用いて,妊娠の結果(自然死産,人工死産,乳児死亡,生存)に母親の職業と年齢がどう影響しているのかを明らかにする。
方法 1995年度,2000年度,2005年度,2010年度の人口動態職業・産業別調査の出生票データと同時期に調整した人口動態調査の乳児死亡のデータを10の指標を用いてリンケージしたうえで,人口動態職業・産業別調査の死産票データを追加して分析データを作成した。従属変数として妊娠の結果(自然死産,人工死産,乳児死亡,生存),独立変数として死産時または出生時の母親の年齢と職業,加えて,児の体重,単産・複産の別,出産経験,死産または出生の発生月,死産または出生の発生した年度を統制変数として投入し,従属変数の基準を生存として,多項ロジスティック回帰分析を行った。
結果 母親の年齢も職業も妊娠の結果に影響を示す。30代で自然死産や人工死産になりにくい。児の生存の確率が最も高いのは30~34歳である。職業の影響は年齢の影響より概して高い。自然死産と人工死産については,すべての職業で無職より発生確率が高い。乳児死亡は,専門技術職,事務職,販売職,サービス職で無職より発生確率は低く,管理職,保安職,農林職,運輸職は無職と同程度の発生確率である。
結論 出生に関する厚生の指標として母親の職業は重要である。
キーワード 自然死産,人工死産,乳児死亡,児の生存,リンケージデータ
|
第64巻第15号 2017年12月 保育ソーシャルワークの構成概念と尺度開発-保育士や保育所の実践環境に着目して-山城 久弥(ヤマシロ ヒサヤ) |
目的 今日,少子化や核家族化の進行,地域とのつながりの希薄化などの大きな社会変化を背景に,児童やその家庭を取り巻く環境が厳しい状況の中,保育士や保育所は地域やその家庭の子育て支援を担うためにソーシャルワーク機能を果たすことが求められている。そこで,本研究では,保育士個人として必要な支援スキルだけでなく,保育所組織としての実践環境に着目した保育ソーシャルワークの構成概念を明らかにし,実践環境をアセスメントするための尺度を開発することを目的とした。
方法 2017年2月15日~3月31日にかけて調査を実施した。先行研究から,保育ソーシャルワークに関する40項目の質問項目を採用し,長野県保育園連盟保育部会に所属する保育園に在籍している保育士480名を対象に郵送留置調査法を実施し,回収数は350名(回収率72.9%)であった。その中から,保育ソーシャルワークに関する項目において,無回答数が全体の5%以下(2項目以下)の346名を分析対象者とした。分析方法として,保育ソーシャルワークの項目に対し探索的因子分析を行った。信頼性については,内的整合性(Cronbachのα係数)を算出した。
結果 保育ソーシャルワークの探索的因子分析の結果,「権利侵害の知識とその対応方法」「子育て支援のための知識と活動」「家庭・保護者との援助関係」「支援の限界と専門機関との連携の理解」「保育所内における情報共有」「保育所内における職員の連携」の6つの下位尺度から構成された。各下位尺度のα係数は0.61~0.85であり,6因子構造が示された。さらに,6つの下位尺度を構成する項目が同一因子に0.4以上の因子負荷量を有し,構成概念の妥当性をある程度確保していることも示唆された。
結論 本研究において抽出された因子は,先行研究から得られた理論的構造とほぼ一致しており,ある程度の信頼性と妥当性が確認された。とくに,専門機関との連携においては,その認識として保育士や保育所の支援の限界を理解することに相関がみられ,連携のあり方についての示唆が得られた。今後の課題としては,尺度の改良を重ね,さらなる信頼性と妥当性の確保や実際の保育現場で活用されるよう実用化のためのツール開発もあわせて行っていく必要がある。
キーワード 保育ソーシャルワーク,実践環境,構成概念,保育士,保育所
|
第64巻第15号 2017年12月 障害者グループホーム職員による
|
目的 本研究は,障害者の地域生活実現のために,地域との関係形成に関してグループホーム職員が行っている支援の現状と特徴を明らかにし,その課題を提示することを目的とした。
方法 調査方法は,自記式アンケートの郵送調査である。調査対象者は,「福祉・保健・医療総合情報サイト(WAMNET)」から「指定共同生活援助事業」の主たる事業所を全国の市区町村から各1事業所を選定した。調査・回収期間は,2016年3月1日から4月30日とした。
結果 配布総数1,334通,有効回収数633通,回収率47.5%であった。地域関係形成に関してほぼすべての事業所が行っていると回答した。「地域住民との交流」はあいさつや立ち話などの割合が高い。「自治会等との交流」は清掃活動や行事への参加の割合が高かった。「入居者の関わり支援」は商店や行事への同行が高い。「理解の促進」はトラブルへの対応の割合が高い。「事業所としての取り組み」は情報共有が高かった。グループホームが対象とする障害種別,回答者別に取り組み状況の回答割合は異なっていた。
結論 地域との関係形成に関するグループホーム職員の取り組み状況は,住民との交流ではお互いが都合を合わせる必要のある関わりは少なく,自治会等との交流は参画の程度が低い。トラブルへの対応や回避を重視している。そして,実際に行っていることと必要な支援が乖離していると感じている。グループホーム職員は地域との関係を形成する支援に関わりきれていないことが明らかとなった。入居者への直接的な日常生活上の支援に時間が割かれていることと業務としての共通認識の低さにあると指摘できる。グループホームに入居する障害者を孤立させないためにも,「地域との関係」に関する支援を業務として共通理解を図ることが課題であり,それを実現するための制度的な裏付けが必要となる。
キーワード 障害者,地域生活,グループホーム,グループホーム職員,地域関係形成支援,業務
|
第64巻第15号 2017年12月 「出前・イベント型まちの保健室」に
稲田 千明(イナダ チアキ) 荒川 満枝(アラカワ ミツエ) 高田 美子(タカタ ヨシコ) |
目的 2010年には高齢化率が28%を超え,人口減少が続いている鳥取県倉吉市において,鳥取看護大学は地域貢献として様々な形態の「まちの保健室」を企画・運営している。そのうち気軽に参加可能な「出前・イベント型まちの保健室」参加者の,健康状況と健康意識や健康行動について明らかにすることを目的とした。
方法 調査期間は2015年8月から11月で,鳥取看護大学が実施している「出前・イベント型まちの保健室」で健康に関する質問紙を配布し,参加者に記入していただくとともに,研究協力に同意のあった参加者の健康チェックデータを転記し,属性と健康データや健康に関する意識との関係について解析を行った。
結果 質問紙は528枚を配布し,493枚が有効回答(93.4%)であった。65.4%が女性で,70代が最も多く,体脂肪率,収縮期血圧は年齢とともに増加し,特に20~30代から40~50代での変化が大きかった。健康への自己評価は,約55%が「健康」「まあまあ健康」と答え,男女でも年齢層でも大きな違いはなかった。食事への気づかいについては,男女,年齢層別,イベントの種類別でも違いがみられた。運動については,男女共に半数の人が運動しており,60代から大幅に割合が増加していた。食事や運動以外で気をつけていることについては,年齢が高くなるにつれて気をつけている人が増え,その内容として,男女ともに「睡眠」と答えた人が多く,「ストレスをためない」などの対処法や「前向きに考える」など気持ちの持ち方,「友達と会う」「おしゃべりをする」などという積極的な行動の記述があった。「健診を受けようと思うか」の質問へは,スポーツ系イベントの人は93%が肯定しており,健康への意識の高さがうかがえた。まちの保健室の参加については,約90%の人が「良かった」と答えていた。
結論 40~50代の生活習慣病関連データは,30代に比して急激に悪化し,自身を「健康」だと明言できる割合も低く,健康への意識改革を勧めやすい年代と考えられた。まちの保健室に参加する人の割合が,50代から増えている。この健康意識が高まる時期にまちの保健室を開催することで,介護予防に寄与する可能性も考えられた。今回明らかとなった健康意識・行動の特徴を踏まえ,本人の健康行動から実行可能な行動目標を本人とともに言語化していくことが必要である。
キーワード まちの保健室,健康意識,健康データ,出前・イベント,健康行動
|
第64巻第15号 2017年12月 地域包括ケアシステムの評価指標としての在宅期間-8年間の全国介護レセプトデータによる検討-植嶋 大晃(ウエシマ ヒロアキ) 高橋 秀人(タカハシ ヒデト) 野口 晴子(ノグチ ハルコ)川村 顕(カワムラ アキラ) 松本 吉央(マツモト ヨシオ) 森山 葉子(モリヤマ ヨウコ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) |
目的 重度要介護高齢者の在宅日数は,地域別に算出することで地域包括ケアシステムの達成状況の評価指標となりうる。本研究の目的は,全国介護レセプトデータを用いて在宅日数を都道府県別に算出し,観察期間前後の打ち切り(以下,観察の打ち切り)を考慮して地域を比較する指標としての可能性を示すことである。
方法 厚生労働省の承認を受けて8年間の全国介護レセプトデータを用いた。対象者は65歳以上で要介護4または5の認定を受け,要支援または要介護認定を受けていた期間に介護保険サービスを利用した者とした。観察期間における在宅日数が0日の対象者を在宅ゼロ群,在宅日数が1日以上の対象者を在宅群とし,在宅ゼロ群の人数の割合(以下,在宅ゼロ者割合)および在宅群の在宅日数平均値(以下,平均在宅日数)を算出した。次に在宅群を,打ち切りなし群,開始時打ち切り群,終了時打ち切り群,両側打ち切り群に分類して在宅日数を算出し,各群の割合を都道府県別に算出した。また,在宅ゼロ者割合と,平均在宅日数を都道府県別に算出し,両者の相関係数および散布図を示した。さらに,特定施設入居者生活介護等のサービス利用期間も在宅で生活した期間とした在宅日数(以下,介護保険在宅日数)を算出し,在宅日数との比較を行った。
結果 対象地域は1,630市区町村(全市区町村の93.6%)で,対象者数は3,598,809人であった。在宅ゼロ者割合は37.8%,平均在宅日数は362.6日であった。打ち切りなし群,開始時打ち切り群,終了時打ち切り群,両側打ち切り群の人数(割合)はそれぞれ1,653,443人(45.9%),240,136人(6.7%),331,533人(9.2%),15,013人(0.4%),在宅日数平均値は247.8日,672.1日,610.6日,2570.9日であり,各群の人数の割合は都道府県により異なっていた。都道府県別の在宅ゼロ者割合の最大値と最小値は54.2%,30.3%で,平均在宅日数の最大値と最小値は475.5日,292.4日であった。在宅ゼロ者割合と平均在宅日数の相関係数は-0.55であった。在宅日数と介護保険在宅日数の差は,都道府県によって異なっていた。
結論 在宅ゼロ者割合および平均在宅日数は,「観察の打ち切り」の影響を考慮する必要があるものの,両者を組み合わせることにより,地域の指標として利用可能であると考えられた。
キーワード 高齢者,在宅介護,地域包括ケアシステム,全国介護レセプトデータ,在宅期間,地域指標
|
第64巻第15号 2017年12月 市町村における母子保健対策の取り組み状況:「健やか親子21」
上原 里程(ウエハラ リテイ) 篠原 亮次(シノハラ リョウジ) 秋山 有佳(アキヤマ ユウカ) |
目的 「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向け2015年度から実施されている「健やか親子21(第2次)」では,都道府県の役割として市町村等の関係者間の連携を強化することと県型保健所の役割として市町村に対して積極的に協力・支援することが明記されている。これらの役割を果たすためには,都道府県や保健所が市町村の母子保健に関する課題を認識することが重要である。市町村の母子保健対策の取り組み状況を知ることは課題把握に寄与すると考えられることから,本研究では母子保健対策に関する市町村の取り組み状況について都道府県別の観察を行った。
方法 2013年に実施された「『健やか親子21』の推進状況に関する実態調査」のうち,政令市および特別区を除く市町村(以下,市町村)を対象とした調査票に設定されている27項目の母子保健対策の取り組み状況を分析した。これらの項目に関して,2010年以降の取り組みの充実について市町村が回答した5つの選択肢(充実,ある程度充実,不変,縮小した,未実施)に未回答を加えた6区分の頻度を都道府県別に観察した。取り組み状況の選択肢のうち「充実」と「ある程度充実」を合わせた回答を本研究での「充実」と定義した。さらに,都道府県に対しても市町村と同様の調査が実施されていたため,市町村の取り組み状況と都道府県の取り組み状況との関連を検討した。
結果 27項目の母子保健対策のうち,「予防接種率の向上対策」「発達障害に関する対策」「乳幼児期のむし歯対策」「食育の推進」「児童虐待の発生予防対策」「産後うつ対策」は全国1,645市町村の50%以上が取り組みを充実させていた。各都道府県の管内市町村で取り組みを充実させた頻度の分布を観察すると,「予防接種率の向上対策」では100%の市町村が取り組みを充実させた都道府県もあれば取り組みを充実させた市町村が52%に留まっていた都道府県もあり,多くの項目で都道府県によって管内市町村の取り組み充実頻度の幅が大きかった。母子保健対策に関する市町村の取り組み状況と都道府県の取り組み状況の関連について,「発達障害に関する対策」「産後うつ対策」「妊娠中の喫煙防止対策」「母乳育児の推進」「思春期の心の健康対策」「十代の人工妊娠中絶防止対策」は取り組みを充実させた都道府県において,取り組みを充実させた管内市町村の頻度が有意に高かった。
結論 管内の市町村がどのような母子保健対策を充実させたかについては都道府県によって差異があった。また,母子保健対策の項目によっては市町村の取り組みの充実と都道府県の取り組みの充実が関連していたことから,都道府県が取り組みを充実させることで市町村の取り組み状況に影響を与える可能性が示唆された。
キーワード 健やか親子21(第2次),母子保健,連携,都道府県,市町村
|
第64巻第13号 2017年11月 ネグレクトで育った子どもたちへの虐待防止ネットワーク-10代親への支援の実態調査より-加藤 曜子(カトウ ヨウコ) 安部 計彦(アベ ケイヒコ) 佐藤 拓代(サトウ タクヨ)畠山 由佳子(ハタケヤマ ユカコ) 三上 邦彦(ミカミ クニヒコ) |
目的 ネグレクトの環境下で育った10代の被虐待児の実態を理解し支援するため特定妊婦に焦点をあてた。わが国では,10代の特定妊婦は要保護児童対策地域協議会の進行管理ケースとなっていることから,地域の各関係機関間の連携状況を検討してその課題を抽出した。特に0歳児死亡分析においては,その26.6%が10代親であり,ネットワーク支援の在り方が問われている。
方法 2015年9月,全国の市区966カ所の要保護児童対策地域協議会の調整機関担当者あてにアンケート調査を行った。調査項目は本研究の協力者と検討を重ね,選択回答と自由回答をとることにした。なお10代親を中学,高校,および無所属の16-19歳の3区分とした。また倫理的配慮として,大学倫理委員会へ申請し,個人情報保護に十分配慮することとした。
結果 回答を得た対象となる371事例のうち,被虐待歴は4割を占めた。被ネグレクト経験の占める割合は,複数回答で,中学生,高校生,16-19歳いずれも6割を超えた。背景要因は「経済的困窮」「養育支援者がいない」「児の心身状態に問題がある」「望まない妊娠」が高かった。高校生,16-19歳と年齢があがるにつれ経済的困窮や養育支援者がいない割合が高かった。虐待防止ネットワークとして直接支援者が集まる個別ケース検討会議においては,被ネグレクト経験のある中学生は63.6%であり,高校生50.0%や無所属16-19歳47.3%に比べると高い割合であった。機関連携では,高校の退学問題など学業継続の課題が68.8%該当した。16-19歳では居所不安定の割合や養育者がいない割合が高く,出産後も住居不安定になるなど支援する側の困難点も明らかになった。
結論 高校は要保護児童対策地域協議会活動の理解に乏しく,調整機関との連携が十分でなく,退学せざるを得ないなど,10代妊娠・出産を応援する体制になっていない。無所属の16-19歳においては,妊娠・出産からの子育て環境の整備と,子育てと親の自立へ向け要保護児童対策地域協議会での医療・保健・福祉・教育・司法など関係機関間連携強化,とりわけ,当事者参加を含めた個別ケース検討会議を利用した継続的支援体制の充実が求められる。特定妊婦に関して,要保護児童対策地域協議会の調整機関の認識が低く,母子保健に依存している地域もあるため体制強化が望まれる。
キーワード 虐待防止ネットワーク,ネグレクト,10代特定妊婦,要保護児童対策地域協議会
|
第64巻第13号 2017年11月 社会福祉士後見人の成年被後見人に対する
|
目的 成年後見制度が創設されてから17年目を迎え,その重要性は益々高まってきているが,実際の現場で成年被後見人に対して行われている後見業務内容や,その重要性の実態については明らかになっていない。そこで,社会福祉士後見人に焦点をあて,後見業務の重要性と構造を解明し,成年被後見人に対する支援の方向性を検討する。
方法 予備調査では「社会福祉士後見人の成年被後見人に対する後見業務の重要度調査」の質問項目案を作成するため,アイテムプールの作業を行い,全50項目の質問項目案を作成した。次に本調査では予備調査で作成した調査項目を用い,公益社団法人日本社会福祉士会ホームページ上の独立型社会福祉士名簿登録者一覧402名のうち,住所,氏名が公開されており郵送可能な301名に対して郵送調査を行った。回収されたデータは因子分析を行い,因子抽出には重み付けのない最小2乗法とプロマックス回転を用いた。
結果 送付者301名のうち,188名より返信があり(回収割合62.5%),そのうち,分析対象は回答に欠損を有するもの,回答選択がすべて同一のものを除いた137名の回答とした。因子分析の結果,5因子が抽出され重要度が高い順に,「財産管理と身上監護」「ソーシャルワーク技術を活かした支援」「法的事案に対する支援」「本人の意向尊重」「法的権限を越えた支援」と命名した。
結論 成年被後見人に対する後見業務において,重要性という観点から分析した結果,5つの因子で構成されていることが確認できた。「財産管理と身上監護」と「ソーシャルワーク技術を活かした支援」は因子間の多重比較の結果,有意な差は認められず並列の関係にあり,中心となる因子である。「法的事案に対する支援」は,因子として独立しながらも「財産管理と身上監護」と「ソーシャルワーク技術を活かした支援」の2つの因子に関連性を持つものであり,「本人の意向尊重」は,後見業務全体を覆い,すべての因子に関与するものである。「法的権限を越えた支援」は,法への規定もなく成年後見人は権限を持たないため,他の因子とは少し離れた位置づけであると考えた。また,専有性有無の観点から5因子を検討した結果,前者は法的な支援であり,後者は社会福祉的な支援であることが確認された。成年被後見人への「あるべき支援」を検討する際には,社会福祉的な支援の必要性についても十分考慮されるべきである。
キーワード 成年後見制度,権利擁護,社会福祉士後見人,成年被後見人,後見業務,因子分析
|
第64巻第13号 2017年11月 大都市圏地域の類型化による
皿谷 麻子(サラガイ アサコ) |
目的 本研究は医療費に関連する医療資源,保健活動,居住地環境を示す変数を用いて大都市圏の市をグループ化し,各グループの医療費の差から医療費に影響する要因の違いを分析する。
方法 政府統計調査および日本医師会が公表している市町村別データから,医療資源,保健活動,居住地環境を示す変数を用いて,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県,福岡県の市に対し,階層的クラスター分析によるグループ化を行い,各グループの医療費の差を分散分析する。
結果 大都市圏の市は5つのグループに分類できた。各グループの医療費の平均値は年齢構成を調整した地域差指標でみても入院,入院外ともに1人当たり医療費には有意差はみられなかったが,1日当たり医療費(医療費/診療日数)でみると入院,外来ともに有意差が認められ,医療機関へのアクセシビリティ変数が高いグループ,大病院変数が高いグループでは入院医療費が高く,保健衛生費が高いグループでは外来医療費が高い傾向を示した。また,1件当たりの診療日数でも入院,外来ともに有意差が認められ,入院日数は1日当たりの入院医療費が平均値よりも低いグループの方が高いグループよりも日数が長かった。
結論 大都市圏における医療費の地域差は,医療費の単価(1日当たりの診療費)に存在し,居住環境と保健活動の投入資源によって医療費の単価に影響する要因は異なっていることが明らかになった。1日当たりの入院医療費は,入院医療サービスの供給量よりもむしろ居住地から医療機関までの距離や大病院数が関係し,1日当たりの外来医療費では,保健活動が入院医療に代替している可能性が示唆された。
キーワード 医療費,地域差,大都市圏,クラスター分析
|
第64巻第13号 2017年11月 高齢ボランティアによる介護予防体操の
小澤 多賀子(コザワ タカコ) 田中 喜代次(タナカ キヨジ) 栗盛 須雅子(クリモリ スガコ) |
目的 人口減少・少子高齢化が進展するわが国では,団塊の世代が75歳以上となる平成37年を見据えて,地域包括ケアシステムの構築が喫緊の課題とされている。介護予防の充実に向けては,住民同士の支え合い(互助)による取り組みが希求されており,住民ボランティアによる体操などの通いの場づくりの醸成が期待されている。しかしながら,住民ボランティアによる体操などの通いの場づくりが,地域の介護予防へ及ぼす効果を検討した報告は少ない。そこで,本研究では市町村における高齢のボランティアによる介護予防体操普及活動と軽度の要介護認定者(要支援1・2および要介護1)の割合および介護保険料との関係を明らかにすることを目的とした。具体的には,高齢のボランティアが担う介護予防体操教室の開催実績と軽度の要介護認定者の割合の増減および介護保険料との間に関係がみられるかについて検討した。
方法 茨城県では平成17年からシルバーリハビリ体操指導士養成事業を開始し,地域在住高齢者へ介護予防体操を普及する高齢のボランティアを養成している。本研究の対象は,本事業を展開する茨城県内の全44市町村とした。分析に用いたデータは,市町村ごとの体操教室開催実績として事業開始10年経過時(平成17~26年度の総数)における高齢者人口1,000人(要介護4・5を除く)あたりの教室延べ開催数および住民参加延べ人数,地域の要介護認定状況として9年間(平成18~26年度)の軽度および重度(要介護2~5)の要介護認定者の割合の増減,介護保険料(第6期(平成27~29年度)第一号保険料),平成26年度の高齢化率とした。分析は,市町村ごとの体操教室開催実績と軽度の要介護認定者の割合の増減および介護保険料との関連について,Pearsonの相関係数により検討した。
結果 44市町村において,軽度の要介護認定者の割合の増減については,住民参加延べ人数(r=-0.30,P=0.048)と,介護保険料については,教室延べ開催数(r=-0.32,P=0.032)および住民参加延べ人数(r=-0.36,P=0.016)と,有意な負の相関がみられた。
結論 本研究の結果から,高齢のボランティアによる介護予防体操普及活動は,軽度の要介護認定者の割合および介護保険料の増加抑制に対して有用である可能性が示唆された。
キーワード 介護予防,高齢のボランティア,体操普及活動,軽度の要介護認定者の割合,介護保険料
|
第64巻第13号 2017年11月 社会医療診療行為別調査と健保組合レセプトデータ
谷原 真一(タニハラ シンイチ) 辻 雅善(ツジ マサヨシ) 川添 美紀(カワゾエ ミキ) |
目的 被用者保険の診療報酬明細書(以後,レセプト)から被保険者・被扶養者あたりの傷病大分類別レセプト件数を被保険者・被扶養者の性・年齢構成を調整した上でナショナルデータベース(NDB)から得られる人口あたり傷病大分類別レセプト件数と比較することで特定の保険制度におけるレセプトデータを用いた研究成果を日本全体に適用させる上での問題点を明らかにする。
方法 NDBによる調査として,平成26年社会医療診療行為別調査から年齢階級別傷病大分類別(主傷病)のレセプト件数を総務省統計局による人口推計(平成26年5月1日現在(確定値))に基づく総人口(0~74歳)に基づいて,人口10万人あたりの傷病大分類別レセプト件数を算出した。これを,複数の健康保険組合における性・年齢階級別被保険者・被扶養者10万人あたりの傷病大分類別レセプト件数を総務省統計局による人口推計(平成26年5月1日現在(確定値))に基づく性・年齢階級別人口に乗じた値を合算する直接法にて推計した人口10万人あたりレセプト件数と比較した。
結果 被用者保険の被保険者・被扶養者では30~69歳の者で男の割合が約56%となっていたことや65歳以上の者が占める割合が3%未満であったことなどの点で,総務省統計局による人口推計と性・年齢構成が異なっていた。NDBによる推計人口10万人あたりの傷病大分類別レセプト件数と健保組合の被保険者・被扶養者10万人あたりの傷病大分類別レセプト件数比は,性・年齢調整を行うことで,入院の「Ⅴ精神及び行動の障害」を除き,全体的により1に近い値となった。これらの比は大半の傷病大分類で統計学的に有意な差が認められたが,比の絶対値は1.1前後と,あまり大きくはなかった。
結論 被用者保険の被保険者・被扶養者の性・年齢構成は日本全体とは異なっていたが,年齢調整を行うことで人口当たりのレセプト件数の格差は小さくなる傾向が認められた。疾病大分類によっては性・年齢調整後においても統計学的に有意な差が認められたが,差の絶対値は大きいとはいえず,検定の結果以外に,影響の指標の絶対値や信頼区間を確認することによって,レセプトを用いた大規模データベースを用いた研究から得られた結果を適切に解釈し,研究成果を現実社会により適切に還元することができると考えられる。
キーワード ナショナルデータベース(NDB),被用者保険,診療報酬明細書,性・年齢調整,有病率
|
第64巻第12号 2017年10月 児童養護施設入所児のQOLにおける虐待の影響中富 尚宏(ナカトミ タカヒロ) |
目的 国際連合は,日本の社会的養護を必要とする子どもに,里親や小集団施設養育のような家庭的養育を提供するよう日本政府に勧告している。児童養護施設入所児の生活の質であるQOLの実態は,いまだ十分に明らかとなってはいない。全国の児童養護施設入所児の約60%が被虐待児である。本研究の目的は,児童養護施設入所児のQOLにおける被虐待経験の影響を検討することとした。
方法 児童養護施設入所児の4~15歳で,大舎制児童養護施設2施設37名,小舎制児童養護施設2施設8名の計45名を調査対象とした。QOL質問紙のKINDLを使用した。本研究で使用したKINDLは,身体的健康,精神的健康,自尊感情,施設内対人関係,友達,学校生活の6つの尺度と各尺度の合計からなるQOL総得点で構成されている。対象者を被虐待経験の有無で2群に分け,QOL総得点および6つの尺度においてWelchのt検定を行った。
結果 対象者の平均年齢は8.4歳(標準偏差=2.8)であり,約33%が被虐待児であった。被虐待経験がある児童養護施設入所児は,被虐待経験がない児童養護施設入所児よりもQOL総得点,自尊感情,施設内対人関係,学校生活のQOLが有意に低かった。有意差のあった各尺度ともに,おおむね効果量は大であった。
結論 これらの結果は,被虐待経験が児童養護施設入所児のQOLに負の影響を与えることを示唆している可能性がある。本結果は,虐待発生の予防がいかに重要かということを示した。
キーワード 児童養護施設,QOL,虐待,社会的養護,KINDL,虐待発生の予防
|
第64巻第12号 2017年10月 朝食に菓子パンのみを食べる人の食生活に関する調査平光 良充(ヒラミツ ヨシミチ) |
目的 朝食に菓子パンのみを食べる人の食生活を,理想的な朝食を食べる人および朝食に何も食べない人と比較することを目的として調査を行った。
方法 名古屋市が2012年1月に実施した『健康に関する市民アンケート』のうち,朝食および食生活に関する設問の回答結果について分析を行った。朝食の摂取頻度が「ほとんど毎日食べる」であり,かつ朝食の内容が「ご飯類中心」または「パン類中心」である人を理想食群,朝食の摂取頻度が「ほとんど毎日食べる」であり,かつ朝食の内容が「菓子パンのみ」である人を菓子パン群,朝食の摂取頻度が「ほとんど食べない」であり,かつ朝食の内容が「食べていない」である人を欠食群と定義した。
結果 理想食群が1,289人,菓子パン群が19人,欠食群が95人であった。菓子パン群は理想食群と比較して野菜,果物,旬の食材やカルシウムを摂取することを心掛けている人の割合が有意に低く,間食をよくする人の割合が高い傾向があり,1日のうち少なくとも1食は栄養バランスがとれた適量の食事を摂取している日の頻度も有意に低かった。菓子パン群は,欠食群と比較して野菜をたくさん摂取することを心掛けている人の割合が有意に低かった。
結論 朝食に菓子パンのみを食べる人は,単に朝食の栄養バランスが悪いだけに留まらず,昼食や夕食など他の時間帯の食事においても食事内容が好ましくない状態にある可能性が考えられる。したがって,朝食に菓子パンのみを食べる人に対しては,昼食や夕食において,野菜の摂取など栄養バランスがとれた食事を食べるように啓発する必要があると考えられる。
キーワード 朝食,菓子パン,食生活,欠食,栄養バランス
|
第64巻第12号 2017年10月 市町村国民健康保険による
鈴木 みちえ(スズキ ミチエ) 岩清水 伴美(イワシミズ トモミ) 酒井 太一(サカイ タイチ) |
目的 特定保健指導対象者が,メタボリックシンドローム(以下,MetS)に関する情報や知識を活用して自己の力で生活習慣を改善することができるよう支援することが必要である。本調査では,MetSの基礎知識,健康管理行動,健康情報把握行動で構成する「MetS改善のためのヘルスリテラシー」(以下,ヘルスリテラシー)の獲得状況と関連要因について検討した。
方法 S県中部F市の平成24年度特定保健指導対象者1,196名全員を対象に,平成25年12月に自記式質問紙調査を実施し,有効回答を得た452名(回答率37.8%)のうち,24・25年度継続受診した386名を分析対象とした。調査内容は,属性,背景およびMetSの基礎知識・健康管理行動・健康情報把握行動である。大学倫理委員会の承認を得て,回答は無記名とするが,調査票に任意の番号を記載し,行政機関の協力で,性別,年齢,2年間の健診結果と照合した。基本統計量の算定,「知識正答数」「良好健康管理行動数」「良好健康情報把握行動数」の3変数を用いてクラスター分析を行った。基礎統計量算出,各クラスターと属性・背景・健診結果との関連を検討した。
結果 MetSの基礎知識の正答者は「MetSと生活習慣病との関連」44.0%,「生活習慣病の診断基準との違い」21.2%であった。健康管理行動では「喫煙習慣なし」86.5%,「適正飲酒」65.5%であるが,「検査値変化注意」33.9%,「毎食野菜摂取」19.2%であった。健康情報把握行動は「健康関連のテレビ,新聞記事,行政機関の広報誌,リーフレットから得る」が高く,「インターネット・講演会や学習会」は低かった。ヘルスリテシ―はクラスター分析の結果「良好群」24.6%,「中間群」54.9%,「不良群」20.5%に分類された。「良好群」は女性,職業無し,一緒に運動する人がいる,保健委員の経験有りの割合が高く,翌年の健診結果の体重,BMI,腹囲,LDLが有意に減少し,HDLは有意に増加した。「不良群」は男性,職業有りの割合が高く,体重,腹囲で有意な減少があった。
結論 「MetSに関する知識」の獲得状況は好ましいといえず,良好な食習慣保有者も少なく,健康情報はテレビ,新聞,行政機関の広報誌等から得ていた。また,ヘルスリテラシ―の高低と検査値改善との有意な関連が認められた。ヘルスリテラシ―向上には,わかりやすく活用しやすい広報誌の配布,保健委員活動への参加促進によるポピュレーションアプローチが有効であると示唆を得た。さらに,有職男性には,商工会議所や農業団体等との連携による啓発活動の強化が有効ではないかと思われる。
キーワード 特定保健指導対象者,ヘルスリテラシー,ポピュレーションアプローチ,クラスター分析
|
第64巻第12号 2017年10月 社会経済的要因と特定健診結果の関連について-市町村単位の生態学的研究-中島 富志子(ナカジマ トシコ) 萱場 一則(カヤバ カズノリ) 延原 弘章(ノブハラ ヒロアキ) |
目的 メタボリックシンドロームの対策を主目的とした特定健康診査・特定保健指導では,食事や運動などの個人の生活習慣が重視されているが,健康に影響を与える要因として,環境因子である社会経済的要因も注目されている。そこで本研究では,社会経済的要因に関する5つの指標と特定健診結果との関連について検討を行った。
方法 埼玉県内市町村の財政力指数,1人当たり市町村民所得,就業者1人当たり市町村内純生産,生活保護率および完全失業率を社会経済的要因の指標とし,同県市町村国民健康保険加入者の平成23年度の特定健診結果との関連を,人口規模で調整した偏順位相関係数により生態学的に検討した。特定健診結果からは,生活習慣項目として食習慣,運動習慣,歩行または身体活動,歩行速度,体重の増減,喫煙,飲酒,睡眠に関する質問項目,身体計測項目・血液検査項目としてBMI,腹囲,収縮期血圧,拡張期血圧,中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール,HbA1c,γ-GT,判定項目として高血圧,糖尿病,脂質異常,メタボリックシンドローム判定を抽出し,いずれも男女・65歳未満/以上別に区分して平均値・該当者割合を市町村ごとに集計し,分析に供した。
結果 財政力指数および市町村民所得については,これらの指標値の高い市町村ほど,すなわち社会経済的要因の指標が良好な市町村ほど,食生活を中心に生活習慣が好ましくない状態であり,BMI,腹囲およびγ-GTもおおむね不良で,65歳以上の男では糖尿病,脂質異常,メタボリックシンドローム判定の割合が高くなっていた。一方,一般に社会経済状態の悪い指標とみなされる生活保護率についても,高い市町村ほど特定健診結果は不良の傾向がみられたが,財政力指数および市町村民所得と正の相関がみられるなど,生活保護率の高さは,必ずしも当該市町村の社会経済状態との悪さを直接反映するものではないことが示唆された。また,市町村内純生産および完全失業率と特定健診結果との間には,関連はみられなかった。
結論 財政状況が良好で生活保護率が高い自治体では,特定健診の結果が好ましくない傾向がみられた。健康状態の指標値が市町村国保加入者の平成23年度の特定健診の受診者のものであることや生態学的研究デザインであることなどの制約はあるが,自治体の社会経済状態が住民の健康状態に影響を与えている可能性が示唆された。
キーワード 特定健康診査,社会経済状態,健康格差,市町村国民健康保険
|
第64巻第12号 2017年10月 レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)における
野田 龍也(ノダ タツヤ) 久保 慎一郎(クボ シンイチロウ) 明神 大也(ミョウジン トモヤ) |
目的 レセプト情報・特定健診等情報データベース(以下,NDB)とは,わが国における保険診療の悉皆データである。NDBには,同一患者の複数レセプトを紐付ける変数として,「ID1」と「ID2」が用意されているが,就職・転職や氏名の表記ゆれ等で容易に変わり得る。本研究は,NDBにおける現行の名寄せ手法を改善し,種々の工夫により名寄せの効率を高めた新たな個人ID(ID0)を提案するとともに,その妥当性を検証することを目的としている。
方法 平成25年4月~平成26年3月の医科入院レセプト,医科入院外レセプト,DPCレセプト,調剤レセプト全体を対象とし,ID1,ID2,診療年月,転帰区分を利用した新しい名寄せアルゴリズムを開発した。アルゴリズムの妥当性を検証するため,従来のID1による名寄せとID0による名寄せを,平成25年10月1日時点の推計人口と比較した。
結果 男女とも,ID0による性年齢階級別患者数はID1による患者数を下回っており,ID1による患者数を男性で6.2%,女性で7.1%,圧縮することができた。ID1により名寄せされた患者数は,小児や高齢者,若年女性において推計人口を大きく上回っていたが,ID0により名寄せされた患者数はおおむね推計人口の範囲内に収まった。
結論 本研究で提案した新たな名寄せID(ID0)は,従来の名寄せで用いられてきたID1や,ID1とID2の併用に比し,名寄せの精度が向上した。現状ではID0が最善の名寄せ手法であり,今後,患者数の推計にはID1ではなくID0を用いることが望ましい。
キーワード NDB,レセプト,診療報酬データ,名寄せ,突合,データベース
|
第64巻第12号 2017年10月 喫煙歴とがん検診未受診および未受診理由との関連-協会けんぽ大阪支部大規模調査-山田 恵子(ヤマダ ケイコ) 藤村 昌子(フジムラ アヤコ) 諸冨 伸夫(モロトミ ノブオ)谷 智代(タニ チヨ) 今野 弘規(イマノ ヒロキ) 磯 博康(イソ ヒロヤス) |
目的 がん検診の受診率向上はがん対策の重要な課題の1つである。また,喫煙者の健康意識や健康行動を把握することは,たばこ対策の施策上,大変重要である。協会けんぽ大阪支部が実施した健康に関する大規模調査データを用い,喫煙習慣とがん検診未受診,およびがん検診未受診の理由との関連を検討した。
方法 被用者保険被扶養者全員に特定健診の受診案内と共に無記名アンケートを送付し,健診時に回収した。回答者23,122名(回答率不明)のうち,がん検診受診の有無について回答した18,609名(女性18,221名,男性388名)を解析対象とした。説明変数として喫煙歴(現在喫煙者,非喫煙者)の2値を用いた。分析方法は,①がん検診受診者に対する未受診者,②未受診の理由について,それぞれ,性別ごとに多変量調整ロジスティック回帰分析を用いた。調整変数は年齢,Body Mass Index,運動習慣の有無,就労形態とした。
結果 喫煙率は全体で8.0%(女性7.6%,男性23.2%),過去1年以内のがん検診未受診率は全体で49.9%(女性49.2%,男性81.2%)であった。非喫煙者に対して喫煙者が,がん検診未受診であるオッズ比(以下,OR)(95%信頼区間)は女性1.5(1.3-1.6,p<0.001),男性2.1(1.0-4.4,p<0.05)と有意に高かった。未受診理由については,非喫煙者に対して喫煙者が,「がんとわかったら怖い」と答えたORは女性1.7(1.3-2.0,p<0.001),男性2.4(1.0-5.8,p<0.05)と両性において有意に高かった。その他の未受診理由として,非喫煙者に対して喫煙者が,お金がかかる,受診する時間がない,予約が面倒,どこで受けられるかわからないと答えたORは,女性において,それぞれ1.5(1.3-1.8,p<0.001),1.2(1.0-1.4,p<0.05),1.3(1.2-1.5,p<0.001),1.5(1.2-1.8,p<0.001)といずれも有意に高く,男性では同様の傾向がみられたものの,有意差は認めなかった。
結論 特定健診を受診している者において,喫煙者は非喫煙者と比較してがん検診については未受診である可能性が高い。また,未受診の理由として,男女とも非喫煙者は喫煙者と比べてがんが怖いと回答した者の割合が高く,それに加えて女性ではお金がかかる,受診する時間がない,予約が面倒,どこで受けられるかわからないと答える傾向も認められた。
キーワード 喫煙,がん検診,未受診,理由
|
第64巻第11号 2017年9月 評価指標を用いた評価活動の成果と課題-組織における実践知の形式知化の過程-森本 典子(モリモト ノリコ) 平野 かよ子(ヒラノ カヨコ) |
目的 著者らが開発した「保健師による保健活動の質を評価するための評価指標」を用いて保健師が保健活動の質を話し合い評価することにより,保健師個人あるいは保健師集団,さらに保健師が所属する組織にもたらす効用と課題を明らかにすることを目的とした。
方法 著者らが開発した評価指標を用いて保健活動を評価したことの効用と課題について,検証協力自治体および事業所の計60機関の保健師を対象に,質問紙調査を実施した。
結果 評価指標を用いて評価したことで「役に立った」あるいは「役立ちそうだ」と思われたことについての結果は,「よくあてはまる」「ややあてはまる」をあわせると,全項目で8割以上が「役に立った」あるいは「役立ちそうだ」と回答があった。この結果を経験年数別に比較すると,新人期保健師は,すべての項目が8割を占めていたが,中堅期保健師は,「部署,組織」「他部署,関係機関との連携」のカテゴリーの項目の回答が相対的に低い傾向がみられた。最も効用があったと回答された項目は,「1.活動を見直す機会となる」であった。保健活動の評価を継続することについての意向は,思う:97%,思わない:2%,その他:1%であり,「思う」の中には,“適切な人員体制がないと継続が難しい”という意見や“継続するためには業務に位置づけられることが課題である”という意見があった。
結論 実際に評価指標を用いて取り組んだことで,最も「役に立つ」として挙がった項目は,「活動を見直す機会となる」「保健活動の評価が共有できる」であり,個人および集団にとっての評価することの意義が示せた。また,それと同時に,「個人」の実践知が「組織」としての知とされる過程を示し,評価指標を用いて組織内で対話して評価することが,組織としての成熟を促し,この評価指標がその成長過程を見える化させることを明らかにした。組織内の合意を得て評価指標を用いて評価することの今後の課題は,第一に評価することの重要性を保健師自身が自覚し継続することである。また,組織で評価することに取り組みやすくするためには,より評価指標の簡便化を図ることと考える。
キーワード 保健師,評価指標,保健活動評価,組織,実践知・形式知
|
第64巻第11号 2017年9月 年齢調整された,および年齢構成のみで変動させた
神山 吉輝(カミヤマ ヨシキ) |
目的 近年の日本の人口1人当たり国民医療費の推移に対する人口の年齢構成の変動およびそれ以外の要因の影響をわかりやすい形で示すことを目的とした。
方法 5歳階級幅の年齢階級別でデータが公表されている平成10~26年度の人口1人当たり国民医療費を用い,平成10年の年齢階級別の総人口を基準人口として,平成10~26年度の年齢調整された人口1人当たり医療費(以下,年齢調整1人当たり医療費)を算出した。また,平成10年度の年齢階級別の1人当たり医療費と平成10~26年の年齢階級別の総人口を用いて,人口の年齢構成の変化のみで変動させた平成10~26年度の人口1人当たり医療費を算出した。平成20~26年度においても同様の算出を行った。また,同期間については,男女別にも算出を行った。
結果 平成10~26年度の1人当たり国民医療費,年齢調整1人当たり医療費,年齢構成のみで変化させた1人当たり国民医療費の期間中の増加はそれぞれ,37.3%,9.1%,31.2%であった。年齢調整1人当たり医療費は,平成18年度までは微減傾向を示し,19年度以降は増加に転じていることが示された。一方,1人当たり国民医療費と年齢構成のみで変化させた1人当たり国民医療費とは,グラフ上でその推移がおおむね一致していた。また,平成20~26年度の1人当たり国民医療費,年齢調整1人当たり医療費,年齢構成のみで変化させた1人当たり国民医療費の期間中の増加は,それぞれ17.8%,9.1%,8.1%であった。また,同期間の男女別では,男性で17.8%,8.7%,8.6%,女性で17.8%,9.4%,7.7%であった。
考察 年齢調整1人当たり医療費が,平成18年度までは微減傾向を示したのは,介護保険制度の導入や診療報酬の引き下げ等の制度の変更のためだと考えられた。平成10~26年度で,1人当たり国民医療費と年齢構成のみで変化させた1人当たり国民医療費との推移がおおむね一致していたのも同様の理由からだと考えられた。一方,平成20~26年度では,年齢調整1人当たり医療費の増加がより明瞭に認められ,1人当たり国民医療費と年齢構成のみで変化させた1人当たり国民医療費との推移は乖離していた。それぞれの期間において,年齢構成の変化以外の要因や年齢構成の変化がどの程度医療費の変化に影響しているのかをわかりやすく示すことができたと考えられる。
キーワード 医療費,国民医療費,人口1人当たり国民医療費,年齢調整,年齢構成,高齢化
|
第64巻第11号 2017年9月 ソーシャル・キャピタルと産後うつ有病率との関連-都道府県単位の生態学的研究-榊原 文(サカキハラ アヤ) 濱野 強(ハマノ ツヨシ) 篠原 亮次(シノハラ リョウジ)秋山 有佳(アキヤマ ユウカ) 中川 昭生(ナカガワ アキオ) 山縣 然太朗(ヤマガタ ゼンタロウ) 尾崎 米厚(オサキ ヨネアツ) |
目的 平成24年の「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の改正で,ソーシャル・キャピタル(SC)の醸成と活用によって地域で親子を見守る社会の構築が明確に位置づけられた。「健やか親子21(第2次)」では「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」が基盤課題として示された。このようにSCを生かした子育ての意義が認識されつつある一方,SCが子育てのどのような状況に有益な影響を及ぼすのかは,いまだ定量的な知見が十分に示されていない。そこで本研究では,産後うつ有病率に着目し,SCとの関係を都道府県単位の生態学的研究により明らかにすることを目的とした。
方法 各都道府県のSCは,平成19年に日本総合研究所がWeb方式で行った全国アンケート調査結果を用いて,一般的な信頼度,地縁的な活動への参加状況,スポーツ・趣味・娯楽活動への参加状況をSC指標として選定した。産後うつ有病率は,平成25年に「健やか親子21」の最終評価を目的として全国の自治体を対象に実施された調査結果に基づき,エジンバラ産後うつ質問票9点以上の割合を用いた。各都道府県のSC指標を独立変数,産後うつ有病率を従属変数として,産後うつ有病率を第3四分位数9.93%に基づき2値に分類し,ロジスティック回帰分析を行った。共変量として,母の出産平均年齢,6歳未満の世帯員のいる世帯の母子世帯割合,20歳以上喫煙率,進学率,帝王切開実施率,多胎出生割合,2,500g以下出生割合,25~44歳の育児をしている女性の有業率を用いた。
結果 単変量ロジスティック回帰分析の結果,スポーツ・趣味・娯楽活動への参加状況と産後うつ有病率との間には統計学的に有意な関連を認めた(オッズ比=0.45,95%信頼区間(0.21-0.98),p=0.045)が,一般的な信頼度,および地縁的な活動への参加状況は,同様の結果を認めなかった。多重ロジスティック回帰分析の結果も同様であった。
結論 スポーツ・趣味・娯楽活動といった目的志向の活動への参加が良好な都道府県では,産後うつ有病率が低いことが示された。スポーツ・趣味・娯楽活動は,インフォーマルな地域活動の活発さを示していると考えられ,地域活動を通じた交流が子育て相談の機会にもなることから,産後うつ有病率に関連したのではないかと推察した。
キーワード 産後うつ病,ソーシャル・キャピタル,生態学的研究
|
第64巻第11号 2017年9月 レセプトデータを使用した虚血性心疾患における
藤田 貴子(フジタ タカコ) 原野 由美(ハラノ ユミ) |
目的 わが国においては,心疾患は悪性腫瘍に次いで二番目に死亡順位が高い。また,既設の二次医療圏が入院医療提供を行う圏域として成り立っていない場合は,見直しの検討が必要とされている。医療圏の設定に関する研究はあるものの,加入保険別の受療行動の違いを踏まえた検証はされていない。このことから,本研究では,福岡県内の2保険者のレセプトデータを利用し,虚血性心疾患による入院受療行動の現状を保険者ごとに二次医療圏別に可視化し,現状に合った医療圏の設定について検証を行った。
方法 福岡県後期高齢者医療広域連合および福岡県国民健康保険の被保険者を対象とした。対象期間は2014年4月から2015年3月とし,この期間に虚血性心疾患による入院がある被保険者を抽出し,入院全体,経皮的冠動脈形成術,冠動脈・大動脈バイパス移植術のあるものを集計した。なお,疑い,後遺症によるものは除外した。福岡県の13の二次医療圏別に患者居住圏域と医療機関所在圏域を基に,保険者別の二次医療圏完結率,移動率,交流率を算出した。また,各医療圏の交流率から数値の高い二次医療圏同士を集約し,新たな医療圏の設定の可能性について検証した。
結果 虚血性心疾患による入院を保険者別,二次医療圏別に集計した結果,入院全体の完結率は,23.0%~98.2%,経皮的冠動脈形成術の完結率は,0~98.7%,開胸手術の完結率は0~100%と差が大きかった。また,流入率,流出率についても同様に差が大きく,流入率が90%を超える圏域や,経皮的冠動脈形成術や開胸手術における流出率が100%の圏域もあり,集約化の必要性が認められた。入院全体での交流率を保険者別に算出し,数値の高い医療圏を集約したところ,カットオフ値を1.50とした場合は5および6医療圏,2.0とした場合は7医療圏へ集約することができた。
結論 本研究の結果から,現在の二次医療圏の設定では入院医療は完結できていないこと,加入保険により居住医療圏内での完結率に差があることが明らかとなった。また,先行研究の結果を踏まえ,医療圏の集約を試みたところ,最終的には4医療圏が妥当であると考えられた。現在の医療圏で入院医療は完結できていないため,現状に見合った計画を実施するためにも,保険者別や疾患別のデータ等を使用して受療行動を可視化し,医療圏を見直す必要がある。
キーワード レセプトデータ,虚血性心疾患,二次医療圏,保険者
|
第64巻第11号 2017年9月 特別養護老人ホームからの在宅復帰の可否と
古川 和稔(フルカワ カズトシ) |
目的 介護保険法において指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム;以下,特養)は,入所者の在宅復帰を検討することと明記されている。また,地域包括ケアシステムでは,特養には入所施設としての機能だけでなく在宅で暮らす要介護者の在宅生活継続を支援するという機能も期待されている。そこで,特養に勤務する職員の在宅復帰に関する意識と,在宅復帰の可否に影響を与える要因を明らかにすることを目的に調査を実施した。
方法 A県内に所在する特養のうち,事前の調査協力要請に対して承諾が得られた47施設に勤務するケアに関わる全職員を対象に無記名自記式質問紙調査を郵送法によって実施した。2015年7月,調査票2,535通を郵送した。調査内容は,回答者の基本属性,在宅復帰に関する職員の意識14項目,在宅復帰を実践する上で必要な支援20項目とした。
結果 回収数は929名(回収率36.6%)であった。職種は介護職員が最も多く74.0%,次いで看護職員(11.2%)であった。「特養からの在宅復帰は可能だと思う」という設問には58.9%が肯定的回答を示した。「利用者は在宅復帰を望んでいると思う」という設問には87.9%が肯定的回答を示したが,「家族は在宅復帰を望んでいると思う」に対する肯定的回答は52.4%であり,35.5ポイントの差があった。「特養からの在宅復帰は可能だと思う」に対する回答を従属変数としたロジスティック回帰分析の結果,「高齢者は在宅で暮らした方が良い」「自主的に在宅復帰について学んでいる」という職員の意欲面と,「現在の職場は在宅復帰に取り組んでいる」「直属の上司は在宅復帰を意識している」という職場環境が関連する結果を示した。また,「在宅復帰を実践する上で必要な支援」では,家族支援に関する項目が有意な結果を示した。
結論 特養と地域密着型特養の合計数は9,452施設で,今後も増加すると見込まれていることから,これらの施設が在宅復帰や在宅生活継続に取り組むか否かは,地域包括ケアシステムの完成に向けて非常に大きな影響を与えるであろう。「在宅復帰は可能だと思う」という職員の意識に,職員の意欲面と職場環境が関連する結果を示したことから,在宅復帰に向けた職員の意欲の高まりと,在宅復帰に取り組む職場環境の改善が相まって進めば,その相乗効果により,特養からの在宅復帰の可能性が高まることが示唆されたと考える。また,家族支援の方法と位置づけを明確にする必要があると考える。
キーワード 特別養護老人ホーム,在宅復帰,職員の意識,必要な支援,地域包括ケア,在宅・入所相互利用
|
第64巻第11号 2017年9月 就学前における教育・保育施設の選択が
|
目的 就学前における幼稚園・保育所といった教育・保育施設の種別の選択が,就学後の学校適応や問題行動といった児童の非認知的な側面の発達に与える影響について,保育所入所と母親の就業の同時決定性等の特性を踏まえて,21世紀出生児縦断調査の調査票データを活用した傾向スコアマッチングにより実証分析を行った。
方法 本研究では,同調査の第4回(調査時年齢3歳6カ月)から第6回(同5歳6カ月)までの期間に母親が継続して週20時間以上就業していると推定される世帯(N=8,056)のうち,当該期間を通じて幼稚園に通園している世帯(N=263)(「幼稚園通園世帯」)および当該期間を通じて保育所に通所している世帯(N=4,816)(「保育所通所世帯」)を分析対象とした。分析方法としては幼稚園通園世帯を処置群として,保育所通所世帯から,処置群と同じ背景要因を持つ対照群のペアを,父母の特性,世帯収入,父母の就業状況,児童の特性,児童の発育状況,家庭環境,地域特性等を共変量として,傾向スコアマッチングにより抽出した。これらのペアについて,同調査の結果より作成した小学1年~中学1年の「学校適応指標」,小学1~6年の「問題行動指標」を従属変数,幼稚園通園ダミーおよび学年ダミーを独立変数として,固定効果モデルによる回帰分析を行った。
結果 母親が就業している世帯において,傾向スコアによる調整前の幼稚園通園世帯と保育所通所世帯の比較では,複数の学校適応指標および問題行動指標において有意差が認められたが,傾向スコアによる調整後の推定結果では,幼稚園通園の学校適応指標および問題行動指標への影響は有意ではなかった。
結論 大規模縦断調査を用いた実証分析の結果,母親が就業している世帯について,3歳児から5歳児までの就学前における幼稚園・保育所といった教育・保育施設の種別の違いは,就学後の学校適応や問題行動といった非認知的な側面の発育に必ずしも影響をもたらすものではないことが示唆された。
キーワード 21世紀出生児縦断調査,傾向スコア,幼稚園,保育所,学校適応,問題行動
|
第64巻第8号 2017年8月 交通事故被害者と家族に対する
佐藤 舞(サトウ マイ) |
目的 医療現場で対応する社会福祉士(以下,ソーシャルワーカー)は,被害者やその家族への支援,退院後の次なる支援者や支援機関につなぐことに対する不安や難しさなど,多くの問題を抱えている。その背景には,ソーシャルワーカー養成校において交通事故に対する援助技術習得のためのカリキュラムが義務づけられてはいないことなどが考えられるが明確でない。そこで病院に勤務するソーシャルワーカーへのアンケート調査の分析を通して,被害者に関わるソーシャルワーカーの抱える不安や問題点を明確にし,今後の医療福祉の養成校や講習会等における,交通事故被害者への関与についての教育の充実を図ることを目的とした。
方法 全国の地域医療支援病院,特定機能病院,回復期リハビリテーション病棟協会に登録されている病院,計1,450箇所に勤務するソーシャルワーカーを対象に,無記名自記式の質問調査を実施した。調査項目は,基本属性,交通事故関連のソーシャルワーク内容や連携をとった職種や機関,業務を遂行する上で感じている問題点や不安点,養成校での交通事故関連の学習経験の有無と今後の事前学習の希望を自由記載でデータを得た。自由記載の項目については,テキストデータをKJ法によりサブカテゴリーに分類し,さらにキー概念へ収斂した。
結果 交通事故被害者やその家族とのソーシャルワークで難しい・不安を感じていると回答した者は86.1%であり,「知識・経験不足」「社会資源の不足」「当事者の問題」「事故の複雑さ」が挙げられた。また養成校で交通事故関連の授業等がなかったと回答した者は,全体の89.7%であり,養成校で交通事故関連の授業等があった方がよいと回答した者は,全体の82.6%であった。具体的な内容に関しては「事例検討」「制度の学習」「心理的サポート方法の習得」などが挙げられた。
結論 交通事故被害者・家族に対する支援に対して,多くのソーシャルワーカーが不安や困難さを感じていることが改めて明らかとなった。交通事故のソーシャルワークは個別性が高く,社会保障制度の複雑さや社会資源が不足していることがさらに支援を複雑化させる原因であると考えられる。養成校での交通事故関連の授業に関しては,学生時代から社会保障制度の学習や事例検討を通しての交通事故被害の理解に取り組ませることで,より早期の生活支援や社会復帰することにつながると考える。
キーワード 交通事故,交通事故被害者,家族,ソーシャルワーカー,退院支援,教育の充実
|
第64巻第8号 2017年8月 30代女性の14年間における介護選択,愛情,扶養義務感の変化-2000-2001年および2014年のパネル調査による2地区の比較-太田 美緒(オオタ ミオ) 甲斐 一郎(カイ イチロウ) 石崎 達郎(イシザキ タツロウ) |
目的 介護保険導入直後の2000-2001年,特徴の異なる2地区(東京近郊A市住宅地区,農村地区)在住の30代女性を対象に,親が要介護状態となった場合,どうするのがよいかを問う一般介護選択(自宅介護,施設介護),対象者が主介護者になる場合どうするかを問う主体的介護選択,およびその関連要因を分析した。同調査から14年後,介護が身近な問題となった対象者にパネル調査を実施,介護選択および前回調査で関連要因として指摘された愛情と扶養義務感の変化,2地区の相違点について分析し,介護者に対する適切な支援策の立案に寄与することを目的とした。
方法 2014年8月,2000-2001年に実施した一般介護選択および主体的介護選択に関する調査のパネル調査を実施した。前回の分析対象者256人(住宅地区176人,農村地区80人)のうち,引き続き同地区に在住している186人(各々114人,72人)に対し調査依頼の手紙を送付,承諾した45人(31人,14人)に質問紙調査票を郵送,回収も郵送にて行った。
結果 前回調査との比較では,実の親,義理の親に対する一般介護選択,主体的介護選択ともに自宅介護率は2地区とも低下傾向だった。特に農村地区の義理の親に対する一般介護選択では自宅介護選択率が41.7ポイントの大幅な低下を示した。前回調査で確認された関連要因の愛情は,対実母,義母ともに2地区において低下傾向にあった。扶養義務感は,前回調査では対実親,義理の親の区別をしなかったため,比較検定ができないが,2地区とも低下した。
結論 農村地区における対義理の親の一般介護選択では,自宅介護率が大幅に低下したにも関わらず,対義母の主体的介護選択では変化がなく66.7%と高いのは,自宅介護を望んでいないにも関わらず,現実には介護せざるを得ない嫁の現状が反映されている。義母に対する愛情や扶養義務感も低下している中,嫁としての立場上介護せざるを得ない状況を避けるためには,介護を家庭内のみの問題として抱え込まず,地域包括支援センター等に助言を求め,介護サービスに関する情報を積極的に取得する等,自らの介護選択に真摯に向き合う準備と覚悟が問われている。
キーワード 介護選択,愛情,扶養義務感,パネル調査,2地区比較
|
第64巻第8号 2017年8月 社会保障の分野別にみた高福祉高負担への支持-年金・高齢者医療・介護の比較-武川 正吾(タケガワ ショウゴ) 角 能(カド ヨク) |
目的 本研究は年金,高齢者医療,介護という社会保障の個別分野間の,高福祉高負担を支持する者の割合と構造の比較を行う。
方法 2013年1月に15~79歳の日本全国の1,200名を対象に実施された,第483回NOS(日本リサーチセンター・オムニバス・サーベイ)の調査のデータの一部を用いた。この調査は,エリア,都市規模や性別,年代に関して日本の人口比に合致するように,住宅地図データベースから世帯を抽出して割り当てた個人に対して,調査員による個別訪問留置調査の手法を用いた。分析方法として,2項ロジスティック回帰分析の手法を用いた。社会保障全般,年金,高齢者医療,介護それぞれについての回答を2値変数にして,従属変数とした。独立変数としては,「性別」「学歴」「等価所得」「世帯類型」を用いた。また,主として高齢者を受給者とする社会保障制度に対する距離感が年齢によって異なることから,50歳以上と50歳未満にサンプルを分割して分析を行った。統計的な有意水準は5%とした。
結果 高福祉高負担支持の程度を比較すると,社会保障全般が最も高く,次に年金と介護の順番となり,高齢者医療が最も低かった。次に高福祉高負担支持の構造を分野別にみると,社会保障全般については,50歳以上,50歳未満ともに,学歴の高さが高福祉高負担支持の割合を有意に高めていた。3つの個別の社会保障制度については,50歳未満では,高福祉高負担支持に対して有意な効果が見られる独立変数はなかった。50歳以上では,3つの制度すべてにおいて,等価所得の高さが高福祉高負担支持を有意に高めていた。
結論 50歳未満と異なり,50歳以上の年齢階層では個別の社会保障に対する高福祉高負担の支持は,すべて等価所得によって影響を受けていた。社会保障の受給が現実の段階になってくると,個別の社会保障の財源である税金や社会保険料を負担する能力が相対的に高い高所得者が,財源,給付共に拡充を支持するようになった。今後は低所得者の財源負担が可能な制度設計が重要であろう。
キーワード 高福祉高負担,所得再分配,福祉意識,社会保障,高齢者福祉
|
第64巻第8号 2017年8月 在日韓国朝鮮人における肝がん死亡の推移大島 明(オオシマ アキラ) |
目的 在日韓国朝鮮人においては日本人および韓国に比して肝がん死亡が多いことが先行研究によって明らかにされている。しかし,2000年以降の在日韓国朝鮮人における肝がん死亡の推移に関しての報告はなされていない。そこで,公表された死亡データに基づき,1995年から2015年までの在日韓国朝鮮人における肝がん死亡の推移を調べるとともに,日本人および韓国における肝がん死亡の推移と比較してその要因について考察する。
方法 在日韓国朝鮮人における死亡データは,人口動態調査別表下巻日本における外国人,外国における日本人第1表死亡数(日本における外国人-国籍別,外国における日本人),性・死因(死因簡単分類)別から得た。そして,1995年,2000年,2005年,2010年,2015年の国勢調査による在日韓国朝鮮人の性別,5歳年齢階級別人口と各年における日本人における性別年齢階級別死亡率により肝がんを含む主要部位のがん等による死亡の期待値(E)を計算して実測値(O)との比O/Eにより標準化死亡比(Standardized Mortality Ratio, SMR)を算出した。一方,日本人の年齢調整肝がん死亡率(標準人口:世界人口)の推移のデータは国立がん研究センターがん情報サービス「統計」から,韓国の年齢調整肝がん死亡率の推移はWHOのCancer Mortality Databaseから得た。在日韓国朝鮮人における肝がんの年齢調整死亡率は便宜的に日本人の肝がん死亡率に上記の肝がんのSMRを掛け合わせて求めた。
結果 1995年から2015年における在日韓国朝鮮人の肝がんのSMRは,男では2.75~4.11,女でも2.45~3.40と,胃がん,大腸がん,肺がん,全がん,全死因のSMRに比して高かった。1995年から2015年にかけての肝がんの年齢調整死亡率は,在日韓国朝鮮人においても,日本人や韓国と同様に減少していた。
結論 在日韓国朝鮮人における肝がん死亡は,日本人や韓国に比して約3倍前後高いが,1995年以降日本人や韓国と同様に減少していた。
キーワード 在日韓国朝鮮人,肝がん死亡,B型肝炎ウイルス,C型肝炎ウイルス
|
第64巻第8号 2017年8月 同居家族からのソーシャル・サポートが
山脇 功次(ヤマワキ コウジ) 黒田 佑次郎(クロダ ユウジロウ) 安村 誠司(ヤスムラ セイジ) |
目目的 高齢者の閉じこもりは,要介護状態のリスクファクターである。独居高齢者に比べ同居家族がいる高齢者に閉じこもりが多いことから,家庭内での高齢者へのサポート状況が閉じこもり発生に関連すると考えられる。同居家族がいる閉じこもりは,家族関係が希薄であり,家庭内で心理的に孤立しやすい状況にあることや,家族による過干渉なサポートの可能性が推察される。本研究は,閉じこもり予防・支援に資する目的で,同居家族からのソーシャル・サポートが閉じこもり発生に与える影響を検討した。
方法 福島県大玉村在住の70歳以上高齢者のうち,要支援・要介護認定者,入院中の者を除く全1,347人を対象とした。初回調査は2004年と2005年,追跡調査は2010年に実施した。初回および追跡調査の回答者は839人であった。このうち初回時に独居と閉じこもりを除外し,初回および追跡調査における閉じこもり項目の欠損を除外した665人を分析対象とした。調査項目は,基本属性,家族構成,ソーシャル・サポート(情緒的・手段的),閉じこもりの有無,身体・心理的要因について回答を求めた。ソーシャル・サポートを情緒的,手段的サポートに分けた。性別,年齢,および単変量解析で閉じこもり発生に関連する変数を調整変数としたうえで,2種のサポートを説明変数,閉じこもり項目を目的変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った。
結果 性別は男性284人(42.7%),女性381人(57.3%),年齢の平均値は76.0±4.6歳であった。追跡調査時までの閉じこもり発生は101人(15.2%)であった。閉じこもり発生は非閉じこもりと比べて,年齢(p<0.001),聴力(p=0.001),うつ傾向(p=0.002)の値が有意に高かった。一方,老研式活動能力指標(p<0.001),生活体力指標(p=0.014)は,閉じこもり発生が有意に低かった。多重ロジスティック回帰分析の結果,同居家族からのソーシャル・サポートと閉じこもり発生の関連には,統計的に有意な関連が認められなかった。
結論 同居家族からのソーシャル・サポートと閉じこもり発生の関連には,統計的に有意な関連が認められなかった。さらなる追跡検討が今後の課題である。
キーワード 閉じこもり,ソーシャル・サポート,同居家族,コホート研究
|
第64巻第7号 2017年7月 先天代謝異常症児と家族の生活の医療社会面
|
目的 先天代謝異常症児と家族の生活の医療社会面と健康関連QOLの実態を明らかにし,今後関わっていく患児と家族への理解を深め,必要な支援の方向性の示唆を得ることである。
方法 先天代謝異常症患者登録制度Japan Registration System for Metabolic & Inherited Diseases(以下,JaSMIn)登録者のうち,調査時点において日本国内在住の7歳以上20歳以下の患児本人ときょうだい,および主たる養育者とその配偶者を対象とした無記名自己記入式質問紙調査を行った。調査期間は平成27年8~11月であった。質問項目は,対象者の生活の医療社会面(患児や家族の生活における疾患や治療に関すること)および健康関連QOLとした。健康関連QOLの測定は,患児およびきょうだいには子どもの健康関連QOLを測定する尺度KINDLを,主たる養育者および配偶者にはWHOQOL26を用いた。
結果 203家族より質問紙の返送が得られ,有効回答は201家族であった(有効回答率37.8%)。主たる養育者が回答した先天代謝異常症児の平均年齢は10.2歳であり,年齢分布は未就学児が3割,小学生が3割,中高生が3割,18〜20歳が1割であった。診断分類別に最も多かったのはアミノ酸代謝異常で3割,次いでライソゾーム病が2割,有機酸代謝異常が1割であった。約半数の患児が食事療法を受けており,酵素補充療法・栄養素補充を行っているのはそれぞれ15 %程度であった。主たる養育者の平均年齢は,42.2歳であり,約半数が専業主婦で,8割が子育て世代の30〜40代だった。主たる養育者の7割以上が同病の会に参加しており,QOL尺度の平均得点は3.1点であった。配偶者の平均年齢は,42.9歳であり,8割が30〜40代と働き盛りの世代の父親であった。主たる療育者同様に,9割の配偶者が児の療育に関する不安を抱いており,QOL尺度の平均得点は3.4点であった。患児本人が回答した平均年齢は,12.0歳で性別は男女半々であった。年齢分布は,小学生が約半数,中高生が4割,2名は18歳であった。患児のQOL尺度の平均得点は69.2点であった。きょうだいの平均年齢は,12.7歳で性別は3割が男児であった。6割のきょうだいが患児より年上であった。きょうだいのQOL尺度の平均得点は70.9点であった。
結論 本研究により,患児と主たる養育者のQOLは,既知集団と比べて低い傾向にあり,配偶者と患児のきょうだいのQOLは高い傾向にあるという実態が明らかになった。また,専門医以外の医療者への疾患・治療に関する知識普及が急務であり,ピアサポートを受けていない患児と家族をどのように支援していくか検討する必要があることが示唆された。
キーワード 先天代謝異常症,家族,QOL,医療社会面,ピアサポート
|
第64巻第7号 2017年7月 宮古島市における飲酒の現状と課題-AUDITの調査結果から-波名城 翔(ハナシロ ショウ) 下地 由美子(シモジ ユミコ) |
目的 近年,アルコールと自殺の関係性が指摘されており,全国と比較し自殺率の高い地域である宮古島市(以下,当市)を対象に飲酒量の調査を行い,当市の飲酒問題の現状と課題について示唆を得ることを目的とした。
方法 平成26年4月1日から平成28年3月31日の期間に,①当課が開催した飲酒に関する講演会および研修会の参加者,②地域に出向き飲酒に関する講義を行った際の参加者,③企業に出向き飲酒に関する講義を行った際の参加者(他企業と連携し,その企業で働く多量飲酒者への節酒プログラムを実施した際に回収した分を含む)にAUDIT(アルコール使用障害特定テスト)を配布し回収を行った。その結果をSPSSで分析し全国調査と比較した。
結果 有効回答数は891人であった。全国調査と比較を行うと,「問題飲酒群」「アルコール依存症疑い群」は男性81.2%,女性10.5%で,全国調査よりも高かった。年代別比較では,男性は20代,40代,50代で,女性は20代,40代で多量飲酒割合が高かった。また,AUDIT-C(簡易版)の項目比較では,全国調査が「毎日少量程度の飲酒」が多いのに対して当市は「たまに大量に飲酒する」傾向がみられ,その背景には,酒の手に入りやすさ,お祝いの数,飲酒文化の変化,そして,宮古島の飲酒方法であるオトーリが影響していることが考えられた。
結論 当市では,機会飲酒の割合が高いにも関わらず,「問題飲酒群」「アルコール依存症疑い群」が多い理由として,一度の飲酒量の多さがあり,その背景にはオトーリが関係していると考えられる。常習的な飲酒者の割合は少ないため,今後,オトーリの在り方を再考することで,当市の多量飲酒者が減少することが期待できる。
キーワード 自殺対策,アルコール,多量飲酒,地域特性,オトーリ
|
第64巻第7号 2017年7月 中小規模の病院に勤務する看護師の基本属性と
山田 桜子(ヤマダ サクラコ) 伊東 美佐江(イトウ ミサエ) |
目的 中小規模の病院に勤務する看護師を対象として,その基本属性,ライフスタイルおよび離職意向の関連を明らかにすることである。
方法 インターネットにおいて一般公開されているWAM NETホームページから,全国の100床以上200床未満の病床数を有する一般病院2,267病院のうち,単純無作為に200施設を抽出した。看護師の選択条件は,病棟(精神科・救急科を除く)において,管理責任者の役職に就いておらず,1年以上の看護師(准看護師を含む)としての勤務経験のある者とし,1施設当たり20~50代の各年代の5名ずつ計20名とした。調査内容は,基本属性,ライフスタイル,離職意向である。t検定,一元配置分散分析と多重比較検定(Tukey法)により,基本属性ごとにライフスタイルを比較した。また,年齢,子どもの数,看護職としての経験年数,現在の病院での勤続年数,時間外労働時間数,服薬・疾患の有無,生活習慣病リスクを独立変数,離職意向を従属変数とする単回帰分析を行った。その後,カテゴリー化した基本属性,単回帰分析において有意水準p<0.05となった項目を独立変数,離職意向を従属変数とする重回帰分析(ステップワイズ法)を行った。
結果 年代では30代が50代より,単独世帯群がその他の世帯群より,未婚群が既婚群より,子どもがいない群がいる群より,それぞれ有意に生活習慣病リスクが高かった(p<0.05)。また,看護職としての経験年数では5年未満群が10年以上群より,勤務形態では3交代制群が2交代制群と日勤のみ群より,いずれも有意に生活習慣病リスクが高かった(p<0.05)。さらに,重回帰分析の結果,離職意向に影響する要因として,年齢(β=-0.17,p=0.00),生活習慣病リスク(β=0.17,p=0.00)が有意な変数として認められた。
結論 ライフステージの変化に伴う様々なライフイベントの経験は,ライフスタイルを多様化させ,健康管理について改めて見直す契機の1つとなる。本研究における生活習慣病リスクは,ストレスや精神健康度を介して,離職意向に影響している可能性が示唆された。
キーワード 看護師,ライフスタイル,生活習慣病リスク,離職意向,重回帰分析
|
第64巻第7号 2017年7月 訪問看護師が働き続けられる職場環境要因の検討谷垣 靜子(タニガキ シズコ) 乗越 千枝(ノリコシ チエ) 長江 弘子(ナガエ ヒロコ)仁科 祐子(ニシナ ユウコ) 岡田 麻里(オカダ マリ) |
目的 在宅療養者・家族が期待する良質な訪問看護サービス提供には,訪問看護ステーションの安定的な経営と訪問看護師の確保・定着・育成が不可欠である。そこで,本研究の目的は,訪問看護師の就業継続意志と職場環境要因の関連を検討することである。
方法 調査対象は,2013年1月時点で全国訪問看護事業協会に加盟する3,979カ所のステーションの内,1/3の割合になるよう無作為抽出をした1,466カ所のステーションである。ステーションに無記名自記式質問紙調査を郵送にて配布した。回答者は,ステーション管理者を除いた看護職スタッフ1名とした。調査内容は,性別,年齢,看護経験年数,訪問看護ステーションの概要,現在の訪問看護ステーションでの就業継続の意向,賃金・仕事の満足度などである。職場環境項目は,研究者らの調査内容とマグネット・ホスピタルの特性に基づき看護実践環境に焦点化して開発されたPES-NWI項目を組み合わせて作成した13項目である。
結果 回収した457票(回収率33.6%)のすべてを有効(有効回答率33.6%)として分析を行った。就業継続意志の「できるだけ長く働き続けたい」と回答した人は372人(81.4%)であった。職場環境項目のうち「療養者のケアについて話し合う機会と時間がある」「家庭の事情により生じる事態に柔軟な勤務対応をしている」「ステーション管理者は相談しやすい」の各オッズ比が各々2.300,2.027,1.986と得点が高いほど就業継続意志の割合が高くなった。
結論 訪問看護師を引きつけ,定着させる職場環境を築くことは,訪問看護のやりがいを生み出すことにつながると考える。今後は,この内容をもとに訪問看護ステーション管理者向けの人材定着・育成プログラムの開発を検討していきたい。
キーワード 訪問看護師,訪問看護ステーション,就業継続意志,職場環境
|
第64巻第7号 2017年7月 がん患者の心理社会的サポートサービスの利用に
松井 智子(マツイ トモコ) |
目的 がん患者を対象とした心理社会的サポートサービスの利用に対する態度尺度を作成し,心理社会的サポートサービスの利用行動との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 対象要件を満たす960名のがん患者にインターネットによるアンケート調査への参加を依頼し,有効回答が得られた712名を対象として分析を行った。712名のうち,男性351名(49.3%),女性361名(50.7%),平均年齢は58.1歳(標準偏差=11.9)であった。
結果 作成した尺度は,「利用後のポジティブな結果期待」「主観的規範」「スティグマに対する抵抗感」「利用後のネガティブな結果に対する懸念」「援助要請に対する抵抗感」の32項目5因子からなり,信頼性および妥当性が確認された。各因子の合計得点と利用ステージとの関連を検討した結果,利用経験がない人は「利用後のポジティブな結果期待」が低く,「スティグマに対する抵抗感」「利用後のネガティブな結果に対する懸念」「援助要請に対する抵抗感」のネガティブな方向の要因が高かった。また,「主観的規範」については特に無関心期において低いことが示された。
結論 本研究の結果より,作成した尺度の有用性が示された。また,各行動変容のステージによって心理的特徴が異なることが示され,今後の利用促進のための介入法の開発に向けて有益な知見が得られたと考えられる。
キーワード 心理社会的サポートサービス,援助要請行動,がん患者
|
第64巻第7号 2017年7月 地域在住高齢者における認知機能調査宮原 洋八(ミヤバラ ヒロヤ) 上城 憲司(カミジョウ ケンジ) 井上 忠俊(イノウエ タダトシ)田中 純子(タナカ ジュンコ) 納戸 美佐子(ノト ミサコ) 中村 貴志(ナカムラ タカシ) |
目的 地域在住高齢者のMMSE得点を性別に分類し年齢階級,教育年数別に検討することで,認知症に対する介入研究の基礎資料とすることを目的とした。
方法 佐賀県3町自治体の呼びかけで参加した65歳以上の高齢者698人が対象であった(平均年齢:男性75.7±5.8歳,女性78.3±5.2歳)。基本的属性には,年齢,性別,教育歴を聴取し,認知機能に関してMMSEを用いて調査を行った。
結果 年齢階級ごとのMMSE得点の平均値と標準偏差を男女別に示した結果,各年齢階級におけるMMSE得点は,男性では有意差は認められなかった。女性は65~69歳群と70~74歳群のMMSE得点が75~79歳群,80~84歳群,85歳以上群より有意に高かった。教育年数ごとのMMSE得点の平均値と標準偏差を男女別に示した結果,各教育年数におけるMMSE得点は,男性では9年以上群が6年以下群より有意に高かった。女性は9年以上群が6年以下群および7-8年群より有意に高かった。MMSE得点において28点以上を正常,24-27点をMCI,23点以下を認知症に分けた結果,MCI群の割合が男女とも3割あった。
結論 各年齢階級におけるMMSE得点は女性では年齢階級が上がるにつれて平均値は有意に低かった。男女ともに65~69歳群のMMSE得点平均値は27点代で85歳以上の平均値は25点でありその差は2点であった。他地域と比較すると明らかに年代差は小さかった。各教育年数におけるMMSE得点は男女とも教育年数が上がるにつれて平均値は有意に高かった。本研究においても,教育年数の低さがMMSE得点を低くした要因と推察される。認知機能を早期に調査し認知症を防止する手立てが必要であることが示唆された。
キーワード 地域高齢者,認知症,MMSE
|
第64巻第6号 2017年6月 介護福祉士が受けるハラスメントと職務・職場継続意向の関連原野 かおり(ハラノ カオリ) 出井 涼介(デイ リョウスケ) 中嶋 和夫(ナカジマ カズオ) |
目的 本研究は,介護人材確保に資する資料を得ることをねらいに介護福祉士が受けるハラスメントと職務・職場継続意向の関係を明らかにすることを目的とした。
方法 A県内すべての特別養護老人ホームおよび老人保健施設に勤務する介護福祉士1,347名を対象に郵送法による質問紙調査を実施した。調査項目は,対象者の属性(性別,年齢,介護職経験期間,現施設勤続期間等),職場ハラスメント被害,職務・職場継続意向とした。統計解析には分析に必要な調査項目に欠損値がない743名分のデータを使用し,職場ハラスメント被害と職務・職場継続意向の関連性を構造方程式モデリングにより検討した。
結果 分析モデルのデータに対する適合度は,CFI=0.977,RMSEA=0.028であり,職場ハラスメント被害と職務・職場継続意向の間に有意な負の関連性が認められた。
結論 介護人材の確保には,ハラスメントが発生しない職場環境の整備が急務である。
キーワード 介護福祉士,介護人材確保,ハラスメント,職務継続意向,職場継続意向
|
第64巻第6号 2017年6月 認知症サポーター養成講座受講による
南部 泰士(ナンブ ヒロヒト) |
目的 本研究は,認知症サポーター養成講座(以下,養成講座)の受講が,看護学生の認知症に対する知識,態度,老親扶養意識,介護意識の社会化にあたえる影響を明らかにし,在宅看護学および公衆衛生看護学における認知症高齢者に関する講義や実習の展開に関し,他職種との協働を推進するための基礎資料とすることを目的とした。
方法 対象はA看護大学2年次の学生71人(男性9人,女性62人)とした。質問紙調査にて養成講座前後に,認知症高齢者のイメージ,認知症の知識,老親扶養意識,介護意識の社会化について回答を得て比較した。
結果 養成講座受講後,学生の「認知症高齢者のイメージ」が肯定的となり,「認知症の基礎知識」が豊かになり,「老親扶養意識」の「手段的扶養意識」における考えに変化がみられた。また,「自分が認知症を発症したときに家族に期待する介護意識」について,「家族と社会」の両者に担ってほしいと回答した割合が増加した。
結論 養成講座は,看護学生にとって,認知症高齢者や家族についての知識を豊かにするとともに,認知症を自身の問題として認識することができるようにするという意義を持ち,看護学生が地域包括ケアシステムを理解する上で重要な学習内容の1つとなるものである。
キーワード 認知症サポーター養成講座,認知症,看護学生,意識の変化,看護基礎教育
|
第64巻第6号 2017年6月 都道府県別にみた主たる家族介護者である
|
目的 介護と就業の両立はわが国の喫緊の課題である。介護と就業についての状況を地域別に把握することは,両立を決定する要因を検証し,支援政策を考える上で重要だと思われるが,そうした先行研究は存在しない。そこで,本研究では,家族の介護を担うことが多く,一方で労働力としても期待される中高年女性を対象とし,都道府県別に,同居の主介護者である女性と主介護者以外の女性の就業および就業希望の状況を比較することとした。
方法 平成25年国民生活基礎調査の世帯票を用いた。中高年女性を対象とし,都道府県別に,同居の主介護者である女性と主介護者以外の女性の就業および就業希望の状況を集計し,図示した。
結果 主介護者である女性は主介護者以外の女性よりも就業している割合が低く,主介護者である女性の平均が57.8%であったのに対し,主介護者以外の女性の平均は66.9%であった。就業希望の割合は主介護者である女性の方が高く,主介護者である女性の平均が16.4%であったのに対し,主介護者以外の女性の平均は10.9%であった。主介護者である女性は主介護者以外の女性よりもすべての都道府県において就業している割合が低く,福井県以外の都道府県において就業希望の割合が高かった。就業していない人の中における就業希望の割合も,主介護者である女性のほうがおおむね高かった。主介護者である女性の就業および就業希望の状況には地域差がみられた。
結論 介護と就業を両立できる社会を目指すうえでは,就業希望がある介護者のニーズの実現が1つの課題である。地域の特性を考慮する必要もあると考えられる。
キーワード 国民生活基礎調査,家族介護者,女性,informal care,就業,就業希望
|
第64巻第6号 2017年6月 運動施設利用者の運動実践状況,腹囲と食知識・感覚との関係松原 建史(マツバラ タケシ) 植木 真(ウエキ マコト) 前田 龍(マエダ トオル) |
目的 運動を実践しているにも関わらず,腹囲がメタボリックシンドローム(MetS)の診断基準に該当したまま改善しない者が大勢いる。この原因が摂取カロリーにあることは想像に難くなく,上記の者では食知識の不足や食感覚にズレが生じている可能性がある。そこで本研究では,研究Ⅰとして,公共運動施設利用者を対象に,腹囲と食知識・感覚との関係性について,研究Ⅱとして,運動実践状況を把握できるデータに絞り込んで,運動実践状況,腹囲と食知識・感覚との関係性について明らかにすることを目的とした。
方法 対象を,研究Ⅰでは公共運動施設を利用している男性284人と女性616人の計900人,研究Ⅱでは研究Ⅰの対象者のうち,運動の実践状況が把握できた男性139人と女性295名の計434人とした。腹囲測定は非伸縮性メジャーを用いた自己測定で行い,運動実践状況として,過去1年間における自転車エルゴメータとトレッドミルの運動時間から週当たり運動量を算出した。食知識・感覚の調査は,食品カロリーを伏せた寿司と焼き鳥屋メニューそれぞれ数十種類の中から,自分の好みの組み合わせと一番カロリーが低いと思う組み合わせを選択させ,寿司と焼き鳥屋の自分の好みの組み合わせの平均値を嗜好スコア,一番カロリーが低いと思う組み合わせの平均値を最低予想スコアとし,これと運動実践状況ならびに腹囲との関係性について分析した。
結果 研究Ⅰにおいて,腹囲がMetSに該当する者(MetS群)としない者(正常群)に群分けし,食知識・感覚を比較したところ,嗜好スコアは正常群の方が,最低予想スコアはMetS群の方が有意に高値を示した。研究Ⅱにおいて,最低予想スコアは,週当たり運動量と腹囲を基に群分けをした高運動量&MetS群が高運動量&正常群と低運動量&正常群よりも有意に高値を示し,低運動量&MetS群は二つの正常群と差を認めなかった。
結論 運動を実践しているにも関わらず,腹囲がMetS判定のまま改善していない者の原因として,カロリーが高い食品を好むことが影響しているのではなく,食品カロリーに対する知識不足か,感覚がズレていることが影響している可能性が示唆された。また,運動量が多い者で,この傾向が特に強いことが示唆されたことから,今後の支援では,運動量が多い者を中心に,食品カロリーの正しい知識を浸透させていくことが必要であると考えられた。
キーワード 運動実践者,メタボリックシンドローム,運動量,食品カロリー,横断的研究
|
第64巻第6号 2017年6月 地域の物理的環境と移動に伴う歩行時間との関連森 克美(モリ カツミ) 李 廷秀(リ チョンスウ) 浅見 泰司(アサミ ヤスシ)樋野 公宏(ヒノ キミヒロ) 渡辺 悦子(ワタナベ エツコ) |
目的 近年,居住地域の物理的環境が人々の日常生活における身体活動や歩行行動,移動手段の選択との関連要因として注目されるようになっている。健康日本21(第2次)でも運動しやすいまちづくり・環境整備が身体活動・運動分野の目標に採り入れられているものの,居住地域の物理的環境と身体活動や歩行行動などとの関連を検討した国内での研究は少ない。そこで本研究は,海外での研究で代表的な物理的環境要因の一つとされる密度と人々の日常生活における歩行行動との関連を調べることを目的とし,移動に伴う歩行時間に着目して密度との関連を検討した。
方法 全国130の市町村を対象とした,平成22年度全国都市交通特性調査の個票データから調査対象者の1日の移動行動に伴う歩行時間を求めた。また,居住する市町村の人口密度,および居住地が市街化区域内にあるかどうかを物理的環境要因としての密度の指標とした。まず密度と歩行時間との関連を把握するため,市町村の人口密度と平均歩行時間を市街化区域内,区域外で層別して散布図を描いた。次に1日の歩行時間を目的変数,密度および個人要因を説明変数とした一般線形混合モデルによるマルチレベル分析を実施して,密度と歩行時間との関連を定量的に評価し,個人要因による関連性の違いも検討した。
結果 市町村の密度と平均歩行時間は正の関連を示し,人口密度の大きい市町村ほど,また市街化区域内に居住している方が区域外に居住しているよりも,平均歩行時間が大きい傾向にあった。マルチレベル分析の結果でも人口密度の大きい市町村に居住する者ほど,また市街化区域内に居住する者は区域外に居住する者よりも,移動に伴う歩行時間の期待値は大きくなった。その関連の強さは個人属性によって異なっており,20~39歳の年齢層や職業を持っている者で密度との関連が強く,19歳以下や学生などの比較的若年者で密度との関連が弱い傾向にあった。
結論 移動に伴う歩行時間は,地域の物理的環境としての密度と関連し,密度の高い地域ほど移動に伴う歩行時間が大きいことが示された。密度は商業施設などの多さ,道路網や公共交通機関網の発達の程度,歩道の整備状況など,都市としての機能を総合的に表していると考えられるため,身体活動や歩行行動などとの関連の機序を明らかにするためには物理的環境要因として密度が持つ意味を具体化していく必要がある。
キーワード 物理的環境,密度,歩行,身体活動,全国都市交通特性調査
|
第64巻第5号 2017年5月 高齢者施設スタッフの認知症についての知識・理解と態度王 吉彤(オウ キットウ) 名倉 弘美(ナグラ ヒロミ) 三上 章允(ミカミ アキチカ) |
目的 本研究では,高齢者施設スタッフの認知症についての知識・理解と認知症ケアへの態度の現状を明らかにし,また,スタッフの基本属性や認知症ケアへの態度による認知症の知識・理解の違いを比較・解析し,認知症ケアの今後の課題について検討した。
方法 岐阜県A市の全高齢者施設・事業所を対象に,郵送にて質問紙調査を行い,814人(回収率39.5%)から回答を得た。
結果 スタッフの認知症ケア経験年数が長いほど,認知症についての知識・理解が高いことが明らかになった。施設・事業所別の比較では,特別養護老人ホーム,グループホーム,訪問看護,デイサービスが認知症の知識・理解が高かった。認知症ケアへの態度では,認知症ケアに関する研修に参加したスタッフ,認知症ケアへの関心を示したスタッフ,認知症ケアにやりがいを感じているスタッフで,認知症についての知識・理解が良く,認知症ケアに対する積極的・肯定的態度が認知症についての知識・理解を高めていた。
結論 今回の調査では,認知症ケア経験年数,学歴と研修参加が認知症についての知識・理解を向上させるのに最も重要であることを示した。この結果から,専門教育を受けていない経験年数の短いスタッフへの教育の充実と研修機会の提供が認知症ケアの質向上につながると考えられた。
キーワード 高齢者施設,スタッフ,認知症知識・理解,態度,認知症ケア経験年数,研修
|
第64巻第5号 2017年5月 中年期女性のストレッサー尺度の検討鈴木 淳子(スズキ ジュンコ) 武田 文(タケダ フミ)紀司 かおり(キシ カオリ) 門間 貴史(モンマ タカフミ) |
目的 精神的に不安定な時期とされる中年期の女性のストレッサーの実態を把握するために,「中年期女性のストレッサー尺度」を作成し,信頼性および妥当性について検討することを目的とした。
方法 2015年1月に東京都某区役所の許可を得て,住民基本台帳より層化無作為抽出した区内在住の45~64歳の女性1,000名を対象とし,無記名自記式質問紙調査を郵送法によって実施した。分析対象者は夫,子ども,仕事をもち,完全回答を得た123名(有効回答率12.3%)とした。分析項目は,属性,生活状況,ストレスに関する26項目,構成概念妥当性を確認するために精神健康指標であるK6とした。ストレス項目をPromax回転による探索的因子分析によってストレッサー尺度を作成し,信頼性と妥当性の検討を行った。
結果 「中年期女性のストレッサー尺度」として17項目,「夫との関係」「老後の心配」「ワークライフバランス」「友人関係」「健康の問題」の5つの下位因子が抽出された。尺度全体の信頼性係数はα=0.78,年齢を制御変数としたK6との偏相関係数はr=0.57,確認的因子分析による適合指標はGFI=0.895,AGFI=0.854,RMSA=0.038であった。
結論 本研究における中年期女性のストレッサー尺度の信頼性と妥当性が確認され,使用可能な尺度であることが示された。
キーワード 中年期女性,ストレッサー尺度,信頼性,妥当性
|
第64巻第5号 2017年5月 韓国社会福祉大学生の海外介護就労意識趙 敏廷(チョウ ミンジョン) 谷川 和昭(タニカワ カズアキ) 成 耆玉(ソン キオク) |
目的 日本では介護人材の確保が急がれるなか,経済連携協定による外国人の介護就労に加えて留学生の活用や技能実習制度による外国人の受け入れが拡大される見通しである。こうした動向を踏まえ,本研究では韓国社会福祉大学生の海外介護就労意向および関連要因を検討し,日本の次代を担う外国人介護士受け入れの拡大を視野に入れた人材育成・確保に向けて示唆を得ることを目的とした。
方法 韓国のソウル特別市および京畿道に設置されている11カ所の4年制大学・2年制大学に在学している社会福祉大学生を対象に,調査票を用いて自記式調査を行った。質問項目は,基本属性,関連要因および海外介護就労意向に関する項目で構成した。分析データは,欠損値のない511票を用いた(有効回収率63.1%)。分析方法は,まず基礎集計を行い,次に,海外介護就労意向の有無により対象を2群に分け,χ2検定ならびにt検定を行い,引き続きロジスティック回帰分析を行った。
結果 その結果,韓国社会福祉大学生の海外介護就労意向については,次のようなことが明らかになった。①年齢が低い者の方が海外介護就労意向が高い,②4年制大学の学生の方が2年制の短大より海外介護就労意向が高い,③自分の子どもに介護の仕事を勧める者の方がしない者より海外介護就労意向が高い,④介護就労意向を有する者の方が海外介護就労意向が高い,⑤療養保護士の資格に対する関心がある者の方がより海外介護就労意向が高い。
結論 年齢が低い者の方が海外介護就労意向が高いという結果については,若年層の参入により介護現場が活性化されることが期待できる。また,介護に対する肯定的な視点に加え,高い学習能力を備えている可能性を持つ韓国社会福祉大学生は日本における介護人材として専門性を確保する上での教育・訓練にも積極的に取り組むことが考えられ,質の高い介護サービスの提供につながることが期待できる。さらに,優れた介護人材養成は,近い将来に高齢化問題に直面する韓国やアジア諸国に対し介護人材リーダー育成を通して国際社会への貢献につながると同時に,介護人材のグローバル化を後押しするものと考えられる。以上から,韓国社会福祉大学生が日本の介護人材として貢献できる可能性が示唆された。韓国の若者が日本で介護人材として活躍できるための支援策や条件を整備していくことは,日本にとって有用な方向といえる。また,介護福祉士養成施設においては,外国人留学生に対する教育・支援を考えていく上で有用な資料として役立つことが期待される。
キーワード 韓国,社会福祉大学生,海外就労意向,外国人,介護人材
|
第64巻第5号 2017年5月 地域在住高齢者の身体活動(運動と生活活動)と生活環境の関連-市街地と郊外地による検討-久保田 晃生(クボタ アキオ) 岡本 尚己(オカモト ナオキ) 印鑰 真人(インヤク マサト) |
目的 高齢者の健康づくり,介護予防において,身体活動を高めることは有益である。しかし,高齢者の歩数は低下傾向にあり,今以上に身体活動の促進を図ることが重要である。身体活動の促進には様々な要因が関連するが,近年,身体活動の多寡に影響を及ぼす要因として,生活環境が着目され研究が進められている。一方,先行研究では身体活動の総量の多寡と生活環境との関連についての報告が多く,身体活動を運動と生活活動に分けて検討した分析は少ない。また,これまでの先行研究は生活環境が大きく異なる場所,すなわち国単位での検討,州単位での検討,都市部と地方都市での検討などが行われている。そこで,本研究は地方都市で市街地,郊外地に在住する高齢者の身体活動を運動と生活活動に分け,居住地区の影響を検討するとともに,高齢者個人の生活環境と運動,生活活動との関連を検討した。
方法 本研究は,横断的研究である。調査は,静岡県三島市の市街地のN小学校区と郊外地区のS小学校区で実施した。各地区の800人(男性400人,女性400人),合計1,600人を住民基本台帳で無作為抽出し質問紙調査を実施した。調査期間は,2015年2月末日までの1カ月間である。回答は市街地363人,郊外地430人の計793人(49.6%)から得られた。回答者の内,データの使用を拒否した者と分析項目に欠損値がある者,医師からの運動制限がある者を除いた市街地150人,郊外地187人の計337人(21.1%)を分析対象者とした。分析は各地区の運動,生活活動の状況を把握した後に,居住地区の影響と,生活環境の影響をそれぞれ二項ロジスティック回帰分析により検討した。
結果 市街地と郊外地において,運動と生活活動のMets・時/週の平均値に有意差は認められなかった。二項ロジスティック回帰分析でも居住地区の影響は認められなかった。一方,生活環境の中で,近所の運動場所は,運動で全体と市街地,生活活動で全体と郊外地において,それぞれ有意な関連(p<0.01〜0.05)を示した。
結論 地域在住高齢者において,居住する地区は身体活動との関連が認められなかった。しかし,近所の運動場所と運動,生活活動との関連が示されたように,高齢者の個人的な生活環境が運動や生活活動に影響を及ぼすことが示唆された。
キーワード 身体活動,運動,生活活動,生活環境
|
第64巻第5号 2017年5月 メンタルヘルス不全が所得に及ぼす影響に関する実証分析岡庭 英重(オカニワ フサエ) |
目的 本研究の目的は,メンタルヘルス不全や精神疾患が,所得に及ぼす影響を明らかにすることである。諸外国における先行研究では,メンタルヘルス不全や精神疾患が,労働供給や労働生産性,所得に対してネガティブな影響を及ぼすことが明らかとなっている。しかし,日本において当該分野の研究は少なく,客観的かつ包括的なデータを利用した分析が求められている。本研究では,メンタルヘルス不全の影響として,実際に得た所得が健康な人と比較してどの程度低くなっているのかを明らかにするものである。
方法 平成19年「国民生活基礎調査」の匿名データを利用し,メンタルヘルス指標を導入した所得関数を推定した。メンタルヘルス指標には,3つのK6ダミー(13点以上,10点以上,5点以上)と精神疾患通院ダミーを用いた。また分析においては,所得が低いためにメンタルヘルス不全が生じているのか,メンタルヘルス不全のために所得が低くなっているのかを区別するため,操作変数法を用いてメンタルヘルスが所得に及ぼす影響について実証分析を行った。
結果 基本集計結果から,精神疾患通院者の割合は就業者全体の1.0%,K6-13点以上の者は2.6%であった。また,K6-13点以上の就業者のうち,精神疾患通院者は1割程度となっていることから,メンタルヘルス不全の状態で医療機関を受診せずに就業している者が多く存在することが示された。また精神疾患通院者のうち,身体疾患でも通院している者が6割にのぼった。これらの基礎データを踏まえて推計を行った結果,メンタルヘルス不全や精神疾患は,所得に対して有意に負の影響を及ぼすことがわかった。K6が13点以上の者は,13点未満の者と比較して所得が62.5%低いことが明らかとなった。また,精神疾患通院者はそれ以外の者と比較して79.1%所得が低いことがわかった。検定結果から,最小二乗法よりも操作変数法による推計が妥当であることが示されている。
結論 メンタルヘルス不全や精神疾患の者は健康な者と比較して,逆の因果性を排除してもなお有意に所得が低くなることがわかった。また日本における所得低下割合は,諸外国の先行研究において報告された数値を大きく上回る推計値となった。
キーワード メンタルヘルス,精神疾患,所得,労働損失,国民生活基礎調査,操作変数法
|
第64巻第4号 2017年4月 群馬県内の病院看護職の属性と在宅を見据えた
堀越 政孝(ホリコシ マサタカ) 常盤 洋子(トキワ ヨウコ) 牛久保 美津子(ウシクボ ミツコ) |
目的 在宅医療が急速に推進されている中,在宅ケアを見据えた看護を提供できる人材養成が求められている。特定の地域における人材養成体制を整えるには,その地域の現状を把握する必要がある。地域特性に基づいた現任教育が施されることで,ニーズに対応したより質の高い看護が提供できる。よって,本研究では,群馬県内病院看護職の在宅を見据えた看護活動の実践に関する自己評価得点と属性との関連を明らかにした。
方法 群馬県内11病院(県内6市2郡にある140床以上の病院)の看護職を対象に質問票調査を実施した。基本属性(年齢,経験年数,職位,配属,在宅看護論履修の有無,在宅看護研修の受講有無)と,在宅を見据えた看護活動の実践に関する自己評価得点との関係を検討した。
結果 回収数は2,136名(回収率73.3%)であった。年齢は,30歳未満,30歳代が3割,40歳以上が4割,経験年数は5年未満が3割,5~10年未満は2割で,10年以上が5割を占めた。職位は,9割がスタッフであり,配属は,内科系が3割,外科系が2.5割,混合,外来・中央部門がそれぞれ2割であった。在宅看護論を履修している者が7割,在宅看護研修を受講していない者が7割,看護実習指導を経験していない者が8割であった。全因子において,年齢と経験年数が高いほど有意に高かった。また,在宅看護論を履修していない者,在宅看護研修の受講者,看護実習指導経験者,スタッフよりも管理職である師長・副師長の実践度が有意に高かった。また,「社会資源の活用」では,副師長よりも師長のほうが,実践度が高かった。
結論 看護職の職位,年齢など属性を考慮しながら,在宅を見据えた看護を提供できる人材養成を行う必要がある。経験や役職に関わらず,病棟看護師全員が,日頃からある程度の水準で在宅を見据えた看護を提供できるようなシステムが必要であり,在宅を見据えた視点を持つ看護職を養成するためには,個々の背景を考慮した建設的かつ継続的な現任教育が必要である。
キーワード 在宅ケア,病棟看護,地域包括ケア,人材養成
|
第64巻第4号 2017年4月 全国市区町村における乳幼児期を対象とした
衞藤 久美(エトウ クミ) 石川 みどり(イシカワ ミドリ) 高橋 希(タカハシ ノゾミ) |
目的 市区町村の標準的な保健指導における栄養指導の参考となる手引書作成の資料を得るために,全国市区町村における乳幼児期を対象とした栄養指導の実施状況および指導内容の実態を明らかにする。
方法 全国1,742市区町村の母子保健事業の栄養担当者を対象に,平成25年1~3月にインターネットによる栄養指導に関する調査を実施した。調査は市区町村名の記名式とし,1,043市区町村から回答が得られた(回収率59.9%)。その後,該当項目に不備がみられた656市区町村を対象に郵送法による質問紙調査を実施し,498市区町村から回答が得られた。解析対象は840市区町村であった(有効回答率48.2%)。調査内容は,回答者の職種,管理栄養士・栄養士の配置の有無,乳幼児健診時における栄養指導担当者の業務,乳幼児健診事業における集団・個別指導における母親・子どもへの栄養指導内容とした。指導内容は,母子保健施策の指針,通知等を参考に設定した。
結果 3,4カ月児,1歳6カ月児,3歳児健診に共通して栄養指導担当者が関わる割合が高い業務は,身体発育曲線等を使用した発育評価および食事のリズム(食事時間)であった。3,4カ月児健診時に,集団・個別の栄養指導で共通に多かった内容は,離乳食の調理形態等の知識(72.1%,79.0%),離乳食の食べさせ方の知識(71.2%,74.3%),食物アレルギーの知識(48.8%,51.1%)であった。1歳6カ月児健診時に,母親・子どもへの集団指導で共通に多かった内容は,1日3回の食事や間食のリズム(母親32.5%,子ども12.8%),食事を楽しむこと(27.4%,13.0%),家族と一緒に食べることを楽しむこと(25.5%,11.6%)であった。3歳児健診時には,1日3回の食事や間食のリズム(母親32.2%,子ども16.3%),食事を楽しむこと(25.9%,16.6%),いろいろな食品に親しむこと(23.8%,17.1%)であった。
結論 乳児期(3,4カ月児健診時)は離乳食,幼児期(1歳6カ月児,3歳児健診時)は食事全体に係わる,食事や間食を楽しむこと,食事のリズムが栄養指導の内容として多く取り上げられていた。
キーワード 乳幼児健診,栄養指導,離乳食,食事や間食のリズム,食事を楽しむこと
|
第64巻第4号 2017年4月 日本における性的児童虐待の近年の動向照井 稔宏(テルイ トシヒロ) 後藤 あや(ゴトウ アヤ)馬場 幸子(ババ サチコ) 安村 誠司(ヤスムラ セイジ) |
目的 全国の児童虐待対応件数は増加の一途をたどっているが,性的児童虐待の動向についての報告は乏しい。本研究は政府統計を用いて,国内における性的児童虐待の動向について分析した。また,都道府県別の性的児童虐待件数と関連要因を分析することで,性的児童虐待の社会的決定要因となり得る地域特性を把握した。
方法 総務省統計局e-Statが公開する児童相談所における児童虐待対応報告件数を用いて,性的児童虐待と身体・精神的児童虐待・ネグレクト(以下,その他の虐待)の動向を分析した。都道府県別の性的児童虐待率と関連要因(人口,性行動,安全,経済,家庭環境,地域資源)について,Spearmanの順位相関係数を求めた。
結果 報告件数は,性的児童虐待,その他の虐待ともに増加していた。性的児童虐待の被害児童数は2011年以降,小学生が中学生を上回った。都道府県別性的児童虐待率と図書館数が有意な負の相関(rs=-0.29,p=0.048)を示した。
結論 性的児童虐待は,その他の児童虐待と共に増加傾向にあり,被害児童の低年齢化を認めた。性的児童虐待予防の観点から図書館などの地域資源の重要性が示唆された。
キーワード 児童虐待,性的児童虐待,生態学的研究,社会資源
|
第64巻第4号 2017年4月 東日本大震災被災者における震災後4年間の
関口 拓矢(セキグチ タクヤ) 菅原 由美(スガワラ ユミ) 渡邉 崇(ワタナベ タカシ) |
目的 大規模災害後の被災者の慢性期・復興期における健康問題については今だ明らかでない点が多い。本研究の目的は,東日本大震災被災者の自覚症状有訴者率(以下,有訴者率)の変化を明らかにすることと,有訴者率の増加がみられる自覚症状の新規発生に関与する因子を検討することである。
方法 東北大学地域保健支援センターでは被災者の長期にわたる健康状態を把握するため,健康調査を半年ごとに継続実施している。本研究は被災地域である宮城県内4地区の18歳以上住民のうち,震災約半年後(2011年6月~11月)に行われた第1期調査および4年半後(2015年6,7月)に行われた第9期調査に回答かつ研究同意した者を対象とした。自覚症状の項目は国民生活基礎調査に準拠し,ここ数日における病気やけがなどで体の具合が悪いところに当てはまるものすべてを選択するよう依頼した。第1期,第9期それぞれで,自覚症状の項目ごとに千人当たりの有訴者率を算出した。有訴者率の推移は,McNemar検定により解析した。さらに,有訴者率が有意に増加した自覚症状について新規発生と関連する因子を多重ロジスティック回帰分析を用いて解析した。検討項目は,人口統計的特性(性別,年齢),生活・健康習慣(飲酒習慣,喫煙習慣,歩行習慣),社会経済的因子(震災前からの就労変化,主観的経済状況,居住環境,社会的孤立),心理的因子(心理的苦痛,睡眠障害の疑い)とした。
結果 解析対象者は1,239名であった(平均62.6歳,女性55.6%)。第1期から第9期にかけ有訴者率が有意に減少したものは(第1期,第9期;相対有訴者率比),「いらいらしやすい(118.6,87.2;0.73倍)」「めまい(76.7,54.1;0.71倍)」であった。一方,「腰痛(222.8,286.5;1.29倍)」「尿失禁(尿が漏れる)(32.3,54.1;1.68倍)」は有意に増加した。腰痛の新規発生には,1日2合以上の飲酒習慣(オッズ比2.05,95%信頼区間1.25-3.38)と主観的経済的状況が大変苦しいこと(オッズ比2.28,95%信頼区間1.38-3.76)が関与していた。尿失禁新規発生には高齢(1歳増加あたり,オッズ比1.07,95%信頼区間1.04-1.11)が有意に関連していた。
結論 被災地域住民では,震災半年後と比較して,震災4年半後にいらいら,めまいは減少した一方で,腰痛と尿失禁は増加した。腰痛の新規発生には震災後の生活習慣や社会的要因が関与している可能性がある。
キーワード 東日本大震災,自覚症状有訴者率,被災者,健康,予測因子
|
第64巻第4号 2017年4月 地域医療構想の推進に資する急性期指標の開発野田 龍也(ノダ タツヤ) 松本 晴樹(マツモト ハルキ) 伴 正海(バン マサウミ)石井 洋介(イシイ ヨウスケ) 原澤 朋史(ハラサワ トモフミ) 木下 栄作(キシタ エイサク) 今村 知明(イマムラ トモアキ) |
目的 病床機能報告の公表データを用いて,全国の各病院の高度急性期・急性期の度合いを示す指標(急性期指標)を開発することにより,病床機能区分の定量的な定義づけを目指した。
方法 病床機能報告に含まれるストラクチャー指標およびプロセス指標から,急性期以外の病院に比べて急性期病院で充実していると考えられる項目を選定し,それらを統合した。具体的には,2014年に行われた病床機能報告(報告病院数:7,416施設)をもとに,⑴急性期的な項目の選定,⑵項目の縮約,⑶病床規模による補正,⑷スコアの標準化,⑸合算による急性期指標の作成の5つの段階を経た。
結果 全国7,416施設を対象とする急性期指標の最大値は90.43,最小値は0.00,平均値は21.46,標準偏差は13.8であった。数値の誤報告によると思われる急性期指標スコアは散見されるが,おおむね急性期医療を重点的に行っていると考えられる病院が大きなスコアを獲得した。
結論 本研究では,ある病院が他の病院に比べてどれくらい急性期を主体とした医療を行っているかの相対的な傾向を示す急性期指標を開発し,おおむね妥当と思われる結果が得られた。本指標はあくまで総合的な急性期医療の度合いを示すものであり,特定の傷病に特化した医療やケアミックス,慢性期医療等に注力している病院については測定することができない。本急性期指標にはいくつかの限界があるが,適切な病床機能のあり方を定量的に議論するためのツールとして利用されることが期待される。
キーワード 地域医療構想,病床機能報告,急性期指標,病床機能区分,急性期病床
|
第64巻第4号 2017年4月 自殺予防いのちの電話フリーダイヤルによる
勝又 陽太郎(カツマタ ヨウタロウ) 及川 紀久雄(オイカワ キクオ) |
目的 本研究では,日本いのちの電話連盟が実施している自殺予防いのちの電話フリーダイヤルによる電話相談(自殺予防フリーダイヤル)の相談記録の分析をもとに,当該電話相談を利用する自殺ハイリスク者の心理社会的特徴を探索的に明らかにするとともに,自殺予防対策における電話相談のあり方について考察を行った。
方法 一般社団法人日本いのちの電話連盟が実施している自殺予防フリーダイヤルの相談電話記録のうち,2015年の1年間に受信した計30,387件の相談電話の記録データを分析し,自殺予防フリーダイヤルの利用者の人口動態学的特徴,利用者が抱える心身の問題,および相談の内容について全体的な特徴の把握を行うとともに,電話受信時の自殺傾向の有無や自殺未遂歴の有無とその他の評価項目との関連性について検討を行った。
結果 利用者の性別は女性に比べて男性の割合がやや高く,推測年齢層では40代の割合が最も高かった。ただし,受信時の自殺傾向との関連では,女性の方が男性に比べて強く,推測年齢層では50代が最も高いオッズ比を示していた。利用者の生活形態は独居と同居がほぼ同程度の割合であったが,同居よりも独居の方が自殺傾向との関連は強く,職業については無職者が全体の半数以上を占め,受信時の自殺傾向との関連も相対的に強かった。さらに,身体疾患の既往歴がある者は利用者全体の19.1%,同様に精神疾患の既往歴がある者は全体の45.7%,自殺未遂歴は全体の9.7%に認められ,いずれも電話受信時の自殺傾向と有意に関連していた。相談内容分類では,人生と精神がいずれも25%程度と最も割合が高く,電話受信時の自殺傾向との関連も相対的に強かった。
考察 自殺予防フリーダイヤルによる相談電話形態は,男性や経済基盤が安定していない利用者,自殺ハイリスク者の相談へのつながりやすさを促進するといった面で,重要な機能を有している可能性が示唆された。また,自殺予防フリーダイヤルの啓発のあり方や対応する相談員のトレーニングの内容について,課題と今後の方向性について示唆が得られた。
キーワード 自殺予防フリーダイヤル,自殺,自殺未遂,精神疾患,電話相談
|
第64巻第3号 2017年3月 介護老人保健施設利用高齢者における
渡邊 久実(ワタナベ クミ) 酒寄 学(サカヨリ マナブ) 宇留野 功一(ウルノ コウイチ) |
目的 高齢化の進行にともない,要介護者,認知症者の増加は今後さらに加速することが見込まれている。介護サービス事業所における在宅生活支援,在宅復帰の実現に向けた認知症予防,認知力保持の支援は,喫緊の課題である。本研究は,介護老人保健施設利用者を対象として,歌唱付介護予防体操の認知機能への効果を明らかにすることを目的とした。
方法 参加者は,社会福祉法人Aの介護老人保健施設の入所者および通所サービス利用者41名である。同法人で開発した歌唱付介護予防体操を用いて1カ月間介入を行った。効果測定として体操介入前と介入1カ月後に改訂版長谷川式簡易知能評価スケールを用い,介入前後の認知機能を評価した。分析は,体操介入前と介入1カ月後の改訂版長谷川式簡易知能評価スケールの得点をWilcoxonの符号付順位和検定を用いて比較した。
結果 体操介入前と介入1カ月後の改訂版長谷川式簡易知能評価スケールの得点を比較した結果,介入後に平均得点が向上した。特に身体的自立度の高い群では,有意な認知機能の改善がみられた(P=0.03)。
結論 介護サービス事業所において,利用者参加型の歌唱付介護予防体操が認知機能の保持,改善に有効である可能性が示唆された。
キーワード 高齢者,歌唱付介護予防体操,認知機能,介護予防,社会福祉法人
|
第64巻第3号 2017年3月 DPCデータを用いた平均寿命に係わる長野県型
中島 尚登(ナカジマ ヒサト) 矢野 耕也(ヤノ コウヤ) 長澤 薫子(ナガサワ カオコ) |
目的 平均寿命が最も長い長野県に開設されたDiagnosis Procedure Combination(DPC)対象病院(DPC病院)と他46都道府県のDPC病院のDPCデータを用い,Mahalanobis・Taguchi(MT)法により長野県に類似した都道府県と乖離した都道府県を区分し,長寿の要因を解析した。
方法 対象はDPC病院1,578施設である。長野県内DPC病院38施設のDPCデータ12項目で単位空間を作成した。次に長野県以外のDPC病院1,540施設それぞれのMahalanobisの距離(D2)を求め,その分布パターンで都道府県を長野県型と大都市型に区分した。そして長野県型および大都市型におけるDPCデータを検定し,長野県型および大都市型の特徴を明らかにした。
結果 長野県型のD2分布パターンを示す都道府県は新潟,石川,奈良,鳥取,島根,山口,香川,愛媛,高知,佐賀,長崎,沖縄の長野を含めた13県222病院であり,新潟県にのみ政令指定都市が制定されていた。大都市型は34都道府県1,316病院であり,14都道府県に政令指定都市が制定されていた。そしてχ2検定では,政令指定都市数は大都市型において有意に多かった。男性平均寿命は長野県型と大都市型の間に有意差を認めなかったが,女性平均寿命は長野県型で有意に長寿であった。平均寿命の都道府県別順位では,男性平均寿命では長野県型13県では5県99病院が,大都市型34都道府県では20都府県822病院が上位24位以内であり,χ2検定では大都市型において平均寿命上位の病院数が有意に多かった。一方,女性平均寿命では長野県型13県では10県202病院が,大都市型34都道府県では14都府県550病院が24位以内であり,χ2検定では長野県型において平均寿命上位の病院数が有意に多かった。長野県型は大都市型に比べ調整係数は有意に低いが機能評価係数Ⅱは差を認めない。病床数,入院件数,救急入院件数,手術件数,化学療法件数,救急車搬送件数,全身麻酔件数は有意に少なく,在院日数は長い,という特徴が認められた。
結論 男性平均寿命を延ばす要因として大都市型,女性平均寿命を延ばす要因として長野県型があげられた。長野県型の特徴は,診療件数は小規模であり,在院日数は長いことが明らかになった。
キーワード 平均寿命,DPC,Mahalanobis・Taguchi法,Mahalanobisの距離
|
第64巻第3号 2017年3月 算出プログラムを用いた要介護認定データに基づく
栗盛 須雅子(クリモリ スガコ) 福田 吉治(フクダ ヨシハル) 星 旦二(ホシ タンジ) |
目的 本研究の目的は,2010~2012年度にかけて開発し,茨城県立健康プラザのホームページで公表している「健康寿命(DALE)と障害をもつ人の割合(WDP)算出プログラム」を用いて,47都道府県の2010~2014年の要介護認定データに基づく障害調整健康余命(DALE)と加重障害保有割合(WDP)の算出結果を明確にし,値の活用等について考察することである。
方法 本プログラムに,算出に必要な性・年齢階級別・要介護度別介護保険認定者数と性・年齢階級別・人口を入力し,都道府県生命表をコンピュータのデスクトップ上等に保存し,プログラムの生命表取り込みボタンを押して算出されたDALEとWDPの結果を示し,本プログラムと算出された値の活用等について考察した。
結果 全国のDALEは2010~2014年まで男女ともすべての年齢で,年々短くなり,47都道府県では,65歳DALEの第1位は2010~2013年まで男女とも長野県,2014年は男性1位長野県,女性1位島根県であった。全国のWDPについて,男性では,75~79歳,80~84歳は年々低く(低い方が健康度が高い),その他の年齢階級では高く,女性では,75~79歳,80~84歳は年々低くなる傾向にあった。年齢調整WDP上位県は,男女とも2010~2014年まで1位山梨県であり,その期間,長野県,茨城県がそれぞれ2~5位であった。
結語 プログラムを用いることで,都道府県が独自にDALEとWDPを迅速に算出,可視化することができ,健康増進計画や高齢者プランの策定の根拠と評価指標として,また,ある時点での高齢者の健康状態の把握に活用できる。
キーワード プログラム,要介護認定データ,障害調整健康余命(DALE),加重障害保有割合(WDP),47都道府県,高齢者
|
第64巻第2号 2017年2月 地域医療構想・医療計画の策定と在宅医療等の需要予測浜田 淳(ハマダ ジュン) 伏見 惠文(フシミ ヨシフミ) |
目的 この調査研究では,地域医療構想や医療計画の策定や実施に携わる関係者や地域住民の要請にこたえることを目的として,二つの研究を行った。第一に,タイプの異なる三つの構想区域(二次医療圏)を選定して,その地域特性や医療・介護提供体制の現状,2025年における医療需要の推計結果等を踏まえ,今後,どのように提供体制を整備して行くべきかを検討するにあたっての論点を検討した。第二に,地域医療構想では,慢性期病床の患者を在宅医療等にシフトすることが想定されているが,在宅医療等の需要を把握することは困難なのが現状である。そこで,在宅医療等の需要を,専門的人材・設備が分析のために必要なレセプトデータによることなく把握する手法について検討した。
方法 第一のテーマに関しては,地方都市型として岡山県県南東部医療圏,中山間地域型として同県真庭医療圏および大都市型として福岡県福岡・糸島医療圏の三つの医療圏を取り上げて,地域医療構想の策定状況と今後の論点,こうした動向を踏まえて各医療機関がどのような対応を模索しているかを,検討した。その中で,特に,「地域医療連携推進法人」を活用しようとしている事例に焦点を当てた。第二のテーマについては,在宅医療需要の推計方法について,ストックおよびフローの概念を用いて整理するとともに,現在の各種統計から把握できるデータはなにか,新たに把握する必要のあるデータを得るためにどのような調査が必要か等について検討した。
結果・結論 2025年の医療提供体制の在り方は,人口動向と既存の病床数の多寡により,構想区域ごとで異なっており,各構想区域において実情に見合った対応が要請される。病床の中で慢性期病床については,いずれの構想区域でも2025年にかけて現状よりも大幅に減少する推計となっている。これは受療率の都道府県別の地域差を縮小し,医療ニーズの比較的少ない患者を在宅医療等にシフトさせる前提によるものである。地域医療構想では,慢性期病床は在宅医療等と一体的に患者数が予測されており,2025年における慢性期病床数は療養病床に入院する医療区分1の患者の7割は在宅医療等に移行するといった,割り切りに基づく算定がなされている。しかし,地域医療構想を現実に根付かせるためには,構想区域の市町村ごとに在宅医療等の実態や2025年に向けてのニーズを把握し,構想区域の地域医療構想とすり合わせを図ったうえで現実的な整備方針を県と市町村で確立する必要がある。在宅医療の需要を客観的なデータに基づいて把握することは極めて重要なことであり,ストック,フローという二つの概念を用いて需要把握のフレームを作成した。在宅需要の把握については,医療施設調査等の既存の統計結果の活用と介護保険日常生活圏域ニーズ調査等の世帯を対象とした調査の実施が有効であり,調査事項の中に健康や医療に関する事項を挿入することによって,在宅医療に関する必要な情報を比較的容易に入手することが可能となる。
キーワード 地域医療構想,地域医療連携推進法人,在宅医療の需要把握
|
第64巻第2号 2017年2月 診療科別歯科医師の地域偏在-医師・歯科医師・薬剤師調査データを用いた分析-石丸 美穂(イシマル ミホ) 大野 幸子(オオノ サチコ) 松居 宏樹(マツイ ヒロキ)康永 秀生(ヤスナガ ヒデオ) 小池 創一(コイケ ソウイチ) |
目的 現在までわが国では,歯科医師の診療科別の地域偏在を考慮した研究は存在しない。今後の歯科医師の供給量を検討する上で診療科を考慮することは重要であると考えられるため,本研究では歯科医師の診療科別の地域偏在について明らかにすることを目的とした。
方法 1996年~2014年の医師・歯科医師・薬剤師調査の集計データを用いて,歯科診療科(一般歯科,矯正歯科,小児歯科,口腔外科)別に調査した。また広告可能な専門医(口腔外科,歯周病,歯科麻酔,小児歯科,歯科放射線)についても調査を行った。人口10万人対各診療科の歯科医師数を都道府県単位で求め,2004年と2014年で比較を行った。都道府県別・診療科別の歯科医師数の分布の偏在を調べるため,ローレンツ曲線を描きGini係数を求めた。
結果 各診療科で人口10万人対歯科医師数は2004年と2014年で有意に増加していた。診療科の中で最も都道府県による人数の差が大きかったのは小児歯科であり,小児歯科医師数が最も多い都道府県と最も少ない都道府県では,9倍の違いがあった。地域偏在の指標としてGini係数を用いた分析では,一般歯科,矯正歯科,小児歯科,口腔外科におけるGini係数は1996年から2014年の間で減少しており,歯科医師の地域偏在は改善傾向にあることが示唆された。専門医については2014年現在のGini係数は歯科放射線科専門医,歯科麻酔科専門医,小児歯科専門医,歯周病専門医,口腔外科専門医の順に高いことがわかった。
結論 各診療科の人口10万人対歯科医師数の増加に伴い,Gini係数はすべての診療科で減少していた。専門医については小児歯科専門医を除く専門医についてはGini係数が減少していた。
キーワード 歯科医師,歯科医療,歯科専門分野,専門職の地理的配置,需給,地域偏在
|
第64巻第2号 2017年2月 10代における妊娠中絶率の低下および
|
目的 性に関する正しい知識の普及,エイズなどの性感染症予防,10代の望まない妊娠を回避するための避妊法等の啓発を目的として,釧路市では中学生と高校生を対象に,毎年,思春期保健講座を開催している。講座終了後のアンケート調査の経年集計から高校生における性意識や性行動の変化を探った。
方法 産婦人科医・泌尿器科医・小児科医・助産師等の専門の講師による「人工妊娠中絶」「性感染症」「避妊」「性の自己決定」などについての講義を行い,性意識や性行動,喫煙・飲酒に関するアンケートを実施した。分析対象は釧路市保健所管内の高等学校10~14校の1,2年生で,1,761~2,548名であった。平成13年から平成26年までの経年集計を行い,さらに「性交経験」に関係する要因について解析した。
結果 「性交経験」を有する者の割合は減少しており,平成13年には男子27.6%,女子34.8%であったが,平成26年は男子13.6%,女子16.2%となり,半減している。「初めての性交経験時に避妊を実行した者の割合」は70~80%程度で推移していたが,最近は女子においてその割合は減少している。「愛情のない性交渉を容認する者」は男子において高く,平成13年は35.5%に達していたが,平成26年は14.8%と半分以下に減少している。「自分の体を大切にしている者」は増加している。「性に関わる自分の行動・意識で影響を受けたもの」では「友人」と答える者が最も多かった。「インターネット」と答える者は特に男子において増加しており,平成15年は1.5%であったが,平成26年は17.3%であった。「学校の授業」と答える者も女子において増えており,平成16年は3.0%であったが,平成26年は10.6%と3倍以上に増加した。飲酒率と喫煙率は男女とも激減している。ロジスティック回帰分析の結果,「性交経験あり」と有意に関係する因子は,男子では「飲酒経験あり」,次いで「愛情のない性交渉を容認する」であった。女子では,「愛情のない性交渉を容認する」「飲酒経験あり」「学校の授業」「喫煙経験あり」であった。「学校の授業」は性交経験を抑制する因子であった。
結論 釧路市の思春期保健対策は着実に成果を上げており,高校生の性意識,性行動,喫煙・飲酒行動は大きく改善した。学校において避妊と性感染症の知識を徹底的に学ぶことと,喫煙・飲酒教育の重要性が改めて示唆された。
キーワード 妊娠中絶率,高校生,性交経験,性教育,飲酒,喫煙
|
第64巻第2号 2017年2月 大学生のメンタルヘルスの実態とその関連要因に関する疫学研究-九州大学EQUSITE Study-高柳 茂美(タカヤナギ シゲミ) 杉山 佳生(スギヤマ ヨシオ) 松下 智子(マツシタ トモコ)福盛 英明(フクモリ ヒデアキ) 眞崎 義憲(マサキ ヨシノリ) 一宮 厚(イチミヤ アツシ) 林 直亨(ハヤシ ナオユキ) 淵田 吉男(フチタ ヨシオ) 熊谷 秋三(クマガイ シュウゾウ) |
目的 大学生のメンタルへルス支援を志向したポピュレーションアプローチのための基礎資料収集を目的にして,大学新入生全員を対象とした調査を行い,抑うつ症状保有者の実態およびその関連要因を検討した。
方法 縦断研究モデルの初年度のベースライン調査のデータを横断的に解析した。平成22(2010)年度入学の大学1年生2,631名を対象に調査に関する説明を行い,同意が得られ,欠損を除いた2,038名(男子1,408名,女子630名)を対象として,入学年度の6月に食事内容,睡眠,抑うつ症状(CES-D),ストレス対処能力(SOC),QOL(WHO-QOL,QOSL)を質問紙によって調査した。身体活動量を活動量計によって計測した。CES-D得点を基準に抑うつ症状保有者を判定し,抑うつ症状有無がその他の変数に与える影響を解析した。
結果 抑うつ症状保有者の割合は,27.0%(551名)であった。抑うつ症状非保有者に比べ,抑うつ症状保有者は,WHO-QOLおよびSOCの得点が有意に低く,健康状態のよくない者,睡眠障害の疑いのある者が有意に多かった。抑うつ症状保有者は,「経済的不安がある」「大学に満足していない」の項目が有意に高かった。一方,抑うつ非保有者では,「大学の居心地がいい」「大学の友達とよく遊びに行く」「大学生活が充実している」「困ったときの相談できる友人がいる」と回答した者の割合が有意に多かった。
結論 これらの結果から,大学新入生の約25%が抑うつ症状を有しており,抑うつ症状の有無が生活習慣,ストレス対処能力,経済的不安および大学生活の自己評価に関連することが示唆された。大学入学後の時期に健康や生活習慣,大学生活の満足感を高めるような指導・介入を行うことが新入学生の抑うつ症状の予防につながる可能性が推察された。
キーワード 抑うつ,生活満足感,生活習慣,ポピュレーションアプローチ,一次予防
|
第64巻第2号 2017年2月 介護予防サービス利用者の自律性と
松井 美帆(マツイ ミホ) |
目的 本研究は,介護予防サービス利用者の自律性とソーシャルサポートとの関連を明らかにすることを目的とした。
方法 介護予防サービス利用者149名,老人クラブ会員220名を対象に質問紙調査を行った。調査内容は基本属性として年齢,性別,健康状況,PEA日本語版短縮版,高齢者用ソーシャルサポート尺度についてであった。
結果 対象者の平均年齢は介護予防サービス利用者80.8±6.3歳,老人クラブ会員74.2±6.2歳,性別は女性が同73.6%,32.3%であった。自律性のPEA総得点について両群で有意差は認められなかった。自律性とソーシャルサポートとの関連については,介護予防サービス利用者ではPEA総得点およびすべての下位尺度においてと友人・近隣からの手段的サポートと軽度の相関を認めた。また,重回帰分析の結果,両群において自律性と健康状況が関連しており,さらに介護予防サービス利用者ではソーシャルサポートとの関連が認められた。
結論 介護予防サービス利用者の自律性については,友人・近隣からの手段的サポートが高齢者の一人暮しが増加する中で今後重要である。
キーワード 自律性,介護予防サービス,ソーシャルサポート,一人暮らし高齢者
|
第64巻第2号 2017年2月 生活習慣と医療費支出との関連-4年間のパネル調査分析から-相原 洋子(アイハラ ヨウコ) 川副 延生(カワゾエ ノブオ) |
目的 生活習慣病は国民総医療費の約3割を占めることが報告されており,医療費の適正化に向けて健康行動を促進することは,公衆衛生上の課題である。栄養状態や喫煙,飲酒習慣などの実態は年齢や性別により異なっており,保健指導を実施していくうえで,年齢や性別によってどのような生活習慣の改善を図るかを検討することは重要と考え,年齢,性別による生活習慣病リスクと医療費支出との関連を検証した。
方法 2009~2012年に実施された日本家計パネル調査の個票データを用いた。生活保護受給世帯,2012年時の年齢が71歳以上となる人を除外し,4年間追跡ができた3,802人のデータを分析対象とした。アウトカムは調査前年の1年間の医療費支出とし,生活習慣病リスクとして喫煙習慣,飲酒習慣,体格指数,平日の睡眠時間とした。調査時年齢,等価可処分所得,教育歴,就労,婚姻,心身症状を調整変数とし,男女および年齢区分別に層化し,ガンマ分布を仮定した一般化線形混合モデルを用いて,生活習慣による医療費支出の相対危険度を算出した。
結果 調査初年度の年間医療費支出の平均額は約4万円であり,年齢が高くなるほど医療費支出額,通院・入院した割合は高くなる傾向にあった。40歳代女性以外の年代の男女において,「たばこをやめた」人は「吸わない」人より医療費支出が高く,50歳代男性ではその関連性が有意であった。体格指数が25.0以上の人は,18.5~24.9の人と比べて医療費支出が高くなる傾向にあり,医療費支出の比が最も高かったのは男女ともに40歳代であった。一方,40歳未満の女性では,体格指数18.5未満の人の医療費支出は,標準体重の人よりも高かった。40歳未満の女性では飲酒習慣がある人は,ない人よりも医療費支出が低い傾向がみられた。睡眠時間と医療費支出との関連について統計学的に有意な差はみられなかった。
結論 「喫煙習慣があった」「やせ」「肥満」の人は,そうでない人と比べて医療費支出額が高く,その関連性は性別,年齢によって異なっていた。喫煙対策や適性体重の推進は,医療費抑制の点からも重要であり,疾病に罹患する前に生活習慣の見直しを図れるような保健指導の在り方が今後求められる。
キーワード 医療費支出,生活習慣,日本家計調査,パネルデータ,保健指導
|
第64巻第1号 2017年1月 介護サービス事業所に勤務する
永田 美奈加(ナガタ ミナカ) 鈴木 圭子(スズキ ケイコ) |
目的 養介護施設従業者等による高齢者への虐待行為が問題となっている。虐待を防止するために,その実態を明らかにする必要があるが,介護サービス事業所の看護職を対象とした報告はみられない。本研究は,介護サービス事業所に勤務する看護職において,「自分の行為が虐待に該当すると思ったことがあるか」「虐待と思われる行為や不適切な行為をしそうになったことがあるか」という虐待の認識を明らかにすることで,高齢者虐待の背景と関連要因を明らかにすることを目的とした。
方法 A県介護サービス事業所529施設に勤務する看護職員を対象に自記式質問紙調査を実施した。調査項目は,基本属性,職場環境,高齢者虐待の認識「自分の行為が虐待に該当すると思った経験(虐待の可能性がある行為の経験)」「虐待と思われる行為や不適切な行為をしそうになった経験」等とした。虐待の可能性がある行為の経験および虐待と思われる行為や不適切な行為をしそうになった経験と各特性とのクロス集計,χ2検定を行った。その後,職場環境(職員間の連携,ケアプランの理解,虐待防止規制やマニュアル作成,高齢者虐待研修受講経験),個人特性(仕事継続意思,仕事以外の悩み)を独立変数,虐待の可能性がある行為の経験および虐待と思われる行為や不適切な行為をしそうになった経験を従属変数とし,多重ロジスティック回帰分析を行った。
結果 有効回答数は,297件(有効回答率56.1%)であった。対象者の約3割が自分の行為が虐待に該当すると回答し,その内容は,威圧的な言動等「心理的虐待」,身体拘束等「身体的虐待」に該当する可能性がある行為の順に多かった。背景として,多忙,精神的ゆとりのなさ,安全性を重視した日常的な抑制,認知症への対応の困難さ等が挙げられた。多重ロジスティック回帰分析では,虐待の可能性がある行為の経験において,虐待防止規制やマニュアル作成なし,仕事継続意思なし,高齢者虐待研修受講経験ありが有意となった。虐待と思われる行為や不適切な行為をしそうになった経験では,虐待防止規制やマニュアル作成なし,他職種との協力体制なし,虐待研修受講経験あり,仕事以外の悩みありが有意となった。
結論 高齢者虐待防止の対策として,職場での現任教育,勤務体制からみた問題点の明確化と改善,職場環境の整備等,職員の意欲や職業意識向上につながる働きかけの重要性が示唆された。
キーワード 介護サービス事業所,看護職,高齢者虐待,高齢者虐待防止の対策
|
第64巻第1号 2017年1月 東日本大震災による被害状況が
|
目的 東日本大震災による家屋被害,同居者の死亡・行方不明,失業の状況と被災2年後の被災者の精神健康の状態の関連性を明らかにすることを目的とした。
方法 2011年度に,岩手県で震災の被害が最も大きかった大槌町,陸前高田市,山田町,釜石市下平田地区において健康診断および質問紙調査を実施し,研究参加に同意した者のうち,2011年度と2013年度の調査の両方に回答が得られた6,699名を分析対象とした。調査項目は,精神健康として2011年度および2013年度のK6得点(4点以下=0,5点以上=1),年齢,婚姻状況,仕事の状況,経済的な暮らし向き,治療中の疾患の有無,震災による同居者の死亡・行方不明の有無,震災による家屋被害の有無,震災による失業の有無を用いた。分析は人口学的特性,社会経済的特性,被害状況と2013年度の精神健康の2変量の関連をみるため,年齢についてはK6得点4点以下,5点以上の2群の比較をWelchのt検定で行った。それ以外の変数については,K6得点との関連をχ2検定で検討した。次に,従属変数を2013年度のK6得点,説明変数を年齢,婚姻状況,仕事の状況,経済的な暮らし向き,治療中の疾患の有無,震災による同居者の死亡・行方不明の有無,震災による家屋被害,震災による失業,2011年度調査時のK6得点としたロジスティック回帰分析を行った。以上の分析はすべて男女別に行った。
結果 男性では,2変量の関連性の検討においては震災による家屋被害や失業といった被害状況は震災2年後の精神健康とは関連が認められたが,多変量調整を行った結果,有意な関連性が消失した。一方で,2013年度の仕事の状況や経済的な暮らし向きは多変量調整後も有意な関連性が認められた。女性では2変量の関連性の検討においては震災による家屋被害,失業や同居者の死亡・行方不明と2年後の精神健康との関連が認められ,同居者の死亡・行方不明,家屋被害は多変量調整後も有意な関連性が残存した。また,多変量調整後も仕事の状況や経済的な暮らし向きは有意な関連性が残り,影響は弱まったものの,家屋被害と同居者の死亡・行方不明も有意な関連性が認められた。
結論 男性では震災による家屋被害や同居者の死亡・行方不明,失業は震災2年後の精神健康とは関連が認められなかったが,現在の社会経済的状況との関連が認められた。一方,女性では震災による家屋被害や同居者の死亡・行方不明と2年後の精神健康との関連が認められた。
キーワード 東日本大震災,精神健康,死別,失業,家屋被害
|
第64巻第1号 2017年1月 卵性別ふたご出産率,死産率,乳児死亡率の
|
目的 人口動態統計を用いて,1995~2008年までの1卵性(以下,MZ)と2卵性(以下,DZ)のふたご出産率,死産率,乳児死亡率の年次推移並びにこれらの率に影響を及ぼす要因を調べた。
方法 日本全国における1999~2008年の出生票,死産票,死亡票(1歳未満)の個票テープを使用するため,基幹統計調査の「調査票情報の提供」の承認を得て分析を行った。
結果 MZふたご出産率(分娩千対)は4.15~4.40と横ばいで推移した一方,DZふたご出産率は1995年の4.18から急上昇し,2004年は6.95,2006年は6.93となり,翌年から減少し2008年には5.98まで低下した。DZふたごは1997年以降MZふたごより高い出産率である。MZふたご出産率はすべての母の出産年齢群で横ばいで推移した一方,DZふたご出産率は19歳以下以外のすべての母の出産年齢群で出産率は年次とともに有意に上昇した。MZとDZのふたご死産率は年次と共に有意に減少し,MZはDZより各年次で有意に高い死産率が得られた。DZふたごと単胎児の死産率を比較すると,2003年以降は両者間で差はなかった。卵性別ふたご死産率は両卵性とも母の出産年齢が19歳以下で一番高く,30~34歳で一番低い値が得られた。MZとDZともにふたご死産率は妊娠週数の上昇と共に減少し,37週で一番低い値を示し,その後は上昇した。MZとDZともにふたご乳児死亡率は1995年から2007年までにほぼ半減した。卵性別ふたご乳児死亡率は母の出産年齢が19歳以下で両卵性とも一番高く,一番低い値はMZでは35~39歳,DZでは30~34歳で得られた。一番低い乳児死亡率はMZでは37週,DZでは39週で得られた。妊娠週数が34週まではMZの方がDZより有意に高い値であったが,35週以降は両卵性間で差はなかった。
結論 MZふたご出産率は横ばいで推移した一方,DZふたご出産率は年次と共に上昇し,2004~2006年でピークに達したのちに減少している。MZがDZより有意に高いふたご死産率を示す理由として,MZ特有の死因である双胎間輸血症候群による死産が14%,先天異常による死因割合も高いことが関係している。ふたご乳児死亡率は1995年から2007年までに両卵性ともに1/2まで減少した。両卵性ふたご共に母の出産年齢が19歳以下で一番高い乳児死亡率が得られた。妊娠週数が34週まではMZの方がDZよりふたご乳児死亡率が有意に高い値であったが,35週以降は両卵性間で差はなかった。
キーワード 卵性別ふたご,出産率,死産率,乳児死亡率,母年齢,妊娠期間
|
第64巻第1号 2017年1月 介護施設における湯灌(死後の入浴ケア)の意義-ターミナルケア態度との関連と経験した職員への調査からの考察-宮田 澄子(ミヤタ スミコ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) 金 雪瑩(キン セツエイ)森山 葉子(モリヤマ ヨウコ) 柏木 聖代(カシワギ マサヨ) |
目的 多死社会を迎え,施設での看取りも重要になってきている。そこで,本研究では,湯灌(死後の入浴)がもつ施設におけるケアとしての意義を,早くから実施している一法人における多職種職員への調査を通し,ターミナルケア態度や湯灌経験から検証することを目的とした。
方法 湯灌を実施している一医療法人(有床診療所,訪問看護ステーション,介護老人保健施設,デイケアセンター,グループホーム,支援事業所)の常勤職員151名に,自記式無記名質問紙調査を2012年に実施した。基本属性(性別,年齢,婚姻状況,所属事業所,職種や勤務年数,中間管理職経験の有無・資格や資格数)とFACOD-B-J(日本語版ターミナルケア態度尺度)は全職種対象とした。FATCOD-BJの総得点の中央値によるターミナルケア態度の積極的群(高得点)と消極的群(低得点)を従属変数として各属性を用いロジスティック回帰分析にて関連因子を検討した。また,湯灌経験のある職員(直接介助・間接介助・見学も含めた者)を対象とし,関わった患者・利用者の死への悲嘆に対する対処方法(自由記載),湯灌を経験して感じたこと(13項目),湯灌経験は医療・介護職において,重要な経験と思うか(0~10段階で評価),湯灌の意義や意味について(自由記載),湯灌に対する不安(自由記載)を調査した。
結果 ターミナルケア態度の積極性には,「資格を2つ以上持っている」「湯灌経験がある」が,有意に関連していた。湯灌経験者と未経験者の死への悲嘆対応は,前者はもっと良いケアをしたいと考えて前向きであったが,後者は仕事と割り切って感情を持たない・わからないが多かった。湯灌を経験して感じたことの選択では,プラスのイメージの者が多く,マイナスの感情を持つものは少数であった。湯灌経験が重要という回答は多く,大変重要である(最高点の10)が最多32.7%(18/55)で,平均7.89であった。「湯灌で体をきれいにし,血色が戻り,表情も良くなり旅立つことが出来て,みんなが喜ぶ。湯船にゆっくり浸かってもらい最後のケアをして,お別れの会話も出来て気持ちの整理もついた」と多職種は感じていた。
結語 A介護老人保健施設で始まった湯灌は,多職種の前向きなターミナルケアをする姿勢に関与しており,今後,新しい施設におけるターミナルケアとして,広く検討する意義があると考えられた。
キーワード 湯灌,介護施設,ターミナルケア態度,ターミナルケア,グリーフ
|
第64巻第1号 2017年1月 東京23区における入浴関連死の調査谷藤 隆信(タニフジ タカノブ) 奥村 泰之(オクムラ ヤスユキ) 金涌 佳雅(カナワク ヨシマサ)津田 和彦(ツダ カズヒコ) 鈴木 秀人(スズキ ヒデト) 引地 和歌子(ヒキジ ワカコ) 阿部 伸幸(アベ ノブユキ) 福永 龍繁(フクナガ タツシゲ) |
目的 わが国における入浴関連死(以下,入浴死)は,諸外国と比較して突出して多く認められる死因である。入浴中の溺死は10年間で1.7倍に増加したとされながら,溺死と病死の両者を含めた入浴死を測定できる研究が限られているため,入浴死の発生率についての正確な情報が不足している。入浴死の予防施策を立案するためには,まず,入浴死の実態を調査することが求められる。本研究では,東京23区における浴室内で発生した病死を含めた入浴死に関して,死亡率の経年変化,地域差と季節変動を明らかにすることを目的とした。
方法 東京23区におけるすべての異常死のうち,2005年から2014年に発生した日本人の入浴死11,777名を調査対象とした。
結果 入浴死のうち,男性が6,048名(51.4%),65歳以上が10,537名(89.5%),救急搬送事例が5,846名(49.6%)であった。2014年における死亡率は,0~64歳では1.9,65~69歳では16.1,70~74歳では35.8,75~79歳では66.7,80歳以上では141.9であり,年齢に伴い高くなることが確認された。年間死亡者数の経年変化は小さく,特定の年に死亡率が高い傾向は確認されなかった。例えば,70~74歳の人口10万人当たりの死亡率と95%信頼区間(以下,95%CI)は,2005年に32.7(95%CI:27.3,38.9),2008年に31.9(95%CI:26.8,37.7),2011年に35.9(95%CI:30.4,42.1),2014年に35.8(95%CI:30.6,41.7)であった。東京23区ごとの標準化死亡比の最大値は豊島区のほか8区が1.01であり,最小値は世田谷区の0.97であった。また,8月の死亡率と比較し,1月の死亡率は7倍高いことが確認された。
結論 入浴死の9割は高齢者であるなか,入浴死者率の経年変化が小さいことが示された。高齢者人口の増加に伴い死亡者数は増加することが予想されるため,自治体が主体となり,入浴死の予防法を積極的に高齢者に伝達する取り組みを行うことが望まれる。
キーワード 入浴死,高齢者,異状死,東京23区
|
第63巻第15号 2016年12月 咀嚼機能が低下した要介護高齢者における
大原 里子(オオハラ サトコ) 高田 健人(タカダ ケント) 吉池 信男(ヨシイケ ノブオ) |
目的 介護保険施設における要介護高齢者への効果的な栄養ケア・マネジメント実施のため,口腔の状況と低栄養状況の関連および咀嚼機能低下に対する,きざみ食の有効性の有無を明らかにすることを本研究の目的とした。
方法 平成25年12月に全国37介護保険施設に対し自記式質問紙調査票を郵送し,基本的属性,低栄養関連項目,摂食・嚥下能力,歯の数,義歯使用の有無等を調査した。平成26年7月に入院,死亡,退所等のイベント調査を実施した。BMI,血清アルブミン値,200日までの累積死亡関数と歯の数,義歯使用について関連を分析した。歯の数が19本以下になると比較的硬い食品群がかめなくなる傾向があるため,歯の数が20本以上と19本以下に分けて義歯使用の有無による解析を行った。平成24年に管理栄養士養成課程を持つ3大学の学生(以下,3大学の学生)に対して,生の人参5gを一口大と5㎜角程度にきざんだものを使用して,弱い咀嚼力でかみ砕けるか,また,通常の咀嚼力ですりつぶした状態になるまでの咀嚼回数を調査した。研究協力は任意とし,同意の得られた120名を対象とした。
結果 介護保険施設入所者調査では,35施設から1,646名の調査票を回収した。BMIの有効回答は1,273名(77.3%),血清アルブミン値の有効回答は972名(59.1%),200日までの累積死亡関数の有効回答は1,625名(98.7%)であった。BMIにおいて歯の数が19本以下では,義歯使用有は20.5(±3.5),義歯使用無は19.8(±3.5)であり,差は有意であった(p=0.003)。血清アルブミン値において歯の数が19本以下では義歯使用有は3.6(±0.4),義歯使用無は3.5(±0.4)であり,差は有意であった(p=0.006)。200日までの累積死亡関数において,19本以下では義歯使用無のハザード比は1.547であり差は有意であった(p=0.042)。3大学の学生に対する調査では,有効回答は112名であり,生の人参の一口大を弱い咀嚼力でかみ砕けた者は0名(0%)であった。きざんだものを弱い咀嚼力でかみ砕けた者は1名(0.9%)であった。通常の力ですりつぶすまで咀嚼した場合,平均咀嚼回数は一口大が66.7±25.2回,きざみは77.9±29.0回であった(p<0.001 対応のあるt検定)。
結論 義歯使用有の者のBMI,血清アルブミン値が義歯使用無の者より高いことにより,義歯の栄養改善に対する効果が示唆された。咀嚼力低下に対して,硬い食べ物をきざむことは効果がないことが明らかとなった。また,通常の咀嚼力においても,きざむことによりすりつぶすまでの咀嚼回数が増加することが明らかとなった。
キーワード 要介護高齢者,咀嚼機能,義歯,BMI,血清アルブミン値,きざみ食
|
第63巻第15号 2016年12月 全国介護レセプトを用いた経口移行者実態把握の試み川村 顕(カワムラ アキラ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) 泉田 信行(イズミダ ノブユキ)植嶋 大晃(ウエシマ ヒロアキ) 高橋 秀人(タカハシ ヒデト) 野口 晴子(ノグチ ハルコ) |
目的 わが国では誤嚥等により経口栄養摂取が困難になった高齢者に,経皮内視鏡的胃瘻造設術等の経管栄養が用いられているが,経管栄養の是非について議論するだけでなく,経管栄養から経口摂取へどの程度戻るかについても議論することが求められる。しかし,経口への移行の程度を把握する試みは,アンケート等により一部では行われているものの,全国レベルでは行われていない。そこで本研究では,全国介護レセプト個票データを用いて経口への移行の実態把握を可能な範囲で試みるとともに,その限界について考察することにした。
方法 本研究で用いるデータは,レセプト審査年月が2006年5月~2014年4月の全国介護レセプト個票である。介護レセプトデータのうち,受給者台帳ファイルと明細情報ファイルを用い,経口移行加算の利用状況を,介護老人福祉施設(特養),介護老人保健施設(老健),介護療養型医療施設(介護療養)別に,記述統計によって示した。
結果 経口移行加算者数は,老健と介護療養が同程度に多かったが,入所者に占める経口移行加算者の割合(以下,加算者割合)では介護療養(1.016%)が老健(0.274%)や特養(0.087%)に比べ多かった。加算者割合の経時推移では,3施設すべてで加算者割合の低下が確認できたが,観察期末の加算者割合を期首で除すると,老健が特養や介護療養より高かった。都道府県別の加算者割合では,各施設種類で大きなばらつきがみられた。
結論 施設種類によって経口移行加算の利用にばらつきがあること,地域間の利用にも大きな違いがあることが確認できた。ただし,経口移行者の実態により近い記述をするためには,医療レセプトと介護レセプトとの突合が必要である。
キーワード 全国介護レセプト,経口移行加算,経管栄養,医療レセプト
|
第63巻第15号 2016年12月 The Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS)
藤岡 寛(フジオカ ヒロシ) 田中 陽子(タナカ ヨウコ) 涌水 理恵(ワキミズ リエ) |
目的 PAFAS/CAPESは,前向き子育てプログラム(トリプルP)の主要アウトカムである,子育てと家庭への適応,子どもの適応と親の効力感を包括的に測定できるツールである。PAFAS/CAPESの日本語版を作成し,その信頼性・妥当性を検証することを本研究の目的とした。
方法 保育園を利用している母親に,2015年7月から同年12月に,無記名自記式質問紙を配布し回答を得た。質問項目は,母親や家族の基本属性・育児効力感(PSE尺度)・育児負担感(育児負担感指標)・子どもの心理社会的問題(J-PSC17)・PAFAS/CAPES日本語版とした。PAFAS/CAPES日本語版作成にあたっては,原版からの翻訳および逆翻訳の過程を踏まえて,文意が明確に伝わる表記になるよう検討を重ねた。
結果 質問紙を1,443部配布し,682部を有効回答とした(有効回答率47.3%)。再テストについては,439部配布し,141部を有効回答とした(有効回答率32.1%)。PAFAS/CAPESの各ドメインのクロンバックのαは0.6-0.8程度で,全体を通じて,ある程度の内的信頼性が確認された。しかし,PAFASの子育ての一貫性ドメインのクロンバックのαは著しく低かった。PAFAS/CAPESの各ドメイン間の相関は,中等度もしくは軽度の相関がみられた(相関係数0.36-0.56)。他の一般的尺度との相関については,J-PSC17とCAPES(情緒および行動の問題ドメイン)との間で,中等度の相関がみられた。PSE尺度とCAPES(親の効力感ドメイン)との間で,軽度の相関がみられた。PAFASの因子分析では,原版と異なる8つの因子が抽出され,構成概念妥当性は部分的に確認されるにとどまった。PAFAS/CAPESの各ドメインにおける級内相関係数は0.7-0.8程度で,再テスト信頼性が確認された。
結論 上記の結果から,PAFAS/CAPESともに一定の信頼性・妥当性が確認された。トリプルPの介入効果を評価するのに適した尺度といえる。ただし,PAFASの子育ての一貫性ドメインにおいては,内的信頼性・構成概念妥当性・再テスト信頼性が低く,項目の再検討が必要である。
キーワード 前向き子育てプログラム(トリプルP),育児,尺度,信頼性,妥当性
|
第63巻第15号 2016年12月 高齢者ふれあいサロンへの参加と外出行動-サロン参加者・非参加者の比較-白瀬 由美香(シラセ ユミカ) 泉田 信行(イズミダ ノブユキ) |
目的 高齢者を対象として,地域における交流の場を作り,閉じこもりや孤立を防ぐ,ふれあいサロンを開催する取り組みが各地でなされているが,サロン参加と外出行動との関連は明らかになっていない。本研究は,北海道網走市の高齢者ふれあいサロン参加者と参加していない一般高齢者を対象に実施した調査結果をもとに外出頻度の違いを比較し,外出をサポートする資源となりうる世帯構成との関係について明らかにすることを目的とした。
方法 網走市の高齢者ふれあいサロン13カ所の参加者のうち協力の得られた者(参加者)203名,住民基本台帳から無作為に抽出された65歳以上の居住者(非参加者)600名を対象に2013年2月に行った無記名自記式質問紙調査のデータを用いた。外出頻度に関する回答があった参加者172名,非参加者298名のデータを分析の対象とし,参加者と非参加者の基本属性を比較した。外出頻度が週2~3回以上であることを被説明変数として,共変量をコントールしたうえで,同居者の有無や世帯構成を説明変数とする二項ロジスティック回帰分析を行った。
結果 回答者に占める女性割合は,参加者で78.5%,非参加者で54.4%であった。平均年齢は,参加者78.2歳,非参加者74.5歳であった。同居者の有無,世帯構成,先月の通院経験の有無,老研式活動能力指標の得点については,参加者・非参加者で有意な違いはみられなかった。週2~3回以上外出する者の割合は,参加者が81.4%であるのに対して,非参加者は67.8%であった。ロジスティック回帰分析の結果,サロン参加者で同居者がいることは外出頻度を有意に高くしていた。非参加者では同居者がいることによる外出への有意な影響はなかった。ただし,非参加者で「その他の世帯」の女性は,単身および夫婦のみ世帯の女性と比べて外出頻度が有意に低かった。
結論 ふれあいサロンの参加が,外出頻度の維持に関連していることが示された。参加者については同居者のいるほうが外出頻度は高く,非参加者の女性では単身世帯や高齢者夫婦のみ世帯でない場合に外出頻度が低くなっていた。除雪や自動車の運転が必要となる地方都市では,閉じこもり予防策として交流の場であるサロンを設けるだけではなく,外出への多様な支援体制も検討する必要性が示唆された。
キーワード 高齢者,ふれあいサロン,外出,世帯構成,家族
|
第63巻第15号 2016年12月 3歳児健康診査の実施対象年齢に関する全国調査佐々木 渓円(ササキ ケマル) 新美 志帆(ニイミ シホ) 山縣 然太朗(ヤマガタ ゼンタロウ)佐藤 拓代(サトウ タクヨ) 秋山 千枝子(アキヤマ チエコ) 小倉 加恵子(オグラ カエコ) 溝呂木 園子(ミゾロギ ソノコ) 朝田 芳信(アサダ ヨシノブ) 船山 ひろみ(フナヤマ ヒロミ) 松浦 賢長(マツウラ ケンチョウ) 草野 恵美子(クサノ エミコ) 石川 みどり(イシカワ ミドリ) 黒田 美保(クロダ ミホ) 市川 香織(イチカワ カオリ) 山崎 嘉久(ヤマザキ ヨシヒサ) |
目的 3歳児を対象とした乳幼児健康診査(以下,3歳児健診)について,市町村が設定している対象年齢の分布と受診率の現状を把握することとした。
方法 2015年8月に全国の市町村と特別区(以下,市町村)1,741箇所に質問紙を郵送し,1,172市町村から回答を得た。解析対象は,3歳児健診の対象年齢と対象実人員数を回答した1,095市町村である。対象年齢の区分は,自然階級分類(Jenksの最適化法)を用いて評価した。受診率は対象実人員数に対する受診実人員数の割合として,経験ベイズ法で市町村間の対象者数の偏りを調整して算出した。
結果 対象年齢の始期は二峰性の分布を示したため,2階級として始期の区分を試みた。その結果,3歳児健診の始期は,3歳2カ月以下(以下,3歳児群(542市町村))と3歳3カ月以上(以下,3歳6カ月児群(553市町村))に区分された。3歳児群の終期は二峰性の分布を示し,3歳6カ月以下(230市町村)と3歳7カ月以上(312市町村)に区分された。3歳6カ月児群の終期も二峰性の分布を示し,3歳8カ月以下(248市町村)と3歳9カ月以上(305市町村)に区分された。始期の構成率を都道府県別で比較すると,13都道県では3歳児群の市町村が75%以上を占めており,22府県では3歳6カ月児群の市町村が75%以上を占めていた。3歳6カ月児群の受診率は,3歳児群と比較して低値であった(中央値[四分位範囲](%):3歳児群96.5[94.1-98.2],3歳6カ月児群94.8[92.2-97.3])。
結論 3歳児健診の対象年齢の始期は,3歳0カ月頃と3歳6カ月前後に区分され,各々がほぼ同数の市町村で構成されていた。3歳児健診の始期は,都道府県単位で異なる傾向がみられた。3歳6カ月児群の受診率は,3歳児群と比較すると低値であった。しかし,両群の受診率の差はわずかであり,多くの市町村が高い値を示した。対象年齢に関わらず,保育所等の関連機関との連携により,すべての児の発達や育児支援の必要性を的確に把握できる体制が必要であることが示唆された。
キーワード 乳幼児健康診査,母子保健,受診率,健やか親子21(第2次)
|
第63巻第15号 2016年12月 日本国民における1日の強度別身体活動時間の実態-NIPPON DATA2010-大橋 瑞紀(オオハシ ミズキ) 宮川 尚子(ミヤガワ ナオコ) 藤吉 朗(フジヨシ アキラ)高嶋 直敬(タカシマ ナオユキ) 三浦 克之(ミウラ カツユキ) 門田 文(カドタ アヤ) 上島 弘嗣(ウエシマ ヒロツグ) 中村 好一(ナカムラ ヨシカズ) 永井 雅人(ナガイ マサト) 柳田 昌彦(ヤナギタ マサヒコ) 宮本 恵宏(ミヤモト ヨシヒロ) 森 満(モリ ミツル) 西 信雄(ニシ ノブオ) 宮地 元彦(ミヤチ モトヒコ) 奥田 奈賀子(オクダ ナガコ) 大久保 孝義(オオクボ タカヨシ) 喜多 義邦(キタ ヨシクニ) 岡村 智教(オカムラ トモノリ) 岡山 明(オカヤマ アキラ) NIPPON DATA2010研究グループ |
目的 国民の身体活動の現状を把握することは,循環器疾患リスク等の低減や健康増進に資する情報として重要である。そこで,2010年国民健康・栄養調査と同時に実施した「循環器病の予防に関する調査(NIPPON DATA2010)」の参加者を対象に1日の身体活動を調査し,わが国を代表する一般集団の1日の強度別身体活動時間および身体活動指数を性・年齢階級別に分析した。
方法 NIPPON DATA2010の参加者2,883人(男性割合42.7%,平均年齢58.8歳)を対象に,自記式質問票と調査員による面接にて1日の身体活動の内容と時間を調査し,強い,中度,軽い身体活動,平静な状態(テレビ視聴含む),活動なしに分類した。身体活動指数は,Framingham研究の換算式を用いて算出した。強度別身体活動時間と身体活動指数について,年齢階級別に,性差はMann-WhitneyのU検定,年齢階級の傾向性はJonckheere-Terpstra検定を用いて検定した。
結果 強度別身体活動時間は,男性,女性(中央値/平均値)の順に,強い身体活動0.0/1.5時間,0.0/0.5時間,中度の身体活動1.3/3.3時間,6.0/6.0時間,軽い身体活動4.0/5.6時間,4.0/4.7時間,平静な状態5.0/5.8時間,5.0/5.2時間,活動なし8.0/7.9時間,7.5/7.6時間,テレビ視聴3.0/3.2時間,2.5/2.7時間であった。平静な状態およびテレビ視聴時間は,男女とも高齢になるほど長く,身体活動指数は,男女ともに高齢になるほど低かった。
結論 わが国の一般集団の強度別身体活動時間および身体活動指数が明らかとなり,それらは性・年齢階級により差があった。国民の身体活動量増加に向けた対策立案に有用な知見となると考えられる。
キーワード 身体活動,身体活動指数,国民健康・栄養調査,強度別身体活動時間,NIPPON DATA2010
|
第63巻第13号 2016年11月 韓国都市部在住高齢者の咀嚼状態と日常生活活動との関連人見 裕江(ヒトミ ヒロエ) 小河 育恵(オガワ イクエ) 徳山 ちえみ(トクヤマ チエミ)金 玄勲(キム ヒョンスン) 金 東善(キム ドンスン) 中村 陽子(ナカムラ ヨウコ) 田中 久美子(タナカ クミコ) 郷木 義子(ゴウギ ヨシコ) 寺田 准子(テラダ ジュンコ) 石井 薫(イシイ カオル) |
目的 本研究の目的は,韓国都市部にある老人総合福祉館を利用する高齢者の咀嚼状態と日常生活活動などとの関連を明らかにする。
方法 韓国の都市部在住で,老人総合福祉館を利用する高齢者124名を対象とした。調査方法は,韓国A市の2カ所の老人総合福祉館の施設長に本研究の協力を依頼し,通所者に個人背景,咀嚼状態,日常生活活動についての質問紙を配布し,無記名自記式留め置き調査を行った。分析は,調査項目の基本集計を行った後,咀嚼状態と,歯の状態,かかりつけ歯科医の有無,主観的健康感,日常生活活動との関連を調べ,さらに年齢を前期・後期高齢者2群に分けた層別分析を行った。
結果 対象の韓国都市部の後期高齢者に咀嚼状態の低下が認められ,咀嚼状態の良好群は虫歯・歯周病がなく,主観的健康感も高かった。咀嚼状態と日常生活活動との関係では,よく噛める人の方が,「バスや電車を使ってひとりで外出できますか」「自分で預貯金の出し入れができますか」「新聞や書物を読んでいますか」「続けて1キロぐらい歩くことができますか」「友人の家を訪ねることがありますか」「階段を手すりや壁を伝わらずに昇っていますか」「椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか」について「できる」と回答した人が多かった。年齢階層別分析の結果では,必ずしもこの関連は確認されなかったが,「続けて1キロぐらい歩くことができますか」については,両年齢群とも咀嚼良好群で有意に多く「できる」と回答していた。
結論 韓国の都市部の老人総合福祉館を利用する高齢者では,咀嚼状態が良好だと日常生活活動も良好になることが示唆された。咀嚼状態が良好な人に,長距離の歩行に支障がない人が多いことは年齢による交絡ではなく,高齢者の咀嚼能力の維持は実際に日常生活の改善をもたらす可能性がある。
キーワード 韓国,都市部,高齢者,老人総合福祉館,咀嚼状態,日常生活活動
|
第63巻第13号 2016年11月 日本の統合医療の利用状況-インターネット調査を利用して-石橋 由基(イシバシ ヨシキ) 堀口 逸子(ホリグチ イツコ) 川南 公代(カワミナミ キミヨ)城川 美佳(キガワ ミカ) 丸井 英二(マルイ エイジ) |
目的 いわゆる統合医療の利用実態に関する報告は多くないため,全国の国民を対象として利用実態を把握することを目的とした。
方法 対象者は(株)gooリサーチ消費者パネル約65万人から無作為に抽出された国内在住の20歳から69歳までの国民3,000人である。調査はWebサイトを利用して平成23年1月24日から25日に実施した。質問内容は,性,年齢,職業の他,いわゆる統合医療として「はり・きゅう」「骨つぎ・接骨」「整体」等の19療法について,その利用経験,中止理由,公的機関への相談経験の有無である。
結果 回答者数は3,178人,男性1,590人,女性1,588人であった。年齢は44.7±0.24歳(平均±標準偏差)であった。経験者の割合(経験率)は77.4%で,性別では,男性73.3%,女性81.7%で有意差を認めた(p<0.0001)。年代別では,20歳代73.0%が最も少なく有意差を認め(p<0.05),職業別では専業主婦(夫)79.3%が最も高く有意差を認めた(p<0.05)。1人当たりの利用療法数は,1療法が最も多く18.4%,ついで2療法16.7%で,10療法以上も2.9%あった。各療法の経験率で30%を超えたのは,「サプリメント・健康食品」53.8%,「各種マッサージ」37.5%,「整体」36.5%であった。年代別で有意差を認めたのは,「各種マッサージ」「はり・きゅう」「カイロプラクティック」「アロマテラピー」「ヨガ」「磁気療法」(p<0.01),「整体」「骨つぎ・接骨」(p<0.05)であった。「はり・きゅう」「磁気療法」では年代と共に経験率が上がり,有意差を認めた他の療法では,経験率は年齢に対して,凸型に分布していた。すべての療法において30%以上の人が中止を経験しており,その理由では「効果が感じられない」「お金がかかる」が多かった。「何らかの健康被害があった」も2~25件あった。公的機関への相談割合はいずれも3%未満であった。
結論 先行研究と本調査結果から,日本におけるいわゆる統合医療の利用経験者は8割程度と考えられる。年代が上がるほど,また男性よりも女性が利用する傾向にあることが統合医療の利用実態の特徴と考えられた。健康被害が中止理由としてあがっており,公的機関への相談経験者割合は3%未満と低いが各療法に存在しており,利用については注意が必要と思われる。
キーワード 統合医療,代替医療,利用実態,Web調査
|
第63巻第13号 2016年11月 病院報告に基づく東日本大震災前後における
三重野 牧子(ミエノ マキコ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) 村上 義孝(ムラカミ ヨシタカ) |
目的 東日本大震災前後の病院の患者数の変化について,岩手県,宮城県と福島県の3県で,沿岸部と沿岸部以外の市町村別に,病院報告に基づいて検討した。
方法 平成20年10月~25年2月の病院報告を統計法33条による調査票情報の提供を受けて利用した。東日本大震災から2年間における,地域別の病院の1日平均在院患者数,1日平均外来患者数の変化について,施設の廃止・休止,継続,開設・再開の状況別に分類して観察した。
結果 3県の沿岸部の市町村において,震災1年後の1日平均在院患者数は,震災前と比較して岩手県で3.1%,宮城県で8.4%,福島県で25.1%の減少であった。岩手県と宮城県の減少ではその大部分が病院の廃止・休止であるのに対し,福島県では廃止・休止と継続病院での減少の両方がみられた。震災2年後の1日平均在院患者数は大きな増加がみられなかった。3県の沿岸部以外の市町村では震災1年後に横ばい傾向,2年後に減少傾向がみられた。3県沿岸部の市町村において,震災1年後の1日平均外来患者数は,岩手県では4.2%,宮城県で1.0%,福島県で19.3%の減少であった。岩手県と宮城県では廃止・休止による減少分が継続病院や開設・再開病院での増加によって圧縮されていたが,福島県では,継続病院や開設・再開病院による増加はほとんどなかった。震災2年後の1日平均外来患者数はさらに減少していた。一方,3県の沿岸部以外の市町村では震災1年後に増加し,いずれの県においても継続病院での患者数の増加が大きかったが,震災2年後には減少していた。
結論 3県の沿岸部において,震災前と比較して,震災1年後は患者数が大きく減少し,それには施設の廃止・休止と継続病院の患者数の変化が関連したことが示された。震災2年後では,1年後と比べて大きな増加はみられなかった。
キーワード 病院報告,東日本大震災,病院,患者数,保健統計
|
第63巻第13号 2016年11月 地域で生活する精神障がい者の主観的健康感と健康生活習慣-性別,居住形態別による検討-塚原 厚子(ツカハラ アツコ) 結城 美智子(ユウキ ミチコ) |
目的 精神障がい者が地域で生活をはじめること,継続していくことのためには,日常生活行動の自立を図ることや健康生活習慣を獲得することが重要であることから,地域で生活する精神障がい者を対象とし,主観的健康感および健康生活習慣の実態を明らかにすることを目的とした。
方法 福島県内で訪問看護ステーションによる訪問看護を利用している精神障がい者を対象に自記式質問紙調査により実施し,対象者から調査票が177部返送され,分析対象者とした。性別を「男性」「女性」の2群間で,居住形態を「独居」「家族と同居」「グループホーム」の3群間で,日常生活行動自立度,主観的健康感,健康生活習慣との関連について検討した。
結果 対象者は,男性69.5%,女性30.5%,平均年齢は56.1±11.7歳で,居住形態は,独居34.1%,家族と同居26.3%,グループホーム39.5%であった。居住形態と性別では,有意な差があり,男性は「グループホーム」46.6%,女性は「家族と同居」39.2%が最も多かった。日常生活行動自立度の性別では,「飲む必要のある薬を飲み管理する」「趣味や楽しい時間を過ごす」は,いずれも男性が女性よりも自立の程度が有意に高かった。日常生活行動自立度と居住形態別では,「郵便局や銀行でお金の出し入れをする」は,「独居」が「グループホーム」よりも自立の程度が有意に高かった。主観的健康感の性別では,男性は,女性よりも有意に高かった。健康生活習慣の性別では,「喫煙しない」で男性は女性より平均点が有意に低く,気をつけていなかった。健康生活習慣の居住形態別では,全体において「グループホーム」は「独居」より健康的であった。また,「適正体重を維持する」「バランスのよい食生活をする」において「グループホーム」は「独居」よりも有意に得点が高かった。
結論 女性の自立の程度が低かった項目に対して,定期的に内服ができるような働きかけや,趣味や楽しい時間が過ごせる機会・場の提供が重要である。さらに,日常生活行動の中で郵便局や銀行でのお金の出し入れが自分でできることは,「独居」が可能であることの指標になるといえる。主観的健康感では,女性は男性に比べて健康感が低く,詳細な検討が必要である。「独居」の者に対して,生活習慣病の発症を予防し地域での生活を継続するためには,バランスのよい食生活を維持し,適正体重が維持できるように援助者は働きかけることが必要であることが示唆された。
キーワード 精神障がい者,日常生活行動自立度,主観的健康感,健康生活習慣
|
第63巻第13号 2016年11月 日本版Presenteeism尺度の開発荒木田 美香子(アラキダ ミカコ) 森 晃爾(モリ コウジ)渡部 瑞穂(ワタナベ ミズホ) 古畑 恵美子(フルハタ エミコ) |
目的 日本版presenteeism尺度を開発し,その信頼性・妥当性を確認することを目的とした。
方法 2014年10月にNTTコミュニケーションズが運営するgooリサーチのモニターの中から成人労働者を対象者に無記名の調査を行った。調査は2つからなり,一つは労働者859名(男性535名,女性324名)を対象に,日本版presenteeism尺度案8項目, QOL尺度の短縮版であるSF12(MOS 12-Item Short-Form Health Survey:SF-12),ワーク・エンゲイジメント尺度および回答者の属性を尋ね,信頼性と妥当性の検討を行った。さらに日本版presenteeismの再テストを108名に実施し,再現性を検討した。
結果 確認的因子分析では共分散構造分析を行った。日本版presenteeism尺度案8項目のモデル1ではRMSEAが0.218であった。「通勤で困難を感じる」を削除したモデル2を検討したところ,RMSEAが0.028でAGFI等のモデルの適合度を示す指標も適切な範囲を示した(日本版presenteeism7項目)。SF-12のうち,「身体的な理由で仕事やふだんの活動が思ったほど,できなかった」「心理的な理由で仕事やふだんの活動が思ったほど,できなかった」等の4項目において日本版presenteeism7項目との関係を一元配置分散分析で検討したところ,有意な関係性が認められた。一方,ワーク・エンゲイジメント尺度と日本版presenteeism7項目の相関は認められなかった。信頼性についてはCronbachのα係数は0.911,再現性においても日本版presenteeism7項目のICC(級内相関)の値は0.769~0.669と,十分に高かった。
結論 成人男女労働者を対象として,確認的因子分析にて日本版presenteeism7項目の構成概念妥当性,SF-12の生活の活力に関する項目との基準関連妥当性が確認された。また,信頼性および再テストにおけるICC(級内相関)においても再現性が確認できた。今後,労働生産性の検討ために,業務形態ごとに個人のpresenteeismが職場に与える影響を検討する必要があろう。
キ-ワ-ド 日本版presenteeism,確認的因子分析,再テスト法
|
第63巻第13号 2016年11月 出生地から総合・地域周産期母子医療センターへの
|
目的 出生者の住所地からみた総合・地域周産期母子医療センターへの運転時間について,全国の市区町村単位で地理情報システムを用いて解析し,乳児死亡率,新生児死亡率,周産期死亡率との関係性を生態的に明らかにすることを目的とした。
方法 周産期アウトカムとして,平成22~26年の厚生労働省人口動態統計から乳児死亡数,新生児死亡数,周産期死亡数を集計し,5年間平均の乳児死亡率,新生児死亡率,周産期死亡率を集計した。加えて,地理情報システムを用いて,居住地域の1㎢メッシュから最寄りの総合・地域周産期母子医療センターへの運転時間を計算した上で,1㎢メッシュの出生数による加重平均を市区町村単位で集計した。運転時間を説明変数とし,乳児死亡率,新生児死亡率,周産期死亡率が第3四分位以上となるオッズ比について,ロジスティック回帰分析を用いて算出した。
結果 出生地から最寄りの総合周産期母子医療センターまたは地域周産期母子医療センターへの運転時間の中央値は27.3分,平均値は27.8分(標準偏差,以下,SD17.6),最小値は6.1分(大阪市浪速区,大阪府),最大値は67.8分(芦北町,熊本県)であった。15分未満の市区町村が448箇所,15分以上30分未満の市区町村が600箇所,30分以上45分未満の市区町村が382箇所,45分以上60分未満の医療圏が264箇所,60分以上の市区町村が32箇所であった。すべての指標において運転時間が長い群ほど死亡率が第3四分位以上となるオッズ比が上昇する傾向がみられた。運転時間15分未満を基準として,乳児死亡率では15分以上30分未満,30分以上45分未満,45分以上60分未満,60分以上のすべての群において有意な上昇を認めた。新生児死亡率は30分以上45分未満の群,周産期死亡率は15分以上30分未満,30分以上45分未満,45分以上60分未満,60分以上のすべての群において有意な上昇を認めた。
結論 安心・安全な周産期医療体制の確保にあたっては,妊産婦や乳児,新生児にとって総合・地域周産期母子医療センターに対する適正アクセスの確保が必要であることが示唆された。
キーワード 地理情報システム,乳児死亡率,新生児死亡率,周産期死亡率,運転時間,市区町村
|
第63巻第12号 2016年10月 コミュニティ・エンパワメント展開のためのニーズ把握-3年間での推移-冨崎 悦子(トミサキ エツコ) 平野 真紀(ヒラノ マキ) 田中 笑子(タナカ エミコ)渡辺 多恵子(ワタナベ タエコ) 伊藤 澄雄(イトウ スミオ) 奥村 理加(オクムラ リカ) 安梅 勅江(アンメ トキエ) |
目的 本研究の目的は,住民の「なまの声」からコミュニティ・エンパワメント展開のための当事者ニーズを抽出し,健康に対する考え方や工夫を把握することである。また,2008年と2011年の変化を抽出し,今後の健康長寿に向けた方策策定への一助とすることである。
方法 大都市近郊農村自治体住民と保健福祉専門職10グループ73名(男性34名,女性39名)にフォーカス・グループ・インタビューを2011年に実施した。各グループのインタビューから得られた結果をシステム理論に基づきカテゴリー化し,コミュニティ・エンパワメントに関するニーズを抽出した。その結果を2008年に行ったフォーカス・グループ・インタビューと比較し,3年間の変化をまとめた。
結果 重要カテゴリーとしては大きな変化がみられなかった。しかし,内容に少しずつ変化がみられた。“個”の領域では,『予防の意識づけ』や『心の余裕』さらには『自分で決定』することの重要性が新たに述べられた。また,保健福祉サービスの活用の難しさも述べられた。“相互”の領域では,継続させることの重要性と『情報との交流』の大切さが述べられた。また,『家族の協力と理解』の困難さも語られた。“地域システム”の領域では,交通が不便であるためのポジティブな側面が語られた。また,在宅でより生活しやすくするために医療と福祉の連携を強化する必要性と防災や心のケアの重要性が述べられた。『健康に関する支援の充実』では幼児期からの健康教育とともに,介護している家族への支援の充実を望む声が多く聞かれた。
結論 「地域の絆」「地域の安全」「心の病」に関する関心が高まっていたのは,東日本大震災という未曽有の災害前後の比較であったためと考える。また,個人のペースの重要性が述べられていたのは,時代の変化によるものと考えられた。
キーワード コミュニティ・エンパワメント,フォーカス・グループ・インタビュー,住民の健康に対する考え方や工夫
|
第63巻第12号 2016年10月 東日本大震災の被災3県の
|
目的 東日本大震災の影響をうけた被災3県(岩手県,宮城県,福島県)における在宅療養支援診療所(以下,支援診)の実態を,ストラクチャー,プロセス,アウトカムの3要素から経年的に比較し,今後の在宅医療のあり方の基礎資料を提供することを目的とした。
方法 被災3県の支援診を対象として郵送調査を行った(調査期間:2014年1~2月)。ストラクチャーとして人的資源,プロセスとして多職種連携体制,アウトカムとして療養者数,自宅での看取り数,居住系施設での看取り数の実績を用いて,東日本大震災以前(2010年)と調査時(2013年)とを記述統計学的に比較した。
結果 有効回収数は102件(有効回収率:25%)であった。人的資源は東日本大震災以前と比べて,2013年では常勤医師数がやや多くなっていた。多職種連携体制は,東日本大震災以前と比べて多施設と連携していることが明らかになった。アウトカムは,居住系施設で看取る支援診が増加する傾向がみられた。
結論 東日本大震災以前に比べて,2013年時点での支援診の機能はストラクチャーやプロセス,アウトカムそれぞれが増加していると考えられる。厚生労働省が在宅医療を推進しようとしている方向性と一致しているといえよう。しかし,全国調査結果と比べると,被災3県における支援診の連携体制はまだまだ充分ではないため,連携体制を整備できるようしていくことが望まれる。しかし,療養者や看取りは全国よりも良好な結果であった。この背景には地域コミュニティの豊かさのような地域性の影響が考えられるが,今後の検討が望まれる。
キーワード 在宅療養支援診療所,人的資源,多職種連携体制,看取り,地域コミュニティ,東日本大震災
|
第63巻第12号 2016年10月 日本における喫煙による死亡数の推移大島 明(オオシマ アキラ) |
目的 喫煙による死亡数の推移を知ることはたばこ対策のモニタリングとして重要である。そこで,WHOが2012年に示した方法に沿って1995年から2014年までの日本における喫煙による死亡数の推移を推計し,先進国との比較検討を行った。
方法 Petoが考案したSmoking Impact Ratio(SIR)と,American Cancer Society Cancer Prevention Study Ⅱにおける主要疾患死亡の非喫煙者に対する喫煙者の相対危険(RR)から人口寄与危険割合(PAF)をPAF=SIR・(RR-1)/(1+ SIR・(RR-1))として計算し,このPAFを各死因による死亡数にかけあわせ喫煙による死亡数を推計した。調査対象期間は1995年から2014年までとし,2010年までは5年ごとに,2011年から2014年までは毎年推計した。
結果 日本における喫煙による死亡数は,2014年には男性で14.60万人,女性で7.28万人,男女合計で21.88万人と推計された。1995年からの推移をみると,30歳以上の男性では,1995年の10.63万人から2010年に14.60万人にまで増加し,その後2012年のピークの15.60万人に達して以降はわずかに減少していたもののいまだ明確な減少傾向は認められなかった。30歳以上の女性では1995年の4.36万人から2010年に7.08万人まで増加し,その後2013年に7.45万人のピークに達していた。30~69歳の年齢層に限ると,男性では1995年の3.83万人から2014年の2.85万人に減少し,女性でも1995年の6,100人から2014年の5,300人に減少していた。
結論 日本における喫煙による死亡数は,1995年以降男性では2012年まで,女性では2013年まで増加しその後いまだ明確な減少傾向は認められなかった。喫煙による死亡数を早く減少させるためには,日本においても,英国や米国,フランスに倣って,早急にたばこ規制枠組条約に盛り込まれた各条項を誠実に履行し,環境改善に取り組む必要がある。
キーワード 喫煙,死亡数,たばこ対策,たばこ規制枠組条約
|
第63巻第12号 2016年10月 全国健康保険協会加入者の生活習慣の特徴-業態に注目して-山崎 衣津子(ヤマザキ イツコ) 船川 由香(フナカワ ユカ) 六路 恵子(ロクロ ケイコ) |
目的 全国健康保険協会(以下,協会けんぽ)は加入者数全国約3700万人,185万を超える事業所が加入する,わが国最大の医療保険者である。加えて,全都道府県に支部があり,すべての業態において加入事業所が存在していることから,全国規模で業態別に分析することが可能な数少ない組織である。業態別に効果的な保健事業を展開するための基礎資料とすることを目的に,業態別生活習慣について分析を行った。
方法 平成24年度に協会けんぽが実施する生活習慣病予防健診を受診し,特定保健指導の積極的支援に該当した被保険者のうち,協会けんぽに所属する保健師・管理栄養士による初回面談を受けた約12万人について,面談で得られた生活習慣を分析した。分析方法は,生活習慣17項目について,それぞれ該当する割合の高い業態順に並べ,腹囲がメタボリックシンドロームの基準以上(男性≧85㎝,女性≧90㎝)である者の割合が高い5業態(鉱業・採石業・砂利採取業,総合工事業,情報通信業,道路貨物運送業,その他の運輸業)に着目して分布を調べた。
結果 道路貨物運送業,その他の運輸業は,生活習慣全般が好ましくない者の割合が高かった。総合工事業は,喫煙している者のうち禁煙の意志のある者の割合が比較的高く,休養についてストレスを感じない者,起床時の疲労感がない者の割合が高かったが,ほぼ毎日飲酒している者の割合も高かった。情報通信業は,味付けが薄い,普通の者の割合および通勤時間片道20分以上(徒歩,自転車)の割合が比較的高かった。また,ストレスを感じる者の割合は高いが,解消法を持っている者の割合も高かった。鉱業・採石業・砂利採取業は,適量の食事である者の割合が高いが,味付けが薄い,普通の者の割合,カルシウムを摂取している者の割合が低く,ほぼ毎日飲酒している者の割合が高かった。
結論 着目した5業態は,腹囲がメタボリックシンドロームの基準以上である者の割合が高いという共通点はあるが,業態によって生活習慣に違いがみられた。画一的な保健指導や保健事業ではなく,業態ごとの生活習慣,健康状態の特徴を踏まえた戦略的な保健事業の展開を考える必要がある。
キーワード 全国健康保険協会,協会けんぽ,被保険者,業態,生活習慣,保健事業
※本論文の表3の注で、協会ホ-ムペ-ジを参照することとされている業態別生活習慣全体の表についてはこちらをご覧下さい。
|
第63巻第12号 2016年10月 介護福祉士の職場特性と個人要因と
時實 亮(トキザネ リョウ) 谷口 敏代(タニグチ トシヨ) |
目的 介護福祉職は,他職種に比べて依然と離職率が高く,職場定着に向けてさまざまな対策が行れている。本研究では,介護福祉士が所属する組織の組織特性および個人特性がワーク・エンゲイジメント(以下,WE)に及ぼす影響について明らかにした。
方法 某県の介護福祉士会会員1,204人を対象に自記式の調査票を郵送し,401人から有効回答があった(回収率33.3%)。質問項目に欠損値のない370人(30.7%)を分析対象とした。調査期間は2015年4月1日から4月14日である。調査内容は,個人属性,WEは日本語版WE短縮版尺度,組織特性は日本語版組織的公正尺度, 職場の支援はJCQ職業性ストレス調査票(JCQ)のうち上司の支援4項目,同僚の支援4項目,個人特性は作動性,共同性を測定するジェンダー・パーソナリティ尺度(CAS)を使用した。分析方法はWEを従属変数とし,個人属性,手続き的公正,上司の支援,同僚の支援,作動性,共同性を独立変数とした階層的重回帰分析を行った。
結果 介護福祉士の男女構成は,男性20.8%で,平均年齢は男性36.9歳,女性42.6歳で有意差(p<0.001)が認められた。階層的重回帰分析の結果,年齢,手続き的公正,上司の支援,作動性,共同性がWEに対する有意な主効果が認められた。さらに,上司の支援と作動性の要因間でWEに対する有意な交互作用が認められた。
結論 介護福祉士の年齢,手続き的公正,上司の支援が高いほどWEが高かった。情報提供や意見聴取などの行動および組織内の意思決定への参加などの手続きに関する組織特性がWEに影響を与えることが示されたため,意思決定に係る点について,十分に配慮した形で組織運営を行っていくことが求められる。また,自分の考えをチームメンバーに上手に伝えるなど男性性を表す作動性と他者とうまく協力していくことなど女性性を表す共同性が高いとWEを高めることがわかった。さらに,上司の支援と作動性との間で,WEに対する交互作用が認められた。作動性の高い介護福祉士は,上司の支援が高いほどWEが高いことを意味する。今後,作動性を高めるアサーショントレーニングなどの研修等を導入していくことが求められる。
キーワード 介護福祉職,手続き的公正,上司の支援,作動性