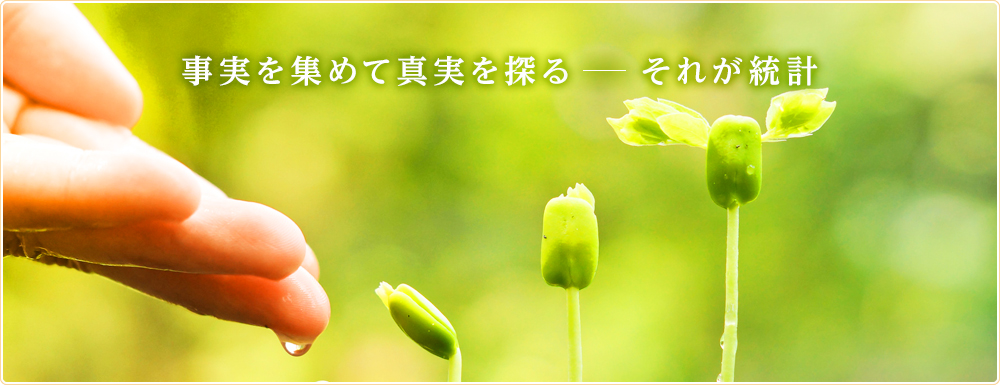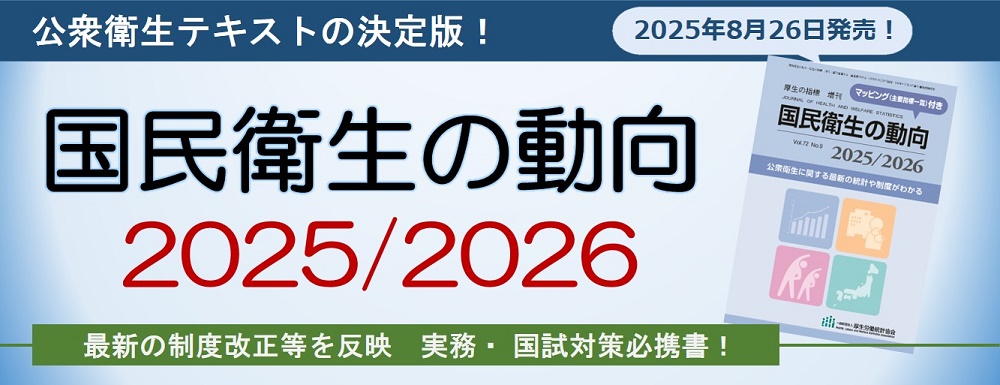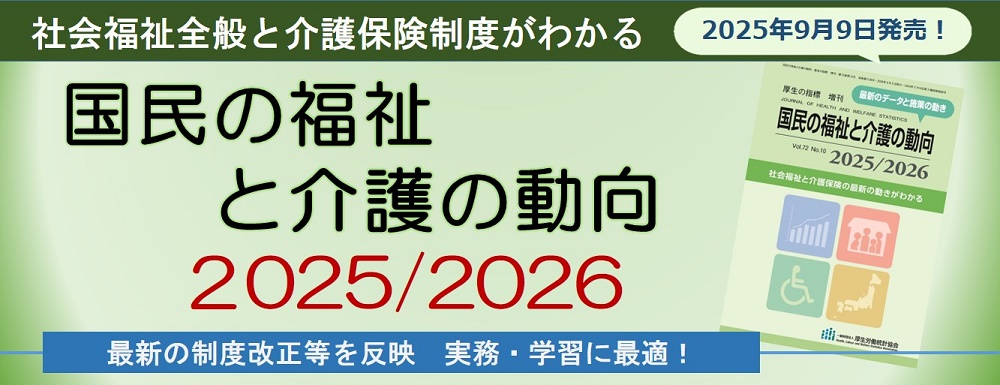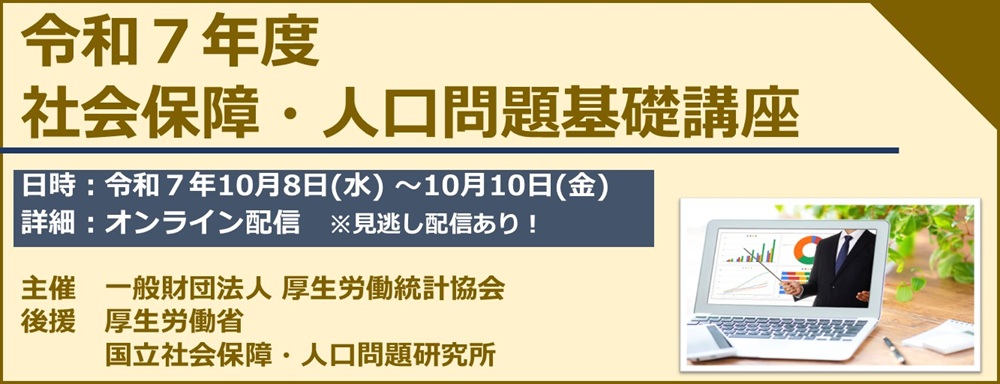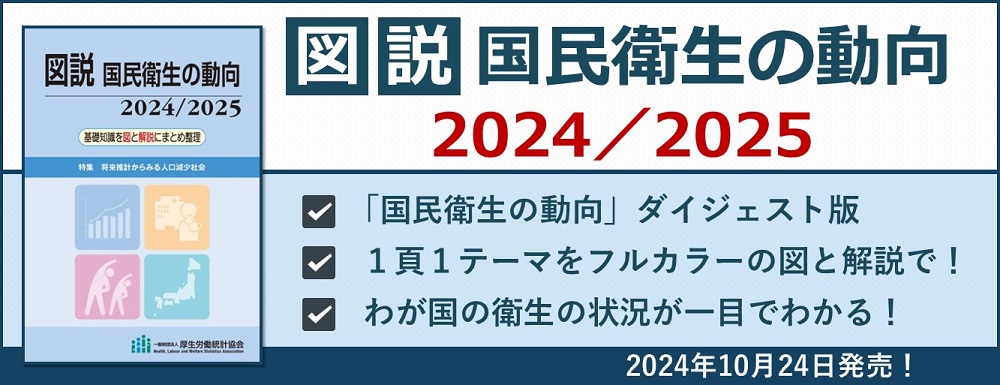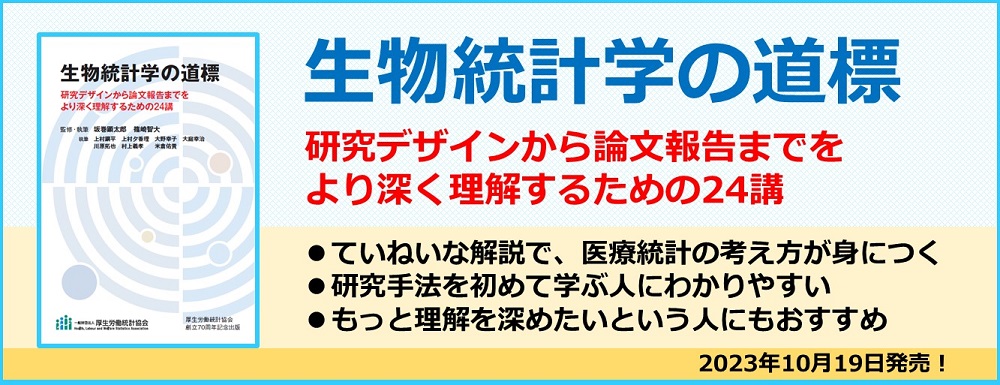|
第59巻第13号 2012年11月 「老衰死」の地域差を生み出す要因-2005年の都道府県別老衰死亡率(性別年齢調整死亡率)と医療・社会的指標との関連-今永 光彦(イマナガ テルヒコ) 山崎 由花(ヤマザキ ユカ) 丸井 英二(マルイ エイジ) |
目的 「老衰死」の地域差を生じさせる要因はこれまで検討されていないことから,今回,2005年の都道府県別老衰死亡率と医療・社会的指標との関連を調べることで,その要因を検討した。
方法 基礎資料として,2005年人口動態特殊報告・都道府県別年齢調整死亡率,2005年人口動態統計,統計でみる都道府県のすがた2007~2010,2004年国民生活基礎調査,2005年医療施設調査,2006年医師・歯科医師・薬剤師調査,2006年度保健・衛生行政業務報告,2005年病院報告,2005年患者調査,2006年度福祉行政報告例を用いた。それらの基礎資料から,老衰死亡率に関連する可能性がある2005年または直近の医療・社会的指標を抽出した。単変量解析としてPearsonの積率相関係数を計算した。次に,それらの中から,Pearsonの積率相関係数の絶対値が0.3以上であった変数を説明変数とし,都道府県別老衰死亡率(性別年齢調整死亡率)を目的変数とした重回帰分析を行った。
結果 重回帰分析の結果,男性では,75歳以上の入院受療率(標準偏回帰係数-0.390,P=0.001),心疾患の年齢調整死亡率(標準偏回帰係数0.229,P=0.04),悪性新生物の年齢調整死亡率(標準偏回帰係数-0.322,P=0.005)が有意な関連指標であった。このモデルの決定係数(R2)は0.824であり,自由度調整済み決定係数は0.800であった。女性では,病院死亡割合(標準偏回帰係数-0.303,P=0.005),85歳以上の年齢階級別死亡率(標準偏回帰係数0.291,P=0.007),訪問診療を行っている病院数(標準偏回帰係数-0.423,P=0.001),第3次産業就業者割合(標準偏回帰係数-0.380,P=0.001)が有意な関連指標であった。このモデルの決定係数(R2)は0.796であり,自由度調整済み決定係数は0.774であった。
結論 2005年の都道府県別老衰死亡率と医療・社会的指標との関連の検討を行ったところ,有意な関連指標をいくつかみとめた。これらの背景には,病院へのアクセスの容易さや医師や患者側の終末期ケア・高齢者ケアへの考え方などの影響があると推測された。今後,実際にどのようなプロセスで老衰死と診断されているかを探索していく必要がある。
キーワード 老衰,老衰死,高齢者医療,超高齢者,地域差