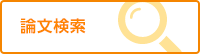論文記事
|
第63巻第5号 2016年5月 看護職における新生児蘇生法の普及の現状と課題樋貝 繁香(ヒガイ シゲカ) 菱谷 純子(ヒシヤ スミコ)橋爪 由紀子(ハシヅメ ユキコ) 立木 歌織(タチキ カオリ) |
目的 看護職における新生児蘇生法(Neonatal Cardio-Pulmonary Resuscitation:以下,NCPR)の普及の現状を明らかにし,課題を検討することとした。
方法 平成25年5~9月に関東近県の病院や診療所26施設の看護職651名を対象とした無記名自記式質問紙調査を実施した。
結果 有効回答は242名(有効回答率37.2%)であった。施設の内訳は病院159名(65.7%),診療所83名(34.3%)であった。対象属性は助産師131名(54.1%)であった。NCPR2010年版の受講者は139名(57.4%)であり,このうち施設内での受講は73名(53.3%)であった。NCPR2010年版への更新者は10名(4.1%)に対し,未更新者は27名(11.2%)であった。産婦人科病棟での勤務の看護職は施設外での講習会受講が有意に多かった(p<0.001)。新生児蘇生法を知っていた165名で職場の勉強会をきっかけとする者が104名(63.0%)と最も多かった一方で,知らない人は77名(31.8%)であった。施設や所属領域と認知や受講の有無の関連は認めなかったが,認知と職種(χ2=13.96,p=0.01)では関連を認め,助産師の認知度が高かった。受講への要望は,受講料の助成78名(32.2%),勤務調整76名(31.4%)であった。
結論 新生児蘇生法の普及には,職場を中心とした情報提供により認知度を上げ,チーム医療の視点を持ちながら地域における講習会の開催が必要である。
キーワード 新生児蘇生法(NCPR),看護職,普及の現状,講習会
|
第63巻第5号 2016年5月 娘による母親の介護と義理の娘による義母の介護の比較-つくば市におけるアンケート調査結果から-桑名 温子(クワナ アツコ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) 森山 葉子(モリヤマ ヨウコ)堤 春菜(ツツミ ハルナ) 柏木 聖代(カシワギ マサヨ) |
目的 家族介護の状況,特に子世代による介護状況を把握することは,今後の介護政策展開の上で重要である。日本ではこれまで,介護者の続柄に焦点をあてた研究は行われてきたが,続柄を娘と義理の娘に限定し,かつ被介護者の要介護度と性別を考慮した上で介護状況を比較した研究はない。そこで,本研究では娘と義理の娘による介護に関し,被介護者の性別を女性に限定した上で,被介護者の要介護度で層別化し,介護期間,介護への考えおよび介護負担感などの状況を比較することとした。
方法 つくば市保健福祉部高齢福祉課が2011年2月に実施したアンケート調査を二次データとして分析した。サンプリングは層化抽出法により,在宅療養中の65歳以上の要支援・要介護認定者1,400名とその主介護者とした。分析対象は介護者が娘または義理の娘である165名のうち,被介護者が女性の115名とした。介護期間や介護者の心情などを比較した後,要介護2以下と要介護3以上で層別化をして同様に分析した。さらに,続柄による違いがあった要介護2以下の層において,年齢や副介護者の有無等を考慮して負担感を検討するために多変量解析を行った。
結果 要介護度で層別化すると,全体で有意差があった項目のほとんどが,要介護2以下の層においてのみ有意差があり,その項目は,娘および義理の娘において,被介護者の年齢(中央値84歳vs88歳),介護期間が3年以上(60.0%vs32.6%),経済的負担がある(22.9%vs4.3%),介護方針の決定に自分の意見が反映される(91.4%vs72.7%)などであった。加えて,住居が持家(88.2%vs100%),介護負担感が高い(31.2%vs54.8%)は,全体ではなく要介護2以下でのみ有意差があった。多変量解析の結果,要介護2以下の層では介護者の年齢,被介護者のIADL,副介護者の有無を考慮しても,義理の娘の方が娘よりも負担感が高かった(オッズ比:3.47,95%信頼区間:1.11-10.88)。
結論 娘と義理の娘という介護者の続柄の違いにより,要介護度が低い場合にのみ被介護者の年齢,介護期間,経済的負担などに違いがみられ,要介護度が高い場合には介護状況にあまり差がないこと,また,義理の娘は年齢や副介護者の有無などの交絡要因を調整しても,被介護者の要介護度が低い場合に娘より負担感が高いことが明らかになった。義理の娘が義母を介護する場合には,要介護度が低くても負担感を軽減するための支援が必要と考えられる。
キーワード 介護者,娘,義理の娘,要介護度,介護負担感,在宅介護
|
第63巻第5号 2016年5月 出生率の都道府県格差の分析田辺 和俊(タナベ カズトシ) 鈴木 孝弘(スズキ タカヒロ) |
目的 現在,わが国の最重要課題の1つである少子化の原因を探るため,生活環境や社会経済的要因との定量的な関係を数理統計モデルに基づいて検討する実証研究を試みた。
方法 47都道府県別の合計特殊出生率のデータを目的変数とし,人口,住居,経済,医療,福祉,教育,生活分野の68種の指標を説明変数として用い,非線形回帰分析手法の1つであるサポートベクターマシン(SVM)により解析した。さらに,それらの候補説明変数の中から感度分析法により決定要因を探索した。
結果 都道府県別の出生率について13種の指標のみを用いて,平均二乗誤差(RMSE)0.042,回帰決定係数(自由度調整済)0.875という高い精度で再現するモデルを構築できた。13種の決定要因の中では,婚姻率,男性失業率,女性管理職等の既検証要因が出生率に大きな影響を与えることを確認した。既検証の要因の他に,女性の喫煙率,デキ婚率,病床数等の決定要因も出生率に大きな影響を与えることを新たに見いだした。
結論 出生率に対する多くの決定要因について先行研究とは異なる結果が得られたが,この原因は,先行研究では限定的な少数の説明変数の中から決定要因を探索しているためであると推測される。
キーワード 少子化,合計特殊出生率,都道府県格差,決定要因分析,サポートベクターマシン
|
第63巻第5号 2016年5月 在宅重度要介護高齢者の
|
目的 短縮版Zarit介護負担感尺度8項目(J-ZBI_8)の下位尺度であるPersonal strainとRole strainという2因子構造を用いて,要介護4以上の重度要介護高齢者を対象として,在宅介護期間別による介護者の介護負担感への関連要因を明らかにすることを目的とした。
方法 A県B市ほか2市において,社会福祉法人や社会福祉協議会が提供する在宅介護サービスを利用しながら在宅生活を継続している重度要介護高齢者とその介護者173組に,2013年7月から12月までに調査を実施した。調査内容は,重度要介護高齢者は属性,状況,居宅介護サービスの利用内容,介護者は属性,状況,意識である。分析は重度になってからの在宅介護期間を「1年未満」「1年以上から3年未満」「3年以上」に区分し,Personal strainと Role strainの2因子それぞれの合計値を従属変数とした重回帰分析を行った。
結果 居宅介護サービスの利用は,いずれの在宅介護期間においても,Personal strainとRole strainでみた介護者の介護負担感を軽減する要因とはなっていなかった。むしろ「1年未満」のPersonal strainと「1年以上から3年未満」のRole strainでは入所系サービスが,「1年以上から3年未満」のPersonal strainでは通所系サービスの利用が有意な正の相関を示し,サービスの利用が介護者の介護負担感を増大させていた。介護生活への充実感や満足感を持っていることは,「1年以上から3年未満」のみ介護者の介護負担感を軽減させていた。重度要介護高齢者との関係性の良さについては,Personal strainでは在宅介護期間に関係なく,また,Role strainは「1年以上から3年未満」で,重度要介護高齢者との関係性が良好であることが介護者の介護負担感を軽減していた。
結論 居宅介護サービスの利用が介護者の介護負担感を軽減することにつながっていないことと,重度要介護高齢者と介護者の関係が良好であることが介護者の介護負担感を軽減していることは,今後の対策を検討する上で重要であろう。今後の課題としては,本研究が横断的調査であることから,縦断的調査による分析により,介護者の介護負担感の経時的変化を検証していくことも必要である。
キーワード 重度要介護高齢者,介護負担感,介護者,Personal strain, Role strain