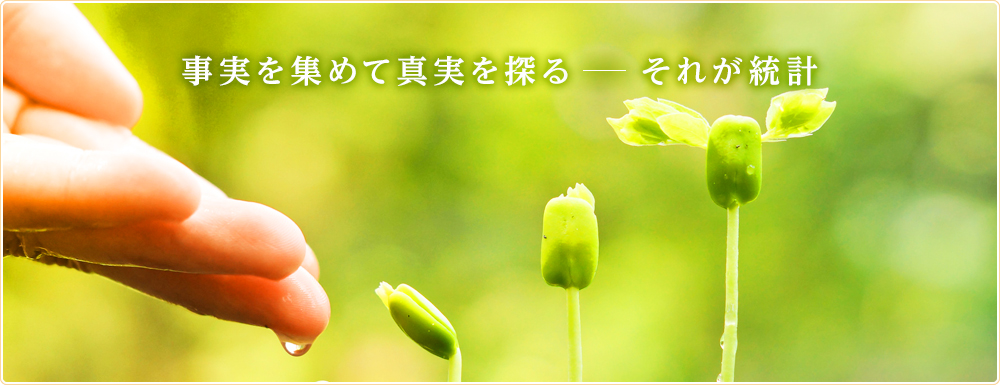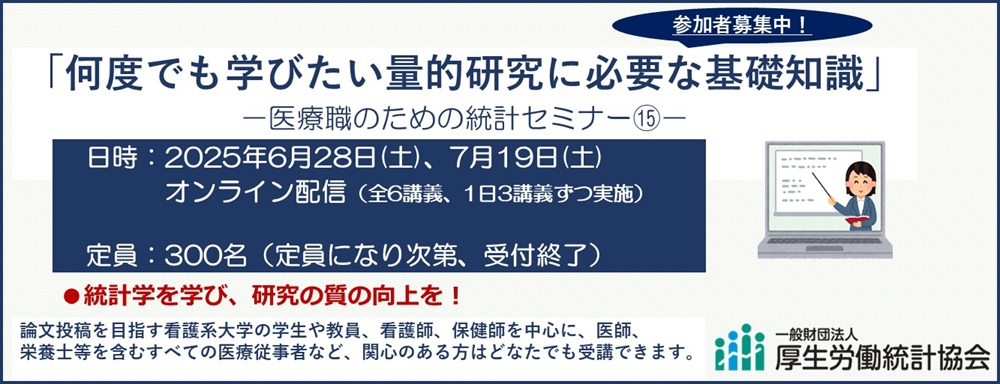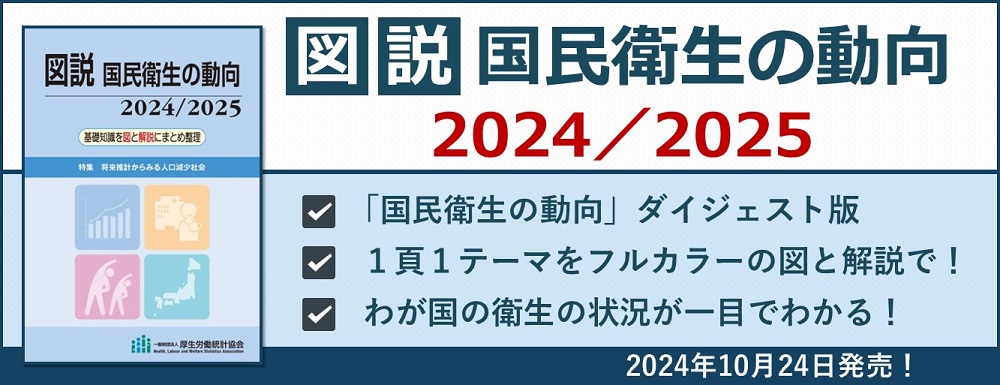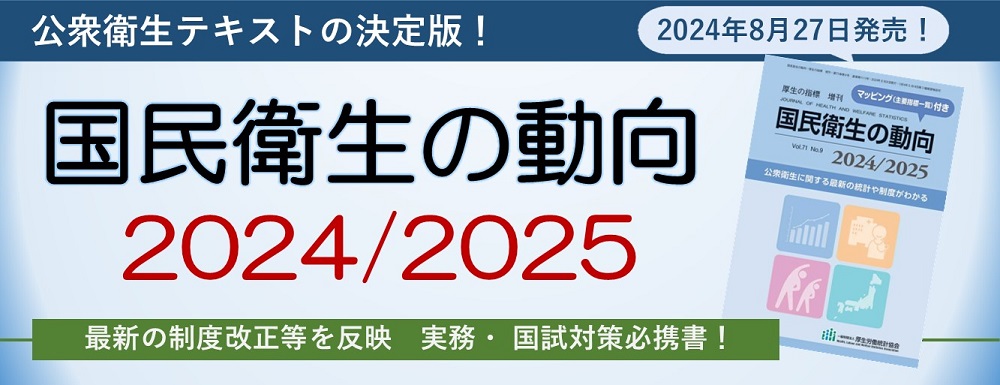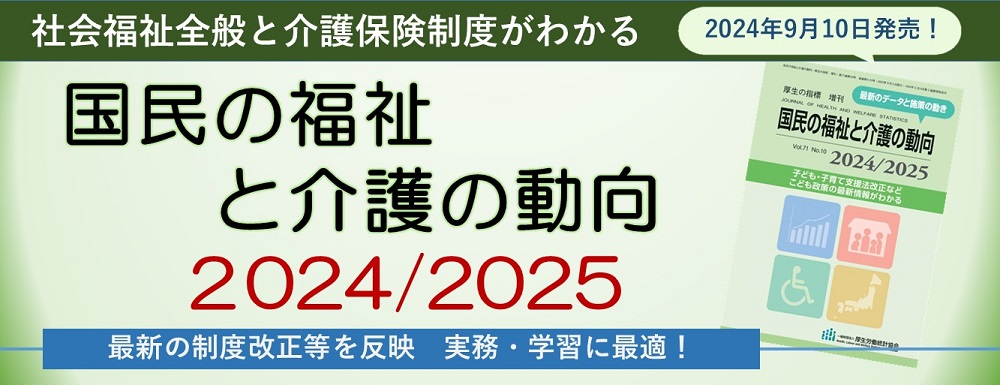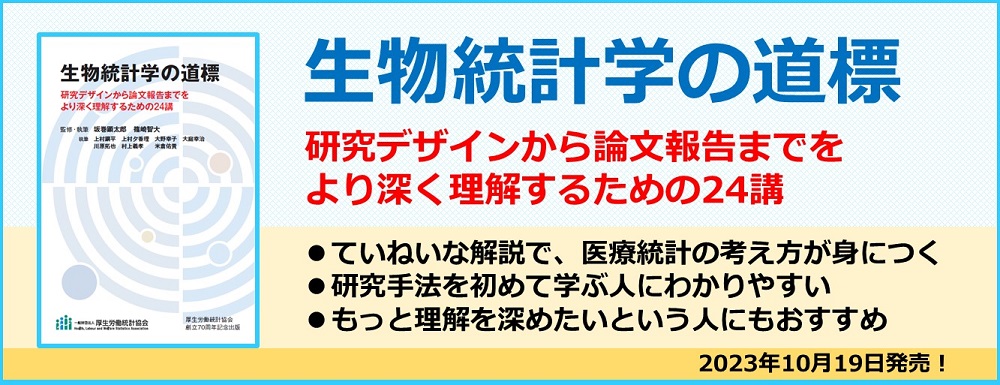|
第57巻第12号 2010年10月 人間ドック受検者の飲酒量が検査値に及ぼす影響と介入効果石川 信仁(イシカワ ノブヒト) 山門 桂(ヤマカド カツラ) 繁田 正子(シゲタ マサコ) |
目的 生活習慣病の進展や関与を指摘されながら,支援や指導への情報が少ない飲酒の問題について,飲酒量による検査値への影響とドックでの介入効果を明らかにする。
方法 対象は2005年に当院ドックを受検した男性5,403名のうち,2007年に再受診した男性3,633名(明らかなアルコール依存症や誤記を除く)とした。問診票より1日当たりの飲酒量に1週間当たりの飲酒日数を掛け,7で割ったものを1回の飲酒量とし,非飲酒群(以下,ND)959名,少量飲酒群(LD:1.0単位/日以下)1,574名,中等量飲酒群(MD:1.1~3.0単位/日以下)943名,多量飲酒群(HD:3.1単位/日以上)157名の4群に分け,検査値との関連を分散分析により検討した。人間ドック当日にCAGE法と久里浜スケールを組み合わせたアルコールアンケートを行い,医師と看護職・栄養士が連携して様々な介入を行い,2年後の飲酒量や検査値の推移を分析した。
結果 各群のγ-GTP(IU/ℓ)の平均値および標準偏差は,ND:34.9±1.2,LD:44.5±1.2,MD:66.7±5.4,HD:96.0±5.8となり,すべての群間で有意差を認めた。その他,中性脂肪,収縮期血圧,BMIが飲酒量に相関して高値であった。適量を超える飲酒量のMDとHDを合せた1,100名において,2年後のγ-GTP,HbA1c,1日当たりの飲酒量,1週間当たりの飲酒日数が有意に低下していた。
結論 健康な成人が受検する人間ドックでさえ,3割の男性は適量超える飲酒,1割は多量飲酒していた。適量を超える飲酒は肝機能や代謝に明らかに悪影響を及ぼしているが,支援や指導により継続受検者では飲酒量の減少が認められ,介入の有効性が示唆された。
キーワード 保健指導,人間ドック,γ-GTP,血圧,中性脂肪,飲酒習慣