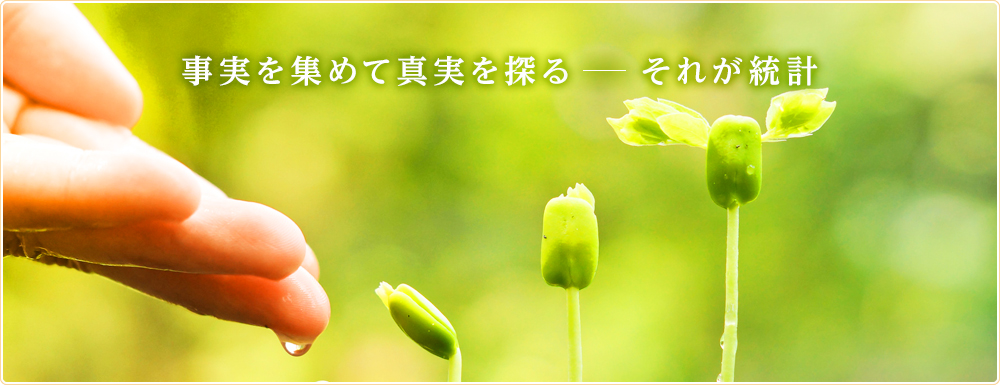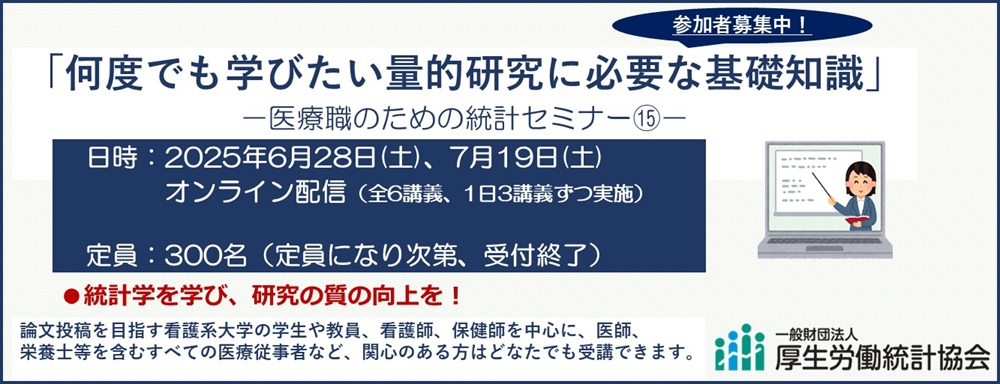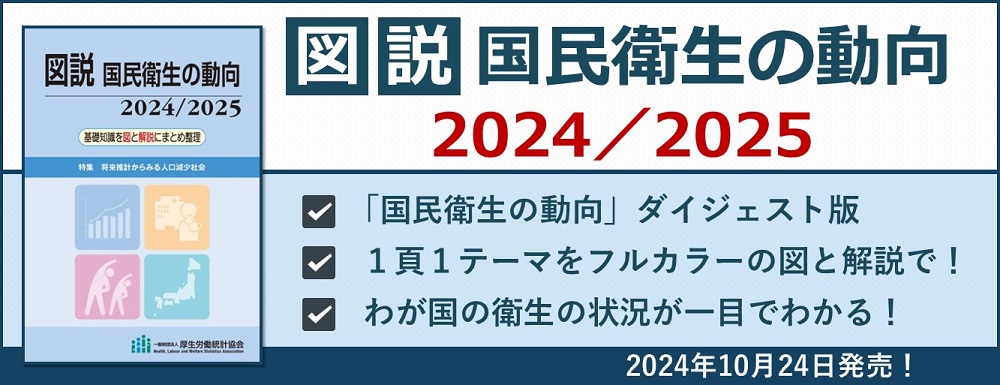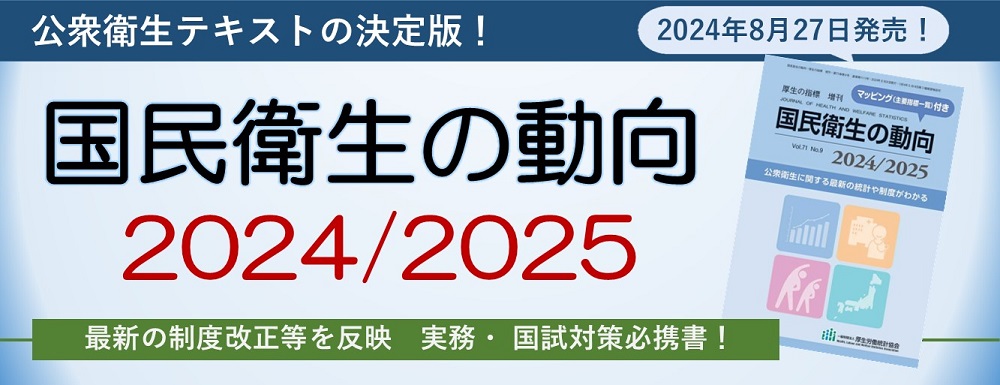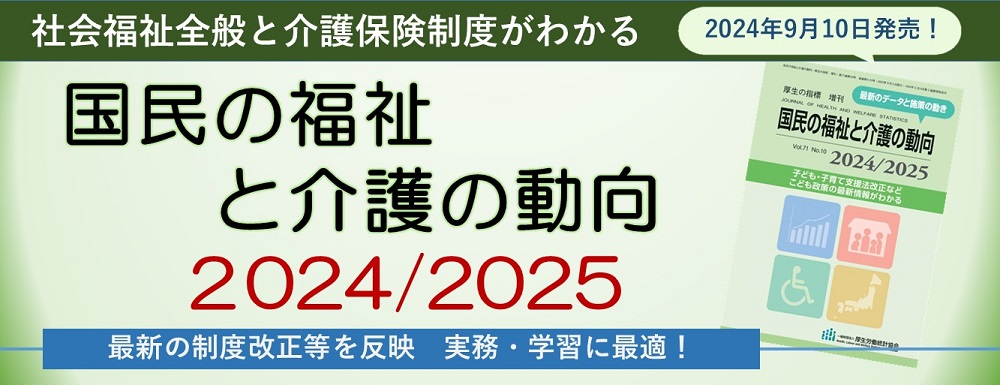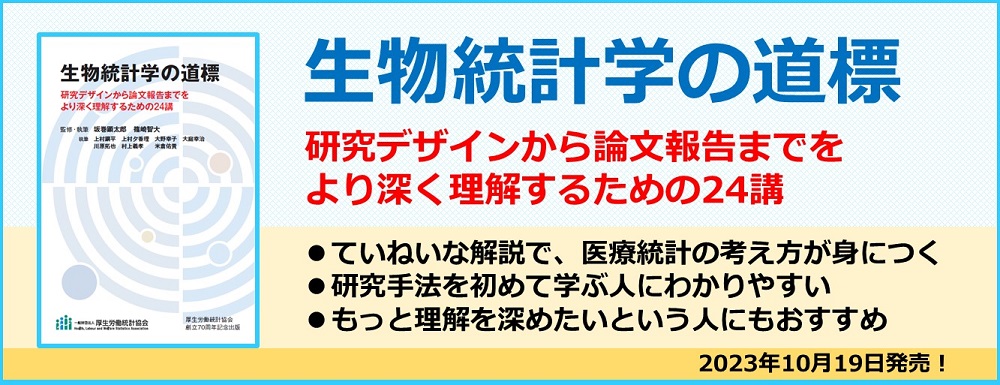|
第51巻第15号 2004年12月 受療のための地域間患者移動に影響する要因の検討寒水 孝司(ソウズ タカシ) 浜田 知久馬(ハマダ チクマ) 吉村 功(ヨシムラ イサオ) |
目的 患者が受療のために地域(医療圏)間を移動する要因を,疾病,医療施設の種類(病院・一般診療所),受療の種類(入院・外来)ごとに明らかにする。
方法 平成11年患者調査データと平成11年医療施設静態調査データから,三次医療圏を単位とした患者の流入・流出割合を「疾病大分類」ごとに計算し,その中でみられた特徴的な患者移動を取り上げる。次に,取り上げた患者移動に影響する要因を,上記データ,関連する統計データ,文献,医師の見解等に基づいて検討する。最後に,得られた結果の一般性を確かめるために,平成8年の調査データについて同様の検討を行う。
結果 どの疾病においても大都市部への患者の流入割合が高いことがわかった。典型的な大都市部圏とその周辺の二次または三次医療圏について,推定流入患者数を目的変数,通勤・通学者数(平成12年国勢調査データ)を説明変数とした単回帰分析を行ったところ,2つの変数間に直線関係がみられた。これは,患者がある一定の割合で通勤・通学先の医療施設を利用しているためであると考えられる。大都市部への通勤・通学者数は多いので,結果として大都市部への患者の流入割合が高くなったと解釈できる。隣接する三次医療圏の患者を除いた流入・流出割合を調べたところ,「新生物」においては,大都市部に患者が流入する傾向がみられた。これは,大都市部に集中する高度な医療技術・設備が患者移動に影響しているためであると解釈できる。「耳及び乳様突起の疾患」の患者の流入割合がある医療圏で高いこと,「精神及び行動の障害」「神経系の疾患」「妊娠・出産に関連した疾病」の患者の流入割合が一般に高いことがわかった。これらの現象は,患者居住地と施設の距離,ドクターショッピング,里帰り出産,という要因によるものと解釈できる。
結論 疾病と地域によって多少の違いはあるが,患者が受療のために医療圏間を移動するのには,①通勤・通学,②高度な医療技術・設備の有無,③患者居住地と施設の距離,④ドクターショッピング,⑤里帰り出産,という要因が影響していると考えられた。各医療圏における患者数を利用するときには,このような要因が影響していることに注意すべきである。
キーワード 患者移動,医療圏,患者調査,医療施設静態調査,医療計画