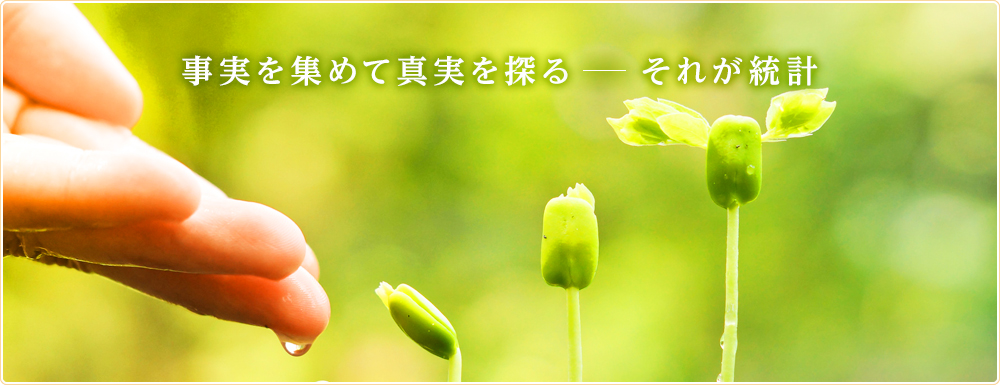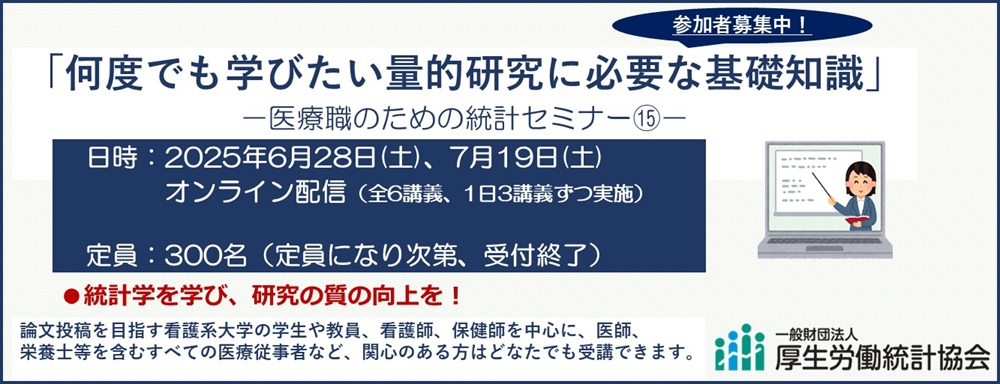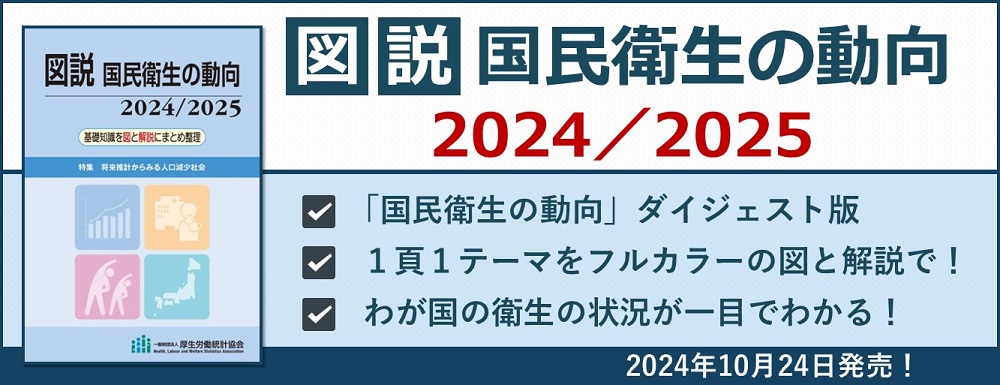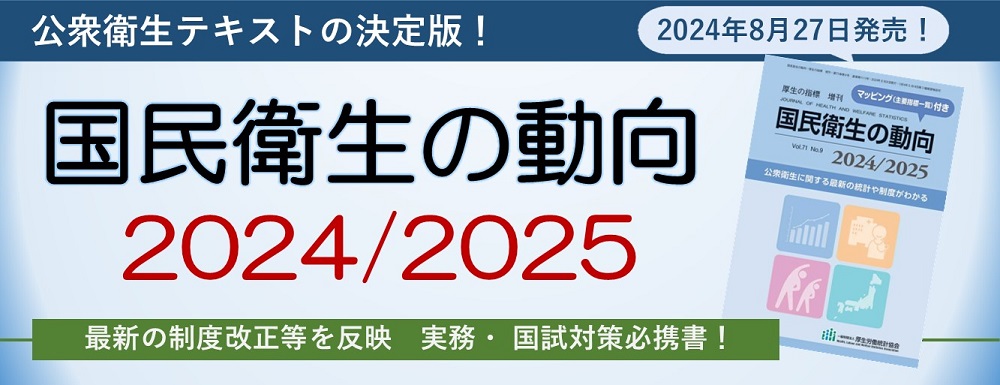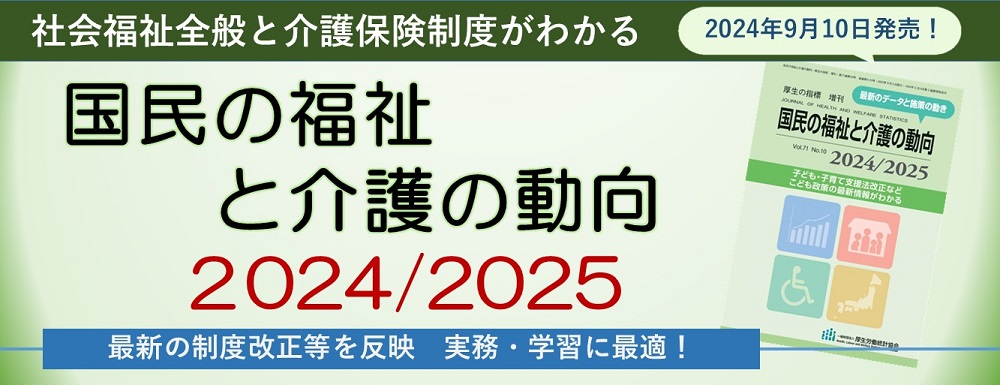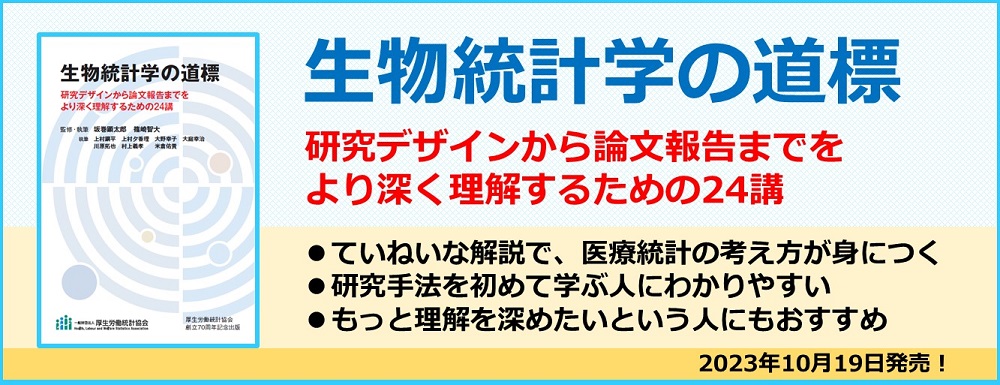|
第59巻第4号 2012年4月 OECDヘルスデータ担当者会合(2011)の報告中山 佳保里(ナカヤマ カオリ) |
Ⅰ は じ め に
OECD(経済協力開発機構)では,34の加盟国から保健医療および保健医療制度に関するデータを収集し,ウェブ上のデータベース「OECDヘルスデータ」として,毎年公表している。データベースの改善のため,加盟国(保健担当省,統計担当機関等)や関係機関(WHO,Eurostat等)が出席するOECDヘルスデータ担当者会合(以下,会合)が,年1回開催されており,データ範囲の拡大や比較可能性の向上について議論している。本稿では,近年の会合における議論の動向を含め2011年10月3,4日に開催された会合(於パリ,参加者数約95名)の議論について報告する。
Ⅱ OECDヘルスデータを巡る近年の動向
はじめに,議論の背景として,ヘルスデータに関する近年の大きな動きを把握しておきたい。第1に,節目となる2010年10月のOECD保健大臣会合(約5年に1回開催)では,コミュニケにおいて「データの違いを説明する要因をより注意深く検証すること等により,データ・情報の比較可能性を高めるべきである」とされた1)。これにより,今年の会合でも,各国から提出された数値を並べるだけでなく,それがどのようなデータであるかの検討に力が入れられ,その分析を受けてデータ区分の改善が進められている。第2に,ヘルスデータ2010から,WHO欧州地域事務局およびEurostatとの合同質問票によるデータ収集が医療支出以外の指標に拡大されたことも,大きな動きの1つである。主に事務局間の調整により,欧州域内の国際比較指標との整理が進められ,新規指標が増えるとともに,既存の指標の定義や区分も見直されている。第3に,これは個々の指標に影響を与えるものではないが,OECDヘルスデータ2011から,公表のプラットフォーム(基盤)が,有料の個別データベースから,OECDの総合統計データベース(保健分野に限らない)であるOECD.Statへ移行することとなった。データベースの70%がID・パスワード不要の無料で提供されるため,データ利用の増大が期待されている2)。
Ⅲ 指標開発に係る議論
OECDヘルスデータに含まれる指標一覧は,ウェブ上で参照可能である2)3)。そのうち,最近の会合の検討対象となった主な指標については表1を参照いただきたい。慢性疾患の増加や医師不足など加盟国における政策課題を反映したものや合同質問票の導入に係る指標が取り上げられ,比較可能性向上のために区分を細分する傾向が見受けられる。以下では,2011年の会合において議論された3点について紹介する4)。
(1) 医療従事者(医師・看護師)の概念に関する議論
現在,医療従事者については,①臨床,②専門活動中,③登録(Practicing, Professionally active, Licensed)の3つの概念についてデータ収集されている。一般的に国際比較で用いられるのは,患者に直接医療サービスを提供する①臨床数であるが,研究者や行政機関で働く者を含む②,あるいは③のみしか提出できない国もある。こうしたデータギャップを埋めるため,今回の担当者会合では,②に関する新たなデータソースとして,労働力調査(Labour Force Survey)の活用について検討された。アイルランド,オランダ,Eurostatにおいて,それぞれ既存の従事者調査あるいは単発で実施した調査と労働力調査をベースとした推計値の比較が行われた。その結果,アイルランドにおいては比較的良い結果が得られたものの,オランダ,Eurostatでは,残念ながら両者の差が非常に大きく,さらには,労働力調査は住民を対象としており,国境を越えた労働力を把握できないとの問題点も指摘され,労働力調査は医療従事者数のデータソースとしては,他にソースがない場合の最後の手段(last resort)とすべきであるとの結論になった。
(2) 医師の種類に関する議論
医師の種類は,従来のデータ収集では,「一般診療」「専門医」「その他」(General practice, Specialist, Others)の3区分に分かれ,専門医については,小児科医,産婦人科医,精神科医等に細分されていた。しかしOECD事務局が2010年に収集されたデータを分析した結果,インターンやレジデントの扱い(訓練中として「その他」と判断する国と実際に診療に携わるため「一般診療」または「専門」とする国),また,専門医ではない医師を「一般診療」「その他」のどちらに振り分けるかにより,データに大きな影響が出ていることが判明した。そのため,OECDヘルスデータ2012からは,一般診療を「家庭医・GP(General Practitioner)」と「その他の一般(インターン等を含む)」に分け,さらに専門の種類にも「その他の専門」の区分を設けることとなった。なお,この論点は,他にも難しい課題が多く,会合でも例えば,GPは専門の一種とすべきであるという見解や口腔科の医師については,歯科医(Dentist)という医師とは別の指標とされているが,医師の専門の1つとすべきであるとの見解等が示されたが,こうした点についてOECDは,国際標準職業分類(ISCO-08)に従っており,現在の分類を維持するとしている。
(3) 手術分類別の手術数に関する議論
手術数については,1人の患者について一連の手術が行われた際,どのように数えるかが1つの論点となる。昨年の議論により,2重計上を避けるためすべての手術・処置ではなく,また過小評価を避けるため主な手術のみの数ではなく,1人の患者の1つの手術分類につき1つのコードまたは患者数(準全数(“Quasi-all”procedures))について報告することとなった。今年はその結果が示され,スペインやイタリアなど報告態様を変更したいくつかの国については,手術数が大幅に減少する例もあったことが紹介された。また,昨年のデータ収集では試験的に日帰り手術の実施場所について,「病院」と「病院以外」の別を設けたところ,病院以外の医療センター等で多くの手術が実施されている国もあることが判明した。一方で病院における手術数しか報告できない国もあり,ひとまずこの区分を維持することが決定された。
Ⅳ データと政策分析プロジェクト
OECDでは,先進国からデータ・情報を入手できる強みを活かし,政策分析のプロジェクトも実施しており,会合でもそうした取り組みの一端が紹介された。現在は,医療サービスの利用のおける格差,メンタルヘルス,介護の質に関する作業等が進んでおり,介護については,2011年5月に増大する需要に対する介護労働力と介護財政に着目した報告書11)が刊行され,今後は,そのフォローアップとして,介護の質に焦点を当てた分析を進めるとのことであった。
Ⅴ お わ り に
OECDヘルスデータは,先進国の保健医療に関する最も包括的なデータソースであり,こうしたOECDによる政策分析での利用に止まらず,各国の政策立案や国際比較研究の基礎資料として頻繁に参照されている。しかし,こうした比較的信頼性が高いといわれるデータベースでも,上述のように,各国が必ずしも同じ中味のデータを提出できているとは限らず,単にデータを並べて,順位を付けるだけでは,現状を正しく理解できないこともある。国際比較データは怪しいという認識を有している人は多いと思うが,実際にデータの中味に踏み込んで検証するのは,かなり手間のかかる作業であり,国際機関でこうした地道な作業が実施されることは歓迎できる。会合でも,山積する課題のほんの一部とはいえ,データの違いによる影響が明確に示され,改めて国際比較データを利用するにあたっての注意喚起となるとともに,有用なデータベースの構築へ向けた重要な取り組みがなされているといえる。
文 献
1)OECD保健大臣会合コミュニケ(http://www.oecd.org/dataoecd/4/55/46163626.pdf)
2)OECD.Stat(Health)(http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT)
3)OECDヘルスデータの指標一覧(和英対照表を含む)(http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_37407_2085193_1_1_1_37407,00.html)
4)OECDヘルスデータ担当者会合2011プレゼン資料(http://www.oecd.org/health/presentations)
5)山﨑亜弥.OECDヘルスデータ担当者会合(2010)の報告,厚生の指標2011;58(4):23-6.
6)山﨑亜弥.OECDヘルスデータ担当者会合(2009)の報告,厚生の指標2010;57(3):1-4.
7)山﨑亜弥.OECDヘルスデータ担当者会合の報告,厚生の指標2009;56(4):1-4.
8)OECD保健医療関係ワーキングペーパー一覧(http://www.oecd.org/els/health/workingpapers)
9)鐘ヶ江洋子訳,OECD編著図表でみる世界の保健医療 OECDインディケータ(2009年版)2010.
10)OECD,“Health at a Glance 2011”,2011.
11)OECD,“Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care”,2011.