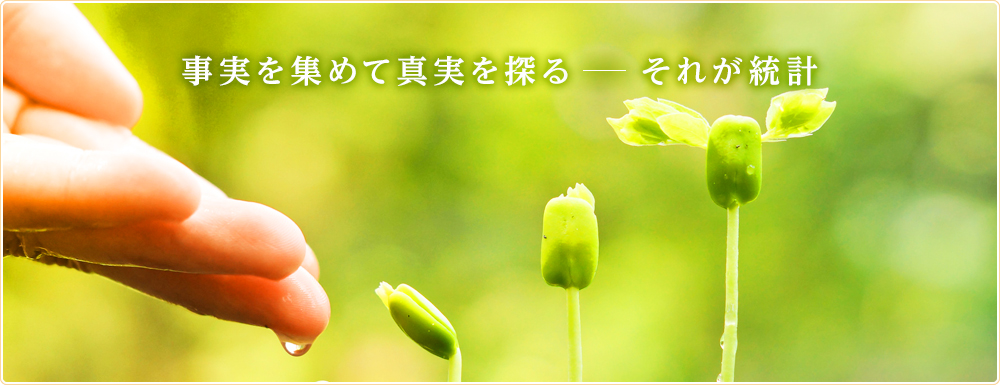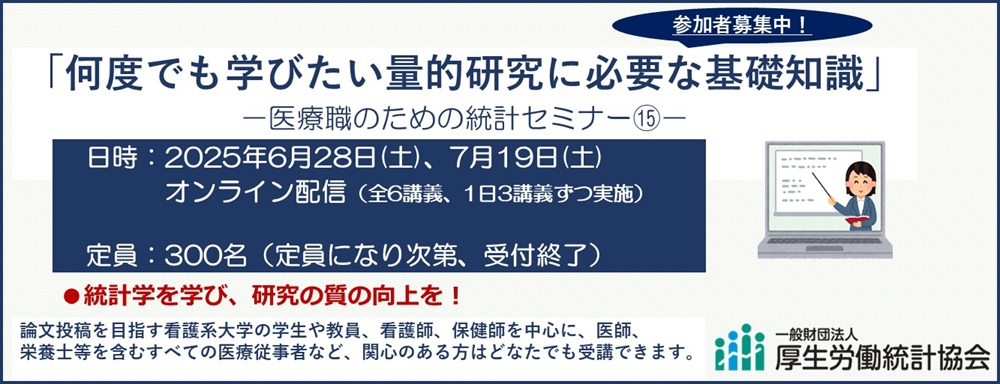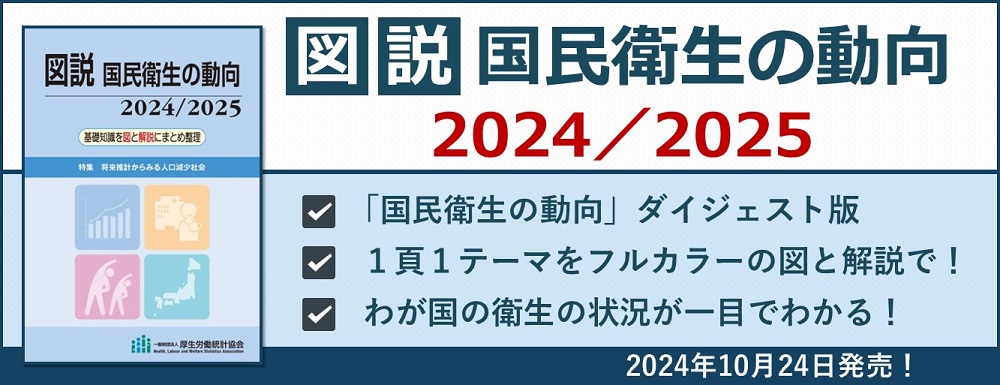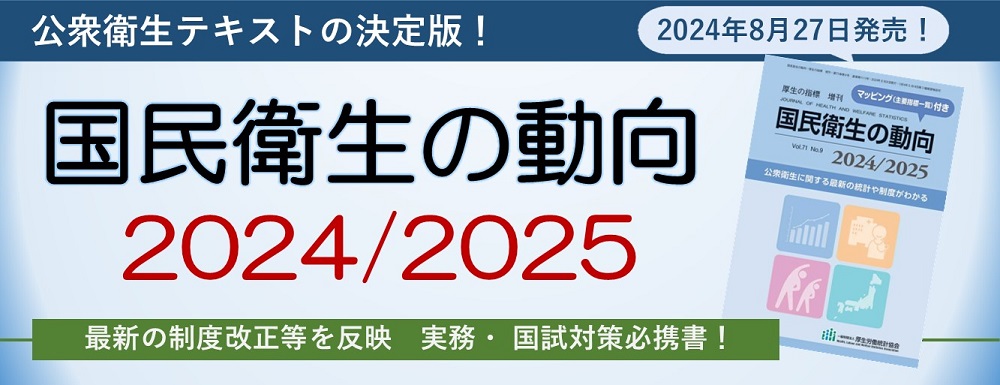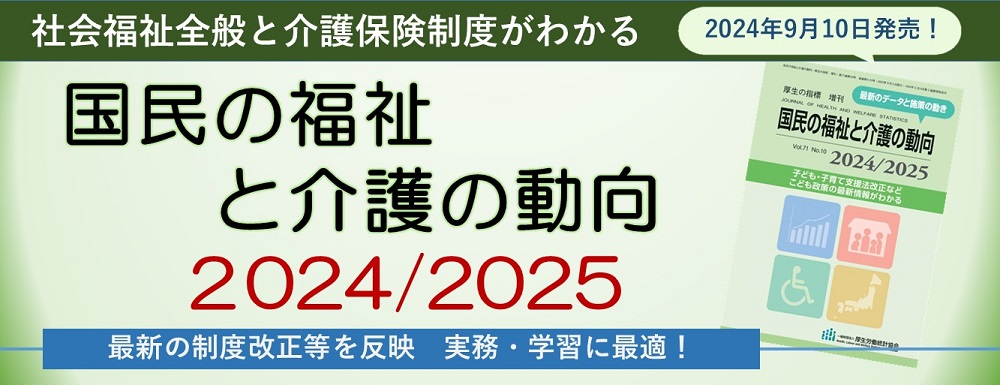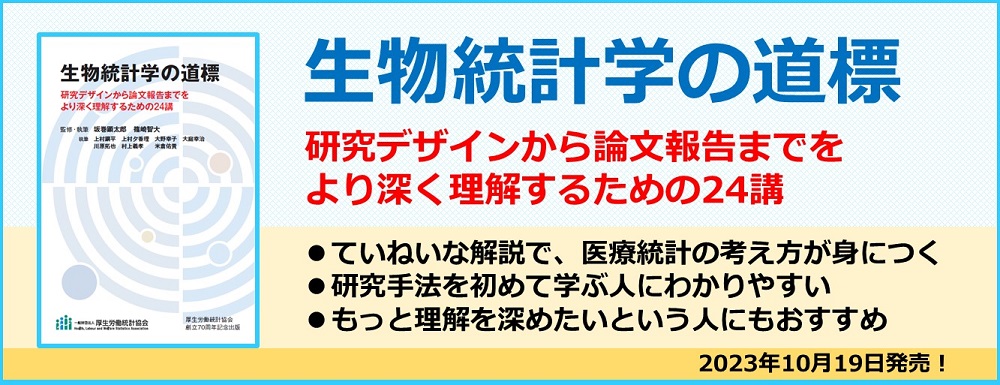|
第51巻第7号 2004年7月 介護サービスに対する家族介護者の意識と評価に関する分析黄 京蘭(ファン ギョンラン) 関田 康慶(セキタ ヤスヨシ) |
目的 (1)介護保険導入前後における介護の社会化に関する家族介護者(以下「介護者」)の意識変化について明らかにする。(2)介護者の介護負担感軽減の程度を明らかにする。(3)介護の社会化に関する介護者の意識(「家族介護重視」「抵抗感」「世間体」)と介護負担感軽減程度の関連性を明らかにする。
方法 介護の社会化に関する介護者の意識と介護負担感軽減程度の関連性を「介護者の意識と評価DB001」データベース(2001年作成、介護者735名)を用いて分析する。分析項目は、前記の3つの介護者意識と介護負担感軽減の程度、介護者および要介護者の属性である。介護保険導入前後の意識変化を明らかにするために、導入前後の意識をクロス分析し、χ2検定を行った。また、介護者の意識と介護負担感軽減程度の関連性を明らかにするために、介護者の意識を4群(「家族中心の介護」群、「介護の社会化肯定」群、「介護の社会化肯定へ変化」群、「家族中心の介護へ変化」群)に分け、分布関数分析を行った。
結果 介護者の大部分が女性であり、65歳以上の介護者の34.8%が老老介護の状態であった。介護者の46.7%が「1日中ほとんど介護している」と回答し、重度(要介護度4、5)の要介護者を抱えている介護者も全体の5割を超えていた。介護保険のサービス利用により、介護者の意識は家族中心の介護観から介護の社会化を肯定する介護観に有意に変化していた(p<0.01)。同サービス利用により介護負担感が減ったと評価した介護者は全体の半数以上であった。介護者の意
識と介護負担感軽減程度の関連分析では、3つの介護者意識ともに、「介護の社会化肯定へ変化」群が他の群より介護負担感が減っていることが判明した。
結論 介護者が家族の絆を大切にしながら在宅介護を続けるために、介護負担を少しでも軽減することを目的としている家族介護支援事業の実施市町村の拡大や、事業対象者に対する広報活動、緊急時のショートステイ、小規模多機能施設の整備や活用などが求められる。また、従来の物理的支援に加え、精神的な支援など様々な活動を行うソーシャルサポートネットワークの地域支援情報システムの整備、活用、運営が必要であり、その拠点として在宅介護支援センターの整備や活動が重要である。ケアマネジャーには地域資源の有効な利用、地域社会との連携や統合などの機能向上が求められる。
キーワード 介護保険、介護の社会化、家族介護者、介護者意識、介護負担感、精神的支援