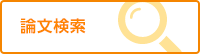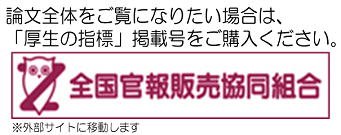論文
|
第72巻第7号 2025年7月 協議会における知的障害者の権利に関する
|
目的 日本は2014年に国連が採択した障害者権利条約を批准した。2022年には障害者権利委員会による総括所見が公表され,公共政策に関する協議における障害者の参加が不十分であることが指摘された。政策に参画する機会には,障害者総合支援法のもと設置される「協議会」があるが知的障害当事者の参画は少なく,参加を保障する研究の蓄積が必要である。またそのためには,知的障害者自身が権利について知る必要があるが,子どもの権利条約のもと自治体が主体となって作成する子どもの権利ノートのように本人に伝える活動もあまりない。本研究の目的は,知的障害者の権利に関する取り組みを促進させるため,当事者への情報提供と協議会への当事者参加に影響する要因および当事者参加の影響を検討することである。
方法 2023年11月から2024年2月までに総務省の「都道府県市町村一覧」にある指定都市および市町村1,741の自治体に依頼文と質問紙を送付した。調査項目は,協議会を設置する自治体の規模,権利擁護部会の設置,当事者また知的障害のある当事者の参加状況などである。
結果 分析対象は回答のあった385の自治体で,人口10万人未満の市・区が33%と最も多かった。協議会への当事者の参加はありが71%で,知的障害当事者の参加ありは6%だった。「権利条約を伝えるパンフレット等の作成」はありが5%,権利ノートへの関心の平均値は1.5(標準偏差0.6)だった。自治体規模と相関係数の高い項目はなく,協議会への当事者参加の有無と権利擁護部会などの項目が関連した。回帰分析の結果,権利擁護部会や自治体規模が当事者に向けた情報提供に,当事者参加が権利ノートへの関心に影響していた。
結論 協議会への知的障害当事者の参加は先駆的自治体を意味し,権利擁護部会などの体制構築は当事者を主体とした取り組みを促進し,当事者参加は直接的なニーズを掘り起こすと考える。政策形成過程の場に当事者が存在することは,人権侵害につながる政策の抑止力につながることから,先駆的自治体をモデルにした知的障害当事者の参加が期待される。そして当事者に権利を伝えることは,「私たち抜きに私たちのことを決めないで」といった権利条約の精神を伝え,政策過程へ当事者の参画を促し,当事者が主体性を獲得することにつながるだろう。
キーワード 協議会,当事者,権利,質問紙調査