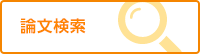論文記事
|
第68巻第3号 2021年3月 地域在住高齢者における社会参加割合変化-JAGES6年間の繰り返し横断研究-渡邉 良太(ワタナベ リョウタ) 辻 大士(ツジ タイシ) 井手 一茂(イデ カズシゲ)林 尊弘(ハヤシ タカヒロ) 斎藤 民(サイトウ タミ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) |
目的 高齢者を対象に就労やグループ活動などの社会参加の推進が進められているが,社会参加割合の内訳を詳細に検討した研究は少ない。本研究の目的は性,年齢階層別に社会参加割合の変化を記述し,その特徴を明らかにすることである。
方法 日本老年学的評価研究(JAGES)の2010~11年度(以下,2010年)および2016年の2時点データを用いた繰り返し横断研究である。要介護認定を受けていない地域在住65歳以上高齢者を対象に郵送自記式質問紙調査を実施した。分析対象は2時点ともに悉皆調査を行った同一の10市町在住の日常生活動作が自立した男性9,567名,女性8,870名(2010年),男性10,038名,女性9,627名(2016年)とした。社会参加の定義は就労やグループ活動(ボランティアの会・スポーツの会・趣味の会)参加の有無とし,就労あり,またはグループ活動いずれか1つでも月1回以上参加で参加ありとした。2時点の参加割合を性・年齢階層別(5歳階層ごと)に記述し,χ2検定で2時点の割合を比較した。また,就労,グループ活動それぞれでも同様の分析を行った。
結果 2010年から2016年にかけて社会参加者割合は,男性で58.1%(5,557名)から61.5%(6,176名),女性で55.1%(4,891名)から62.1%(5,982名)といずれも増加を示した。年齢階層別でも全年齢階層で増加を示した(男性0.7~8.5ポイント,女性2.7~11.8ポイント増加)。内訳をみると就労割合は男女ともに65~69歳で特に増加を示した(6.6~9.0ポイント)。一方,グループ活動参加割合は約6年間で男性の65~74歳は2.1~9.0ポイント減少し,75歳以上で4.9~7.0ポイント増加,女性の65~69歳で1.3ポイント減少し,70歳以上で3.3~11.5ポイント増加していた。また,最もグループ活動参加している年齢階層は2010年で男性70~74歳,女性65~69歳に対し,2016年で男性75~79歳,女性70~74歳とより高年齢化していた。
結論 全国10市町の2010~16年の6年間における社会参加割合の変化を検討した。社会参加割合はすべての年齢階層で増加を示した。内訳をみると就労割合は65~79歳でより大きく増加し,グループ活動参加割合は後期高齢者でより大きく増加を示した。また,最もグループ活動参加している年齢階層が6年間で高年齢化していた。今後も高齢者の若返り,環境整備が進むことで就労割合は増加するとともに,グループ活動参加割合が高い年齢階層がより高年齢化する可能性がある。
キーワード ポピュレーションアプローチ,介護予防,就労,グループ活動,経年変化
|
第68巻第2号 2021年2月 医療系大学の双方向型授業における
山本 隆敏(ヤマモト タカトシ) 田邊 香野(タナベ カノ) 登尾 一平(ノボルオ イッペイ) |
目的 大学教育における実習や演習などの双方向型授業はインフルエンザ感染集団発生のリスクとなることが考えられるが,感染拡大防止を目的とした授業停止の有用性についてはあまり論じられていない。本研究では,季節性インフルエンザ発生増加に伴い双方向型授業のみを停止する機会を得たことから,その感染拡大防止への効果を検証した。
方法 医療系K大学A学科2年次113名を対象に,2018/2019年シーズンのインフルエンザ感染症による出席停止者数を双方向型授業停止前後で約2週間モニタリングした。さらに全員に対してインフルエンザ感染の有無,インフルエンザワクチン接種の有無,感染時の症状,インフルエンザ感染への意識の計4項目のアンケート調査を行った。また,双方向型授業停止の実施時期の妥当性を検証するために過去のデータから基準値を設定し,分析した。
結果 調査対象集団のインフルエンザ感染による出席停止者数は経時的に増加し,出席停止者の割合が15%を超えた時点(113名中18名)で,6日間の双方向型授業のみの停止を実施した(一方向型授業は継続)。その結果,双方向型授業停止解除後の観察期間中の出席停止者の割合は1.8%(113名中2名)まで減少し,対象集団内の流行は収束した。アンケートは111名から回答が得られ(回答率98.2%),すべて有効回答であった。対象集団全体のインフルエンザワクチンを接種した割合は94.6%(111名中105名)と極めて高く,感染した割合は19.0%(111名中21名)であった。インフルエンザ感染者に限っても90.5%(21名中19名)はワクチンを接種していた。感染者の症状では発熱が最も多く(21名中19名),36.9℃以下から40.0℃以上と最高体温は幅広く分布していた。次に,今回行った双方向型授業のみの停止時期が妥当であったか検証したところ,今回の授業停止開始時には既にこの基準値を超えていたことが判明した。
結論 学内でのインフルエンザ感染拡大防止には,双方向型授業のみを感染拡大早期に停止することが効果的であることが明らかとなった。また,ワクチンを接種した割合は極めて高いが,ワクチンの効果に対する知識が乏しいことが明らかとなった。今後は,ワクチン効果の限界について学生への啓発が重要であると考えられた。
キーワード インフルエンザ,ワクチン接種,一方向型授業,双方向型授業,感染拡大防止
|
第68巻第2号 2021年2月 高齢者における熱中症予防行動と
萱場(木村) 桃子(カヤバ モモコ) 近藤 正英(コンドウ マサヒデ) 本田 靖(ホンダ ヤスシ) |
目的 高齢者における熱中症予防行動の実態を明らかにし,さらにシール型温度計の配布が高齢者の熱中症予防における意識や行動を変容させるか評価することを目的とした。
方法 2013年7月に埼玉県A市の住民基本台帳から無作為抽出した65歳以上の高齢者2,124名に郵送で質問票を送付し,2012年夏季の熱中症予防行動について尋ねた。介入群(1,018名)にはシール型温度計を同封した。9月に同様の質問票を送付し,2012年と2013年の熱中症予防行動の比較,また,シール型温度計配布による介入効果を検討した。
結果 有効回答数は989名(有効回答率46.6%)であった。対象者は65-84歳(平均年齢72.5±4.9歳)の男性433名(43.8%),女性556名(56.2%)であった。2012年と2013年の行動を比較すると,エアコン使用時間,エアコン使用開始温度,エアコン設定温度,室温測定で差が認められた。飲水行動については,「喉が渇かなくても時々/定期的に水をよく飲むようにした」との回答が95%以上を占めており,2012年と2013年に差は認められなかった。シール型温度計を配布した介入群では対照群に比べ,2013年のエアコン使用開始室温「暑いと感じたら」,エアコン設定温度「一定の設定温度で決めていない」との回答が少なかった。また,対照群(62.1%)に比べ,介入群では2013年に温度計を「よく見る」と回答した人が75.1%と多かった。
結論 高齢者の熱中症予防行動の実態が明らかになった。シール型温度計配布による介入は高齢者の室温に対する意識を変化させる可能性が示唆された。安価で大量に作成および配布することが可能であるため,大規模集団における熱中症予防に向けた啓発に一定の効果はあると考えられるが,介入群の25%は温度計をあまり見ていなかったという結果を踏まえると,シール型温度計の配布だけでは高齢者の熱中症予防対策としては不十分である。今後,高齢者の熱中症予防行動の変容につながる効果的な介入方法について,さらなる検討が必要である。
キーワード 高齢者,熱中症,シール型温度計,エアコン使用
|
第68巻第2号 2021年2月 年齢層別住民ボランティアの地域活動への認識の特徴橋口 綾香(ハシグチ アヤカ) 池田 直隆(イケダ ナオタカ)岡本 双美子(オカモト フミコ) 河野 あゆみ(コウノ アユミ) |
目的 本研究では住民ボランティアの年齢層と地域活動への認識の関連を明らかにする。
方法 大阪府A市で地域活動を実施する住民ボランティア1,812名を調査対象者とし,無記名自記式質問紙調査を実施した。調査項目は,基本属性,地域活動への認識である。地域活動を見守り活動とし,地域活動への認識として地域コミットメント,地域高齢者見守り自己効力感を把握した。
結果 回収者数1,121名のうち分析対象者は764名であり,64歳以下が177名(23.2%),65~74歳が381名(49.9%),75歳以上が206名(27.0%)であった。対象者の基本属性では,住民ボランティアの年齢層が上がるにつれて女性の住民ボランティアの割合は低くなり(p<0.001),64歳以下が最も就業していた(p<0.001)。また,住民ボランティアの年齢層が上がるほど居住年数や地域活動の活動年数が長かった(p<0.001)。年齢層別にみた対象者の見守り活動および見守り関連活動への認識は,地域コミットメント得点では年齢層と統計学的な有意差はみられなかった。地域高齢者見守り自己効力感得点では,年齢層が高くなるほど見守り活動への自己効力感が高かった(p<0.001)。多重比較の結果,64歳以下と65~74歳(p<0.01),64歳以下と75歳以上(p<0.001),65~74歳と75歳以上(p<0.01)の群間で有意差がみられた。
結論 住民ボランティアの性別は,女性の住民ボランティアの割合が,男性ボランティアの割合より高かった。女性の就業率が上昇する現代日本においては,就業と地域活動によって女性の住民ボランティアの役割が過重になる可能性があり,今後活動内容を工夫する必要があると考えられる。また,地域活動への自己効力感は年齢層が上がるにつれて高くなることが示されたが,地域コミットメントは年齢層と関連がなかった。地域活動の内容は,前・後期高齢世代のニーズや興味に合わせたものである可能性が高いため,幅広い年代の住民ボランティアに調査を実施し,年代のニーズに応じた地域活動の内容へと工夫する必要がある。
キーワード 住民ボランティア,地域活動,地域コミットメント,地域高齢者見守り自己効力感
|
第68巻第2号 2021年2月 障害者手帳所持者数は,なぜ「推計」値か-障害者手帳の交付および所持に関する情報等の管理運用の現況-今橋 久美子(イマハシ クミコ) 北村 弥生(キタムラ ヤヨイ) 竹田 幹雄(タケダ ミキオ)竹島 正(タケシマ タダシ) 飛松 好子(トビマツ ヨシコ) 岩谷 力(イワヤ ツトム) |
目的 現在,身体・療育手帳の所持者数は,標本調査の結果から「推計」されている。平成28年の身体障害者手帳所持者数の推計値は436万人,交付台帳登載数(発行数)は515万人であり,後者が約80万人多い。交付台帳は発行者が管理しており,登載情報は死亡等により手帳が返還された場合に台帳から削除される。未返還により死亡が交付台帳に反映しきれないことが,所持者数の推計値と交付台帳登載数との乖離の原因となっている。もし動態情報を管理している市区町村において手帳交付情報との照合作業が行われていれば,推計に頼らずとも手帳所持数が得られることになる。そこで本研究では,将来的な障害保健福祉データベース構築のための基礎的な情報収集の一環として,手帳発行数と所持者数に違いが生じる背景要因を明らかにするために,市区町村における障害者手帳の交付および所持に関する情報等の管理運用に関する現況調査を行った。
方法 全国1,741市区町村の障害福祉担当部門に調査票を郵送配付した。質問内容は,①障害者手帳交付情報の主な管理方法,②死亡や転出等動態情報との照合状況,③他の制度とのデータ連携状況とした。
結果 1,445市区町村(83.0%)から有効回答を得た。管理方法は,①専用システムを導入し,住民基本台帳システムにおける死亡や転出の情報が自動的に反映される,②都道府県から紙媒体で市区町村に送られた決定内容や住民基本台帳システムの情報を手動で入力する,③動態を全く確認していない,の3つのパターンがあった。方法は一様ではないものの,有効回答のうち,98%は電子媒体で交付情報等を管理し,96%は動態情報と照合していた。動態把握は,手当等の適切な給付のためにも不可欠である旨が自由記述に記載されていた。なお3障害で管理方法や専用システム導入率に大きな差はなかった。
結論 本研究では,市区町村を対象に調査した。回答した市区町村の9割以上において交付情報と動態情報を照合していることから,管理運用上の課題を解決することにより,正確な所持者数の捕捉が可能であることが示唆された。一方で都道府県においては,返還届が進達されない限り,障害者手帳交付台帳に動態情報を反映することが制度上困難である。全国的には都道府県と市区町村との情報共有方法も一様でないことが推察されることから,都道府県における交付台帳の管理運用に関する調査も今後必要と考えられる。
キーワード 障害者手帳,障害者数,交付台帳,市区町村,人口動態,情報管理
|
第68巻第2号 2021年2月 横浜市産婦健康診査の産婦健診補助券からみた
杉原 麻理恵(スギハラ マリエ) 丹野 久美(タンノ クミ) 岩田 眞美(イワタ マミ) |
目的 近年,妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の必要性が重要視され,横浜市では産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図る観点から平成29年度より産婦健康診査事業を実施している。今回,横浜市産婦健診補助券に記載された内容を用いて,産婦健康診査の実施状況を分析し,さらに,エジンバラ産後うつ病質問票(以下,EPDS)の点数が産婦の支援にかかわる人に適切に解釈されるために,産婦の特性によるEPDSの推移の差に関する検討を行った。
方法 平成29年6月から平成30年3月までに横浜市産婦健診補助券を使用して産婦健康診査を受診した産婦15,605人の健診の実施内容・結果を分析した。さらに,2週間健診,1カ月健診の両方を受診し,両健診にてEPDSを使用した産婦8,880人を対象に,独立変数を健診時期(2週間と1カ月),産婦の特性(分娩歴,若年出産,高齢出産,多胎の有無),従属変数をEPDSの合計点数とし,反復測定二元配置分散分析を行い,産婦の特性の差によるEPDSの点数の推移について,有意な差異がみられるかを検討した。
結果 当該期間に2週間健診を受診した産婦は9,585人であった。2週間健診で「異常あり」とされた産婦は1,133人で,うち805人が9点以上であった。81人が区の福祉保健センターに報告され,7人が精神科に紹介された。2週間健診で9点以上だった産婦の32%が1カ月健診においても9点以上であったが,1カ月健診で9点以上であった産婦の約半数は2週間健診では低値であった。初産婦のEPDSの点数は2週間・1カ月健診共に経産婦に比べ有意に高く,高齢産婦の点数は,2週間健診では有意に低かったが,1カ月健診では有意差は認めなかった。いずれの要因でも,2週間健診のEPDSの点数が1カ月健診に比べて高値であった。2週間と1カ月健診の間での初産婦の点数の低下は顕著であり,他要因による交互作用が示唆された。分娩歴および高齢出産の有無による4層の層別解析では,2週間・1カ月健診ともに初産婦のほうが有意に高値であったが,高齢出産の有無による有意差は認めなかった。
結論 初産婦のEPDSの点数は経産婦と比較して一貫して高値であった。特に初産婦の産後2週間前後におけるメンタルヘルスの悪化は明確であるが,産後1カ月後には急速に回復する。EPDSの推移を参考にしながら,回復が遅れる初産婦の特性を把握し,早期介入に結び付けることが重要である。
キーワード 産婦健康診査,産後うつ,エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS),妊産婦のメンタルヘルス,産後の支援
|
第68巻第2号 2021年2月 東京都の医師の近隣県への派遣の状況に関する検討-2018年東京都が実施した調査に基づく分析-山内 和志(ヤマウチ カズシ) 田口 健(タグチ タケシ)森脇 睦子(モリワキ ムツコ) 河原 和夫(カワハラ カズオ) |
目的 東京都から近隣県への医師の派遣の状況を明らかにする。
方法 東京都が実施した専攻医プログラムの基幹施設である都内の医療機関および基幹施設となっていない大学病院,分院を対象とした医師派遣に関する調査の再分析を通じて,他の医療施設に派遣された医師数の詳細を分析し,さらに都外に派遣された医師数がその県内の医師数の占める割合を診療科別に推計した。
結果 派遣された東京都の医師のおよそ半数は都外の医療機関で診療に派遣されていた。女性医師は男性医師と比較して派遣地域が東京都や埼玉県である割合や,派遣期間が6カ月~1年未満である割合は高い傾向を示した。派遣された医師は,その県の医師数の10%を超え,また病院に従事する医師数の20%を超える診療科もあった。この場合,最低でもその県の診療科医師の4~5人に1人は東京都内の医療機関からの派遣医師であることを示しており,近隣県において,特に病院診療において医師確保が都内医療機関から移動する医師を供給源として一定の割合を占めている状況が明らかになった。
結論 東京都と近隣県の医師の供給については,一つの都県内だけでなく地域全体の現状を含めて考えていくことの重要性が示唆された。
キーワード 医師派遣,地域医療,医師確保,東京都
|
第68巻第1号 2021年1月 医療施設の曜日別診療状況と
三重野 牧子(ミエノ マキコ) 橋本 修二(ハシモト シュ二ウジ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) |
目的 患者調査の総患者数の推計方法は1990年頃の診療状況に基づくことから,見直しの必要性が指摘されている。最近の医療施設の曜日別診療状況を観察するとともに,推計方法の調整係数(平日の調査による再来外来患者数を1週間の平均再来外来患者数に調整する係数)について,1週間のうちで日曜が休診の想定による現行値(6/7),土曜の午後と日曜が休診の想定による代替値(5.5/7)の適切性を検討した。
方法 2005~2017年の患者調査と医療施設調査を利用した。患者調査による平日1日の再来外来患者数に対する,医療施設調査による1カ月間の平均再来外来患者数の比(調整係数の相当値と呼ぶ)を算定した。
結果 2017年の診療施設割合をみると,病院では午前・午後・18~19時ともに月~金曜でほぼ一定であり,土曜でそれより低かった。一般診療所と歯科診療所では午前・午後・18~19時ともに月・火・水・金曜でほぼ一定,木曜と土曜でそれより低かった。2005年と2017年の診療施設割合の差をみると,病院・一般診療所・歯科診療所,月~日曜と祝日の午前・午後・18~19時ともに-4~5%の範囲内であった。2005~2017年の調整係数の相当値は病院で平均6.2/7(範囲6.1/7~6.3/7),一般診療所で同5.8/7(5.7/7~6.0/7),歯科診療所で同4.7/7(4.4/7~5.0/7)であった。
結論 2005~2017年の曜日別診療施設割合は病院,一般診療所,歯科診療所の間に相違がみられたが,年次間ではほぼ一定傾向であった。調整係数としては,代替値への変更が支持されず,また,歯科疾患の推計に課題があるものの,現行値が比較的適切であると示唆された。
キーワード 医療施設調査,患者調査,総患者数,調整係数,保健統計
|
第68巻第1号 2021年1月 現代日本における格差と貧困の所在地平原 幸輝(ヒラハラ ユウキ) |
目的 地域福祉の地域アセスメントにおけるニーズ調査として,どの地域において経済的な格差が大きく,貧困に直面している人々が多いのかという点を明らかにする。
方法 2018年の『住宅・土地統計調査』データから算出される所得関連指標を,2015年の『国勢調査』データから算出される社会経済指標によって説明するモデルを,相関分析と重回帰分析を通じて導く。そこで導かれた回帰モデルに基づき,『住宅・土地統計調査』にデータのある自治体(または政令指定都市の区。以下同じ)は実測値,データのない自治体は推定値を用いることで,日本全国の市区町村における所得関連指標を網羅する。そして,得られた所得関連指標の値をZ得点化した上で,極めて深刻な格差や貧困の問題に直面している自治体を明らかにする。
結果 各自治体における社会経済指標が所得関連指標に影響を与えていることが示される中で,経済的な格差の大きさを示すジニ係数には単独世帯比率が,貧困層の多さを示す年間収入200万円未満世帯比率には老年人口比率が,最も強い正の影響を与えていた。また,格差や貧困の状況が空間分布として示され,極めて深刻な格差や貧困の問題に直面している自治体も示された。特に,格差への対策が求められる自治体には都市部,貧困への対策が求められる自治体には離島地域,格差や貧困への対策が求められる自治体には町や村といった郡部の自治体が,それぞれ多く含まれていた。
結論 本研究を通じ,日本全国の市区町村における所得関連指標を網羅することが可能になり,格差や貧困に対する取り組みが必要となる自治体が明らかになった。そして,このマクロ的な統計分析によって,現代日本における格差と貧困の現状を把握することが可能となり,格差と貧困に関する地域アセスメントにおけるニーズの把握が実現された。
キーワード 福祉,地域福祉,地域アセスメント,格差,貧困,ジニ係数
|
第68巻第1号 2021年1月 虚弱高齢者の自己決定を尊重した
笠原 幸子(カサハラ サチコ) 畑 智惠美(ハタ チエミ) |
目的 本研究では,超高齢社会を支えるために,専門職としての成熟が求められている介護福祉士が,虚弱高齢者の自己決定をどのように支援しているのか,介護福祉士の実践の構造を明らかにし,その実践に関連する要因を検討することを目的とする。
方法 A県介護福祉士会の会員を対象に自記式調査票を用い,2017年7月15~31日に郵送調査を実施した。分析は,第1に,虚弱高齢者の自己決定を尊重する介護福祉士の実践の構成因子を実証的に捉えるために,因子分析を行った。第2に,介護福祉士の実践の関連要因をとして有能感を取り上げ,その構成因子を実証的に捉えるために,因子分析を行った。第3に,介護福祉士の実践の構造に関連する要因を検討するために,従属変数には介護福祉士の実践の因子ごとの合計素得点を,独立変数は「職場外のスーパービジョン」「実践の振り返り」,介護福祉士の有能感の因子ごとの合計素得点等を投入し,強制投入法による重回帰分析を行った。
結果 第1の因子分析の結果,虚弱高齢者の自己決定を尊重する介護福祉士の実践は,「意向と主体性の把握」「主体的実行を引き出す支援」「関係づくり」の3因子が抽出された。第2の因子分析の結果,「業務の達成」「仕事上の予測と問題解決」「自己啓発と能力発揮」の3因子が抽出された.第3の重回帰分析の結果,「意向と主体性の把握」では,「仕事上の予測と問題解決」「実践の振り返り」「職場外のスーパービジョン」が正の有意な関連を示した。「主体的実行を引き出す支援」では,「自己啓発と能力発揮」「実践の振り返り」「介護福祉士としての経験年数」が正の有意な関連を示した。「関係づくり」では,「実践の振り返り」「自己啓発と能力発揮」が正の有意な関連を示した。
結論 虚弱高齢者の自己決定を尊重する介護福祉士の実践は,①「意向と主体性の把握」(虚弱高齢者の主体性を尊重しつつ意向を把握すること),②「主体的実行を引き出す支援」(選択肢の提示や待つこと等によって虚弱高齢者の主体的実行を引き出すこと),③「関係づくり」(自らの心を開いて接すること等によって虚弱高齢者との関係づくりをすること)の3領域が確認された。また,自らの実践を振り返っている,仕事上の予測と問題解決ができる,自己啓発と能力を発揮していると回答した介護福祉士ほど,虚弱高齢者の自己決定を尊重する実践ができていた。
キーワード 自己決定,介護福祉士,虚弱高齢者,量的研究,主体性,関係づくり
|
第68巻第1号 2021年1月 有料老人ホームにおける虐待予防策への取り組みの実態と課題-「介護付き」「住宅型」有料老人ホームと「特別養護老人ホーム」との比較をもとに-松本 望(マツモト ノゾミ) |
目的 本研究は,有料老人ホームのタイプ別に,虐待予防に向けた取り組みの実態と課題を明らかにすることを目的とした。
方法 調査は質問紙を用いて行い,A県にあるすべての有料老人ホーム,「特別養護老人ホーム」に書面にて調査への協力を依頼し,同意が得られた施設に勤務する全介護職員を調査対象として実施した。質問紙では,虐待予防策,基本属性について調査した。
結果 1,412名分の質問紙を回収し(回収率43.8%),そのうち「健康型」の有料老人ホームの3名分の回答と,欠損値のあった回答を除外した1,309名分を有効回答とした(有効回答率40.6%)。まず「虐待予防策」について探索的因子分析を行った結果,「職員の特性」「職場の人間関係」「上司の特性」「負担感のなさ」「職場の虐待への対策」の5因子が抽出された。次に,施設種別ごとに虐待予防策への取り組み状況を比較したところ,「職員の特性」「職場の人間関係」「職場の虐待への対策」の三つの因子に有意な差がみられた。まず「職員の特性」では,「住宅型」と「特別養護老人ホーム」(p<0.01),「介護付き」と「特別養護老人ホーム」(p<0.01)で有意な差がみられ,「住宅型」「介護付き」「特別養護老人ホーム」の順に得点が高かった。「職場の人間関係」では,「特別養護老人ホーム」と「介護付き」(p<0.05),「特別養護老人ホーム」と「住宅型」(p<0.05)で有意な差がみられ,「特別養護老人ホーム」「介護付き」「住宅型」の順に得点が高かった。最後に「職場の虐待への対策」では,「特別養護老人ホーム」と「住宅型」(p<0.01)で有意な差がみられ,「特別養護老人ホーム」「介護付き」「住宅型」の順で得点が高い傾向がみられた。
結論 「介護付き」「住宅型」の有料老人ホームにおいても実際に虐待が発生していることから,より質の高いケアを目指す必要がある。具体的な取り組みとしては,研修等により職員の知識や意識を維持・向上させるような取り組みや,職員同士が連携・協働できる体制づくり,施設全体で虐待の未然防止や相談・対応の体制整備に取り組むこと,そして経営層も含め施設全体の虐待に対する認識を高めていくことなどが求められる。
キーワード 介護付き有料老人ホーム,住宅型有料老人ホーム,特別養護老人ホーム,虐待予防策
|
第68巻第1号 2021年1月 改正健康増進法の必要性坂口 早苗(サカグチ サナエ) 坂口 武洋(サカグチ タケヒロ) |
目的 近年,喫煙防止教育や活動の成果によって,喫煙率は確実に低下しているが,喫煙者のマナーは向上しているとはいえない。大学生の喫煙および受動喫煙に関する調査を実施し,実際にどのような迷惑が生じているかについて把握し,併せて健康増進法の改正がいかに必要であったかを示すことを目的とした。
方法 調査対象者は関東地方にある女子大学の学生1,274人のうち,年齢および喫煙経験の記載があった1,214人であり,調査時期は2008~2019年の毎年秋に,協力の得られた約100人ずつに対し,その場で質問紙およびデータ用紙に記入を依頼し回収した。調査項目は,自記式の質問紙調査,呼気中のCO量および手先の皮膚温度の測定である。
結果 調査対象者の喫煙未経験率は,91.9%であった。呼気中のCO量の平均値は2.0±2.2(±標準偏差)ppm,COHbの平均値は0.8±0.6%,手先の皮膚温度の平均値は30.9±2.5℃であった。タバコの有害性に関する認知度は「身体への有害性」「肺がん」「胎児への影響」および「子どもへの影響」が90%以上であった。一方,「中年太り」「女性の禁煙しにくさ」および「女性の易依存性」については50%以下であった。喫煙未経験者1,024人の呼気中のCO量は,5~6ppmが7.4%,7ppm以上が2.0%であった。直近の暴露場所はアルバイト先が26.7%,居間が24.2%,居酒屋および歩きタバコがそれぞれ8.2,8.1%であった。2018~2019年の対象者126人に追加質問した結果,三次喫煙の認知度は38.9%,「喫煙30分後まで呼気中に有害物質が排出」されることを知っている者は63.5%であった。受動喫煙により迷惑と感じた経験については,喫煙後の人がタバコ臭いと感じた者は96.8%,タバコの煙で食事がまずくなった経験を有する者は78.6%,自分の髪の毛や洋服がタバコ臭いと感じた者は69.8%であった。
結論 最初の1本を口にしないための喫煙防止対策はかなり充実してきているが,タバコが身近にない環境(受動喫煙防止,防煙)対策はいまだ進んでいないこと,分煙では受動喫煙防止に効果がないことが明白となった。改正健康増進法の遵守と同時に,飲食店従業員の健康を護る対策が引き続き求められる。
キーワード 改正健康増進法,呼気中CO量,受動喫煙,三次喫煙,受動喫煙防止条例
|
第67巻第15号 2020年12月 奈良県における後期高齢者医療費と保険料水準の理論推計西岡 祐一(ニシオカ ユウイチ) 野田 龍也(ノダ タツヤ) 今村 知明(イマムラ トモアキ) |
目的 今後の日本の人口と医療費の推移のモデルとして,奈良県の後期高齢者医療制度の悉皆(全数)調査である国保データベース(以下,KDB)を用いて奈良県の後期高齢者医療費の推移について推計し,今後の医療費と後期高齢者医療保険料水準について考察する。
方法 奈良県人口調査年報および奈良県年齢別人口調査を用いて,男女別年齢別人口を1歳刻みで調査した。2018年10月1日現在の奈良県の年齢別人口から,①奈良県と奈良県外との間の男女別年齢別人口の流出入が同じである,②男女別年齢別死亡率は2018年簡易生命表のもので不変である,と仮定してその死亡率を基に2019年から2093年までの75歳以上の人口の推計を行った。医療費については奈良県KDBを用いて75歳以上の医療費合計を集計し,後期高齢者医療保険制度の75歳以上の被保険者1人当たりの医療費を年齢別に集計した。最後に人口1人当たりの医療費と75歳以上の人口推計を掛け合わせて,2019年度から2093年度までの75歳以上の医療費を推計し,これを基に後期高齢者医療保険の被保険者1人当たりの医療費を推計した。
結果 奈良県の75歳以上人口は,2017年の197,702人から2028年の261,400人まで増加し続け,それを境になだらかな減少ないし横ばいに転じる。その後2050年には227,899人となり,その後さらに減少し続けた。死亡率,現状の医療・介護体制がこのまま継続したとすると,2030年度以降は奈良県における後期高齢者医療費は,およそ1人当たり87,000~90,000点の間で推移した。特に今後10年間,後期高齢者人口は急激に増加し,総医療費も増加傾向を示す。一方,保険料水準と強く相関する後期高齢者1人当たりの医療費は,後期高齢者人口が急激に増えるタイミングで一旦減少傾向を示し,その後再び増加傾向に転じると推測された。
結論 本研究は,奈良県における75歳以上の後期高齢者の人口,医療費についての推計手法・推計結果を提供し,保険料水準の推移について考察した。0~74歳の人口は既に決まっており,死亡率,医療費のデータを用いることで,今後の医療費や保険料水準の推移を精緻に推計できることを示した。これらの推計は今後の社会保障制度を考えるうえで重要な基礎資料となる。
キーワード 後期高齢者,医療費,KDB,国保データベース,奈良県
|
第67巻第15号 2020年12月 ADL維持向上等体制加算における
松岡 森(マツオカ シン) 山田 修(ヤマダ オサム) 中上 和洋(ナカウエ カズヒロ) |
目的 消化器内科入院症例における入院日数が長期化する要因を明らかにし,ADL維持向上等体制加算におけるリハビリテーション(リハ)開始基準を検討した。
方法 対象は,2018年4月1日から9月30日の間に当院消化器内科に入院した396例を対象とした。今回の対象集団の入院期間の中央値である7日を基準とし,7日未満を短期入院群(S群),7日以上を長期入院群(L群)に分類し,患者因子(年齢・性別・入院方法:緊急/予定)・身体機能(入院時Barthel Index(BI)60点以上/未満・自立歩行可否)・社会的背景(独居有無・介護保険有無)・治療因子において比較・検討した。入院日数7日以上/未満により分類された2群を単変量解析し,単変量解析にて有意差を認めた項目を説明変数とした多重ロジスティック回帰分析にて入院日数との関連性を検討した。
結果 対象期間に消化器内科に入院した症例は,S群196例/L群200例であった。単変量解析では,年齢・緊急入院・入院時BI60点未満・自立歩行不可・介護保険有は,L群で有意に高値を示した。独居有無・治療因子は,有意差を認めなかった。多重ロジスティック回帰分析では,入院日数7日以上は緊急入院(オッズ比=0.47,95%信頼区間:0.29-0.77,p=0.003),入院時BI60点未満(オッズ比=0.34,95%信頼区間:0.14-0.80,p=0.013)と関連を示した。
結論 消化器内科入院患者において,緊急入院・入院時BI60点未満の症例は入院期間が長期化しやすく,ADL維持向上等体制加算による早期リハ介入の適応基準となる可能性が示唆された。
キーワード ADL維持向上等体制加算,リハビリテーション開始基準,消化器内科,入院日数
|
第67巻第15号 2020年12月 社会福祉施設における高齢者ボランティア受け入れの現状と課題-地域活動への展開を目指して-守本 友美(モリモト トモミ) |
目的 本研究では,まず,近年着目されている「地域共生社会」の担い手として期待されている高齢者の実践活動を進めるために,ボランティア活動が誘因となるという仮説を立てた。それを証明するための前段階となる基礎的資料を提示するとともに,高齢者ボランティアの意識および活動の展開・発展につながる福祉施設による支援方法を考察することを目的とした。
方法 A市所管の介護老人福祉施設への質問紙調査を実施した。調査期間は2019年6月20日から7月31日であった。A市所管の介護老人福祉施設数は151施設であり,調査票回収数は58件で,回収率は38.4%であった。調査項目は,運営主体,開設からの年数,入所定員,職員数,ボランティアの受け入れの有無,ボランティア受け入れの目的,65歳以上のボランティアの受け入れ状況と募集の方法,ボランティア活動の内容,ボランティアを受け入れる際の課題,ボランティア受け入れ担当者の有無,ボランティアコーディネーションの内容とした。
結果 介護老人福祉施設におけるボランティア受け入れの現状から,87.9%の施設がボランティアを受け入れており,そのうちの86.3%の施設で高齢者が活動していることから,高齢者のボランティアが高齢者福祉分野で活躍していることがわかった。ボランティア受け入れ担当者については,37施設,63.8%の施設が配置をしている。ただし,ボランティアを受け入れている施設は51施設,87.9%という調査結果からみると,ボランティアを受け入れていても,担当者が配置されていない施設があるということがわかる。また,受け入れに際しては,活動内容・範囲などの配慮を行っていることが明らかになった。
結論 社会福祉施設で活動するボランティアが地域活動にも活動範囲を拡大していくためには,ボランティアが施設で受け入れられ,安定して活動を継続することから生まれる自信が必要になると考えられる。したがって,受け入れ施設の支援としては,ボランティア受け入れの体制を整え,ボランティアコーディネーションの内容を充実させることが必要になる。また,その上で,地域活動への展開のためにも,コミュニティソーシャルワークの視点も求められる。
キーワード 高齢者ボランティア,社会福祉施設,ボランティア受け入れ,ボランティアコーディネーション
|
第67巻第15号 2020年12月 学童期におけるゲームに費やす時間と
射場 百花(イバ モモカ) 内藤 義彦(ナイトウ ヨシヒコ) |
目的 学童期は生活習慣の形成期であり,成人期の生活習慣に大きな影響を及ぼす大事な時期と考えられる。近年,ICTの生活全般への普及に伴い,学童期の日常生活におけるゲームに費やす時間(以下,ゲーム時間)の増加による様々な影響が危惧されており,望ましい生活習慣の形成を阻害するおそれがある。そこで,本研究では,一自治体の学童期の全員を調査対象として設定し,ゲーム時間と食生活および生活習慣との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 大阪府S市の全公立小学校に在籍しているすべての児童3,524人を対象とし,家庭における食生活と生活習慣に関する17項目からなる質問紙調査を実施した。このデータを用いて,ゲーム時間と児童の食生活・生活習慣との関連を,単変量および多変量ロジスティック回帰分析によりオッズ比と信頼区間を求め検討した。
結果 解析対象者は,年齢・性別等に記入漏れがなかった3,235人とした。解析対象者のうち,ゲーム時間が「2時間以上/日」の児童は,男子716人(44.1%),女子370人(23.0%)であり,女子より男子においてゲーム時間が長かった。食生活について,学年とは独立して男女ともに,朝食,野菜,間食,味が濃い料理の摂取頻度および食事の挨拶とゲーム時間との間に有意な関連を認めた。さらに男子では,共食,果物,カルシウムが多く含まれる食品,油の多い料理の摂取頻度でゲーム時間との間に有意な関連を認めた。他の生活習慣では,男女ともに身体活動,起床・就寝時刻との間に有意な関連を認めた。ゲーム時間が長いと就寝時刻が遅く,身体活動が少ない関連を認めた。
結論 ゲームに長時間費やしていることにより,就寝時刻が遅くなり,その結果,起床時刻も遅くなり,朝食の欠食,野菜の摂取頻度の低下や間食頻度の増加など食生活の乱れにつながることが示唆され,児童が健全な食生活および生活習慣を身につけるためには,ゲーム時間の制限が必要と考えられた。長時間ゲームに費やすことは,ゲーム依存という精神疾患に関係するという問題だけでなく,将来の生活習慣病のリスクを高めるおそれがあることにもっと注意をはらうべきである。なお,具体的対策としては,ゲーム時間の上限の設定および啓発が現実的であり,今後,上限の根拠の検討が必要になると考えられる。
キーワード 学童期,ゲーム,食生活,生活習慣,生活習慣病
|
第67巻第15号 2020年12月 貧困世帯の子ども・若者への支援-支援者ミーティングと支援記録の実践への活用に関連して-三沢 徳枝(ミサワ トクエ) |
目的 困難を有する子ども・若者を支援する民間団体(以下,法人)では,支援者ミーティングが実施されず支援記録をつけない状況がある。本研究では,貧困世帯の子ども・若者支援に注力する法人を対象とする調査データを用いて,支援者ミーティングと支援記録と関係機関との協力・連携や教育訓練における活用との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 「困難を有する子ども・若者の支援者調査,2011」(内閣府子ども若者・子育て施策総合推進室)から「ひきこもり」「発達障がい」等の支援を行う法人が回答したA調査票(447法人)を使用した。このうち貧困世帯の子ども・若者支援に注力する法人(122法人)の支援者ミーティングと支援記録の実施状況の二次分析でχ2検定あるいはFisher’s exact testを行った。
結果 貧困を経験した子ども・若者支援を行う法人の支援者ミーティングと支援記録の実施状況と協力・連携する機関や支援環境の整備,支援者の教育訓練の機会との関連が捉えられた。医療機関や特別支援学校,高等学校との協力・連携で,支援者ミーティングや支援記録が活用されている。地域活動へ参加する法人は,支援者ミーティングを支援者全員での実施が多く,ネットワークの構築をする法人はすべての対象者の支援記録をつける割合が多い。また教育訓練の機会について公的機関の研修・講演会への派遣を行う法人は,支援者ミーティングを全職員で行い,支援記録をすべての支援対象者につける割合が多いことがわかった。
結論 支援者ミーティングと支援記録は,貧困を経験した子ども・若者の支援をする法人が医療・福祉・教育機関と情報を共有し協力・連携するために,その活用について検討する必要がある。支援者ミーティングでは多様なメンバーを受け入れて,多様な地域の資源とつながることで,結果として子どもの社会に参画する力を育てることになる。また支援記録は支援の経緯を可視化して,多様な機関とのネットワークを構築するという点から,子ども・若者支援への介入に向けた活用方法を考える必要がある。支援者が公的機関の研修・講演会に参加して,子どもの多様なニーズに対応する知識とスキル,実践力を高め,様々な視点から実践の評価を可能にするために支援者ミーティングと支援記録が活用されると考えられた。
キーワード 子どもの貧困,ミーティング,支援記録,ネットワーク,情報共有
|
第67巻第13号 2020年11月 1期目の民生委員・児童委員の任期満了時点における
|
目的 1期目の民生委員・児童委員(以下,委員)の任期満了時点における2期目の活動継続意向と関連要因を明らかにすることとした。
方法 三重県内で活動する1期目委員全員を対象に,2016年8月~11月に4群34項目で構成する質問紙を用いた無記名自記式質問紙調査を行った。分析は継続・退任の意向で2群に分け,各項目について比較を行った。
結果 1,840名に調査票を配布し,1,566名から回答を得て,欠損値等のあるものを除外し,1,047名分(有効回答率:56.9%)を分析した。435名(41.5%)が1期目満了時点で退任する意向であった。継続・退任の2群間比較で有意差の認められた項目を説明変数とした二項ロジスティック回帰の結果,年齢(オッズ比(以下,OR):1.34,95%信頼区間(以下,CI):1.08-1.66,p=0.008),地域包括支援センターとの活動上の相談(OR:1.46,95%CI:1.10-1.94,p=0.009),民生委員同僚との活動上の相談(OR:1.43,95%CI:1.09-1.89,p=0.011),民生委員同僚との情報交換(OR:1.50,95%CI:1.14-1.96,p=0.003),活動に対する負担感(OR:1.68,95%CI:1.38-2.04,p<0.000)の5項目で継続・退任の意向と有意な関連が認められた。
結論 1期目の委員に対する支援として,地域包括支援センター等の関係機関側が活動について相談できる機会,委員が活動を振り返り,相互に情報交換できる機会,を設けていく必要性が示唆された。
キーワード 民生委員,児童委員,1期目,活動継続意向,連携,情報共有
|
第67巻第13号 2020年11月 回復期リハビリテーション病棟入院料と
奈良 浩之(ナラ ヒロユキ) 和泉 優子(イズミ ユウコ) |
目的 過疎地では,コメディカルをはじめとするスタッフに乏しく,回復期リハビリテーション病棟入院料の高い施設基準を満たせない可能性がある。そこで,二次医療圏における人口と届け出た回復期リハビリテーション病棟の最も高い入院料との関連を明らかにする。
方法 二次医療圏ごとの最も高い回復期リハビリテーション病棟入院料は,各地方厚生局のホームページから,二次医療圏の人口は2015年国勢調査から引用した。統計処理は,Mann-Whitney U検定を行い,Bonferroniの補正を行った。
結果 最も高い回復期リハビリテーション病棟入院料により二次医療圏を分類して居住人口の中央値を求めると,回復期リハビリテーション病棟入院料届け出医療機関のない場合では56,788人,入院料1では387,945人,入院料2では143,548人,入院料3では103,250人,入院料4では107,724人,入院料5では121,387人,入院料6では117,192人であった。施設基準(アウトカム評価)の最も高い入院料1の二次医療圏人口が,他の入院料の二次医療圏人口に比べ有意に多く,施設基準上の専門職の人員配置でほぼ類似する入院料1と2の二次医療圏人口においても,有意差を認めた(ともにBonferroniの補正後p<0.01)。
結論 良好な回復度を有し,高い施設基準を満たす入院料1の回復期リハビリテーション病棟は,人口規模の大きな二次医療圏に限られることが明らかになった。国民の間に健康格差があることは望ましくなく,リハビリテーションの質が都市部のみ高くなる診療報酬制度に課題があると思われる。さらに,地域の医療連携や病床機能分化により,回復期リハビリテーション病棟をより有効に機能させるべきである。また,専門職の人員不足や病床利用率低下,在宅復帰にも苦慮する過疎地においても達成可能なアウトカム評価を設定する必要性があろう。
キーワード 回復期リハビリテーション病棟入院料,アウトカム評価,二次医療圏人口,診療報酬,施設基準
|
第67巻第13号 2020年11月 若年成人女性の体成分と健康度・生活習慣の関連辛島 順子(カラシマ ジュンコ) 小林 理佐(コバヤシ リサ) |
目的 成人女性は,やせの者(BMI<18.5㎏/㎡)の割合が多いことが健康課題として挙げられる。一方で,BMIは正常でありながら体脂肪率が高い正常体重肥満者,いわゆる「隠れ肥満」の存在も注目されている。本研究の目的は,女子大学生を対象とした体成分測定と健康度・生活習慣診断検査を実施し,正常BMIかつ体脂肪率高値の者の体成分の特徴と健康度・生活習慣の関連から,次世代の健康を担う若年成人女性の生活習慣改善の方策を示すことである。
方法 2019年6月から7月に,A大学の女子大学生3・4年生80名を対象として,生体電気インピーダンス分析法(BIA法)の体成分測定と自記式質問紙調査を実施した。
結果 BMI18.5以上25.0未満の普通体重64名のうち,体脂肪率30%未満の者が49名(76.6%),30%以上の者が15名(23.4%)であった。体脂肪量,BMI,ウエストヒップ比は,体脂肪率30%以上の者が有意に高かった。筋肉バランスにおける体幹発達率,右足発達率,左足発達率は,体脂肪率30%未満の者が有意に高かった。部位別脂肪バランスにおける右手体脂肪量・体脂肪分布,左手体脂肪量・体脂肪分布,体幹体脂肪量・体脂肪分布,右足体脂肪量,左足体脂肪量は,体脂肪率30%以上の者が有意に高く,右足体脂肪分布,左足体脂肪分布は,体脂肪率30%未満の者が有意に高かった。精神的健康度は,体脂肪率30%以上の者が有意に高かった。また,健康度の総合得点は体脂肪率30%以上の者が高く,運動意識は体脂肪率30%未満の者が高い傾向がみられた。
結論 体脂肪率30%以上の者は内臓脂肪の蓄積と生活習慣病・骨粗しょう症のリスクが予測された。また,体脂肪率30%以上の者の方がグループ適応・対人関係が良好でイライラがなく,勉強や仕事がスムーズな傾向であると判定された。普通体重の若年成人女性は体脂肪率の違いにより,現時点で健康度や生活習慣に多くの差はみられていない。しかしながら,早い段階で体脂肪率の違いによる体成分や健康度,ならびにそれらに影響を及ぼすと考えられる生活習慣について自身が把握し,自分に合った適切な対処方法を学び,可能なことから実践することが望ましく,そのための環境整備も進める必要がある。
キーワード 若年成人女性,体成分,健康度,生活習慣,健康管理
|
第67巻第13号 2020年11月 都道府県別の女性未婚率の要因分析-自治体の少子化対策の観点から-田辺 和俊(タナベ カズトシ) 鈴木 孝弘(スズキ タカヒロ) |
目的 わが国の近年の出生数低下の最大原因は未婚化の進行にあるとされるが,未婚率には多数の要因が複雑に絡み合っている。そのため,要因解明を試みた研究は多数あるが,未婚要因はいまだに十分に解明されていない。本研究では自治体の少子化対策に有用な情報を得るために,都道府県別の女性の未婚率について非線形重回帰分析により多種多様な指標の中から要因を探索する分析を試みた。
方法 平成27年国勢調査からの47都道府県の女性の生涯未婚率(45歳~54歳)を目的変数とし,各種政府統計から得られる47種の指標を説明変数とし,非線形重回帰分析の一手法であるサポートベクターマシンを用いて,未婚率に対して統計的に有意な影響を及ぼす要因を探索し,さらに,感度分析法により,それらの要因の未婚率に及ぼす相対的影響度を評価した。
結果 都道府県別の女性未婚率に対して有意となる9種の要因を見いだし,そのうち,未婚率を下げる要因は親との同居率,持家率,製造業就業率,交際率,育児休業制度と介護休業制度利用率の6種,未婚率を上げる要因は所得,大学・大学院卒率,医療・福祉業就業率の3種であった。また,親との同居率が未婚率の低下に最大の影響を与える一方,高学歴かつ高所得女性の増加が未婚率の上昇に大きく寄与するという興味深い結果を得た。さらに,これまで未検証の製造業と医療・福祉業の就業率,交際率,育児休業制度と介護休業制度の利用率の5種の要因が有意となった。
結論 女性未婚率の要因として,親との同居率,所得,持家率,大学・大学院卒率などの他に,これまで未検証の要因を含む計9種を見いだし,本研究の解析方法の有効性を実証した。
キーワード 女性未婚率,要因分析,都道府県差,非線形重回帰
|
第67巻第13号 2020年11月 定年退職後の心のあり様尺度(PSAR)の開発谷口 千絵(タニグチ チエ) 小野 美月(オノ ミヅキ)北 素子(キタ モトコ) 久田 満(ヒサタ ミツル) |
目的 本研究の目的は,定年退職後の心のあり様尺度(以下,PSAR)を開発し,信頼性の検討および関連する要因を明らかにすることである。
方法 2017年12月時点でWeb調査会社に登録している人で,日本国内の企業に勤続し,定年退職を経験した60-74歳の男性308人を対象とした。PSARの暫定46項目について探索的因子分析を行った。抽出された各因子と退職後の人生設計,退職前から続けている趣味,現在のコミュニティへの関与度,現在の経済状況,現在の主観的身体的健康状態,基本属性について,対応のないt検定,一元配置分散分析を行い,有意な場合は多重比較を行った。さらに,各因子を従属変数とする重回帰分析を行った。
結果 3因子23項目が抽出された。第1因子10項目は〔定年後充実感〕,第2因子7項目は〔人生終わった感〕,第3因子6項目は〔現役への未練〕とした。Cronbachのα係数は,それぞれ0.84,0.83,0.73であった。〔定年後充実感〕は,趣味があり,同居人がいて,既婚者で,大学/大学院を卒業した群が高い得点であった。現在の経済状況を「苦しい」,健康状態を「不健康」,コミュニティへ「関わりはない」と回答した群の得点が低かった。〔人生終わった感〕は,定年退職前から続けている趣味がない群の得点が高かった。現在の経済状況が「苦しい」,健康状態を「不健康」,退職後の人生設計を,「考えていなかった/漠然と考えていた」と回答した群は高い得点であった。〔現役への未練〕は,現在パート・アルバイトに就いている群が高い得点で,コミュニティへ「関わりがない」,健康状態を「不健康」と回答した群の得点が低かった。重回帰分析の結果,〔定年後充実感〕は,定年退職前に考えていた人生設計があり,趣味があり,現在の経済状況に余裕があり,健康であると認識しているほど高かった。〔人生終わった感〕は,退職後の年数が浅く,定年退職前に考えていた人生設計がなく,現在の経済状況に余裕がないほど高かった。〔現役への未練〕は,現在のコミュニティへの関与度が高く,パート・アルバイトに就いており,経済状況に余裕がなく,退職後の年数が浅いほど高かった。
結論 定年退職後の男性を対象とし,定年退職後の人生や生活を営む過程における心の状態を客観的に把握するための心理尺度として〔定年後充実感〕〔人生終わった感〕〔現役への未練〕の3因子23項目が明らかになった。
キーワード 定年退職,心のあり様,男性,尺度の開発,退職移行期,人生設計
|
第67巻第13号 2020年11月 乳児を持つ父親が幼少期に受けた愛情の実感と
藤田 芙美子(フジタ フミコ) 吉田 和樹(ヨシダ カズキ) |
目的 乳児を持つ父親自身が幼少期に受けた愛情の実感と現在の精神的健康度との関連,さらには,育児状況との関連を調べることを目的とした。
方法 福島市で2017年10月から2018年3月に4カ月児健康診査を受診予定だった乳児945人の家庭に対して,通常の問診票に父親対象のアンケートを同封して郵送し,健康診査時に回答を回収した。加えて,健診票と問診票からもデータを転記した。アンケート回収率は54.8%であり,父親509人のデータを分析対象とした。父親の精神的健康度は「お父さんの気持ちの状態はいかがですか」と質問して,3件法で回答を求め,「よい」とそれ以外(「なんともいえない」「いいえ」)に2区分した。受けた愛情の実感は,「あなた自身は子どものころから愛情を受けて育ったという実感がありますか」と質問して,4件法で回答を求め,「ある」とそれ以外(「なんとなくある」「あまりない」「ない」)で2区分した。
結果 受けた愛情の実感が「ある」以外の父親は214人(42.1%),気持ちの状態が「よい」以外の父親は125人(24.6%)だった。父親の仕事の量的負担,母親の気持ちの状態,人間関係の問題,そして出生順位を調整した多変量解析の結果から,受けた愛情の実感が「ある」以外の場合,気持ちの状態が「よい」以外の調整オッズ比は1.99(95%信頼区間=1.30-3.06)であった。さらに,父親自身が受けた愛情の実感と父親の児に対する愛着に有意な関連が認められた(怒り:p=0.016,低い愛情:p=0.028)。
結論 父親自身の幼少期の親との関係と現在の精神的健康度が関連し,さらには現在の育児状況にまでも関連するという愛着の世代間伝達と育児への影響が示唆された。悪循環を断ち切るためには,父親に対する早期の育児支援が必要である。
キーワード 乳児健康診査,産後うつ,愛情,精神的健康度,父性行動
|
第67巻第12号 2020年10月 母子健康手帳に綴じ込まれた松井式便色カードの
顧 艶紅(コ エンコウ) 孔 元原(コウ ゲンゲン) 趙 金琦(チョウ キンキ) |
目的 2012年度から,デジタル印刷技術を利用した松井式便色カードが,改正された母子健康手帳に綴じ込まれて全国配布されるようになった。日本胆道閉鎖症研究会の報告では同便色カードの3番(陽性)と5番(陰性)の中間色である4番(陰性)が,約4割の胆道閉鎖症の患児で報告され,4番の新生児・乳児に対して,胆道閉鎖症の精査を行うかどうか議論されている。今回は北京市での追跡データを用いて,松井式便色カードの4番の回答頻度や転帰について解析し,生後4カ月までの便色の経時的変化,4番の便色と胆道閉鎖症の発症などの関係について明らかにすることを目的とした。
方法 2013年12月~2014年10月に北京市において,保護者が日本の母子健康手帳に綴じ込まれた松井式便色カードと同様のカード(中国語訳付き)を受け取った29,799人の出生児を研究対象とした。産科において訓練された産科のスタッフらが,保護者に家庭内で便色を観察し,1~3番の便色になったら,直ちに北京市新生児マススクリーニングセンターの外来へ受診をするように,また生後2週間,生後1カ月,生後1~4カ月の計3回記録するように説明した。記録情報は同センターの追跡システムや生後42日健診などを通して,フィードバックしてもらった。便色番号の報告頻度とその95%信頼区間を2項分布で計算し,検証した。
結果 有効回答数は27,561(92.5%)であった。生後2週間,生後1カ月,生後1~4カ月の3回の時点で最も報告の頻度の高かったのが5番で,次いで4番であった。4番と別の便色との組み合わせで出現する頻度が高い傾向にあった。しかし,4番と1番,2番,3番の組み合せと報告されたのはそれぞれ0人(0.0%),1人(0.02%),4人(0.07%)であった。4番便色と1~3番便色,5~7番便色と1~3番便色はそれぞれ交互に出現することもあったが,頻度は低く,両者の有意差はなかった。本研究で診断された2人の胆道閉鎖症患児では,3つの記録時点では,それぞれ4番→2番→(未観察),5~7番→5~7番→3番であった。
結論 健常児と胆道閉鎖症の患児において,生後4カ月まで,便色の経時的変化または複数の便色の組み合わせがみられた。4番の便色を示されてもすぐに精密検査をする必要はなく,引き続き観察し,1~3番に変化したら,すぐに受診するように勧める。胆道閉鎖症患児では必ずしも1番の「灰白色便」を呈するとは言い切れない。また,便色の変化を観察しながら,遅延性黄疸等のサインも見逃さないようにしてほしい。今後便色カードの異常便色のパネルを増やす選択肢を検討する必要がある。
キーワード 胆道閉鎖症,松井式便色カード,早期発見,陽性者,精密検査
|
第67巻第12号 2020年10月 運動実践者の体重減少に向けて食品カロリーの
松原 建史(マツバラ タケシ) 植木 真(ウエキ マコト) |
目的 運動実践者で腹囲がメタボリックシンドロームに該当する者は,食品カロリーの正しい知識が乏しいことが明らかにされている。そこで,食品カロリーの知識向上を図ることで,体重や腹囲の減少が期待できるため,この縦断的関係性について検討することを目的とした。
方法 対象を,公共運動施設を利用していて腹囲が85㎝以上だった女性74名とした(年齢:66±7歳,体重:58.1±7.0㎏,腹囲:90.5±6.4㎝)。対象者には平成28年2月と9月に,体重,腹囲,食品カロリーの知識調査を実施した。食品カロリーの知識調査は,ポスターに掲載した食品カロリーを伏せた寿司と焼鳥屋メニューそれぞれ数十種類の中から,一番カロリーが低いと思う組み合わせをクイズ形式で選択させ,そこから総合カロリー得点を算出して評価した。食品カロリーの正しい知識の浸透を図る支援として,2月と9月の食品カロリーの知識調査と同様の方法で,3月から8月まで食品カロリーを伏せた定食メニューやパン類など内容を変えながらクイズ式ポスターを掲示し,月末に答え合わせを行うことを繰り返した。その他の項目として,公共運動施設での自転車エルゴメータとトレッドミルの週当たり有酸素性運動時間を2月と9月それぞれで算出した。そして,2月から9月にかけて総合カロリー得点が全対象者の中で高水準を維持していた群,低水準から高水準に変化した群,低水準を維持していた群,高水準から低水準に変化した群の4群に分けた上で,年齢と週当たり有酸素性運動時間を調整因子にとった二元配置共分散分析を行った。
結果 全対象者では総合カロリー得点の向上傾向と体重の減少傾向を認めたが,変化量はそれぞれわずかであった。次に,4群の比較では,体重,腹囲とも有意な交互作用も群と時期の主効果を認めなかった。
結論 食品カロリーの正しい知識が向上しても体重や腹囲の減少にはつながらないことが明らかになった。知識の向上は全く必要ないということではなく,食行動の変容を図る支援を優先して実施し,その後に知識の向上を図っていくことで,より有効な支援になる可能性が高いと考えた。
キーワード メタボリックシンドローム,食行動,行動変容,縦断的研究
|
第67巻第12号 2020年10月 生活保護の厳格化は今も支持されているか?-時代効果,社会経済階層,利用するメディアとの関連-山田 壮志郎(ヤマダ ソウシロウ) 斉藤 雅茂(サイトウ マサシゲ) |
目的 生活保護の厳格化志向に関する先行研究では,包括的な従属変数を用いて,社会経済階層および利用するメディアとの関連が分析されてきたが,生活保護の厳格化をめぐる論点は多岐にわたるため,細分化された従属変数によって検討する必要がある。また,生活保護バッシング報道が沈静化する中,厳格化志向の時代的な変化を明らかにすることも重要である。そこで本研究では,生活保護の厳格化志向を細分化して捉えたうえで,それらが時代的にどう変化しているのか,また社会経済階層やメディア接触は厳格化志向にどう影響しているのかを分析することを目的とした。
方法 2014年と2018年に実施した生活保護に関するインターネット意識調査の結果を分析した。生活保護の厳格化に関する6つの側面(高生活保護費,不正受給厳罰化,扶養義務強化,外国人保護禁止,医療費一部負担,ギャンブル禁止)に対する態度を従属変数とした。第1に,2014年と2018年の態度の変化について記述統計量を確認した。第2に,厳格化志向に関連する要因を,時代効果,社会経済階層(職業,世帯税込年収),利用メディアを独立変数とする2項ロジスティック回帰分析により検討した。
結果 高生活保護費,不正受給厳罰化,扶養義務強化の3項目で時代効果が確認され,2014年より2018年の厳格化志向は弱まった。時代効果をコントロールした解析では,高生活保護費と医療費一部負担の2項目は,非正規社員や無職が厳格化志向をもちにくかった。また,不正受給厳罰化とギャンブル禁止の2項目は,年収が高いほど厳格化志向をもちやすかった。信頼できるメディアとしてインターネットを選択する人は,ほとんどの項目で厳格化志向をもちやすかった。特に,外国人保護禁止でその傾向が顕著だった。
結論 生活保護の厳格化志向のうち,高生活保護費,不正受給厳罰化,扶養義務強化は時代の影響が強く近年になって厳格化志向は弱まっている。また,不安定な就労状態にある人は,社会保障の抑制につながる厳格化に賛同しにくく,高収入層は生活保護受給者のモラルの観点から厳格化を求める傾向にある。
キーワード 生活保護,厳格化志向,時代効果,社会経済階層,利用メディア,インターネット調査
|
第67巻第12号 2020年10月 高校生ヤングケアラーの存在割合とケアの状況-埼玉県立高校の生徒を対象とした質問紙調査-濱島 淑恵(ハマシマ ヨシエ) 宮川 雅充(ミヤカワ マサミツ) 南 多恵子(ミナミ タエコ) |
目的 本研究は,2016年に実施した大阪府立高校10校の生徒を対象とした質問紙調査(以下,大阪府高校生調査)とほぼ同様の調査票を用い,子ども自身の認識に基づいたヤングケアラーの実態を把握することを目的として行った。
方法 2018年11月~2019年3月に,埼玉県の公立高校11校において,生徒を対象とした質問紙調査を実施した。調査対象の選定,調査票の配布・回収は高校に依頼した。11校の生徒4,550名が調査対象となった。
結果 4,260名に調査票を配布でき,4,252票の調査票が回収され,本研究の分析対象は3,917票となった。別居している家族も含め,家族にケアを必要としている人(以下,要ケア家族)がいるか否かを尋ねた結果,はいと回答した者が541名(13.8%)であり,そのうち241名(6.2%)は回答者自身がケアをしていると回答していた。障がいや疾病等はなく,幼いきょうだいがいるという理由のみでケアをしている者35名を除外し,残りの206名を対象とした。この206名がヤングケアラーと考えられ,存在割合は5.3%となった。また,負荷が大きいと考えられるヤングケアラーの存在割合は約1%となった。要ケア家族は祖母,母,祖父が多く,要ケア家族が祖母,祖父のみの場合,身体障がい・身体的機能の低下,認知症,病気が多く,母のみの場合,病気や精神疾患・精神障がい・精神的不安定が多かった。ケアの内容は,家事,感情面のサポート,力仕事が多かった。ケアの期間については中央値が3年11カ月であり,少なくとも半数が高校入学前からケアをしていた。ケアの頻度は毎日が最も多く,週4,5日と合わせて半数を超え,ケアの時間は学校がある日,学校がない日ともに1時間未満が最も多いが,2時間以上と回答した者が学校がある日では49名(23.8%),学校がない日では79名(38.3%)いた。ケアをしていることを家族以外の誰かに話したことがあるかを尋ねたところ,ないと回答した者が112名(54.4%)であった。話した相手は,友人が最も多く,次いで親戚,学校の先生であった。
結論 本研究では,高校におけるヤングケアラーの実態(ケアの状況,存在割合等)を示し,これらの結果は大阪府高校生調査と類似するものが多かった。ケアが長期化する者,負担が大きい者,孤立が懸念される者も確認され,教員,支援者による支援の必要性が示唆された。
キーワード ヤングケアラー,介護,手伝い,家族,高校生,質問紙調査
|
第67巻第12号 2020年10月 有職女性の周産期におけるケアニーズとケアの満足度木島 楓(キジマ カエデ) 浦中 桂一(ウラナカ ケイイチ) 朝澤 恭子(アサザワ キョウコ) |
目的 日本では女性就業者数が増加しているが,有職女性に焦点を当てた周産期のケアニーズに関する調査は見当たらない。本研究の目的は,育児中の有職女性における周産期ケアニーズと周産期ケアの満足度を明らかにすることである。
方法 量的横断的記述研究デザインを用いて,0~6歳の保育園に通園する子どもをもつ有職女性278人に無記名自記式質問紙でデータ収集した。首都圏にある7カ所の認可保育園に研究協力を得て,研究対象者に口頭と書面で研究の趣旨を説明した後に,無記名の自記式調査票を配布した。調査内容は属性,周産期ケアの実態,周産期ケアニーズ,周産期ケアの満足度であった。分析はマクネマー検定,マン・ホイットニーのU検定,フィッシャーの正確確率検定を用いた。
結果 調査票を認可保育園に子どもを預けている有職女性の278人に配布し,回収は194部(回収率69.8%)であり,有効回答149部(有効回答率53.6%)を用いてデータ分析を行った。周産期に看護職者に求めるケアニーズとして高かったものは,乳房マッサージが92.6%,産後の心身変化の説明が91.9%,乳房トラブル防止の情報提供が91.9%,ミルクの足し方の説明が89.3%であった。一方,ケアニーズのうち,保育園入園の情報提供が55.0%,育児時間の情報提供が55.0%,労働時間の情報提供が53.7%,職場復帰の情報提供が37.6%であった。周産期ケアの実態よりケアニーズの比率が高かった内容は,育児時間,保育園入園,労働時間の情報提供であった(p<0.001)。ケアの満足度は,看護職者・病院の総合的な対応が65.8%,職場復帰に関する情報提供が0.7%以下であった。
結論 有職女性への職場復帰の情報提供は,育児や母乳に関するケアよりニーズの比率が高く,職場復帰や保育園入園に関する情報提供の満足度が低かった。看護職者には育児や授乳に関するケアにプラスして職場復帰に関する情報提供が求められていることが示唆された。
キーワード 有職女性,助産ケア,量的横断的記述研究,職場復帰,情報提供,周産期
|
第67巻第12号 2020年10月 傾向スコア・マッチング法を用いた中・高年齢層の
|
目的 主観的健康感は,従来の罹患率や死亡率といった客観的健康指標を超えた生活の質をも含む指標として注目されている。主観的健康感とソーシャル・キャピタル(以下,SC)との関連についての既存の研究は一致していない。その理由の一部として不十分な交絡制御の可能性がある。そこで,観察研究での交絡因子の調整において有効な手法である傾向スコア・マッチング法により共変量を調整し,その関連性を解析した。
方法 平成27年度「滋賀の健康・栄養マップ調査」(以下,平27調査)参加者を対象に,40歳未満,または必要変数に欠損のある者を除外した男性1,245人(平均年齢62.9歳),女性1,470人(平均年齢63.2歳)を対象とした。平27調査項目である“地域の人々が互いに助け合っているか”および“あなたの現在の健康状態はいかがですか”の設問をもとにSCの『SCの自覚有り』『SCの自覚無し』および主観的健康感『良好』『良好でない』をそれぞれ定義した。傾向スコア算出モデルは,ロジスティック回帰分析にてAkaike’s Information Criterionを指標とした変数増減法により共変量を選択した。傾向スコアを用いてマッチングしたSCの『SCの自覚有り群』と『SCの自覚無し群』のペア間での主観的健康感良好群の割合を比較した。
結果 傾向スコア算出モデルに選択された共変量は「性別」「年齢」「世帯員数」「住んでいる市町名」「食事内容(野菜摂取量,果実類摂取量,食塩摂取量)」「1年以上の運動習慣」「徒歩10分の場所への移動手段」「高血圧および高脂血症の既往歴の有無」「過去1年間の健診受診有無」「喫煙の肺がんへの影響に関する知識」であった。マッチングにてSCの自覚有り・無し各群1,121人を選んだ。両群における各共変量に有意な差は認められず(p>0.10),また,Standardized Difference scoreの絶対値も0.1未満であった。主観的健康感『良好群』の割合は,SCの自覚有り群では49.3%,SCの自覚無し群では40.8%と有意な差があった(p<0.01)。
結論 傾向スコアを用いた交絡因子の調整を行った結果,SCが住民の主観的健康感と関連があることが示唆された。このことより,充実したSCの構築が健康や生活の質を高める可能性がある。
キーワード 傾向スコア・マッチング法,主観的健康感,ソーシャル・キャピタル
|
第67巻第11号 2020年9月 農村に住む高齢女性の食料品の調達方法と
野邊 政雄(ノベ マサオ) |
目的 多くの高齢者が地方の農山村に住み続けている。高齢者が農山村で暮らし続けるためには,食料品の調達および病院や診療所に通院する交通手段の確保が最低限必要である。本稿では,高齢女性がどのように食料品を調達したり,病院や診療所へ通院するための交通手段をどのように確保したりして,農村での暮らしを維持しているかを明らかにする。
方法 岡山県高梁市宇治町と松原町で2016-17年に高齢女性を対象に個別面接調査を実施した。65歳以上80歳未満の女性を全数調査した。有効票数は139票であった。食料品の調達および病院・診療所への通院の主要な方法を取った回答者の特徴をχ2検定もしくはフィッシャーの直接確率検定で明らかにした。
結果 ①食料品の調達方法について多かった調達方法は,「自分で自動車・バイクを運転して,買い物をした」(59.7%),「同居家族員が運転する自動車に乗って行った」(43.2%),「生協による自宅への配達」(36.7%)であった。②地域外の病院や診療所へ通院するための交通手段で多かったものは,「自分で自動車・バイクを運転して,通院した」(52.5%),「同居家族員が送迎」(39.6%),「バス・タクシーを利用」(19.4%)であった。③高齢女性が自分で自動車を運転できる場合,自ら自動車を運転して地域外で買い物をしていた。しかし,自分で自動車を運転できない場合,同居家族員がいれば,高齢女性は同居家族員に自動車を運転してもらって,地域外で買い物をしていた。移動販売や配達によって食料品を調達している高齢女性には,特定の特性が見られなかった。④高齢女性が自分で自動車を運転する場合,自ら自動車を運転して地域外の病院や診療所へ通院していた。しかし,自分で自動車を運転できない場合,同居家族員がいれば,同居家族員が高齢女性を送迎していた。自分で自動車を運転できず,同居家族員もいなければ,高齢女性はバスやタクシーを利用していた。
結論 ①半数以上の高齢女性は自分で自動車やバイクを運転して,買い物や通院をしていた。これは,68.3%の高齢女性が自動車やバイクを運転できたためである。多くの高齢女性が運転免許証を保有していたので,移動手段の確保は以前ほど深刻な問題ではなかった。②同居家族員は高齢女性の食料品調達や病院・診療所への通院で大きな役割を果たしていたのに対し,別居している近親者はあまり役立っていなかった。③近所の人が高齢女性の食料品の調達や病院・診療所への通院を支援することはあまりなかった。
キーワード 農村,高齢女性,食料品調達方法,通院方法,交通手段,相互扶助
|
第67巻第11号 2020年9月 労働者のインターネット依存と痩せおよび肥満との関連中村 優(ナカムラ ユウ) 榊原 文(サカキハラ アヤ) |
目的 近年,急速なインターネット(以下,ネット)の普及の一方で,ネットに過度に没入し,対人関係や日常生活への弊害が生じても,ネットに精神的に依存するネット依存が問題視されている。ネット依存の先行研究は思春期に焦点を当てたものが多く,壮年期のネット依存が健康や労働にどのような影響を及ぼしているのかは明らかにされていない。そこで本研究は,労働者を対象に,生活習慣病のリスクを高める痩せと肥満に焦点を当て,ネット依存との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 2019年8~9月,A製造業事業所の従業員530人を対象に,無記名自記式質問紙調査を行った。調査内容は,年齢,性別,身長,体重,ネット依存度,生活習慣である。ネット依存度は,Young’s Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction score(YDQ)を使用し,問題のあるネットユーザーとされるYDQ3点以上をネット依存と判定した。痩せ,肥満の評価は,BMI([体重(㎏)]÷[身長(m)2])を使用し,18.5未満を「痩せ」,25以上を「肥満」と判定した。男女別に痩せ・肥満を従属変数,ネット依存を独立変数として単変量ロジスティック回帰分析を行い,その後,睡眠時間,運動習慣,飲酒習慣等を共変量として投入し,多変量ロジスティック回帰分析を行った。
結果 調査票の回収数は384枚(回収率72.5%)であった。YDQ3点以上は全体で19.3%,男性19.8%,女性17.7%であった。痩せは,全体で5.5%,男性4.5%,女性8.3%であり,肥満は,全体で21.9%,男性25.3%,女性11.5%であった。痩せとネット依存の多変量ロジスティック回帰分析の結果,ネット依存の男性従業員がそうでない従業員と比較して痩せとなる調整オッズ比は,3.91(95%信頼区間[CI]:1.14-13.49)であったが,女性の痩せとネット依存に有意な関連は認められなかった(調整オッズ比=2.23(95%CI:0.29-17.19))。肥満とネット依存の多変量ロジスティック回帰分析では,男女ともに有意な関連は認められなかった(調整オッズ比=0.59(95%CI: 0.27-1.31),2.62(95%CI:0.47-14.52))。
結論 ネット依存の男性従業員はそうでない従業員と比較して約4倍痩せになることが示された。その理由として,ネットに夢中になるあまり食への関心が低下し,食欲減退により痩せになることが推察される。
キーワード インターネット依存,労働者,痩せ,肥満,BMI,生活習慣病
|
第67巻第11号 2020年9月 成人喫煙率の都道府県比較および経年変化-国民生活基礎調査の集計表より-冨岡 公子(トミオカ キミコ) |
目的 国民生活基礎調査の集計表を用いて,成人喫煙率の都道府県比較および経年変化を統計解析した。
方法 e-Statで提供されている2001年~2016年までの国民生活基礎調査の集計表を用いた。「昭和60年モデル人口」を基準集団とした年齢調整喫煙率(直接法)で都道府県比較を行った。年次推移に関する分析は,各調査年の年齢調整喫煙率と標準誤差を用いて,Joinpoint regressionで検定を行った。本研究において,喫煙状況不詳の者は解析対象外とし,男女別に分析した。2016年は震災の影響で熊本のデータが含まれていないため,都道府県比較は2013年を用いた。
結果 2016年の全国の粗喫煙率は男性31.7%,女性9.7%であった。2013年の年齢調整喫煙率(%)は,全国平均が男性37.3(95%信頼区間(CI)=36.9~37.8),女性12.9(12.6~13.1),都道府県別にみると,男性では青森45.4(40.9~49.8)が最も高く,奈良32.4(28.3~36.5)が最も低く,女性では北海道21.5(19.9~23.2)が最も高く,奈良8.5(6.2~10.7)が最も低かった。性別年齢調整喫煙率に関して,男女共に低いのは近畿地方,男女共に高いのは北海道および東北地方,女性のみ高いのは都市圏,男性のみ高いのは九州地方および中国地方に多い傾向がみられた。Joinpoint regressionの結果,2001年以降,年齢調整喫煙率は男女共に有意に減少していた[2001年~2016年平均年変化率(%):男性 -8.4(95%CI:-9.1,-7.7),女性 -7.3(95%CI:-9.7,-4.9)]。都道府県別にみると,男性では石川以外の都道府県では有意な減少傾向を認めたが,女性では47都道府県中15の自治体は有意な増減が確認できなかった。
結論 国民生活基礎調査の集計表を利用することで,高齢化の影響を調整した成人喫煙率を性別に都道府県比較したり,経年変化を検討することができた。一方,集計表では千人単位のため500人未満は「0」表記となっており,人口の少ない都道府県や女性の年齢階級別喫煙率の算出における限界が示唆された。今後,個票データを用いて,年齢以外の要因(学歴など)や個人レベルでの喫煙関連要因を検討する必要がある。
キーワード 国民生活基礎調査,e-Stat,公的統計,成人喫煙率,年齢調整,年次推移
|
第67巻第11号 2020年9月 在院日数の短縮に影響を及ぼす主要診断群分類と診療行為について中島 尚登(ナカジマ ヒサト) 矢野 耕也(ヤノ コウヤ) |
目的 Diagnosis Procedure Combination(DPC)制度では,在院日数の短縮が高く評価されるため,在院日数の短縮に影響する主要診断群分類(Major Diagnostic Category:MDC)と診療行為を検討した。
方法 2012-2017(以下,’12-’17)年のDPC対象病院(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ群)とDPC準備病院(以下,準備病院)のMDC比率,DPC算定病床数/準ずる病床数,手術数,化学療法数,放射線療法数,救急車搬送数,救急医療入院数,全身麻酔数および在院日数を用い,在院日数を目的変数として重回帰分析で検討した。
結果 ①Ⅰ群では’12年のMDC04(呼吸器系疾患),’15年のMDC06(消化器系疾患,肝臓・胆道・膵臓疾患),’16年のMDC15(小児疾患),Ⅱ群では’15-’16のMDC05(循環器系疾患),’16年のMDC02(眼科系疾患),Ⅲ群では’12-’17年のMDC02とMDC15,’12と’14-’17年のMDC03(耳鼻咽喉科系疾患),’12-’15と’17年のMDC12(女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩),’12-’14と’17年のMDC05,’12年のMDC14(新生児疾患,先天性奇形),’17年のMDC09(乳房の疾患),準備病院では’16-’17年のMDC02,’12-’13と’16-’17年のMDC03,’12-’13と’17年のMDC05,’13と’17年のMDC06,’17年のMDC07(筋骨格系疾患)とMDC11(腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患),’12-’13,’15と’17年のMDC14,これらが在院日数短縮に影響した。また’12-’17年を通じて,Ⅰ群ではMDC08(皮膚・皮下組織の疾患),Ⅱ群ではMDC01(神経系疾患),Ⅲ群ではMDC01とMDC04,MDC13(血液・造血器・免疫臓器の疾患),MDC16(外傷・熱傷・中毒),これらが在院日数延長に影響した。②Ⅰ群,Ⅱ群,準備病院ともに’13-’17年を通じて,手術件数は在院日数短縮に影響した。またⅠ群では’12-’14年と’16年の救急車搬送件数,Ⅱ群では’14年の放射線療法件数,’12年救急入院,準備病院では’16-’17年の化学療法件数,これらが在院日数短縮に影響した。
結論 在院日数の短縮に影響するMDC比率の調整が評価を高くする要因となる。
キーワード 在院日数,Diagnosis Procedure Combination(DPC)対象病院,主要診断群分類(Major Diagnostic Category:MDC),機能評価係数Ⅱ,効率性指数,重回帰分析
|
第67巻第11号 2020年9月 履歴書等データに基づく認知症対応型共同生活の
渡邊 裕文(ワタナベ ヒロフミ) |
目的 介護職の早期離職者数の削減を目的として,認知症対応型共同生活介護の施設への介護職としての入職希望者について,履歴書データを用いて,採用者・不採用者,早期離職者の特性を分析した。
方法 Aグループホームに開設当初より2018年3月までに残されていた介護職としての入職希望者の履歴書に書かれている内容を用いて分析を行った。本分析では,全履歴書データ(328通)のうち,開設当初で職員を多く採用していた3年間,性別,年齢に欠損のあるデータを除いた189名分の履歴書データを用いた。「採用・不採用」「勤続年数」を従属変数とし,履歴書に書かれている「性別」「年齢」「学歴」「転職回数」「福祉転職回数」「保有資格」の履歴書データを独立変数としてロジスティック回帰分析を行った。また,志望動機欄の記載内容について,テキストマイニングによる分析を合わせて行った。
結果 採用・不採用について分析の結果,年齢,保有資格について,採用・不採用との間に統計学的に有意な関連が認められた。他の独立変数の影響を除いて,30歳代に比べて20歳代以下,40歳代がそれぞれ5.52倍(95%CI:1.75-17.35),3.02倍(95%CI:1.04-8.72)採用されやすいことがわかった。統計学的に有意ではないが,50歳代以上は2.88倍(95%CI:0.93-8.92)採用されやすくなっている。テキストマイニングでは,「認知症」「高齢者」「家庭」など認知症対応型共同生活介護の本質に関するキーワードを記載している人が採用されていた。早期離職について分析の結果,保有資格との統計学的に有意な関係がみられ,ヘルパー等の資格を持つものは,6.93倍(95%CI:1.39-34.49)早期離職しやすいという結果が得られた。また,統計学的に有意ではないが,福祉関係の転職回数が2回以上の人は0.61倍,つまり福祉関係の転職経験が1回以下の人は1.64倍早期離職しやすくなっている。性別,年齢,学歴については,統計学的に有意な関係はみられなかった。テキストマイニングでは,「認知症」「人生」「関わる」「力づける」「施設見学」といった他者との関わりや理解,意欲に基づくと考えられる単語を記載している人が,早期離職していなかった。
結論 介護職の早期離職には,これまで施設の対応や施設内での人間関係が論じられてきた。今回の分析で,入職希望者の個人的特性や保有資格,転職経験との関連性が確認され,早期離職を減らすためには,介護職へ入職する前の段階での教育や体験の必要性が示唆された。
キーワード 認知症対応型共同生活介護,個人の特性,介護職,保有資格,転職回数,ロジスティック回帰分析
|
第67巻第11号 2020年9月 主観的経済状況と幼児の未処置う蝕の関連-仙台市認可保育所における横断研究-鎌田 由香(カマダ ユカ) |
目的 保護者の経済状況と幼児の未処置う蝕の関連とその要因について検討した。
方法 平成27年10月~12月に,仙台市内の保育所に通う4歳児の保護者を対象として,質問紙調査を実施した。経済的なゆとりを「ゆとりあり」「どちらともいえない」「あまりゆとりはない」「全くゆとりはない」に分類した。処置をしたう蝕のある者とう蝕のない者を「未処置う蝕なし」,未処置う蝕のある者を「未処置う蝕あり」とした。食物摂取頻度調査から主成分分析を行って,同定された食事パターンを使用した。経済状況を説明変数,未処置う蝕を従属変数とした多変量ロジスティック回帰分析を用い,オッズ比(95%信頼区間)を算出した。
結果 調査対象2,738人のうち解析対象は1,948人であった。経済状況は「ゆとりあり」30.6%,「どちらともいえない」32.1%,「あまりゆとりはない」28.9%,「全くゆとりはない」8.4%であった。「未処置う蝕あり」の幼児は309人で,経済的な「ゆとりあり」23.6%,「どちらともいえない」30.4%,「あまりゆとりはない」31.4%,「全くゆとりはない」14.6%であった(p<0.001)。多変量ロジスティック回帰分析の結果,「ゆとりあり」を基準としたオッズ比は「どちらともいえない」1.37(0.94-1.98),「あまりゆとりはない」1.35(0.92-1.97),「全くゆとりはない」2.17(1.32-3.58)であった(p=0.006)。未処置う蝕に影響を与える因子は,「遅い起床時間・遅い就寝時間」1.52(1.05-2.21),「幼児と保護者朝食欠食あり」1.79(1.22-2.64),「第2食事パターン(甘い食品や飲料,インスタント食品が多い)」1.24(1.10-1.41)であった。
結論 経済状況が厳しい保護者の子どもは,未処置う蝕の有症率が高かった。幼児の起床・就寝時間,朝食欠食やインスタント食品が多い食事などは,経済状況に関わらず未処置う蝕の有症率と関連していた。従って,幼児の未処置う蝕を減らしていくためには,経済状況の改善は重要であるが,それと同時に基本的な生活習慣の形成と,食事全体の質に着目した栄養の教育が重要であると考えられた。
キーワード 主観的経済状況,幼児,未処置う蝕,起床・就寝時間,朝食欠食,食事パターン
|
第67巻第8号 2020年8月 社会的養護における専門職の人材育成に関する実態と課題-職場研修のニーズを中心に-小林 理(コバヤシ オサム) 中原 慎二(ナカハラ シンジ) 新保 幸男(シンボ ユキオ) |
目的 本研究は,社会的養護分野における常勤専門職の「働く環境」などの自己評価を通じて,職場環境の実態を把握し,人材育成の課題を考察することを目的とした。
方法 調査対象は,全国の乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設の保育士・児童指導員などの常勤専門職の全員として,郵送法による無記名自記式調査を行った。調査項目は,「自らの専門性」「仕事への思い」「働く環境」など50項目を設定し,それぞれ1~10の数字(得点が高い方が高評価)で自己評価の回答を得た。調査期間は,2018年2月から3月であった。
結果 2018年3月末時点で回収された調査票のうち,期限を過ぎて返送された調査票を含み,すべての調査項目が有効回答であった調査票5,000通を対象として分析を行った。調査項目の50項目の平均得点は6.18点,標準偏差は2.32点であった。10点満点で8点以上と高い得点の項目は,「児童を理解しようとしている」(8.47点),「自らの専門性をより高めようと思っている」(8.35点)であった。一方,低い得点の項目は,「職場外でスーパービジョンを受ける機会が十分ある」(4.70点),「地域資源の活用に関して,自らの専門職としての能力は高い」(4.78点),「制度理解に関して,自らの専門職としての能力は高い」(4.81点),「自分の年収に満足している」(4.86点)であった。職場環境についての項目の合計点は,経験年数が低い群で低く,年数とともに得点が上がっていた。結果を年齢,経験年数の平均値を参考に,グループ化して分布をみた。「35歳以上45歳未満で経験5年未満」「45歳以上で経験5年未満」の者に,職場内外の研修や勉強会の機会が十分でない。職場内のスーパービジョン(SV)は,調査項目全体に相関があり,特に職場への誇り,専門性を高めやすいか,に相関があった。職場内SVは,年齢が低く経験が浅い群で課題がある。
結論 職場環境は,本来,新人にとって手厚くあるべきだが,本研究の結果から,年齢や経験年数が低い群に充実と捉えられていない傾向がみられた。これは,年齢が若く経験年数の少ない「新人組」の「仕事の継続」に壁となっていると考えられる。職場内外のSVの機会は,年齢は低いが経験年数が少なくない「若手組」と,年齢は低くないが経験年数が少ない「転職組」に十分ではない。特に,「転職組」は,内外の研修会や勉強会の課題を今後さらに調査していく必要が示唆された。
キーワード 社会的養護,常勤専門職,職場環境の実態,人材育成の課題,スーパービジョン(SV)の機会
|
第67巻第8号 2020年8月 農林業への関わりと助け合い活動への
服部 真治(ハットリ シンジ) 市田 行信(イチダ ユキノブ) |
目的 中山間地域等の農村部の特徴であり,人的ネットワークや自治活動に密接に関係している農林業の活動に着目し,農林業に関わる地域住民が,それに関わらない地域住民と比較して,どの程度生活支援の意識を持っているかを検証することを目的とした。
方法 鳥取県智頭町において2017年7月に行われた介護予防・日常生活圏域ニーズ調査をもとに,要介護状態でない高齢者2,452人に対し自記式調査票を用いて郵送調査を行った。このうち,年齢と性別に欠損値のない有効回答1,358票(55.4%)を対象として分析を行った。統計的分析は,目的変数を助け合い活動への参加意識,説明変数は農林業への関わりとし,年齢,性別,経済状況,認知機能,身体機能を調整変数としたロジスティック回帰分析を行った。また,助け合い活動への参加意識の有無と,地域活動への参加状況を分析した。
結果 年齢,性別,経済状況,身体機能,認知機能について調整した上で,助け合い活動(全体・無償)への参加意識と農林業への関わりとの関連を分析した結果,農林業への関わりがある人ほど,助け合い活動への参加意識があるという結果が得られた。また,地域活動のうち,「ボランティアのグループ」「スポーツ関係のグループやクラブ」「趣味関係のグループ」に関し,助け合い活動への参加意識がある群は,参加意識のない群に対し有意に参加者が多いという傾向がみられた。
結論 本研究で,農林業への関与は,助け合い活動への参加意識の高さに関連することが示された。
キーワード 高齢者,助け合い活動,中山間地域,農林業,生活支援,ボランティア
|
第67巻第8号 2020年8月 男女別にみた都市旧ニュータウンに居住する
相原 洋子(アイハラ ヨウコ) 前田 潔(マエダ キヨシ) |
目的 高齢化が進展する都市旧ニュータウンに居住する高齢者を対象に,認知症になったときの居場所,支援に対する希望について,男女別に実態を把握することを目的とした。
方法 1960年代に住宅地開発が行われた兵庫県内最古のニュータウンの明舞地区に居住する65歳以上の人全員を対象に,半構造化質問紙を用いた横断調査を2019年5~9月に実施した。認知症になったときに住みたい場所として,自宅での暮らし,施設への入居など5つの項目から選択してもらい,また認知症・軽度認知障害(MCI)になったときに必要と思う支援として,構造化した5つの支援項目について必要の度合いならびに自由記述による回答を得た。調査協力の得られた2,269人(回収率22.4%)のうち,性別の記載がある2,252人を分析対象とし,居場所と支援希望をアウトカムとして単変量解析ならびに内容分析の手法を用い,男女で比較を行った。
結果 認知症となったときの居場所は,男性は「今の家に住み続けたい」の回答が4割と最も多く,女性は「施設・サービス付き高齢者住宅に入居」「今の家に住み続けたい」を希望する人が35%とほぼ同数であった。居宅生活を希望する人は,男女ともに家庭内介護者がいること,男性のみに持ち家(戸建)に住んでいる,近所付き合いをしている人に多い傾向が示された。認知症・MCI診断時の支援として,定量分析の結果は「日常生活支援」を希望する人が最も多かった。定性分析の結果は,想像できない・わからないといった「不明」に関する記述が全体ならびに男性に最も多く,女性高齢者は施設入所,在宅生活の継続といった「居場所」に関する内容が多く記述されていた。
結論 認知症時の居場所の希望として,男性は自宅,女性は施設を希望する傾向がみられた。また希望する支援においても女性は「居場所」に関する記載が多く,介護環境の性差がこのような結果につながったと考える。一方の男性は,支援を不明とする回答が多かった。認知症時の住まいや住まい方を本人が選択していけるように,住宅や介護サービスの情報提供,相談場所や介入方法など,性差に着目した認知症施策や制度の設計が求められる。
キーワード エイジング・イン・プレイス,支援,性差,ニュータウン,認知症,高齢者
|
第67巻第8号 2020年8月 栃木県における画像検査の地域偏在岡野 員人(オカノ カズト) |
目的 本研究は,栃木県における診療放射線技師の地域偏在状況と画像検査で広く使われているCTおよびMRIの装置数や患者数を調査し画像検査の需給状況について調査することを目的とした。
方法 対象は,2017年の医療施設調査からCTおよびMRIの「装置数」および「患者数」,「診療放射線技師数」とした。また,比較対象として「医師数」を用いた。各データは栃木県の6つの二次医療圏ごとに集計を行い,地域偏在の指標の一つであるジニ係数と集中度を示すハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)を算出し比較した。
結果 人口10万対CT装置数の最少は県北9.2台,最多は宇都宮および県南11.7台であった。人口10万対MRI装置数の最少は県東2.7台,最多は県南6.8台であった。一方,人口10万対CT患者数の最少が県東1,261人,最多は県南2,710人であった。人口10万対MRI患者数の最少は県東468人,最多は宇都宮1,333人であった。人口10万対診療放射線技師数の最少は県東22.4人,最多が県南53.7人であった。装置数および患者数,診療放射線技師数のジニ係数は医師と比較して低値であり,医師よりも均一な分布を示した。特にCT装置数のジニ係数は0.038と高い均一を示した。一方で,各対象のHHIは人口と比較して高値を示しており,すべてにおいて特定の地域に集中している傾向にあった。
結論 栃木県における画像検査の需給状況について二次医療圏の人口や地理的要因により地域偏在状況や地域の特徴を捉えたが,画像検査の医療資源の適正な配置については他の都道府県との比較や継続的な調査が必要である。
キーワード 画像検査,医療資源,地域偏在,診療放射線技師,ジニ係数,ハーフィンダール・ハーシュマン指数
|
第67巻第8号 2020年8月 大阪府内市町村における大腸がん検診の個別受診勧奨の実態濱 秀聡(ハマ ヒトミ) 田淵 貴大(タブチ タカヒロ)中山 富雄(ナカヤマ トミオ) 宮代 勲(ミヤシロ イサオ) |
目的 大阪府のがん検診受診率は低い。受診率の向上を目的とした個別受診勧奨が推奨されているが,その実態はほとんどわかっていない。そこで,市町村が実施する大腸がん検診の個別受診勧奨の実態を把握し,勧奨方法とがん検診受診率との関連について検討した。
方法 大阪府が府内全43市町村に対して実施した2017年度の大腸がん検診における個別受診勧奨と検診受診率に関する調査データを分析した。各市町村の勧奨方法を対象年齢に応じて4群(40~69歳の年齢すべて・特定の年齢層・節目の年齢・その他)に分類し,個別受診勧奨の実態を把握した。さらに市町村における勧奨方法と受診率の関連について検討した。
結果 個別受診勧奨を実施していた市町村は39(90.7%)であった。そのうち「40~69歳の年齢すべて」に勧奨していた市町村数は4,「特定の年齢層」は7,「節目の年齢」は19,「その他」は9であり,節目の年齢に勧奨している市町村が多かった。個別受診勧奨実施の群では,受診率にバラツキがあるものの,未実施の群と比べて受診率は有意に高く,その差は8.0ポイントであった(p=0.017)。勧奨方法4群と未実施をあわせた5群間で受診率を比較した結果,40~69歳の年齢すべてに勧奨している群は,他の4群と比べて受診率が有意に高く,その差は10ポイント以上であった(特定の年齢層:p=0.028,節目の年齢:p=0.004,その他:p=0.032,未実施:p=0.001)。
結論 大阪府内の多くの市町村で,がん検診の個別受診勧奨が実施されていたが,対象者全員に対する勧奨は少なかった。対象者への勧奨ができるよう,国や都道府県による検診体制整備の支援が必要だと考えられた。
キーワード がん検診,個別受診勧奨,受診率,大腸がん,検診体制整備の支援
|
第67巻第8号 2020年8月 非喫煙者における家庭での受動喫煙と高血圧の関連-東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホート調査より-平田 匠(ヒラタ タクミ) 小暮 真奈(コグレ マナ) 成田 暁(ナリタ アキラ)土屋 菜歩(ツチヤ ナホ) 中村 智洋(ナカムラ トモヒロ) 目時 弘仁(メトキ ヒロヒト) 中谷 直樹(ナカヤ ナオキ) 丹野 高三(タンノ コウゾウ) 菅原 準一(スガワラ ジュンイチ) 栗山 進一(クリヤマ シンイチ) 辻 一郎(ツジ イチロウ) 呉 繁夫(クレ シゲオ) 寳澤 篤(ホウザワ アツシ) |
目的 近年,受動喫煙が高血圧と関連することを示す疫学研究が散見されるが,関連を示さない報告もあり,一定の結論は得られていない。また,受動喫煙に関して10年前と最近1年間の受動喫煙状況を反映した検討も行われていない。そこで,本研究では非喫煙者を対象とした家庭での10年前および最近1年間における受動喫煙の組み合わせと高血圧有病との関連につき,国内の大規模コホートデータを用いた検討を行った。
方法 本研究は東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホート調査のベースライン調査データ(2013年5月~2016年3月に実施)を用いた断面研究である。宮城県在住で同調査のベースライン調査を特定健診共同参加型で受けた非喫煙者を解析対象とし,全解析対象者を10年前と最近1年間の家庭における受動喫煙の有無の組み合わせにより4群に分類した。家庭における10年前・最近1年間の受動喫煙の組み合わせと高血圧有病との関連を多変量ロジスティック回帰分析により検討し,10年前・最近1年間ともに受動喫煙のない者を参照群とした他群の高血圧有病に対するオッズ比と95%信頼区間を算出した。
結果 本研究の解析対象者は15,381名(男性2,370名,女性13,011名)であり,高血圧の有病者は5,603名(36.4%)であった。最近1年間に家庭での受動喫煙を認めた者は1,961名(12.7%)であり,そのうち1,775名(90.5%)が10年前にも家庭での受動喫煙を認めた。多変量解析の結果,10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認める者では,10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認めない者と比較して,年齢・BMI・飲酒歴などの高血圧の危険因子と独立し,高血圧の有病と有意な正の関連を認めた(オッズ比1.15,95%信頼区間1.02-1.29)。男女別の解析では,10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認める女性が10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認めない女性と比較し,高血圧の有病と有意な正の関連を認めた(オッズ比1.15,95%信頼区間1.02-1.30)。
結論 非喫煙者において家庭での長期間の受動喫煙があると年齢・BMIや飲酒歴などの古典的な高血圧の危険因子と独立して高血圧の有病リスクが有意に上昇した。公衆衛生上の観点からは家庭での受動喫煙の防止が肺がん・慢性閉塞性肺疾患や虚血性心疾患等の予防だけでなく血圧値の低下にも寄与する可能性が示唆された。
キーワード 受動喫煙,高血圧,疫学研究,非喫煙者,家庭
|
第67巻第7号 2020年7月 人生の終盤に向かう過程の事前準備支援に関する
島田 千穂(シマダ チホ) 伊東 美緒(イトウ ミオ) 児玉 寛子(コダマ ヒロコ) |
目的 人生の終盤を支えるエンドオブライフケアの質向上のためには,ケア利用者の意思に添ったケア計画が求められる。本研究は,利用者や家族との人生の終盤に向けた対話へのケアマネジャーの関与の実態とその程度に関連する要因を把握することを目的とした。
方法 居宅介護支援事業所5,612カ所に調査票を郵送し,管理者と最も多くの利用者を担当する所属ケアマネジャー最大3名を対象として自記式調査を実施した。返信用封筒を個別に添付し,回収した。調査内容は,人生の終盤に向けた対話への関与の程度,ケアマネジャーの属性,担当利用者属性(要介護度,独居,訪問診療利用者,認知症利用者など),ケアマネジャーの介護規範意識である。
結果 人生の終盤に向けた対話へのケアマネジャーの関与には個人差があり,担当する利用者の6割以上と対話経験があるケアマネジャーは,回答者3,320名のうち25.7%であった。一方,6割以上の利用者家族との対話は,36.2%が実施していた。ロジスティック回帰分析の結果,利用者本人との対話は,経験年数に加えてケアマネジャーの介護規範意識と有意に関連し,「家族が看取りにかかわるべき」と考える人ほど本人との対話は少なかった(p=0.038)が,利用者家族との対話と介護規範意識とは有意な関連が見られなかった。
結論 人生の終盤に向けた事前の対話は,本人より家族と実施しやすく,本人との対話はケアマネジャーの介護に対する規範意識と関連し,家族との対話はケアマネジメント業務上の必要性に基づく動機で開始されやすい可能性が考えられる。本人との事前対話の推進のためには,規範意識の変容をサポートする介入の必要性が示唆されたと考える。エンドオブライフケアを家族のみの責任としてとらえるのではなく,本人の意思に基づき社会で担うという考え方に基づくことで,事前準備のための対話への関与を高められる可能性があるだろう。本研究は,限られた地域のケアマネジャーを対象とした点で限界があるが,人生の終盤に向けた事前の対話に関与しているケアマネジャーの実態を示した初めてのデータとして価値があると考える。
キーワード エンドオブライフケア,アドバンスケアプランニング,ケアマネジメント,対話,ケアマネジャー,人生の終盤
|
第67巻第7号 2020年7月 健康寿命および平均寿命に関連する高齢者の生活要因の特徴細川 陸也(ホソカワ リクヤ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) 山口 知香枝(ヤマグチ チカエ)岡田 栄作(オカダ エイサク) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) |
目的 健康日本21(第二次)では,「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」が目標のひとつに掲げられている。効果的な取り組みを実施するためには,市区町単位の社会参加などのアプローチ可能な地域の特徴を明らかにしていく必要がある。そこで,本研究は,健康寿命および平均寿命に関連する高齢者の生活要因の特徴を地域レベルで検証することを目的とした。
方法 本研究は,JAGES(Japan Gerontological Evaluation Study,日本老年学的評価研究)の一環として,2013年の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に参加した全国85市区町を分析対象とした。地域レベルの指標として,高齢者の生活要因を社会参加,うつ傾向などの各割合とし,また,健康寿命・平均寿命を健康寿命の算定プログラムを用いた値とし,市区町単位で算出した。
結果 市区町を分析単位とし,健康寿命と平均寿命を従属変数,高齢者の生活要因を説明変数とし,種類ごとに個別に投入して重回帰分析を実施したところ,男性では,趣味の会への参加,スポーツの会への参加,ボランティアの会への参加,外出の機会,歯科医療機関への通院割合の高い市区町ほど健康寿命と平均寿命が長く,うつ傾向,喫煙の割合の高い地域ほど健康寿命と平均寿命が短い傾向がみられた。一方,女性に関しては,趣味の会への参加,スポーツの会への参加,ボランティアの会への参加,歯科医療機関への通院が有意な関連を示した。
結論 社会参加や歯科医療機関への通院など健康寿命と平均寿命に関連していた高齢者の生活の特徴にアプローチすることは,市区町などにおける健康寿命・平均寿命の延伸に寄与する可能性が示唆された。
キーワード 健康寿命,平均寿命,高齢者,生活要因,地域レベル
|
第67巻第7号 2020年7月 一人暮らし高齢者に対する
|
目的 本研究では,一人暮らし高齢者に対する支援において,介護支援専門員が感じている困難感についての実態を明らかにした。
方法 調査対象者は,一人暮らし高齢者を担当した経験のある介護支援専門員である。調査対象は大阪府下の居宅介護支援事業所と地域包括支援センターから2,500カ所を無作為に抽出し,1カ所につき1名の介護支援専門員とし,調査期間は平成31年1月30日~同年2月25日とした。質問紙調査は自記式質問紙を用いた郵送調査を行った。分析方法は,単純集計と記述統計量を用いた。
結果 回収された質問紙数は909票で,回収率は36.4%であった。介護支援専門員が感じる一人暮らし高齢者支援における困難感は,大きく2つに分けることができる。1つは,「対人支援を進めていく際の困難感」であり,もう1つは,「地域資源の不足による困難感」である。「対人支援を進めていく際の困難感」の代表的な困難感に,一人暮らし高齢者や別居家族の支援拒否に対する対応の困難感があげられ,「地域資源の不足による困難感」の代表的な困難感に,一人暮らし高齢者を支援していく際に重要となるキーパーソンの不在や地域住民に支援を求める際に生じる困難感があげられた。
結論 一人暮らし高齢者を支援していく際,介護支援専門員が感じる困難感を軽減していくための対応策では,一人暮らし高齢者事例に個別性が伴うため,容易な軽減策を見いだすことは難しいが,①地域包括支援センターの主任介護支援専門員によるスーパービジョンや後方支援,②地域ケア会議等の有効活用,③地域資源不足解消のための新たな制度設計や制度の見直し等を組み合わせることで適切な軽減策を見いだすことができると考える。
キーワード 介護支援専門員,支援困難感,一人暮らし高齢者,対人支援,地域資源,支援拒否
|
第67巻第7号 2020年7月 職員主体性の尊重とパーソンセンタードケア実践との関連-特別養護老人ホームと認知症型グループホームの介護職員に対する調査より-鄭 尚海(テイ ショウカイ) |
目的 本論文は,認知症ケアにおいて重要な役割を果たしている特別養護老人ホームと認知症型グループホームをフィールドにしながら,近年注目されているパーソンセンタードケア実践をよりよく行うための方策を提案することを目的とし,そこで働く職員の主体性の尊重とパーソンセンタードケア実践との関連を検討した。
方法 WAMNETに登録されている全国の特別養護老人ホームと認知症型グループホームのうち,それぞれ1,000カ所を無作為に抽出し,1施設につき1部,計2,000部の無記名の自記式調査票を各施設宛てに郵送した。回答者は,現在の施設において1年以上の認知症介護経験があり,現在も認知症介護に直接携わっている介護職員1名とし,その選出は各施設に一任することとした。分析は,単純集計と多重指標モデルを用いて,必要項目に欠損値のない556票を分析対象とした。
結果 単純集計において,職員主体性の尊重は,全体平均得点が3.50点(5点満点)であり,パーソンセンタードケアの実践は3.96点(5点満点)であった。また,パーソンセンタードケアの実践を従属変数,職員主体性の尊重を独立変数とした多重指標モデルは,いずれの指標においても統計学的な許容水準を満たしており,決定係数(説明率)が0.42と中程度であった。さらに,この多重指標モデルを用いて検証した結果,主体性が尊重されると感じる職員ほど,パーソンセンタードケア実践度が高かった。
結論 本研究の結果,パーソンセンタードケア実践をよりよく行うためには,職員主体性の尊重が重要であると示唆された。また,職員主体性の尊重を行う際に参考となる過程を提示し,重要となる中間管理職に対する研修の実施やスーパービジョン体制の構築を提言した。
キーワード 職員主体性の尊重,パーソンセンタードケア,職場環境,介護職員
|
第67巻第7号 2020年7月 高齢者の社会貢献活動の取り組みの現状と
|
目的 地域の生活課題の解決には高齢者の力がより活用されることが目指されているという背景から,本論文の目的は,高齢者の社会貢献活動の取り組みの状況,社会貢献活動に取り組めるきっかけや条件を性別および社会貢献活動(以下,活動への意向)への意向別に検討し,高齢者の社会貢献活動の取り組みが進展するための促進方法について考察することである。
方法 東京都A市にある集合住宅(分譲マンションと都営住宅)に居住する高齢者に,事前に自治会長に許可を得た上で無記名自記式質問紙調査を行った。調査期間は,2017年6月20日から10月15日である。分析対象者数は,性別の回答があった330人である。性別や活動への意向別の差の比較検討ではχ2検定を行った。
結果 本研究において,社会貢献活動をしたいと思っている高齢者は男女とも6割であったが,実際には7割の人が何らかの社会貢献活動を行っており,多くの高齢者において取り組まれていることが確認された。自治会活動が男女ともに最も多く取り組まれていた。シルバー人材センターを通した活動は男性で有意に多く行われていた。活動に取り組めるきっかけとして男性で一番多かったのは「行政や社協などによる募集」であり,女性で多かったのは「家族や他者からの勧め・誘い」であった。活動に取り組める条件では男女ともに「友人・知人と一緒にできること」と「自らの健康状態がよくなること」が多かったが,「通う手段が確保されること」は女性に有意に多かった。活動への意向別にみると,活動への意向がある人の方がそうでない人に比べ実際に活動に取り組んでいる傾向があった。活動への意向があまりない人においても,きっかけや条件によって取り組めると感じている人がいることが明らかになった。
結論 社会貢献活動に取り組む人を増やすための視点としては,活動への意向のある人を情報発信の強化や研修会の開催,活動への誘いを通してより実際の活動につなげていくこと,また活動への意向があまりない人に対しては,まずきっかけをつくり,活動に参加してもらうことで自らの役割を認識してもらうことや地域課題を学ぶ学習会などを通して活動に関心を持ってもらうことが有効である。社会貢献活動をする際に友人と一緒にできることや同世代と交流できることを取り組める条件としてあげている人が多かったことから,その点も考慮した活動の展開が求められる。また特に女性においては通う手段が確保されることも条件としてあげられており,活動に参加するための送迎も含めた支え合い活動も今後より重要である。
キーワード 社会貢献活動への意向,社会貢献活動に取り組めるきっかけ・条件,高齢者,地域の生活課題
|
第67巻第7号 2020年7月 高齢者のICT利用状況の変化要因について-縦断調査データを用いて-深谷 太郎(フカヤ タロウ) 小林 江里香(コバヤシ エリカ) |
目的 高齢者のインターネット利用率は年齢が高くなるにつれて低下するが,60代では7割を超えており,年々増加傾向にある。しかし,横断調査の繰り返しでは,高齢者集団の中で利用者が増えているのか,それとも利用率の高い年齢層が順次高齢者の仲間入りをしているのかは不明である。そこで,同一人物を対象とした縦断調査のデータを用いて,高齢者のICT(電子メール,インターネット)の利用状況の変化と,その要因を検討した。
方法 東京都健康長寿医療センター研究所,東京大学,ミシガン大学が共同で行っている全国の60歳以上を対象とした調査において,2012年に新規に調査対象者となり,かつ,2017年に行われた追跡調査にも回答があった865人を分析対象とした(平均年齢70.5歳)。電子メールとインターネットは,それぞれ利用頻度が週1回以上を「利用あり」として2時点の利用の有無の変化を調べた。また,2012年調査時点での利用者と非利用者に分け,2017年時点での利用の有無により,「利用開始」と「利用中止」のそれぞれを従属変数とするロジスティック回帰分析を実施した。独立変数は,2012年調査時点での性別,年齢,独居,居住地の都市規模,教育年数,暮らし向き(主観的な経済状態),就労状況,親しい友人・近隣数,手段的日常生活動作(IADL),抑うつ傾向,および2時点間での退職の有無とした。
結果 電子メール,インターネットとも,2回の調査間では,利用開始者と利用中止者の数はほぼ等しかった。さらに,両ICTともに,年齢の若い人や教育年数の長い人ほど利用を開始しやすく,電子メールは友人・近所とのつきあいがない人ほど開始しにくい傾向がみられた。利用中止の要因は電子メールとインターネットでは異なり,電子メールについては教育年数の短い人や経済状態が悪い人,就労していない人で中止しやすい傾向があった。
結論 既存の調査においてみられる高齢者のインターネットなどの利用率の上昇は,同一コホート内で実際に利用者が増えているのではなく,出生コホートの入れ替えに伴うものであり,短期的には高齢者のICT利用率は低いという前提で施策を立案すべきと思われる。また,利用開始と利用中止(利用継続)の関連要因は必ずしも同じではなく,ICT利用率の向上のためには,利用開始だけでなく利用中止の要因についても多面的に検討していく必要がある。
キーワード 高齢者,ICT利用,縦断研究,電子メール,インターネット
|
第67巻第6号 2020年6月 医師調査の届出率の推移-2002年から2016年の個票データを用いた推計-石川 雅俊(イシカワ マサトシ) |
目的 日本における医師調査は,厚生労働省によって二年に一回,すべての医師を対象として実施されているが,届け出を行わない医師が一定程度存在することが以前から指摘されてきた。先行研究によれば,届出率は約90%と推計されているが,近年の研究はない。本研究では,2002年から2016年の医師・歯科医師・薬剤師調査(以下,三師調査)の個票データを用いて生存率を補正した届出率を算出し,医師調査の届け出の現状について明らかにし,さらに,届出率を上げるための政策提言を行う。
方法 2002年から2016年の三師調査の個票を加工したデータを厚生労働省の許可を得て入手した。2002年から2016年までの医籍登録年ごとの届出数,医籍登録者数のデータを用いて,生存率を補正しない届出率の推移を推計した。さらに,2016年の生存率を補正した届出率を推計した。
結果 生存率を補正しない届出率は,2014年89.4%と上昇傾向にあった。医籍登録25年以上では,登録年数が長いほど,届出率は低くなる傾向にあり,医籍登録40~44年の届出率は80%を下回っていた。一方,医籍登録4年以下の医師の届出率は,2016年は95%を超える水準まで上昇傾向にあった。男女差をみると,医籍登録10年以上では女性医師の届出率が低くなっており,医籍登録15~19年で80%を下回っていた。生存率を補正した届出率は2016年で90.2%だった。
結論 女性医師は出産や育児の影響,高齢医師は退職や死亡の影響で,届出率が低下していると考えられる。届出率を向上させる施策として,医師データベースの構築,マスメディア等を活用した広報,未届けに対する罰則適用の厳格化等が考えられる。三師調査は,医療政策の適切な遂行のために重要な調査であり,届出率向上に向けた施策を検討し,適切に実施していく必要がある。
キーワード 届出率,医師調査,縦断研究,医籍登録,医療政策
|
第67巻第6号 2020年6月 患者調査データを用いた
奥井 佑(オクイ タスク) |
目的 患者調査のデータを用いて近年の循環器疾患の患者数と通院率の動向について年齢・時代・コホート分析(APC分析)を行った。
方法 1999年から2017年までの患者調査の循環器疾患患者の総患者数,人口動態調査の人口のデータを用いた。循環器疾患として,高血圧性疾患,心疾患(高血圧性を除く),虚血性心疾患,脳血管疾患の4疾患の動向を分析した。年齢区分は30-34歳から85-89歳まで5歳刻みで全12年齢階級とし,コホート情報として,1910-1914年生まれから1983-1987年生まれ世代まで1歳刻みでコホートを定義して用いた。分析手法として,ベイジアンAPCモデルを用い,男女別に通院率の変化を年齢効果,時代効果,コホート効果の3つに分離した。
結果 循環器疾患のうち,高血圧性疾患の患者数は男女とも増加傾向であるのに対して,虚血性心疾患や脳血管疾患は減少傾向であった。APC分析の結果,男女とも年齢効果が他の効果よりも相対的に変動が大きい場合が多く,通院率に対する年齢効果が高齢になるほど高まることが確認された。高血圧性疾患について,男女とも1948年生まれ近辺から通院率に対するコホート効果が世代を経るごとに減少していたが,男性の方が効果の減少度合いが緩やかであり,1976年生まれ近辺からは効果が上昇に転じていた。心疾患(高血圧性を除く)について,男性で1930年生まれ近辺から,女性では1920年代生まれ近辺からコホート効果の減少がみられたが,女性における効果の減少度合いがより顕著であり,男性では1965年生まれ近辺から効果が横ばいとなっていた。脳血管疾患については,男女ともコホート効果の減少が認められたが,男性においては1970年生まれ近辺から,女性においては1960年生まれ近辺からコホート効果が緩やかに上昇に転じていた。
結論 患者調査データを用いて循環器疾患通院率の動向をAPC分析した結果,疾患および性別により時代効果とコホート効果の動向が異なることが示され,男女で患者数の動向が類似する場合においても各効果の動向が異なる傾向が示された。
キーワード 循環器疾患,年齢・時代・コホート分析,患者調査,公的統計,ベイジアンAPCモデル
|
第67巻第6号 2020年6月 安全衛生担当労働者における加熱式タバコの利用状況加藤 善士(カトウ ヨシジ) 太田 充彦(オオタ アツヒコ) 八谷 寛(ヤツヤ ヒロシ) |
目的 職域では受動喫煙対策とともに喫煙労働者への禁煙指導が課題となっている。日本の職域における加熱式タバコの使用実態を報告した論文は少ない。本研究の目的は,職域における加熱式タバコの使用実態を把握し,喫煙対策の実施につながる知見を得ることである。
方法 某労働災害防止団体の地方センターにおいて2019年4月~6月末の3カ月間に開催した安全衛生教育受講者(819人)を対象にした自記式質問紙調査を実施した。喫煙率,加熱式タバコ利用状況,年齢,性別,役職,企業規模,喫煙習慣との関連を調べた。回答者741人のうち,男性回答者で分析に必要な項目に欠損がなかった653人を解析した。
結果 喫煙率は37.8%(247人)であった。現喫煙者割合は40~49歳で高く(40.1%),過去喫煙者割合は50歳以上で高く(37.8%),非喫煙者割合は40歳未満で高かった(49.1%)(p<0.001)。役職,企業規模と現喫煙,過去喫煙,非喫煙の割合に有意な関連は認めなかった。現喫煙者247人の内,加熱式タバコのみを利用する者が67人(現喫煙者の27.1%),加熱式タバコと通常のタバコとの併用者が55人(現喫煙者の22.3%)であった。加熱式タバコの利用状況(加熱式のみ,併用,通常のタバコのみ)と年齢,役職,企業規模との間に統計学的に有意な関連は認めなかった。加熱式タバコの利用理由は「においが少ない」(67.2%),「煙が少ない」(47.5%),「火の心配が少ない」(43.4%),「自分の健康被害が少ないと思う」(35.2%),「周囲の健康被害が少ないと思う」(34.4%)であった。
結論 男性労働者の喫煙率には年齢による差はあったが,企業規模や役職による差はなかった。男性労働者の加熱式タバコの利用は20%程度で,全喫煙者の約半分であった。本研究では,健康被害よりもにおいや火に関連した危険を理由として加熱式タバコを利用する者が多かった。事業場においては,通常のタバコへの喫煙対策と併せて加熱式タバコへの対策も行うことが望まれる。
キーワード 男性労働者,喫煙,年齢,企業規模,役職,加熱式タバコ
|
第67巻第6号 2020年6月 自主継続型運動教室の参加状況の違いが
田島 聖也(タシマ マサヤ) 安田 俊広(ヤスダ トシヒロ) |
目的 介護予防を目的とした高齢者対象介護予防運動教室の参加者において,教室への参加状況の違いがその後の要介護認定率に与える影響を明らかにすることを目的とした。
方法 2011年7月から2015年3月の期間において,福島県伊達市の高齢者対象介護予防運動教室に参加経験のある834名を対象者とし,1年度内に50回以上の参加経験を有する者202名(74.2±5.5歳)を参加群とし,1年度内に50回以上の参加経験のない者632名(72.6±5.6歳)を不定期参加群に群分けした。さらに不定期参加群の内,2015年4月時点で参加していない者398名(72.7±5.8歳)を不参加群として抽出した。分析は,累積介護認定率,リスクファクターのハザード比を算出して介護予防効果を検証した。累積介護認定率は,対象期間の自立と認定を追跡し,Kaplan-Meier法により各群の推移を比較した。群間の有意差検定は,ログランク検定と一般化ウィルコクソン検定を用いた。また,ハザード比はCox比例ハザードモデルを用いて,目的変数に要介護認定の有無(自立=0,認定=1),説明変数に年齢(+1),性別(女=0,男=1),教室参加状況(0=参加群,1=不定期参加群)を設定して尤度比による変数増加法にてハザード比を算出した。
結果 Kaplan-Meier法による累積要介護認定率は,観察期間48カ月時点において参加群7.3%,不定期参加群12.9%,不参加群18.8%であり,参加群と不参加群の間において統計的有意差が認められた。Cox比例ハザードモデル分析の結果,性別は変数選択の段階で排除され,年齢が1歳増加した時のハザード比は1.20倍であった。また,教室参加状況において参加群と比較した際の不定期参加群のハザード比は2.99倍であった。
結論 高齢者対象介護予防運動教室における要介護認定を受けた者の割合を比較,検討したところ,Cox比例ハザードモデル分析の結果から,不定期参加群は参加群より3倍要介護認定を受けやすいという結果となった。しかし,本研究の限界により,週1回以上の運動教室への参加が要介護認定を遅延させると結論づけることはできなかった。
キーワード 高齢者,要介護認定,介護予防運動教室,Kaplan-Meier法,Cox比例ハザードモデル
|
第67巻第6号 2020年6月 子育て期の女性における精神的健康の関連要因岩佐 一(イワサ ハジメ) 石井 佳世子(イシイ カヨコ)吉田 祐子(ヨシダ ユウコ) 安村 誠司(ヤスムラ セイジ) |
目的 子育て期の親においては,精神的健康が損なわれやすいとされ,支援の重要性が認知されている。子育て期の女性における精神的健康の関連要因について調査し,支援策の構築に資する知見を報告することは重要である。本研究は,子育て期の女性を対象として,就労状況,睡眠時間,疲労感,ソーシャルサポート,神経症傾向,認知的失敗と精神的健康の関連について検討した。
方法 インターネット調査会社に委託して調査を実施し,生後3カ月~6歳の児を養育する母親310人を分析の対象とした(25~45歳,常勤職員155人,主婦155人)。精神的健康(「ポジティブ感情」「ネガティブ感情」各6項目ずつ計12項目,5件法),就労状況,母親の年齢,末子の年齢,児の人数,世帯収入,ソーシャルサポート,育児サービスの利用状況,1日の睡眠・余暇時間,疲労感,神経症傾向,認知的失敗(15項目,5件法)を分析に用いた。精神的健康の関連要因を検討するため重回帰分析を行った。
結果 重回帰分析の結果,ポジティブ感情では,末子の年齢(β=-0.15),疲労感(β=-0.36),情緒的サポート(β=0.16),神経症傾向(β=-0.13)が有意な関連を示した。ネガティブ感情では,母親の年齢(β=-0.11),疲労感(β=0.20),情緒的サポート(β=-0.16),神経症傾向(β=0.17),認知的失敗(β=0.38)が有意な関連を示した。
結論 認知的失敗が高い者ほど精神的健康が低かった。認知的失敗を低減させるための方略(メモ等の外部記憶補助の使用等)を日常生活に導入することによって,母親の精神的健康を維持する可能性が示唆される。疲労感が高い者ほど,精神的健康が低かった。母親の精神的健康維持のためには,専門的なケア,ソーシャルサポート,育児・家事サービスの利用等によって,疲労を軽減する必要がある。神経症傾向が高い者ほど,精神的健康が低いため,神経症傾向の程度を予め把握し,精神的健康の防御要因(ソーシャルサポート等)を周産期に至る前に補強しておくことは,母親の精神的健康の維持に有用であると考えられる。情緒的サポートが高い者ほど,精神的健康が高かった。傾聴する,苦労をねぎらう等の母親に対する情緒面の支援が,母親の精神的健康維持に有用である。
キーワード 母親,子育て,精神的健康,認知的失敗,神経症傾向,情緒的サポート
|
第67巻第6号 2020年6月 要介護認定率の影響要因-全国市町村(組合)別と石川県津幡町の地区別年齢階層別データを用いた分析-谷下 雅義(タニシタ マサヨシ) |
目的 全国市町村(組合)別および石川県津幡町の地区別データを用いて,要介護認定率に影響を及ぼす要因について検討した。
方法 全国市町村(組合)別の分析では,可住地人口密度,「後期高齢者割合(65歳以上人口に対する75歳以上人口の割合)」「単身・夫婦のみ世帯割合(高齢者を含む世帯のうち単身もしくは夫婦のみ世帯の割合)」そして可住地面積を説明変数として,非線形性および空間相関を考慮した加法モデルを用いて要介護認定率の推定を行った。津幡町の地区別年齢階層別の分析では,地区別年齢階層別に要介護認定率について町の平均との差の検定を行った。有意な差がみられた地区や年齢階層の抽出を行うとともに,その要因について国勢調査の基本単位区(集落)の人口・世帯データを用いて検討を行った。
結果 全国市町村(組合)別の分析では,可住地人口密度,「後期高齢者割合」および「単身・夫婦のみ世帯割合」が高いほど,要介護認定率が高いと推定された。津幡町の地区別年齢階層別の分析では,年齢階層別要介護認定率が町の平均より統計的に有意に低いと推定された地区は,相対的に可住地人口密度が低くかつ基本単位区における「単身・夫婦のみ世帯割合」が低かった。
結論 可住地人口密度に加えて,世帯類型が要介護認定率に影響を与えている可能性を明らかにした。
キーワード 要介護認定率,可住地人口密度,後期高齢者割合,単身・夫婦のみ世帯割合,加法モデル
|
第67巻第5号 2020年5月 求人票からみた高校生の志望傾向(就職)白木 香(シラキ カオル) |
目的 人手不足が深刻になり,事業所は高校生に対する求人を積極的に行っている。しかし,高校生の就職は1人1社受験なので,どの事業所を選ぶべきか迷うことが多い。岐阜県A高校の協力のもと,平成29年度に届いた求人票(高卒)について分析し,事業所の求人傾向と生徒の志望傾向を考察するのがこの研究の目的である。
方法 分析できた求人票285枚を,受験のあった求人票106枚,受験のなかった求人票179枚に分け,この2群での比較を行った。①産業や職種の種別等で求人票の枚数が多かった「大手・準大手事業所」「中小事業所」「製造業」「卸売・小売業」「医療・福祉業」「事務」「販売」「サービス」「生産工程」の区分について,受験・非受験の偏りについて確かめた。②求人票に記載されている報酬と休日に関する情報(「基本給」「月平均残業時間」「月平均労働日数」「年間休日数」「年収」)について,2群間の平均値の差を検定した。
結果 求人票を産業・職種で分類した結果,特定の産業・職種に大きく偏って届けられていた。①では,「事務」「販売」について受験求人票の割合が有意に多くなっていた。②については,報酬面においても休日面においても,平均値は受験求人票の群が,非受験群に比べて高い傾向が認められたが,統計的に有意な差は休日面だけであった。
結論 A高校では事務職と販売職の人気が高いことがわかった。生徒の応募傾向は,報酬面に関しては傾向が判断できるような結果が明らかにならなかったが,休日面に関しては,休日が多い求人票を優先的に選んでいる傾向があるという結論になった。
キーワード 高校生の就職,求人票(高卒),偏り,応募傾向,報酬,休日
|
第67巻第5号 2020年5月 自治体における自殺予防のためのゲートキーパー研修の
小高 真美(コダカ マナミ) 高井 美智子(タカイ ミチコ) 太刀川 弘和(タチカワ ヒロカズ) |
目的 本研究では,自治体における自殺予防のためのゲートキーパー研修開催の実態およびその研修評価の実施状況や評価を促進するために必要な要件を明らかにすることを目的とした。
方法 全自治体(47都道府県,20政令指定都市,1,721区市町村)の自殺対策担当課に郵送法による質問紙調査を実施した。質問紙は,1)平成28年度の自殺予防のためのゲートキーパー研修の実施状況,2)平成28年度に実施した研修のうち,最もプログラムが充実していたと考えられる研修1つに関する詳細(評価実施状況を含む),3)研修評価に重要であると考える要素,で構成した。
結果 平成28年度にゲートキーパー研修を実施した自治体は,調査への有効回答を得た自治体全体の52.7%(都道府県(92.7%),政令指定都市(94.7%),区市町村(50.2%))であった。平成28年度の代表的なゲートキーパー研修の評価について,研修参加者人数および参加者の属性の記録,研修参加者の満足度や感想などのアンケートの実施など,研修プログラムのプロセス評価は多くの自治体で実施されていた。しかし既存の評価指標等を用いて研修のアウトカムを評価するための調査は,全体では14.6%の実施状況にとどまっていた。また研修評価を行う上では「評価指標などを含む評価方法についての情報」「評価に必要な知識やスキル」「評価結果の活用方法」が重要であることが明らかになった。
結論 本調査で回答を得た自治体のうち,9割以上の都道府県,政令指定都市が,また区市町村でも5割がゲートキーパー研修を実施していたが,その実施形態は多様であることがうかがえた。研修評価については,大多数の自治体でプロセス評価を実施している一方,アウトカム評価は不十分である状況が確認された。今後はアウトカム評価を中心に,その実施方法や必要な知識・スキル,また評価結果の活用方法を中心に全国の自治体に提案していくことが急がれる。
キーワード 自殺予防,自殺対策,ゲートキーパー研修,実施状況,プログラム評価,実態調査
|
第67巻第5号 2020年5月 医療計画におけるへき地医療に関する研究小池 創一(コイケ ソウイチ) 松本 正俊(マツモト マサトシ) 鈴木 達也(スズキ タツヤ)寺裏 寛之(テラウラ ヒロユキ) 前田 隆浩(マエダ タカヒロ) 井口 清太郎(イグチ セイタロウ) 春山 早苗(ハルヤマ サナエ) 小谷 和彦(コタニ カズヒコ) |
目的 第7次医療計画からへき地保健医療計画は医療計画へ統合された。この統合は,より効率的な計画策定や,国民にとってもより理解しやすい計画となることを期待してのものであったが,独立した計画がなくなることによって,へき地医療対策が埋没してしまう懸念も生じている。本研究の目的は,へき地保健医療計画の医療計画への統合の前後で,医療計画の記載内容がどのように変化しているかを評価することで,都道府県におけるへき地医療への取り組み状況の変化について明らかにすることにある。
方法 千葉県,神奈川県,大阪府を除く44都道府県の第6次および第7次医療計画に関し,5疾病・5事業および在宅医療に関する記載から,へき地医療についての記載ページ数・評価指標数ならびにこれらが5疾病・5事業および在宅医療についての記載ページ数・評価指標数に占める割合を算出した。また,今後のへき地医療の課題と考えられる項目について記載の有無を調査した。
結果 第6次医療計画のへき地医療関連の記載量は,平均7.8ページであったものが,第7次医療計画では,9.8ページとなっており,2.1ページ増加していた。一方,5疾病・5事業および在宅医療に占めるへき地医療に関する記載の割合は,7.5%から7.2%と減少した。同様に,評価指標数は,第6次保健医療計画で平均2.3項目,第7次医療計画で平均2.9項目と増加した。一方,評価指標に占める割合は5.5%から3.9%に減少した。医療計画内に記載されている内容については,へき地医療に従事する医療従事者の継続的確保や医療従事者の養成課程等におけるへき地医療への動機付けや,ICTによる診療支援体制やドクターヘリの活用等を評価指標とする都道府県が第6次計画時点に比較して大きく伸びているが,へき地医療拠点病院による巡回診療,医師派遣,代診医派遣の実施状況に関しては,第6次,第7次で大きな差はなかった。
結論 へき地保健医療計画が医療計画に統合され,記載の有無や分量という観点からは一定程度の充実が図られたが,より効率的で,医療を受ける側の国民にとってもより理解しやすい計画となっているかについてはさらなる検討が必要である。また,計画を実行し,事業の進捗状況を把握・評価し,必要な修正を加えるといったPDCAサイクルが実践されているかという観点からも引き続き検討が必要であることが明らかとなった。また,へき地や無医地区・準無医地区の定義についての議論も必要である。
キーワード へき地保健医療計画,医療計画,PDCA
|
第67巻第5号 2020年5月 子育て支援における感染症流行の
細井 菜々美(ホソイ ナナミ) 小林 千幸(コバヤシ チユキ) 畠山 佳織(ハタケヤマ カオリ) |
目的 少子化が進む中で女性の社会進出を促進し,同時に出生率を改善させるためには,子育てと仕事の両立支援を行うことや働き方改革を進める必要がある。子育て支援として求められているものに,子どもの急病(主に感染症)時の対応がある。感染症発生状況の情報共有は保育園関係者のみでの活用にとどまっており,地域の子育て支援には活用されていない。本研究では,地域の子育て支援策に感染症流行のリアルタイム情報を提供することが子育て当事者にとってどのように役立つのか,また予防行動について検討した。
方法 本研究は東京都内のある自治体のファミリーサポートセンターに登録をする利用者を対象とした。センターから登録している会員に配布する会報誌に本調査の依頼書を同封し,感染症流行リアルタイム情報提供の配信希望の登録のあった方にインターネットを用いた無記名のアンケート調査を2018年12月16日から同月26日の期間に実施した。
結果 感染症流行リアルタイム情報提供の配信希望の登録は302名,そのうちアンケート調査の回答者数は40名(回答割合13%)であった。回答者は30代が38%,40代が60%で,ほとんどが女性であった。子どもの通園通学先は保育園が最も多く,次いで小学校であった。子どもの通園通学先での感染症の流行について,園や学校から情報提供がある人が多かったが,その情報が当日のものである人は63%,当日の情報でない人は37%であった。子どものインフルエンザ予防接種の接種状況は,「毎年している」が最も多かった。子どもの体調不良に伴う急な予定変更の可否は,「変更できる」が全体で38%,子どもが保育園にいる保護者で53%,「変更できない」「わからない」が全体で43%,子どもが保育園にいる保護者で48%であった。感染症情報の配信を受けた場合どのようなことに役立ちそうかは,全体と子どもが保育園にいる保護者で差が最も大きかったものは「職場での業務内容調整」で,全体で12人(30%),子どもが保育園にいる保護者で11人(47%)であった。
結論 感染症流行のリアルタイム情報の提供に加えて,ファミリーサポートの利用会員と提供会員の間で情報を共有することにより,さらに子どもを感染症から守るために役立つのではないかと考えられた。今後は地域の多様な子育て支援に関わる人にとって,本研究結果を用いることができるかどうか検討する必要がある。
キーワード ファミリーサポートセンター,感染症,子育て支援,保育園,子ども,感染症流行のリアルタイム情報
|
第67巻第5号 2020年5月 被保険者・被扶養者別にみた子育て世代女性における
月野木 ルミ(ツキノキ ルミ) 村上 義孝(ムラカミ ヨシタカ) |
目的 子育て中の49歳以下女性を対象に,自身の健康管理状況と受診しやすい健診環境との関連を被保険者・被扶養者別に比較する目的で,ニーズ調査を実施した。
方法 2018年9月~2019年5月に関東・関西地域の子育てサロン・イベント等に参加した者のうち,小学校以下の子どもを持つ49歳以下の母親を対象とした。解析対象者は上記対象者の中で血液検査と質問紙調査両方に参加した165名とした。調査方法は,自記式質問紙法により母親と子どもの基本的属性,健康管理状況,受けやすい健診スタイル,理想の健診所要時間などを尋ねるとともに,身長・体重(自己申告),血圧値(測定値)を収集した。血液検査値は,「DEMECALメタボリックシンドローム&生活習慣病セルフチェック」を用い測定した。
結果 対象者の年齢の平均値と標準偏差(以下,SD)は,被保険者が35.6(SD:4.5)歳,被扶養者が36.6(SD:4.3)歳で,共に35~39歳の割合が多かった。最近の健診・がん検診受診状況は,毎年・数年ごとの定期受診者は,被保険者55名(73.3%)に対し,被扶養者34名(37.8
%)と低かった。健診・がん検診未受診者は,被保険者2名(2.7%)に対し,被扶養者37名(41.1%)と多かった。生活習慣は,毎日飲酒する被扶養者が14.4%と被保険者6.7%に比べて多い傾向を示した。また十分な睡眠がとれていない者が,共に49~51%を占めた。血圧・血糖・脂質は,「測ったことがあるが,覚えていない」者が共に40~50%を占めた。受診しやすい健診スタイルは,被保険者・被扶養者共に「待ち時間が短い」「子連れ可」が72~82%を占めた。被扶養者は,被保険者と比べて「ワンコイン(500円)」「がん検診とセット」「健診項目が多い」「自宅でできる健診」の要望が有意に多かった。さらに,健診・がん検診未受診の被扶養者でみると,「待ち時間が短い」32名(86.5%),「子連れ可」31名(83.8%)の順で多く,他は「ワンコイン(500円)」17名(45.9%),「がん検診とセット」16名(43.2%)であった。理想の健診所要時間は,「30分」が被保険者36名(48.0%),被扶養者32名(35.6%)で,「1時間」が被保険者28名(37.3%),被扶養者50名(55.6%)であった。
結論 子育て中である49歳以下の被扶養者に対する生活習慣病予防健診・特定健診の受診対策では,健診時間の短縮・費用負担の軽減・がん検診同時受診に加え,託児・子連れ可というニーズに対応した柔軟な健診体制づくりが重要である。併せて自身の健康への関心を高めることも重要と考える。
キーワード 母親,生活習慣病,特定健康診査,被扶養者,未受診
|
第67巻第5号 2020年5月 がん患者における医療保険の種別・本人家族別にみた
森島 敏隆(モリシマ トシタカ) 佐藤 亮(サトウ アキラ) 中田 佳世(ナカタ カヨ) |
目的 がん検診受診率は市町村国民健康保険(市町村国保)加入者よりも被用者医療保険加入者のほうが高く,被用者保険の中では被保険者本人は家族よりも高い。しかし,がん患者における検診発見や早期がんの割合について,保険の種類や本人・家族による差異は知られていない。就労世代のがん患者の検診発見がんと早期がんの割合を保険種別と本人・家族別に明らかにする。
方法 データソースは大阪府がん登録と府内のがん診療拠点病院36施設のDPCデータの連結データである。大阪府がん診療連携協議会のがん登録・情報提供部会に2017年にDPCデータを提供した病院で2010~15年に胃,大腸,肺,乳房(女性)のがん(上皮内を含む)と診断され,がん診断年月に保険診療を受けた40~59歳の患者と,子宮頸部(女性)のがん(上皮内を含む)と診断された20~59歳の患者を対象とした。がん診断時のDPCデータから患者の加入する保険を市町村国保と,被用者保険である健康保険組合(健保),協会けんぽ(協会),共済組合(共済)と,その他(国保組合,生活保護等)に分類し,さらに被用者保険加入者を本人と家族に分類した。がん登録に報告された発見経緯の「検診・健康診断・人間ドックで発見」を検診発見がん,進展度の「上皮内」と「限局」を早期がんと扱った。保険種別・本人家族別の検診発見がんと早期がんの割合の算出をがんの部位ごとに行った。
結果 分析対象のがん患者数は胃,大腸,肺,乳房,子宮頸部の順に,3,392,6,012,2,420,9,296,6,816人であった。5つの部位の検診発見と早期がんの割合は概して,保険種類別では健保か共済のどちらかが最も高く,それらに続いて協会,市町村国保の順であった。被用者保険の本人・家族別では家族よりも本人のほうが高かった。
結論 就労世代のがん患者において,市町村国保加入者と被用者保険の被保険者家族の検診発見および早期がんの割合が低いことがわかった。がん検診の受診勧奨において留意するべき知見であると考える。
キーワード 腫瘍,検診,二次予防,早期診断,医療保険,診療報酬明細書
|
第67巻第4号 2020年4月 DPCデータを用いたミトコンドリア病の記述的研究居林 興輝(イバヤシ コウキ) 藤本 賢治(フジモト ケンジ) 松田 晋哉(マツダ シンヤ)伏見 清秀(フシミ キヨヒデ) 三牧 正和(ミマキ マサカズ) 後藤 雄一(ゴトウ ユウイチ) 藤野 善久(フジノ ヨシヒサ) |
目的 従来,わが国のミトコンドリア病の疫学調査は,おもに病院アンケート調査によって行われ,全国規模の患者調査は実施困難であった。しかし,近年電子レセプトデータの利用環境が整備・拡充されつつあり,研究目的の利用も推進されている。本研究では,DPCデータを用いてミトコンドリア病の有病者数の推定を行った。また,今回利用したDPCデータの利用可能性および今後の課題について検討した。
方法 一般社団法人診断群分類研究支援機構の調査研究に協力している国内のDPC参加病院のデータを用いて,病名検索によりミトコンドリア病患者を抽出した。主要評価項目は,ミトコンドリア病の有病者数とした。また,副次評価項目として,ミトコンドリア病患者の各種集計(疾病グループ,性別,年齢,在院日数,ICD10分類,各種医療行為,入院患者の都道府県別分布,入院中の死亡)を行った。
結果 ミトコンドリア病の有病者数は1,386人と推定された。
結論 DPCデータを利用することで,ミトコンドリア病の有病者数は推定可能であることが示唆された。しかし,より悉皆性の高い調査を行うためには,DPCに参加していない病院の入院患者,および外来患者のデータベースを加えて調査する必要がある。
キーワード ミトコンドリア病,指定難病,有病者数,DPC,記述疫学
|
第67巻第4号 2020年4月 ヒトT細胞白血病ウイルス1型キャリア支援に
滝 麻衣(タキ マイ) |
目的 本調査研究の目的は,ヒトT細胞白血病ウイルス1型(以下,HTLV-1)のHTLV-1感染者(以下,キャリア)を対象とした健康関連QOL(以下,HRQOL)実態調査を行うことで,HTLV-1総合対策におけるキャリア支援体制の確立に向けた布石とすることである。
方法 対象は,関西地区に存在するHTLV-1専門外来で経過観察中のキャリアのうち,2017年11月から1年の期間内に調査協力が依頼できた120名とした。調査項目は基本属性,キャリアと診断された際の経緯や思いに関する質問およびHRQOL測定のためのMOS Short-Form 36-Item Health Survey Ver.2(以下,SF-36)を用いた。得られた回答の度数分析はExcelを用いて集計し,HRQOL平均得点や変数間の比較においてはRを用いたt検定を実施した。
結果 有効回答53件のうち女性が84.9%,50代が35.8%を占めていた。キャリアであることを知ったきっかけは「献血後の通知」が最も多く47.2%,次いで「妊婦健診」が28.3%であった。その他の回答には,術前検査や,家族の関連疾患発症をきっかけに検査を勧奨された者も含まれていた。キャリア診断後は家族やパートナー,医療者に相談したとの回答が多い一方,18.9%は「誰にも相談できなかった」と回答していた。96.2%は医師に相談したいと回答しており,必要なHTLV-1関連情報は「専門的な知識」が最も多かった。HRQOL得点は,全体では男性より女性の方が低い傾向にあり,女性では50歳未満において全体的健康感(p<0.05),活力(p<0.01),こころの健康(p<0.05),精神的健康感(p<0.01)が50歳以上の女性および健康成人女性の国民標準値より有意に低かった。
結論 女性の回答者割合が多かったのは全国的な男女比に合致していた。回答者の大半が「医師」による「関連疾患の発症や治療に関する情報」を必要としていたのは,キャリアが相談窓口で期待する情報を入手できなかった経験や,一般診療では関わることのない臨床心理士の役割を知らないなどの可能性が考えられた。HRQOL得点で50歳未満の女性キャリアが50歳以上の女性および同年代における健康成人女性の国民標準値より有意に低かったのは,出産・子育て世代の女性特有のストレスに加え,キャリア診断後の支援体制が十分とは言えないことが不安材料となっている可能性が高いと考えられる。HTLV-1総合対策が推進するHTLV-1母子感染対策協議会の設置や研修,普及・啓発活動が行われていない都道府県も少なくないが,キャリアが少ない地域こそ徹底した母子感染・水平感染防止策を講じる必要があるといえ,抗体価検査後の確定検査を含む相談・支援体制の整備を図る必要があると考える。
キーワード ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1),ヒトT細胞白血病ウイルス1型感染者(キャリア),健康関連QOL(HRQOL),実態調査,HTLV-1総合対策,キャリア支援
|
第67巻第4号 2020年4月 学校・学区を単位とした子ども・子育て支援の実施状況-全国市町村調査結果を踏まえて-澁谷 昌史(シブヤ マサシ) |
目的 地域共生社会への関心が高まる一方,学校教育を目的として設置・設定される学校・学区を,学齢期の子どもと保護者の生活課題に取り組むためのプラットフォームとしていくことに関心がもたれるようになっている。しかし,そのための素地が実際にどの程度形成されているのかについては明らかにされていない。本研究では,この点についての実態把握を行い,学校・学区を単位とした子ども・子育て支援の課題について検討した。
方法 全国1,698市町村(政令市を除く)を対象に質問紙調査を実施した。調査期間は2018年12月中とした。学齢期の子どもと保護者を対象に含む19の子ども・子育て支援を取り上げ,それらの学校・学区単位での実施例の有無をたずねるとともに,実施必要性・実施可能性の有無,実施にあたっての障壁について回答を求め,自治体の規模別でクロス集計とχ2検定を行った。
結果 有効回収率は26.1%(443件)であった。「子どもの居場所の設置」はほとんどすべての自治体で「実施例あり」として回答された。障害児や要保護児童等への支援を学校・学区単位で行うことについては,「実施例あり」の回答割合が中程度以上みられた一方,ショートステイやトワイライトステイ,食事サービスのように,既存の学校教育機能の範疇にないと考えられやすいものは「実施例なし」の回答割合が大きかった。学校・学区を単位とした連携システムについては,幼稚園・保育所・小学校間での連携にかかるものを除くと,施策として明示的に発達させる対象とはなっていなかった。
結論 学校のプラットフォーム化はまだ普及しておらず,学校数減少という課題に直面している自治体が少なくないこともあって,今後も急速にその方向へと動いていく状況にはない。ただし,国が予算措置を含むリーダーシップを発揮することが施策の推進に大きく関与するものと推測された。また,学校・学区単位で支援を実施するだけでなく,支援者同士が連携を図るシステムができるように市町村で計画的な施策の推進を行う必要がある。
キーワード 地域共生社会,学校プラットフォーム,子ども・子育て支援,市町村
|
第67巻第4号 2020年4月 各市町村における病児対応型保育定員と一般保育所在所者数,
江原 朗(エハラ アキラ) |
目的 乳幼児は月に平均2回程度医療機関を受診しているが,軽微な急性疾患に罹患した子どもの登園を保育所は原則認めていない。病児対応型保育施設が整備されつつあるが,地方間の偏在が認められる。そこで,市町村の病児対応型保育定員の地方間格差を人口,医療資源,財政的な側面から説明する。
方法 重回帰分析(線形回帰)により,各市町村における病児対応型保育定員を,一般保育所在所者数,小児科医師数,実質単年度収支および市町村の所在する地方,市町村の人口規模のダミー変数により説明する回帰式を計算した。
結果 重回帰における調整済み決定係数(R2)は,0.684(P<0.001)であり,各市町村の病児対応型保育定員の68.4%を今回の解析で説明することができた。各市町村の病児対応型保育定員は,一般保育所在所者千人あたり1.806人,小児科医師数1人あたり0.071人,市町村の実質単年度収支10億円あたり0.735人増加した(ともにP<0.001)。また,関東地方の市町村に比べて,他の地方の市町村では保育定員が多く,その差の最高値は中国地方の2.656人であった(中部,中国,四国,九州・沖縄では差が0である確率はP<0.05)。一方,人口規模20~30万人の市町村に比べて,政令指定都市では定員が2.920人少なかった(P=0.020)。また,各説明変数の影響の大きさを比較するために,平均0標準偏差1にそろえた標準偏回帰係数を求めると,その絶対値は,(一般保育所在所者数)>(小児科医師数)>(実質単年度収支)>(地方による加算定数のうち正の最高値,中国地方)>(人口規模による加算定数のうち負の最低値,政令指定都市)の順であった。
結論 病児対応型保育定員の全国格差は,養育環境その他の地域性よりも市町村における一般保育所在所者数,小児科医師数や財政収支といった構造的な問題によるところが大きく,全国であまねく病児対応型保育を普及するには,病児保育事業を実施する主体を市町村から都道府県などの広い圏域に拡大することや財政の脆弱な市町村へのさらなる財政支援が必要であると思われた。
キーワード 病児保育,子育て支援,感染症,外来受療率,地方間格差
|
第67巻第4号 2020年4月 都市部高齢者における
田中 泉澄(タナカ イズミ) 北村 明彦(キタムラ アキヒコ) 横山 友里(ヨコヤマ ユリ) |
目的 高齢期の精神的な健康に寄与する要因の一つとして食品摂取に着目し,都市部の高齢者の精神的健康度と食品摂取多様性の関連について,経済的要因としての所得等を考慮して検討した。
方法 対象は,東京都大田区に在住し要介護認定を受けていない65歳以上の男女である。15,500名に自記式調査票を郵送し,回答を得た11,925名のうち,本研究の条件を満たす10,266名を解析対象とした。精神的健康度はWHO-5(日本語版)により,食品摂取多様性は10品目からなる食品摂取多様性スコア(DVS)によりそれぞれ評価した。DVSおよび所得と精神的健康度との関連は,目的変数を精神的健康度,説明変数を等価所得区分およびDVS区分とし,その他の関連因子を強制投入した二項ロジスティック回帰分析を用いた。
結果 低DVS群に比べて高DVS群では,精神的健康度が良好である多変量調整オッズ比(OR)は,男性で1.99(95%信頼区間:1.73-2.30),女性で1.73(1.52-1.96)であった。また,等価所得が最も低い群に比べて高い群では,精神的健康度「良好」の多変量調整オッズ比は,男性で2.27(1.95-2.64),女性で1.37(1.19-1.58)であった。DVSと等価所得を組み合わせた検討では,低所得・低DVS群を基準とすると,男性では低所得・高DVS群(OR 1.54),中所得・高DVS群(OR 1.83),高所得・高DVS群(OR 1.73)の精神的健康度「良好」の多変量調整オッズ比が有意に高値であった。女性では,中所得・高DVS群(OR 1.56),高所得・低DVS群(OR 1.47),高所得・高DVS群(OR 2.16)において,精神的健康度「良好」の多変量調整オッズ比が有意に高かった。
結論 都市部在住の高齢者において,DVSおよび等価所得は精神的健康度と有意に関連し,等価所得を考慮した上でもDVSが高い群では精神的健康度が良好であることが明らかとなった。本研究より,多様な食品を摂取することは精神的な健康と関連している要因の一つとなる可能性が示された。
キーワード 高齢者,食品摂取多様性,都市部,等価所得,精神的健康度
|
第67巻第3号 2020年3月 国際生活機能分類(ICF)の
|
目的 国際生活機能分類(ICF,以下,ICF)は健康状態を生活機能(「心身機能,身体構造」と「活動と参加」)であらわし,その規定要因として「環境因子」「個人因子」を考える統計分類である。またICFは「生活実現化モデル」として,様々な対象者に対し,「個人の生活状況」「生活を支えるための必要な支援」を記述することができるようになり,これにより国家統計(社会統計)として国別比較などのより広い分野での活用が期待されている。その一方で,国際障害者権利条約(CRPD,以下,CRPD)や,持続可能な開発目標(SDGs,以下,SDGs)における包摂性として,「障害者」「生活弱者」などの権利保全や対策効果の見える化としての社会統計が求められている。本研究の目的は,ICFの国の代表指標(社会統計)への活用に関し,CRPDの観点から諸外国(スイス,ドイツ)では,どのようにCRPDへ取り組んでいるのか,社会指標としてどのようにICFを活用しているのかについて明らかにし,今後の日本における「社会統計」への実装に関する検討を行うことである。
方法 第7回厚労省ICFシンポジウム(2019年1月)における,シンポジストおよびWHO-FIC総会(2018年10月)資料,ICF関連ポスターの紹介(501-527)計27研究より本研究に関連する発表(訪問先)を2題(スイスとドイツ)決定し,その発表者を訪問しヒアリングを行った。質問項目は,貴国ではどのようにCRPDに取り組んでいますか,社会指標としてどのようにICFを活用していますか等である。
結果 スイスではICFを用いた社会統計の実装は進んでいない。ドイツではCRPD履行のための法律整備および法律をもとにした行動計画が進んでいる。これはICFの概念に基づいているため,CRPD履行による統計整備がそのままICFに基づいた社会統計の実装につながると考えられる。
結論 ICFを国の代表指標(社会統計)として実装するためには,CRPDへの対応としての「法律整備」をICFの概念を用いて整理すること,すなわち「健康に関する生物心理社会的モデル」を用いることが重要となる。また他の指標と組み合わせて政策・介入効果を検証できるような仕組みを加えることで,この分野のエビデンスの飛躍的な創出が期待できる。そのためには,対象者を「障害者」のみならず「生活弱者」「福祉対象者」を含むようにより広く設定すること,およびICF概念の数量化のために,既存の統計調査をICFコンポーネントにより読み替える,あるいはICF一般セットやWHO障害調査スケジュール(WHO-DAS)2.0などの既存セットを活用する,または新たに数量化方法を開発するなど,具体的な方法が必要となる。
キーワード 社会統計,国際生活機能分類(ICF),国際障害者権利条約(CRPD),持続可能な開発目標(SDGs),WHO障害調査スケジュール(WHO-DAS2.0)
|
第67巻第3号 2020年3月 原死因確定作業についての実態・問題点の把握,
今井 健(イマイ タケシ) 明神 大也(ミョウジン トモヤ) 大井川 仁美(オオイガワ ヒトミ) |
目的 人口動態調査は国勢調査と並ぶ国の主要統計で公衆衛生施策の中心的資料である。本研究ではこの中で死亡票に着目し,わが国における原死因確定作業の実態と問題点を明らかにすること,また,正確・効率性向上に向けた機械学習の適用可能性と課題について調査・検討を行うことを目的とした。
方法 まず,文献と厚生労働省担当者へのヒアリングを通じて,わが国における原死因確定プロセスの概要ならびに現状のオートコーディングシステムと人手確認作業の実態について調査を行った。次に,検証用に作成したダミーの死亡診断書ならびに原死因確定作業データを対象とし,諸外国で広く用いられているオートコーディングシステムIrisを用いた原死因確定作業の検証を行った。また,これらのプロセス分析結果を元に,正確・効率性向上のための機械学習の適用可能性について検討を行った。
結果 現行のオートコーディングシステムはルールに基づいた処理であること,同システムでICD-10コードが完全付与できないケースや付帯情報が含まれている場合については人手での目視確認による原死因確定作業が行われ,月約10万件の死亡票データのうち,約4割を占めていることが判明した。また死亡票ダミーデータを用いた分析から,特に付帯情報は最終原死因コードの確定に大きく影響を及ぼし得ることが判明した。原死因確定作業のさらなる高精度化と効率化のための機械学習の適用については,①Ⅰ欄Ⅱ欄傷病名に対するICD-10コーディングや②ICD-10コードの組み合わせからの選択ルールに基づいた仮原死因確定作業については,機械学習の適用が困難,あるいはメリットが大きくない一方で,③付帯情報を考慮した最終的な原死因確定プロセスについては,機械学習適用のメリットが大きいことが判明した。また,機械学習の適用シナリオとしては,「プロセス全体に対する適用」と「プロセス分解による部分的適用」の2つが考えられたが,後者は前者に比べて大幅な精度向上が期待できると共に,付帯情報の影響に特化して学習できる点からより適していると考えられた。
結論 今後,わが国の原死因確定プロセスに対し,上記のシナリオに準じ機械学習を部分適用することによって,現状の月約4万件に及ぶ人手確認作業の大幅な効率化と高精度化が期待できると考えられた。
キーワード 人口動態調査,死亡票,原死因確定プロセス,ICD-10,機械学習
|
第67巻第3号 2020年3月 全国市区町村別にみた自宅死に占める外因死の割合谷口 雄大(タニグチ ユウタ) 渡邊 多永子(ワタナベ タエコ) 翠川 晴彦(ミドリカワ ハルヒコ)太刀川 弘和(タチカワ ヒロカズ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) |
目的 急速に高齢化が進むわが国では,地域包括ケアシステムの構築に向けて在宅医療体制の充実が求められている。その際に考慮すべき重要な課題の1つが看取りの場であるが,現状では国民の多くが自宅で最期を迎えることを希望しているにも関わらず,実際は大半が自宅ではなく病院で死亡している。一方,厚生労働省による「在宅医療にかかる地域別データ集」等の統計や多くの先行研究では,死亡場所が自宅であった死亡すべてを自宅死としてきた。しかし,この定義による自宅死の中には自宅での看取り以外に自殺や孤独死も含まれるため,すべてが望まれた自宅死ではない可能性がある。本研究では,自宅死に占める外因死の割合を全国の基礎自治体別ならびに都道府県別に明らかにし,在宅医療体制の指標として現行の自宅死を用いることの妥当性を検証した。
方法 厚生労働省より提供を受けた2014年人口動態調査死亡票を用いた。全国の基礎自治体における65歳以上の日本人の自宅死数ならびに自宅での外因死数を把握し,自宅死に占める外因死の割合を算出した。
結果 自宅死数が1名以上であった1,700市区町村について,自宅死に占める外因死の割合の中央値(四分位範囲)は6.25(1.99,10.6)%であった。また都道府県別にみた場合,最大値は13.5%(福岡県),最小値は3.66%(和歌山県)であり,自治体間のばらつきを認めた。
結論 在宅医療体制の指標として自宅死数を用いる際は,その中に自宅での看取り以外の死が一定数含まれること,その割合は自治体ごとに異なることに留意する必要がある。またより適切な在宅医療体制の指標として,自宅死全体から外因死を除いた値を用いることも検討すべきである。
キーワード 自宅死,在宅医療,地域包括ケアシステム,外因死,高齢者,指標
|
第67巻第3号 2020年3月 発達障害のある子どもを養育する家族のレジリエンス涌水 理恵(ワキミズ リエ) |
目的 養育レジリエンスとは,「発達障害のある子どもの養育が困難であるにもかかわらず,親が良好に養育に適応していることを表す特徴やその過程」を指す。家族の養育レジリエンスは,当該児と家族を外来や地域コミュニティで継続的にケアしていくための家族看護における主要アウトカムである。今回は,当該家族を対象に,家族の養育レジリエンスの実態を把握し,その関連要因を探索することを目的とした。
方法 2017年4月に,当該家族に対し,web上で無記名自記式質問紙調査を実施した。質問項目は,回答者の属性・子どもの属性・養育に関連したサービスの利用・家族の養育レジリエンスであった。家族の養育レジリエンスは,①子どもの特徴に関する知識,②社会的支援,③育児への肯定的な捉え方,の3要素で構成されるParenting Resilience Elements Questionnaire(PREQ)日本語版を用いて評価した。
結果 315名の子どもを育てる281名の親が調査に参加した。調査時の当該児年齢は平均11.3±5.1歳,診断時年齢は平均6.3±4.2歳であった。いずれのサービスも利用していない子どもが約4割を占め,利用割合が多かったのは児童デイサービスで約3割だった。現在利用しているサービスを今後も継続することを希望する親が多い一方で,新規サービスについては約8割が親向け子育てプログラムを希望していた。PREQ総得点は平均78.7±12.7点であり,ホームヘルプサービスを利用していること(p=0.042),その他のサービスを利用していること(p<0.001),きょうだいがいないこと(p=0.023),当該児の養育について頼れる家族外のサポーターがいること(p=0.049)が高いPREQ総得点に関連していた。
結論 本研究により,発達障害のある子どもの属性やライフステージに応じたサービスの利用実態や家族のニーズ,養育レジリエンスの実態が示された。今後は発達障害のある子どもと家族が必要とするサービスのアドボカシーを進めると同時に,家族の養育レジリエンスを高める具体的な支援の方策を検討する。
キーワード 家族看護,サービス,発達障害,養育レジリエンス
|
第67巻第3号 2020年3月 レセプトデータからみた認知症の地域差-新潟県の全後期高齢者による検討-田代 敦志(タシロ アツシ) 菖蒲川 由郷(ショウブガワ ユウゴウ) 齋藤 玲子(サイトウ レイコ) |
目的 住民の高齢化に伴い増加が予想される認知症患者について,新潟県の全後期高齢者のレセプトデータより市町村別の男女別入院割合や住民当たりの入院医療費の地域差を明らかにし,将来的に認知症に伴う入院医療費がどのように変化するか検証することを目的とした。
方法 新潟県後期高齢者医療広域連合が保有し,外部委託機関で匿名化処理された2012年から5年間の医科レセプトデータを元に,市町村別の認知症入院割合(住民全体に対して認知症で入院した者の割合)と住民当たりの認知症入院医療費(認知症による入院総医療費を住民数で除したもの)について地理情報システム(GIS)を用いて可視化し,認知症の入院割合と住民当たりの認知症入院医療費の関連についてピアソンの相関係数を求めた。認知症に関連する入院医療費推計は,国立社会保障・人口問題研究所の市町村別人口構成の将来予測を参考に医療圏単位の人口構成の変化を年齢階層別に再構成し,2015年の世代別の住民当たり認知症医療費が一定という仮定の下で2040年までの予測を行った。
結果 認知症の入院割合は男性で3.5%~6.1%,女性で3.2%~6.7%(2012~2016年の5年間の平均値)と自治体によって大きく異なっていた。認知症の住民当たりの入院医療費は,男性で4.5万円~10.1万円,女性で3.9万円~11.4万円(2012~2016年の5年間の平均値)であり,入院割合と同様に地域差が大きかった。入院割合と住民当たりの入院医療費の相関は,男性でr=0.76(P<0.001),女性でr=0.78(P<0.001)の相関を認めた。医療圏別の認知症の入院医療費は,新潟市を除いて2040年までにピークに達し,人口減少が大きい佐渡医療圏では減少に転じると予測された。
結論 新潟県において認知症による入院割合や住民当たりの入院医療費は,自治体により大きく異なり2倍以上の地域差を認めた。認知症の入院医療費は人口減少により2040年までに都市部を除いてピークに達することから,今後は人口が集中する地域において介護分野を含めた認知症対策の重要性が増すことが予想される。
キーワード 認知症,入院割合,入院医療費,データヘルス,地域差
|
第67巻第2号 2020年2月 認知症の人の家族介護者(主たる介護者)に対する
菅沼 一平(スガヌマ イッペイ) 南 征吾(ミナミ セイゴ) |
目的 本研究の目的は,認知症の人の家族介護者(主たる介護者)のエンパワーメントを測定するための評価尺度(Empowerment Assessment Scale for Principal Family Caregivers of Persons with Dementia:EASFCD)を開発し,その尺度の妥当性および信頼性を検証することである。
方法 調査対象者は,吹田市,豊中市,京都市,加古川市,北九州市,伊万里市における介護事業所等のサービス利用者の家族介護者(主たる介護者)190名である。調査票については,調査協力に同意した家族介護者に手渡し等で配布を行い,郵送あるいは手渡しでの回収(無記名)を行った。その結果,117部を回収(回収率61.6%)した。尺度の基本的な構成概念の確定のために探索的因子分析を行い,併存的妥当性の検証のために,基準となる標準尺度を用いて相関分析を行った。また,尺度の信頼性の検証を行うために,Cronbachのα信頼性係数を用いた信頼性分析を行った。
結果 45項目のEASFCD試作版は,因子分析の結果,6因子33項目となった。その因子は,因子1(介護への否定的感情),因子2(介護の知識・技術に関する自己効力感),因子3(介護に対する意識・結果・期待),因子4(介護への肯定的感情),因子5(被介護者との関係性),因子6(相談相手の有無と情動的サポート)であり,累積寄与率は57.1%であった。また,基準となる尺度との相関については,中程度(0.3~0.4程度)の負の有意な相関がみられた。因子ごとのCronbachのα信頼性係数は,相談相手の有無と情動的サポート以外は,おおむね0.7以上であった。これらのことから,尺度の構成概念について,基本的な構成概念は検証されたと考える。尺度の基準関連妥当性については,基準となる尺度との関連性がみられたため,基準関連妥当性があると判断でき,因子ごとのCronbachのα信頼性係数も,ある程度の高い数値を示しているため,尺度の内的一貫性(信頼性)があると判断できた。
結論 本研究で開発された尺度(EASFCD)の構成概念については,一部の変更があったが,基本的な構成概念については検証されたと考えられる。また,基準関連妥当性や内的一貫性(信頼性)については検証され,本尺度は,妥当性および信頼性を有する尺度であると言える。
キーワード 認知症の人,家族主介護者,エンパワーメント,尺度開発
|
第67巻第2号 2020年2月 墓数の推計と今後の予測モデルの確立に関する検討久保 慎一郎(クボ シンイチロウ) 西岡 祐一(ニシオカ ユウイチ)野田 龍也(ノダ タツヤ) 今村 知明(イマムラ トモアキ) |
目的 墓は年間約130万人が死亡している中で,今後その需要が増大すると考えられている。しかし,墓制を見直す動きもある中,日本は少子高齢化が進み,人口は減少傾向にある。そのため現在は墓が増加しているが,将来は一転して人口減少により墓数の大幅な減少(未継承墓の増大)が見込まれる。よって,日本は未継承墓(無縁仏)が乱立する危機的な状況に陥る可能性がある。これは大きな社会問題となり得るが,正確な将来推計がないため問題提起されているとは言い難い。この推計は一見すると簡単だが,日本の複雑な墓の継承制度を考慮すると,男系の継承の複雑さや死亡・未婚で未継承となるため,きわめて困難な推計となる。本研究では,人口の推移と死亡率等より過去から将来にわたる墓数の推移について推計し,墓地行政への基準となる算定方法を確立することとした。さらに,墓制は文化や家族の在り方・心情などが影響することを含め,今後の墓制の在り方を検討する。
方法 墓数の推計モデルとして1960年(昭和35年)を起点とし,世代間は30年を想定し,基準となる第一世代の墓の数(その世代の長男の数)を100万基とし,継承のプロセスを経ることによってその推移を推計した。80年で1世代が終了すると仮定し,その後の5世代を経て2160年には,「継承墓」「新規墓」「未継承墓(無縁仏)」の3種類で墓数が何基になるか推計した。4世代以降の推計は3世代と同様の発生確率であったと仮定して,どのように推移するかを5世代目まで算出した。継承には様々な確率や誘因を伴うため,各種統計調査より未婚・死亡・男子の生まれる比率を確率化し,その世代ごとに何%継承するかを算出した。これらを基に墓数を集計し,簡易的な計算方法として合計特殊出生率を用いた墓数の推計と比較した。その結果をもとに今後の方策を政策提言し,未継承を低減させる方法を提唱した。
結果 合計特殊出生率を用いて単純に墓数を算出した際は,1世代目の時点で5%ほど墓数は減少し,3世代を経ることで半分以下となることがわかった。出生比率から計算した墓数の推計によって,墓数は3世代を経ることでほぼ2倍,5世代を経ることで2.6倍になることがわかる。また,既存の墓で継承する墓数は合計特殊出生率を用いた計算法方法とほぼ一致した。ただし,一方で未継承墓(無縁仏)は年々増加し,5世代を経ることで急激に増加することがわかった。今後の墓政としては,継承の在り方を変える,現在の形式にとらわれない様々な埋葬を行う,墓地のルールを変えるなどの方策が考えられる。
結論 今後日本では,墓数は増大するが,継承できる墓数は減少し,墓地には無縁仏があふれる状況がわかった。ただし,これは単純集計に基づいたものであり,今後の出生率や死亡率の変化によっては大きく数値が変わる可能性がある。従って,この数値が重要なのではなく,この数値をもとに今後の墓政の見直しを日本全体で見直すことが一番重要であるといえよう。
キーワード 墓数,未継承墓,新規墓,無縁仏,墓制
|
第67巻第2号 2020年2月 市町村長申立事案を担う市民後見人の
|
目的 市民後見人の選任が進まない現状を踏まえ,市民後見事業のモデルとなっている地域で活動する市民後見人に焦点をあて,市民後見人と被後見人の現況,後見事務実施状況,関連機関との連携経験と内容を分析することで,市民後見人の必要性と期待される後見事務を明らかにし,支援課題を検討した。
方法 2016年12月~2017年3月に,Z県10カ所の成年後見実施機関(以下,実施機関)を後見監督人とする個人受任の市民後見人142名に対して質問紙調査を実施し,市民後見人の基本属性と「市民後見人の定義」,被後見人の概要と受任調整時に用いられる「市民後見人選任基準」とを比較した。後見事務の実施状況は,契約を伴う法律行為と日常生活を支援する行為は頻度,非日常性の対応は経験の有無と内容,また,関連機関との連携経験と内容の回答を求めた。
結果 市民後見人は「国家資格等を所有」「受任経験がある」「実施機関の支援・監督下にある」点で最高裁判所の定義を超え,また,選任基準を超えた在宅生活者の被後見人への後見活動が確認された。後見事務実施状況では,受任ケースは純粋に財産管理のみの後見事務は極めて少なく,大部分は医療,福祉,介護サービスの受給を含む日常の契約行為や生活支援が多くなされていた。一方で「ケア会議への出席」は,「活動なし」が全体の1/4程度みられた。「緊急入院」等の非日常性の対応経験がみられた。市民後見人が連携した関連機関は,実施機関に集中しており,連携内容では「ケースの相談」「専門的助言」が多く行われていた。
結論 市町村長申立案件,低報酬等から,市区町村が市民後見人を公共的な後見人として活用している現状が認められた。これらの実績を他の第三者後見人との違いとして成年後見制度の利用支援システムにおいても明確にする必要がある。今後期待される後見事務は,施設ケアのプラン作成に関わるスタッフと意見交換するケア会議に,市民後見人が被後見人と共に参加することが望まれる。支援課題の検討では,非日常性の対応において実施機関担当者が適宜,市民後見人の活動報告書に対するフィードバックを行うことで,市民後見人自身の判断の振り返り,支援関係者との連携に役立つ基礎資料となる。一方で,実施機関は相談支援の要として関連機関との連携・調整といった役割が一層期待されており,市民後見人の選任促進のためには,実施機関の人員確保が課題である。
キーワード 成年後見制度,市民後見人,市町村長申立,成年後見実施機関,成年後見制度利用促進基本計画
|
第67巻第2号 2020年2月 日本における40代から70代の性別,年代別
井本 知江(イモト チエ) 中井 あい(ナカイ アイ) |
目的 日本における40代から70代の性別,年代別健康増進ライフスタイル,ヘルスリテラシーの評価値を明らかにし,健康増進ライフスタイル,ヘルスリテラシーに関わる今後の研究の基礎資料を提供する。
方法 対象者は40~79歳の男女1,197名とし,調査は郵送による無記名の自記式質問紙法で行った。健康増進ライフスタイルの把握には日本語版健康増進ライフスタイルプロフィール(以下,HPLPⅡ)を,ヘルスリテラシー(以下,HL)の把握には14-item Health Literacy Scaleを用いた。性別にHPLPⅡ,HLの合計得点と下位尺度の得点の平均値をt検定で比較した。さらに,年代別にHPLPⅡ,HLの合計得点と下位尺度の得点の平均値を一元配置分散分析で比較し,有意差があった項目はTukeyまたはGames-Howellで差の検定を行った。加えて,年代による変化傾向をみるためTrend検定を行った。
結果 有効回答率は男性37.6%,女性41.9%であった。HPLPⅡの合計得点の平均値は,男性2.53±0.38(平均±標準偏差)点,女性2.69±0.35点であった。合計得点と下位尺度の平均値はいずれも男性が女性を下回り,合計得点,健康の意識,人間関係,栄養,ストレス管理において有意差があった。また,男性,女性とも年代が上がるにつれて合計得点の平均値が有意に高くなる傾向にあった。性別HLの合計得点の平均値は,男性51.65±8.52点,女性55.61±8.04点であった。合計得点と下位尺度の平均値はいずれも男性が女性を下回り,合計得点,相互作用的HL,批判的HLにおいて有意差があった。また,男性,女性とも年代が上がるにつれて合計得点の平均値が有意に低くなる傾向にあった。
結論 HPLPⅡの合計得点,健康の意識,人間関係,栄養,ストレス管理の平均値は男性が女性に比べて有意に低く,男女とも年代が上がると合計得点の平均値は有意に高くなった。性別HLの合計得点,相互作用的HL,批判的HLの平均値は男性が女性に比べて有意に低く,男女とも年代が上がると合計得点の平均値は有意に低くなった。
キーワード 健康増進ライフスタイル,ヘルスリテラシー,性別,年代別
|
第67巻第2号 2020年2月 在宅での看取りに関連する住民の認識-在宅死が多い地域を対象とした分析を通して-末田 千恵(スエダ チエ) |
目的 在宅死が多い地域住民の在宅療養や在宅看取りおよび地域特性に対する認識から,在宅での看取りに関連する要因を明らかにすることを目的とした。
方法 平成29年11月~平成30年1月に,横須賀市の市民活動サポートセンターが主催する地域活動に参加している住民700名を対象に,無記名自記式質問紙調査を実施した。調査項目は,基本属性や在宅看取りの経験や在宅療養や地域特性に関する認識40項目であった。分析方法は,探索的因子分析により,在宅での看取りに関連する要因を検討した。
結果 調査対象者は349名(有効回答率49.9%)で,基本属性は女性が226名(64.8%)で,年齢は65歳以上の高齢者が245名(70.4%)を占めていた。また200名(59.3%)が家族・友人知人・近所のいずれかに在宅看取りをした人がいると回答した。因子分析の結果,在宅死に影響を与えている要因として30項目から8因子が抽出された(累積寄与率51.2%,全体のCronbachのα係数0.90)。抽出された因子は『安心できる療養体制(医療・看護・介護)』『家族の結びつき』『地元への愛着』『地域とのつながり』『死への畏敬と受容』『在宅療養への行政の支援』『療養する場への安心感』『在宅療養に必要な知識』であった。
結論 各自治体で在宅での看取りを促進していくためには,医療・看護・福祉のフォーマルな社会資源の充実,住民への在宅療養に関する知識の普及啓発により在宅療養に安心感をもてるようにすること,地域において住民同士が助け合えるようなインフォーマルな地域の介護力を醸成し,これからも住み続けたいという地域への愛着を感じられるような方略が重要である。
キーワード 在宅死,看取り,地域,住民,在宅療養
|
第67巻第2号 2020年2月 無料低額診療事業の利用者の特性に関する研究-無料低額診療の実態と効果に関するコホート研究より-西岡 大輔(ニシオカ ダイスケ) 玉木 千里(タマキ チサト) 古板 規子(フルイタ ノリコ)中川 洋寿(ナカガワ ヒロカズ) 佐々木 恵林(ササキ エリン) 長谷川 美智子(ハセガワ ミチコ) 植松 理香(ウエマツ リカ) 近藤 尚己(コンドウ ナオキ) |
目的 医療アクセスの格差は世界的に観察されている。日本でも所得が低い人ほど受診抑制を経験するなど,経済状況による医療アクセスの格差が知られている。無料低額診療事業は「生計困難者が経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないように無料又は低額な料金で診療を行う事業」として社会福祉法に規定されており,医療アクセス格差の是正に寄与している可能性があるが,実際の運用状況や利用者の特性等についてはほとんど明らかになっておらず,意義や効果を疑問視する政策議論もある。そこで本研究では,同制度の利用者の特性を分析することを目的とした。
方法 進行中の「無料低額診療の実態と効果に関するコホート研究」の2018年7月1日から12月31日までのデータを用いた。同研究は京都府の3つの医療機関で無料低額診療事業を適用した成人患者のうち,研究に対して同意を得た者を対象としている。適用を審査する際に用いた面談データ,および生活歴等を聴取する質問紙と健康関連QOL(SF-8)の調査データを用いて,利用者の背景要因を集計・記述した。
結果 対象者は80人で,平均年齢は68.3歳であった。40人(50.0%)が男性で,42人(52.5%)が独居であった。生活保護制度の支給基準額周辺の世帯所得の人が多く,無収入のものもいた。41人(51.3%)は友人知人に会う機会が月1回もなく,過去1年間に経済的な理由で受診を控えたことがある者は23人(28.8%)であった。傷病の罹患については,「糖尿病」が17人(21.3%),「脂質異常症」が20人(25.0%),「高血圧症」が26人(32.5%),「悪性腫瘍」が18人(22.5%)であった。利用者のSF-8のサマリースコア(偏差値)の中央値は,身体的スコアが37.4で,精神的スコアが41.9であった。
結論 無料低額診療事業の利用者は,実際の疾病の罹患に加え,一般集団に比べて健康関連QOL尺度のスコアが低く,無就労や友人知人との交流が少ないなど,心理社会的な課題を有している可能性が示唆された。同事業の利用をきっかけとして,経済的な支援に加えて,地域での社会的包摂につながるような制度設計が望ましい。今後は全国的なデータにより本研究同様に利用者や医療機関の特性,無料低額診療事業が及ぼす健康と健康格差への効果,および経済的影響を明らかにすることが求められる。
キーワード 無料低額診療事業,無低診,社会福祉,健康の社会的決定要因,健康格差,社会的処方
|
第67巻第1号 2020年1月 里親委託等を推進するための指標の在り方に関する考察平林 浩一(ヒラバヤシ ヒロカズ) |
目的 社会的養護を必要とする児童の養育について,平成28年の児童福祉法改正では,原則として里親や養子縁組といった家庭養護を優先して推進することとした。しかし,里親委託等の推進に係る現行指標である「里親等委託率」の定義(算出方法)には課題があり,養子縁組の成立が里親等委託率を低下させる要因となっている。本研究では,各都道府県の乳児院・児童養護施設の定員と里親委託等の状況を比較・分析し,その上で,特別養子縁組等に係る児童福祉法改正や民法改正の方向性を踏まえながら,里親委託等を推進するための指標(数値目標)の在り方について考察した。
方法 平成28年度「福祉行政報告例」のうち,乳児院・児童養護施設の定員・入所児童数,里親・ファミリーホームに委託されている児童数,里親数の統計データを用いて里親委託等の状況の比較・分析を行った。次に,各年度の「福祉行政報告例」のうち,里親委託解除理由の統計データにより,里親委託解除から養子縁組となった児童の状況等をみるとともに,現行指標の定義を見直し,里親委託等と養子縁組の両制度の成果を一つの指標とした場合について試算を行った。
結果 都道府県別の「乳児院・児童養護施設定員の要保護児童数に対する割合」と「里親等委託率」との相関をみると,施設定員が要保護児童数に比べて多い都道府県ほど,里親等委託率は低くなる傾向にある。また,指標の定義を見直し,現行の里親等委託率を構成する数値に,養子縁組成立により里親委託解除となった児童数を加え,里親委託等と養子縁組の両制度の成果を一つの指標とした場合,成果値は25.1%となり,現行(里親等委託率18.3%)よりも6.8ポイントの増加となった。
結論 現行指標の定義では,里親委託等と養子縁組との間に相殺関係が生じており,両制度を推進するとした国の方向性と齟齬がある。試算の結果,現行指標では成果値も過少となる。現行指標のままでは,例えば,妊娠中から児童相談所が相談に対応し,特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託を行うなどの,地方公共団体の先進的取組の成果も十分に反映できないだろう。令和元年の民法改正により特別養子縁組の対象年齢が拡大となったが,これにより,今後さらに相殺の影響も拡大するだろう。このため,家庭養護優先の考え方を徹底し,現行指標の定義を改正して,里親委託等と養子縁組の両制度の成果を表す指標を採用すべきであろう。
キーワード 里親委託,養子縁組,特別養子縁組,家庭養護,指標,里親等委託率
|
第67巻第1号 2020年1月 障害者支援施設の生活支援員の不適切なケアの実態と関連要因岡本 健介(オカモト ケンスケ) 時實 亮(トキザネ リョウ) 谷口 敏代(タニグチ トシヨ) |
目的 障害者支援施設で発生する虐待の背景要因には風通しの悪い組織風土や職員相互の指摘ができない人間関係が指摘されており,不適切なケアから虐待へと移行する可能性がある。不適切なケアの予防には職員自身のストレスのない活気ある働き方や風通しの良い組織風土は重要である。本研究は不適切なケアの実態把握と,職員の活気ある働きと組織の特性との関連を明らかにすることを目的とする。
方法 中国地方5県の障害者支援施設217施設の生活支援員を対象とし,1施設6名分郵送した。調査内容は,個人特性,不適切なケア尺度,日本語版組織的公正尺度,職業性ストレス簡易調査票の職場の支援尺度,日本語版ワーク・エンゲイジメント短縮版尺度を使用した。分析方法は,本研究で用いた変数の度数と割合を不適切なケアの「あり群」と「なし群」別に算出し,割合の比較にはχ2検定を行った。不適切ケアの下位尺度のうち,「あり群」が30%以上を示した項目を従属変数とし,組織風土,職場の支援,ワーク・エンゲイジメントの各変数を独立変数としたロジスティック回帰分析を行った。
結果 未記入などの欠損データを除いた616名(有効回答率47.8%)を分析対象とした。不適切なケアの下位尺度のうち,あり群は「不当な言葉遣い」が42.7%,「施設・職員の都合を優先した行為」が38.3%,「プライバシーに関わる行為」が5.4%,「職員の怠慢」が5.0%,「自己決定侵害」が3.2%であった。「不当な言葉遣い」と「施設・職員の都合を優先した行為」の有無では,それぞれ,「手続き的公正が高い群」を基準としたとき,中群と低群では「あり群」が有意に高かった。
結論 情報提供や意見聴取などの行動および組織内の意思決定への参加などの手続きに関する組織特性が高いことが不適切なケアの発生を防ぐ可能性が示唆された。しかし,風通しの良い組織風土は生活支援員の独自の努力で改善することには限界がある。障害者支援施設の管理者は,上司,部下間との信頼関係の形成や支援に必要な情報の共有や協力体制を整備し,組織として不適切なケアの防止に取り組むことが求められる。
キーワード 生活支援員,不適切なケア,組織の公正,職場の環境整備,障害者支援施設
|
第67巻第1号 2020年1月 妊娠の種類別にみた多胎出生の特徴大木 秀一(オオキ シュウイチ) |
目的 国内で入手可能なデータを基に,過去10年間における妊娠の種類別多胎出生の動向について詳細に分析した。
方法 厚生労働省が公表している人口動態統計と日本産科婦人科学会(日産婦)が公表しているARTデータブック(ART:生殖補助医療)を分析に用いた。目的にかなった年齢階級別データが入手できる2007年から2016年の値を分析(推定)に用いた。
総多胎出生数=自然妊娠多胎出生数+不妊治療妊娠多胎出生数=自然妊娠多胎出生数+(一般不妊治療妊娠多胎出生数+ART妊娠多胎出生数)より 一般不妊治療妊娠多胎出生数=総多胎出生数-ART妊娠多胎出生数-自然妊娠多胎出生数 となる。自然妊娠多胎出生数の推定に当たっては,自然の多胎出生数は30歳代後半までは母親の年齢(階級)とともに上昇し,40歳以降で急減するという生物学的現象を用いた。1970年代は不妊治療の影響が非常に少ないと考えられるので,1974年から1978年までの多胎妊娠を自然妊娠とみなし,この5年間の加重平均を年齢階級別自然妊娠多胎出生割合の基準値とした。ART治療中の自然妊娠はないとみなし,あらかじめこれを除き,年ごとに(総出生数-ART出生数)×年齢階級別多胎出生割合 により年齢階級別自然妊娠多胎出生数を推定した。日産婦が公表しているARTデータブックの数値を基に,2007年から2016年(最新)までのARTによる年齢階級別総出生数と総多胎出生数の推定を行った。
結果 全体的な傾向は以下のとおりであった。①自然妊娠の割合は,不妊治療妊娠の割合よりも多く,2011年に最も高かった。②不妊治療妊娠では,一貫して一般不妊治療妊娠の割合がART妊娠の割合を上回っていた。年齢階級別にみると,35歳以上に関しては,2007年を除いて自然妊娠が最多であるが,その割合は現在横ばいであり,不妊治療ではART妊娠が一般不妊治療妊娠を上回るとともに,2011年以降上昇傾向にあった。
結論 不妊治療による多胎出生割合はピークを過ぎたとはいえ,今なお多胎出生全体の半数近くに迫っており重要な課題である。特に,35歳以上のARTによる妊娠の増加傾向が注目された。正確な疫学的な記述を求めるのであればARTだけではなく一般不妊治療の登録も必須であると思われた。
キーワード 多胎出生,自然妊娠,不妊治療妊娠,一般不妊治療妊娠,生殖補助医療,人口動態統計
|
第67巻第1号 2020年1月 NSAIDs貼付剤の処方状況に関する調査-後発医薬品の使用促進と処方制限の視点から-田中 博之(タナカ ヒロユキ) 石井 敏浩(イシイ トシヒロ) |
目的 日本において,非ステロイド性抗炎症薬(non-steroidal anti-inflammatory drugs:NSAIDs)貼付剤は広く使用されているが,過去のNSAIDs貼付剤の処方状況を調査した報告では,後発医薬品の処方割合が極端に低いことや処方量の地域差などが指摘されている。また,2016年4月の診療報酬改定では,医療資源の効率化や医薬品の適正使用のために外来患者に対する貼付剤の処方が70枚/回に制限された。そこで,本論文では,近年の日本における医療費削減に関する施策である後発医薬品の使用促進や処方制限がNSAIDs貼付剤の処方量に与える影響を検討するとともに,処方量に関連し得る因子を明らかにすることを目的とした。
方法 厚生労働省ホームページで公開されている第2回,第3回レセプト情報・特定健診等情報データベースオープンデータの「薬剤」データより,NSAIDs貼付剤の処方量を調査した。また,得られたデータを処方区分別(「外来(院内)」「外来(院外)」「入院」),薬剤別,先発医薬品-後発医薬品別,年齢群別(非高齢者:0~64歳,高齢者:65歳以上),性別,都道府県別に再集計し,解析を行った。
結果 NSAIDs貼付剤の処方量は2015年度から2016年度の間に5.8億枚以上減少していることが明らかとなり,薬価ベースでの削減額は約273億円であると試算された。薬剤別の処方量は,両年度ともにケトプロフェンが最も多く,次いでロキソプロフェンであった。2016年度におけるNSAIDs貼付剤全体の後発医薬品処方割合は,2015年度と比較して5.9ポイント増加しており,特にロキソプロフェン貼付剤では29.1%から38.2%まで上昇した。年齢群別,性別の検討からは,高齢者および女性でNSAIDs貼付剤を多く使用している状況が明らかとなった。処方量の減少率は,年齢群間には差がみられず(高齢者:△12.3%,非高齢者:△11.7%),性別間では女性で△12.9%,男性で△10.6%と女性で大きくなる傾向がみられた。2016年度には,すべての都道府県で処方量の減少がみられ,また,その地域の高齢化率と処方量との間には正の相関がみられた。
結論 本研究によりNSAIDs貼付剤の処方状況が明らかとなり,近年の日本における医療費削減に関する施策である後発医薬品の使用促進や処方制限の効果が明確になった。また処方量に関連し得る因子として,性別や地域の高齢化率が示唆された。
キーワード 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs),貼付剤,処方量,後発医薬品,処方制限
|
第67巻第1号 2020年1月 大都市居住傘寿者のコホート調査-追跡対象者の特性と4年6カ月後の生命予後および介護・医療サービスの利用状況-長田 斎(オサダ ヒトシ) 古谷野 亘(コヤノ ワタル) 安藤 雄一(アンドウ ユウイチ)澤岡 詩野(サワオカ シノ) 甲斐 一郎(カイ イチロウ) |
目的 東京都杉並区は80歳の高齢者を対象に5年間のコホート調査を行う健康長寿モニター事業を実施した。本論文の目的は,基礎自治体が自ら企画・実施した後期高齢者対象のコホート調査の概要と結果の一部を示し,その意義について考察することである。
方法 2012年9月に杉並区が対象年齢の区民全員(3,749名)に郵送した質問紙調査に回答し,杉並区および東京都後期高齢者医療広域連合が所管する個人情報の利用に同意した1,846名を追跡対象者,無回答または不同意の者のうち9月中の死亡者を除く1,888名を非追跡対象者とした。追跡期間は2012年10月から2017年3月までの4年6カ月であった。住民基本台帳,介護保険情報,その他の区が所管する情報のほか,医療保険に関する情報を広域連合から提供を受けて追跡調査項目とし,追跡対象者の特性および調査期間中の生命予後,介護・医療サービスの利用状況の分析に供した。調査期間中の介護・医療サービスについては,月平均介護サービス点数および月平均医療費とその内訳を指標とした。
結果 追跡対象者は2012年10月時点の対象年齢集団全体の約半数(49.4%)だが,非追跡対象者に比較して男女とも介護保険料区分が低位である者が少なく,要支援・要介護認定者率,1人あたり介護サービス点数,1人あたり医療費が低かった。特に重度認定者率,入所・居住系サービスの利用点数,入院医療費において差が顕著に認められた。追跡対象者においては,調査期間中の死亡率は男性17.7%,女性8.7%,要支援・要介護認定率は男性43.6%,女性52.3%であった。月平均介護サービス点数はすべての指標において女性の方が高かった。月平均医療費は最大値を除く各指標で男性の方が女性より高かった。調査期間中の死亡による影響は介護サービス点数よりも医療費に強く現れていた。
考察 追跡対象者は対象年齢集団の中では比較的社会経済状態が良好で,より健康度の高い集団であった。自治体が実施主体となった調査では,選択バイアスを量的に把握できること,自治体独自の情報も付加して,生活保護受給者を含め漏れなくデータ収集が可能であることなどの特長が認められた。
キーワード 大都市,後期高齢者,コホート調査,生命予後,介護サービス点数,医療費
|
第66巻第15号 2019年12月 農林業への関わりと高齢者の健康との関連性についての分析廣松 正也(ヒロマツ マサヤ) 和田 有理(ワダ ユリ)服部 真治(ハットリ シンジ) 市田 行信(イチダ ユキノブ) |
目的 介護予防の観点から,農林業への関わりと高齢者の主観的健康感との関連性を調べることを目的とした。
方法 鳥取県智頭町において2017年7月に行われた介護予防・日常生活圏域ニーズ調査をもとに,要介護状態でない高齢者2,452人に対し自記式調査票を用いて郵送調査を行った。年齢と性別に欠損値の無い有効回答は1,358票(55.4%)で,このうち,目的変数である主観的健康観の欠損が無い1,307票(53.3%)を対象として分析を行った。目的変数は主観的健康感とし,説明変数は,「何らかの作物を育てているか」「山仕事をしているか」「農林業をいつからしているか」「農林業の頻度はどのくらいか」の4つの指標をそれぞれ用いた。統計的分析には,年齢,性別,経済状況を調整因子として多重ロジスティック回帰モデルを用いた。
結果 年齢,性別,経済状況について調整した上で主観的健康感と農林業への関わりの関連性を見たところ,農林業に関わりがある人ほど主観的健康感が良い傾向にあることがわかった。また,何らかの農林業を行っている人と行っていない人との間で,要介護リスクのうち,「運動機能低下者割合」「1年間の転倒あり割合」「閉じこもり者割合」「うつ割合」の計4指標について比較を行ったところ,農林業に関わっている人の方が関わっていない人よりも該当者が少ないという傾向がみられた。
結論 本研究で,農林業に関わることは,主観的健康感の良さに関連することを明らかにした。
キーワード 主観的健康感,農業,林業,要介護リスク,高齢者
|
第66巻第15号 2019年12月 就労継続支援事業所に通所する精神障がい者における
中井 寿雄(ナカイ ヒサオ) 板谷 智也(イタタニ トモヤ) |
目的 就労継続支援事業所に通所する精神障がい者の,災害時の症状マネジメント,精神障がいによる生活のしづらさやこだわり,災害時の支援の必要性を明らかにすることである。
方法 対象地域は,南海トラフによる大津波の被害が想定されている太平洋側に位置するB市とした。対象者は,精神障がいによりA障害福祉サービス事業所(事業所)に通所する精神障がい者37人だった。調査方法は,K-DiPSシートを用いた聞き取り調査を行った。聞き取りは事業所の看護師に依頼した。K-DiPSシートとは,在宅療養者が,生活支援を担当している専門職と一緒に記入することで,災害時に必要となる医療機器や処置,材料,投薬,生活上の留意点などを把握することができるシートである。精神障がい者版は,災害時の症状マネジメント,精神障がいによる生活のしづらさやこだわり,災害時に必要な支援の必要性が含まれている。
結果 対象者の約68%が,自分の病状悪化の徴候を知っており,約57%が,自分の病状悪化をイメージでき,73%が,対処ができると考えていた。一方で,一般避難所で生活できると答えた者は約22%だった。したがって,症状マネジメントができる者も,一般の避難所では生活できないと考えている可能性がある。80%以上の者が,服薬行動に生活のしづらさやこだわりを持っており,約95%の者が災害時に支援が必要と考えていた。約68%の者が,運動,仕事等と休息・睡眠に生活のしづらさやこだわりを持っており,災害時に支援が必要と考えていた。
結論 服薬を継続するための支援ができる専門職の配置と,平時から自分の薬剤を備えておける仕組みの必要性が示唆された。
キーワード 精神障がい者,災害,症状マネジメント,就労継続支援事業所
|
第66巻第15号 2019年12月 周囲の自殺者の有無と援助希求行動に
平光 良充(ヒラミツ ヨシミチ) |
目的 本研究の目的は,周囲の自殺者の有無と援助希求行動に対する抵抗感の関連について明らかにすることである。
方法 名古屋市が2017年12月から2018年1月に実施した質問紙調査の回答データを使用して二次解析を行った。質問紙は,名古屋市内在住の16歳以上の市民から無作為抽出された10,000人を対象に配布され,4,747人から回答を得た(回収割合47.5%)。質問紙では,援助希求行動に対する考え方(他人を頼る行為への見解,相談の意思),自殺念慮の有無,周囲の自殺者の有無,精神的健康状態などを尋ねていた。周囲の自殺者との関係は「家族」「親戚」「その他」に区分した。自殺念慮の有無,他人を頼る行為への見解または相談の意思を目的変数,周囲の自殺者の有無を説明変数としてロジスティック回帰分析によりオッズ比を算出した。オッズ比は周囲に自殺者がいない人を対照とした。調整オッズ比を算出する際には,性別,年齢層,職業の3変数で調整するモデル1と,さらに精神的健康状態を加えた4変数で調整するモデル2の2種類を検討した。
結果 周囲の自殺者の有無および調整変数に欠損がなかった4,244人を分析対象者とした(有効回収割合42.4%)。モデル1とモデル2で調整オッズ比に顕著な差はみられなかった。最近1年以内に自殺念慮を抱いた調整オッズ比(モデル2による,以下同様)を自殺者との関係別にみると,「家族」が3.22(95%信頼区間:1.53-6.78),「親戚」が1.62(1.06-2.48),「その他」が2.21(1.63-3.00)であった。他人を頼る行為を恥ずかしいことだと思う調整オッズ比は「家族」が1.67(1.05-2.66),「親戚」が1.40(1.12-1.75),「その他」が0.99(0.83-1.17)であった。深刻な悩みを抱えても相談しない調整オッズ比は「家族」が1.96(1.17-3.28),「親戚」が1.15(0.88-1.50),「その他」が1.00(0.82-1.22)であった。
結論 「家族」を自殺で亡くした人は自殺念慮を抱きやすい一方で,援助希求行動に対して抵抗感を抱くリスクが高い可能性が示唆された。今後は援助希求行動に対する抵抗感を減らす方法について検討する必要がある。
キーワード 自死遺族,援助希求行動,相談,抵抗感,オッズ比,家族
|
第66巻第15号 2019年12月 乳児用液体ミルクは母親の育児負担を軽減するか-韓国の母親に対する調査結果からみえた課題-水野 智美(ミズノ トモミ) 徳田 克己(トクダ カツミ) 趙 洪仲(チョウ ホンジュン) |
目的 韓国において,乳幼児を育てている母親が乳児用液体ミルク(以下,液体ミルク)をどのように利用しているのか,育児負担の軽減につながっているのかについて明らかにし,日本で液体ミルクを製造,販売する際に,どのようなことに留意しなければならないのかを明確化することを目的とした。
方法 韓国の麗水市内の幼稚園,保育所に子どもを通わせている母親453名に対する自記式の質問紙調査と韓国の麗水市内の保育所に子どもを通わせており,子どもに液体ミルクを飲ませた経験のある母親40名に対するヒアリング調査を行った。
結果 質問紙調査の結果,子どもが授乳期に液体ミルクを与えた経験のある人は約1割に過ぎなかった。また,与えていた人は,日常的に使用しているケースは少なく,外出時など使用場面が限定されていた。ヒアリング調査の結果,液体ミルクを子どもが飲まなかった,飲みたがらなかったケースがあった。その理由として,普段飲んでいる粉ミルクと液体ミルクの味が異なること,液体ミルクの温度が低いことが挙げられていた。液体ミルクを使用することによって,外出時にミルクを作る手間が減ったことが挙げられる一方で,デメリットとして値段の高さを挙げる人が多かった。また,液体ミルクが育児負担の軽減に効果があったと答えた人は20%のみであった。
結論 日本で液体ミルクを製造,販売する際に,値段,温度と味,賞味期限,販売形態について検討する必要性が考えられた。
キーワード 乳児用液体ミルク,育児負担,韓国,災害,人工乳
|
第66巻第15号 2019年12月 運動・スポーツ施設の開設が近隣地区の
|
目的 気軽に運動・スポーツを開始できる運動・スポーツ施設やレクリエーション施設は,住民の身体活動に影響を及ぼす可能性がある。そこで,本研究では新たな運動・スポーツ施設の開設が,近隣住民の身体活動と身体活動促進要因へ及ぼす影響を健康づくりの長期的調査結果から施設の利用を促進するための施策の認知や利用の状況も合わせて把握し,検討することを目的とした。
方法 静岡県長泉町民対象の健康づくりの調査結果を分析した。調査対象者は静岡県長泉町在住の30歳から75歳で,住民基本台帳を基に各調査年(2013,2014,2015,2017年)3,200名が無作為抽出され質問紙調査が実施された。調査項目は,基本属性(年齢,性,ほか),身体活動(歩行頻度,運動習慣),身体活動促進要因(運動・スポーツ環境の認知,運動・スポーツ実践者の認知,運動・スポーツ実践の意欲),開設された多目的運動施設と施設の利用を促進するための施策である健康マイレージの認知と利用の状況であった。分析は郵便番号から多目的運動施設に近い近隣地区と遠い非近隣地区に分け,各調査年の調査項目の変化を把握するとともに,長期的な変化について一般化線形モデルを用い検討した。
結果 分析対象者は,2013年が近隣地区706人,非近隣地区308人,2014年が近隣地区738人,非近隣地区315人,2015年が近隣地区864人,非近隣地区312人,2017年が近隣地区879人,非近隣地区363人であった。基本属性はいずれも両地区で統計的な有意差は認められなかった。歩行頻度,運動習慣,運動・スポーツ環境の認知,運動・スポーツ実践者の認知,運動・スポーツ実践の意欲は経年的に多少の変化があったものの,長期的な変化の検討では有意差はなかった。多目的運動施設の認知は両地区とも90%以上であったが,利用は50%以下で非近隣地区は近隣地区より低い傾向であった。また,健康マイレージの認知は両地区とも約30%で,利用は5%以下であった。
結論 本研究の結果,新しい多目的運動施設が開設されても,近隣地区の住民の身体活動は向上しなかった。運動・スポーツ実践の意欲は,既に住民の8割以上にあることから,多目的運動施設の利用や実際の運動・スポーツ実践といった行動変容へとつなげる仕組みや支援を増やすことが,地域の身体活動を促進する上で重要なことかもしれない。
キーワード 身体活動,運動習慣,運動・スポーツ施設,生活環境
|
第66巻第13号 2019年11月 高校生の自傷行為の経験率における性差の検討石田 実知子(イシダ ミチコ) 井村 亘(イムラ ワタル) 江口 実希(エグチ ミキ)渡邊 真紀(ワタナベ マキ) 國方 弘子(クニカタ ヒロコ) |
目的 本研究は,「殴る」「刺す」「つねる」「かきむしる」「切る」の自傷行為様式および種類数別における経験率の性差を検討することを目的とした。
方法 岡山県内の高等学校5校に通う高校生3,820名を対象に,無記名自記式の質問紙調査を実施した。調査内容は,対象者の性,学年,自傷行為で構成した。統計解析には,分析に必要な調査項目に欠損値がない3,316名分のデ-タを使用した。統計解析は,自傷行為の経験率および自傷行為種類数別の経験率を男女2群に分け,その割合の比較をpearsonのχ2検定を用いて検討した。いずれの検討においても,有意水準を両側検定で5%未満とした。
結果 何らかの自傷行為を行った者の経験率は,男性が有意に高かった(p<0.01)。また,「自分のからだや壁をこぶしで殴る」は,各学年および全生徒で,また,「自分の髪や皮膚をかきむしる」は,1年生,3年生および全生徒で占める割合は男性が有意に高かった(p<0.01)。その他の自傷行為では,有意差が認められなかった。さらに,自傷行為種類数別では,いずれの種類数においても有意差が認められなかった。
結論 何らかの自傷行為を行った者の経験率は,男性が女性と比較して有意に高く,「殴る」「かきむしる」を経験した割合は,男性が有意に高かった。自傷行為種類数別では,いずれの種類の選択数においても男女差はなかった。今後,自傷行為に対する正しい知識と理解を持ち,特に男性に配慮した支援方法が求められる。
キーワード 自傷行為,性差,経験率,高校生
|
第66巻第13号 2019年11月 全国データによるわが国のヤングケアラーの実態把握-国民生活基礎調査を用いて-渡邊 多永子(ワタナベ タエコ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) 高橋 秀人(タカハシ ヒデト) |
目的 わが国で全国データを用いてヤングケアラー(家族の介護を行う18歳未満の子ども)の実態把握を行った例はない。本研究では,わが国の公的統計の中で介護者の実態を最も明らかにすることができる国民生活基礎調査を用い,ヤングケアラーの同定とヤングケアラーおよび彼らが介護している被介護者についての記述を行った。
方法 平成16・19・22・25・28年国民生活基礎調査の匿名データを用いた。同世帯の介護が必要な人に対して主介護者として介護を行っている18歳未満の子どもをヤングケアラーと定義し,ヤングケアラーおよびその被介護者を分析対象とした。
結果 ヤングケアラーのいる世帯は,世帯構造ではひとり親と未婚の子のみの世帯(以下,ひとり親世帯)と三世代世帯が多く,人口15万人以上の市ではひとり親世帯が,人口15万人未満の市および郡部では三世代世帯が最も多かった。一月の家計支出総額では20万円未満が最も多かった。ヤングケアラーの12.8%は主観的健康観がよくなく,35.6%は心理的ストレスがあるとされるK6が5点以上であった。ヤングケアラーが介護している被介護者は,ひとり親世帯では80%以上が母親,三世代世帯では80%以上が祖父母・曽祖父母であった。被介護者の最も気になる疾病はうつ病やその他のこころの病気が16.7%と一番多く,被介護者が母親の場合は特に多かった。
結論 わが国のヤングケアラーは,ひとり親世帯で親(主に母親)を介護している場合と,三世代世帯で祖父母・曽祖父母の介護をしている場合が多かった。人口15万人以上の市ではひとり親世帯が,それ以外では三世代世帯が最も多いという地域差がみられた。経済的に豊かでない世帯,心身の健康に不安のあるヤングケアラーも多かったことから公的支援が望まれるが,地域の実情に応じた対策を考える必要があるだろう。一方,先行研究より,本研究ではヤングケアラーを捉えきれてはいないと考えられる。今後さらなる調査・研究,支援を行っていく際には,実施方法について慎重に検討する必要があると考える。
キーワード 国民生活基礎調査,家族介護,インフォーマルケア,ヤングケアラー,若年介護者,介護者支援
|
第66巻第13号 2019年11月 児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」
松村 香(マツムラ カオリ) 鈴木 寛(スズキ ヒロシ) |
目的 児童養護施設の入所児童の約6割は被虐待児童であることから,その養育には困難が伴い,状況によっては,施設内において人権侵害問題に発展する場合がある。そのため,施設内で子どもが安全で安心に生活できることは重要な課題である。施設内で子どもが感じる安全感・安心感の向上のために,松村らは児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」(Scale of Children’s Sense of Safety and Security:以下,SCSSS)を開発している。本研究では,その尺度を児童養護施設で活用することが,子どもの安全感・安心感の向上のために有効であるか評価することを目的とした。
方法 2015~2017年の間に毎年1回,合計3回児童養護施設に暮らす子どもを対象に,SCSSSの効果を評価するために,SCSSSを使った調査を実施した。3回とも調査を実施できたのは神奈川県,埼玉県にある5施設であった。そのうち調査の条件が異なる2施設を除外した3施設に入所中の子ども(有効回答 調査1回目:154名,調査2回目160名,調査3回目:158名)を対象に,SCSSSの生活安全感・生活安心感得点の経年的推移から,SCSSSを活用した介入の有効性を検討した。
結果 生活安全感得点は,調査3回目が調査1回目に比し,有意に上昇するなど(P<0.01),子どもが感じる施設内での安全感は高まった。一方,生活安心感得点には,調査3回目は調査1回目に比し得点の伸びは認められたものの,両者間で有意差は認められなかった。また,SCSSSを使った調査に関して約7割の子どもが有効性を感じ,調査の継続性も望んでいた。また,自由記述の中には,安全感・安心感に関して,子どもの意識が向上していることを示す記述があった。
結論 SCSSSを使った調査による介入は,児童養護施設で暮らす子どもが感じる安全感・安心感の向上ならびに安全感・安心感に対する子どもの意識の変化に有効であることが示唆された。
キーワード 児童養護施設,生活安全感・安心感尺度,介入,評価研究
|
第66巻第13号 2019年11月 保育士が必要とする保育ソーシャルワーク内容の因子構造山本 佳代子(ヤマモト カヨコ) 山根 正夫(ヤマネ マサオ) |
目的 保育所では虐待や貧困,発達障害など福祉的な課題をもつ子どもへの支援に際し,保育士などがソーシャルワーク機能を果たすことが求められている。しかし,支援に必要なソーシャルワークの内容や専門性,それらを習得するための方法論等について統一した見解は明らかにされていない。本研究では保育士養成や具体的な支援のあり方の検討に資するため,保育士が現場実践において必要としている保育ソーシャルワークの内容について,その因子構造を明らかにすることを目的とした。
方法 2016年12月から2017年2月にかけてA県内の保育所等951施設に勤務する保育士および施設管理者,計2,853名(通)を対象に,48項目からなる保育ソーシャルワーク内容に関する質問紙調査(郵送法)を実施し,1,006名(通)の有効回答を得た。調査内容について因子分析の解析およびCronbachのα信頼係数を算出して,因子構造および因子の内的整合性の検討を行った。また,各因子の尺度としての妥当性と因子間の関連を検証するため確認的因子分析を行った。
結果 探索的因子分析の結果,7因子が抽出され,保育士が必要とする保育ソーシャルワーク内容は「特別な配慮を要する子どもと保護者への支援知識」「地域子育て支援」「ソーシャルワーク知識」「権利保障」「個別援助」「地域連携」「社会資源」の因子から構成された。また,Cronbachα係数は0.729~0.978であり,各因子の内的整合性が確認された。さらに,確認的因子分析によるデータと因子構造の適合度はGFI=0.909,AGFI=0.891,RMSEA=0.048であり,因子構造の妥当性を確認した。
結論 本研究において得られた保育士が必要とする保育ソーシャルワークの内容は,先行研究を系統的かつ包括的に網羅する結果であり,一般妥当性を有すると判断できた。今後は,調査対象や範囲の拡大による調査結果の累積および現場での有効なソーシャルワーク活用を目指し,保育ソーシャルワークに関連する要因とそれらの因果関係性について検討する。さらに,保育士のソーシャルワークに対する認識と実際行動との乖離の検証等を行うことも課題としたい。
キーワード 保育ソーシャルワーク,保育士,保育所,保育ソーシャルワークの内容,因子構造
|
第66巻第13号 2019年11月 小児慢性特定疾病がある医療的ケア児における
|
目的 本研究は,2016年の児童福祉法や障害者総合支援法など,医療的ケア児支援に関連する法改正後の,就学の有無別にみた支援ニーズとその要因を比較検討することを目的とした。
方法 対象は,小児慢性特定疾病医療給付制度を利用している医療的ケア児とし,全国の保健所および全国規模の医療的ケア児親の会経由で募集した。医療的ケアは,人工呼吸器・在宅酸素・気管切開・痰の吸引・胃ろう・経管栄養のいずれかと定義した。調査期間は2017年7~10月で,WEB無記名自記式質問紙法で母親に調査した。調査内容は,医療的ケア児の基本的属性9項目,生活環境因子10項目とし,調査内容のうち支援ニーズは『ケアによる負担』5項目,『生活リズムの維持』1項目,『児の体調管理』1項目,『社会資源に関する情報不足や利用困難』3項目で構成した。有意水準は5%未満とし,就学の有無と支援ニーズの関連はχ2検定を用いた。
結果 研究協力機関(36保健所・親の会4団体)が選定した272名のうち,102名から回答が得られ(回収率:37.5%),95名を解析対象者とした(有効回答率:93.1%)。その結果,医療的ケア児の未就学・就学群双方において,支援ニーズが高いと答えた者の割合が,全項目で58.8~100%と高かった。就学群は,未就学群と比較して,医療的ケアと介護サービスに関する支援ニーズが有意に高かった[「サービス利用中や学校等に通っている間の医療的ケアの提供」41名(93.2%,p=0.04),「子どもに対応する訪問介護サービス」38名(86.4%,p=0.003),「子どもの生活リズムに合わせたサービス」40名(90.9%,p=0.02)]。就学群の特徴として,神経・筋疾患の占める割合が高く(31名,70.5%),人工呼吸器に関連するケアが必要な児が29名(65.9%)であった。母親は,主観的健康状態が悪く[身体平均57.8点(標準偏差:SD25.5),精神平均58.6点(SD25.9)],福祉・教育サービスへの不満を抱える者が多かった[福祉18名(40.9%),教育21名(47.7%)]。
結論 就学している医療的ケア児は,自宅以外での医療的ケアの提供と訪問介護サービス,子どもの生活リズムに配慮したサービス提供について,特に支援を必要としていた。その背景として,成長や病気の進行,学校生活に関連するケアが新たに加わることによる介護負担増加の影響が考えられる。また,24時間体制を必要とする高度な医療的ケアの代行者がいないことの影響も推察された。
キーワード 医療的ケア,小児在宅療養,重症心身障害児,難病,就学
|
第66巻第13号 2019年11月 幼児の食行動問題のタイプ別からみた養育環境の検討志澤 美保(シザワ ミホ) 志澤 康弘(シザワ ヤスヒロ) 義村 さや香(ヨシムラ サヤカ)趙 朔(チョウ サク) 十一 元三(トイチ モトミ) 星野 明子(ホシノ アキコ) 桂 敏樹(カツラ トシキ) |
目的 本研究は,4~6歳の幼児を持つ養育者を対象に,食行動の問題をもつ子どもの養育環境について検討することを目的とした。
方法 対象者は,A県2市において研究協力の同意が得られた保育所,幼稚園に通う4~6歳の子ども1,678人の養育者とした。協力機関を通じて養育者に無記名自記式質問紙を配布し,回収は,各協力機関に設置した回収箱および郵送とした。調査は845人から回答が得られ(回収率50.4%),その内,有効回答数は766人(有効回答率45.6%)であった。調査項目は,①子どもの基本属性,②養育者による食行動評価,および③育児環境指標(Index of Child Care Environment;ICCE)であった。統計解析は,χ2検定,Fisherの直接確率検定,因子分析およびt検定を行った。食行動の問題については,養育者による食行動評価を因子分析により3因子が抽出された。分析には,食行動問題の3因子「偏食と食事中の行動」「食事環境への固執性」「食べ方の特徴」の個人の因子得点を用いて食行動問題のタイプ分類し,育児環境指標(ICCE)の4つのサブカテゴリー別に平均値を比較した。
結果 食行動の問題の第Ⅱ因子「食事環境への固執性」については,問題のない児(タイプ1)と問題のある児(タイプ2)のいずれかに明確に分かれることが示された。第Ⅱ因子タイプ別2群で属性を比較したところ,タイプ2において母子・父子家庭などのひとり親家庭の割合が有意に高かった(p<0.05)。次に,第Ⅱ因子タイプ別2群でICCEの各カテゴリーのスコアを比較すると,タイプ2において統制的で罰の頻度が高いことが明らかとなった(p<0.05)。
結論 養育として「制限や罰」を用いることとひとり親家庭は,食行動の上で負の影響を与えていることが明らかとなった。子どもの食行動の問題への支援には養育環境も視野に入れ,対応していく必要性が示唆された。
キーワード 幼児,食行動の問題,養育環境,ひとり親家庭,制限や罰
|
第66巻第12号 2019年10月 Age-period-cohort分析を用いた男児出生割合の変動と
内田 博之(ウチダ ヒロユキ) 小田切 陽一(オダギリ ヨウイチ) |
目的 男児出生割合は,震災後に受ける心的外傷後ストレス障害(PTSD)により低下する可能性が危惧されている。本研究は,2011年3月11日に発生した東日本大震災後に受けたであろう心的外傷後ストレスの影響が男児出生割合の年次推移に影響を及ぼす可能性について,年齢効果,時代効果およびコホート効果のトレンドを推定することで検討した。
方法 出生数は,1979~2016年(全国は1947年から)の人口動態統計から都道府県別に母の年齢別(15~44歳)の性別出生数を使用した。震災による死亡者数,不明者数および負傷者数から,PTSDの発症の危険が低かったであろうと考えられた33都道府県(非被災地域)および発症の危険が中等度以上であったであろうと考えられた14都道府県(被災地域)に分類した。男児出生割合の移動平均(3年移動平均)の年次推移を観察するとともに,ベイズ型age-period-cohort(APC)分析を用いて,非被災地域および被災地域の男児出生割合の経時的変動に対する年齢効果,時代効果およびコホート効果を推定した。
結果 男児出生割合の移動平均の年次推移は,全地域および被災地域では2011年および2012年において低下傾向,非被災地域では2012年に低下が観察された。全地域と比較して被災地域の方は低下傾向が強かった。また,非被災地域と比較して被災地域は,時代効果が震災前に比べ震災時の2011年および翌年の2012年に低減し,男児出生割合が震災前に比べて震災後に低下する可能性が観察された。そして,コホート効果が1967年生まれから1973年生まれのコホート,1987年生まれから1997年生まれのコホートにかけて低減し,男児出生割合が震災後,1967年生まれから1973年生まれの母親の出産,1987年生まれから1997年生まれの母親の出産で低下する可能性が観察された。
考察 男児出生割合の移動平均の年次推移の観察,ベイズ型APC分析の時代効果,コホート効果のトレンドの観察は,いずれも趨勢変化を伴うために,震災が男児出生割合に与える影響を明らかにするためにはさらなる研究が必要である。
キーワード 男児出生割合,震災,心的外傷後ストレス障害,出生コホート,ベイズ型age-period-cohort分析
|
第66巻第12号 2019年10月 単身赴任が身体的・精神的健康および
中田 ゆかり(ナカダ ユカリ) |
目的 一製薬企業で企業戦略により転勤を余儀なくされ,同時期に初めて単身赴任となった労働者を対象に,単身赴任が身体的・精神的健康およびQOLに及ぼす影響について,1年間縦断的に検討することを目的とした。
方法 2012年11月から2013年3月までに初めて単身赴任者となった労働者36名を対象とした。そのうち16名(男性15名,女性1名)から同意が得られ,欠損値のない男性14名を分析対象とした。調査項目は,基本属性として年齢,性別,測定項目としてBody Mass Index(BMI),収縮期・拡張期血圧,唾液アミラーゼ,睡眠効率,自記式質問紙調査項目として,平日・休日睡眠時間,日本版General Health Questionnaire-12(GHQ-12),WHOQOL26を使用した。データ収集は「転勤前」「転勤3カ月後」「転勤6カ月後」「転勤12カ月後」の4回実施した。「転勤前」「転勤3カ月後」「転勤6カ月後」「転勤12カ月後」の各々の数値化されたデータについて反復測定による分散分析を行い,有意差が認められた場合,Tukey法を用いた多重比較を行った。
結果 BMI,収縮期・拡張期血圧,唾液アミラーゼ,睡眠効率,平日・休日睡眠時間,GHQ-12において有意差は認められなかったが,WHOQOL26の「身体的領域」「環境領域」「平均QOL」において有意差が認められた。Tukey法を用いた多重比較によれば,「身体的領域」では「転勤前」と「転勤12カ月後」および「転勤6カ月後」と「転勤12カ月後」で有意差が認められた。また,「環境領域」では「転勤前」と「転勤3カ月後」,「平均QOL」では「転勤前」と「転勤12カ月後」で有意差が認められた。
結論 転勤3カ月後や転勤12カ月後での単身赴任者へのフォローの必要性が示唆された。しかし,本研究では単身赴任者のみを対象とし,対象者数も少なかったため,今後はさらに対象者を増やし,家族帯同者との比較検討や長期的な検討を試みていく必要がある。
キーワード 単身赴任,メンタルヘルス,健康影響,睡眠,QOL,Actiwatch
|
第66巻第12号 2019年10月 心の健康問題で休職した看護師の
木村 恵子(キムラ ケイコ) 榎本 敬子(エノモト ケイコ) 三上 章允(ミカミ アキチカ) |
目的 心の健康問題で休職した看護師の現場復帰状況の現状と課題を検証することが本研究の目的である。
方法 岐阜県内の200床以上の20病院518名の役職看護師(看護師長,主任,業務リーダー)を対象に心の健康問題で休職した看護師の現場復帰支援の状況に関する自記式質問紙調査を2016年1~3月に実施し,20病院316名(回収率61.0%)から回答を得た。その中で無効回答が顕著なケースを除く286名を解析対象とした。統計検定にはKruskal-Wallis検定,Mann-WhitneyのU検定を用い,統計的有意水準は5%とした。
結果 心の健康問題で休職した看護師の現場復帰率は54.5%であり,そのうち休職と現場復帰を繰り返している看護師は13.9%であった。一方,退職率は41.6%であり,休職後現場復帰した看護師より高かった。看護師のメンタルヘルス対策への役職看護師の参加率は30.4%と低かった。参加者の内訳では特に業務リーダーが4.4%と低かった。不参加理由は「対策を必要としていない」が66.3%を占めた。心の健康問題で休職した看護師に対応する職種は看護師長が86.0%を占め,看護師以外の職種は15.0%にとどまった。現場復帰支援の方法は「個人の力量で行っている」が44.1%で多かった。現場復帰支援の経験率は,役職看護師間で違いがあった。現場復帰後の問題発生率は,多数の項目で80%以上となった。「復職可能となった判断基準」での問題の発生については,役職看護師間で発生率に統計的に有意な差があった。現場復帰支援未経験の役職看護師で,統計的に有意に問題発生率が高かった。
結論 役職看護師の約7割はメンタルヘルス対策の必要がないと認識していた。現場復帰支援は,病院全体で行われず看護師が独自に支援している現状であった。そのため,役職看護師間の復職可能基準の共通認識がなく,現場復帰後の業務に問題が発生していた。さらに復帰基準がないことにより,現場復帰支援未経験の役職看護師が心の健康問題で休職した看護師の受け入れについて不安や偏見を持つことにつながる可能性がある。役職看護師の職階によって,病気情報開示の範囲に差が生じていた。そのため,現場復帰した看護師の病状を直接対応する現場看護師が知らされていないことで業務上の問題を生じ,さらに再休職や退職の要因となることが示唆された。心の健康問題で休職した看護師の現場復帰支援が十分に行われず,順調に現場復帰できる環境が整っていないことが示唆された。
キーワード 心の健康問題,看護師,休職,現場復帰支援,メンタルヘルス対策
|
第66巻第12号 2019年10月 山梨県の肝がん死亡率低下と医療行政施策の関連の検討-Joinpoint回帰-横道 洋司(ヨコミチ ヒロシ) 岩佐 景一郎(イワサ ケイイチロウ) 内田 裕之(ウチダ ヒロユキ)小野 千恵(オノ チエ) 米山 晶子(ヨネヤマ アキコ) 高倉 江利花(タカクラ エリカ) 山縣 然太朗(ヤマガタ ゼンタロウ) |
目的 日本の肝がん有病率は,世界の中で大きい。国と県は,1970年代より肝がん対策を行ってきた。全国と同様に,山梨県の肝がんによる死亡率は低下を続けている。これには多くの肝炎,肝がん対策が奏効していると考えられるが一方で,どの施策がその死亡率低下にどれだけ影響しているかは明らかではない。治療の向上や施策の導入の効果を推定した資料は,今後,感染症に起因する疾病に対抗する施策を考える上で必要となる。本研究は,国と山梨県が行ってきた肝炎,肝がん対策の歴史と県内の肝がんによる死亡率の変曲点との関係を,生態学的に検討することを目的とした。
方法 国と県の肝炎,肝がん対策を年次推移にまとめた。次に2000年から2015年までの10万人あたりの山梨県における肝がん死亡率の分岐点をJoinpoint回帰により探索し,統計学的に変曲点を探索した。肝がん死亡率は昭和60年の日本人モデル人口により直接法で調整した。肝炎,肝がん対策の変遷と肝がん死亡率の推移を比較し,死亡率の変曲点の意味づけを試みた。
結果 肝がん死亡率は2000年から2016年にかけて大きく低下し,全年齢では3つの変曲点が検出された。年齢階級別の解析では死亡率に単調な低下傾向はあるものの,変曲点は見いだされなかった。
結論 B型肝炎ウイルス(HBV)ワクチン投与は1982年から段階的に拡大され,現在では乳児の定期接種ワクチンとなっている。このワクチンが肝がん死亡率低下に効果を現すのは2020年代後半以降だろうと考えられた。B型肝炎ウイルスの持続感染に対し,1985年にインターフェロン(IFN)療法が,2000年代に相次いで核酸アナログ製剤の投与が導入された。2005年からの急峻な肝がん死亡率低下にこの治療成績が寄与している可能性が示唆された。C型肝炎ウイルス持続感染に対して1992年にIFN療法が開始されている。2002年に老人保健法による「節目検診」として肝炎ウイルス検査も行われるようになった。2005年からの肝がん死亡率低下にこれらの施策も同様に貢献している可能性がある。2011年からの急峻な低下には,2001年のHCV持続感染に対するIFNとリバビリンの併用療法導入が貢献している可能性がある。山梨県がん登録データから,B型・C型肝炎の治療の発展が肝がん死亡率の低下に貢献している可能性が示された。
キーワード 肝がん,肝炎ウイルス対策,がん登録,B型肝炎ワクチン,日赤献血事業,核酸アナログ製剤
|
第66巻第12号 2019年10月 経済協力開発機構方式を用いた
中島 尚登(ナカジマ ヒサト) 矢野 耕也(ヤノ コウヤ) |
目的 経済協力開発機構(以下,OECD)は,日本の医療制度パフォーマンス(以下,PERF)の悪化を指摘しており,その現状を把握するため,都道府県別(以下,県)PERFを検討した。
方法 OECD方式に従って27指標を用い,指標別に平均値からの相対値(以下,RV)±2標準偏差(以下,SD)を求めて,PERFを評価した。
結果 北海道・東北で,-2SD>RVと悪いのは,北海道の喫煙率,青森の男・女平均寿命(以下,寿命),男・女65歳時平均余命(以下,65歳余命),喫煙率,岩手の30㎞圏救命救急センター人口カバー率(以下,人口カバー),入院の性・年齢調整標準化レセプト出現比・一般病棟7対1・10対1(以下,入院レセプト比),秋田の男寿命,人口カバー,山形の肥満率,福島の女虚血性心疾患(以下,心疾患)死亡率,肥満率,男・女心筋梗塞(以下,AMI)死亡率,+2SD<RVで良いのは,岩手と山形の抗菌剤販売量であった。関東で-2SD>RVは,栃木の男・女心疾患死亡率,埼玉の女心疾患死亡率,医師数,看護師数,東京のアルコール消費量(以下,飲酒量),大気汚染,神奈川の大気汚染,+2SD<RVは,埼玉と千葉の要介護認定率,東京の大腸がん生存率であった。中部で-2SD>RVは,福井の収入対医療費,石川の抗菌剤販売量,+2SD<RVは,福井の肥満率,長野の男65歳余命であった。近畿で-2SD>RVは,大阪の大気汚染,和歌山の女心疾患死亡率,収入対医療費,三重の周産期死亡率,+2SD<RVは,滋賀の男寿命であった。中国・四国で-2SD>RVは,鳥取の周産期死亡率,岡山の男AMI死亡率,徳島の抗菌剤販売量,高知の男AMI死亡率,+2SD<RVは,高知の入院レセプト比,後期高齢者医療制度医療費,看護師数,病院病床数であった。九州・沖縄で-2SD>RVは,長崎の要介護認定率,大分の入院受療費,宮崎の飲酒量,鹿児島の飲酒量,人口カバー,沖縄の肥満率,大腸がん生存率,+2SD<RVは,福岡の後期高齢者医療制度医療費,佐賀の医療費地域差指数,大分の入院レセプト比,沖縄の女65歳余命,入院レセプト比であった。
結論 健康状態7指標のうち,4以上RVが悪いのは,青森,秋田,福島,栃木,和歌山,リスク要因4指標のうち,3以上悪いのは青森,医療へのアクセス5指標のうち,3以上悪いのは栃木,医療の質6指標のうち,4以上悪いのは岡山,医療資源5指標のうち,3以上悪いのは茨城,栃木,埼玉,千葉,東京,静岡,愛知であった。特に健康状態,医療へのアクセス,医療資源が悪い栃木,健康状態とリスク要因が悪い青森では,PERF全体が悪く,早急な対応が必要である。
キーワード 医療制度パフォーマンス,健康状態,リスク要因,医療へのアクセス,医療の質,医療資源
|
第66巻第12号 2019年10月 肺炎で入院した高齢者の退院支援のための
新山 美柳(ニイヤマ ミリュウ) 近藤 尚己(コンドウ ナオキ) |
目的 高齢肺炎患者にとって長期入院は廃用症候群や認知症のリスクとなる。医療施設側や患者の社会的な背景も踏まえた長期入院リスク要因のスクリーニング票を開発した。また,退院支援の必要性を判断する目的で同スクリーニングスコアのカットオフ値を検討した。
方法 東京都内の1医療施設で過去の患者の診療記録を用いた。2013年10月から2014年9月までの1年間に肺炎の病名で退院した患者のうち,肺炎の診断で内科に緊急入院し抗菌薬の経静脈投与により治療を受けた65歳以上の患者を対象にした。入院21日以上を長期入院とし,身体的・社会経済的・医療サービス利用に関する要因を測定した。ポアソン回帰分析で長期入院リスク比を求めて点数化し,スクリーニングカットオフ値を検討した。
結果 対象者371人中,長期入院は157人であった。高齢,肺炎重症,認知症,医療処置,独居,要介護1-2は長期入院リスクが高く,生活保護,かかりつけ医ありの者はリスクスコアが低かった。スクリーニング点数は76から102点まで分布,91点では感度66%,特異度62%,陽性尤度比1.71であった。
結論 かかりつけ医との連携は長期入院を減らす可能性がある。スクリーニングカットオフ値として91点以上を提案する。
キーワード 肺炎,高齢者,退院支援,長期入院要因,スクリーニング票,かかりつけ医
|
第66巻第11号 2019年9月 グループホーム利用者の退所実態に関する研究-グループホーム退所者の「退所理由」に着目して-古屋 和彦(フルヤ カズヒコ) |
目的 本研究では,2018年4月より障害者福祉サービスにおける共同生活援助(以下,グループホーム)の新類型として,重度化・高齢化の障害者の利用者を想定した「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されることをかんがみ,現状の「外部サービス利用型共同生活援助」「介護サービス包括型共同生活援助」の2類型のグループホームの退所者を対象に,具体的な退所理由に着目し,退所者の実態を明らかにすることを目的とした。
方法 全国のグループホームを運営する6,603事業所を対象に,2017年8月4日~8月21日を調査期間として,郵送方式でのアンケート調査を行った。調査内容は,2017年8月1日時点でのグループホーム利用者全体の定員数と現員数,障害支援区分,年齢等の基礎情報および,2016年度1年間にグループホームを退所した利用者の退所後の居住の場,退所の理由等とした。得られた回答より,死亡退所者を除く退所者を抽出し,そのうち退所理由を記述した退所者を主な分析対象とした。
結果 3,586事業所より回答があり(回収率54.3%),その後にデータクリーニングを行い,3,509事業所を有効回答とし,10,485ホーム,58,299人の利用者データが得られた。そのうち2016年度退所者について,死亡退所者295人以外の3,487人から退所理由の回答が得られたのは2,473人であった。集計の結果,ステップアップ型(自立,一人暮らし,就労,結婚等を理由とした退所者の群)が628人,身体・医療的ケア型(病気・入院,高齢・介護,障害支援区分上昇,身体的困難等を理由とした群)が1,038人,集団生活不適応型(規約違反,問題行動,犯罪,なじめず等を理由とした群)が496人,自宅可逆型(本人が同居を希望,親や親族が同居を希望,事業所が同居を勧めた,親と同居のため等を理由とした群)が311人であった。
結論 グループホーム退所者の実態をみると,利用者の多くは継続利用だが,毎年一定数の退所者が存在していると推測される。制度設計の段階で想定されていたであろう,グループホームを経由して自立生活へ移行する「ステップアップ型」は,利用者全体からみると1.1%であった。この結果より,現時点ではグループホームが暮らしの場の終着点となっていることが多いといえる。今後は,重度化・高齢化など多様なニーズに応えられるグループホームの整備を進めていくとともに,退所理由に応じて相談支援事業所等と連携した地域支援ができる環境の整備が,今後のグループホームに求められる機能の重要な課題といえるだろう。
キーワード グループホーム,退所者,退所理由,年齢,障害支援区分,転居先
|
第66巻第11号 2019年9月 都道府県別にみた5年間の障害調整健康余命(DALE)と
栗盛 須雅子(クリモリ スガコ) 福田 吉治(フクダ ヨシハル) 星 旦二(ホシ タンジ) |
目的 65歳以上の健康寿命に関連して,都道府県別の障害調整健康余命(DALE)と年齢階級別加重障害保有割合(WDP)の2010~2014年の年次推移および年間比較を行い,その変化を明らかにし,「健康日本21(第二次)」の目標達成に向けた,都道府県も活用できる基礎資料の整備を行うことを研究目的とした。
方法 DALEとWDPは,サリバン法で算出した。算出には,各年10月の介護保険認定者のデータ,各年の住民基本台帳の人口,2010年の都道府県別生命表を用いた。2010~2014年のDALEとWDPについて分散分析およびBonferroni法による多重比較検定にて平均値の比較を行った。
結果 DALEの上位県,下位県は島根県と鳥取県を除いて,どの年齢においても,男女とも都道府県の順位に大きな変化はなかった。WDPは上位県は年齢が上がるほど,いずれの年次も上位であり,下位県はどの年齢階級でもいずれの年次も下位であった。多重比較検定の結果から,男女とも年順にDALEが有意に低下していた。WDPについては,女性の75~79歳では有意な低下が認められたが,85~89歳では男女とも有意な上昇が認められた。
結論 都道府県がDALEを延伸させ,ならびにWDPを低下させるとともに,順位の改善を図ることを目標に掲げ,そのための具体的な方策を示し,年次推移をモニタリングしながら,方策を実践していくことが地域間格差の縮小につながり,平均余命を上回る健康余命の延伸は可能と考えた。年間比較から,WDPが年々低下した年齢階級はあるものの,全体のDALEの延伸には反映されていないことが明らかになった。本研究結果は,都道府県が策定する「健康日本21」の目標達成に向けた基礎資料を整備したという点では意義は大きいと考えられた。
キーワード 障害調整健康余命(DALE),加重障害保有割合(WDP),65歳以上,年次推移,年間比較,基礎資料