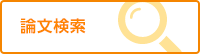論文記事
|
第63巻第12号 2016年10月 市町村における精神障がい者支援活動-8地方別活動状況-長澤 ゆかり(ナガサワ ユカリ) 山口 忍(ヤマグチ シノブ)綾部 明江(アヤベ アキエ) 鶴見 三代子(ツルミ ミヨコ) |
目的 全国の市町村の精神保健福祉活動の状況を8地方別に把握し,今後の精神障がい者支援活動の方向性を探る一助を得る。
方法 全国の市町村の精神保健福祉担当保健師のうち,無作為抽出にて550名を対象に質問紙調査表を配布,回収した。
結果 237件(回収率43.1%)の有効回答を得た。ほとんどの市町村では,随時の所内相談,電話相談,訪問指導を実施しているが,定期相談7割やデイケア5割とその実施率は低いことがわかった。また,市町村における精神保健福祉活動には保健部門および福祉部門の精神保健福祉担当保健師の他,担当でない保健師も関わっていた。なお,地方別の特徴はみられなかった。
結論 市町村において精神保健福祉活動が保健師を中心として定着してきているが,事業として定着するにはもう少し時間を要すると推察された。また,地域独自の特徴を把握するまでには至っておらず,今後,特徴を踏まえた活動が求められる。また,市町村では精神保健福祉担当経験の短い保健師が多く,担当を支えることや支援技術向上のための体制を作ることが,市町村全体の精神障がい者支援体制整備につながる可能性が示唆された。
キーワード 市町村,精神保健福祉活動,精神障がい者支援,保健師,8地方別
|
第63巻第11号 2016年9月 地域包括支援センターが受診援助を行っている
中尾 竜二(ナカオ リュウジ) 杉山 京(スギヤマ ケイ) 三上 舞(ミカミ マイ) |
目的 地域包括支援センターが認知症の疑いのある高齢者を早期に発見し,早期受診を実現するために有用な資料を得ることをねらいに,地域包括支援センターが受診援助を行っている認知症の疑いのある高齢者の援助依頼者とその遠近構造を明らかにすることとした。
方法 中国・四国地方ならびに九州地方(沖縄県を除く)に設置されている地域包括支援センターに勤務する専門職1,500名を対象に,無記名自記式の質問紙調査を実施した。調査内容は,過去1年以内に認知症の疑いのある高齢者の受診援助を行った経験の有無,認知症の疑いのある高齢者の援助依頼者などで構成した。解析には,各項目に欠損値のない480名の資料を用いた。統計解析は,認知症の疑いのある高齢者の援助依頼者の遠近構造はクラスター分析を用いて類型化し,コンボイモデルを参考に地域包括支援センターとの関係を構造化した。
結果 地域包括支援センターの専門職における認知症の疑いのある高齢者への受診援助に関するケースの援助依頼者(紹介元の機関および人)について,クラスター分析を行った結果,3つのクラスターが抽出された。コンボイモデルを参考に模式化した結果,内層には,「民生委員」「高齢者の同居家族」「高齢者の別居家族」,中層には,「同じ市町村の福祉事務所」「高齢者の近隣住民」「高齢者本人」,外層には,「通所介護事業所」「福祉用具貸与・給付関連事業」「特別養護老人ホーム」など18の機関および人が位置していることが確認された。
結論 地域包括支援センターが,受診援助を行っている認知症の疑いのある高齢者の援助依頼者とその遠近構造が明らかとなった。しかし本研究では,認知症の疑いのある高齢者の受診援助における地域包括支援センターの直近に位置する機関および人が明らかとなったものの,地域包括支援センターへ至るまでの過程は明らかとならなかった。今後は,認知症の疑いのある高齢者が地域包括支援センターへ至るまでの詳細な過程を検証していくことが課題である。
キーワード 認知症,受診,地域包括支援センター,民生委員,コンボイモデル
|
第63巻第11号 2016年9月 EPA介護福祉士候補者の介護現場における経験-日常業務での他者からの支援に焦点をあてて-河内 康文(コウチ ヤスフミ) |
目的 本研究の目的は,EPA(Economic Partnership Agreement=経済連携協定,以下,EPA)介護福祉士候補者が介護現場において,誰とかかわり,どのような支援を得ているのかを明らかにする。
方法 方法は,EPA介護福祉士候補者を調査協力者として,富士ゼロックス総合教育研究所が開発した「業務支援」「内省支援」「精神的支援」の尺度を用いて,聞き取りをする形式で実施した。2015年1月1日現在の平成24年度入国者129名のうち,50.4%にあたる65名から回答を得た。
結果 EPA介護福祉士候補者は,介護現場において,上司にかかわることが多い。上司からは,「業務支援」を最も受けており,そこから自らの成長を実感している。施設長・医師,多職種からは,自らを振り返る機会となる「内省支援」により成長が促される。また,同僚・後輩から受けることが多いものには,「精神的支援」「動機づけ支援」があることが確認された。
結論 介護現場におけるEPA介護福祉士候補者に対する支援としては,上司のモデリングによる「業務支援」,施設長・医師,多職種による「内省支援」の機会の提供,および同僚・後輩の「精神的支援」「動機づけ支援」が効果的であり,それぞれの特徴を踏まえたチームアプローチによる多様な他者とのかかわりが重要であることが示唆された。
キーワード EPA介護福祉士候補者,介護人材の確保,経験学習,他者からの支援,チームアプローチ
|
第63巻第11号 2016年9月 犯罪被害者等の実態から見えてくる暮らしの支援の必要性-511名の犯罪被害者等のWEB調査実態調査結果から-大岡 由佳(オオオカ ユウカ) 大塚 淳子(オオツカ アツコ)岸川 洋紀(キシカワ ヒロキ) 中島 聡美(ナカジマ サトミ) |
目的 被害者支援は,平成16(ʼ04)年犯罪被害者等基本法の施行に伴って大きく前進し,裁判に絡めた法律的側面や心のケアの側面から多くの支援策が講じられてきた。一方で,被害者の生活ニーズへの支援に着目されることは多いとは言えず,それらの支援策については地域格差が生じている。犯罪被害者等における苦悩の程度や生活の実態・支障を把握し,今後の犯罪被害者等支援の在り方を模索する。
方法 調査は,平成27(ʼ15)年3月6日~10日の5日間で行った。犯罪被害にあった被害者等に,WEB調査によって回答を求めた。調査項目は,性別,年齢,学歴,年収,被害後の生活困難内容,社会生活障害の程度,受診の有無,相談先,支援制度の知識に加え,K6(うつ病・不安障害に対するスクリーニング尺度)を用いた。
結果 平均年齢は47.8歳,犯罪種別は,殺人・殺人未遂,傷害等の暴力犯罪,交通事故,性犯罪等で,被害後平均15.8年経過している計511名の犯罪被害者等から回答を得た。K6による精神健康状態については,平均値は12.4点で,K6(≧13)の精神障害のハイリスク者は41.7%に上った。83.8%が心理・精神面で苦痛を感じ,被害後の生活維持・再建のために,居住,経済,医療・介護,生活,司法面のサービスを求めていた。事件事故からの時間の経過とともに,精神健康状態は良好になる一方で,若い犯罪被害者ほど精神健康状態が悪かった。
結論 犯罪被害者等の精神的苦悩は深刻であり,被害者の暮らしを支える制度・サービスの拡充・広報の充実とともに,相談を受けた際の適切な相談支援が行える地方公共団体等の体制整備が求められる。
キーワード 犯罪被害者,精神的不調,K6,暮らし,相談支援
|
第63巻第11号 2016年9月 療育サービスの子どもと家族への効果の評価に関する全国実態調査植田 紀美子(ウエダ キミコ) 米本 直裕(ヨネモト ナオヒロ) |
目的 わが国において療育サービスの子どもと家族への効果が評価されているかを把握する。
方法 全国の児童発達支援センター(医療型・福祉型)444箇所に対して,記名式自記式質問票を用いた郵送調査法による実態調査を実施した。調査内容は,障害児通所支援の規模,療育サービスの子どもと家族への効果の評価状況(評価有無,評価内容)についてである。療育サービスの効果の評価状況をセンター種別に示し,評価内容を整理した。子どもと家族への効果を評価している児童発達支援センターの特徴を検討した。
結果 調査票は197施設(回収率44.3%)から回答を得て,有効回答であった186施設を解析対象とした。37.6%の施設が療育サービスの子どもへの効果を評価していた。評価していると回答した施設の52.9%が,ポーテ―ジプログラム,津守・稲毛式乳幼児精神発達診断,新版K式発達検査などの発達検査を療育サービスによる子どもへの効果の評価であると考え,1年に1~2回,これらの様式による発達検査を行っていた。また,個別支援計画を活用した施設もあった(24.3%)。残りの施設は,家族へのアンケート,聞き取り,関係者会議などで各施設独自の方法で療育サービスの子どもへの効果を評価していた。療育サービスの家族への効果は,19.4%の施設が評価していた。評価していると回答した施設の69.4%が,療育サービスの利用満足度のアンケートを実施していた。その他の30.6%は,アンケートなどの特定の様式を使用するのではなく,懇談や聞き取りなどで評価を行っていた。療育サービスにより家族の知識や行動が変化したかどうかを評価した施設はなかった。子どもへの効果を評価している施設の方が有意に多く,家族への効果を評価していると回答していた。家族への効果を評価していると回答したところは評価していないところに比べて,就学前乳幼児の利用契約総数が有意に多かった。
結論 療育の代表的施設である児童発達支援センターにおける療育サービスの効果の評価状況を明らかにした。療育サービスの子どもと家族への効果は十分に評価されておらず,今後,療育の充実のためには,療育サービスの標準化された評価法の開発および普及と活用が望まれる。
キーワード 障がい児,療育,療育サービス,児童発達支援センター,評価,実態調査
|
第63巻第11号 2016年9月 壮年・中年期男性における産業別死亡率の
|
目的 わが国で安定経済成長期からバブル経済崩壊を経て長期経済停滞となった期間(1980~2010年)に,その健康への影響を最も受けたと思われる壮年・中年期男性における産業別死亡率の経年変化を明らかにする。
方法 国勢調査の実施年に合わせて行われた人口動態職業・産業別調査での公表されている統計表と国勢調査(1980年から2010年までの7回分)の結果を用いた反復横断研究を行った。「農業,林業」「漁業」「鉱業」「建設業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「運輸業,情報通信業」「卸売・小売業」「金融・保険業,不動産業」「サービス業」「公務」の11分類と「無職」に分類し,直接法(1985年日本モデル人口)による年齢調整死亡率(男性30-59歳に限定)を1980年度から2010年度まで5年ごとの産業別に算出し,経年変化を調べた。また調査期間の前半で最も大きな人口割合を占め,死亡率が最も低い傾向にあった製造業を対照にした相対危険(死亡率比)を算出した。
結果 就業者総数の死亡率は1980〜2010年度の間に継続的に低下し1980年度には293.9であったが2010年度には150.6(それぞれ人口10万人対)であり30年間で49%低下した。産業別にみると1980~1995年度では「製造業」の死亡率が最も低く,その後は「卸売・小売業」が最も低かった。1980年度と2010年度の死亡率を比較すると,「漁業」と「鉱業」を除き死亡率は33%(「電気・ガス・熱供給・水道業」)から75%(「公務」)減少していた。無職では死亡率が上昇した期間があったが1980年度と2010年度の死亡率を比較すると死亡率は52%減少していた。製造業を対照にした死亡率比は,「公務」の1980年度の死亡率比は2.30で「農業,林業」の2.40と同程度の水準であったが,2010年度には「公務」で1.12,「農業,林業」で2.90と差が開いていた。
結論 壮年・中年期男性における産業別死亡率の経年変化の傾向は産業によって大きく異なっていた。1980年度から2010年度の間に「建設業」「卸売・小売業」「サービス業」「公務」などで死亡率が大きく減少していた一方で,「農業,林業」「漁業」「電気・ガス・熱供給・水道業」では他の産業に比べて死亡率が高く減少率が小さいことが観察された。産業ごとに就業環境,就業形態や仕事量の増減などの特徴が健康に影響し,死亡率の傾向の違いにつながっている可能性がある。
キーワード 産業,職業,産業別死亡率,壮年・中年,男性,人口動態職業・産業別調査
|
第63巻第11号 2016年9月 障害福祉サービス事業所の整備状況に関する研究-地理情報システム(GIS)を基にした地域資源の把握-筒井 澄栄(ツツイ スミエイ) 大夛賀 政昭(オオタガ マサアキ) |
目的 障害者の地域・在宅生活継続を支える基盤的なサポートである障害福祉サービス事業所の地域配置状況と利便性の把握を目的とした。
方法 「地理情報システム」(GIS:Geographical Information System)を用いて,障害福祉サービス事業所の配置状況の可視化と都道府県単位および障害保健福祉圏域単位における各種障害福祉サービスの最寄の事業所までのアクセス距離を計測し,都道府県単位および障害保健福祉圏域単位の平均アクセス距離を算出した。平均アクセス距離と各サービスの利用状況との関連性について分析を行った。
結果 算出の結果,以下のことが明らかとなった。①居宅介護,重度訪問介護,生活介護,同行援護の介護サービスの平均アクセス距離は3㎞未満であり,就労継続支援B型,共同生活援助,就労移行支援の通所系サービスの平均アクセス距離は5㎞未満であった。②各種障害福祉サービス事業所までの平均アクセス距離は,介護サービスについては,居宅介護が大阪府0.5㎞に対して岩手県は3.1㎞,行動援護が東京都1.7㎞に対して山口県の38.1㎞,訓練等サービスについては,共同生活援助が東京都1.1㎞に対して三重県の6.8㎞などの都道府県格差が認められた。③平均アクセス距離とサービス利用には,介護サービスでは居宅介護,重度訪問介護,同行援護,共同生活介護,短期入所,行動援護,施設入所支援,訓練等サービスでは自立訓練(機能訓練),宿泊型自立訓練,就労移行支援で相関が認められた。
結論 障害福祉サービス体制を地域圏域で整備していくには,今回行ったような手法による地域資源の把握が有効と考えられた。今後は,より小さな単位,自治体単位や日常生活圏域での実態把握も必要と考えられた。
キーワード 地理情報システム(GIS),障害福祉サービス体制,障害福祉計画,障害福祉サービス事業所
|
第63巻第8号 2016年8月 事業者における加工食品の栄養成分表示に関する
荒井 裕介(アライ ユウスケ) 林 芙美(ハヤシ フミ) |
目的 事業者における加工食品の栄養成分表示に関する全国保健所での相談,支援の現状と課題を明らかにし,新たな法制度の下での保健所の体制や事業者への支援方策の検討に資することを目的とした。
方法 全国494保健所を対象に,2013年10月に郵送による質問紙調査を実施した。加工食品の栄養成分表示に関する相談の状況として,2012年度の相談件数と内容,相談を行うにあたり困難なこと等の4項目を,事業者が栄養成分表示を行うための支援の状況として,具体的な手順を解説した資料の作成や研修の機会等の3項目をたずねた。集計は設置主体別に4群に分け,有効回答数を分母に各項目の割合を算出した。
結果 367保健所(74.3%)から回答があった。栄養成分表示に関する相談件数は,都道府県で少なく,特別区で多く,内容は指定都市,特別区で強調表示や栄養機能食品の相談が多かった。「相談回答の全国的なデータベースがないこと」「食品事業者自らが表示を行う際に参考となる資料や教材がないこと」が相談時の困難さの理由として多く挙げられた。事業者が栄養成分表示を行うための資料の作成や,研修,情報提供の支援は現状では限られていた。
結論 保健所の相談の現状として,法規集だけでは対応が難しい相談があること,事業者からは表示が適切かどうかの判断を求められることもあること,トラブルに発展する事例もあることがわかった。新たな法制度の下で,全国保健所が円滑に事業者への対応ができるよう,対応マニュアルや研修の提供等の人材育成や,事業者への支援の充実が望まれる。
キーワード 加工食品,栄養成分表示,食品表示法,保健所,相談
|
第63巻第8号 2016年8月 福祉的就労における利用者の工賃の現状と課題-山口県における就労系サービス事業所の実態調査より-佐藤 真澄(サトウ マスミ) |
目的 本研究の目的は,福祉的就労における利用者の工賃の実態とその条件となる事業所の収益事業について明らかにすることにある。「福祉的就労」について明確な定義はなく,本来は一般労働市場において福祉的な支援を受けながら働くという形態も含まれている。ただし,本研究では,「障害福祉サービスによって提供される就労の場」に限定して論じた。
方法 調査は2014年11月に行い,対象は山口県保健福祉施設等名簿(2014年5月)に掲載されている障害福祉サービス事業所302カ所のうち就労継続支援(A/B型),就労移行支援事業を実施している104カ所である。調査票の内容は,事業所の沿革と概要,サービス内容,事業実績など多岐に渡っている。
結果 調査票の回収割合は,就労継続支援(A/B型),就労移行支援事業を実施している事業所で58.6%であった。「おおむね週5日働く」という想定での平均的な工賃(月額)は,「1~3万円以下」が68.6%と最も多く,「1万円以下」と合わせると9割以上の事業所が月額3万円以下である。工賃の支払い規定を,①作業時間と工賃との関係,②月給・日給・時間給等の算定の2段階で調査した。作業時間との関係では,77.6%の事業所が作業時間・日数に応じた日給制もしくは時間給制を採用している。一方で,基本となる時間給等の算定については,業務内容や作業能力等による差を付けず,「すべての利用者で一律」としている事業所が33.3%ある。その点が企業等の一般労働市場との大きな違いである。各事業所で行われている収益事業は,「施設内での下請・内職作業」が最も多いが,これらの事業は収益性が低く,その点を課題だと事業所は感じていた。
結論 福祉的就労は,訓練の場であり,就労の場である。そして,福祉サービスである。単純に就労の場であれば,収益性の高い事業を実施することで高い工賃を支払うことだけをめざすが,訓練であり,福祉サービスであるから,すべての利用者の作業能力や障害特性に応じた内容を選択せざるを得ない。利用者の高齢化・重度化が進むなかで,多様なニーズに対応しようとすればするほど,事業所としての収益の確保は難しい。その結果,すべての利用者が低賃金での就労を余儀なくされている。制度改革では,高工賃の事業所を高く評価するなど成果主義的な方針が示されているが,事業所の自主努力だけでは限界がある。賃金補填を含む公的な支援が必要な段階にあるのではないだろうか。
キーワード 障害者,福祉的就労,就労系サービス,工賃
|
第63巻第8号 2016年8月 認知の偏りと抑うつの関連-認知の偏り測定尺度の妥当性と信頼性の検討から-江口 実希(エグチ ミキ) 國方 弘子(クニカタ ヒロコ) 土岐 弘美(トキ ヒロミ) |
目的 認知行動療法は,抑うつに関連する変容可能な認知要因として,認知の偏り,自動思考を取り扱う。認知の偏りは,出来事を肯定的に捉えるか否定的に捉えるかに関係し,抑うつに大きな影響力をもつ。これまで認知の偏りを測定する尺度は少なく,尺度の妥当性と信頼性の検討は十分に行われていない。本研究は,認知の偏り測定尺度(Cognitive Bias Scale :CBS)の妥当性と信頼性の検討に加え,認知の偏りと抑うつの関連を検討する。
方法 調査は平成26年9~10月に行われ,対象は,A病院に勤務し調査協力が得られた543名の看護師とした。調査項目は, CBS,ベック抑うつ尺度(Beck Depression Inventory:BDI),属性で構成した。分析は,CBSの確証的因子分析による因子構造妥当性の検討に加え,BDIの得点で健常群と抑うつ群の2群に分類した対象を,CBSでどの程度識別できるか判別的妥当性の観点から検討した。次いで,CBSとBDIの関連をSpearmanの順位相関係数を算出して検討した。尺度の信頼性の検討にはCronbachのα係数を用いた。
結果 CBSとBDIの回答に欠損値がない444名を分析対象とした。確証的因子分析の結果,CBS の6因子二次因子モデルと6因子斜交モデルのデータへの適合度は統計学的許容水準を満たさなかった。しかし,6下位尺度ごとの直交モデル(先読み,べき思考,思い込み・レッテル貼り,深読み,自己批判,白黒思考)は,直交モデルすべてのデータへの適合度が良好であった。この時,Cronbachのα係数は0.693~0.825の範囲であった。CBS6下位尺度の中央値は,BDI抑うつ群と健常群においてすべての下位尺度で2群間に有意差がみられた。また,CBSの6下位尺度とBDIの関係係数は0.357~0.575であった。
結論 CBSの6下位尺度直交モデルの因子構造妥当性と判別的妥当性ならびに信頼性は支持され,CBSは抑うつに関連した認知的要因を測定しうる尺度であることが示唆された。
キーワード 認知の偏り,推論の誤り,CBS,BDI,抑うつ,妥当性
|
第63巻第8号 2016年8月 乳児期の母親の喫煙と市区町村の継続的育児支援の関連-健やか親子21最終評価から-篠原 亮次(シノハラ リョウジ) 秋山 有佳(アキヤマ ユウカ) 山縣 然太朗(ヤマガタ ゼンタロウ) |
目的 妊産婦の喫煙は自身に留まらず,成長・発育に重要な時期である児にとっても深刻な影響を及ぼす。このことから,母子保健における重要な課題であり各市区町村の母親への育児支援を検討することは重要である。そこで本研究では,乳児期の母親の喫煙と市町村の継続的育児支援の関連を検討し,自治体における今後の育児支援への一助とすることを目的とした。
方法 対象は,「健やか親子21」最終評価の調査実施対象となった全国472市区町村(各都道府県,約10カ所)および平成25年3月から8月の期間に34カ月健診を受診した児の保護者20,728名である。方法は,各市区町村に『「健やか親子21」の推進状況に関する実態調査票』の記入を依頼した。また各市区町村の母子保健担当課から『親と子の健康度調査アンケート』を乳幼児健診の対象となった保護者に記入を依頼し,健診時に回収した。分析は,目的変数を3・4カ月健診時の母親の喫煙の有無,説明変数を各市区町村の<子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減>に関する推進事業5項目の各継続状況とし,母親の年齢,児の性別,児の出生順位,3・4カ月児健診時の父親の喫煙の有無,経済状況感,母親の就業状況の有無を投入したマルチレベル・ロジスティック回帰分析(都道府県でネスト)にて評価した。説明変数は,平成21年と25年の両調査で支援に取り組んでいる市区町村を「継続群」,両年のうち片方のみ実施もしくは両年とも未実施を「非継続群」とした。
結果 3・4カ月健診時の母親の喫煙割合は,5.0%(898/17,880人)であった。多変量解析では,5項目の推進事業のうち「生後4カ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれにも接触のなかった全乳児の状況把握」に関し「非継続群」を基準として「継続群」で,3・4カ月児の母親の喫煙リスクを低下させる傾向[オッズ比=0.71, 95%信頼区間:0.55-0.92]を示した。
結論 「生後4カ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれにも接触のなかった全乳児の状況把握」の継続的な実施は,3・4カ月児の母親の喫煙リスクを低下させる傾向を示した。この継続的な取り組みは,支援が必要または必要と判断される母親への早期介入やその他のアクションプランにつながる重要な情報を提供している可能性がある。
キーワード 母親の喫煙,市区町村の育児支援,3・4カ月児健康診査,健やか親子21最終評価
|
第63巻第8号 2016年8月 介護老人福祉施設における人的資源運用のための
柿沼 倫弘(カキヌマ トモヒロ) 柿沼 利弘(カキヌマ トシヒロ) 関田 康慶(セキタ ヤスヨシ) |
目的 本研究の目的は,人的資源確保の視点から高齢者雇用,腰痛対策,リフトの活用実態を組織特性や利用者像別に明らかにし,人口減少社会における資源運用(高齢者,介護福祉機器等)について提言を行うことである。
方法 高齢者雇用の実態,腰痛の発生状況,リフトの活用状況等を把握するためにWEBアンケート調査を実施した。また,リフトの活用に関する仮説を設定した。WEBアンケート調査のデータを用いて単純集計分析,比較分析,仮説の検証を試みた。比較分析と仮説検証は,介護老人福祉施設の施設特性,利用者像別で行った。仮説の検証方法は,データの確率分布から判断し,Mann-WhitneyのU検定を用いて行った。有意水準は5%とした。
結果 本研究の回答施設の属性は,全国調査と比較しても特異的なものではなかった。高齢者の雇用はほとんどの施設で行われていた。高齢者雇用をされている職員が身体介護(排せつ,入浴,食事介助)業務を担っている割合が62.3%,看護業務が53.2%,運転業務が41.8%であった。業務の実態分析から,若年層の代替資源,補完資源として介護職の不足解消への寄与が期待できる。何らかのリフトを導入している施設は36.6%であった。そのうち固定式(天井走行)リフトは9.9%,可動式(床走行)リフトは8.1%であった。また,何らかのリフトの導入をしている施設のほうがリフトを導入していない施設と比較して,車いす利用者の割合が有意に高かった(p<0.05)。リフトの導入有無別で介護職員の腰痛を有する職員割合に関しては有意な差はみられなかった。腰痛が発生すると考えられている業務はベッドの移乗で9割以上を占めた。しかし,実際のリフトの活用場面では入浴介助時が最も多く8割以上を占めた。ベッド移乗介助時は2割程度であった。腰痛を引き起こす実態と腰痛を緩和,予防するための機器の利用実態に齟齬がみられた。
結論 本研究から次の3点を提言する。第1に,今後の大幅な不足が予想される介護分野の人的資源確保策としての高齢者の積極的な雇用である。第2に,腰痛予防のためのリフトの積極的な活用である。正しい運用により移乗の負担を軽減し,介護本来の時間の確保につなげる必要がある。第3は,介護福祉士等の養成課程における教育プログラムの変革である。今後のさらなる人口減少社会を見据えた資源運用に関する価値観の変革と共有化が望まれる。
キーワード 人的資源,高齢者雇用,腰痛一次予防,リフト,人口減少社会
|
第63巻第7号 2016年7月 地域作りに向けた回想法の認知度-地域包括支援センターと社会福祉協議会への意識調査から-津田 理恵子(ツダ リエコ) |
目的 地域福祉を担う地域包括支援センターと社会福祉協議会の地域における回想法活用に関する意識を明確にし,今後の地域作りに向けた方向性を見いだすことを目的とした。
方法 調査対象は,日本全国の各都道府県から7件ずつ無作為抽出した地域包括支援センター329件と社会福祉協議会329件の合計658件で,2013年12月~2014年2月の期間に往復はがきによる郵送法で回想法に関する意識調査を実施し,無記名,自己記入式で回答を求めた。分析にSPSS21.0を使用し,施設間の比較にはχ2検定を用いた。自由記述回答は,内容を忠実にカテゴリー化して施設ごとに表に整理した。倫理的配慮について説明し同意書による承諾を得た。
結果 有効回答は地域包括支援センターが232件(63.6%),社会福祉協議会が133件(36.4%)で,回想法の技法を「知っている」と答えたのは全体の56.7%で,回想法の技法が地域作りに役立つことを「知っている」と答えたのは32.6%,回想法を活用した地域作りに「関心がある」と答えたのは68.5%であった。地域包括支援センターと社会福祉協議会の比較では,地域包括支援センターの方が回想法の技法が地域作りに役立つことを知っていると答え,回想法を活用した地域作りに関心があると答えていた。
考察 地域福祉を担う地域包括支援センターと社会福祉協議会は回想法を活用した地域作りの拠点としてその役割を担うことが期待できることから,回想法の技法が地域作りに役立つことを広く啓発していくことが大切である。そして,地域で回想法を活用した地域作りに取り組むことで介護予防効果が期待できるだけでなく,既存の社会資源や地域住民の力を活用した認知症高齢者を地域で支える仕組み作りに発展する可能性がある。
キーワード 回想法の認知度,地域作り,地域包括支援センター,社会福祉協議会
|
第63巻第7号 2016年7月 若年性認知症の人とその家族の生活実態-愛知県における8年間の推移-小長谷 陽子(コナガヤ ヨウコ) |
目的 65歳未満で発症する若年性認知症は,高齢者の認知症と比べて社会的認知が不十分で,必要な支援が本人や家族に届いていない。国の支援施策が進められている中,平成26年度に愛知県における若年性認知症の人の生活実態調査を行い,18年度に行った結果と比較し,8年間の推移を検討した。
方法 愛知県内の介護保険施設,医療機関,障害者福祉施設に対し,2段階で調査を行った。1次調査で若年性認知症の有無を問い,「あり」と回答した施設に対して2次調査票を送付した。内容は,性別,年齢,発症年齢,診断名,合併症の有無,認知症の家族歴と既往歴の有無,認知症の程度,日常生活動作の状況,認知症の行動・心理症状の有無,要介護認定の有無と要介護度,障害者手帳取得の有無と種類,障害年金受給等の有無等である。
結果 2次調査で把握できた該当者数は平成18年度は624人,26年度は356人であった。性別では両年度において男性の割合が多く,年齢は,60~64歳が最も多かった。原因疾患では平成18年度には血管性認知症の割合が最も高く,26年度にはアルツハイマー病が最多であった。平成18年度には重度の人が最も多く,次いで中等度であり,26年度には軽症者が最も多く,重症者の割合は少なかった。平成18年度には,歩行,食事が自立している人の割合は約5割であり,排せつも自立が最も多かった。入浴と着脱衣では自立は3割以下であり,一部介助が最も多かった。平成26年度においてもほぼ同様であった。要介護認定者の割合は,平成18年度に比べ,26年度には,6.6ポイント増加していたが,有意差はなかった。要介護度は,平成18年度には要介護4が最も多く,次いで要介護3と要介護5であったが,26年度には要介護3が最も多く,次いで要介護5であった。障害者手帳取得者の割合は,平成18年度には33.5%で,26年度は40.4%と有意に増加し,精神障害者保健福祉手帳取得者の割合は2倍以上となり,身体障害者手帳取得者の割合とほぼ同程度であった。障害年金等の受給者の割合も,平成26年度は約1.8倍と有意な増加がみられた。
結論 若年性認知症に関する理解や支援は8年間に着実に進んできているが,まだ不十分である。医療機関,介護保険制度だけでなく,雇用,障害者福祉など様々な既存の制度の活用とそれらの間の密な連携が必要である。特に診断直後の支援は重要であり,必要な情報の提供と適切な助言,本人や家族の不安を軽減し,今後の生活の方向性を示し,本人と家族の生活を再構築する支援が求められる。
キーワード 若年性認知症,生活実態調査,愛知県,8年間の推移
|
第63巻第7号 2016年7月 医療観察法対象者の地域ケアにおける保健所の支援実態-司法精神医療機関と行政機関の連携の課題-原田 小夜(ハラダ サヨ) 辻本 哲士(ツジモト テツシ)角野 文彦(カクノ フミヒコ) 中原 由美(ナカハラ ユミ) |
目的 医療観察法施行から10年が経過し,地域処遇の事例が増加している。本研究は,保健所の医療観察法対象者(以下,法対象者)の支援の実態から司法精神医療機関と行政機関との連携に関する課題を検討した。
方法 全国の保健所に対し,自記式質問紙法による郵送調査を平成25年10月に実施した。調査内容は,保健所の法対象者の支援経験,共通評価項目の知識と活用,地域支援に関する課題25項目とし,記述統計を実施し,法対象者の有無による比較,指定医療機関の有無による比較にはχ2検定を実施した(有意水準5%)。
結果 回答数は311(回収率63.0%)のうち,指定入院医療機関有は14.0%,指定通院医療機関有は43.3%であった。支援経験有76.8%,事例数は1,124件,平均支援数は3.6,指定入院機関有で6.7,指定通院医療機関有で4.5,無し1.9であった。共通評価項目のカンファレンス使用は14.6%,情報提供が必要との回答が70%を超えた項目は「幻覚・妄想等の精神症状」「病識の有無」「非社会性」であった。法対象者に「特別な対応が必要」55.8%,支援に対する「不安がある」65.3%であった。地域支援に関する課題では,「法処遇終了後の対応,支援体制に不安がある」「保健所のマンパワーが不足し,きめ細やかな対応は難しい」「被害者支援,同じ町で生活するにあたって,被害者への配慮がいる」「処遇困難な事例に対する丁寧な関わりをするには時間がない」で課題有が70%を超えた。支援経験有の保健所の指定入院医療機関有,指定通院医療機関有,指定医療機関無しの3群比較では,「発達障害,アルコール等,統合失調症以外の対象者の処遇が難しい」「指定通院医療機関が遠いので,治療を中断する心配がある」「ホームヘルパーにとって法対象者のケアは難しい」「サービス決定をする行政機関と退院後の居住地が異なるとタイムリーに対応できない」で,課題有の割合は指定医療機関無しが最も高く,指定通院医療機関有,指定入院医療機関有の順であった。「家族支援について,法以外のケースと異なり,対応方法がわからない」は,課題有の割合は指定医療機関無し,指定入院医療機関有,指定通院医療機関有の順で高かった。
結論 保健所の支援事例数が増加し,法処遇終了後の支援体制に不安を持っている。指定医療機関の無い保健所における処遇困難事例に対する対応,法対象者の治療中断や指定医療機関とのタイムリーな連携の課題が大きい。法処遇終了後の継続した支援体制づくりが重要である。
キーワード 医療観察法,保健所,指定医療機関,地域処遇,連携,共通評価項目
|
第63巻第7号 2016年7月 地域包括ケアシステム構築における住民参加の可能性坂本 俊彦(サカモト トシヒコ) |
目的 見守り活動を中心とする生活支援活動に対する地域住民の意識・態度の分析を通して,活動参加の傾向と参加促進のあり方について検討することを目的とした。
方法 全域が中山間地域であるA県B市C,D,E地区在住の,20歳以上住民2,250人を対象とする無作為抽出質問紙調査によって得られたデータについて,生活支援活動に対する「参加経験」の有無を従属変数,①基本属性,②近隣関係,③地域参加,④地域意識,⑤介護経験,⑥活動支持理由の6領域14変数を独立変数とするロジスティック回帰分析を地区別に行い,その結果について地区間比較を行い,結論を導いた。
結果 C地区では,「交流深度深い」群が「浅い」群より2.32倍,「身内介護経験あり」群が「経験なし」群より2.50倍,「情念互助同意あり」群が「同意なし」群より3.75倍,参加経験を有していた。D地区では,「貢献意欲あり」群が「意欲なし」群より3.77倍,「情念互助同意あり」群が「同意なし」群より2.32倍,参加経験を有していた。E地区では,「年齢50歳以上」群が「50歳未満」群より7.16倍,「地域活動参加あり」群が「参加なし」群より2.45倍,「貢献意欲あり」群が「なし」群より2.88倍,「情念互助同意あり」群が「同意なし」群より2.73倍,参加経験を有していた。
結論 3地区の結果を比較した結論は次のとおりである。①住民参加の様態は地域社会ごとに多様であり,その促進方法は地域社会の実情に合わせてきめ細かく検討のうえ住民自治組織との協働によって実施すべきである。②3地区共通の変数は,身近で具体的な事例の認知とこれに対する共感を意味する「情念互助」であり,支援対象者の生活困難の様態と支援の意義について可能な範囲で周知する必要がある。③2地区で確認できた変数は「地域貢献意欲」であり,平素より居住地域に対する貢献意欲の維持向上に努めるとともに,生活支援活動が支援対象者のQOL維持向上のみならず,安心な地域社会の構築につながることを周知していく必要がある。④C地区では「交流深度」「身内介護」,E地区では「年齢50歳以上」「地域活動参加」との関連が認められ,地域特性あるいは活動特性による影響が想定されるが,あくまで1つの地域についての結果であり,今後の比較調査によって検証していく必要がある。
キーワード 地域包括ケアシステム,住民の助け合い,生活支援活動,住民参加
|
第63巻第7号 2016年7月 介護予防の優先順位づけのためのデータ可視化ツールの開発芦田 登代(アシダ トヨ) 近藤 尚己(コンドウ ナオキ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) |
目的 介護予防における地域包括ケアの推進には,地域課題の把握や資源開発などによる社会環境の整備が必要である。それらを進めるためには,地域ごとの課題の把握やリスクの高い地域を明らかにして,それらに優先的に取り組むことが必要である。そこで,多面的に地域間比較をする「介護予防事業優先対象地域選定シート」(以下,地域選定シート)を開発し,同ツールを用いた効果を質的に検証することを目的とした。
方法 地域選定シートの開発には,神戸市の業務上の集計データとJAGES(Japan Gerontological Evaluation Study,日本老年学的評価研究)プロジェクトにおいて開発した日常生活圏域ニーズ調査に相当する住民調査のデータを用いた。調査は,神戸市で2011年12月から2012年1月にかけて実施された。市内在住の要介護認定を受けていない65歳以上の男女15,014名を対象に自記式質問紙を郵送して行った(回収率65.9%)。地域選定シートの評価枠組みとして,「要介護リスク要因」「地域の資源」「地域活動の要因(人材の有無や力量,関係性,ボランティアの集まりやすさ等)」「その他」の4つを設定した。「要介護リスク要因」と「地域の資源」の各項目は,神戸市の介護保険課の重点課題であった高齢者の社会参加の推進に関連が強い9項目を選択した。集計単位は,78の日常生活圏域とし,各項目の該当者割合は年齢調整(直接法)を施して算出した後,5段階評価にして,各地域の合計スコアを算出した。また,自治体職員に対して,改良後の同ツールを活用した効果について質問紙調査とインタビューを実施した。
結果 各地域の担当者が同ツールを使って地域診断を行った結果,他の圏域と比べてリスク該当者の割合が高いといった情報を活用して各圏域の課題の設定が可能となった。その結果をもとに,神戸市の担当者らは,介護予防事業の優先対象地域として4地域を選定した。使用後の自治体職員を対象とした質的な調査から,ツールを活用したことによって,数値指標を用いて地域ごとの課題が明確になったこと,そのことで関係諸機関同士の他職種との共通認識を得るなど合意形成が円滑に進んだこと等が抽出された。
結論 地域選定シートを開発し,それを活用することで,地域づくりの介護予防を優先的に進めるべき地域を指標に基づき選定できた。
キーワード 地域診断,介護予防,高齢者,社会参加,ツール開発
|
第63巻第7号 2016年7月 受療行動調査を用いた自宅療養の希望および
上原 里程(ウエハラ リテイ) 柏原 康佑(カシワバラ コウスケ) |
目的 患者の医療ニーズ把握を目的とした受療行動調査では,在宅医療に関連していると考えられる設問である「今後の治療・療養の希望」と「退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し」が収集されている。本研究では,在宅医療に関する情報源としての受療行動調査の利活用を目的として,受療行動調査と医療施設静態調査を突合し,自宅療養の希望と療養できる見通しについて医療施設静態調査の医療施設項目との関連集計を行った。
方法 平成23年受療行動調査と医療施設静態調査を統計法33条に基づく申請により入手し,これらを突合してデータセットを作成した。今後の希望は「入院」「転院」「自宅」「その他」に,見通しは「療養できる」「療養できない」「必要なし」「わからない」に区分した。医療施設項目として「開設者」「退院調整支援担当者」「在宅医療サービスの実施状況(医療保険等および介護保険)」「緩和ケアの状況(緩和ケア病棟および緩和ケアチーム)」を選び,病院種および開設者別に自宅療養の希望とその見通しとの関連を観察した。また,目的変数を自宅療養の希望および療養できる見通しとしたロジスティック回帰分析を行った。
結果 解析対象者は受療行動調査の入院患者49,193人であった。今後の希望で「自宅」と回答した頻度が大きかったのは,小病院や療養病床あるいは開設者が医療法人やその他で退院調整支援担当者がいる場合,療養病床を有する病院あるいは開設者が医療法人やその他で緩和ケア病棟や緩和ケアチームがある場合であった。見通しで「療養できる」の頻度が大きかったのは,大病院を除く全病院種あるいはすべての開設者で退院調整支援担当者がいる場合,療養病床を有する病院あるいは医療法人で緩和ケア病棟がある場合,大病院,中病院,療養病床を有する病院あるいはすべての開設者で緩和ケアチームがある場合だった。退院調整支援担当者がいることは自宅での療養希望とともに自宅療養できる見通しとも独立して関連しており(オッズ比[95%信頼区間];自宅療養希望1.07[1.01-1.13],自宅療養できる見通し1.07[1.02-1.14]),緩和ケアチームがあることは自宅療養できる見通しと独立して関連していた(1.29[1.21-1.37])。
結論 受療行動調査と医療施設静態調査を用い関連集計を実施することで,在宅医療を進める上での有用な情報を提供できることが示された。
キーワード 受療行動調査,医療施設静態調査,在宅医療,退院調整,緩和ケア
|
第63巻第6号 2016年6月 養介護施設従事者がとらえる
吉田 輝美(ヨシダ テルミ) |
目的 高齢者虐待防止法は2006年4月に施行され,厚生労働省は毎年都道府県ごとの高齢者虐待の状況を公表している。高齢者虐待判断件数は平成18年度54件であったが,平成25年度には221件となっている。本研究では,養介護施設従事者がとらえる高齢者虐待発生要因は何か,さらに高齢者虐待を再発させないために必要なことを,養介護施設従事者等はどのように捉えているのかを明らかにすることを目的とした。
方法 都道府県ごと人口最多自治体と最少自治体を選び,その中から調査対象事業所を①特別養護老人ホーム,②老人保健施設,③通所介護,④訪問介護,⑤グループホームの5種類とした。1種類ごとに5カ所ずつ無作為に事業所を抽出したが,人口最少自治体で事業所数の少ない場合は,その数のみとして合計1,368事業所へ郵送で調査を依頼した。調査期間は2014年8月11日から2014年9月10日である。アンケート回答者からは,個人ごとに厳封し郵送で返信してもらった。
結果 高齢者虐待発生要因の選択肢項目で最も高かったのは,全事業所で「職員のストレスや感情コントロールの問題」であった。高齢者虐待防止法にもとづく高齢者虐待の状況の公表について知っているか否かで2群に分け,知っている群と知らない群ともに,高齢者虐待発生要因の選択肢項目で最も高かったのは「職員のストレスや感情コントロールの問題」であった。
結論 厚生労働省の公表で最も高かった項目は,「教育・知識・介護技術等に関する問題」であったが,本調査では,「教育・知識に関する問題」は中位の認識であり,「介護技術等に関する問題」については事業所別,年代別,取得資格別にみると最下位に認識された点で大きく異なる。この差異は,虐待を調査もしくは判断する側と,養介護施設従事者の発生要因の捉え方によるものと考えられる。現場の養介護施設従事者等は「教育・知識・介護技術等に関する」研修ではなく,「職員のストレスや感情コントロールの問題」に対応する研修を望んでいるのではないかと考えられた。
キーワード 高齢者虐待,養介護施設従事者による虐待,虐待の発生要因,職員のストレス,感情コントロール
|
第63巻第6号 2016年6月 たばこ規制に対するたばこ使用者を
仲下 祐美子(ナカシタ ユミコ) 大島 明(オオシマ アキラ) |
目的 たばこ使用者のたばこの健康影響に関する認識,たばこ規制に対する意識や規制から受けているインパクトについて把握し,調査結果の国際比較により,今後,日本が取り組むべきたばこ規制の課題を検討した。
方法 全国のたばこ使用者2,000人を対象に,たばこの健康影響に関する認識,たばこ規制(受動喫煙防止,たばこ価格政策,たばこの警告表示)に対する意識や規制から受けているインパクトについてインターネット調査を行った。調査期間は2014年10~11月である。諸外国の調査結果との比較は,2004~2013年に17~21カ国で実施されたITC Projectの調査結果を用いた。たばこ規制の進展度の評価はWHOによるMPOWER報告を用いた。
結果 たばこの健康影響に関する認識は,能動喫煙と脳卒中,受動喫煙と心筋梗塞,肺がんの関係について「いいえ」もしくは「わからない」と回答した割合は51~57%であった。たばこ規制が進んでいる諸外国では日本の1/2~1/3と低率であり,わが国と同程度の規制の国でも日本より低率であった。受動喫煙防止規制に関しては,過去1カ月以内に職場もしくは過去6カ月以内にレストラン・喫茶店,居酒屋・バーでたばこを吸っている人がいたと回答した割合は,それぞれ54%,66%,83%であり,たばこ規制が進んでいる諸外国ではいずれも30%以下であった。また,規制への支持として,これらの場所の屋内全面禁煙に賛成した割合は6~14%であり,たばこ規制が進んでいる諸外国では日本の5~15倍高く,わが国と同程度の規制の国でも2~10倍高かった。たばこ価格政策に関しては,たばこに費やすお金が原因で生活費が圧迫されたことがあったと回答した割合は11%であり,諸外国と比べて低かった。たばこ包装の警告表示をきっかけに健康への害を考えることが「大いにある」と回答した割合は3%にすぎず,たばこ規制が進んでいる諸外国では日本の4~15倍,わが国と同程度の規制の国でも2.6~8倍高かった。
結論 たばこ規制の進展度を評価したWHOのMPOWER報告において,たばこ規制が進んでいる国だけでなく,わが国と同程度の規制とされた国と比べてもたばこ規制の政策から受けるインパクトは小さく,それが日本のたばこ使用者の健康影響の認識やたばこ規制に対する意識の低さに現れていた。
キーワード たばこ規制枠組条約,ITC Project,たばこ使用者,国際比較
|
第63巻第6号 2016年6月 認知症の人の在宅生活を支援する地域包括ケアに関する研究-地域包括支援センターの調査に基づいて-原 直子(ハラ ナオコ) 佐藤 ゆかり(サトウ ユカリ) 香川 幸次郎(カガワ コウジロウ) |
目的 認知症の人の在宅生活を支えるには,医療・介護・生活などを一体的に支援する地域包括ケアの必要性が指摘され,地域包括支援センターが中核となりその推進を目指しているが,具体的な方向性を描けていないのが現状である。そこで,認知症の人の在宅生活支援に対する具体的な方向性を提示することを目的とした。
方法 調査対象者は,兵庫県下の地域包括支援センター198カ所の職員のうち,保健師等,社会福祉士,主任介護支援専門員(以下,三職種)とした。調査期間は,2014年8月18日~同年9月4日で,自記式質問紙法を用い郵送による配布回収を行った。調査項目は,先行研究や報告書,ケアマニュアルをもとに,認知症の人の在宅生活を支えるために必要と指摘されている事項を検討し,認知症の人の在宅生活を支えるために必要な117項目をアイテムプールし,予備調査による検討を経て,60項目とした。分析方法は,職種間の差の検定をχ2検定で行い,三職種が重要と捉える認知症の人への支援内容の構造を明らかにするために,最尤法とプロマックス回転による探索的因子分析を行った。これにより,三職種が重要と捉える認知症の人への地域支援の活動内容について,構成要素と重要度を検討した。
結果 63カ所のセンター(回収率31.8%)より174人の回答が得られた。認知症の人の在宅生活を支える活動に関する職種間比較では,有意差が認められた項目は,60項目中1項目のみであった。探索的因子分析の結果では,7つの因子を抽出し,「細やかな配慮」「家族会と擁護の視点」「地域の人の理解」「多職種連携」「医療体制」「家族の理解」「相談体制」と命名した。重要性の高い順に,「家族の理解」「相談体制」「地域の人の理解」「多職種連携」「細やかな配慮」「医療体制」「家族会と擁護の視点」であった。重要性に関する順位には,有意差が認められたが,因子ごとの職種による有意な差は,どれも認めらなかった。
結論 認知症の人の在宅生活支援に重要な7つの要素を確認することができた。本人に身近な支援から広域的な支援までが構成要素として抽出され,これらを統合してケアが展開されることで,認知症の人への在宅生活支援や地域包括ケアが,実のあるものになると思料される。
キーワード 認知症,在宅生活,地域包括ケア,地域包括支援センター,因子分析
|
第63巻第6号 2016年6月 児童相談所で把握される自殺の実態と自死遺児支援の状況白神 敬介(シラガ ケイスケ) 竹島 正(タケシマ タダシ) 川野 健治(カワノ ケンジ)小野 善郎(オノ ヨシロウ) 藤林 武史(フジバヤシ タケシ) 川崎 二三彦(カワサキ フミヒコ) 白川 教人(シラカワ ノリヒト) 勝又 陽太郎(カツマタ ヨウタロウ) 大塚 俊弘(オオツカ トシヒロ) |
目的 児童相談所を対象に自死遺児の実態とその支援の状況を明らかにすることを目的として調査を実施した。また,自死遺児への支援において,児童相談所が認識する課題について検討を行った。
方法 全国207カ所の児童相談所を対象に調査票を配布し,平成25年度中に同居家族等に自殺既遂がみられた事例等の数,児童相談所に統合もしくは併設されている他の専門機関との組織的関連付け,児童相談所における自死遺児支援サービスの実施有無,自死遺児への支援もしくは自殺対策を行ううえでの困難について回答を求めた。
結果 160の児童相談所から回答を得た(回収率76.9%)。平成25年度中に児童相談所で把握された同居家族等の自殺を経験した児童の数は,138人であった。自死遺児支援としてのサービスを実施している児童相談所は,5.6%(9/160)であった。児童相談所において自死遺児への支援もしくは自殺対策を行う場合の困難として,最も多かった回答は「人材の確保」であった。
考察 本調査より,自死遺児あるいはその同居家族等のうちの自殺者が児童相談所において一定数把握されていることが示された。一方で,自死遺児向けのサービスを実施していると回答した児童相談所は一部に限られており,児童相談所における自死遺児支援の実施には困難が存在することが示唆された。今後,児童福祉領域における自殺リスクの高さを踏まえ,児童相談所において人材の確保や専門家養成を進めるとともに,児童福祉領域全体で自死遺児支援への共通理解を形成し,仕組み作りを行っていくことが必要であると考えられる。
キーワード 自殺,自死遺児,児童相談所,児童福祉,自殺対策,自死遺児支援
|
第63巻第6号 2016年6月 都市部在住の自立高齢者の社会関連性の実態と関連要因の検討紅林 奈津美(クレバヤシ ナツミ) 田髙 悦子(タダカ エツコ) 有本 梓(アリモト アズサ) |
目的 本研究は,都市部在住の自立高齢者の社会関連性の実態と関連する高齢者の個人特性と地域環境特性について明らかにすることとした。
方法 研究対象は,A政令市B区在住の65歳以上の自立高齢者であって,同区地区センターの利用者308名である。方法は,自記式無記名質問紙調査であり,調査項目は基本属性,社会関連性指標,個人特性として抑うつ,主観的健康管理能力,地域コミットメント,地域高齢者見守り自己効力感であり,地域環境特性として包括的環境要因,健康情報希求行動のための情報源の種類,住み心地である。
結果 対象者の平均年齢は73.1±5.7歳,男性41.7%,女性58.3%であり,社会関連性指標の平均点は15.3±2.7点であった。社会関連性指標の得点の高さは,基本属性では年齢が低いこと(β=-0.151,p=0.021),個人特性では主観的健康管理能力が高いこと(β=0.230,p=0.001),地域コミットメントが高いこと(β=0.156,p=0.048),地域高齢者の見守り効力感が高いこと(β=0.199,p=0.008)が有意に関連していた。また,地域環境特性では,包括的環境要因における安心安全を強く感じていること(β=0.243,p<0.001),健康情報希求行動のための情報源の種類が多いこと(β=0.299,p<0.001)が社会関連性の高さにおいて有意に関連していた。
結論 高齢者の社会関連性を高めるためには,高齢者が自身の健康への関心や,地域への関心をもてるような方策を講ずるとともに,高齢者が安心して生活を送れるための地域づくりや情報授受のあり方等を勘案することが重要である。
キーワード 高齢者,地域環境,個人特性,地域づくり,社会関連性
|
第63巻第5号 2016年5月 地域高齢者におけるライフスタイルと
宮原 洋八(ミヤバラ ヒロヤ) 楠 正和(クス マサカズ) 深堀 辰彦(フカホリ タツヒコ) |
目的 地域高齢者のライフスタイルと,生活機能・社会的属性などの要因との関連を明らかにすることで,サクセスフル・エイジングに対する介入研究の基礎資料とすることを目的とした。
方法 佐賀県3町自治体の呼びかけで参加した65歳以上の女性128人(平均年齢:80.1±7.8歳)を対象とした。ライフスタイルに関する22項目,生活機能に関する13項目を測定した。
結果 ライフスタイル全項目の通過率(「はい」という回答の比率)では,「ボランティア」が26.6%で最も低く,次いで「挑戦」47.7%,「美化活動」52.3%が低かった。反対に通過率が高かったのは,「健康診断」89.1%,「明るく考える」85.9%,「庭いじりなどの軽い運動」85.9%の順であった。調査した項目のうち,家族構成や転倒歴によって分けても,群間にライフスタイル得点に有意差は認められなかった。一方,年齢では,後期高齢群の社会的,心理的ライフスタイル得点が前期高齢群より有意に低い値を示した。ライフスタイル3尺度と老研式指標3尺度の偏相関では,すべての項目間で有意な相関がみられた。
結論 本研究で調査した佐賀のライフスタイル各項目の通過率は,社会的ライフスタイルでは26.6-84.4%,心理的ライフスタイルでは47.7-85.9%,身体的ライフスタイルでは53.9-89.1%であった。また,家族構成や転倒歴によって分けても,群間にライフスタイル得点に有意差は認められなかった。本研究で対象とした高齢者は,教室に自ら参加できる者であったことから比較的元気な高齢者集団と考えられる。従って家族構成や転倒歴による差が認められなかった可能性がある。ライフスタイルを調査することが高齢者の自立性の指標となり,ライフスタイル得点の高い高齢者が,サクセスフル・エイジングの獲得や維持に関連していることが示唆された。
キーワード 地域高齢者,ライフスタイル,生活機能,生活の質,サクセスフル・エイジング,コンピーテンス
|
第63巻第5号 2016年5月 看護職における新生児蘇生法の普及の現状と課題樋貝 繁香(ヒガイ シゲカ) 菱谷 純子(ヒシヤ スミコ)橋爪 由紀子(ハシヅメ ユキコ) 立木 歌織(タチキ カオリ) |
目的 看護職における新生児蘇生法(Neonatal Cardio-Pulmonary Resuscitation:以下,NCPR)の普及の現状を明らかにし,課題を検討することとした。
方法 平成25年5~9月に関東近県の病院や診療所26施設の看護職651名を対象とした無記名自記式質問紙調査を実施した。
結果 有効回答は242名(有効回答率37.2%)であった。施設の内訳は病院159名(65.7%),診療所83名(34.3%)であった。対象属性は助産師131名(54.1%)であった。NCPR2010年版の受講者は139名(57.4%)であり,このうち施設内での受講は73名(53.3%)であった。NCPR2010年版への更新者は10名(4.1%)に対し,未更新者は27名(11.2%)であった。産婦人科病棟での勤務の看護職は施設外での講習会受講が有意に多かった(p<0.001)。新生児蘇生法を知っていた165名で職場の勉強会をきっかけとする者が104名(63.0%)と最も多かった一方で,知らない人は77名(31.8%)であった。施設や所属領域と認知や受講の有無の関連は認めなかったが,認知と職種(χ2=13.96,p=0.01)では関連を認め,助産師の認知度が高かった。受講への要望は,受講料の助成78名(32.2%),勤務調整76名(31.4%)であった。
結論 新生児蘇生法の普及には,職場を中心とした情報提供により認知度を上げ,チーム医療の視点を持ちながら地域における講習会の開催が必要である。
キーワード 新生児蘇生法(NCPR),看護職,普及の現状,講習会
|
第63巻第5号 2016年5月 娘による母親の介護と義理の娘による義母の介護の比較-つくば市におけるアンケート調査結果から-桑名 温子(クワナ アツコ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) 森山 葉子(モリヤマ ヨウコ)堤 春菜(ツツミ ハルナ) 柏木 聖代(カシワギ マサヨ) |
目的 家族介護の状況,特に子世代による介護状況を把握することは,今後の介護政策展開の上で重要である。日本ではこれまで,介護者の続柄に焦点をあてた研究は行われてきたが,続柄を娘と義理の娘に限定し,かつ被介護者の要介護度と性別を考慮した上で介護状況を比較した研究はない。そこで,本研究では娘と義理の娘による介護に関し,被介護者の性別を女性に限定した上で,被介護者の要介護度で層別化し,介護期間,介護への考えおよび介護負担感などの状況を比較することとした。
方法 つくば市保健福祉部高齢福祉課が2011年2月に実施したアンケート調査を二次データとして分析した。サンプリングは層化抽出法により,在宅療養中の65歳以上の要支援・要介護認定者1,400名とその主介護者とした。分析対象は介護者が娘または義理の娘である165名のうち,被介護者が女性の115名とした。介護期間や介護者の心情などを比較した後,要介護2以下と要介護3以上で層別化をして同様に分析した。さらに,続柄による違いがあった要介護2以下の層において,年齢や副介護者の有無等を考慮して負担感を検討するために多変量解析を行った。
結果 要介護度で層別化すると,全体で有意差があった項目のほとんどが,要介護2以下の層においてのみ有意差があり,その項目は,娘および義理の娘において,被介護者の年齢(中央値84歳vs88歳),介護期間が3年以上(60.0%vs32.6%),経済的負担がある(22.9%vs4.3%),介護方針の決定に自分の意見が反映される(91.4%vs72.7%)などであった。加えて,住居が持家(88.2%vs100%),介護負担感が高い(31.2%vs54.8%)は,全体ではなく要介護2以下でのみ有意差があった。多変量解析の結果,要介護2以下の層では介護者の年齢,被介護者のIADL,副介護者の有無を考慮しても,義理の娘の方が娘よりも負担感が高かった(オッズ比:3.47,95%信頼区間:1.11-10.88)。
結論 娘と義理の娘という介護者の続柄の違いにより,要介護度が低い場合にのみ被介護者の年齢,介護期間,経済的負担などに違いがみられ,要介護度が高い場合には介護状況にあまり差がないこと,また,義理の娘は年齢や副介護者の有無などの交絡要因を調整しても,被介護者の要介護度が低い場合に娘より負担感が高いことが明らかになった。義理の娘が義母を介護する場合には,要介護度が低くても負担感を軽減するための支援が必要と考えられる。
キーワード 介護者,娘,義理の娘,要介護度,介護負担感,在宅介護
|
第63巻第5号 2016年5月 出生率の都道府県格差の分析田辺 和俊(タナベ カズトシ) 鈴木 孝弘(スズキ タカヒロ) |
目的 現在,わが国の最重要課題の1つである少子化の原因を探るため,生活環境や社会経済的要因との定量的な関係を数理統計モデルに基づいて検討する実証研究を試みた。
方法 47都道府県別の合計特殊出生率のデータを目的変数とし,人口,住居,経済,医療,福祉,教育,生活分野の68種の指標を説明変数として用い,非線形回帰分析手法の1つであるサポートベクターマシン(SVM)により解析した。さらに,それらの候補説明変数の中から感度分析法により決定要因を探索した。
結果 都道府県別の出生率について13種の指標のみを用いて,平均二乗誤差(RMSE)0.042,回帰決定係数(自由度調整済)0.875という高い精度で再現するモデルを構築できた。13種の決定要因の中では,婚姻率,男性失業率,女性管理職等の既検証要因が出生率に大きな影響を与えることを確認した。既検証の要因の他に,女性の喫煙率,デキ婚率,病床数等の決定要因も出生率に大きな影響を与えることを新たに見いだした。
結論 出生率に対する多くの決定要因について先行研究とは異なる結果が得られたが,この原因は,先行研究では限定的な少数の説明変数の中から決定要因を探索しているためであると推測される。
キーワード 少子化,合計特殊出生率,都道府県格差,決定要因分析,サポートベクターマシン
|
第63巻第5号 2016年5月 在宅重度要介護高齢者の
|
目的 短縮版Zarit介護負担感尺度8項目(J-ZBI_8)の下位尺度であるPersonal strainとRole strainという2因子構造を用いて,要介護4以上の重度要介護高齢者を対象として,在宅介護期間別による介護者の介護負担感への関連要因を明らかにすることを目的とした。
方法 A県B市ほか2市において,社会福祉法人や社会福祉協議会が提供する在宅介護サービスを利用しながら在宅生活を継続している重度要介護高齢者とその介護者173組に,2013年7月から12月までに調査を実施した。調査内容は,重度要介護高齢者は属性,状況,居宅介護サービスの利用内容,介護者は属性,状況,意識である。分析は重度になってからの在宅介護期間を「1年未満」「1年以上から3年未満」「3年以上」に区分し,Personal strainと Role strainの2因子それぞれの合計値を従属変数とした重回帰分析を行った。
結果 居宅介護サービスの利用は,いずれの在宅介護期間においても,Personal strainとRole strainでみた介護者の介護負担感を軽減する要因とはなっていなかった。むしろ「1年未満」のPersonal strainと「1年以上から3年未満」のRole strainでは入所系サービスが,「1年以上から3年未満」のPersonal strainでは通所系サービスの利用が有意な正の相関を示し,サービスの利用が介護者の介護負担感を増大させていた。介護生活への充実感や満足感を持っていることは,「1年以上から3年未満」のみ介護者の介護負担感を軽減させていた。重度要介護高齢者との関係性の良さについては,Personal strainでは在宅介護期間に関係なく,また,Role strainは「1年以上から3年未満」で,重度要介護高齢者との関係性が良好であることが介護者の介護負担感を軽減していた。
結論 居宅介護サービスの利用が介護者の介護負担感を軽減することにつながっていないことと,重度要介護高齢者と介護者の関係が良好であることが介護者の介護負担感を軽減していることは,今後の対策を検討する上で重要であろう。今後の課題としては,本研究が横断的調査であることから,縦断的調査による分析により,介護者の介護負担感の経時的変化を検証していくことも必要である。
キーワード 重度要介護高齢者,介護負担感,介護者,Personal strain, Role strain