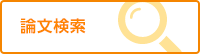論文記事
|
第51巻第3号 2004年3月 在宅療養高齢者の看取りを終えた介護者の満足度の関連要因-在宅ターミナルケアに関する全国訪問看護ステーション調査から-島田 千穂(シマダ チホ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) 樋口 京子(ヒグチ キョウコ)本郷 澄子(ホンゴウ スミコ) 野中 猛(ノナカ タケシ) 宮田 和明(ミヤタ カズアキ) |
目的 在宅ターミナルケアのアウトカム評価として,訪問看護師が介護者の満足度を推定して用いる際の留意点を検討するため,1)介護者本人が評価した満足度と,訪問看護師が推定した「介護者の満足度」との一致度を明らかにし,2)これら2つの満足度に関連する要因との比較を行うことを目的とした。
方法 3次に分けて行われた調査から得られたデータを統合し,訪問看護師を対象とした2次調査と介護者を対象とした3次調査の両方のデータが得られた65歳以上の高齢者229事例を対象とした。
結果 介護者本人が評価した満足度と,訪問看護師が推定した「介護者の満足度」とはおよそ7割が一致しているが,「悔い」については双方が一致していたのは3割であった。また,これら2つの介護者の満足度に関連する要因は異なることが明らかとなった。介護者本人が評価した満足度は,「できる限りの介護ができ(オッズ比5.0)」,「死への心構えや準備ができた(オッズ比3.0)」介護者ほど高くなり,看護師は,「死の時期の予測ができ(オッズ比3.4)」,「死亡場所が
自宅(オッズ比2.5)」であるほど「介護者の満足度」が高いと推定していた。
結論 介護者は,主観的な思いが満足度を高める要因であったのに対し,看護師は,客観的な指標に基づき「介護者の満足度」を推定していた。看護師の推定する「介護者の満足度」を在宅ターミナルケアの評価指標として生かすためには,看護師がずれを発生させる要因を自覚し,ケアの過程で本人や家族の思いが表出できる機会を作り受けとめたり,死後の介護者へのグリーフケアで心理的な援助をするとともに,介護者の思いを確認する機会とするなど,看護師の推定した満足度とのずれを縮小させる方法が必要と考えられる。
キーワード 在宅ターミナルケア,高齢者,介護者満足度,アウトカム評価
|
第51巻第3号 2004年3月 岐阜県内市町村における健康診査受診率に影響する因子篠田 征子(シノダ マサコ) 日置 敦巳(ヒオキ アツシ) 山田 美奈子(ヤマダ ミナコ)金山 みずほ(カナヤマ ミズホ) 田中 耕(タナカ タガヤス) |
目的 市町村が実施する基本健康診査およびがん検診の受診率に影響する因子について分析する。
方法 1984年度から2000年度までの4年ごとの岐阜県内市町村における健康診査(健診)受診率について推移を分析するとともに,社会参加率としての県知事選挙投票率との相関,および健診の個別・集団実施別の受診率から健診受診行動に関与する因子について分析した。
結果 1984年度から1992年度にかけては,基本健康診査,胃がん検診および子宮頚がん検診受診率の上昇がみられたものの,1992年度から2000年度までの後半期にはほとんど上昇は認められなかった。この間,市町村における各種健診受診率は知事選投票率と正の相関を示したが,その回帰係数は漸次低下した。
結論 健診受診率には社会参加意識が関与しているものの,近年はその程度が低下しており,健康づくりの意識に基づいた受診を増やすように働きかける必要がある。
キーワード 基本健康診査,がん検診,受診率,選挙投票率
|
第51巻第3号 2004年3月 山村住民における性別年齢階層別
畑下 博世(ハタシタ ヒロヨ) 笠松 隆洋(カサマツ タカヒロ) 弓庭 喜美子(ユバ キミコ) |
目的 山村地域における健康作り事業の基礎資料とするため,住民の生活習慣の特徴を性別年齢階層別に明らかにする。
方法 20歳以上の全住民を対象に自記式生活習慣調査を実施した。有効回答のあった男性87人,女性136人の計223人を解析対象として,性別年齢階層別に生活習慣の状況,年齢と肥満度との関連,性別年齢階層別にみた健康習慣得点の比較,性別健康習慣得点別にみた血液検査値,血圧,肥満度との関連性を検討した。
結果 男女ともに65歳以上群に比べて20~64歳群では濃い味付けを好む,野菜や乳・乳製品の摂取が少ない,運動不足など生活習慣に問題があった。なお,同じ年齢階層では女性に比べ男性の生活習慣は良くなかった。ライフスタイルを包括的に示す健康生活習慣8項目の平均得点は,20~64歳女性が5.5点と最も高く,以下,65歳以上女性が5.3点,65歳以上男性が4.9点,20~64歳男性が4.1点の順であった。性別健康習慣得点と血液検査値等との検討では,女性において健康習慣得点の高得点群に比べ低得点群で血糖値とBMIが有意に高値を示すと同時に,血糖値異常者率も高かった。男性においても有意差は認められなかったものの,高得点群に比べ低得点
群において中性脂肪,血糖,BMI値が高く,血糖値異常者率も高かった。
結論 性別年齢階層別の保健対策の必要性が示唆され,生涯を通じた健康づくりのために,特に男性の若年齢層に対して,生活習慣改善に向けての働きかけを強化することが重要である。
キーワード 山村住民,生活習慣,食生活,行動変容,肥満
|
第51巻第4号 2004年4月 地域在住高齢者の生きがいを規定する要因についての研究藤本 弘一郎(フジモト コウイチロウ) 岡田 克俊(オカダ カツトシ) 泉 俊男(イズミ トシオ)森 勝代(モリ カツヨ) 矢野 映子(ヤノ エイコ) 小西 正光(コニシ マサミツ) |
目的 地域在住高齢者の生きがいを規定する要因を明らかにし,充実した高齢者の生きがいづくり
を行っていくための基礎的な知見を得ることを目的とした。
方法 愛媛県重信町の60歳以上の住民5,660人を対象とする生活実態調査を行い,対象者本人から回
答が得られ,かつ,調査時点で寝たきりでなかった4,081人を分析対象として,生きがいの有無
を規定する要因を分析した。生きがいの規定要因の分析は,まず,各項目と年齢を独立変数,
生きがいの有無を従属変数とした多重ロジスティック・モデル解析を用いて行った。次に,上
記の分析で統計的に有意であった全項目と年齢を独立変数として投入し,ステップワイズ法に
よる多重ロジスティック・モデルを用いた多変量解析で生きがいの規定要因を分析した。
結果 上記の解析で,生きがいを規定する要因として採択されたのは,男性では,職業があること,
主観的健康感が良好であること,老研式活動能力指標得点が高得点であること,老人用うつス
ケール(GDS)得点が低いこと,運動やスポーツを実施していること,保健行動を多く行って
いること,同居家族外の情緒的サポート得点が高いこと,生活満足度尺度K(LSIK)得点が高
いこと,健康ボランティアへの参加意志があること,の9項目であった。女性では,低年齢で
あること,主観的健康感が良好であること,老人用うつスケール(GDS)得点が低いこと,よ
く眠れること,運動やスポーツを実施していること,同居家族内情緒的サポート得点が高いこ
と,生活満足度尺度K(LSIK)得点が高いこと,健康ボランティアへの参加意志があること,
の8項目が採択された。
結論 生活満足度と生きがいは正の関連を持ち,生きがいを保持することが高齢者にとってその
QOLを高くしていくために非常に大切であると考える。また,主観的健康感や保健行動の実施
状況等が生きがいと関連し,高齢者の健康づくりは生きがいの保持・向上にも重要である。
キーワード 高齢者,生きがい,QOL,健康づくり
|
第51巻第4号 2004年4月 要介護高齢者の家族員における介護負担感の測定東野 定律(ヒガシノ サダノリ) 桐野 匡史(キリノ マサフミ) 種子田 綾(タネダ アヤ)矢嶋 裕樹(ヤジマ ユウキ) 筒井 孝子(ツツイ タカコ) 中嶋 和夫(ナカジマ カズオ) |
目的 本研究は,要介護高齢者を介護する家族員の負担感を測定するための尺度の開発を目的とした。
方法 調査対象は,S県O市に在住し,平成14年4月1日現在で,要介護認定を受けた第1号被保険者である要介護高齢者5,189人の主介護者のうち,協力が得られた1,143人とした。主介護者の介護負担感は「要介護高齢者に対する拒否感情」「社会活動に関する制限感」「経済的逼迫感」を下位概念とする12項目(以下「介護負担感指標」)で測定した。介護負担感指標の構成概念妥当性は,「要介護高齢者に対する拒否感情」「社会活動に関する制限感」「経済的逼迫感」を一次因子,「介護負担感」を二次因子とする二次因子モデルのデータへの適合度を構造方程式モデリングを用いて検討し,介護負担感と主介護者の性,年齢,介
護継続期間と負担感の関係を背景変数を伴う確証的因子分析を用いて検討した。信頼性は内部一貫性をクロンバックのα信頼性係数で検討した。
結果 介護負担感を評価する尺度に関する因子モデルはデータに適合し,妥当性が検証された。また,この介護負担感指標によって測定された負担感は,介護者の性が関連しており,女性が男性に比べて得点が高く,女性の方が負担感を高く感じる傾向があることがわかった。クロンバックのα信頼性係数は0.87であった。
考察 本研究で開発した「介護負担感指標」の構造概念妥当性について議論した。
キーワード 要介護高齢者,介護負担,構成概念妥当性
|
第51巻第4号 2004年4月 特別養護老人ホームは入居者の重度化に耐えられるか?-タイムスタディに基づく最適入居者構成のシミュレーション-小埜寺 直樹(オノデラ ナオキ) 大下 晋一(オオシモ シンイチ) 寺本 岳志(テラモト タケシ)成行 貴久(ナリユキ タカヒサ) 高村 純一(タカムラ ジュンイチ) 古谷野 亘(コヤノ ワタル) |
目的 今後予想される入居者の重度化に,特別養護老人ホーム(特養)が,現在の労働力の範囲で,サービス水準の低下をきたすことなく対応できるか否か検討することを目的とした。
方法 6か所の特養で他記式1分間タイムスタディを実施し,介護職の業務を通して入居者が受けるサービスの量を計測して,要介護度別の「標準的介護時間」を算定した。全国の特養の要介護度平均入居者構成に「標準的介護時間」を乗じて算出した1施設当たりの日勤帯の総介護時間を上限として,介護報酬が最大となる要介護度別の入居者構成を試算した。試算は,入居者構成に条件を設けない試算(1)と,要介護1および要介護2の入居者がいないという条件を課した試算(2)の2つのケースについて行った。
結果 特養入居者の要介護度別に求めた「標準的介護時間」は,要介護1が23.39分,要介護2が30.12分,要介護3が49.96分,要介護4が59.05分,要介護5が71.96分であった。全国の特養の平均入居者構成に基づいて算出した1施設当たりの総介護時間は5,325分であった。試算(1)で介護報酬が最大になったのは,入居者の約半数を要介護5とし,残りの約半数を要介護2としたときであり,この場合,介護報酬は現在の全国平均より多かった。他方,試算(2)で介護報酬が最大
になったのは,要介護5をゼロとし,要介護3と要介護4を2対1の割合にしたときであったが,この場合でも介護報酬は現在の全国平均より少なかった。
考察 これらの試算結果は,現行の職員配置ではサービス水準の低下や介護職の労働強化をもたらさずに,入居者の重度化に対応するのが困難であることを示している。入居者の重度化に対応するためには,要介護度別の介護報酬の設定を実際の介護時間の長短に合った形に改め,介護職の増員によって,総介護時間の増加を図ることが不可欠である。
キーワード 特別養護老人ホーム,重度化,介護報酬,介護労働,シミュレーション
|
第51巻第4号 2004年4月 介護者の自己効力感および介護負担感にかかわる関連要因の検討谷垣 靜子(タニガキ シズコ) 宮林 郁子(ミヤバヤシ イクコ)宮脇 美保子(ミヤワキ ミホコ) 仁科 祐子(ニシナ ユウコ) |
目的 本研究は,在宅療養における介護者の自己効力感および介護負担感にかかわる要因について検討することを目的とした。
方法 4か所の訪問看護ステーションのいずれかを利用している介護者106人を対象に,自記式調査票による郵送調査を行った。調査内容は,自己効力感,介護負担感,介護期間,人間関係,介護の自信,生活満足感などである。自己効力感の測定には,坂野らの開発した「一般性セルフ・エフィカシー尺度」(16項目),介護負担感の測定には,中谷らの開発した「介護負担感スケール」(12項目)を用いた。
結果 自己効力感と介護の自信の間に有意な関連が認められた。また,介護に自信のある人ほど,家族関係に満足している傾向があった。介護負担感と年齢,介護期間,自由時間との間には有意な関連は認められなかった。関連があったものは,介護者の健康状態,生活満足感,家族関係の満足感などであった。また,介護
負担感と介護による健康への影響との間には有意な関連が認められ,介護によって健康が損なわれていると思っている人ほど介護負担を感じていた。
結論 介護に自信をもっている介護者のほうが,自己効力感が高くなっていた。看護者の立場からは,介護に対する自信がもてるようなかかわりが示唆された。
キーワード 介護者,自己効力感,介護負担感,介護継続意思,介護の自信
|
第51巻第4号 2004年4月 ディーゼル車排出ガスとスギ花粉症星山 佳治(ホシヤマ ヨシハル) 川口 毅(カワグチ タケシ) 津村 智恵子(ツムラ チエコ)山岸 善樹(ヤマギシ ヨシキ) 齊藤 祐磁(サイトウ ユウジ) |
目的 スギ花粉症患者はディーゼル車排出ガス濃度の高いところにより多く居住しているかどうかを,オッズ比を用いて検討する。
対象と方法 都内6地区に居住する20歳から65歳未満の女性10,123人に調査票を郵送し,6,707人から有効回答(回収率66%)を得た。調査票の質問において,「医者から花粉症と診断された」と回答したものを症例,それ以外のものを対照とし,6地区に分けてロジスティック回帰分析を
行った。ディーゼル車排出ガスの各種指標(EC,PM2.5,SPM,NOx)を説明変数とし,年齢・花粉量調整オッズ比を求めた。説明変数は実測値をカテゴリ化しないでそのままモデルに投入する解析を行った。さらに補足的に濃度の濃いほうから10%,20%,それ以外の3カテゴリによっても解析を行った。また,ECについては4カテゴリの解析を行った。解析は地区ごとに行うものとし,6地区は,1:大田(上池台),2:大田(馬込),3:大田(山王),4:大森西,5:昭島,6:福生とした。大気汚染物質の推計は,地区内を走行する自動車から狭域モデルにより計算された大気汚染物質の予測濃度を広域の濃度分布に重ね,各地点の濃度を求めた。花粉濃度は,広域モデルによって求めた周辺地域の推定濃度を,境界条件として狭域モデルに導入し,花粉が対象地域に流入したときの,地区内でのより詳細な濃度分布を求めた。
結果 各種指標の年齢・花粉量調整オッズ比は1に近い値をとり,有意なものはなかった。
結論 花粉症患者のほうがそうでない人より,ディーゼル排ガス濃度の高いところにより多く居住しているという結果は得られなかった。
キーワード ディーゼル車排出ガス,スギ花粉症
|
第51巻第5号 2004年5月 沖縄県と日本本土における胞状奇胎の発生頻度前濱 俊之(マエハマ トシユキ) |
目的 東アジアにおいて,台湾,フィリピン,インドネシアの胞状奇胎の頻度が日本より高いことが報告されている。この研究の目的は台湾に近い沖縄県の胞状奇胎の発生頻度を解析し,日本本土より高いかどうか比較検討することである。
方法 日本における全国的な絨毛性疾患の調査は日本産科婦人科学会が主導し,1974年に登録の実施が開始され,現在まで22の都道府県が参加している。本研究では沖縄県の1986年から1995年まで登録された絨毛性疾患の症例を検索し,人口10万人,出生1,000人に対する発生率を求めた。そして,日本本土の21の都道府県のそれと比較検討した。
結果 沖縄県において10年間で,417例の胞状奇胎が登録されている。また,同じ10年間で13,322例の胞状奇胎が21の都道府県で登録されている。人口10万人に対する胞状奇胎の発生率は日本本土より沖縄県において有意に高い(p=0.011)にもかかわらず,出生1,000人に対する発生率に有意差は認められなかった(p=0.81)。この10年間の沖縄県における胞状奇胎の頻度は徐々に減少し,1995年は出生1,000人に対し約1.5となっている。
結論 沖縄県の出生1,000人に対する胞状奇胎の発生頻度は日本本土と比較し高くないことが示された。この結果は,胞状奇胎発生に対して環境因子が人種因子より重要であるとは言えないことを示唆している。
キーワード 胞状奇胎,沖縄諸島,環境因子,人種因子
|
第51巻第5号 2004年5月 栃木県脳卒中One Day調査の公的調査との整合性の検討菅野 靖司(スガノ ヤスジ) 須賀 万智(スカ マチ) 杉森 裕樹(スギモリ ユウキ)田中 利明(タナカ トシアキ) 高田 礼子(タカタ アヤコ) 吉田 勝美(ヨシダ カツミ) 中村 俊夫(ナカムラ トシオ) |
目的 栃木県脳卒中One Day調査は,脳血管疾患の病院病床への負担と予後の経時的変化を明らかにすることを目的に,平成7年1月から行われている。本研究では,同One Day調査と公的調査との整合性を検討した。
対象と方法 栃木県脳卒中One Day調査は栃木県内のすべての病院(約120施設)を対象に毎年1月と8月に栃木県の委託を受け栃木県病院協会が実施している,郵送法による質問紙調査である。調査内容は,病床数,調査当日の入院患者数,入院患者のうち脳卒中患者の年齢,性別,診断名,初発/再発の別,状態,機能,予定等である。平成8年1月から平成14年1月までの計13回で,回答の得られた平均95.5施設について,病床数,脳卒中入院患者数を集計し,厚生労働
省の患者調査,同医療施設調査,栃木県脳卒中登録の値と比較した。また初発/再発別の割合についての年次推移,脳卒中登録との比較,1月と8月の比較,診断名別病床負担率についての年次推移,診断名の割合の脳卒中登録との比較,1月と8月の比較について検討を加えた。
結果と考察 13回のOne Day調査の結果,病院数は平均81.2%,病床数は平均80.4%と高い回収率が得られ,1病院当たりの平均病床数は188.2床であり,医療施設調査から求められる190.1床と近い値であった。栃木県の全病床に占める脳卒中患者の割合は平均13.1%であった。患者調査と医療施設調査から,栃木県の脳血管疾患患者の病床負担率を計算すると,平成8年10.7%,平成11年12.2%であり,一方One Day調査の結果は平成8年11.1%,平成11年13.2%と大きな
差異を認めなかった。また,One Day調査から得られた脳卒中患者数を医療施設調査の病床数で補正すると,平成8年2,483人,平成11年2,928人であり,患者調査の脳血管障害の推計入院患者数平成8年2,400人,平成11年2,700人に近い値が得られた。以上から,栃木県脳卒中OneDay調査は信頼性のおける調査と考えられた。初発/再発別の割合では初発の割合が平均62.6%であり,再発の割合が平均28.2%であった。脳卒中患者の病床負担率は増加傾向を認め,診断名の内訳は脳梗塞が69.1%,脳出血が17.9%,くも膜下出血が5.5%を占めた。One Day調査は,栃木県下の全病院を対象にした調査であり,脳卒中入院患者数の実数を把握することができ,救急医療や療養などの医療福祉資源の構築や配分を検討,計画していく上で有用性が期待される。
キーワード 脳卒中,疫学,One Day調査,病床負担,有病率
|
第51巻第5号 2004年5月 わが国におけるDOTSの費用対効果分析-大阪市住所不定者を1モデル集団として-木村 もりよ(キムラ モリヨ) |
目的 経済状態の悪化に伴い,結核は再興感染症として復活し,特に,住所不定者居住地区を中心とした都市部の罹患割合は高く,社会問題となっている。大阪市のあいりん地区は罹患割合535(人口10万対)とネパールに匹敵するほどである。このような地区の住所不定者における治療中断失敗割合は一般人口と比べて著しく高い。1999年,あいりん地区では病院・保健所間連携を強化した日本型DOTS(直接監視下短期治療)としてDOTSが開始され,大阪市全域に拡大しつつある。本研究では,大阪市の住所不定者,塗抹陽性初回登録患者を対象として非DOTS群とDOTS群の費用対効果分析結果を比較検討することを目的とする。
方法 1993年から1995年までの,あいりん地区塗抹陽性新登録患者529名を「非DOTS群」,2000年の大阪市住所不定者塗抹陽性新登録患者219名を「DOTS群」として費用対効果分析を行った。
結果 DOTSの導入により,治療失敗中断割合は25.7%から5.0%へ低下し,平均入院期間も5.5か月から2か月へ短縮された。失敗中断は40~49歳の年齢層で最も高く,年齢が上がるにつれて低下傾向にある。年齢調整を行った費用対効果分析では,非DOTS群に比べてDOTS群がQALY当たりの費用対効果が高かった。また,DOTS導入による1人年額約65万円,総数で約1億4000万円の費用節約が可能と計算された。分析結果は,DOTS群の中断失敗割合とDOTSの費用に対してセンシティヴであった。
結論 本研究での分析結果から,大阪市住所不定者,塗抹陽性初回登録者に対するDOTSは非DOTSよりも費用対効果が良いことが示された。この結果は,節約可能な費用をシェルター建設などの下層構造改善に役立てることにより,DOTSが結核問題の解決を促進することを提言しようとするものである。
キーワード 住所不定者の結核,DOTS,費用対効果分析
|
第51巻第5号 2004年5月 韓国における外来看護師のバーンアウト趙 敏廷(チョウ ミンジョン) |
目的 看護師のストレスに関する先行研究を俯瞰すると,病棟看護師を対象にしたものは多いが,外来看護師に関するものは韓国においてもほとんどみられない。本研究では,外来看護師のメンタルヘルスの観点から,ストレスの典型例であるバーンアウトに焦点を置いて検討することを目的とした。
方法 韓国・ソウル市内の総合病院に勤める外来看護師に対して留置調査を行い,319人から得られた回答をもとに分析を行った。バーンアウト尺度はMBI(Maslach Burnout Inventory)を翻訳・修正した田尾・久保(1996)の尺度を用いた。
結果 因子分析の結果,いくつかの先行研究から支持を得ている「情緒的消耗感と脱人格化」,「個人的達成感の後退」の2因子が抽出された。階層的重回帰分析の結果,情緒的ネットワーク・サポート,コーピング,職務ストレッサーが「情緒的消耗感と脱人格化」,「個人的達成感の後退」へ及ぼす影響の有無について明らかになった。「情緒的消耗感と脱人格化」については,情緒的ネットワーク・サポートを構成する“仕事への支持者”とコーピングを構成する“問題回避型”“対人依頼型”,職務ストレッサーを構成する“業務遂行に関する対人関係”に有意な影響が認められた(β=-0.277,p<0.001;β=0.139,p<0.05;β=-0.145,p<0.05;β=0.264,p<0.01)。一方,「個人的達成感の後退」については,情緒的ネットワーク・サポートを構成する“仕事への支持者”とコーピングを構成する“認知操作型”“対人依頼型”,職務ストレッサーを構成する“業務遂行に関する対人関係”に有意な影響が認められた(β=-0.241,p<0.001;β=-0.132,p<0.05;β=-0.234,p<0.001;β=0.247,p<0.01)。
結論 韓国における外来看護師のバーンアウトの実態は,2~3割の者が要注意・危険領域に達していることが推察された。バーンアウトは2因子構造を示したが,より明確にする必要性が認められた。影響因として,問題回避型のコーピング,業務遂行に関する対人関係,仕事への支持者,対人依頼型コーピング,認知操作型コーピングが特定された。
キーワード 韓国,外来看護師,バーンアウト,ストレス,因子分析,階層的重回帰分析
|
第51巻第5号 2004年5月 介護予防の経済評価に向けたデータベース作成-高齢者の自立度別の医療・介護給付費-吉田 裕人(ヨシダ ヒロト) 藤原 佳典(フジワラ ヨシノリ) 熊谷 修(クマガイ シュウ)新開 省二(シンカイ ショウジ) 干川 なつみ(センカワ ナツミ) 土屋 由美子(ツチヤ ユミコ) |
目的 増加を続ける老人医療費・介護給付費の削減に向けて,介護予防事業による効果が期待されている。本研究では,群馬県草津町を事例として,70歳以上高齢者の老人医療・介護給付費を自立度別に算出し,その将来推計を行い,介護予防事業の経済評価を行うためのデータベース作成を行った。
方法 群馬県草津町において,平成13年10月~11月に実施した高齢者健康調査(対象:70歳以上の全住民1,039人)の結果と,70歳以上高齢者の医療および介護保険の利用状況(平成13年10月~平成14年9月)をレコードリンケージし(個人情報保護のため,個人を特定できない形式で同町からデータを入手),総合的移動能力尺度(1=遠出可,2=近隣可,3=少しは動ける,4=あまり動けない,5=寝たり起きたり,6=寝たきり,7=入院・入所)別に老人医療・介護
給付費を算出した。次に,総合的移動能力尺度のランク1を自立,ランク2を要支援,ランク3~7を要介護者と仮に定義し,それぞれの群における老人医療費・介護給付費/人/月を,性・年齢階級別に算出した。最後に,健康調査で明らかになった性・年齢階級別の要支援および要介護者の出現率が今後とも一定と仮定して,平成12年簡易生命表をもとに推計した性・年齢階級別将来人口に掛け合わせることにより,要支援および要介護高齢者数の将来推計を行った。これらをもとにして,同町全体の老人医療・介護給付費の将来推計を行った。
結果 群馬県草津町の70歳以上高齢者における要支援および要介護者の人数割合は,それぞれ15.9%,19.6%に過ぎないが,同町の総老人医療費に占める割合は16.8%,47.0%,同介護給付費に占める割合は9.9%,85.3%であった。また,要支援・要介護高齢者の中でも障害のランクが高くなるほど,1人当たりの老人医療費と介護給付費はともに高くなっていた。老人医療費・介護給付費/人/月を性・年齢階級別にみると,男女ともに要介護へと自立度が低下することに
より,医療・介護給付費が大きく増加することが認められた。同町においては,10年後(平成23年)には,要支援および要介護者数はそれぞれ,244人(平
成13年に比べ約1.5倍),311人となり(同約1.6倍),これに伴って70歳以上の老人医療費は約11億円となり(平成13年に比べ約1.6倍),要介護者の老人医療費はその47.6%を占めると推計された。また,介護給付費は約3億円となり(同約1.6倍),要介護者の介護給付費はその85.0%を占めると推計された。
結論 自立を維持し,重篤化を先送りすることが高齢者の医療・介護コストの低減につながる可能性が示唆された。医療・介護給付費削減的な介護予防事業を実現するためには,地域で多くを占める自立した高齢者に対して生活機能の維持を働きかけるとともに,老年症候群(高齢による虚弱,転倒,痴呆,低栄養など)のハイリスク者の早期発見(スクリーニング)と早期対応が重要である。
キーワード 介護予防,経済評価,医療費,介護給付費,データベース,将来推計
|
第51巻第6号 2004年6月 全国保健所におけるたばこ対策実施状況調査の
|
目的 健康日本21において生活習慣病対策の一つとしてたばこ対策には重要な役割が与えられており,保健所が果たす役割は大きいと考えられる。全国の保健所を対象に昭和62年と平成3年に厚生省(当時)が,平成7~9年に国立公衆衛生院疫学部(当時)がたばこ対策実施状況調査(以下「前回の調査」)を行ったが,その後行われておらず,また健康日本21によってたばこ対策が変化していると考えられることから,全国の保健所におけるたばこ対策実施状況調査を行った。
方法 調査対象は全国592保健所(平成13年11月現在)とし,平成13年12月に自記式調査票を所長あてに郵送し,回答を求めた。督促を1回行った。回収率は94.4%(592保健所のうち559から回答)であった。
結果 (1)たばこ対策を実施した保健所は県型保健所(以下「県型」)の83%,県型以外の保健所(以下「県型以外」)の79%で前回の調査に比べて増加した。たばこ対策と喫煙実態調査を行った保健所は前回の調査に比べて増加し,県型は46%で,県型以外は33%であった。(2)たばこ対策の対象のうち最も多いものは,県型の76%が学校,県型以外の60%が地域であった。(3)保健所長の喫煙率は男22%,女3%,職員の喫煙率は男31%,女10%であった。所長の喫煙状況と保健
所のたばこ対策実施状況には関連はなかった。
結論 喫煙状況調査を行い,管内の喫煙実態を把握した上で,たばこ対策を実施している保健所は十分に多いとは言えない。保健所単独で実施できるたばこ対策は実施しているが,市町村,関連団体,事業所などとの調整,連携が必要なたばこ対策は十分に実施できていない。しかしながら保健所においてたばこ対策は劇的ではないが進みつつある。
キーワード 保健所,たばこ対策,実態調査
|
第51巻第6号 2004年6月 2003/04年シーズンにおける
延原 弘章(ノブハラ ヒロアキ) 渡辺 由美(ワタナベ ユミ) 三浦 宜彦(ミウラ ヨシヒコ) |
目的 インフルエンザワクチンの計画的な供給に資することを目的として,2003/04年シーズンのインフルエンザワクチンの需要予測を行った。
方法 インフルエンザワクチン供給に実績のある医療機関等5,245施設を対象として,2002/03年シーズンのインフルエンザワクチンの購入本数,使用本数,接種状況および2003/04年シーズンの接種見込人数について調査を行い,2003/04年シーズンのインフルエンザワクチン需要見込本数の推計を行った。
結果 2003/04年シーズンのインフルエンザワクチン需要は,約1244万本から約1308万本と推計された。
結論 2003/04年シーズンのワクチンメーカーの製造予定数は1445万本であり,需要に見合う量の供給が行われるものと推測された。
キーワード インフルエンザワクチン,需要予測
|
第51巻第6号 2004年6月 居宅介護支援事業所の特性と介護保険における住宅改修村上 浩章(ムラカミ ヒロアキ) 高木 安雄(タカギ ヤスオ) 萩原 明人(ハギハラ アキヒト) |
目的 ケアマネージャーと建築事業者との連携によって,介護保険による住宅改修がどのように進められているかを把握するため,居宅介護支援事業所の特性と住宅改修に関する要因との関連を調査した。
方法 調査対象は,2003年9月時点で福岡市介護保険事業所検索システムで検索された居宅介護支援事業所(185か所)である。調査方法は,自記式質問票を用いた横断調査で,郵送法により行った。調査期間は,2003年10月9日から30日であった。調査項目は,居宅介護支援事業所の特性と住宅改修に関する要因である。居宅介護支援事業所の特性と住宅改修に関する要因との関
連をχ2検定によって検討した。
結果 有効回収率は47.0%(87事業所)であった。事業所の設立主体,所在地,規模(ケアマネージャー数)といった要因と,住宅改修に関する要因(セミナーや勉強会への参加,保険適用外分野の利用者ニーズへの対応,介護保険住宅改修費支給手続きの代行,クレーム対応等)との間に関連がみられた。さらに,ケアマネージャー1人当たりの平均改修件数が多い事業所ほど相談できる建築事業者数が多く,相見積もりを取る頻度が高かった。
結論 介護保険による住宅改修は,医療・福祉職が主であるケマネージャーにとって専門外であるにもかかわらず,ほとんどのケアマネージャーに関与の経験があり,相談できる建築事業者をもっていた。制度が始まってから日が浅いにもかかわらず,居宅介護支援事業所の規模や設立主体といった特性によって,住宅改修のプロセスで差異がみられた。本来,制度の趣旨は,住宅改修によって,利用者である要援護者やその家族に安価で質の高い住環境を提供することで
ある。今後,要援護者がたまたま利用することになった居宅介護支援事業所によって,提供さ
れる住宅改修の結果に差が生じることのないよう,行政や立法の関与が必要になると思われる。
キーワード 住宅改修,居宅介護支援事業所,ケアマネージャー,介護保険
|
第51巻第6号 2004年6月 運動教室参加による「閉じこもり」改善効果-精神健康度・体力との関連より-奥野 純子(オクノ ジュンコ) 徳力 格尓(デリ ギリ) 村上 晴香(ムラカミ ハルカ)松田 光生(マツダ ミツオ) 久野 譜也(クノ シンヤ) |
目的 「閉じこもり」は,将来,寝たきりや痴呆に発展する危険性が指摘されている。われわれの先の研究結果からも,「閉じこもり」者は精神健康度が低く,体力,特に歩行能力が低いことが示唆された。本研究では,運動教室が「閉じこもり」を解消するかどうか検討し,精神健康度・体力との関連を検討し,介護予防事業の資料とすることを目的とした。
方法 対象者は,3市町が実施する運動教室へ参加した,医師から運動を止められていない184名であった。参加者は個別プログラムを提供され,教室では筋力トレーニング,トレーニングバイクによる有酸素性運動,ストレッチングを週2回,自宅では筋力トレーニングとストレッチングを週3回実施し,ウォーキングは毎日行った。アンケート調査と文部科学省の体力テストを開始月と3か月目に実施した。血圧は教室参加時に測定し平均を求めた。アンケート項目は,
属性,外出頻度,老研式活動能力指標,精神健康度(GHQ-12),自己健康感,体力への不安であった。
結果 開始時,「閉じこもり」者は11名(6.0%),低い精神健康度の者は15名(8.2%)であった。運動開始3か月目には,約7割が「閉じこもり」を解消しており,低い精神健康度であった者も,全員,高い精神健康度に改善していた。悪化群は,改善群に比べて,男性・変形性膝関節症を治療中の者の割合が有意に高く,手すりや壁を使わず階段を昇ることができる者の割合が有意に低かった。「閉じこもり」改善群では,歩行数,体力が向上していたが,悪化群ではこれ
らの改善がみられなかった。
結論 地域高齢者が,個別プログラムに基づいた運動教室に参加することは,体力の向上・精神健康度の改善をもたらし,「閉じこもり」改善に効果があることが示唆された。さらに,男性や膝に問題のある者を対象としたプログラムを提供することも「閉じこもり」改善の対策として検討する必要があると思われた。
キーワード 閉じこもり,運動教室,体力,精神健康度,高齢者,介護予防事業
|
第51巻第6号 2004年6月 虐待が子どもの発達に与える影響-児童養護施設における発達検査結果の分析-野津 牧(ノヅ マキ) |
目的 本研究は,児童養護施設に入所している児童を対象に発達検査を実施することにより,不適切な養育環境で育った子ども,虐待を受けた子どもが発達面でどのような影響を受けているのかについて検証する目的で実施した。
方法 調査施設と調査期間;A児童養護施設(1996~2000年),B児童養護施設(2002年7月・2003年7月),C児童養護施設(2003年8月)。検査方法;A・B児童養護施設は新版K式発達検査,C児童養護施設は児童相談所が実施した田中ビネー式,WISC-R。対象と虐待の内訳;A児童養護施設15名,B児童養護施設36名,C児童養護施設17名。被虐待児46名,虐待以外の理由22名,計68名。虐待種別は,主たる虐待はネグレクト(保護の怠慢・拒否)32名,身体的虐待13名(各複数の虐待を含む),心理的虐待1名,性的虐待単独はなし。
結果 入所理由にかかわらず児童養護施設入所児童の発達指数は低い(平均81)。被虐待児と虐待以外の理由による入所の比較では,虐待を受けた子どもの発達指数が低い(同75:91)。また,虐待を受けた子どもは,認知面と言語面との差があるが,虐待以外の理由により入所した子どもでは差はみられなかった。虐待種別では,ネグレクト(保護の怠慢・拒否)の子どもの発達指数が低い(同71)。一定期間後に再検査した20名のうち,発達指数が10ポイント以上改善した児
童は3名で12名がほとんど変化なし,5名が10ポイント以上下がっており,養育環境が改善しても発達指数の面ではあまり改善がみられない。
結論 児童養護施設に入所している子どもの多くが発達面で影響を受けており,虐待を受けた子ども,特にネグレクトの子どもに顕著に現れている。また,情緒面で影響の大きいと思われる子どものなかに発達のバランスの悪い子どもが多くみられる。このことから,虐待を受けた子ども,不適切な養育環境のもとで育った子どもに対する援助では,発達という視点で援助に当たることが重要と思われる。
キーワード 児童養護施設,虐待,ネグレクト,発達
|
第51巻第7号 2004年7月 福祉政策の費用・効果分析-墨田区のショートステイを事例として-塚原 康博(ツカハラ ヤスヒロ) |
目的 黒田区のショートステイを取り上げ、イギリスで行われている「福祉の生産アプローチ」に基づく費用関数の推定を試み、費用対効果の観点からショートステイの有効性を検証した。
方法 墨田区に在住する介護保険の要支援・要介護の認定者を対象として2002年に実施された2回のパネル調査から得られたデータを用いて、福祉の生産アプローチに基づく分析を行った。具体的には、墨田区におけるショートステイの費用関数を重回帰式を用いて推定した。被説明変数に、要介護高齢者が利用したショートステイの費用を、説明変数に、要介護高齢者が利用したショートステイから主介護者が得る満足度の変化、その2乗、要介護者の初期のADLとその変化、主介護者の初期の健康状態とその変化を使用した。
結果 推定結果は以下のとおりである。(1)ショートステイから主介護者が得る満足度の差とショートステイの費用との間に有意に正の関係がある。(2)要介護者のADLとショートステイの費用との間には有意に負の関係がある。(3)主介護者の健康悪化とショートステイの費用との間には有意に正の関係がある。
結論 ショートステイの費用は、要介護者側の事情と主介護者側の事情の両方から影響を受けており、ショートステイへの費用投入は、主介護者の介護負担の軽減を通じて、主介護者の満足を増加させる可能性が示唆された。これによって、ショートステイの政策効果の有効性と介護サービスの政策評価に福祉の生産アプローチが有効に適用できる可能性が示された。
キーワード ショートステイ、福祉の生産アプローチ、費用・効果分析、政策評価
|
第51巻第7号 2004年7月 健康関連QOLの向上を目指した健康づくりの展開斉藤 功 (サイトウ イサオ) 伊南 冨士子(イナミ フジコ)池辺 淑子(イケベ トシコ) 森脇 千夏(モリワキ チナツ) |
目的 30歳以上の住民に対する悉皆調査から、健康関連QOL(クオリティー・オブ・ライフ)に関連する生活習慣等の要因を抽出し、その現状把握と今後の健康づくりの展開に資することを目的とした。
方法 大分県M町の住民基本台帳に基づく30歳以上人口3,108人(平成14年11月1日現在)のうち、入院中等を除く2,870人を調査対象とした。基本的事項(家族構成、職業)、生活習慣、食習慣、食物摂取頻度、健診受診状況、生活習慣病、ADL(日常生活動作能力)、IADL(老研式活動能力指標)、健康関連QOLに関する154項目からなる調査票を作成し、留置式アンケートを実施した(有効回答数2,695人、有効回答率93.9%)。健康関連QOLは、SF-36日本語版を用い、日常役
割機能(身体)、全体的健康感、活力、日常役割機能(精神)、心の健康の5つの下位尺度について標準化された偏差得点(基準値=50、標準偏差=10)を算出した。
結果 M町のSF-36下位尺度別の偏差得点は、男性の総数でみると、日常役割機能(身体)47.1点、全体的健康感48.2点、活力48.1点、日常役割機能(精神)48.3点、心の健康47.9点であった。女性の総数では、それぞれ46.3点、47.1点、47.3点、47.1点、47.4点であった。男女とも全国平均よりも低い得点であり、男性では65~74歳の各尺度の得点が比較的高かった。75歳以上になると、男女とも日常役割機能(身体)と日常役割機能(精神)が低下した。本調査から把握した各生活習慣等の項目と健康関連QOLとの関連を検討したところ、1)寝不足を感じている(男19.5%、女26.5%)、2)運動をほとんどしていない(男55.2%、女57.0%)、
3)多量飲酒(飲酒者のうち:男15.4%、女3.1%)、4)欠食をする(男23.6%、女16.4%)、5)20本以上の歯の喪失(男49.6%、女55.3%)、6)糖尿病治療中(男4.3%、女3.4%)、7)IADLの低下(65歳以上のうち:男14.7%、女21.8%)、を有する者の健康関連QOLが低下した。
結論 上記の7つの要因の改善へ向けた取り組みは、地域においてQOLの向上を目指した具体的な健康づくりを展開するためのキーになる。
キーワード 健康関連QOL、SF-36、地域住民、生活習慣
|
第51巻第7号 2004年7月 「虐待」に関する保育者の意識と経験土屋 葉(ツチヤ ヨウ) 春原 由紀(スノハラ ユキ) |
目的 個々の虐待ケースに対応する保育者の意識と経験を分析し、保育者支援のあり方を探る。
対象と方法 千葉県、東京都の保育所に勤務する保育者2,000人を対象とし、両都県内の公立・私立保育所に返信用封筒を添付して質問紙を郵送、回収した。調査期間は2002年10月~12月である。
結果 約7割の保育者がなんらかの「虐待のきざし」に出会っていた。とくに「衣服や身体がいつも不潔な子ども」や「子どもに冷淡な態度で接している保護者」に多く出会っていた。一方、約4割の保育者が「虐待ケース」を担当した経験を有していた。保育者の多くは誰かに相談し、協力相手・機関を得ながら対応しており、多種多様な職種との連携もうかがわれた。通告を行った保育者は40.8%であった。通告をしなかった理由は「ほんとうに虐待なのかが判断できなかった」、「保護者と十分に話し合いをかさねて改善した」などであった。「手や足に不自然な傷が絶えない子ども」「服を脱ぐのを異常にこわがる子ども」「身体接触を
極端に嫌がる子ども」「「子どもが自分になつかない」と頻繁に口にする保護者」、「家族のなかで暴力を受けている保護者」「体罰を「しつけ」であると思っている保護者」は「虐待ケース」として認識されやすく、逆に「衣服や身体がいつも不潔な子ども」「食が細い、盗み食い、食べ過ぎなど食行動に問題をもつ子ども」「病気ではないのに身長や体重が増えない子ども」は「虐待ケース」としてみなされにくかった。「虐待ケース」に対応するなかでケース会議が開かれた
場合、保育所は他機関と連携していくことに困難を抱えていた。とくに情報共有にかかわる問題があった。
結論 「虐待」にかかわる保育者の困難は、「虐待」の発見・通告にかかわる困難、保護者・子どもへの支援にかかわる困難、他機関との連携にかかわる困難の3つがあることがわかった。これらはいわゆる虐待問題の広がりとともに、新たに設けられた保育者の役割にかかわるものである。保育者が対応していくためには、保育者を支えるための機能、保育所が他機関と連携していくためのコーディネート機能の設置が必要不可欠である。
キーワード 保育者、子ども、虐待、保育所、連携、児童相談所
|
第51巻第7号 2004年7月 介護サービスに対する家族介護者の意識と評価に関する分析黄 京蘭(ファン ギョンラン) 関田 康慶(セキタ ヤスヨシ) |
目的 (1)介護保険導入前後における介護の社会化に関する家族介護者(以下「介護者」)の意識変化について明らかにする。(2)介護者の介護負担感軽減の程度を明らかにする。(3)介護の社会化に関する介護者の意識(「家族介護重視」「抵抗感」「世間体」)と介護負担感軽減程度の関連性を明らかにする。
方法 介護の社会化に関する介護者の意識と介護負担感軽減程度の関連性を「介護者の意識と評価DB001」データベース(2001年作成、介護者735名)を用いて分析する。分析項目は、前記の3つの介護者意識と介護負担感軽減の程度、介護者および要介護者の属性である。介護保険導入前後の意識変化を明らかにするために、導入前後の意識をクロス分析し、χ2検定を行った。また、介護者の意識と介護負担感軽減程度の関連性を明らかにするために、介護者の意識を4群(「家族中心の介護」群、「介護の社会化肯定」群、「介護の社会化肯定へ変化」群、「家族中心の介護へ変化」群)に分け、分布関数分析を行った。
結果 介護者の大部分が女性であり、65歳以上の介護者の34.8%が老老介護の状態であった。介護者の46.7%が「1日中ほとんど介護している」と回答し、重度(要介護度4、5)の要介護者を抱えている介護者も全体の5割を超えていた。介護保険のサービス利用により、介護者の意識は家族中心の介護観から介護の社会化を肯定する介護観に有意に変化していた(p<0.01)。同サービス利用により介護負担感が減ったと評価した介護者は全体の半数以上であった。介護者の意
識と介護負担感軽減程度の関連分析では、3つの介護者意識ともに、「介護の社会化肯定へ変化」群が他の群より介護負担感が減っていることが判明した。
結論 介護者が家族の絆を大切にしながら在宅介護を続けるために、介護負担を少しでも軽減することを目的としている家族介護支援事業の実施市町村の拡大や、事業対象者に対する広報活動、緊急時のショートステイ、小規模多機能施設の整備や活用などが求められる。また、従来の物理的支援に加え、精神的な支援など様々な活動を行うソーシャルサポートネットワークの地域支援情報システムの整備、活用、運営が必要であり、その拠点として在宅介護支援センターの整備や活動が重要である。ケアマネジャーには地域資源の有効な利用、地域社会との連携や統合などの機能向上が求められる。
キーワード 介護保険、介護の社会化、家族介護者、介護者意識、介護負担感、精神的支援
|
第51巻第8号 2004年8月 医師臨床研修制度義務化に伴う地域医療への影響の検討-福岡県メディカルセンターによる病院調査の結果から-大河内 二郎(オオコウチ ジロウ) 堀口 裕正(ホリグチ ヒロマサ) 鍋島 史一(ナベシマ フミカズ)佐藤 彰記(サトウ アキノリ) 横倉 義武(ヨコクラ ヨシタケ) 陣内 重三(ジンノウチ ジュウザブ) 松田 峻一良(マツダ シュンイチロウ) 伊東 清四郎(イトウ セイシロウ) 堤 康博(ツツミ ヤスヒロ) |
目的 2004年4月から新医師卒後臨床研修が施行されると、研修医の病院外での勤務が制限される。福岡県メディカルセンターでは、新医師卒後研修の影響を明らかにする目的で、福岡県内の病院に対して、この新臨床研修への参加予定の有無および大学から派遣されている医師数、研修医数を調査した。この調査では、新臨床研修に参加する病院と参加しない病院の特徴や、これらの区分における大学派遣医数、研修医数を定量的に記述し、新臨床研修制度が地域医療を担
う医師数にどのような影響を与えるか推察した。
方法 福岡県の開設者別病院名簿(2003年1月現在)をもとに県内の全484病院に対し、2003年2月、郵送によるアンケート調査を行った。調査内容は、新臨床研修への参加予定状況、病院の属性、業態別(常勤、非常勤の外来、当直、日勤)の大学からの派遣医数、研修医数等であった。
結果 対象病院のうち324病院から回答を得た(回収率67%)。このうち、大学付属病院等9病院と回答に不備があった8病院を除いた307病院(県内全病院に対して63%)を用いて検討を行った。これらのうち48病院(16%)が新医師卒後臨床研修の指定を受ける予定であると回答した。これらの病院の73%は、現在臨床研修を行っているか、各種学会の臨床研修病院の指定を受けていた。回答病院における全常勤医師数は4,349人であり、このうち医科大学から派遣された医師は1,915
人(全常勤医の44%)であった。また大学から派遣された研修医は234人(同5%)であった。大学から派遣された医師に占める常勤の研修医の割合は12%であった。一方、新臨床研修の指定を受ける予定がない187病院(61%)における常勤医師数は1,339人で、このうち大学派遣医数は447人(全常勤医の33%)であった。これらの病院での大学派遣医に占める研修医の割合は、常勤6%、非常勤の外来診療8%、非常勤の当直15%、非常勤の日勤診療15%であった。
結論 研修医のアルバイトの禁止により影響を受ける医療機関は比較的少なく、新医師卒後臨床研修の実施に伴って勤務医師数が大幅に減る医療機関は例外的であると考えられた。一方、福岡県内の病院は派遣医師の多くを大学に依存していた。したがって、新卒後臨床研修の実施に伴い大学派遣医師の引き上げが起きれば、その影響は無視できないと推察された。
キーワード 医師数、研修医、卒後研修、病院、地域医療、大学病院
|
第51巻第8号 2004年8月 国民栄養調査を用いたわが国の成人飲酒者割合、多量飲酒者割合の推計尾崎 米厚(オサキ ヨネアツ) 松下 幸生(マツシタ サチオ) 白坂 智信(シラサカ トモノブ)廣 尚典(ヒロ ヒサノリ) 樋口 進(ヒグチ ススム) |
目的 わが国の成人の飲酒者割合と多量飲酒者割合を、既存統計を活用して推計するために国民栄養調査の原データ(1990~1999年の10年間)を利用して解析を行った。
方法 研究に用いた資料は国民栄養調査の原データの磁気テープである。国民栄養調査のうち、保健師らが20歳以上の者を対象に問診して飲酒状況を把握した身体状況調査票に基づき飲酒者を定義した。飲酒者は、飲酒習慣があると回答した者、多量飲酒者は、飲酒量が平均3合(日本酒換算)以上の者とした。飲酒者割合等の算出には、直接法による年齢調整を実施した。基準人口には、1990(平成2)年の国勢調査確定数の総人口を用いた。
結果 国民栄養調査のデータのうち23%(1990~1999年)は飲酒習慣が不明であった。これらを除くと、1999年の年齢調整飲酒者割合は、男51%、女8%であった。1999年の多量飲酒者割合は、男7%、女0.4%であった。飲酒者割合の推計を行って以下のような問題点が指摘された。①調査の回答率が不明で調査の信頼性に問題がある、②飲酒習慣の定義が必ずしも国際的ではない、③都道府県によっては調査対象地域が1か所であるため都道府県別分析には適さない、④面接
調査であるにもかかわらず、「不明」が多い、⑤女性の多量飲酒者数が少なく詳しい解析ができない、⑥飲酒者割合が1995年に急増しており、理由がはっきりわからない、⑦地域ブロック別分析の結果が、一般常識的にみた酒どころに一致しない等であった。
結論 国民栄養調査を用いたわが国の成人飲酒者割合、多量飲酒者割合の推計には問題点が認められ、成人の飲酒者割合を明らかにするためには、それを直接目的とした全国を代表するような調査が必要であるといえる。
キーワード 飲酒、栄養調査、疫学、ライフスタイル
|
第51巻第8号 2004年8月 家庭内暴力における暴力の双方向性と連鎖についての研究-個人のライフコースの視点から-山西 裕美(ヤマニシ ヒロミ) 山﨑 きよ子(ヤマサキ キヨコ) |
目的 1980年代の日本では、子どもから親への暴力は家庭内暴力と呼ばれ、家庭病理現象として問題視された。しかし、今日、家庭内では、子どもから親への暴力だけでなく、ドメスティック・バイオレンスをはじめ、児童虐待・老人虐待など様々な種類の暴力が起こっていることが表面化してきた。本研究は、このような家庭内における暴力の仕組みについての解明と考察を行うことを目的とした。
方法 平成14年3月から7月にかけて、宮崎県内4市でアンケート調査を行い、家庭内暴力の被害と加害の現状などについて尋ねた。また、平成14年3月から平成15年3月の1年間にわたり、女性相談センターや市老人福祉課・在宅介護支援センター・児童養護施設などで聴き取りを行い、保護された女性や老人・児童などのケースについて検討を行った。
結果 ドメスティック・バイオレンスなど家庭内に暴力があることは、同時に子どもも暴力の対象となるだけでなく、子どもにとっては暴力の社会的学習の場となる危険性が高い。さらに、被害者である妻が、より弱者である子どもに対して、自分の受けたストレスを向けるといった“暴力の連鎖”の構造の問題がある。また、ドメスティック・バイオレンスは、年数の経過に伴って介護問題などが生じると老人虐待等の問題へ発展していくことが分かった。このように、家庭内における暴力は、個人のライフコースを通じ、色々な形態をとりながら連鎖する“暴力のスパイラル現象”を描いていくものである。
結論 現実には、家庭内で1つの問題だけが起こっているのではなく、多問題家族として問題が連鎖し、発展するという形をとっていることが判明した。しかし、現状は、老人・児童・女性に対し各機関がバラバラに対応し、情報の連携も取られてはいない。このような暴力から家族を救うためには、個人を対象とする今の支援方法から家族全体に対する支援の方法に切り替えていくべきではないかと考える。そのため、今後の課題としては、家族を対象とした相談窓口の設置が求められる。家族内で起こる様々な葛藤はどの家庭でも起こり得ることであり、このような初期の段階でのサポートによって問題の暴走を食い止めることができると思われる。
キーワード 家庭内暴力、暴力のスパイラル、暴力の連鎖、家族支援、ファミリーサポートセンター、家族保全
|
第51巻第8号 2004年8月 在宅要介護高齢者の心身機能の変化と影響要因の検討
金 貞任(キム ジョンニム) 平岡 公一(ヒラオカ コウイチ) |
目的 介護保険実施後の介護サービスを受けている在宅要介護高齢者の心身機能の程度と変化との関連や心身機能の変化に影響を与える要因を分析し、要介護高齢者の心身機能に関する課題を抽出することを目的とした。
対象と方法 2002年に東京都S区の在宅要介護高齢者を対象に訪問面接法により実施したパネル調査によって得られたデータを用いた。第1回調査の有効票は911票、パネル調査の第2回調査の有効回答は719票であり、要介護高齢者65歳以上のケース693票を分析の対象とした。分析方法として、相関関係分析とロジスティック回帰分析を用いた。
結果 ADL(日常生活動作能力)の程度が中間以上であった者はIADL(手段的日常生活動作能力)が低下しており、IADLが中間以上であった者はADLと痴呆症状が改善されていた。痴呆度が軽度であった者はADLが改善され、痴呆度が中度以上であった者はIADLが改善されていた。それらの層のなかに、改善と悪化のいずれの方向にも変化しやすい過渡的段階にある高齢者が含まれている可能性が示唆されている。また、ADL変化には、前期高齢者と訪問看護サービスの利用が有意な正の関連を示していた。IADL変化には、通所・リハビリ利用が有意な負の影響を及ぼしていた。痴呆度の変化には、短期入所の利用が有意な負の効果があった。
結論 本研究では、ADL、IADL、痴呆症状が特定の水準にある高齢者の状態を、改善と悪化の双方への変化の可能性をもつ動的な状態としてとらえることの必要性が確認された。サービス利用について、訪問看護利用を除く、他の介護サービスの利用が要介護高齢者の心身機能の変化に負の影響を及ぼしているという知見が得られた。こうした状況を踏まえ、要介護高齢者の心身機能を維持または改善できるような、新たなサービス体系の開発が今後の課題であると考えられる。
キーワード 要介護高齢者、心身機能、介護サービス、パネル調査
|
第51巻第10号 2004年9月 全国市町村におけるたばこ対策実施状況谷畑 健生(タニハタ タケオ) 尾崎 米厚(オサキ ヨネアツ) 青山 旬(アオヤマ ヒトシ)川南 勝彦(カワミナミ カツヒコ) 簑輪 眞澄(ミノワ マスミ) |
目的 たばこ対策は国民の健康の保持と増進を図るための国の健康施策として重要とされている。本研究では,市町村がたばこ対策をどのように行っているのか,また,自治体が国の健康施策をどのように反映させているのかを明らかにするために,全国の市町村に対してたばこ対策実施状況調査を行った。
方法 調査対象は全国3,239の全市町村(平成14年11月1日現在)とし,平成14年11月に市町村保健衛生主管部局担当者に調査票を送付し,自記式郵送法により調査を実施した。未回答市町村への再依頼を1回行った。調査対象3,239のうち,2,723の市町村から回答を得た(回答率84.1%)。
結果 たばこ対策を実施した自治体は政令指定都市,中核市,保健所設置市に多く,市町村と特別区で少なかった。そのうち学校,職域などの対象別に行った自治体は多く,学校と地域を対象としたのは政令指定都市,中核市,保健所設置市に多かった。庁舎の分煙は十分ではなかった。また,未成年者がたばこを買いにくい環境を作っている自治体はほとんどなかった。
考察 たばこ対策は全国の市町村でまだ十分ではなかった。それは専門職の確保が困難であり,健康教育を行う適切な技術がないために健康教育を実施する上で自治体に問題がある可能性がうかがえた。このことから,現状では国の健康施策の1つであるたばこ対策は,住民の健康問題解決の方向として自治体に反映しているとはいえない可能性がある。
キーワード 市町村,たばこ対策,施策評価
|
第51巻第10号 2004年9月 長時間保育が子どもの発達に及ぼす影響に関する追跡研究-1歳児の5年後の発達に関連する要因に焦点をあてて-安梅 勅江(アンメ トキエ) 田中 裕(タナカ ヒロシ) 酒井 初恵(サカイ ハツエ)庄司 ときえ(ショウジ トキエ) 宮崎 勝宣(ミヤザキ カツノブ) 渕田 英津子(フチタ エツコ) 丸山 昭子(マルヤマ アキコ) |
目的 1歳児の5年後の発達について,長時間保育を含む保育形態,育児環境,属性等の影響を明らかにする。
方法 全国認可保育園87園にて保護者と園児の担当保育専門職に質問紙調査と訪問面接調査を実施し,追跡可能であった91名を分析対象とした。
結果 5年後の子どもの発達への性別調整後の関連要因は,生活技術で相談者がいない場合にリスクが21.4倍,社会適応で相談者がいない場合にリスクが8.7倍,入園年齢が0歳の場合に0.2倍であった。全変数投入の多重ロジスティック回帰分析では,コミュニケーションで男児を1とした場合,女児のリスクは0.09倍,社会適応では入園年齢が1歳を1とした場合,0歳のリスクは0.08倍であった。5年後の子どもの発達への有意な関連要因として,保育時間はいずれの分析でも有意とならないことが示された。
結論 認可保育園という保育の質が保障された環境では,5年後の子どもの発達と社会適応に相談者の有無が有意に関連し,保育時間の長さは関連していなかった。子育て支援においては,今後さらに長時間保育を含む多様なニーズに柔軟に対応し,相談機能の充実等,保護者の子育て機能を支える地域に開かれたサービスの充実が期待される。
キーワード 発達,社会適応,長時間保育,育児環境
|
第51巻第10号 2004年9月 累積接種率曲線導入による予防接種評価に関する研究宮地 洋雄(ミヤジ ヒロオ) 豊田 誠(トヨタ マコト) 福田 夕紀(フクダ ユウキ)岡林 久(オカバヤシ ヒサ) 一圓 四郎(イチエン シロウ) 横井 秀隆(ヨコイ ヒデタカ) 大野 賢次(オオノ ケンジ) 山脇 忠幸(ヤマワキ タダユキ) 山下 泉恵(ヤマシタ イズエ) |
目的 予防接種累積接種率を算定するコンピュータシステムの開発により,予防接種の接種月齢から,実施方法と接種行動の関係を評価することを目的とした。
方法 市町村が利用する定期予防接種管理台帳に登録されている接種歴データから,標準接種期間終了時,各月齢での累積接種率などの接種状況を簡便に計算表示できるシステムを開発し,これにより累積接種率曲線を用いた予防接種評価の方法を検討した。
結果 疾病ごとの目標値達成度確認,早期接種の状況確認ができ,地域の実情に合わせた目標の設定や,市町村ごとの達成状況の確認が可能となった。また,累積接種率曲線を用いた予防接種評価方法として,各年齢での最終の接種率や標準接種期間終了時の接種率といった,ある特定の月齢での接種率を比較する方法と,どれだけ早い月齢での接種が増えているかといった,曲線の形状を比較する方法の2つが考えられた。
結論 モデル市町の状況では,実施方法や流行による保護者などの意識の違いにより接種率が大きく異なっていた。累積接種率曲線による予防接種評価は,市町村における現在までの実施方法の変更による接種機会の変化や通知方法,広報・啓発,地域での流行状況といったことを照らし合わせながら評価分析することが特に重要である。市町村の事業や対策により,目標時期の接種率や最適な時期での接種率などに効果があったのか,それらを今回の開発システムで視覚的に確認することができ,今後の対策をたてる上での指標とすることができる。
キーワード 予防接種,累積接種率,母子保健,健やか親子,計画,評価
|
第51巻第10号 2004年9月 介護支援専門員に対する教育的・支持的
|
目的 介護支援専門員が業務の中でどのような点で悩み困っているのか,また,どのような状況にある者が悩み・困りごとをもっているのかを明らかにし,今後のサポートにおける課題を述べることを目的とする。
方法 居宅介護支援事業所の介護支援専門員400名を調査対象として,2002年8月に自記式調査票を発送。有効回答数は269通,有効回収率は67.3%となった。調査項目は,介護支援専門員と所属機関の基本特性,さらに回答者の「仕事に対する考え」と「職場の状況・環境」を設定した。介護支援専門員の「悩み・困りごと」については,教育的側面と支持的側面から項目を設定した。
分析方法は,まず「仕事に対する考え」「職場の状況・環境」,そして「悩み・困りごと」の構造を明らかにするために,それぞれ因子分析を行った。さらに,悩み・困りごとに関連する要因を明らかにするために,各要因を独立変数,因子分析によって抽出された悩み・困りごとに関する意識の因子ごとの素得点合計を従属変数とする重回帰分析を行った。
結果 因子分析の結果,「仕事に対する考え」は『業務遂行への自信』『仕事への肯定的イメージ』『仕事の負担感』の3因子に,「仕事の状況・環境」は『職場内でのサポート』『利用者との肯定的関係』『収入の十分さ』『職場外でのサポート』『業務に対する職場理解』の5因子に分かれた。また,「悩み・困りごと」は,『対人援助職の価値観についての悩み』『コミュニケーションについての悩み』『社会資源の開発についての悩み』『困難時のサポート不足に対する悩み』『ケアプランの作成についての悩み』『制度の知識についての悩み』の6因子に分かれた。さらに重回帰分析の結果,複数の悩み・困りごとに関連する要因は,『業務遂行への自信』『仕事の負担感』『職場内でのサポート』であった。
結論 重回帰分析の結果から,業務遂行への自信,仕事の負担感,職場内でのサポートの3つの側面から介護支援専門員へのサポートを考えていく必要性が示唆された。業務遂行への自信を高めるために教育体制の整備や評価の実施が,仕事の負担感を減らすために雇用条件の整備や事務作業の簡略化が,職場内でのサポートを高めるために管理者の意識改革や連携体制の整備が必要だと考えられる。その中でも特に職場内のサポートについては,身近な今後の課題である。制度が施行されて初期の段階では行政から細かく指導された事柄も,今後は職場内で上司や先輩が新人へのアドバイスやサポート役割を担うよう期待される。地域や社会の規模で介護支援専門員へのサポート体制を整備する第一歩として,職場として彼らを支えていく体制を作っていかなければならない。
キーワード 介護保険,介護支援専門員,悩み・困りごと,教育的・支持的サポート
|
第51巻第10号 2004年9月 保健機関が実施する母子訪問対象者の
鈴宮 寛子(スズミヤ ヒロコ) 山下 洋(ヤマシタ ヒロシ) 吉田 敬子(ヨシダ ケイコ) |
目的 保健機関で実施されている母子訪問の対象者について,産後うつ病などのメンタルヘルスの実態を把握し,地域母子保健における精神保健対策の必要性を検討した。
方法 出産後120日以内の母親を対象とした母子訪問時に,エジンバラ産後うつ病質問紙票(以下「EPDS」),産後うつ病発症のハイリスク因子に関する質問票,赤ちゃんへの気持ち質問票および虐待のリスクに関連する追加設問に母親が自己記入した。
結果 全国12地域(38保健機関)から協力が得られ,総計3,370人が調査を完了した。全対象者中,産後うつ病スクリーニングの区分点とされているEPDSが9点以上であった母親の比率は13.9%であった。訪問時産後日数でみると,9点以上の高得点者(高得点群)の頻度は,出産後28日以内が19.2%と最も高かった。高得点群では,赤ちゃんへの気持ち質問票の全10項目中6項目で否定的な気持ちを表す母親の比率が有意に高く,ほとんどの項目は乳児への拒絶や怒りに関連していた。虐待のリスクに関する追加設問の結果は,虐待傾向を疑われた母親の割合は高得点群において3.2%で,低得点群の2倍近い頻度であった。
結論 産後うつ病を疑われるEPDS9点以上の母親は,出産後120日以内に13.9%存在し,EPDSの高得点者は産後早期ほど高い傾向にあった。EPDS高得点群では,愛着障害を示唆する赤ちゃんへの気持ち質問票得点が高く,『虐待傾向』を疑われる母親の頻度も有意に高い結果となった。保健機関のスタッフによる精神面支援の観点からは,母子訪問をより早い時期に実施することによって,母親の精神保健のニーズを早期に見いだし,時期を逃さず支援することが可能になると考えられた。
キーワード 産後うつ病,愛着障害,EPDS
|
第51巻第11号 2004年10月 確率数理モデルを用いたSARS対策の評価-大阪の事例の検討-大日 康史(オオクサ ヤスシ) 菊池 宏幸(キクチ ヒロユキ) |
目的 本研究では、2003年5月における台湾人医師の国内移動に伴う患者発生の可能性を、確率数理モデルを用いて検証し、公衆衛生的対応が感染抑制にどの程度貢献していたかを検討する。
方法 人口を一定とした確率モデルを用い、自然史や感染性R0は先行研究による。また、その対応として公衆衛生当局による接触者の捕捉をパラメーターとして用いて、国内での患者発生の可能性を評価する。また、公衆衛生当局が行うのは接触者の把握、健康状態の把握、前駆期、症状期の入院隔離までで、それ以上の、例えば未発症の接触者の隔離等は行わない。感応性分析として、接触者捕捉率を変化させる。なお、把握された接触者が前駆期に入った場合、および未把握の接触者が症状期に入って十分に期間が経過した場合の入院隔離率は100%とする。
結果 接触者捕捉率を日率50%、R0を3としたときの推定国内患者発生数は2.948人である。感応性分析の結果、接触者捕捉率が0%であれば3人以上の患者が発生していたであろう確率は90%以上であるが、接触者捕捉率が100%であればその確率は約10%未満まで低下する。
考察 SARSによる国内患者の発生数を0にすることはできない。これは初期段階の遅れによるところが大きい。つまり台湾人医師により国内で感染患者が発生しなかったのは、適切な公衆衛生対応の結果というよりは、むしろ偶然の産物である可能性のほうが強いと示唆される。
キーワード 感染症対策、SARS、確率数理モデル、政策評価
|
第51巻第11号 2004年10月 勤労者の通勤時運動時間と
高田 康光(タカタ ヤスミツ) |
目的 勤労者の通勤時の歩行あるいは自転車利用時間(通勤時運動時間)と虚血性心疾患危険因子の高血圧、高脂血症、糖尿病の発症率との関連を明らかにする。
方法 同一職場に属し、1998年度定期健康診断時の血圧、血清コレステロール、血糖の項目で精密検査の対象とならなかった者で、慢性疾患で治療中の者を除いた男性429名、女性61名、平均年齢50歳の計490名を5年間観察した。検査基準では、収縮期血圧160mmHg未満、拡張期血圧100mmHg未満、空腹時血清コレステロール値260mg/dl未満、空腹時血糖値110mg/dl未満、空腹時血清中性脂肪値300mg/dl未満のすべてを満たした者を対象とした。観察期間中に治療開始あるいは基準値を2回以上超えた場合を発症とした。通勤時運動時間とその他の運動習慣の頻度、飲酒、喫煙習慣、睡眠時間等の生活習慣を自己記入式問診票により調査した。通勤時運動時間が20分未満(A群:279名)、20分以上40分未満(B群:163名)、40分以上(C群:48名)の3群で、疾病発症件数、前後の健康診断結果を比較した。
結果 期間中に治療開始となった対象者は、高血圧6名、高コレステロール血症2名で、糖尿病はいなかった。検査値から発病したと判定したものは、高血圧1名、高コレステロール血症4名、糖尿病8名、境界型高血糖48名だった。疾病の81%、境界型高血糖の71%がA群に属し、通勤時運動時間とこれら虚血性心疾患危険因子となる疾患の発症率に有意な関連を認めた。健康診断結果では、BMI、血圧、血糖、血清コレステロール、肝機能検査のAST、ALT、GGTの平均値には各群間で有意差は認めなかった。しかし、AST/ALT比、GGT、BMI値は、A、B群でのみ5年後に有意な上昇を認めた。
結論 通勤時運動時間が長い群ほど高血圧、高コレステロール血症、糖尿病の発症が5年間、有意に低率だった。その機序としては、通勤時の運動がGGTの上昇で疑われる脂肪肝発症を抑制していることが考えられた。
キーワード 通勤時運動時間、生活習慣病、運動習慣、高血圧、糖尿病、高脂血症
|
第51巻第11号 2004年10月 国民生活基礎調査における無回答データ等の
新田 功(ニッタ イサオ) |
目的 国民生活基礎調査による世帯数の推計値に無回答データが及ぼす影響を補正する方法について検討することを目的とした。
方法と結果 性別・年齢階級別人口について国民生活基礎調査の推計値と他の調査の推計値とを比較すると乖離がみられる。その原因は、国民生活基礎調査における無回答(面接不能等)世帯の増加にあると考えられ、国勢調査等との比較を行うと、国民生活基礎調査における無回答世帯が65歳未満の単独世帯、特に20歳代、30歳代の単独世帯に多いことが明らかになった。無回答世帯に起因する非標本誤差の影響を除去する方法として加重法と補完法があるが、国民生活基礎調査においては調査不能世帯の属性に関する情報が得られることから、この情報に基づいて、推計の際に用いる加重を調整する方法を検討した。数種類の加重を比較検討のうえ、世帯を、①65歳未満の単独世帯、②65歳以上の単独世帯、③2人以上世帯に区分し、それぞれのグループの回収客体数に国勢調査に基づいて決定した加重を乗じて推計値を求める方法を採用した。その結果、世帯を3種類に区分して異なる大きさの加重を乗じるこの補正方法により、国民生活基礎調査の世帯数の全国推計値の改善がみられた。
結論 国民生活基礎調査による世帯総数、単独世帯数等の推計値を実態に近づけるという点において、本研究の補正方法は有効である。しかし、この補正方法を利用する場合には、従来の方法による推計結果との接合方法等の検討が必要である。
キーワード 国民生活基礎調査、無回答、補正、加重法、世帯票、世帯数の推計
|
第51巻第11号 2004年10月 重度身体障害者の孤独感に関する研究―孤独感に対する社会福祉的援助の視点から―村岡 美幸(ムラオカ ミユキ) 本名 靖(ホンナ ヤスシ) |
目的 重度身体障害者の抱える孤独感を明らかにし、重度身体障害者がより充実した生活を送るために必要な、孤独感緩和へのアプローチ方法を社会福祉の視点から探究することを目的とした。
方法 1997年から2002年の間に3回、施設および在宅で生活している重度身体障害者について、自記式によるアンケート調査を実施した。対象者と実施期間は異なるものの、いずれの調査も改訂版UCLA孤独感尺度を使用して行った。また、孤独感と生活実態との関連を検討するため、日常生活の内容、日常の移動手段や外出頻度、介護者の接し方に対する満足度など、重度身体障害者の生活に日常的にかかわっていると考えられる項目を設定した。
結果 重度身体障害者の孤独感は、第一因子「自己の他者理解における孤独」、第二因子「他者の自己評価の反映における孤独」、第三因子「積極的交流のなさにおける孤独」の3因子ないし、第一因子と第二因子の2因子であることが明らかとなった。
また、施設生活者の孤独感の要因を検討した結果、「職員の態度に対する満足度」「コール対応に対する満足度」「排泄・入浴介助に対する満足度」においては第二因子で有意な関連が認められ、「主観的健康観」「主観的外出頻度」では、第一因子と第二因子で有意な関連が認められた。
結論 孤独感へのアプローチとして、まず在宅で生活している重度身体障害者の場合には、通所サービスや外出付き添いサービス、移送サービスなどの利用による外出機会の増加を図り、他者との交流の機会をサポートしていく必要性が示唆された。次に、施設で生活している重度身体障害者の場合には、職員との直接的なかかわり(援助行為と人間関係)が利用者の孤独感を強める要因の1つとなっていることを施設職員各自が認識し、利用者1人ひとりの生活が尊重され、刺激がもたらされるような援助や介助ができるよう、現在の援助を見直していくことの重要性が示唆された。
キーワード 重度身体障害者、孤独感、社会福祉からのアプローチ、身体障害者療護施設
|
第51巻第11号 2004年10月 出生コホート分析を用いた脳卒中罹患率の検討―富山県脳卒中情報システム事業より―三輪 のり子(ミワ ノリコ) 成瀬 優知(ナルセ ユウチ) |
目的 富山県の1992~2000年における脳卒中全体および脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血の罹患率の現状について検討し、今後の脳卒中予防対策の基礎資料とすることを目的とした。
方法 富山県脳卒中情報システム事業の登録情報および死亡小票を利用して、1992~2000年における40歳以上の脳卒中罹患件数(明らかな再発ケースを除く)を把握した。脳卒中全体と主要病型の男女別罹患率の動向を、9年間の年齢群別罹患率、5歳年齢階級の出生コホート曲線および出生コホート間の平均罹患変化率により検討した。
結果 9年間の年齢群別罹患率は、脳卒中全体および脳梗塞・脳出血では、男女とも年齢群が上がるにつれて高くなり、特に70~74歳以上からは急激な上昇がみられた。クモ膜下出血では、女性は年齢群が上がるにつれて高くなる傾向がみられたが、男性はあまり明らかな傾向は示さなかった。9年間平均の40~84歳の罹患率(人口千対)は、脳卒中全体では男性4.0、女性2.8、脳梗塞では男性2.6、女性1.7、脳出血では男性1.0、女性0.7、クモ膜下出血では男性0.3、女性0.5であった。出生コホート別罹患率は、脳卒中全体および脳梗塞・脳出血では、男女とも1992~1998年はほとんどのコホートは加齢とともに上昇していたが、1999~2000年では一律に低下する傾向がみられた。クモ膜下出血では、全コホートに共通する傾向は認められなかった。出生コホート間の平均罹患変化率では、男女に共通して、脳卒中全体では1926~30年生まれ以前の出生コホートが、脳梗塞では1931~35年生まれ以前の出生コホートが、それぞれ直前の出生コホートに比べて有意に24~51%、17~63%減少していた。脳出血およびクモ膜下出血では、男女に共通する出生コホート間の変化は認められなかった。
結論 脳卒中全体および脳梗塞・脳出血では、加齢が罹患率の上昇に影響していた。脳卒中全体および脳梗塞では、おおよそ第2次世界大戦以前生まれのコホートにおいてそれぞれ直前コホートに比べて罹患率が有意に低下しており、世代が新しくなるにつれて罹患の少ないコホート特性に変化していると考えられた。しかし戦後生まれコホートでは、その特性に明らかな違いは認められなかった。
キーワード 脳卒中罹患率、脳卒中登録、コホート分析
|
第51巻第13号 2004年11月 仙台市宮城野区内T地区における
鈴木 修治(スズキ シュウジ) 畑山 明美(ハタヤマ アケミ) 横田 節子(ヨコタ セツコ) |
目的 高齢化が顕著となった大都市の住宅団地において、必ずしも明確にされていない高齢者の身体状況や家庭と地域社会における生活の実態を明らかにし、高齢者の健康づくりや生活の質の向上を図る事業展開を考えるために、ひとり暮らし高齢者世帯を調査して日常生活活動や家庭および社会環境についての実態を把握することを目的とした。
対象と方法 仙台市宮城野区内の住宅団地T地区に居住している65歳以上でひとり暮らしの667名を対象に、在宅看護師12名が各世帯を戸別訪問のうえ、訪問指導記録票を用いて面接聞き取りによりアンケート調査を実施した。
結果 667名の対象者中、465名(69.7%)から回答を得た。このうち、全項目の回答者431名(64.6%)を解析対象者とした。日常生活自立度ではランクJが421名(97.7%)であった。介護の有無については411名(95.4%)が介護なしとの回答であった。主たる既往歴については高血圧症が102名(23.7%)と最も多かった。また、身体障害や何らかの自覚症状ありが、302名(70.1%)に上った。生活状況のうち社会参加については、近所付き合い、町内会活動、老人クラブ参加の順に多かったが、他方、町内会活動不参加が179名(41.5%)、近所付き合いなしが109名(25.3%)であった。居住環境では77%の人が公営住宅等の借家に居住している状況であった。
結論 仙台市内都市部に属するT地区は公営住宅が多い住宅団地であるが、この地区に居住するひとり暮らし高齢者は借家住まいが多く、何らかの疾病を有しながらも、介護を受けないでどうにか自立した生活をしている。また、社会参加では近隣との付き合いや町内会行事に参加をしている状況がみえてくるが、反面で町内会活動不参加が41.5%、近所付き合いなしが25.3%あり、地域コミュニティーネットワークの希薄化が考えられる。今後の行政施策にとっては、増加する高齢者に対して、希薄になってゆく地域コミュニティーを視野にいれながら、生きがいと心身の健康づくりの両面で高齢者の健康寿命の延伸と生活の質の向上を図るために、いかに支援していくかが課題と考えられる。
キーワード 高齢者、ひとり暮らし、身体状況、生活実態
|
第51巻第13号 2004年11月 わが国における将来の出生・死亡低下
逢見 憲一(オオミ ケンイチ) |
目的 わが国における少子化と高齢化の関連を知るため、将来の出生・死亡の変化が人口に与える影響の機序と要因を正確に理解することを目的とした。
方法 資料としては、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口 平成14年1月推計」を用いた。ここで推計されている人口、出生率、死亡率(生命表)を用いて、様々な前提からシミュレーションを行った。すなわち、コーホート要因法を用いて、基準年の2002年から100年後の2102年までシミュレーションを行った。
結果 出生・死亡とも2002年の水準で一定とした場合であっても、老年人口の割合は着実に増大し、2052年には34.0%に達していた。また、出生が「将来推計人口」の高位推計に従い死亡が改善しない場合でも、老年人口割合は2052年には30.2%と、総人口の30%以上が老年人口となると推計された。その一方で、出生が低位推計に従う場合、老年人口割合は、2052年に40.8%に達した後も増大を続け、2102年には44.5%となっていた。
出生、死亡という要因別に人口の変動をみると、死亡の改善による総人口の増加は601万8千人で、うち560万8千人とそのほとんどが老年人口の増加であった。出生が高位推計に従った場合、2052年には、総人口は1642万3千人増加し、2102年には2682万5千人増加していた。一方で、出生が低位推計に従った場合、総人口は、出生・死亡が一定であった場合よりも減少をしており、2052年には48万9千人、2102年には747万7千人減少していた。これは、出生変化による総人口減少が、死亡改善による総人口増加を上回った結果であった。
結論 出生・死亡とも2002年の水準で一定とした場合であっても、あるいは出生が改善した場合でさえ、老年人口の割合は21世紀中ごろまでに30%以上に増大することが示された。また、中・長期的にみると、出生の変化は、総人口の変動を通じて人口の高齢化に大きな影響を与えることが示された。「少子(・)高齢化」という場合、このような出生と死亡の関連についても、あらかじめ理解していることが必要であろう。
キーワード 少子高齢化、少子化、高齢化、人口推計、人口転換、第二の人口転換
|
第51巻第13号 2004年11月 障害幼児の母親における情報源の利用と評価種子田 綾(タネダ アヤ) 中嶋 和夫(ナカジマ カズオ) |
目的 障害児通園施設を利用している母親を対象に、情報ニーズと情報源の利用および情報源の評価の関係を検討することを目的とした。
方法 調査は、S県とW県の障害児通園施設を利用する児の母親を対象として実施した。調査内容は、児の特性(性、年齢、療育手帳、障害者手帳)、母親の基本属性(年齢、児の数、家族構成、職業)、情報ニーズ、情報源の利用と評価で構成した。情報ニーズは、「The Family Needs Survey」のうちの情報に関連した7項目で測定した。情報源の利用と評価は、マスメディア4項目、障害児の療育にかかわりの深い専門家集団としてのパーソナルメディア5項目とそれ以外のパーソナルメディア4項目で測定した。統計解析では、情報源の評価に対する一次要因を情報源の利用、二次要因を情報ニーズとする因果モデルを仮定し、そのモデルのデータへの適合度を検討した。
結果 前記因果モデルのデータに対する適合度は、統計学的に許容される基準値を満たしていた。情報ニーズは、14点満点で平均値が12.6点(標準偏差1.9)であり、個別には、「子どもの発達に関する情報が知りたい」「将来利用できる福祉サービスに関する情報が知りたい」「子どもの障害に関する情報が知りたい」に関する、より専門的な情報ニーズの頻度が高かった。情報源の利用頻度は、専門家等のパーソナルメディア、その他のパーソナルメディア、マスメディアの順であった。また、情報源の評価は、その他のパーソナルメディア、専門家等のパーソナルメディア、マスメディアの順であった。情報源の利用と評価は密接に関連していた。
考察 専門家等のパーソナルメディアは、障害幼児の母親の情報ニーズの内容から判断すると、必ずしも十分な対応関係になく、今後、総合的かつ体系的な療育システムの一層の充実が望まれることが推察された。
キーワード 障害児、母親、情報源
|
第51巻第13号 2004年11月 児童虐待の要因に関する研究-乳幼児発達相談・発達訓練事業の事例対照研究-横田 恵子(ヨコタ ケイコ) 今井 美香子(イマイ ミカコ) 吉留 慶子(ヨシドメ ケイコ)渡辺 恵美子(ワタナベ エミコ) 桐生 康生(キリュウ ヤスオ) 樋口 和子(ヒグチ カズコ) |
目的 児童虐待に関する問題が深刻化するなか、児童虐待の要因を明らかにし、今後の支援方策について検討することを目的とした。
方法 2002年度における甲府保健所の乳幼児発達相談・発達訓練事業の対象者110例から、事例群「親からの虐待が認められるかその恐れがある事例」16例と、対照群「親からの虐待が認められない事例」32例を抽出し、事例対照研究を行った。この2群について、ケース記録をもとに「児の状況」「母の状況」「家庭・家族の状況」「地域における状況」に関する合計43項目の説明変数を抽出し、オッズ比を求めるとともに、統計学的検定を行った。
結果 虐待事例の7割が男児で、年齢は3.2±1.2歳(平均±標準偏差)であり、母の年齢は、33.3±4.8歳であった。主たる虐待者は、実母が81%と最も多く、虐待の種類は、心理的虐待が50%と最も多かった。
児の状況について事例対照研究を行った結果、児の発達の遅れ、心理的問題、問題行動について有意差を認めた。母の状況については、被虐待歴、生育歴の問題、病気等の有無、妊娠・出産に関する問題、過大な育児負担、過大な育児不安、児とのかかわりの少なさ、家事能力の問題、性格的な問題について有意差を認めた。家庭・家族の状況については、経済的問題、家族の人間関係の問題、父の育児参加、親族からの孤立、他の兄弟への虐待について有意差を認めた。また、地域における状況として、近隣・友人からの孤立について有意差を認めた。
キーワード 児童虐待、要因、母親、家庭・家族、地域、事例対照研究
|
第51巻第13号 2004年11月 国民の代表サンプルを用いた
早川 岳人(ハヤカワ タケヒト) 岡村 智教(オカムラ トモノリ) 上島 弘嗣(ウエシマ ヒロツグ) |
目的 日本人の代表集団において、高齢者の5年間の日常生活動作(ADL)の推移を明らかにすることと、5年後のADL低下者数を算出できる簡易予測表の作成を試みることを目的とした。
方法 1980年に厚生省が実施した循環器疾患基礎調査の受診者のうち、1994年の時点で65歳以上の高齢者を対象として、居住地域の保健所を通じてADL追跡調査を実施した。その後、5年経過した1999年に同様のADLの追跡調査を実施し、1994年のADL区分ごとにADLの推移状況を検討するとともに、ADL低下者数を算出できる簡易予測表を作成した。
結果 断面で比較すると、1994年と1999年で生存者の各項目別のADL低下状況に大きな差はみられなかった。自立から5年の間に新たにADLが低下した者は、男性8.1%、女性13.2%であり、本集団における自立者からの5年間のADL低下の発症率は10%であった。また、自立者のうち5年間で死亡した者の割合は、男性が女性に比べ2倍高かった。1994年時のADL低下者のうち、5年後もADLが低下し続けている者の割合は、男性が女性に比べ1.5倍高かったが、1994年時のADL低下者のうち死亡した者の割合は、男性が女性に比べ1.5倍高かった。ADL低下者の5年間の死亡率は、自立者の死亡率に比べて2.5倍から3倍高かった。一方、ADL低下者のうち、約20%の者が5年間で自立状態まで回復することが明らかとなった。
本調査結果を利用し、年齢階級別にADL自立者とADL低下者の人数から、5年後のADL低下者数(要介護者数)を計算するための表(簡易予測表)を作成した。
結論 国民の代表集団の疫学資料を用いて、わが国における高齢者のADLの状況を明らかにし、さらにその5年間の推移を明らかにすることができた。本研究において、現在の年齢階級別の自立者と要介護者数から5年後の要介護者数を推計する式が作成され、今後、各市町村、都道府県における福祉保健計画の見直し等の基礎資料として活用することが可能である。
キーワード コホート研究、国民の代表集団、日常生活動作(ADL)、ADL低下者数簡易予測表、NIPPON DATA
|
第51巻第13号 2004年11月 大都市に居住している在宅高齢者
蘇 珍伊(ソ ジニ) 林 暁淵(イム ヒョヨン) 安 壽山(アン スサン) |
目的 大都市に居住している在宅高齢者の生きがい感の現状を調査・把握し、生きがい感に影響を与えている様々な要因を明らかにすることを目的とした。
方法 (1)調査対象者は無作為抽出した大阪市A区に居住している65歳以上の高齢者1,000人であり、調査方法は、自記式質問紙を用いた郵送調査である。調査期間は、2003年2月18日~3月12日であり、有効回答率は62.7%であった。調査項目は、「基本属性」と「生きがい感」「健康感」「経済的満足感」「社会参加」「サポート受領」「サポート提供」「世代間の交流」「信仰の有無」を設定した。(2)分析方法は、まず、生きがい感の現状を把握するために、生きがい感の各項目の単純集計を行った。次に、生きがい感に関連する要因を明らかにするために、基本属性および設定した各項目を独立変数とし、生きがい感の合計得点を従属変数とする重回帰分析を行った。
結果 生きがい感の単純集計の結果、すべての項目で「かなりそう思う」と「まあまあそう思う」が半数以上を占め、肯定的な傾向がみられた。生きがい感に関連する要因を明らかにするための重回帰分析の結果、「社会参加」「世代間の交流」「サポート提供」「健康感」「経済的満足感」が高いほど、また、「年齢」が低いほど、生きがいを感じやすいことが明らかになった。なお、この重回帰モデルの決定係数は0.39であり、0.1%水準で有意であった。
結論 在宅高齢者は、社会参加、世代間の交流、サポートの提供といった人々とのかかわりの中で生きがい感を感じることが多いことがわかった。そのため、人々とのかかわりがもてるような機会の提供を通じて、高齢者の社会参加を促し、ソーシャルサポートの提供や世代間交流が活発に行えるような場の整備が必要であると考えられる。また、在宅高齢者の生きがい感を高めるためには、高齢期の経済的安定性と良好な健康状態を保持することが重要であることが明らかになった。そのためには、高齢者が安心できる年金制度の改革と高齢者に対する健康教育やヘルスプロモーションといった健康政策の充実が必要であると考えられる。
キーワード 大都市在宅高齢者、生きがい感、社会参加、ソーシャルサポート
|
第51巻第15号 2004年12月 「医師・歯科医師・薬剤師調査」の現状に関する検討-全保健所,全県,保健所設置市アンケート調査-藍 真澄(アイ マスミ) 島田 直樹(シマダ ナオキ)近藤 健文(コンドウ タケフミ) 下門 顕太郎(シモカド ケンタロウ) |
目的 医師・歯科医師・薬剤師調査(以下「三師調査」)においては従来から届出漏れが生じている可能性があることが示唆されている。届出漏れの解消策を講じることが最終目標であるが,本研究では実際の調査上の問題点を明らかにする目的で,全国レベルでの実態調査を行った。
方法 平成14年の三師調査の実施直後に,日本国内582か所の全保健所に対して医師・歯科医師・薬剤師調査に関する業務の実態等についてアンケート調査を実施した。さらに,三師調査の調査票のとりまとめにおいて保健所から厚生労働省までの経路にある都道府県や保健所設置市にも同様のアンケートを実施した。
結果 アンケートの回収率(有効回答率)は保健所78%,設置市77%,都道府県94%と高値であった。本来,有資格者が自ら届け出ることになっているが,保健所に直接調査票をとりにきた有資格者は,医師,歯科医師,薬剤師の順にそれぞれ全体の0.1%,0.7%,2.4%と非常に少なかった。実際には主に保健所実務者による努力によって届出が維持されていた。また,彼らの努力によっても休職中の有資格者は把握が困難で,そこで生ずる届出漏れが大きな課題と認識されていた。さらに,届出率向上に対しては広報活動が重要であるという認識が示された。調査票の内容についても届出率に影響を与えている可能性が指摘された。
結論 保健所実務者がいかに有資格者を把握し,把握できた有資格者に調査票を提出させるかで届出率が規定される現状が明らかになった。現状の下で,届出漏れの解消策として以下の3点を提言する。第1点は広報活動として,三師調査が当該有資格者の法律で定められた義務であり,就職の有無にかかわらず届出義務があることを免許を与える時点で強調するとともに,マスメディアなどを通じた広報を行うこと。第2点は調査票の内容について,診療科目の記載について説明文を入れることや,届出義務者のプライバシーに関する項目については必要な理由等を調査票上に説明するなどの改善を図ること。第3点として実際の届出漏れ数を具体的に把握すること,すなわち,有資格者で届出がされていない対象者をある時点で国レベルで医籍などとの突合により調査することである。今後,このような改善により,届出義務者の自発的な届出が誘導されることが重要である。
キーワード 医師・歯科医師・薬剤師調査,届出率,保健所,休職者
|
第51巻第15号 2004年12月 受療のための地域間患者移動に影響する要因の検討寒水 孝司(ソウズ タカシ) 浜田 知久馬(ハマダ チクマ) 吉村 功(ヨシムラ イサオ) |
目的 患者が受療のために地域(医療圏)間を移動する要因を,疾病,医療施設の種類(病院・一般診療所),受療の種類(入院・外来)ごとに明らかにする。
方法 平成11年患者調査データと平成11年医療施設静態調査データから,三次医療圏を単位とした患者の流入・流出割合を「疾病大分類」ごとに計算し,その中でみられた特徴的な患者移動を取り上げる。次に,取り上げた患者移動に影響する要因を,上記データ,関連する統計データ,文献,医師の見解等に基づいて検討する。最後に,得られた結果の一般性を確かめるために,平成8年の調査データについて同様の検討を行う。
結果 どの疾病においても大都市部への患者の流入割合が高いことがわかった。典型的な大都市部圏とその周辺の二次または三次医療圏について,推定流入患者数を目的変数,通勤・通学者数(平成12年国勢調査データ)を説明変数とした単回帰分析を行ったところ,2つの変数間に直線関係がみられた。これは,患者がある一定の割合で通勤・通学先の医療施設を利用しているためであると考えられる。大都市部への通勤・通学者数は多いので,結果として大都市部への患者の流入割合が高くなったと解釈できる。隣接する三次医療圏の患者を除いた流入・流出割合を調べたところ,「新生物」においては,大都市部に患者が流入する傾向がみられた。これは,大都市部に集中する高度な医療技術・設備が患者移動に影響しているためであると解釈できる。「耳及び乳様突起の疾患」の患者の流入割合がある医療圏で高いこと,「精神及び行動の障害」「神経系の疾患」「妊娠・出産に関連した疾病」の患者の流入割合が一般に高いことがわかった。これらの現象は,患者居住地と施設の距離,ドクターショッピング,里帰り出産,という要因によるものと解釈できる。
結論 疾病と地域によって多少の違いはあるが,患者が受療のために医療圏間を移動するのには,①通勤・通学,②高度な医療技術・設備の有無,③患者居住地と施設の距離,④ドクターショッピング,⑤里帰り出産,という要因が影響していると考えられた。各医療圏における患者数を利用するときには,このような要因が影響していることに注意すべきである。
キーワード 患者移動,医療圏,患者調査,医療施設静態調査,医療計画
|
第51巻第15号 2004年12月 慢性閉塞性肺疾患死亡の性差,年齢差,地域差と年次推移山本 真梨(ヤマモト マリ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) 谷脇 弘茂(タニワキ ヒロシゲ)栗田 秀樹(クリタ ヒデキ) 橋本 修二(ハシモト シュウジ) |
目的 慢性閉塞性肺疾患の死亡について,性差,年齢差,地域差と年次推移を記述するとともに,2020年までの死亡数の推計を試みた。
方法 基礎資料として,1982~2001年における性・年齢階級別の慢性閉塞性肺疾患死亡数と人口,2000年における性・都道府県別の慢性閉塞性肺疾患の年齢調整死亡率,2005・2010・2015・2020年における性・年齢階級別の将来推計人口を用いた。慢性閉塞性肺疾患について,2001年の性・年齢階級別死亡率,1982~2001年の死亡数・粗死亡率・年齢調整死亡率の推移,および2000年の性別年齢調整死亡率の都道府県分布を観察した。1982~2020年の性・年齢階級別死亡率が毎年一定倍で変化するという仮定の下で,2005・2010・2015・2020年における慢性閉塞性肺疾患の死亡数を推計した。
結果 粗死亡率(人口10万対)は男15.7,女5.3であり,年齢階級別死亡率は男女とも年齢とともに指数関数的に上昇していた。1982~2001年において,死亡数は男で2.26倍,女で1.94倍,粗死亡率は男で2.13倍,女で1.81倍と増加していたが,年齢調整死亡率は男で1.04倍,女で0.70倍であった。2000年の都道府県別年齢調整死亡率は,同年の全国値と比べて男で0.75~1.74倍,女で0.45~2.6倍であり,西日本に高い府県が多い傾向がみられた。2020年の推計死亡数は男で19,700人,女で4,800人と推計され,2001年と比べて男で約2.0倍,女で約1.5倍であった。
結論 慢性閉塞性肺疾患の死亡には,性差,年齢差と地域差が認められた。最近20年間の死亡数の推移は人口の高齢化の影響を強く受けており,また,今後20年間で死亡数は約2倍になると推計された。
キーワード 慢性閉塞性肺疾患,死亡,人口動態統計,記述疫学
|
第51巻第15号 2004年12月 脳神経外科クライエントに対するソーシャルワークの実践-早期介入の有用性と意義に関する一考察-田中 希世子(タナカ キヨコ) |
目的 急性期医療機関における脳神経外科入院患者やその家族をはじめとするクライエントに対するソーシャルワーク支援の主内容を明確にし,クライエントにとって有意義なソーシャルワーク方法について検討することを目的とした。
対象と方法 急性期医療機関A病院における脳神経外科入院患者を対象として,平成14年4月から平成15年12月までの21か月間に所属のソーシャルワーカーが行った退院支援の追跡調査である。本稿ではA病院のソーシャルワーカーが退院支援を行った脳神経外科入院患者36名における在院要因と退院支援経過等について分析を行った。
結果 脳神経外科入院患者に対するソーシャルワークに関する調査の分析から,「突然の発症・入院にまつわるクライエントの精神的不安」と「ソーシャルワーク介入頻度が極めて高いこと」,「在院長期化とそれに伴う生活上の諸問題の多発と多様化」との間に有意の関係が見いだされた。
結論 脳神経外科疾患は,発症後,クライエントの社会生活に重篤かつ多様な影響を長期にわたって及ぼすことが考えられ,ソーシャルワーカーは個人と社会環境との関係性に着目し,クライエントを取り巻く環境の整備,家族関係の調整,社会資源に関する情報提供,クライエントにとって有益な社会資源の活用への支援等を実施することが重要となる。このようにソーシャルワーカーはクライエントの生活を総合的にとらえる視点から,問題の解決,緩和にかかわるところに特徴があるが,充実したソーシャルワーク支援を行うため,早期かつ適時のソーシャルワーク介入が重要な課題である。
キーワード ソーシャルワーク介入の時期,心理・社会的支援,クライエント本位
|
第51巻第15号 2004年12月 難病患者のQOLと医療・保健ニーズとの関連小寺 さやか(コテラ サヤカ) 丹治 和美(タンジ カズミ) 渡邊 愛子(ワタナベ アイコ)横田 昇平(ヨコタ ショウヘイ) 中村 昇(ナカムラ ノボル) 弓削 マリ子(ユゲ マリコ) |
目的 難病患者の主観的QOLに影響する要因(医療・保健ニーズ)を明らかにし,地域難病ケアシステムの構築と保健所難病対策の充実を図る上での基礎資料とする。
方法 京都府中部地域の特定疾患医療受給者計665人を対象に自記記名式の郵送調査を実施した。分析対象は,回収した525人のうち川南らの開発した「難病患者に共通の主観的QOL尺度」の全項目に回答があった411人とした。
結果 主観的QOLと療養上の困難・医療の満足度との間に有意な関連が認められ,療養上の困難を抱えている者や医療に満足していない者ほど主観的QOLが低かった。
保健所難病事業との関連では,主観的QOLと医療相談や保健師等による訪問事業の利用との間に有意な関連が認められた。また,属性では,年齢,疾病群,療養場所,外出時の介助の必要性,補装具の使用,医療処置の有無と有意な関連が認められ,神経系難病患者や歩行障害等で外出が制限される者,医療処置が必要な重症難病患者で主観的QOLが低かった。
結論 主観的QOLは,療養困難を抱えている者や神経系難病患者,外出が困難な者,医療処置が必要な重症者で低く,保健所の個別支援は主観的QOLの低い者に実施されていた。今後,歩行障害をきたし重症化しやすい神経系難病を中心に難病対策の充実を図るとともに,患者のニーズに応じた地域難病ケアシステムを構築していく必要がある。
キーワード 難病,主観的QOL,医療ニーズ,保健ニーズ,地域難病ケアシステム
|
第52巻第1号 2005年1月 既存の統計資料を用いた推計による
|
目的 新規治療薬を導入するにあたり,医療経済的側面からの評価は治療薬の利用可能性を表し,導入の根拠になる。国家単位の新規治療薬導入の効果を検討する場合,マクロ経済的評価が有用である。また,DALYやQALYなど質的調整変数を指標にする一方,疾患内の重症度を補正することも評価の妥当性を高めると考えられる。本研究では,関節リウマチ(RA)の新規治療薬導入による医療経済効果をマクロ経済的観点から試算した。
方法 患者調査の患者数と総務省統計局の推計人口から2000年のRA患者数を算出した。障害による損失年(YLD)は,患者数と障害度の重み付けの積により時間割引や年齢補正なしに算出した。RA患者の重症度分布の情報は,日本リウマチ財団リウマチ登録医を対象にした質問票調査から収集した。重症度別構成割合とQOLスコアの積を係数にして重症度別の患者数とYLDを算出した。厚生省研究班の推計によるYLDと国民医療費から効果単価(万円/YLD)を算出した。コクランライブラリーのメタアナリシスを参照して,アメリカリウマチ学会の評価基準による20%改善(ACR20),50%改善(ACR50),70%改善(ACR70)を指標にしたオッズ比を係数にしてレフルノミド導入によるYLDや医療費の変化を算出した。なお,レフルノミドは中等症以上が投与対象になると仮定した。
結果 レフルノミドの投与対象患者数は64,760人(20.8%)と推計された。レフルノミド導入によるYLDの減少は,ACR20を指標にしたとき3,172YLD(5.8%減),ACR50を指標にしたとき9,394YLD(17.3%減),ACR70を指標にしたとき12,469YLD(23.0%減)と推計された。全体および1患者当たりの医療費の削減は,ACR20を指標にしたとき136億円,21.0万円,ACR50を指標にしたとき403億円,62.2万円,ACR70を指標にしたとき535億円,82.6万円と推計された。感度分析の結果から,1患者当たりの医療費の削減は投与対象患者数が少ないほど大きく,上記の推計値の安定性が示された。
結論 モニタリングの費用や副作用のスクリーニングの費用などの必要経費を考慮すべきであるが,概してレフルノミド導入の経済的妥当性が示された。本研究の手法は各種疾病,各種治療法の医療経済効果をマクロ経済的観点から試算するために応用可能である。
キーワード 関節リウマチ,抗リウマチ薬,障害による損失年,医療費,費用対効果
|
第52巻第1号 2005年1月 虚血性心疾患死亡数年次推移における
入野 了士(イリノ サトシ) 池上 直己(クリハラ ユキオ) |
目的 虚血性心疾患死亡数の近年の年次推移は,健康日本21における高脂血症の減少目標設定における重要な根拠となっているが,1995年に実施された心不全診断基準の大きな改訂は虚血性心疾患死亡数の年次推移に影響を及ぼしている。そこで,この影響を補正した虚血性心疾患死亡数の年次推移曲線を推計することを試みた。
方法 心不全診断基準の改訂前後の虚血性心疾患死亡数と心不全死亡数との年次推移を比較することにより,改訂前に心不全死亡とされていた虚血性心疾患死亡の数を推計した。その推計値を1995年以前の虚血性心疾患死亡数に加えることにより,心不全診断基準の改訂の影響を除いた虚血性心疾患死亡数の年次推移曲線を求めた。
結果 提案した算出方法により,現在の心不全死亡診断基準を過去に適用した場合の虚血性心疾患死亡数が推測でき,一貫した死亡診断基準で虚血性心疾患死亡数の推移をみることが可能となった。
結論 推計された虚血性心疾患死亡数の年次推移曲線は緩やかな増加を示しており,健康日本21に言われている大きな増加は確認できなかった。
キーワード 高脂血症,虚血性心疾患,死亡統計,死亡年次推移,疾病予防
|
第52巻第1号 2005年1月 「健康日本21」地方計画策定状況
三浦 宜彦(ミウラ ヨシヒコ) 萱場 一則(カヤバ カズノリ) 國澤 尚子(クニサワ ナオコ) |
目的 「健康日本21」の策定から3年経過した2003年6月現在の市区町村における「健康日本21」地方計画策定状況,計画の内容,および健康づくり関連事項の現状を明らかにするために,「健康づくりに関する市区町村の現状調査」を実施した。本研究の目的は,全国の状況を各市区町村に提供し,健康づくり事業の推進に役立てることである。
方法 調査は,2003年7月現在の3,207市区町村を対象として郵送法により実施し,未回答市町村には2回の調査再依頼を行った。
結果 調査時点の地方計画策定状況は,策定済み24.3%,策定中13.6%,策定予定18.3%,策定予定なし41.5%であり,都道府県別に策定済みと策定中を合わせてみると,80%超から10%未満までと都道府県格差が認められた。策定された地方計画に含まれる分野をみると,栄養・食生活が最も多く93.2%,このほかに身体活動・運動,たばこ,心の健康,歯の健康が80%以上の高率を占めていた。また,アルコール,休養が70%台であり,循環器病,がん,糖尿病も半数以上であった。「健康日本21」の各論に取り上げられている分野のうち,栄養・食生活に関する項目,身体活動・運動に関する項目,休養・こころの健康づくりに関する項目,喫煙に関する項目,飲酒に関する項目を取り上げ,現状把握と目標値の設定状況について質問を行った結果,各分野とも基本的な項目に関しては,ほぼ60%以上の市町村で現状把握が出来ていることが示唆された。目標設定に関しても同じ項目が取り上げられていたが,その割合は現状把握と比べて,かなり低い値にとどまっていた。
結論 「健康日本21」で求められている目標値の設定に関して,管轄保健所,都道府県,公衆衛生関係の専門家などの協力を得て,できるだけ早く科学的な根拠に基づく目標値を設定すべきと考えられた。
キーワード 健康日本21,地方計画,目標値
|
第52巻第1号 2005年1月 介護保険制度による介護資源の指標と死亡場所との関連-高齢社会にマッチした介護保険制度による資源の充実を求めて-定村 美紀子(サダムラ ミキコ) 馬場園 明(ババゾノ アキラ) |
目的 高齢者の多くは自宅での死を望みながら病院で亡くなっているという現実がある。介護保険制度が要介護状態にある高齢者の在宅ケアの推進を目的としていることを考えれば,介護保険の資源が充実すれば,死亡場所に影響を与える可能性がある。本稿は,介護給付費実態調査から介護保険制度による資源の充足状況を把握し,各都道府県における介護保険制度の資源と死亡場所との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 目的変数を各都道府県の死亡場所の割合(病院,診療所,自宅)とし,説明変数として介護保険制度による資源の指標(在宅サービス・短期入所サービス・施設入所サービス受給者数,老年人口割合,がん死亡割合,脳卒中死亡割合,一般病床数,持ち家割合,平均世帯人数)を用いた重回帰分析を行った。
結果 ①在宅サービスの資源の指標は,病院死亡割合と強い負の関連を示し,在宅サービスの資源が病院死亡を減少させる可能性があることを示唆した。また,診療所死亡とも強い正の関連があり,在宅サービスと診療所との連携が病院死亡割合を減少させる鍵となる可能性が示唆された。②短期入所に関する資源の指標は,診療所死亡と強い負の関連,自宅死亡と強い正の関連を示しており,短期入所は診療所死亡を減少させ,自宅死亡を増加させる可能性があることが示唆された。③施設入所に関する資源の指標は,病院死亡割合に影響を与えておらず,自宅死亡割合との強い負の関連が示された。
考察 介護保険による資源が死亡場所に影響を与えていることが考えられた。このことから,在宅で終末期ケアを行うためにも介護保険サービスの充実が必要であると考える。特に,在宅で医療依存度が高い者の介護を継続するために,病院や診療所の連携が必要である。また,在宅で介護を行う者を支援するためには,短期入所を利用しやすい環境を整えていくことが重要であると考える。
キーワード 介護保険,高齢者,死亡場所,終末期医療,重回帰分析
|
第52巻第1号 2005年1月 市区町村別平均寿命の全国順位からみた
竹森 幸一(タケモリ コウイチ) 三上 聖治(ミカミ セイジ) 工藤 奈織美(クドウ ナオミ) |
目的 各都道府県における市区町村別平均寿命の全国順位の変化から,各都道府県の平均寿命の特徴を明らかにすることを目的とした。
方法 1985年,1990年,1995年および2000年の市区町村別平均寿命を用いて2005年の市区町村別平均寿命を予測した。各年の全国市区町村の平均寿命について,平均寿命の長いものから1,2というように順位を付けた。各都道府県における市区町村の全国順位の中央値(以下「中央値」)を求め,1985年から2000年までの中央値の回帰係数(以下「回帰係数1」)と1985年から2005年までの中央値の回帰係数(以下「回帰係数2」)を計算した。回帰係数1と1985年から2000年までの都道府県別平均寿命の延び(年)との相関係数を求めた。また,回帰係数1と1985年の中央値との相関係数を求めた。
結果 回帰係数1は都道府県により異なり,男の場合,回帰係数が正で有意な都道府県は東京都,岐阜県,島根県,愛媛県,沖縄県で,負で有意な都道府県は長崎県であった。女の場合,回帰係数が正で有意な都道府県は青森県,千葉県,東京都,神奈川県で,負で有意な都道府県は富山県,広島県であった。回帰係数が正の都道府県では,はじめ順位の低い方に市区町村が集中していたが,次第に順位の高い方に移行している様子を視覚的にとらえることができた。回帰係数1と1985年から2000年までの都道府県別平均寿命の延び(年)の間に負の有意な相関がみられた。回帰係数1と1985年の中央値の間にも負の有意な相関がみられ,1985年の中央値が高い都道府県は中央値が次第に低下し,逆に1985年の中央値が低い都道府県は中央値が次第に上昇する傾向がみられた。
結論 都道府県別平均寿命の特徴をみるには平均寿命自体より市区町村別平均寿命の全国順位の中央値の変化で観察する方が,特徴をよりよく把握できることが示された。
キーワード 都道府県別平均寿命,市区町村別平均寿命,平均寿命の延び,平均寿命の全国順位,平均寿命の予測
|
第52巻第2号 2005年2月 高齢者におけるウエスト身長比の適性と判定基準中山 晃志(ナカヤマ テルユキ) 藤澤 洋徳(フジサワ ヒロノリ) 緒方 可奈子(オガタ カナコ) |
目的 肥満指標の1つにウエスト身長比(=ウエスト周囲径╱身長,以下「WHt比」)があり,0.5が肥満の判定基準として用いられている。しかし,加齢に伴い腹筋力の低下や腹部脂肪のゆるみによるウエスト周囲径の増加は避けられず,高齢者のWHt比は若年・中年者に比べて大きくなる傾向にあると考えられるため,高齢者における肥満指標としてのWHt比の適性と判定基準について検討することを目的とした。
方法 基本健康診査の実施時に協力の得られた男性228人(うち65歳以上181人),女性421人(同290人)を対象として,回帰分析を使用した年齢によるWHt比の差異,ロジスティックモデルを使用したWHt比と肥満に関連する健診項目(収縮期血圧,拡張期血圧,総コレステロール,HDLコレステロール,中性脂肪,血糖,HbA1c)の検査値との関連,WHt比およびBMIと各検査の要指導・要医療者出現に関するオッズ比について比較検討した。
結果 男女ともに高齢者のWHt比は若中年者よりも大きい傾向にあり,回帰分析およびロジスティックモデルの両面でWHt比0.55が肥満を判定するための1つの値として得られた。男女の血圧および女性の中性脂肪では,WHt比0.55を肥満の判定基準とした場合に有意なオッズ比が認められ,WHt比0.5を基準とした場合に男性の総コレステロールと中性脂肪で有意なオッズ比が認められた。また,男性のHDLコレステロールと女性の総コレステロールでWHt比によるオッズ比がBMIによるオッズ比よりも高かった。女性のHbA1cではBMIで有意なオッズ比が認められた。
結論 高齢者においてWHt比は血圧や血液検査の要指導・要医療の判定に対してBMIよりも敏感に反応しており,高血圧症や高脂血症といった肥満に伴う疾患へのリスク予測指標として優れていることが示唆される。しかし,性別および検査項目によって適切な肥満指標および判定基準は異なるため,WHt比とBMIの併用による保健指導や健康の自己管理が望まれる。
キーワード 高齢者,肥満,ウエスト身長比,BMI
|
第52巻第2号 2005年2月 OECD A System of Health Accounts準拠の
|
目的 経済開発協力機構(OECD)により作成された「国民保健計算National Health Account(NHA)」の推計方法である「国民保健計算の体系A System of Health Accounts(SHA)」に準拠したわが国の保健医療支出の推計を行った。特に2000年度に導入された介護保険の下での保健医療支出額の推計手法の確立を主たる目的とし,2000年,2001年度の推計を行った。
方法 SHAマニュアルに基づき,国民医療費,介護給付等の状況ならびに各種衛生関係公表資料を用いて推計を行った。
結果 2001年度の「総保健医療支出Total Expenditure on Health」の推計値は,39兆5251億円であった。このうち,「設備投資分」1兆2938億円を除いた「総経常保健医療支出」は38兆2313億円であった。この値を2001年度の国民医療費との比較でみると,国民医療費は31兆3234億円であり,総保健医療支出では約26%,総経常保健医療支出で約22%多い金額であった。
結論 国際基準に基づく国民保健計算の推計手法を確立したことにより国際比較の質についての改善が図られた。また,介護保険部分についても多次元テーブルでの推計が可能になったことで,医療行政の政策利用の可能性をより高めることができた。今後も,保健医療費支出の多岐にわたる分析を踏まえた医療制度改革の方向性を検討することが重要であり,継続的な研究が必要と考えられた。
キーワード 保健医療支出,国民保健計算,国民医療費,OECD,A System of Health Accounts(SHA),介護保険
|
第52巻第2号 2005年2月 一保健所管内の小・中学生を対象とした喫煙行動
藤田 信(フジタ マコト) |
目的 本研究は,小・中学生の喫煙行動に関する実態調査を実施し,その関連要因を明らかにして,小・中学生の喫煙対策の企画立案に資することを目的とする。
方法 静岡県A保健所管内の小学校35校,2,428名,中学校17校,2,316名に対して,無記名自記式の調査票によるアンケート調査を実施した。実施場所は学校の教室で,調査期間は,平成15年1月7日から2月17日までの間とした。回答用紙は,あらかじめ配布した封筒に回答者が封をしてクラス単位および学校単位にまとめ,郵送により回収した。
結果 小学生の非喫煙者は95.8%(男子94.7%,女子96.9%),前喫煙者は3.9%(男子4.9%,女子2.9%),時々喫煙者は0.2%(男子0.3%,女子0.2%),習慣的喫煙者は0.0%(男子0.1%,女子なし),中学生の非喫煙者は90.5%(男子87.4%,女子93.7%),前喫煙者は7.0%(男子9.1%,女子4.9%),時々喫煙者は1.4%(男子2.0%,女子0.8%),習慣的喫煙者は1.1%(男子1.5%,女子0.6%)であった。小学生,中学生ともに20歳時に自分が喫煙していると「思わない」者は「思う(かもしれない)」者より喫煙経験者率が有意に低く,喫煙の習慣性が高くなるに従って「思う(かもしれない)」者が多くなる傾向であった。また,小学生,中学生ともに初めて喫煙した時の感想が「おいしかった」「気持ちよかった」「気分スッキリ」であった者は,「吐き気がした」「苦かった」であった者と比べて喫煙の習慣性の高い者が多い傾向であった。また,喫煙による健康影響について,ほとんどの項目で男女差はなかったが,「低出生体重児」で小学生,中学生ともに女子は男子より知っている者が多い傾向であった。また,小学生,中学生ともに朝食を食べないことがある者は,いつも食べる者と比べて喫煙経験者率が有意に高く,喫煙の習慣性の高い者が多い傾向であった。
結論 ①20歳時に自分が喫煙していると思わない者には非喫煙者が多く,喫煙の習慣性が高くなるに従って,思う(かもしれない)者は多くなる傾向がある。②家庭,地域,学校の少なくとも1つが(すべてが理想であるが),子どもたちにとって楽しい場であることは,喫煙防止の一助になるのではと考えられる。③喫煙防止教育では,身近な健康影響の危険性について説明することは重要である。④生活習慣の1つである朝食摂取が身に付いていない者には喫煙経験者が多く,喫煙の習慣性の高い傾向がある。
キーワード 小・中学生,喫煙行動,質問紙調査,現在喫煙者率,食習慣,喫煙防止教育
|
第52巻第2号 2005年2月 地方における新しい救急医療体制-日南町方式救急自動車医師同乗システム-細田 武伸(ホソダ タケノブ) 渡辺 勝也(ワタナベ カツヤ) 高見 徹(タカミ トオル)谷垣 靜子(タニガキ シズコ) 黒沢 洋一(クロサワ ヨウイチ) 能勢 隆之(ノセ タカユキ) |
目的 本研究は,平成13年から鳥取県西部の日南町において導入した,救急自動車医師同乗システムの現状を把握し,運用方法の改善を模索するために行った。
方法 まず,本システム実施期間内(各年度5月7日~2月28日,平日13時~18時まで)の医師が同乗したケースと同乗しなかったケースの救急活動報告書により,年齢,性別,事故種別,傷病程度,傷病名(初診時),救急隊の日南病院滞在時間を調べた。病院滞在時間は,医師同乗ケースと非同乗ケースで比較した。次いで,救急救命処置記録により,同乗した医師と救急救命士の主な処置内容を調べた。最後に,急病による救急搬送者の抑制に関与していると思われる過去5年間の日南病院の訪問診療と訪問看護の件数および急病による救急搬送件数,人口を調べた。
結果 平成13年度の対象地区対象時間内の医師同乗件数は,36件中26件(72.2%)であり,平成14年度の同件数は,34件中25件(73.5%)であった。医師同乗では事故種別は,急病によるものが約半数を占めていた。傷病程度は,中等症以上の者の占める割合が,平成13年度は73.1%, 14年度は88.0%であった。65歳以上の搬送者の割合は,平成13年度53.8%,平成14年度72.0%であった。これに対し非同乗では,急病の占める割合が平成13年度は70.0%,14年度は77.8%であった。傷病程度は,中等症以上の者の占める割合が,平成13,14年度ともに100%であった。65歳以上の搬送者の割合は,平成13年度は80.0%,14年度は77.8%であった。医師同乗,非同乗時の各種指標(性,年齢,事故種別,傷病程度,収容先)をFisherの直接法で比較したが有意差はなかった。病院滞在時間中央値は,平成13年度は医師同乗あり13.0分,なし19.0分でありχ2にて5%の有意差があった。平成14年度は医師同乗あり10.0分,なし14.0分であり有意差はなかった。医師が同乗時の処置内容は,応急処置ならびに病院についてから本格的な治療行為に移行するための準備処置が多かった。訪問診療件数は,平成11年度の2,591件に比べて平成14年度は1,699件と大きく減少していた。訪問看護は,平成11年度が1,872件,平成14年度が1,409件であり,往診の減少を補ってはいなかった。往診が減少した年度は,急病による救急搬送が増加している年度もあった。
結論 医師同乗は効果があった。しかし,有意差こそなかったが医師非同乗のケースが同乗のケースより重症度が高くかつ高齢者の割合も高いため,医師同乗率をより高めることが望ましいと思われた。日南病院滞在時間は,医師同乗ケースが,非同乗ケースより短かった。客観的な評価方法を模索したが現状では見つからなかった。日南町方式の医師同乗システムは地域医療の一端であるので,日南町における地域医療全体と合せて評価する必要があると思われた。
キーワード 救急車,病院前救護体制,ドクターカー,救急救命士
|
第52巻第2号 2005年2月 介護者における老親扶養義務感と人口学的要因の関係東野 定律(ヒガシノ サダノリ) 桐野 匡史(キリノ マサフミ) 種子田 綾(タネダ アヤ)矢嶋 裕樹(ヤジマ ユウキ) 筒井 孝子(ツツイ タカコ) 中嶋 和夫(ナカジマ カズオ) |
目的 在宅要援護高齢者の介護者のデータを用い,老親扶養義務感と人口学的要因の関連性について検討する。
方法 調査に必要なデータは,S県O市に在住し,平成14年4月1日現在,要介護認定を受けた第1号被保険者5,189名の要介護高齢者のうち,協力が得られたその主介護者1,143名を調査対象に実施した「高齢者を介護する家族の健康と生活の質に関するアンケート調査」から抜粋した。抜粋した項目は,主介護者の性,年齢,介護期間,要援護高齢者との続柄,老親扶養義務感とした。主介護者の性,年齢,介護継続期間が老親扶養義務感に与える影響をMIMICモデリングで検討した。このとき,性については女性を「0」,男性を「1」とカテゴリ化し,年齢は60歳未満を「0」,60歳以上を「1」,さらに継続期間は48か月未満を「0」,48か月以上を「1」とカテゴリ化した。
結果 老親扶養義務感には,性差のみが統計学的に有意な水準で差が認められ,女性に比べて男性が老親扶養義務感の得点が高い傾向を示した。なお,老親扶養義務感の下位因子との関連では,男性は女性に比べて「経済安定のための援助」と「保健のための身体的補助」に関連する得点が高く,また年齢が高いほど「経済安定のための援助」の得点は高かった。
考察 本研究では老親扶養義務感の下位概念(因子)別に前記要因の関連性を検討したが,性差は特に「経済安定のための援助」と「保健のための身体的補助」に関連する傾向を示していた。このうちの「保健のための身体的補助」に関しては,男性の半数は伴侶としての妻の介護を行っており,男性の特性が関与しているものと推察される。また,「経済安定のための援助」の義務感が男性で高かったことは,男性の社会的役割を前提にした傾向と推察されるが,さらに年齢が高い者ほど「経済安定のための援助」に影響していたことは年代差も影響している結果と推察された。
キーワード 要援護高齢者,介護者,老親扶養義務感
|
第52巻第4号 2005年4月 大都市部における後期高齢者の
|
目的 本研究は,大都市部における後期高齢者の閉じこもりに関連する要因を明らかにすることを目的とした。
対象と方法 墨田区に居住する75歳以上の男女1,000人(二段階無作為抽出)を対象に,2001年7月に調査を行った。調査は,訪問面接法によって行い,618人から回答を得た(回収率61.8%)。閉じこもりは,外出頻度や生活の行動範囲を指標とする「空間面」,社会関係や社会参加状況を指標とする「対人関係面」,孤立感を指標とする「心理面」の3側面から定義し,2つ以上の閉じこもりが重複しているか否かを総合指標として用いた。分析は,空間面・対人関係面・心理面の閉じこもりの有無と総合指標からみた閉じこもりの有無を従属変数とし,学歴,所得,世帯構成,生活機能障害の有無,疾患の有無,視力障害の有無,聴力障害の有無,性別,年齢を独立変数として投入したロジスティック回帰分析によって行った。閉じこもりの出現率の分析は,測定指標に欠測がない577人を分析対象とし,関連要因の分析は,投入する独立変数に欠測がない557人を分析対象とした。
結果 空間面の閉じこもりに該当した者の比率は11.3%,対人関係面では23.9%,心理面では21.8%であった。総合指標(2つ以上の閉じこもりの重複)からみた閉じこもりの比率は12.3%であった。ロジスティック回帰分析の結果,空間面の閉じこもりに関連する要因は,世帯構成(無配偶・同居子あり),生活機能障害,視力障害,高齢であった。対人関係面では,低所得,世帯構成(無配偶・同居子あり),生活機能障害,性別(男性)であった。心理面では,学歴,低所得,世帯構成(単身),生活機能障害,罹患であった。総合指標では低所得,世帯構成(無配偶・同居子あり),生活機能障害,罹患であった。
結論 階層的地位に関して,低所得の者ほど,対人関係面・心理面の閉じこもり,および2つ以上の閉じこもりが重複しているリスクが高い点が確認された。家族的地位に関して,無配偶・同居子ありの者は,空間面・対人関係面の閉じこもりのリスクが高い傾向,単身者は,心理的閉じこもりのリスクが高い点が示された。本研究の結果は,外出を促すものなのか,社会参加を促進するものなのか,孤立感の解消を目指すものなのかといった,閉じこもり予防の主要な目的によって,その介入対象が異なることを示唆している。
キーワード 閉じこもり,後期高齢者,所得,世帯構成
|
第52巻第4号 2005年4月 日本人渡航者のマラリア予防対策についての状況川上 桂子(カワカミ ケイコ) 木村 幹男(キムラ ミキオ) 橋本 迪子(ハシモト ミチコ)青木 和子(アオキ カズコ) 浜田 勝(ハマダ マサル) 谷畑 健生(タニハタ タケオ) |
目的 日本人渡航者が,マラリアに対する基本的知識,渡航先の流行の有無,帰国後にマラリア発症を疑うときの対処方法などについて認識できているかを明らかにし,日本人渡航者にはどのようなマラリア対策が必要なのかを検討する。
方法 2001年10月末から12月中旬の期間に,東京検疫所と大阪検疫所に予防接種を受けに来所した16歳以上の日本人渡航予定者に対して,自記式質問紙票を用いた調査を行った。調査内容は,渡航歴,渡航形態,渡航頻度,マラリアに対する基本的な知識(病名・症状・感染経路・予防法)の有無,渡航先のマラリア流行状況の把握の有無とその情報源,マラリアに関する知りたい情報,帰国後風邪症状が続く場合の対処行動,帰国後マラリアが疑わしい場合の相談先の把握の有無など,計25項目とした。
結果 調査依頼数468通のうち,回収数(率)は284通(60.7%)であった。そのうち,渡航国にWHOが規定するマラリア流行地を含む248通(53%)を有効回答とした。85%の者がマラリアの感染経路を「蚊」と正解回答し,83%の者がマラリアの主な症状を「発熱」と正解回答したが,マラリアの第1の予防法について「蚊に刺されないこと」と正解を答えた者は69%であった。渡航先でのマラリア流行の有無について「知っている」と回答した者の割合は41%と少なかった。渡航先のマラリア流行の有無の情報源は,「旅行の本・雑誌・ガイドブック」が最も多く,「旅行会社」は少なかった。また,80%の者は,帰国後マラリアが疑わしいときの相談先を「知らない」と答えていた。
結論 日本人渡航者のほとんどは,マラリアの病名,感染経路,主な症状についての知識は有していた。しかし,マラリアの予防法である渡航先の流行状況についての情報の入手,マラリアが疑わしいときの対処行動および相談先など,渡航者が自分で身を守るために必要な知識,態度が不足していた。今後,⑴渡航者が自分で身を守るという意識改善を目指す効果的な啓発を行うこと,⑵旅行会社が渡航者にマラリアについての正しい情報提供を行うことと,そのための公的機関(検疫所,保健所など)による支援が行われること,⑶国内各地でのマラリアを扱う医療機関が広く認知されること,が望まれる。
キーワード 渡航者,マラリア,予防,情報提供
|
第52巻第4号 2005年4月 介護保険サービスの給付費用増加の要因分析-次期介護保険事業計画策定における利用者ニーズの反映-牧野 雅光(マキノ マサミツ) |
目的 介護保険サービスの給付費用は,認定率の上昇によりその費用を大幅に増加させてきたが,サービスによっては各サービスに対する利用者の選好が著しく高まった影響により,費用が増加しているケースもあると考えられる。また,サービス間の代替が各サービスの選好率に対しても影響を及ぼすと考えられる。したがって,次期介護保険事業計画の策定においては,これまで以上に利用者の意向を反映したものにする必要があり,それによって昨今介護保険特別会計が赤字になっている市町村が増えているが,それに歯止めをかけることを目的として,調査分析を行った。
方法 厚生労働省と国民健康保険中央会が公表する介護保険サービスにかかわる給付費用などのデータを用い,それを各構成要素に要因分解することで,どのサービスの寄与度が費用増加に大きく寄与していたかを比較した。また,利用したいサービスが利用できなかった場合に利用したであろう副次的なサービス需要については,サービス間の代替を各サービスの選好率の相関をみることで分析した。
結果 総じて認定率の上昇が各サービスの給付費用の増加をもたらしているものの,居宅の3サービスにおいて利用者の選好が高まったことが大きく費用増加に影響を及ぼしていた。また,3サービスのうち福祉用具貸与と痴呆対応型共同生活介護は通所系や介護保険施設から,特定施設入所者生活介護は訪問系やショートステイから,それぞれサービスの代替がある可能性が認められた。
考察 サービスによっては認定率よりも選好率の高さが費用増加に大きく寄与しており,選好率の高いサービスで介護需要の大半を担っている市町村では介護保険財政が逼迫する恐れがある。また,これらの選好率が高かったサービスは他のサービスが利用できなかった二次的な潜在需要が顕在化したものと考えられる。したがって,次期介護保険事業計画においては利用者の意向の調査に際して,直接的なサービス需要のみならず,利用したいサービスが利用できなかった場合の二次的なサービスの需要についても捕捉することが望まれる。
キーワード 介護保険,給付費用,需要,要因分析,サービス代替,介護保険事業計画
|
第52巻第4号 2005年4月 HIV抗体検査受診者の特性についての保健所間差渡辺 晃紀(ワタナベ テルキ) 中村 好一(ナカムラ ヨシカズ) 城所 敏英(キドコロ トシヒデ)梅田 珠実(ウメダ タマミ) 長谷川 嘉春(ハセガワ ヨシハル) 田村 嘉孝(タムラ ヨシタカ) 谷原 真一(タニハラ シンイチ) 橋本 修二(ハシモト シュウジ) |
目的 保健所で実施するHIV抗体検査受診者の特性について保健所間差を記述する。
方法 任意の協力を得た全国131保健所における検査を受診した者を調査の対象とした。調査対象期間である2001年4月~2002年3月の検査受診者14,900人のうち8,972人に調査票を配布し,5,079人から回答を得,同時期に行われたHCV抗体検査目的とされる者を除いた4,102人を解析対象とした。保健所別の解析では,解析対象者が20人以上であった56保健所を対象とした。
結果 各指標の保健所別の分布を25パーセンタイル値~75パーセンタイル値の範囲で観察すると,男の割合が55.8~67.6%,25歳未満の若年者の割合が16.7~30.3%,再受診者の割合が21.5~30.9%,不特定多数との性的接触経験者が32.3~46.0%,男性同性間性的接触経験者の割合が3.7~9.9%であった。これらの保健所別の分布は地域ブロックによって違いがみられ,設置主体によってもいくつかの指標では違いがみられた。
結論 保健所のHIV抗体検査受診者の特性は,保健所間で差が認められた。地域や保健所の特性により検査受診者の特性が異なる可能性が考えられ,それらを考慮した感染防止対策の必要性が示唆された。
キーワード HIV,AIDS,HIV抗体検査,保健所
|
第52巻第4号 2005年4月 札幌市営地下鉄における投身事故の疫学西 基(ニシ モトイ) |
目的 札幌市営地下鉄で発生した投身事故に関し,疫学的な解析を行う。
方法 1994年4月1日から2004年3月31日までの10年間に札幌市営地下鉄で発生した99件の投身事故に関し,札幌市交通局がその都度報道機関へ発表したデータの提供を受け,これを解析した。
結果 1カ月を上旬・中旬・下旬に分けると,冬季休暇・春期休暇・夏季休暇明け(1月中旬,4月上旬,8月下旬)に発生頻度が有意に高まり,中2旬または中1旬おいた2月中旬,4月下旬,9月下旬に有意に低下する(件数はゼロ)という,明らかな傾向が認められた。朝の通勤・通学の時間帯(6時00分~9時59分)においては,件数は全体の24.2%を占め,かつ札幌市の中心から3㎞以上離れた駅で多かった。ターミナル駅での件数は,他の交通機関との接続のため利用客が多いにもかかわらず,有意に少なかった。1回の投身事故につき,平均16.7本の地下鉄が運休し,平均8,916.9人の利用客に影響が出た。
結論 日ごろ地下鉄を利用している者が,長期休暇が明けるなどして,通勤・通学などで地下鉄を利用しなければならない状況になって駅へ行き,衝動的に投身する場合が少なくないものと思われた。運休本数や被影響人員数から推定して,1回の投身事故で平均数千万円の経済損失が発生すると思われた。ターミナル駅での件数が少ないことについては,今回の資料のみでは合理的な説明ができず,投身者の特性などのデータにより,今後分析すべき課題と考えられた。
キーワード 疫学,時間的要素,自殺,地下鉄,投身事故
|
第52巻第3号 2005年3月 電算システムによる標準接種年齢時点における
樺澤 禮子(カバサワ レイコ) 田辺 直仁(タナベ ナオヒト) 関 奈緒(セキ ナオ) |
目的 わが国の小児予防接種事業は,感染症の好発年齢などを考慮して標準的な接種年齢が設定されている。予防接種事業の評価に際し,標準的な接種年齢終了時点での接種率を用いる有用性を明らかにする。
対象と方法 新潟県M地区7町村における平成12 年生まれの児のうち,転入・転出者を除外した838名を対象とした。複数回接種が必要なポリオワクチン(ポリオ)と三種混合ワクチン(三混)の接種率を, マイクロソフトエクセルのワークシートで作成した接種率計算プログラムにより計算し,町村ごとの予防接種の実施方法と対比することにより予防接種事業を検 討した。その際,ポリオは満18月,三混は満12月における接種率を用いた。
結果 ポリオ2回目の接種率は65.9~89.2% と町村間に大きなばらつきがみられた。80%を超えたのは3町村のみであり,さらなる接種活動の促進が望まれた。三混3回目の接種率でも 9.3~75.0%と低く,しかも大きなばらつきがあった。9.3%と特に低かったD町では集団接種の初回が満9~13月と実施月齢に問題があった。また D町を除いた集団接種と個別接種の町村間で3回目の接種率は,集団接種町村において高く,しかも年間の実施回数が多いほど高い傾向であった。ポリオ,三混 の初回接種月齢は,標準的な接種年齢での接種完了者(ポリオ:6.0±2.2月,三混:6.2±1.9月)が非完了者(ポリオ:11.1±5.8月,三 混:11.1±3.4月)に比べて有意に低かった(p<0.001)。
結論 標準的な接種年齢終了時点でのポリオ,三混両者の接種率は低値であり,初回の接種を早く行うように保護者と接種担当者への啓発活動を行う重要性が示唆された。また,接種率による各町村での予防接種事業の評価の普及が強く望まれた。
キーワード 予防接種,接種率,予防接種台帳,ポリオワクチン,三種混合ワクチン
|
第52巻第3号 2005年3月 勤労世代男女の死生観と終末期のケアへの期待日置 敦巳(ヒオキ アツシ) 田中 耕(タナカ タガヤス) 和田 明美(ワダ アケミ) |
目的 自己の死と終末期のケア・医療環境についての勤労世代住民の意識およびそれに関連する因子を明らかにする。
方法 二段抽出法により無作為抽出した30~59歳の岐阜県岐阜地域住民1,200人に対し,死に対する意識,終末期のケアおよび医療への期待について面接調査を実施した。回答率は77.2%であった。
結果 死についてどう感じているかという質問に対し,「考えたことがない」と回答した者の割合は30 歳代では約4割であり,40歳代と50歳代では約1/4であった。臨終立会経験のある者ではその割合は低かった。予後不良の疾患の告知希望に関与する因子 として,「低年齢」「臨終立会経験」「死を恐れていないこと」「死を受け入れようと努力していること」「死について気になるが恐れていないこと」が選択さ れた。自己の死を迎える場所として約8割が自宅を希望しており,現状との大きな乖離がみられた。
結論 死を取り巻く現状を知り,自己の死についての考察を深めることによって,住民に終末期のケアに関して真剣に考えてもらうようにすることも必要と考えられた。
キーワード 終末期,死,死生観,告知
|
第52巻第3号 2005年3月 急性期と終末期の患者が混在する
佐藤 康仁(サトウ ヤスト) 有賀 悦子(アルガ エツコ) 大堀 洋子(オオホリ ヨウコ) |
目的 本研究は,急性期と終末期の患者が混在する大学病院の一般病棟において,終末期医療にどのような問題が生じているのかを,医療従事者の立場から明らかにすることを目的とした。
方法 調査は,2001年12月中旬から2002年1月中旬にかけて,東京都内のA大学病院本院に勤務する全医師と全看護師を対象として行った。回収率は,医師35.3%(n=338),看護師86.8%(n=1,082)であった。
結果 医師については,「一般病棟は終末期患者が過ごす場として適切ではない(71.9%)」 「一般病棟は終末期患者の家族への配慮ができにくい(71.6%)」「終末期医療の知識・技術が不足であると感じる(68.9%)」の割合が高くなってい た。看護師については,「終末期医療の知識・技術が不足であると感じる(75.7%)」「急性期と終末期の患者が混在することによりストレスや疲労が増す (65.5%)」の割合が高くなっていた。グラフィカルモデリングの結果,医師と看護師に生じる問題点について,ほぼ同様のモデルが得られた。
結論 本研究から,大学病院の一般病棟において急性期と終末期の患者が混在することによる問題点が明らかとなった。質の高い医療の提供を実現するためには,大学病院における終末期医療について本格的な取り組みを行う必要があることが明らかとなった。
キーワード 大学病院,緩和ケア病棟,終末期医療
|
第52巻第3号 2005年3月 医療機関における院長と事務長の意識の違い-疾患に注目して-真野 俊樹(マノ トシキ) 水野 智(ミズノ サトシ) 小林 慎(コバヤシ マコト)井田 浩正(イダ コウセイ) 山内 一信(ヤマウチ カズノブ) |
目的 院長と事務長では,患者の医療機関選択についての認識に相違があるという仮説の検証を試みた。もし,認識に違いが生じていれば,患者の医療機関選択における医療情報提供に対する姿勢が異なっている可能性があり,ひいては患者の望む医療情報を提供していない可能性がある。
方法 調査対象を日本病院会会員病院(2,621施設)の事務長および院長とし,調査方法は無記名式質問紙郵送調査で行った。回収は1,090通で,回収率は21%であった。
結果(成績) 「患者さんが風邪と思われる症状の場合に何を基準に医療機関を選ぶと思われますか」という問いに有意水準5%で有意差がみられた。すなわち,患者が風邪と 思われる症状の場合では,事務長は専門性を重視したが,院長は重視しなかった。一方,「風邪」「吐血」「糖尿病の疑い」「糖尿病の診断」の各々の問いに は,院長の回答,事務長の回答ともに,「糖尿病の疑い」「糖尿病の診断」についての組み合わせを除き,x2検 定で有意差がみられた。結論風邪という軽症疾患を除いて,上述の仮説は成立していない。医療機関は必ずしも消費者が必要な情報を発信していない理由とし て,院長と事務長の認識の差であるという要因の関与は,重症疾患では,本研究の結果からは少ないといえる。しかしながら,軽症疾患,あるいは予防といった 領域では,異なった結果が出る可能性もあるので今後の研究が重要である。
キーワード 医療情報,事務長,院長,医療機関選択
|
第52巻第3号 2005年3月 在宅要介護高齢者の主介護者における
桐野 匡史(キリノ マサフミ) 矢嶋 裕樹(ヤジマ ユウキ) 柳 漢守(ユ ハンス) |
目的 高齢者虐待の早期発見あるいは予防に向けた取り組みに資することをねらいとして,在宅要介護高齢者の主介護者を対象に,彼らの介護負担感の各側面と心理的虐待の関連性を明らかにすることである。
方法 調査対象は,平成14年4月1日現在,S県O市内に居住し,かつ要介護認定を受けていた65歳以上の高齢者(第1号被保険者)の主介護者5,189名であり,そのうち,協力が得られた1,143名に対して質問紙法による調査を実施した。介護負担感の測定にはFamily Caregiver BurdenInventory(FCBI)を使用した。FCBIは, 介護負担感を「社会活動に関する制限感」「要介護高齢者に対する拒否感情」「経済的逼迫感」の3つの側面から評価する尺度である。心理的虐待の測定には, 既存の研究を参考に,著者らが独自に作成した測定尺度を使用した。この尺度は,要介護高齢者に対する「言語的攻撃」と「拒絶」の2領域計10項目で構成した。統計解析には構造方程式モデリングを使用し,介護負担感の3つの側面(因子)を独立変数,心理的虐待を従属変数とする多重指標モデルを検討した。
結果 介護負担感を測定するFCBIの3つの側面のうち,「要介護高齢者に対する拒否感情」因子と「経済的逼迫感」因子は「心理的虐待」因子と有意な関連性を示した。特に,要介護高齢者に対する拒否感情は心理的虐待と強い関連性を示した。介護負担感の3つの下位因子の「心理的虐待」因子に対する説明率は47.9%であった。
考察 本 結果から,早急に介護負担感を軽減するための対策,たとえば介護者のメンタルケアや介護状況の改善を企図した支援はもとより,虐待の早期発見・早期介入に 向けた支援体制の確立が求められる。さらに,高齢者虐待の予防・早期発見といった観点を強調するなら,単に虐待発生要因を探索するのみならず,虐待発生ま でのメカニズムをとらえるためのモデルの拡張と洗練が必要である。
キーワード 高齢者,介護負担感,心理的虐待,在宅介護,家族介護者
|
第52巻第4号 2005年4月 株式会社等の病院経営参入問題-開設主体による意識の相違-堀 真奈美(ホリ マナミ) 真野 俊樹(マノ トシキ) |
目的 株式会社による医療機関への経営参入が議論されるようになっているが,十分な資料に基づき議論がなされているとは言いがたい。そこで株式会社などの経営参入問題について,開設主体(「国公立・公的病院」「個人・医療法人」「その他」)による意識の相違など実態把握を目的に調査を実施した。
方法 2003年1月,日本国内病院2,621施設の院長あてに「医療機関における営利・非営利性問題」の意識を問うアンケート調査を実施し,開設主体による意識の相違の有無を検討した。
結果 (1)「総論として株式会社の病院経営」は反対が多い(64.1%)。個人・医療法人では賛成が22.9%と多く,開設主体間に有意差が認められる(p<0.01)。「既存病院が株式会社化して病院経営を行う」「病院が株式を上場する」にも,個人・医療法人は他より好意的で,開設主体間に有意差がある(p<0.01)。(2)「病院が株式会社化したときのメリット」として,個人・医療法人は「資金調達が容易になる」をあげ,開設主体間に有意差が認められる(p<0.01)。(3)現行の医療法人制度について,国公立・公的病院は「現行のままでいい」が多い(59.1%)。個人・医療法人は「若干の手直しが必要」40.8%,「根本的な改革が必要」29.9%が多く,統計的に有意である(p<0.01)。「現行のままでいい」以外の病院に対して,「他の制度がよい」「持分を廃棄すべき」「財団法人になるべき」「特定医療法人になるべき」「特別医療法人になるべき」「持分限度額法人になるべき」の是非を尋ねると,「どちらとも言えない」が多い。「他の制度がよい」以外では開設主体間の差は統計的に有意である(p<0.01~0.05)。(4)カテゴリカル主成分分析により,2つの軸(「医療機関をとりまく競争環境」と「医療機関の意識と規模」)が認められる。
結論 株式会社の病院経営については,いずれの開設主体でも反対意見が多いが,個人・医療法人病院の中には,経営健全化の手段として,株式会社の病院経営や医療法人制度の改革に少なからず関心を持っているものもある。その場合でも,外部からの参入に関しては否定的である。一方,国公立・公的病院は,株式会社の病院経営に関しては否定的であるが,医療法人制度については,当事者でないためか意見が中立的である。ただし,開設主体と医療機関をとりまく競争環境・病床規模に密接な関係がみられたため,意見の相違が開設主体によるものなのかその他の要因によるものなのか厳密に区分することができず,今後の課題である。
キーワード 医療機関,株式会社等の病院経営参入,開設主体,医療法人制度,非営利性,アンケート調査
|
第52巻第6号 2005年6月 救急搬送者の追跡調査細田 武伸(ホソダ タケノブ) 藤田 利治(フジタ トシハル) 谷畑 健生(タニハタ タケオ)武本 和之(タケモト カズユキ) 足立 三紀(アダチ ミキ) 亀崎 幸子(カメザキ サチコ) 小谷 和彦(コタニ カズヒコ) 黒沢 洋一(クロサワ ヨウイチ) 能勢 隆之(ノセ タカユキ) |
目的 本調査は,救急搬送車の救急車要請要因および傷病程度別分類(重症,中等症,軽症)と実際の傷病程度別分類の定義による入院期間の一致の割合,救急車の要請要因(一般的属性,特異的属性),救急車が有料になった場合の使用の是非等について把握することを目的として実施した。
方法 調査対象は,鳥取県広域行政管理組合消防局の救急搬送記録に記載されている鳥取県西部地区(2市12町村)で搬送された平成13年の救急搬送者6,948人から,その他(医療機関の要請による転院搬送者),死者,海外居住者,住所不定者,重複利用記録分を除外し,残った5,450人を傷病程度別に分け,系統抽出法により2分の1を抽出した,2,725人(重症474人,中等症1,080人,軽症1,171人)とした。平成14年8~9月に,郵送法による自記式無記名の質問紙調査を行った。督促を1回行った。不配達分を除いた回収率は,56.3%であった。
結果 傷病程度別分類と救急車要請要因でクロス表を作成し比較した。χ􌛌検定にて有意であった項目は,「要請するまでの時間」(p<0.05),「居住形態」(p<0.01),「年齢」「居住地区」「住居形態」「要請者」「要請手段」「要請原因」「要請理由」(いずれもp<0.001)であった。「病気の症状が発生してからまたはけがにあってから要請するまでの時間」の項目では,重症の者ほど,その時間が長い傾向があることが推測された。「搬送先医療機関希望の有無」では,56.1%の者が搬送先の医療機関を指名し搬送を希望しており,重症の者ほど,搬送先を希望する傾向があった(p<0.05)。搬送者が搬送時に区分された傷病程度別分類と分類の定義に従った実際の入院期間は,重症で21日以上入院または入院中に死亡した者は63.4%,中等症で1~20日入院した者は38.4%,軽症で実際に入院をしなかった者は65.2%であった。「有料使用の是非」では,軽症の者は14.4%が有料になったら救急車を使用しないと答えていた。
結論 現行の傷病程度別分類を用いて傷病者の増加・減少を論ずるには一考を要すると思われた。救急搬送された高齢の者は,重症でかつ予後も悪い傾向にあることが示唆された。疾病の予防や介護も含め高齢社会に対応した救急医療体制を構築することが急務と思われた。
キーワード 救急搬送車,救急車,追跡調査
|
第52巻第6号 2005年6月 日本におけるがん生涯リスク評価加茂 憲一(カモ ケンイチ) 金子 聰(カネコ サトシ) 吉村 公雄(ヨシムラ キミオ)祖父江 友孝(ソブエ トモタカ) |
目的 今日のがんリスクを一般国民にとってわかりやすい形で示すことは,効果的ながん対策を行うにあたって非常に重要な役割を果たすと考えられる。そのための指標の1つとして,わが国における生涯がん罹患(死亡)リスクと,年齢を限定しての累積リスクを推定した。生涯がん罹患(死亡)リスクとは,一生涯のうちにがんに罹患(死亡)する確率の推定値である。また年齢を限定しての累積リスクとは,がん未発症年齢と到達年齢を限定しての罹患(死亡)確率の推定値である。
方法 わが国における1975年から1999年のデータを用い,がんリスクを推定した。リスク推定には人口,全死亡数,がん死亡数,がん罹患数を用いた。粗罹患率,粗死亡率を用いて,がん罹患(あるいは死亡)に関する生命表を作成した。その際にリスクの過大評価を避けるために,がん以外の死亡率を組み込んだ。また最高齢の階級に対しては,人年計算による補正を行った。この生命表をもとに,生命表上でのがん罹患数(死亡数)を求め,生涯リスク,あるいは年齢を限定しての累積リスクを推定した。
結果 1999年の生涯がん罹患リスクは男性で46.3%,女性で34.8%,同年の生涯がん死亡リスクは男性で29.4%,女性で20.5%と推定された。経年的には1975年以降,罹患,死亡リスクともほぼ単調に増加し,1999年には男性で罹患リスクが1.8倍増,死亡リスクが1.6倍増となり,女性で罹患リスクが1.7倍増,死亡リスクが1.5倍増となった。部位別にみると,生涯罹患リスクは男女とも胃がんが最も高く,男性で10.5%,女性で5.6%であった。生涯死亡リスクが最も高かったのは,男性では肺がんで6.6%,女性では胃がんで3.4%であった。
考察 1999年の生涯リスクから,男性の約半分,女性の3人に1人ががんに罹患し,男性の3人に1人,女性の4人に1人ががんにより死亡することがわかる。経年的にも生涯リスクは増加しており,この指標により今日のがんリスクの高さが直感的でとらえやすい形になったと考えられる。一方で,がん未発症年齢と到達年齢を限定してのリスク表から今後のリスクの変遷を知ることができる点も,国民にとってこの指標はリスクを直感的に認識しやすいものにしたと考えられる。今後は,競合リスクやがん因子の曝露を組み込んだ「発展形」によるリスク評価が期待される。
キーワード 生涯罹患リスク,生涯死亡リスク,生命表,DEVCAN
|
第52巻第6号 2005年6月 認知症高齢者のケアマネジメントにおける
|
目的 介護支援専門員の研修を企画・実施する基礎資料を得るため,認知症高齢者のケアマネジメントにおける社会保障制度の理解と活用状況について,医療職と福祉職との比較を通して,実態を明らかにすることを目的とした。
方法 調査対象者は岡山県内の指定居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員1,234名とし,郵送調査法により調査を実施した。調査内容は,属性,認知症高齢者が活用できる17の制度の活用状況,理解していない制度の有無,社会保障制度活用の能力不足感で構成した。統計解析には,各調査項目に欠損値のないものを用いた。解析方法として,医療職と福祉職の群間比較にはχ2検定を用い,社会保障制度の活用状況にはクラスター分析を用いて類型化し,コンボイモデルを用いて模式化した。
結果 回答は502名(回収率41%)から得られた。認知症高齢者のケアマネジメントにおいて,社会保障制度の活用状況では医療職と福祉職との間に有意差は認められなかったが,両職種ともに医療系サービスを利用する上で最も有効と考えられる通院医療費公費負担制度ですら理解されていないことが判明し,概して福祉職に比べて医療職は制度を理解していない傾向がみられた。また,両職種ともに多くの者が社会保障制度活用に対して能力不足を感じていることが明らかとなった。
結論 事例を通した制度活用の演習,医療職の理解度に重点を置いた制度概要の講義の実施,センターの医療ソーシャルワーカーによる助言・情報提供の体制づくりが必要であると考えられた。
キーワード 認知症高齢者,ケアマネジメント,社会保障制
|
第52巻第6号 2005年6月 虚血性心疾患の男性入院患者における
蓮尾 聖子(ハスオ セイコ) 田中 英夫(タナカ ヒデオ) 脇坂 幸子(ワキサカ サチコ) |
方法 対象者は,1998年6月~2002年3月の間に大阪府立成人病センターに入院した虚血性心疾患の男性喫煙患者(入院当日に喫煙中または禁煙後31日以内であった者)290名とした。全入院患者に依頼する自記式の入院時問診票に,喫煙状況調査票とエゴグラム調査票を添付して配布した。看護師が全数を回収し,添付した調査票を著者らが病棟から回収した。回収日から約6ヵ月後(6ヵ月調査)と12ヵ月後(12ヵ月調査)に自記式の喫煙調査用往復葉書を自宅へ郵送し,把握された喫煙行動と入院時ベースラインデータとの関連を調べた。
結果 喫煙調査の返信者割合は6ヵ月で67.2%(195/290),12ヵ月で70.0%(203/290)であった。両調査とも,返信者と未返信者の属性に有意な違いを認めなかった。両調査時点における断面禁煙率をみると,6ヵ月調査では返信者で46%,未返信者をすべて喫煙者とみなすと31%であった。同様に12ヵ月調査では45%と31%であった。次に,退院後となる6,12ヵ月の各調査時点の喫煙行動と関連する要因を調べた。6ヵ月調査では,在院日数,入院日喫煙状況,ニコチン依存度,自己効力感の4要因との有意な関連がみられ,12ヵ月調査では,在院日数と入院日喫煙状況との有意な関連がみられた。退院後の禁煙状態に関連する要因をロジスティック回帰分析で調べると,「在院日数が15日以上であること」と,「入院の前日までに禁煙していたこと」が6ヵ月後の禁煙に有意に関連しており(オッズ比,順に3.6,5.6),その関連は12ヵ月後でも同様に認められた(同2.1,4.4)。退院後の喫煙行動と特定のパーソナリティには,明らかな関連は認められなかった。
結論 当施設に入院を経験した虚血性心疾患の男性喫煙患者の少なくとも5割は退院後に喫煙を続けていたと推測された。また,在院日数が長くなることは,退院後の禁煙状態を継続させやすい要因であることが示された。
|
第52巻第5号 2005年5月 筋萎縮性側索硬化症患者における
岡本 和士(オカモト カズシ) 紀平 為子(キヒラ タメコ) 近藤 智善(コンドウ トモヨシ) |
目的 筋萎縮性側索硬化症(以下「ALS」)患者におけるQOL(生活・生命の質)の維持・確保のための精神的支援を含めた本人・家族と医療・福祉従事者との間の支援体制の構築が急務とされている。そこで,本研究の目的は,ALS患者のQOLを1年前の状況との比較から評価するとともに,その変化に関連する要因を明らかにすることである。
対象と方法 2004年9月に,愛知県内に居住するALS患者258名に郵送による質問票調査を行い,回答の得られた98名(回収率:38.0%)を解析対象とした。QOL関連要因として「身体の痛み」「精神的安定度」「食欲」「睡眠状況」「コミュニケーション」を用い,1年前との比較からQOLの変化の状況を評価した。QOLの変化の指標として,各々の要因について変化の程度(悪化=1点,不変=0点,改善=-1点)を合計して求めたQOL低下度を用いた。
結果 5つのQOL関連要因のうち1年前と比べ悪化したと答えた者の割合が最も高かった要因は「精神的不安定の増加」で,次いで「身体の痛みの増加」であった。QOL低下度と性,年齢,発症時年齢およびADLとの間に有意な関連はなかった。QOL低下度は精神的活動性の高いものほど有意に小さかった。また,人工呼吸器非装着者のQOL低下度は装着者に比べ有意に大きかった。
結論 ALS患者のQOLの維持・確保のために,患者家族や地域の医療担当者を含めた包括的な精神的活動性および食事量の維持・確保のためのサポート体制を構築する必要性を示唆する知見を得た。
キーワード 難病,筋萎縮性側索硬化症,QOL,ソーシャルサポート
|
第52巻第5号 2005年5月 患者調査における病院での
寒水 孝司(ソウズ タカシ) 浜田 知久馬(ハマダ チクマ) |
目的 患者調査では,施設あたりの調査数が多いことで,大規模な病院に大きな負担がかかっている。平成11 年の調査では,出生の日が奇数の患者については,性別,出生年月日,疾病名,診療科名など複数の項目を詳細調査し,出生の日が偶数の患者については,性 別,出生年月日,入院・外来の種別のみを簡易調査している。そこで,大規模病院での詳細調査率を削減する調査シナリオを考える。そのような調査シナリオが 患者数の推定精度に与える影響を評価し,標本設計の改善を試みるのが本稿の目的である。
方法 詳細調査数を削減し,これを簡易調査で補えば,調査票の記入者負担が軽減される。そこで,詳細調査率を現在の1/2 から1/3または1/4に削減することを考える。まず,詳細調査率削減の適用条件・非適用条件を設定し,詳細調査率を削減する施設を選ぶ。適用条件につい ては2つの基準を想定する。次に,適用条件と詳細調査率の各組み合わせによる調査シナリオを平成11年患者調査データに適用し,各疾病の患者数の推定精度 の変化をシミュレーションによって評価する。最後に,推定精度低下の許容範囲を設定し,どの調査シナリオが適当であるかを評価する。推定精度の指標には標 準誤差率を用いる。
結果 適用条件を「医療施設静態調査の在院患者数が200 以上の施設」にすると,詳細調査率を1/3に削減できるのは32都道府県,1/4に削減できるのは21都道府県であった。さらに,適用条件を「医療施設静 態調査の在院患者数が300以上の施設」にすると,詳細調査率を1/3に削減できるのは39都道府県,1/4に削減できるのは34都道府県であった。これ より,患者数の推定精度をある程度維持した下で,すべての都道府県を対象に調査シナリオを適用するのであれば,適用条件を「医療施設静態調査の在院患者数 が300以上の施設」,詳細調査率を1/3にするのが適当であることが分かった。このとき,詳細調査率削減の対象とする母集団施設数は,9,286施設中 802施設(8.6%)であった。
結論 患 者数の推定精度をある程度維持した下で,詳細調査数を削減することは可能である。患者数の推定精度は都道府県ごとに異なるので,都道府県ごとに詳細調査率 削減の適用の可否を設定できるのであれば,患者数の推定精度が低い都道府県では,詳細調査率の削減は避けるべきである。
キーワード 患者調査,記入者負担,詳細調査率
|
第52巻第5号 2005年5月 ポピュレーション・ストラテジーのための評価指標の開発須賀 万智(スカ マチ) 吉田 勝美(ヨシダ カツミ) |
目的 ポピュレーション・ストラテジーによる健康増進対策を進めるにあたり,優先課題を選定する基準や各種健康増進対策の効果を測定する基準が必要である。本研究では,集団の分布の違いを包括的に表わす評価指標を開発した。
方法 東京都内の某健診機関から,2001年に実施された労働安全衛生法による定期健康診断のデータ136,524名(20~59歳;男性84,592名:女性51,932名)を収集した。全体を基準集団,そのうち3事業所(集団T382名;集団S1,858名;集団K2,345名)を対象集団にした。BMI,収縮期血圧,拡張期血圧,中性脂肪,総コレステロール,空腹時血糖,尿酸,GOT,GPT,γGTP,ヘモグロビンの11項目について,性年齢階級別の平均と有所見率と分布を求め,4種類の指標,すなわち,⑴平均,⑵有所見率,⑶分布カテゴリーに単純増加する重みを乗じた値(分布単純型),⑷分 布カテゴリーにJ字増加する重みを乗じた値(分布J字型)により,対象集団における上位3項目(基準集団に比べ,好ましくない方から3項目)を選定した。 平均による上位3項目とそれ以外の3種類の指標による上位3項目を比較して,一部の項目のデータが不足している集団Sの20歳代男女を除いた22性年齢階級66項目のうち両者が一致した割合(一致率)を求めた。
結果 平均による上位3項目を基準にした一致率は,有所見率が50% (33/66),分布単純型と分布J字型が62%(41/66)であり,分布単純型と分布J字型の方が大きかった。実際の分布から,平均,分布単純型,分 布J字型による上位3項目において,観察度数分布は期待度数分布よりも右方シフトしていることが確認された。4種類の指標の統計学的特性や臨床的妥当性を 比較検討した結果,分布J字型が推奨された。
結論 分布カテゴリーにJ字増加する重みを乗じるという本研究の指標は対象集団において優先課題を選定する基準を提供して,ポピュレーション・ストラテジーによる健康増進対策を支援すると期待される。
キーワード ポピュレーション・ストラテジー,健康増進,評価指標
|
第52巻第5号 2005年5月 東京都定点HIV検査相談センターにおける
橘 とも子(タチバナ トモコ) 阿保 満アポ ミツル) 杉下 由行(スギシタ ヨシユキ) |
目的 東京都定点HIV検査相談センターにおける既存情報の分析結果から受検者情報の活用に要する改善案を考察し,今後のHIV検査相談推進策の一助とすることが目的である。
方法 対象期間は1993年9月1日~2002年12月31日,対象情報は東京都定点HIV検査相談センターを受検した非感染者のうち日本語質問票への自記式回答協力者延べ67,804人分である。
結果 定点センター受検HIV抗体陰性者の基本属性について年次推移を分析した。男性:女性=7:3であり,「20 歳代」と「勤務者」の回答割合が多かった。一方,「初回」受検者は数・割合とも年々減少し,複数回受検割合は年々増加していた。受検動機となった感染不安 内容は「不特定パートナー」との「異性間性的接触」であり,感染不安から受検までの期間は1年以内が多く,年々増加傾向であった。
結論 定点センター受検者は,「20歳代」と「勤務者」が多いと推定され,都内保健所において平日昼間開設のHIV検査相談利用不可能層を補完する利便性改善が図られていると考えられた。今後,個人の行うHIV/AIDS予防行動を一層きめ細かく支援できる具体的施策立案の根拠として情報を活用し,住民や団体と協働で取り組むヘルスプロモーションの媒体としての利用を提案する。
キーワード 自発的HIV検査相談,HIV血清抗体検査,受検行動,匿名,施策企画立案
|
第52巻第5号 2005年5月 医療経営からみた医療事故および
今村 知明(イマムラ トモアキ) |
目的 医療事故に関する民事裁判で必要となる経費および医療事故での民事裁判の現況を明らかにする。
方法 東 大病院において医療訴訟を維持していく上で蓄積された情報,最高裁判所の公表情報,公的に損害賠償の基準の1つになっている自動車損害賠償責任保険の保険 金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準をもとに,医療裁判に必要となる経費を分析する。また,最高裁判所の資料等をもとに医療裁判の現況を 調査する。
結果 医療事故に関する民事裁判にかかる経費のうち,裁判費用と弁護士費用については,国や弁護士会等において基準が定められており,その詳細を示した。最も大きな金額となったのは損害賠償金額であり,死亡のケースで逸失利益を除く慰謝料だけで2000~2800 万円程度,後遺障害については状況により100~3000万円程度となった。医療裁判の現状として,一般的に通常民事事件における原告勝訴率が85%程度 であるのに対し,平成2年以前の民事医療過誤訴訟事件における原告勝訴率は35%程度である。近年,原告勝訴率は50%程度まで上昇してきていると考えら れている。また,現状では和解が64%程度,認容が18%程度となっており,病院からすると何らかの賠償金を支払ったとみられるケースは全体の82%に達 すると考えられた。
結論 安全対策に道義的上限はないが,病院経営の視点からすれば,人の命や障害を換金して考えることに社会的抵抗があるものの,最終的に安全性と経済性のバランスをとる必要があり,この判断は各医療機関の責任者の最も重要な使命であると考える。
キーワード 医療経営,医療事故,費用,医療裁判
|
第52巻第7号 2005年7月 認知症ケアに関する施設管理職の意識人見 裕江(ヒトミ ヒロエ) 寺田 准子(テラダ ジュンコ) 中村 陽子(ナカムラ ヨウコ)畝 博(ウネ ヒロシ) 小河 孝則(オガワ タカノリ) 斎藤 美智子(サイトウ ミチコ) 郷木 義子(ゴウギ ヨシコ) 岡 京子(オカ キョウコ) 森山 美恵子(モリヤマ ミエコ) 廣野 祥子(ヒロノ ショウコ) |
目的 グループホームを除く介護保険施設(以下「介保施設」)および老人性痴呆疾患治療病棟(以下「病棟」)における管理者の認知症ケアに関する意識を明らかにすることを目的とした。
方法 山陰地方および大阪市に登録されている介保施設である介護老人保健施設,介護老人福祉施設,介護療養型医療施設および全国老人性痴呆疾患治療・療養病棟一覧(平成13 年)から抽出した病棟における,看護および介護直属の管理者を対象とした質問紙調査を実施した。介保施設は依頼した226施設のうち57施設(25%), 病棟は依頼した191施設のうち43施設(23%)の管理者から回答を得た。調査内容は,施設の概要,認知症のある利用者の状況のほか,認知症ケアに関す る施設管理者の意識,すなわち,認知症の判断,認知症ケアに関するスタッフへの特別の指示,事故防止対策,自助グループ育成についてである。介保施設と病 棟との2群を比較検討し,管理者の意識についてはFisherの直接確率で有意差の有無を調べ,自由記載項目については内容を分析した。
結果 事故防止対策を介保施設と病棟の2群で比較すると,病棟で非常によく対策をとっており,有意差(p<0.05) が認められた。また,自助グループ育成活動を2群で比較すると,有意差は認められなかったものの病棟で積極的に推進している可能性があった。認知症ケアに 関するスタッフに対する特別の指示は病棟で有意に多く,その内容は抑制や拘束に関するものが多い傾向が示された。また,介保施設では,病棟に比べ事故対策 が徹底していた。
結論 施設の法的枠組みも考慮した,対象の人権を保障する管理者の意識改革が必要である。
キーワード 管理者,認知症ケア,施設,身体拘束,自助グループ
|
第52巻第7号 2005年7月 日常生活の関心の志向性と主観的生活の質が
|
目的 主観的健康感の分布の地域差を観察し,主観的健康感を規定する因子としての日常生活の関心の志向性や主観的生活の質(主観的QOL)が主観的健康感に及ぼす影響を,社会文化的環境が異なる地域で,性,年齢別に比較検討する。
方法 全国16 の市区町村で,65歳以上の高齢者を500人ずつ無作為(一部任意)抽出し,8,364人を対象として,2002年7~10月に留置法により調査した。調 査項目のうち,目的変数として主観的健康感を用いた。説明変数としては,調査した16項目の日常生活の関心の志向性を再編した4つの「日常生活の関心の志 向性」,および調査した16項目の主観的QOLを再編した5つの「主観的QOL指標」を評価した。対象を,男女別,年齢によって前期・後期高齢者,居住地域によって都市部・郡部に分け,合計8群にし,各群を主観的健康感によって「健康群」「非健康群」の2群に分けた。χ2検定を用いて各説明変数について単変量解析を行い,非健康群に対する健康群のオッズ比と95%信頼区間を求めた。
結果 調査票の回収率は80% (6,699人)であった。解析はすべての項目に回答のあった5,627人を対象とした。このうち健康群は70%,非健康群は30%で,健康群の割合は後 期高齢者,郡部居住者で低かった。日常生活の関心の志向性については,高いオッズ比が観察された項目は主に地域別によって異なっていた。都市部では男女と も安楽悠々志向以外の多くの項目で有意に高いオッズ比が観察されたが,郡部では女の後期高齢者を除けば自己実現志向のみでオッズ比が有意に高かった。主観 的QOL指標については,主に性,年齢別に高いオッズ比が観察された項目が異なっていた。男の前期高齢者では生活のハリの項目で,男の後期高齢者では自立の項目でオッズ比が高く,女では満足感や心理的安定の項目でオッズ比が高い傾向にあった。
結論 地域によって主観的健康感の分布が異なっていた。また,性別,年齢別,居住地域ごとに主観的健康感に影響を与える日常生活の関心の志向性や主観的QOL指標が異なっていた。このことから,高齢者に一様に接するのではなく高齢者一人一人の背景因子を考慮し,これらの関連の強い主観的QOL指標を高めるように留意しながら高齢者に対応することによって主観的健康感の向上,あるいは維持につながると思われた。
キーワード 高齢者,主観的健康感,日常生活の関心の志向性,主観的生活の質,年齢差,地域差
|
第52巻第7号 2005年7月 A市における乳幼児健康診査の受診
|
目的 乳幼児健康診査の受診の有無と育児支援事業の利用の有無に関連する要因の探索を目的とし,育児環境に対する母親の認知および抑うつ状態に焦点をあてて検討した。
方法 研究の対象は,3歳前後の子どもを末子にもつA市在住の母親400名とした。期間は2003年1月9日~2月9日,方法は無記名自記式調査票の郵送配布・訪問回収法で,分析対象者は231名(57.8%)であった。
結果 3回の乳幼児健康診査(4ヵ月・7ヵ月・1歳6ヵ月)のうち1回以上未受診であることには「気が合わない子どもがいる」という母親の認知が関連していた(オッズ比3.85)。 一方,5種の育児支援事業(訪問指導・育児講座・育児サークル・面接相談・電話相談)について,利用経験の有無に関連する要因は各事業ごとに異なり,それ ぞれの特性とニーズが示唆された。訪問指導・育児講座・育児サークルの利用に共通して関連していたのは,母親仲間からのねぎらいや援助に対する期待であ り,面接相談の利用に関連していたのは,夫婦関係の困難さ,否定的な母性意識であった。また,電話相談の利用に関連していたのは,母子・夫婦・隣人関係の 困難さ,否定的な母性意識,そして母親の抑うつ状態であった。
結論 「子どもと気が合わない」という母親の認知が乳幼児虐待の危険因子であることを踏まえ,乳幼児健康診査未受診の家庭を対象とした積極的なフォローアップ体 制を整備していく必要性が示唆された。育児困難ケースのスクリーニングという観点からも,今後は,乳幼児健康診査の受診・未受診状況を活用することが有用 であろう。また,各種の育児支援事業ごとに異なる利用者特性を踏まえた事業運営の重要性が示唆された。特に相談事業においては,育児困難を抱える母親や抑 うつ状態にある母親が利用している可能性を前提とし,必要に応じた個別の介入が求められよう。
キーワード 乳幼児健康診査,母子関係,メンタルヘルス,育児
|
第52巻第7号 2005年7月 うつ1次スクリーニングにおける
中俣 和幸(ナカマタ カズユキ) 相星 壮吾(アイホシ ソウゴ) 西 宣行(ニシ ノブユキ) |
目的 鹿児島県では平成14 年度から各種保健事業の場を活用して「うつ状態」の1次スクリーニング(以下「うつスクリーニング」)を5保健所管内で実施している。その中で,基本健康 診査(老人保健事業)(以下「基本健診」)の場を活用して実施したうつスクリーニングは受診者数が最も多いことから,判定結果と各設問ごとの回答状況につ いての基礎資料を得る上で基本健診での状況を分析することが最も有用であると考え,性・年齢別の分析と各設問の回答状況の分析を行うこととした。
方法 平成14 年度と15年度にうつスクリーニングを受診した者のうち,基本健診とその結果報告会の場で受診した5,492人を調査対象として,うつスクリーニングの 「1次陽性確定者」の性・年齢別の出現状況およびうつスクリーニングの8項目の設問ごとの性・年齢別の回答状況について分析した。
結果 全体の「1次陽性確定者率」は7.1% で,性・年齢別では4.8%から13.6%までの幅があった。40歳代・50歳代を除いた年代で,陽性者率は女性の方が男性よりも高かった。男女ともに年 齢が増すにつれて陽性者率は低下する傾向が認められた。うつスクリーニングの8調査項目ごとの「初期陽性反応率」は1.3%から20.2%の範囲であっ た。特に高かった項目は,「自分は役に立つ人間だと考えることができない」(20.2%)で,「以前は楽にできていたことが,今ではおっくうに感じられ る」(19.4%)と続いていた。8項目すべてによる総合的な評価である「1次陽性確定率」の評価と共に,各設問ごとの「初期陽性反応率」を求めることに より,より詳しい「こころの健康」状態の把握が可能となると考えられた。
結論 うつスクリーニングの「1次陽性確定者」は40 歳代・50歳代の男性で比較的多く出現しているが,鹿児島県ではこの年代の基本健診受診率は他の年代の受診率よりも低い現状である。今後の「こころの健康 づくり」活動を展開する上で,この年代層の基本健診受診率向上対策が求められる。性・年代によって「生きがい維持を主としたアプローチ」「身体機能維持を 主としたアプローチ」「うつ気分への対応方法を主としたアプローチ」を適宜組み合わせてプログラムを企画するなどの工夫が,対策を考える際により効果的で あろうとの示唆を得た。
キーワード うつスクリーニング,基本健康診査,こころの健康づくり,1次陽性確定者率,初期陽性反応率
|
第52巻第7号 2005年7月 介護充実感尺度の開発西村 昌記(ニシムラ マサノリ) 須田 木綿子(スダ キウコ) Ruth Campbell(ルース キャンベル)出雲 祐二(イズモ ユウジ) 西田 真寿美(ニシダ マスミ) 高橋 龍太郎(タカハシ リュウタロウ) |
目的 高齢者を介護する家族介護者の介護体験への肯定的認知評価を測定するための尺度として「介護充実感尺度」(Caregiving Gratification Scale)を開発し,その構成概念妥当性(因子的妥当性),交差妥当性(因子不変性)および信頼性の検証を行った。
方法 東京都葛飾区および秋田県大館市・田代町に在住の65 歳以上の要介護認定者(施設サービス利用者を除く)を介護する家族(主介護者)を対象に訪問面接調査を行い,それぞれ655人,381人から回答を得た (回収率は各62.0%,73.3%)。尺度の妥当性の検討には構成方程式モデリングを用いた。まず,地域別に因子的妥当性を検討した。次に,両地域の同 時分析を行い,地域間における因子構造の異同,すなわち交差妥当性の検討を行った。尺度の信頼性の検討には,信頼性係数αおよび多因子構造を前提とした信頼性係数ωを算出した。
結果 地域別の分析の結果から,「介護役割における自己達成感(達成感)」と「被介護者との通 じ合い(一体感)」の2因子各4項目からなるモデルの適合度が受容水準を十分に満たしていることが明らかになった。両地域の同時分析の結果から,因子負荷 量,因子の分散共分散,誤差分散を等値制約した2因子モデルが採択され,両サンプルの共分散構造の相等性が確認された。信頼性係数αおよびωは,いずれも十分な値を示した。
結論 本研究で開発された「介護充実感尺度」は,構成概念妥当性,交差妥当性および信頼性を有する尺度であることが示された。
キーワード 家族介護者,介護充実感,構成概念妥当性,交差妥当性,信頼性
|
第52巻第7号 2005年7月 新基準集団における質問紙健康調査票THIの
浅野 弘明(アサノ ヒロアキ) 竹内 一夫(タケウチ カズオ) 笹澤 吉明(ササザワ ヨシアキ) |
目的 東大式自記健康調査票Todai Health Index(THI)が開発されてから,約30年が経過した。従来,THIにおける個人得点の判定は,1975年に調査を実施した都内某大手商社員集団のデータをもとに行われてきたが,時代の推移を考慮し,THI処理用新システムの開発を契機に新たに基準集団を設定することとした。本稿では,この新基準集団とそこにおけるTHIデータ分布の概略について報告する。
方法 1993年,群馬県のS市とK村において,40~69歳の地域住民を対象とした「寝たきりとボケを予防するための健康調査」の一環として,THIを用いた健康調査を実施した。両地域合わせて12,630名の対象者中,11,565名(91.6%)の有効回答を得た。THIは,肯定・否定・中間の3選択肢をもつ130の質問から構成され,12の健康尺度得点と3つの傾向値(判別値)を計算することができる。今回,各得点の信頼性に配慮して,有効回答者のうち総未記入数が5問以下の者10,596名を新基準集団とし,このデータに対して各種統計指標を算出した。
結果 各 健康尺度得点の平均値は,多くの尺度において男女差が小さくなっていた。また,男性,女性のいずれにおいても,平均値が従来より低くなる傾向が認められ, 特に,女性において顕著であった。累積相対度数分布も,平均値同様に,低い値にシフトしていた。年齢区分別の平均値を分散分析により比較した結果,多くの 尺度において,年齢とともに有意に低下する(健康状態の自己評価が良くなる)傾向が認められた(p<0.05)。
結論 新基準集団による尺度得点などの評価は,従来と比較し,特に女性において,みかけの陰性者を少なくする判定結果をもたらすことになる。これは,THIの利用目的である,不健康者の早期発見にもつながることであり,2004年から運用を開始したパソコン用THI処理システムにおいては,新基準集団でのデータを採用している。これらシステムも活用しながら,新基準集団の妥当性について,今後様々な角度から検討していく予定である。
キーワード THI,Total Health Index,質問紙健康調査票,データ分布,平均値,累積相対度数
|
第52巻第6号 2005年6月 全国の市町村における「健康日本21」地方計画の策定と評価若林 チヒロ(ワカバヤシ) 國澤 尚子(クニサワ ナオコ) 新村 洋未(シンムラ ヒロミ)尾島 俊之(オジマ トシユキ) 川島 美知子(カワシマ ミチコ) 萱場 一則(カヤバ カズノリ) 三浦 宜彦(ミウラ ヨシヒコ) 柳川 洋(ヤナガワ ヒロシ) |
目的 全国の市町村における「健康日本21」地方計画の策定と評価の現状について明らかにすることを目的とした。
方法 全国3,207市町村(2003年3月現在)を対象に行った「健康づくりに関する現状調査」(2003年6月実施)で回答のあった2,570市町村のうち,市町村合併が行われなかった2,516市町村を対象に,2004年3月,自記式質問紙による郵送調査を行った結果,1,641市町村から回答があった(回答率65.2%)。
結果 「健康日本21」地方計画を策定済みまたは策定予定の市町村は72.6%に達していたが,都道府県別の開きが大きく,人口規模の小さい市町村で策定率が低かった。地方計画の最終評価時期は2010年または策定から10年後と位置づけており,中間評価もそれに合わせて予定していた。評価方法は,健診結果の利用または質問調査の実施とした市町村が多かったが,人口規模の小さい市町村では質問調査の実施予定率が低く,評価方法の種類も少なかった。
結論 「健康日本21」地方計画の策定状況,中間および最終評価の実施予定,評価に用いる資料について,人口規模別の違いを明らかにした。中間・最終評価の実施に当たっては,地域の保健所,大学などの支援が必要である。
キーワード 健康日本21,市町村,地方計画,評価
|
第52巻第8号 2005年8月 認知症高齢者の家族介護者における家族からの
北村 世都(キタムラ セツ) 時田 学(トキタ ガク) 菊池 真弓(キクチ マユミ) |
目的 認知症高齢者の家族介護者を対象に,①非認知症高齢者の家族介護者とQOLを比較すること,②家族(配偶者・子ども・親族)からの心理的サポートの認知(心理的サポートニーズ充足状況)と主観的QOLはどのように関係しているかについて,介護者と要介護者の続柄ごとに明らかにする。
方法 対象は東北地方のI市在住の在宅要介護認定者の家族介護者7,500名で,平成15年1月に郵送法により質問紙調査を行った(回収率61.0%)。そのうちの有効回答2,544名を分析対象とした。質問紙の内容は,①介護者・要介護者の基本属性,②介護者の心理的サポートの現状とニーズ,③介護者の主観的QOL尺度(石原ら,1992)の3項目とした。なお,心理的サポートニーズ充足状況について,ニーズと現状との組み合わせから,サポートの提供者ごとに充足・不足・過多・非関与の4群に分類した。
結果 QOL尺度を従属変数,認知症の区分(3区分)と介護者の続柄(8種)を独立変数とした二元配置分散分析および認知症家族介護者のみについて介護者の続柄ごとに行ったQOL尺度を従属変数,サポートニーズ充足状況を独立変数とした一元配置分散分析の結果,以下のことが明らかとなった。①認知症介護者は非認知症介護者よりQOLが全般に低い。②子どもからの心理的サポートはQOLを低下させていた。③実親の介護者は親族からの過剰なサポートでQOLを低下させていた。④夫を介護する妻は要介護者本人からの情緒的サポートがQOLを高めていた。⑤義母を介護する嫁はQOLが高く,配偶者のサポートがQOLをさらに高めていた。⑥介護者の続柄によりQOLを高めるサポート種は異なっていた。
結論 認知症家族介護者のQOLは要介護者に認知症がない場合に比べて低いことが示された。さらに,介護者と要介護者の関係の近さが介護者のQOL低下と関係があること,特に実子による同性の親の介護では介護者の年齢が中年期から老年期への移行期であり,介護を通じて介護者が自分自身の生涯発達課題に直面する可能性があることを指摘した。今後は認知症介護のもつ特殊性などを質的に分析することが必要である。
キーワード 認知症家族介護者,心理的サポート,QOL,生涯発達,続柄
|
第52巻第8号 2005年8月 最近のわが国の低体重児割合の上昇要因
角南 重夫(スナミ シゲオ) 勝山 博信(カツヤマ ヒロノブ) |
目的 最近のわが国の低体重児割合の上昇の原因を探る。
方法 わが国の昭和55年から平成12年までの21年間の人口動態統計を用いて,①死産率,複産割合,妊娠期間別出生割合,出生順位別出生割合,母の平均年齢,非嫡出割合のそれぞれと低体重児割合との相関,②同期間の低体重児割合の変化と,死産率,複産割合,妊娠期間,出生順位,母の年齢,非嫡出割合の変化との比較,③低体重児割合の変化に対するこれらの要因の寄与率を調べた。
結果 最近のわが国の低体重児割合の上昇と,死産,複産,妊娠期間,出生順位,母の年齢,非嫡出に関連が認められたが,これに対する寄与率は,死産,複産,妊娠期間が比較的大きかった。
結論 最近のわが国の低体重児割合の上昇に死産の減少,複産の増加,妊娠期間の短縮の関与が考えられる。
キーワード 低体重児,死産,複産,妊娠期間,人口動態統計
|
第52巻第8号 2005年8月 精神的健康度と受診行動との関連について-レセプト情報を活用した保健事業の推進-八尋 玄徳(ヤヒロ モトノリ) 馬場園 明(ババゾノ アキラ) 西岡 和男(ニシオカ カズオ)石原 礼子(イシハラ レイコ) 亀 千保子(カメ チホコ) |
目的 精神的健康度を1つの健康指標とした保健事業を展開することが医療経済的観点から効果があることを示すために,レセプト情報等を用いて精神的健康度と受診行動との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 対象者を精神的健康度に問題ある群,問題ない群の2群に分類し,2群間で入院外医療費,診療実日数,レセプト件数等について対応のないt検定を行った。また,同様に,1人当たり複数・多・重複受診件数,PDM法を用いて算出した生活習慣病における1人当たり傷病別診療実日数・傷病別医療費についても対応のないt検定を行った。さらに,入院外医療費,診療実日数,レセプト件数を従属変数とし,栄養,運動,休養といった一般的な健康指標とGHQ30得点結果を独立変数として重回帰分析を行った。この際,性,年齢,家族形態,就業状況を独立変数に含めることで交絡因子の影響を調整した。
結果 精神的健康度に問題ある群は問題ない群に比べ,入院外医療費,診療実日数,レセプト件数が有意に高く,年間の1人当たり複数受診件数と多受診件数が多い傾向が認められ,また,傷病分析により,精神的健康度が生活習慣病の中でも内分泌,栄養及び代謝系の疾患の傷病別医療費に影響を及ぼす可能性が示唆された。さらに,重回帰分析により,GHQ30得点が入院外医療費,診療実日数,レセプト件数に対して有意な影響要因であるとの結果を得た。
結論 精神的健康度と受診行動との間に何らかの関連がある可能性が示唆された。これにより,多受診や複数受診を対象とした保健事業においてメンタルヘルス面の施策を行うことが医療経済的に効果がある可能性が示唆されたものと考えられる。
キーワード 精神的健康度,GHQ30,レセプト,複数受診,重複受診
|
第52巻第8号 2005年8月 静岡県における在宅特定疾患患者の状況林 敬 (ハヤシ タカシ) |
目的 静岡県内在宅特定疾患医療費受給者(以下「特定疾患患者」)の生活や災害対応の状況を明らかにすることにより,同県における難病施策向上の参考にする。
方法 平成15年度の特定疾患制度改正時に,国(46疾患),県(3疾患)指定の医療費公費負担の新規および更新申請者を対象に,療養状況,生活自立度,医療処置,障害者認定と介護保険認定の状況,QOL(痛み,不安,社会との接触),災害時の対応について,記名自記式アンケート調査を行った。
結果 筋萎縮性側索硬化症に加え,スモン,パーキンソン病関連疾患,広範脊柱管狭窄症,後縦靱帯骨化症,脊髄小脳変性症,悪性関節リウマチなどの平均年齢が高い疾患(以下「高齢疾患」)において,日常生活に何らかの支障がある者が多く,QOLの各指標が低かった。その他,特発性間質性肺炎では,酸素療法などの在宅医療処置を受けている者が多く,QOLの中の社会との接触が減っている者が多かった。主要な高齢疾患においては,生活に支障がある者の75%以上が障害者(身体障害者手帳所持)または介護認定を受けていた。災害対応について,全体の14%が本人または家族で避難が困難としており,筋萎縮性側索硬化症や高齢疾患に多かった。このうち約6割が,個人情報の市町村等への提供について行ってもよいと回答していた。
結論 静岡県における在宅特定疾患患者の状況として,原疾患に加えて加齢による日常生活の支障やQOLの悪化への影響が示唆された。また,筋萎縮性側索硬化症のほかにも,呼吸器系の疾患において支援強化の必要性が考えられた。生活に支障がある多くの患者が障害者や介護保険の認定を受けていたことから,難病患者にかかわる居宅生活支援事業などに加え,介護保険や障害にかかわるサービスも充実させる必要がある。災害対策については,平常時から患者自らによる防災対策の推進に加え,個人情報の保護に配慮した要援護者台帳の関係機関での共有が必要である。
キーワード 難病,特定疾患,高齢化,呼吸器系疾患,災害対策,個人情報
|
第52巻第8号 2005年8月 HIV感染者の社会福祉施設利用受け入れに
小西 加保留 (コニシ カホル) |
目的 HIV感染者が社会福祉施設サービスを利用しようとするときに,サービス提供者側が抱える不安や課題となる要因を明らかにするとともに,どのような要因がサービス提供や受け入れ意向に影響を及ぼしているかを分析することを目的とした。
方法 調査対象は,重度身体障害者更生援護施設,身体障害者療護施設,知的障害者更生施設,児童養護施設,精神障害者生活訓練施設の全数(計2,377)で,調査方法は自記式質問紙を用いた郵送法,調査期間は2003年10~11月とした。調査項目は,①基本属性,②環境要因,③HIV感染者の受け入れに関連する83項目,④受け入れ意向にかかわる2項目であり,分析は,単純集計,因子分析,一元配置分散分析,重回帰分析により行った。
結果 ⑴22施設においてHIV感染者の受け入れ経験があった。⑵受け入れに関連する因子として,抗体検査実施義務,性への陽性価値観,他者への対応困難感,感染対応理解困難,医療体制,性への対応困難感,性支援システム,法的責任,感染発生時不安,健康管理,自慰行為容認,コスト保障の12因子が抽出された。⑶各因子のうち,性への陽性価値観,感染対応理解困難,医療体制は,施設間で有意な差がみられなかった。⑷受け入れに際して阻害要因となりうる因子は,他者への対応困難感,感染発生時不安,感染対応理解困難,抗体検査実施義務,コスト保障,健康管理であり,促進要因となりうる因子は,性への陽性価値観,性支援システム,自慰行為容認であった。⑸受け入れ意向に影響を与えている因子は,施設間で差がみられた。
結論 今後のHIV感染者の受け入れを促進するには,マイナス要因を解決し,プラス要因を促進するような働きかけが重要である。例えば,「性に関する価値観や支援システム」に関する学習の機会の提供,「感染発生時の不安」に対する的確な知識の提供,「他者への対応困難感」に関する具体的な場面を想定した理解や組織のリーダーシップのあり方の検討,福祉・医療の制度全体にかかわる課題としての「コスト」の問題の考察などである。また,利用者の特性や対応への不安の程度など,施設種別による個別の課題への方策の必要性も示された。
キーワード HIV感染者,社会福祉施設,サービス利用,受け入れ意向,阻害要因,促進要因
|
第52巻第10号 2005年9月 市区町村別平均寿命の全国順位の変化からみた
竹森 幸一(タケモリ コウイチ) 三上 聖治(ミカミ セイジ) 工藤 奈織美(クドウ ナオミ) |
目的 平均寿命の年次推移に特徴がある長野県と沖縄県について,市区町村別平均寿命の全国順位の変化から,両県平均寿命の特徴を明らかにすることを目的とした。
方法 1985 年,1990年,1995年,2000年の市区町村別平均寿命を用いて2005年の市区町村別平均寿命を予測した。各年の全国市区町村の平均寿命につい て,平均寿命の長いものから,1,2,...というように順位を付けた。長野県,沖縄県それぞれの各市町村の平均寿命全国順位について,1985年から 2000年までの回帰係数(回帰係数1)と1985年から2005年までの回帰係数(回帰係数2)を計算し,p値を求めた。回帰係数1と回帰係数2の相関 を男女別に計算した。回帰係数1と1985年から2000年までの市町村別平均寿命の延び(年)との相関係数と回帰式を求めた。
結果 市区町村平均寿命の全国順位の回帰係数は長野県・男の場合,負の市町村が多く,県全体の順位中央値では1985 年の299から2000年の234と順位が改善された。女の場合も下降すなわち順位がよい方に移行した市町村が多く,県全体の順位中央値では1985年の 808から2000年の578と順位が改善された。沖縄県・男の場合,順位が上昇すなわち順位が悪い方に移行した市町村が多く,県全体の順位中央値では 1985年の436から2000年の1753と順位が悪化した。女の場合,男の場合と同様に上昇すなわち順位が悪い方へ移行した市町村が多く,県全体の順 位中央値では1985年の29から2000年の91と順位が悪化した。沖縄県・女の場合,市区町村別平均寿命の全国順位の中央値が指数関数的に悪化し,将 来,順位が急速に悪化することが予測された。長野県,沖縄県の男女とも回帰係数1と回帰係数2に有意の相関がみられた。1985年から2000年までの市 区町村別平均寿命の全国順位の回帰係数1と同期間の市町村別平均寿命の延び(年)の間に負の有意の相関がみられた。
結論 長野県は男女とも市区町村別平均寿命の全国順位が改善した市町村が多かった。一方,沖縄県は男女とも順位が悪化した市町村が多く,特に女は将来急速に順位が悪化することが予測された。
キーワード 都道府県別平均寿命,市区町村別平均寿命,平均寿命の延び,平均寿命の順位,平均寿命の予測
|
第52巻第10号 2005年9月 OLAPによるDPCデータの解析伏見 清秀(フシミ キヨヒデ) |
目的 平成15年にわが国独自の診断群分類DPC(Diagnosis Procedure Combination)を用いた包括評価が導入されているが,制度設計上議論となる点が残っており今後の改善が必要とされている。そのためには,毎年7月から10月にDPC包括評価対象病院から収集される膨大な調査データの効率的で正確な解析が不可欠であるが,その手法は確立されていない。本稿では,DPC調査データの解析にOLAP(On Line Analytical Processing)を活用する方法を検討し,その実効性を検証することを目的とした。
方法 調査データからリレーショナルデータベースと多次元データキューブを構築し,ネットワークおよびローカルファイルを介してクライアントソフトを用いてOLAP解析を実施した。OLAPキューブは定義表の項目に沿って7から26個の集計軸を設定し,病名集計軸に関してはICD10コード,DPC傷病名分類,MDC分類レベルの3段階の粒度で集計する設計とした。副傷病は併存症と続発症に分けてその影響度を集計した。
結果 システム構築,分析の実施,データの配布の実現可能性と有用性が確認された。対話的な分析により,手術グループの差異による在院日数への影響の違い,化学療法,放射線療法などの在院日数,診療報酬点数への影響の違いなどが示された。また,副傷病の解析では,DPC傷病分類レベルの集計によって,循環器系疾患においては呼吸不全,腎不全の影響が大きく,消化器系疾患においては肺炎の影響が大きいなど,主たる疾患によって医療資源必要度に影響を与える副傷病が異なることが示された。
結論 DPC調査データの解析におけるOLAP法の活用の実現可能性と有用性が示された。特に現在のDPC定義表では十分に整理されていない副傷病の評価については意義が大きいと考えられる。DPCの恒常的な見直し作業にOLAP法が活用され,データに基づく医療評価の1つのツールとしての地位が確立されることが期待される。
キーワード 包括評価,診断群分類,医療費,医療評価,探索的分析
|
第52巻第10号 2005年9月 市町村合併が市町村の地域保健サービスに
安武 繁(ヤスタケ シゲル) 名越 雅彦(ナゴシ マサヒコ) 烏帽子田 彰(エボシダ アキラ) |
目的 市 町村合併の進展により,県が実施している保健事業が市町村に移譲される動きがある状況下で,市町村合併が市町村の地域保健サービスに及ぼす影響の見通しな どの実態を把握し,市町村合併による市町村の地域保健活動の機能強化,県の支援のあり方について検討することを目的とした。
方法 平成14年12月に中国地方5県の36カ所の県型保健所を対象として,郵送によるアンケート調査を実施した。調査内容は,管内における市町村合併の進ちょく状況と地域保健業務に及ぼす影響,県が実施している専門的事業の市町村への移譲の可能性,県の広域的取り組みなどである。
結果 中国地方5県において市町村合併後の管内市町村数までわかっている23 の県型保健所では平均で3.0市町になることが分かった。また,市町村合併が予定どおり進んだ場合,管内市町村数が1ないし2になる保健所では,組織体 制,予算配分などの点において現状のままでは合併自治体間におけるアンバランスが生じる可能性があると認識している傾向が認められた。合併後の県の専門的 事業のあり方との関係では,ひきこもり対策において,合併後でも管内市町村数が5以上と比較的小規模の合併が予定されている保健所で,今後も県が実施すべ きという傾向が認められた。
結論 市町村合併が進展する時代にあって,地方機関としての県の保健所は高度な専門的機関へと特化することが求められる。市が新たに保健所を設置する場合の要件として人口30 万人がその目安となっている。この人口要件については,検査体制の整備や健康危機管理事案に対する人材の養成,事案の発生頻度,あるいは現在の一般の市町 村で実施可能な保健サービスの内容を勘案すると,効率性や技術水準の担保の視点からも人口要件を緩和することは適当でないと考えられる。また,今後も市町 村合併が進展すれば,特に比較的中規模の市については,県は地域保健サービスの展開にあたり,県の有する保健所,総合精神保健福祉センター,試験研究機 関,学術団体(大学)など相当高度な専門機関の技術力を背景とした機能強化を踏まえて,市と協働した,広域的な幅広い分野で先駆的な課題と調査研究に取り 組み,充実展開を図ることに重点を置くべきと考えられる。
キーワード 市町村合併,地方分権,保健所
|
第52巻第10号 2005年9月 障害有病率に入院患者数を
丸谷 祐子(マルタニ ユウコ) 京田 薫(キョウダ カオル) 伊藤 美樹子(イトウ ミキコ) |
目的 切明らが提唱する介護保険データのみを用いたdisease(disability)-free life expectancy(以下「DFLE」)と,介護保険データに入院患者を加味した新たなDFLEを算定し,標準誤差,構成概念妥当性という点から比較,検討することを目的とした。
方法 まず,都道府県,性,年齢階級別の平成11年患者調査の入院患者および平成14年10月の介護保険認定者を年齢調整した上で,Sullivan法を用いて都道府県,性,65歳,75歳,85歳の年齢階級別にDFLEを算定した(以下「DFLE 」)。その比較対照として,介護保険認定者のみを用いて同様にDFLEを算定した(以下「DFLE 」)。次に,年齢階級別の静岡県男性DFLE , の標準誤差と,人口規模をシミュレーションさせた場合の標準誤差を算定し,それぞれの値を比較,検討した。最後に,65歳における都道府県・性別のDFLE , と死亡や受療,高齢者の活動性を示す指標などとの相関関係から構成概念妥当性を検討した。
結果 65歳静岡県男性の標準誤差はDFLE が0.011年,DFLEⅠが0.010年であった。シミュレーションした人口規模の比較では,DFLEⅠ, ともに28万人から2.8万人に,2.8万人から2,800人に変化させたとき,標準誤差はそれぞれ約3倍増加したものの標準誤差自体は小さかった。また,DFLEⅠ,Ⅱとも標準化死亡比や入院・外来患者数とr>-0.3の負の相関がみられ,高齢者の活動性を示す指標とはr>0.3の正の相関がみられた。さらにDFLEⅠは,1人当たり老人医療費と負の相関を示し,老人クラブ参加者割合,入院患者数との正の相関係数はDFLEⅡより高かった。
結論 DFLEⅠは人口規模が小さい場合でも標準誤差が小さかった。また,健康指標との相関関係の結果から,DFLEⅠはDFLEⅡより妥当性が高いことが示唆された。これらのことから入手可能な既存データを用いたDFLEⅠの算定は有用であると考えられた。
キーワード DFLE,介護保険認定者,入院患者,標準誤差,構成概念妥当性,地域指標
|
第52巻第10号 2005年9月 児童館の利用が子どもの遊びや生活に与える影響八重樫 牧子(ヤエガシ マキコ) |
目的 子どもの遊びの実態を明らかにするとともに,児童館の利用が子どもの遊びや生活にどのような影響を与えているのか検討することを目的とした。
方法 平成15年6~7月,小学3年生950人を対象に子どもの遊びや生活について,留め置き自計によるアンケート調査を実施した。有効回答数は917人(有効回答率97%)であった。子どもの遊びや生活に関する15項目を得点化し,児童館利用との関連性を検討した。
結果 子 どもは,小人数の同年齢(同じクラス)の友達と,屋外ではスポーツや運動,屋内ではパソコン・テレビ・ゲームで遊んでおり,受動的な遊び方と能動的な遊び が共存していることが明らかになった。遊び友達の人数は男子の方が多かった。児童館を利用している子どもは3割弱と少なかったが,男女差は認められなかっ た。子どもの遊び・生活に関する15 項目については,女子の平均点が高く,因子分析の結果から得られた「共感性得点」「自主性得点」「表現・鑑賞得点」のいずれも女子の方が高かった。児童館 を利用している子どもと利用していない子どもの遊び・生活の平均得点については有意差が認められなかったが,得点の高い群に児童館を利用している子どもが 多く,有意差が認められた。単回帰分析の結果,児童館の利用頻度が高いと共感性が高くなり,遊び友達の人数が多くなると推察された。しかし,重回帰分析の 結果からは,子どもの遊び・生活得点に影響を与える要因は,性別,塾・習い事,遊び友達の人数であり,児童館利用頻度との間に関連性は認められなかった。 また,遊び友達の多い子どもほど児童館をよく利用していることが推察された。
結論 児 童館を利用する子どもは遊び友達が多く,また,児童館を利用することによって遊び友達も多くなることが明らかになった。遊び友達が多い子どもほど子どもの 遊び・生活得点が高くなっており,子どもの仲間集団の重要性が示唆された。今日,地域社会の遊びの拠点として位置づけられた児童館は,子どもが豊かな遊び を展開し,子ども同士・子どもと大人の相互行為を通じて,社会力や対人関係能力を育てることができる場として重要な役割を担っていると言える。
キーワード 児童館,遊び,児童健全育成,仲間集団,社会力
|
第52巻第10号 2005年9月 静岡県における健康寿命と要介護疾患渡辺 訓子(ワタナベ ノリコ) 久保田 晃生(クボタ アキオ) 鈴鹿 和子(スズカ カズコ)赤堀 摩弥(アカホリ マヤ) 藤田 信(フジタ マコト) |
目的 要介護となる原因疾患を分析し,健康寿命の延伸対策に資するための基礎資料を作成する。なお,この研究では,「健康寿命」を要介護でない期間,「障害期間」を介護の必要とする期間とし,要介護状態の人員は介護保険制度の利用者とした。
方法 健 康寿命と障害期間の算出は切明らが開発した計算式を使用した。要介護の人員は国民健康保険団体連合会による確定給付統計の人員とした。要介護疾患の特定は 介護保険関係書類の転記と分析によった。その際,「疫学研究に関する倫理指針」に基づき,県内7市町のデータ提供者に承諾を求めた(男性526人,女性1,148人)。
結果 静岡県の健康寿命は,平成16 年では男性77.0年,女性80.0年であった。7市町での健康寿命は65歳以上の介護保険認定割合が低いほど長くなる傾向があり,男性は0.82,女性 は0.61の負の相関がみられた。要介護となる原因疾患は,単一の疾患では男女ともに脳梗塞が最も多く,男性では27.5%,女性では20.7%を占め た。三大要介護疾患についてその占める割合をみると,脳血管疾患は男性で39.5%,女性で27.6%,筋骨格系疾患は男性で18.6%,女性で 34.8%,認知症は男性で8.1%,女性で14.0%であった。
結論 介 護保険制度利用者数を健康寿命算出に用いる場合は,制度利用率により結果が左右されるため,同一の自治体で比較することが適当である。また,介護保険申請 書類からは要介護となる原因疾患やその発病年齢や介護度が判明し,介護予防の事業根拠や評価に利用できることが示唆された。介護保険データを保健事業に定 例的に還元するためには,還元データを最小限にし,原因疾患をコードに変換するなど簡素化することが課題と考えられた。
キーワード 健康寿命,疫学研究に関する倫理指針,介護保険,三大要介護疾患
|
第52巻第11号 2005年10月 高齢者における多受診,重複受診と薬剤処方に関する研究小川 裕(オガワ ユタカ) |
目的 地方都市の無床診療所で受診した高齢者について,多受診,重複受診に関する実態とそれに伴う薬剤処方上の問題点について検討する。
方法 65 歳以上の診療所受診者を対象として,性,年齢,日常生活動作能力,受診時の主訴,他医療機関受診の有無,受診ありの場合は受診先,診療科,診断(症状)名 とその認識度,使用中の薬剤とその認識度,薬剤の受領先などについて,記録票をもとに診療録からの転記と問診を行った。
結果 記録票作成完了者は,男性80 人(37%),女性134人(63%)の計214人であった。受診目的(主訴)は男女とも「慢性疾患継続治療中(定期受診)」が最も多く,次いで「急性疾 患」であった。当診療所受診時に他医療機関受診継続中の者は男性49人(61%),女性83人(62%)で,そのうち「病院受診あり」は男性23人,女性 28人,「診療所受診あり」は男性36人,女性67人であった。受診している診療科は男性では歯科,眼科,内科,女性では眼科,内科,歯科の順であった。 他医療機関で処方を受けていた者は男性35人(44%),女性73人(54%)と分析対象者の約半数を占めた。薬剤の受領先は,「2カ所以上の院外薬局」 が男性17人,女性39人と処方薬ありの者の約半数を占め,次いで「院内薬局と院外薬局」が男性9人,女性22人で,「1カ所の院外薬局」は男性8人,女 性8人のみであった。また,記録票作成時に他医療機関での処方内容が何らかの根拠で把握できた者は,男性19人(処方薬ありの者の54%),女性26人 (36%)のみであった。
結論 複 数の医療機関受診者の他医療機関での処方内容を受診時に把握することが困難な例が多く,処方上のトラブルを回避するためには,個々の診療場面や地域保健活 動を通じて注意を喚起するとともに,調剤薬局でのチェック機能を強化するなど,多面的な対策を講じる必要があると考えられた。
キーワード 高齢者,多受診,重複受診,医薬分業
|
第52巻第11号 2005年10月 保健統計に基づく糖尿病と高血圧の
村田 沙和美(ムラタ サワミ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) 谷脇 弘茂(タニワキ ヒロシゲ) |
目的 保健統計に基づいて,糖尿病と高血圧の受療者数と有病者数について,1995~2002年の年次推移を観察した。
方法 患者調査と国民生活基礎調査から,1995~2002 年における糖尿病と高血圧の1日患者数,総患者数,通院者数と主傷病通院者数を算定した。糖尿病実態調査から1997年と2002年の糖尿病有病者数を, 国民栄養調査と循環器疾患基礎調査から1995年と2000年の高血圧有病者数を受療の有無別に算定した。
結果 糖 尿病の年次推移では,通院者数と主傷病通院者数が増加傾向,総患者数と1日患者数がほぼ横ばい傾向であった。高血圧の年次推移では,通院者数が増加傾向, 主傷病通院者数,総患者数と1日患者数が減少傾向であった。人口の年齢構成を調整すると,通院者数は糖尿病で増加傾向,高血圧でほぼ横ばい傾向となった。 有病者数は両疾患ともに増加傾向であり,人口の年齢構成を調整すると糖尿病で増加傾向,高血圧で減少傾向となった。有病者の受療割合は両疾患ともに20%程度で,やや上昇傾向であった。
結論 糖尿病と高血圧の受療者数と有病者数について最近の推移傾向を記述した。両疾患ともに有病者の受療割合が高くないと示唆された。
キーワード 保健統計,糖尿病,高血圧,有病者,受療者,年次推移
|
第52巻第11号 2005年10月 国民生活基礎調査における健康のとらえ方
|
目的 公的統計調査における自覚的健康状態の測定方法や,健康状態に影響する社会環境因子の測定法などについて検討を行うとともに,測定結果をもとに計算されうる地域健康指標について内外の事例をもとに実用可能性について考察する。
方法 国 民生活基礎調査健康票と米国・英国などの健康・世帯面関連公的統計質問票について自覚的健康状態などの測定尺度を比較した。内外の大規模疫学調査などで用 いられた実績があり,日本語版の妥当性評価がなされている健康尺度について,その適応・内容・長所短所などを比較した。健康余命をはじめとする地域健康指 標概念についてはMurrayら(2000)の概念整理をもとに分類し,現在入手可能な公的統計を用いた場合の実施可能性などを比較した。
結果 こ れまで内外で用いられてきた5段階の自覚的健康度評点尺度は,死亡率などの予測因子としては意義が認められているものの,事実上2値変数として取り扱われ ることが多く,健康量を連続量的にとらえるには問題がある。また「こころの健康」やストレスの状況についてはこれまで取り扱いが不十分であり,今後,大規 模疫学調査で実績をもつ既存尺度の導入や,測定項目の理論的再整理などが必要である。地域健康指標については様々な指標が試算・発表されてきているが,入 手可能な統計の範囲と指標の解釈可能性を考えると,実施可能性の高い尺度は限られている。地域健康指標を計算する上でも,自覚的健康度の測定は内外の統計 との比較可能性や信頼性・妥当性検証の状況を考慮し,既存の健康尺度の導入を考える必要がある。健康に影響する社会因子として社会的支援や社会関係資本な どの測定項目を加えることについても検討の余地がある。
結論 公 的統計における健康状況の測定尺度については世帯面調査で「健康」「こころの健康」を調査する目的を明確にした上で,比較可能性・妥当性の高い既存尺度か ら選択する必要があると考えられた。各種地域健康指標にもそれぞれ長所短所がみられるため,データ入手の可能性,政策的解釈の実用性などから,選択的・戦 略的に尺度を選ぶことが重要と思われる。また健康の測定方法については内外の統計間の互換性・整合性についても配慮が求められる。
キーワード 自覚的健康,こころの健康,地域健康指標,公的統計,国民生活基礎調査
|
第52巻第11号 2005年10月 SMRの経験的ベイズ推定量についての検討-奈良県市町村別死因統計を用いて-佐伯 圭吾(サエキ ケイゴ) 岡本 希(オカモト ノゾミ) 森田 徳子(モリタ ノリコ)車谷 典男(クルマダニ ノリオ) |
目的 市町村別の年齢調整死亡率の検討には,標準化死亡比(Standardized Mortality Ratio。以下「SMR」)が多く用いられるが,死亡数の偶然のばらつきによってSMRは大きく変動する。こうしたばらつきの調整方法として,SMRの経験的ベイズ推定量(Empirical BayesEstimateof SMR。以下「EBSMR」)の有用性が示され,ハイパーパラメータの推定方法が異なる2つのEBSMRの算出方法も紹介されている。本稿は,奈良県の市町村別死因統計を用いて,SMRとEBSMRの差と期待死亡数との関連を観察するとともに,奈良県で多く発生する胃がん死亡を例に,SMRを含めたこれら3つの統計量の比較を目的とした。
方法 奈良県の市町村別に,主な40死因のSMRを算出し,Poisson-Gammaモデルのベイズ推定法に基づく丹後の方法に従って,モーメント推定量(ME)に基づくmeEBSMRと,死亡数の周辺尤度の最尤推定量(MLE)からmleEBSMRを求め,SMRと2つのEBSMRの差との期待死亡数の関係を検討した。続いて,男性の胃がん死亡について,奈良県下47市町村別に1969~2002年の5年ごとの期間それぞれのSMR,meEBSMR,mleEBSMRを求め,3つの統計量に関する分散,平均値の推移と,それぞれの統計量で示した疾病地図を比較検討した。
結果 SMRと2つのEBSMRの差についての検討では,meEBSMRとmleEBSMRの両者はともに,期待死亡数が増加するとSMRに近似し,期待死亡数が減少すると差が大きくなる関係を認めた。EBSMRを用いた奈良県男性胃がん死亡についての検討では,SMR,meEBSMR,mleEBSMRの3つの統計量では,その分散がSMR>meEBSMR>mleEBSMRの順に小さくなった。また,MLEの解が収束しないためにmleEBSMRが欠損値となる場合が,奈良県性別市町村別の主要な40死因のうち18死因(45%)でみられたほか,期待死亡数が小さい死因ではmleEBSMRが得られにくい傾向がみられた。
結論 市町村別疾患別の死亡状況の集積性の検討には,欠損値がなく,SMRの偶然変動が調整され,疾病地図で地域の相対危険の変化の傾向が評価しやすいmeEBSMRが好ましいと考える。
キーワード 経験的ベイズ推定量,EBSMR,標準化死亡比,SMR,モーメント推定量,最尤推定量