看護師国家試験必修問題まとめ(2)【看護の倫理・対象】
看護師国家試験の必修問題の詳細については、看護師国家試験必修問題まとめ(1)【国民衛生の動向対応】をご確認下さい。
当ページでは、保健師助産師看護師国家試験出題基準の必修問題の大項目として示される「看護における倫理」「人間のライフサイクル各期の特徴と生活」「看護の対象としての患者と家族」を中心に、第113回(2024年)から第102回(2013年)看護師国家試験までの必修問題の中からピックアップし、解説とともに掲載します。
必修問題まとめ(1)【国民衛生の動向対応】、必修問題まとめ(3)【人体の構造と機能・健康障害・薬物】、必修問題まとめ(4)【看護技術】と合わせて、12年分のほぼすべての必修問題を網羅していますので、学習や確認にご活用下さい。
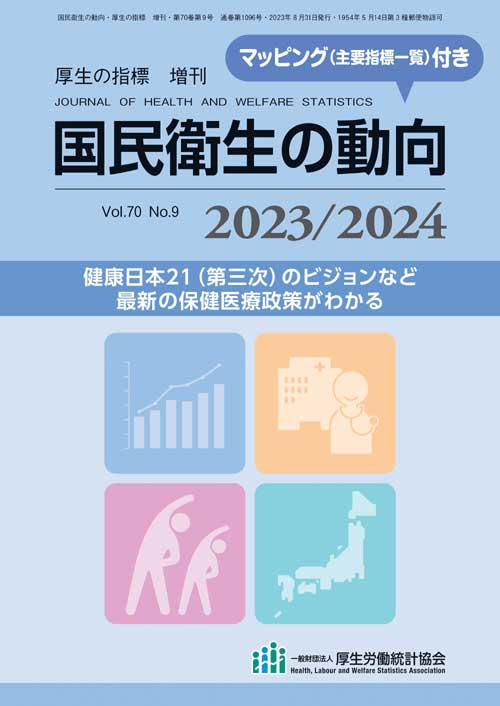 |
厚生の指標増刊
発売日:2023.8.29 定価:2,970円(税込) 432頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
必修問題目次
- 新生児・乳幼児期
- 学童期
- 思春期・青年期
- 成人期
- 更年期
- 老年期
看護における倫理
倫理原則
- 看護実践における倫理原則として、「自律尊重」「無危害」「善行」「公正と正義」「誠実と忠誠」の5原則がある。
- 善行の原則は、患者のために最善を尽くすことをいう(患者の症状、感情に合わせた最良の医療・看護提供など)。
倫理原則の「善行」はどれか。
- 患者に身体的損傷を与えない。
- 患者に利益をもたらす医療を提供する。
- すべての人々に平等に医療を提供する。
- 患者が自己決定し選択した内容を尊重する。
看護師の倫理綱領
国際看護師協会〈ICN〉による看護師の倫理綱領における看護師の基本的責任はどれか。
- 疾病の回復
- 医師の補助
- 苦痛の緩和
- 薬剤の投与
人間の特性
QOL(生活の質)
QOLを評価する項目で最も重要なのはどれか。
- 高度医療の受療
- 本人の満足感
- 乳児死亡率
- 生存期間
マズローの欲求階層説
マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最も低次の欲求はどれか。
- 自己実現の欲求
- 所属と愛の欲求
- 生理的欲求
- 安全の欲求
マズロー, A. H.の基本的欲求の階層で、食事・排泄・睡眠の欲求はどれか。
- 安全の欲求
- 自己実現の欲求
- 承認の欲求
- 生理的欲求
マズロー, A. H.の基本的欲求の階層で社会的欲求はどれか。
- 安全の欲求
- 帰属の欲求
- 自己実現の欲求
- 睡眠の欲求
マズロー, A. H.の基本的欲求の階層構造で承認の欲求はどれか。
- 尊重されたい。
- 休息をとりたい。
- 他人と関わりたい。
- 自分の能力を発揮したい。
マズロー, A. H.の基本的欲求階層論で最高次の欲求はどれか。
- 安全の欲求
- 承認の欲求
- 生理的欲求
- 自己実現の欲求
- 所属と愛の欲求
フィンクの危機モデル
フィンク, S. L.の危機モデルで第2段階はどれか。
- 衝撃
- 承認
- 適応
- 防御的退行
キューブラー・ロスの死にゆく人の心理変化
キューブラー・ロス, E.による死にゆく人の心理過程で第2段階はどれか。
- 死ぬことへの諦め
- 延命のための取り引き
- 死を認めようとしない否認
- 死ななければならないことへの怒り
キューブラー・ロス, E.による死にゆく人の心理過程で第5段階はどれか。
- 怒り
- 否認
- 死の受容
- 取り引き
セリエのストレス反応
セリエ, H.が提唱した理論はどれか。
- 危機モデル
- ケアリング
- セルフケア
- ストレス反応
人間のライフサイクル各期の特徴と生活:新生児・乳幼児期
運動発達
成長・発達における順序性で正しいのはどれか。
- 頭部から脚部へ
- 微細から粗大へ
- 複雑から単純へ
- 末梢から中心へ
原始反射
出生時からみられ、生後4か月ころに消失する反射はどれか。
- 手掌把握反射
- 足底把握反射
- パラシュート反射
- Babinski〈バビンスキー〉反射
出生時からみられ、生後3か月ころに消失する反射はどれか。
- 足踏み反射
- パラシュート反射
- Moro〈モロー〉反射
- Babinski〈バビンスキー〉反射
乳児の発達目安
生後4か月の乳児の発達を評価するのはどれか。
- 寝返り
- お座り
- 首のすわり
- つかまり立ち
幼児の発達目安
運動機能の発達で3歳以降に獲得するのはどれか。
- 階段を昇る。
- ひとりで立つ。
- ボールを蹴る。
- けんけん〈片足跳び〉をする。
乳児期の分離不安・人見知り
乳児期の特徴はどれか。
- 分離不安
- 第一次反抗期
- ギャングエイジ
- 自我同一性の確立
乳幼児で人見知りが始まる時期はどれか。
- 生後1〜2か月
- 生後6〜8か月
- 生後18〜24か月
- 生後36〜42か月
乳児期の発達課題
エリクソン, E. H.の乳児期の心理・社会的発達段階で正しいのはどれか。
- 親密
- 同一性
- 自主性
- 基本的信頼
乳児期の呼吸の型
- 新生児期や乳児期では、横隔膜を上下に動かす腹式呼吸が中心である。
- 7~8歳ころの学童期以降は胸式呼吸が優位となり、その間の幼児期後期ころは両者を組み合わせた胸腹式呼吸がみられる。
乳児期における呼吸の型はどれか。
- 肩呼吸
- 胸式呼吸
- 腹式呼吸
- 胸腹式呼吸
新生児の生理的体重減少
正期産の新生児が生理的体重減少によって最低体重になるのはどれか。
- 生後3〜5日
- 生後8〜10日
- 生後13〜15日
- 生後18〜20日
乳幼児の身体の発達
標準的な発育をしている乳児の体重が出生時の体重の約2倍になる時期はどれか。
- 生後3か月
- 生後6か月
- 生後9か月
- 生後12か月
乳歯
乳歯がすべて生えそろう年齢はどれか。
- 0〜1歳
- 2〜3歳
- 4〜5歳
- 6〜7歳
乳歯がすべて生えそろったときの本数はどれか。
- 16本
- 20本
- 24本
- 28本
大泉門の閉鎖
大泉門が閉鎖する時期に最も近いのはどれか。
- 6か月
- 1歳6か月
- 2歳6か月
- 3歳6か月
乳幼児の脳重量の発達
標準的な発育をしている児において脳重量が成人の約90%に達する年齢はどれか。
- 5〜6歳
- 8〜9歳
- 11〜12歳
- 15〜16歳
人間のライフサイクル各期の特徴と生活:学童期
学童期の特徴
- エリクソンが示す発達課題では、学童期(5歳から13歳ころ)には様々な課題の達成に挑戦して他者と比べた有能感を獲得する過程で、勤勉性対劣等感の葛藤が生じる。
- 親から離れて仲の良い仲間同士で集団行動をとるギャングエイジは、学童期の特徴である。
エリクソンが提唱する発達理論において、学童期に達成すべき心理社会的課題はどれか。
- 親密 対 孤立
- 自律性 対 恥・疑惑
- 勤勉性 対 劣等感
- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立 対 自我同一性〈アイデンティティ〉の拡散
学童期中学年から高学年にみられる、親から離れて仲の良い仲間同士で集団行動をとる特徴はどれか。
- 心理的離乳
- 自我の芽生え
- ギャングエイジ
- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立
人間のライフサイクル各期の特徴と生活:思春期・青年期
思春期の特徴
思春期にみられる感情の特徴はどれか。
- 情緒的に安定し穏やかになる。
- 思い通りにならないと泣き叫ぶ。
- 親に対して強い愛情表現を示す。
- 依存と独立のアンビバレント〈両価的〉な感情をもつ。
思春期に特徴的にみられるのはどれか。
- 愛着行動
- 分離不安
- 自己同一性の確立
- 基本的信頼関係の確立
思春期の子どもの親に対する行動の特徴で適切なのはどれか。
- 親からの干渉を嫌うようになる。
- 親と離れると不安な様子になる。
- 親に秘密を打ち明けるようになる。
- 親からの助言を素直に聞けるようになる。
思春期にある人が親密な関係を求める対象はどれか。
- 教師
- 祖父母
- 友人
- 両親
男子の第二次性徴(精通)
男子の第二次性徴による変化はどれか。
- 精通
- 骨盤の拡大
- 皮下脂肪の増加
- 第1大臼歯の萌出
第二次性徴の発現に関与するホルモン
第二次性徴の発現に関与するホルモンはどれか。
- 抗利尿ホルモン〈ADH〉
- 黄体形成ホルモン〈LH〉
- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉
- 甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉
思春期に分泌が増加するホルモンはどれか。
- グルカゴン
- オキシトシン
- カルシトニン
- アンドロゲン
第二次性徴に伴う意識の変化
第二次性徴が発現し始めた思春期に関心が向くのはどれか。
- 善悪の区別
- 仕事と家庭の両立
- 自己の身体の変化
- 経済力の確保と維持
青年期の発達課題
エリクソン, E. H.の発達理論で青年期に生じる葛藤はどれか。
- 生殖性 対 停滞
- 勤勉性 対 劣等感
- 自主性 対 罪悪感
- 同一性 対 同一性混乱
成人の基礎代謝量
次の時期のうち基礎代謝量が最も多いのはどれか。
- 青年期
- 壮年期
- 向老期
- 老年期
人間のライフサイクル各期の特徴と生活:成人期
成人期の発達課題
ハヴィガースト, R. J.が提唱する成人期の発達課題はどれか。
- 経済的に自立する。
- 身体的衰退を自覚する。
- 正、不正の区別がつく。
- 読み、書き、計算ができる。
壮年期以降の特徴
壮年期の男性で減少するのはどれか。
- エストロゲン
- プロラクチン
- アルドステロン
- テストステロン
人間のライフサイクル各期の特徴と生活:更年期
平均閉経年齢
日本の女性における平均閉経年齢に最も近いのはどれか。
- 30歳
- 40歳
- 50歳
- 60歳
更年期ころの女性
閉経前と比べ閉経後に低下するホルモンはどれか。
- 卵胞ホルモン
- 黄体形成ホルモン〈LH〉
- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉
- 副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉
更年期の女性で増加するのはどれか。
- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉
- テストステロン
- プロラクチン
- エストロゲン
人間のライフサイクル各期の特徴と生活:老年期
老年期の発達課題
ハヴィガースト, R. J.が提唱する老年期の発達課題はどれか。
- 子どもを育てる。
- 退職と収入の減少に適応する。
- 社会的責任をともなう行動を望んでなしとげる。
- 男性あるいは女性としての社会的役割を獲得する。
老年期の身体的変化
加齢により、以下のような多くの身体的変化がみられる。
- 大動脈の硬化による血管抵抗の増大(収縮期血圧の上昇、拡張期血圧の低下)
- 視野(特に周辺視野)の狭まり、近見視力の低下、色の識別能の低下(老視)
- 高音域が聞こえづらくなる(加齢性難聴)
- 嗅覚機能の低下(反応下限値(閾値)の上昇)
- 外来抗原に対する抗体の産生能の低下
- インスリン分泌量の低下による空腹時血糖の上昇
- 最大換気量の大幅な低下
- 総水分量が成人期(約60%)から減少(約50~55%)
- 自律性体温調節反応の低下により熱中症を引き起こしやすくなる
- 代謝・排出機能の低下等により薬物の副作用〈有害事象〉が生じやすい
老年期にみられる身体的な変化はどれか。
- 血管抵抗の増大
- 消化管の運動の亢進
- 水晶体の弾性の増大
- メラトニン分泌量の増加
老年期の身体的な特徴はどれか。
- 総水分量が増加する。
- 胸腺の重量が増加する。
- 嗅覚の閾値が低下する。
- 高音域における聴力が低下する。
加齢に伴い老年期に上昇するのはどれか。
- 腎血流量
- 最大換気量
- 空腹時血糖
- 神経伝導速度
老年期の身体的な特徴で正しいのはどれか。
- 尿量の増加
- 味覚の感度の向上
- 体温調節能の低下
- 外来抗原に対する抗体産生の亢進
老化に伴う視覚の変化で正しいのはどれか。
- 視野が狭くなる。
- 近くが見やすくなる。
- 色の識別がしやすくなる。
- 明暗順応の時間が短縮する。
加齢に伴う知能の変化
- 加齢とともに、新しい環境に適応するために、新しい情報を獲得し、処理・操作していく知能である流動性知能(記銘力等)は低下を続ける。
- 一方、長年の経験や教育、学習から獲得する知能である結晶性知能(洞察力、判断力、統合力等)は、20歳以降も上昇し、高齢になっても維持・安定している。
加齢によって衰えやすい機能はどれか。
- 記銘力
- 洞察力
- 判断力
- 統合力
成人(高齢者)の水分量
健常な成人の体重における水分の割合に最も近いのはどれか。
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
高齢者の体重に占める水分量の割合に最も近いのはどれか。
- 45%
- 55%
- 65%
- 75%
成人の体重に占める体液の割合で最も高いのはどれか。
- 血漿
- 間質液
- 細胞内液
- リンパ液
看護の対象としての患者と家族
家族成員
家族成員の最少人数はどれか。
- 4人
- 3人
- 2人
- 1人
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回










