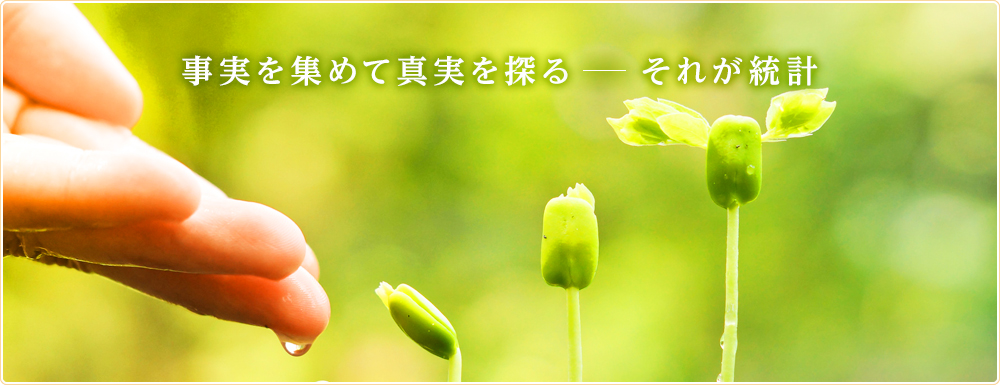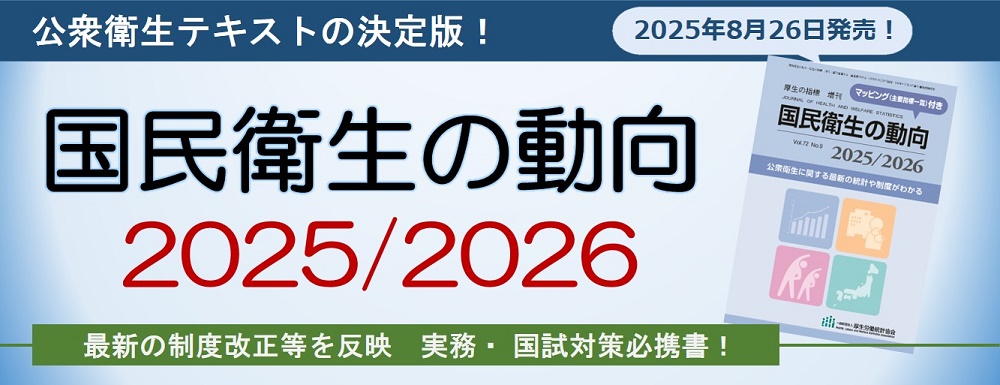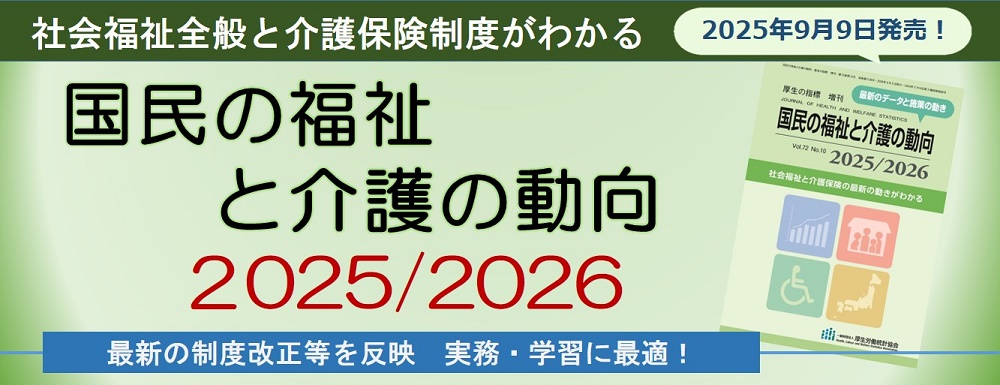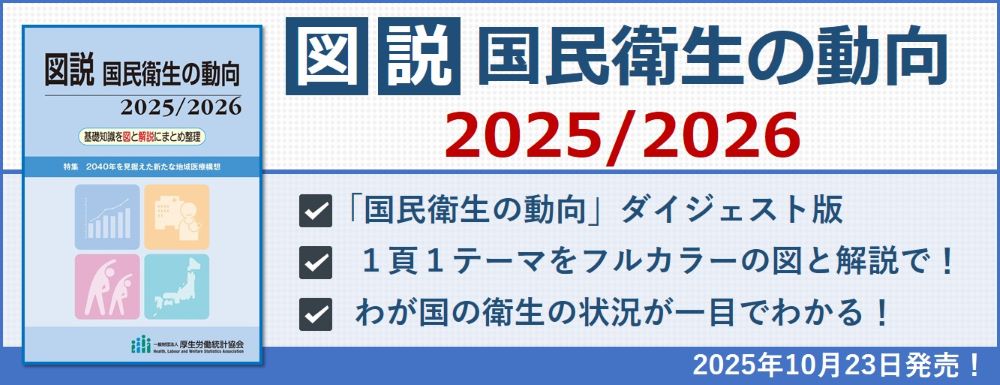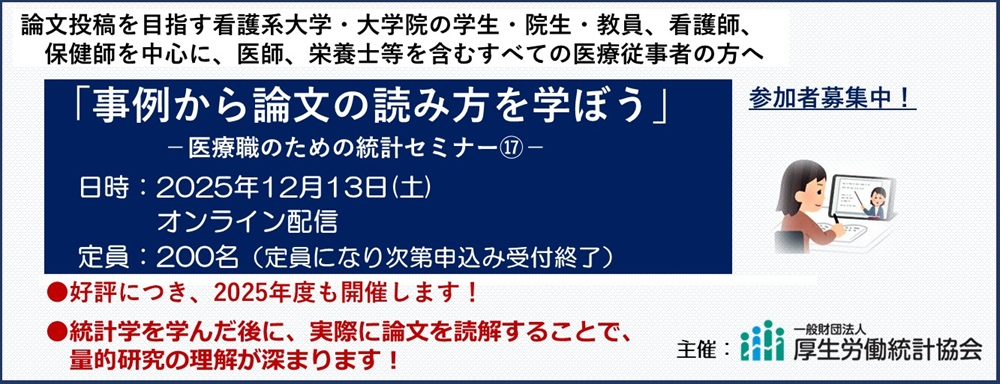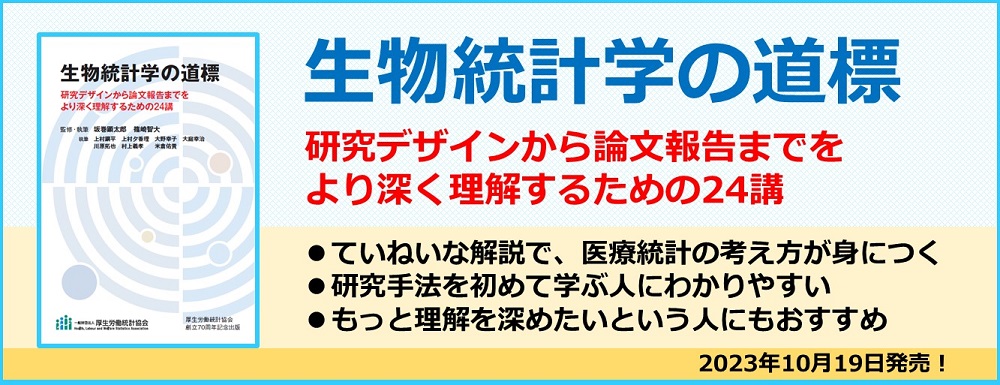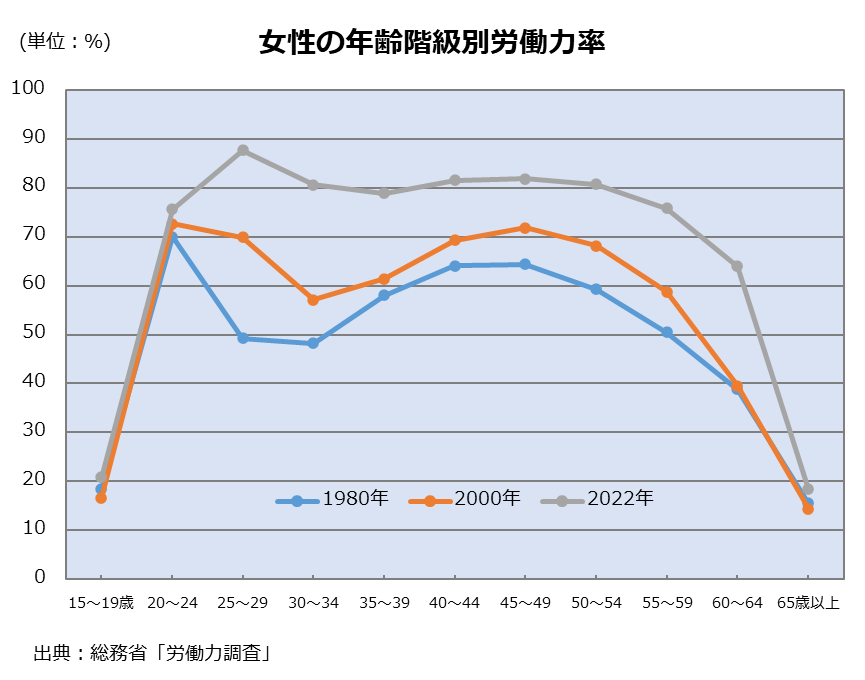令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第112回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
▶午前26
骨格筋の細胞膜には( )に対する受容体がある。自己抗体がこの受容体の働きを阻害すると骨格筋は収縮できなくなる。
( )に入る神経伝達物質として正しいのはどれか。
- アセチルコリン
- アドレナリン
- ドパミン
- ノルアドレナリン
▶午前27
健常な女子(15歳)が野外のコンサートで興奮し、頻呼吸を起こして倒れた。
このときの女子の体内の状態で正しいのはどれか。
- アルカローシスである。
- ヘマトクリットは基準値よりも高い。
- 動脈血酸素飽和度〈SaO2〉は100%を超えている。
- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉は基準値よりも高い。
▶午前28
薬物の分解、排泄の速さの指標となるのはどれか。
- 最高血中濃度
- 生物学的半減期
- 濃度曲線下面積
- 最高血中濃度到達時間
▶午前29
多発性骨髄腫で腫瘍化しているのはどれか。
- B細胞
- T細胞
- 形質細胞
- 造血幹細胞
▶午前30
くも膜下出血の成因で最も多いのはどれか。
- 外傷
- 脳腫瘍
- 脳動脈瘤
- 脳動静脈奇形
▶午前31
社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。
- 医療保険――健康保険法
- 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉
- 雇用保険――社会福祉法
- 年金保険――生活困窮者自立支援法
▶午前32
老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。
- 介護医療院
- 介護老人保健施設
- 老人福祉センター
- 老人デイサービスセンター
▶午前33改題
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について正しいのはどれか。
- 令和4年(2022年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。
- 日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。
- 早期に発見して治療を開始すれば完治する。
- 保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。
▶午前34
医療計画について正しいのはどれか。
- 基準病床数を定める。
- 5年ごとに見直しを行う。
- 特定機能病院の基準を定める。
- 一次、二次および三次医療圏を設定する。
▶午前35
ノロウイルス感染症に罹患した患者の嘔吐物が床に飛び散っている。
この処理に使用する消毒薬で適切なのはどれか。
- 70%エタノール
- ポビドンヨード
- 塩化ベンザルコニウム
- 次亜塩素酸ナトリウム
▶午前36
臨死期の身体的変化はどれか。
- 尿量が増加する。
- 全身の筋肉が硬直する。
- 不規則な呼吸が出現する。
- 頸動脈が触れなくなった後、橈骨動脈が触れなくなる。
▶午前37
成人女性に対するベッド上での排泄援助とその目的の組合せで適切なのはどれか。
- 窓を開ける。――寒冷刺激による排尿促進
- 上半身を挙上する。――腹圧のかけやすさによる排泄促進
- 外陰部にトイレットペーパーを当てる。――尿臭の防止
- 便器の底にトイレットペーパーを敷く。――寝具の汚染防止
▶午前38
成人のノンレム睡眠の特徴はどれか。
- 体温が上昇する。
- 急速な眼球運動がある。
- 加齢に伴い時間が長くなる。
- 睡眠周期の前半にみられる。
▶午前39
穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。
- 胸腔穿刺――胸骨柄
- 骨髄穿刺――第3・4腰椎間
- 腹腔穿刺――腹直筋外側の側腹部
- 腰椎穿刺――上前腸骨棘
▶午前40
毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
- 薬剤師法
- 毒物及び劇物取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉
▶午前41
輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。
- 血小板成分製剤――2~6℃
- 赤血球成分製剤――2~6℃
- 血漿成分製剤――20〜24℃
- 全血製剤――20〜24℃
▶午前42
真空採血管とホルダーを用いて静脈血採血を実施するときに、駆血を解除するタイミングで適切なのはどれか。
- 採血針を皮膚に刺した直後
- 真空採血管内への血液の流入が始まったとき
- 真空採血管内への血液の流入が終わったとき
- ホルダーから真空採血管を抜去した後
▶午前43
MRI検査室に持ち込んでよいのはどれか。
- 耳栓
- 携帯電話
- 使い捨てカイロ
- キャッシュカード
▶午前44
ムーア, F. D.が提唱した外科的侵襲を受けた患者の生体反応で正しいのはどれか。
- 傷害期では尿量が増加する。
- 転換期では循環血液量が増加する。
- 筋力回復期では蛋白の分解が進む。
- 脂肪蓄積期では活動性が低下する。
▶午前45
関節拘縮の予防を目的とした関節可動域〈ROM〉訓練で正しいのはどれか。
- 関節を速く動かす。
- 運動麻痺がある場合は患側から行う。
- 他動運動は痛みが生じないように行う。
- 徒手筋力テストの結果が1以下の場合は自動運動を促す。
▶午前46
放射線治療で人体の吸収線量を表す単位はどれか。
- Bq
- eV
- Gy
- Sv
▶午前47
Aさん(62歳、男性)は呼吸困難と咳嗽が増強したため外来を受診した。胸部エックス線写真と胸部CTによって特発性肺線維症による間質性肺炎と診断され、呼吸機能検査を受けた。
換気障害の分類を図に示す。
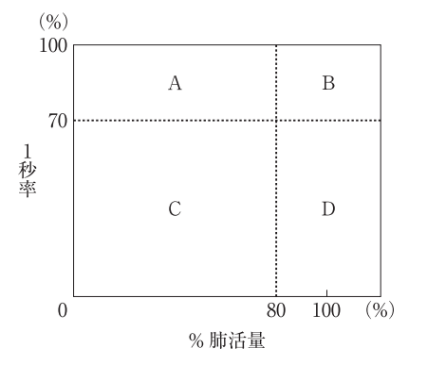
Aさんの換気障害の分類で当てはまるのはどれか。
- A
- B
- C
- D
▶午前48
右肺尖部の肺癌の胸壁への浸潤による症状はどれか。
- 散瞳
- 構音障害
- 閉眼困難
- 上肢の疼痛
▶午前49
胃切除術後のダンピング症候群を予防するための食事指導で適切なのはどれか。
- 15分以内に食べる。
- 糖質の多い食事を摂る。
- 1回の摂取量を少なくする。
- 1日の食事回数を少なくする。
▶午前50
重度の肝硬変で基準値よりも低い値を示す血液検査項目はどれか。
- 血清アルブミン〈Alb〉
- 血清ビリルビン〈Bil〉
- 血中アンモニア〈NH3〉
- プロトロンビン時間〈PT〉
▶午前51
成人のばね指で正しいのはどれか。
- 男性に多い。
- 原因は腱の炎症である。
- 好発部位は示指である。
- 積極的にストレッチを行う。
▶午前52
広汎子宮全摘出術を受けた患者への退院後の生活に関する説明で正しいのはどれか。
- 「術後2週から性交は可能です」
- 「定期的に排尿を試みてください」
- 「調理のときは手袋をしてください」
- 「退院当日から浴槽の湯に浸かることができます」
▶午前53
老化に伴う血液・造血器系の変化で適切なのはどれか。
- エリスロポエチンが増加する。
- 黄色骨髄が減少する。
- 顆粒球数が増加する。
- 赤血球数が減少する。
▶午前54
高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。
- 身体拘束の実施は担当看護師が決定する。
- ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。
- 本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。
- 切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。
▶午前55
65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。
- 介護予防教室
- 介護老人保健施設
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護〈デイサービス〉
▶午前56
入院中の高齢者への看護師の対応で適切なのはどれか。
- 入院当日から複数の看護師が関わる。
- 1回の訪室で多くの情報を聴取する。
- 1日のスケジュールは口頭で説明する。
- 退院後の生活を予測して情報収集する。
▶午前57
1歳6か月の身体発育曲線(体重)を示す。
異常が疑われるのはどれか。
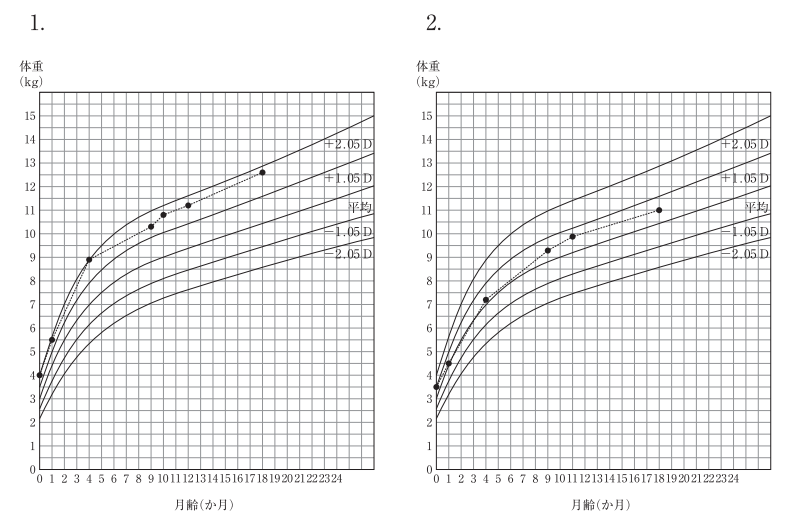
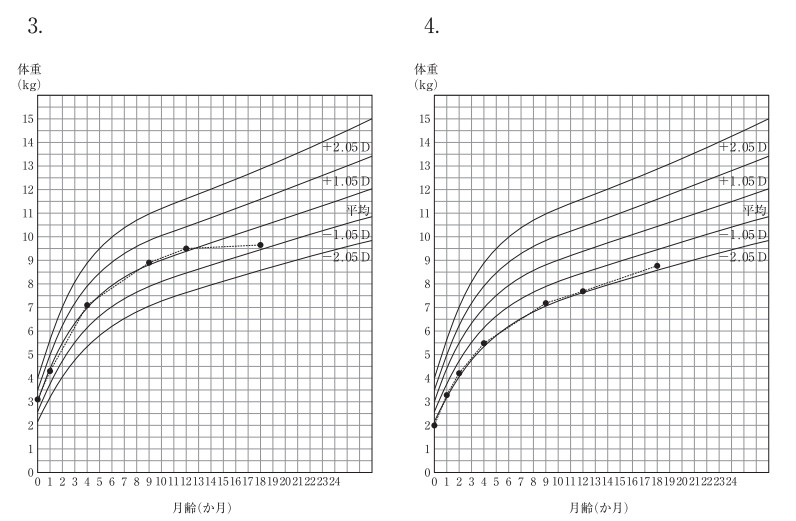
▶午前58
幼児期の心理社会的特徴はどれか。
- 自己中心性
- 心理的離乳
- ギャングエイジ
- ボディイメージの変容
▶午前59
正常な幼児期の基本的生活習慣で、2歳0か月ころまでに習得するのはどれか。
- 鼻をかむ。
- スプーンを使う。
- 夜間のおむつがとれる。
- 洋服のボタンをとめる。
▶午前60
母子保健法に規定されているのはどれか。
- 母子健康包括支援センター
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 助産施設
- 特定妊婦
▶午前61
排卵のある正常な月経周期で正しいのはどれか。
- 黄体は形成後1週間で萎縮する。
- エストロゲンの作用で子宮内膜が分泌期になる。
- 発育した卵胞の顆粒膜細胞からプロゲステロンが分泌される。
- エストロゲンのポジティブフィードバックによって黄体形成ホルモンの分泌が増加する。
▶午前62
不妊症について正しいのはどれか。
- 約6割は原因不明である。
- 検査に基礎体温測定がある。
- 治療の1つに不妊手術がある。
- 女性の年齢は治療効果に影響しない。
▶午前63
正常な分娩経過はどれか。
- 骨盤入口部に児頭が進入する際、児の頤部が胸壁に近づく。
- 骨盤出口部に達した時点で、児頭の矢状縫合は母体の骨盤の横径に一致する。
- 児頭娩出後、胎児は肩の長軸が骨盤出口部の横径に一致するよう回旋する。
- 児頭が発露したころに胎盤が剝離する。
▶午前64
新生児の呼吸窮迫症候群〈RDS〉で正しいのはどれか。
- 呼吸数が減少する。
- 過期産児に発症しやすい。
- 生後24時間ころから発症する。
- 肺サーファクタントの欠乏が原因で生じる。
▶午前65
小児期から青年期に発症し、運動性チック、音声チック及び汚言の乱用を伴うのはどれか。
- Down〈ダウン〉症候群
- Tourette〈トゥレット〉障害
- 注意欠如・多動性障害〈ADHD〉
- Lennox-Gastaut〈レノックス・ガストー〉症候群
▶午前66
患者の権利や力を尊重し、自己制御している感覚を持たせ、患者が社会生活に必要な技能や能力を獲得する支援を意味するのはどれか。
- リカバリ
- ストレングス
- レジリエンス
- エンパワメント
▶午前67
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。
- 障害基礎年金
- 一定割合の雇用義務
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療〈精神通院医療〉
▶午前68
Aさん(85歳、男性)は1人暮らしで判断能力が不十分である。4親等以内の親族はいない。
訪問看護事業所におけるAさんの情報管理で適切なのはどれか。
- 成年後見人にAさんの訪問看護計画を説明する。
- 地域の民生委員にAさんの経済状況を知らせる。
- Aさんの訪問記録を電子メールに添付して援助者間で共有する。
- 新たなサービスの利用を検討する他の利用者にAさんのケアプランを見せる。
▶午前69
Aさん(80歳、女性)は1人暮らしで、在宅酸素療法〈HOT〉を受けている。訪問看護師はAさんに停電時を想定した避難行動の指導を行うことにした。
Aさんの停電時の避難行動で優先度が高いのはどれか。
- 電気のブレーカーを落とす。
- 玄関の扉を開けて出口を確保する。
- 訪問看護ステーションに連絡をする。
- 酸素濃縮器から酸素ボンベに切り替える。
▶午前70
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
- 福祉用具貸与
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉
▶午前71
Aさん(70歳、男性、要介護1)は脳梗塞の後遺症で左不全麻痺がある。家屋内は杖を使用して移動が可能である。Aさんから「入浴が不安なので安全な方法を教えてほしい」と訪問看護師に相談があった。
Aさんへの助言で適切なのはどれか。
- 手すりは左手で持つ。
- 左足から浴槽に入る。
- 浴室内を杖で移動する。
- 浴槽から出るときは入浴台〈バスボード〉を使う。
▶午前72
看護マネジメントのプロセスの「統制」はどれか。
- 看護職員の仕事への動機付けを行う。
- 病棟の目標をもとに看護活動の年間計画を立案する。
- 褥瘡ケアの改善に取り組むための担当チームを構成する。
- 病棟の1年間の業務評価に基づき看護活動の計画を修正する。
▶午前73
職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。
- 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。
- 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。
- 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。
- 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。
▶午前74
国際協力として5歳未満児死亡率の高い地域に1年間派遣されることになった看護師が、派遣される地域の住民に対して行う活動でプライマリヘルスケアの原則に基づいた活動はどれか。
- 高度な治療を目的とした活動
- 医学的研究の遂行を優先した活動
- 派遣先で入手できる資源を利用した活動
- 派遣される専門家チームを中心とする活動
▶午前75
音を感知するラセン器〈Corti〈コルチ〉器〉があるのはどれか。
- 蝸牛管
- 半規管
- 鼓室
- 鼓膜
- 前庭
▶午前76
正常な糸球体で濾過される物質はどれか。
- フィブリノゲン
- ミオグロビン
- アルブミン
- 血小板
- 赤血球
▶午前77
冷たい川に飛び込んだときに急激に体温が低下する原因で正しいのはどれか。
- 対流による体熱の放散
- 放射による体熱の放散
- 熱伝導による体熱の放散
- 代謝による熱エネルギー産生の低下
- 骨格筋における熱エネルギー産生の低下
▶午前78
インスリンを過剰に投与したときに現れる症候で正しいのはどれか。
- 発熱
- 浮腫
- 口渇感
- 顔面紅潮
- 手足のふるえ
▶午前79
僧帽弁狭窄症について正しいのはどれか。
- 弁口面積が拡大する。
- 左心房内圧が上昇する。
- 狭心痛を合併することが多い。
- 弁尖の先天的な3尖化が原因となる。
- 胸骨右縁第2肋間で心雑音を聴取する。
▶午前80
検査の画像を別に示す。
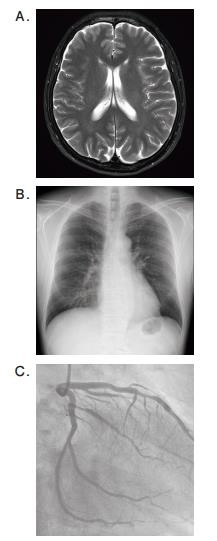
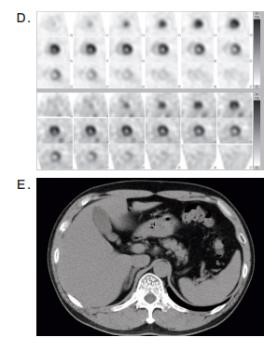
狭心症の手術に最も重要な検査はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
▶午前81
変形性膝関節症について正しいのはどれか。
- 男性に多い。
- 第一選択は手術療法である。
- 変形性関節症の中で2番目に多い。
- 二次性のものが一次性のものより多い。
- 経時的に進行して10年で半数が悪化する。
▶午前82
学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。
- インフルエンザ
- 細菌性赤痢
- ジフテリア
- 腸チフス
- 流行性角結膜炎
▶午前83
成人におけるバイタルサインで緊急に対応が必要なのはどれか。
- 脈拍 70/分
- 体温 34.4℃
- 呼吸数 14/分
- 血圧 130/80mmHg
- グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉15点
▶午前84
老化による尿の生成と排尿機能の変化はどれか。
- 排尿回数の減少
- 膀胱容量の増加
- 夜間尿量の減少
- 残尿量の増加
- 尿比重の上昇
▶午前85
定期予防接種について正しいのはどれか。
- BCG接種前にツベルクリン反応を実施する。
- ロタウイルスワクチンは不活化ワクチンである。
- ポリオウイルスワクチンの定期接種は廃止された。
- 麻疹ウイルスワクチンは就学までに4回接種する。
- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンは筋肉内注射する。
▶午前86
緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 眼球が突出する。
- 視神経が萎縮する。
- 硝子体が混濁する。
- 眼底に出血がみられる。
- 眼圧の上昇が原因となる。
▶午前87
高齢者に脱水が起こりやすくなる要因はどれか。2つ選べ。
- 骨量の減少
- 筋肉量の減少
- 細胞内液量の減少
- 渇中枢の感受性の亢進
- 抗利尿ホルモンの反応性の亢進
▶午前88
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 応急入院は72時間以内に限られている。
- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
▶午前89
クリニカルパスについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- 在宅療養には適用できない。
- 医療者と患者が治療計画を共有できる。
- バリアンス発生の判断は退院日に行う。
- 多職種間のコミュニケーションが不要になる。
- 一定の質を保った治療と看護ケアの提供につながる。
▶午前90
看護のアウトカムを評価するために収集する情報はどれか。2つ選べ。
- 褥瘡発生率
- 患者の満足度
- 研修会の開催回数
- 新人看護師の離職率
- 退院指導の実施回数
資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第112回看護師国家試験
令和4年2月13日(日)に実施された第111回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第111回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後7(必修除外)
ハヴィガースト,R.J.の発達課題で善悪の区別を学習するのはどれか。
- 乳幼児期
- 児童期
- 青年期
- 中年期
▶午後26
生体内でタンパク質が分解され、アミノ酸の代謝が進んで生じたアンモニアは肝臓で( )に変換される。
( )に入るのはどれか。
- 尿酸
- 尿素
- 亜硝酸
- 一酸化窒素
若年者よりも高齢者が熱中症を起こしやすい理由はどれか。
- 熱産生量の増加
- 熱放散量の増加
- 自律性体温調節反応の低下
- 視床下部の体温調節中枢のセットポイントの低下
▶午後28
ABO式血液型におけるオモテ検査とウラ検査の結果の表を示す。
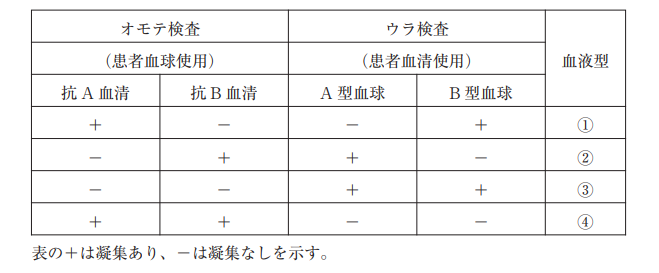
血液型判定の結果がO型となるのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
▶午後29
上位運動ニューロン徴候および下位運動ニューロン徴候の有無について表に示す。
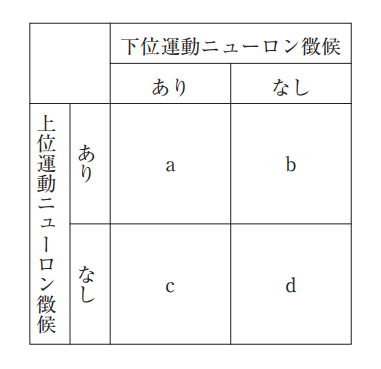
筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉において正しいのはどれか。
- a
- b
- c
- d
診療報酬制度について正しいのはどれか。
- 診療報酬の点数は3年に1回改定される。
- 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。
- 医療機関への支払いは出来高払いのみである。
- 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。
次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。
- 未成年者喫煙禁止法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- アルコール健康障害対策基本法
- ギャンブル等依存症対策基本法
21世紀における第三次国民健康づくり運動〈健康日本21(第三次)〉では、( )つの基本的方向に沿った目標が設定された。
( )に入る数値はどれか。
- 3
- 4
- 5
- 6
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
▶午後34
クリティカル・シンキングで適切なのはどれか。
- 物事を否定的にみる。
- 根拠に基づいて考える。
- 主観的な情報を重視する。
- 直感的に状況を判断する。
▶午後35
構音障害がある成人患者への対応で適切なのはどれか。
- 手話で説明する。
- 筆談を提案する。
- 耳元で話しかける。
- 不明瞭な言語は繰り返し聞き直す。
▶午後36
看護過程において評価する項目はどれか。
- 看護技術の習得度
- 看護教育の活用度
- 看護記録の完成度
- 看護目標の達成度
医療器材と消毒・滅菌の組合せで正しいのはどれか。
- 手術用持針器――第4級アンモニウム塩
- ステンレス製便器――熱水消毒
- 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌
- ベッド柵――グルタラール
▶午後38
点眼薬の投与について正しいのはどれか。
- 点眼時は上眼瞼を上げる。
- 点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。
- 点眼後は眼球を圧迫する。
- 眼から溢れた薬液は拭き取る。
▶午後39
52歳の女性が上腹部痛と吐血を主訴に受診し輸血を行うこととなった。
輸血時の対応で正しいのはどれか。
- 赤血球製剤を30〜37℃で融解する。
- 血液型検査とクロスマッチ検査用の採血を同時に行う。
- クロスマッチ検査の結果を医師と看護師で確認する。
- 輸血開始から15分後にアレルギー反応の初回観察を行う。
▶午後40
四肢の動脈性外出血に対する止血法で適切なのはどれか。
- 出血部位を心臓より高く保つ。
- 止血帯は幅1cm未満を用いる。
- 止血帯は連続して4時間使用する。
- 出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。
▶午後41
成人の後腸骨稜からの骨髄穿刺で正しいのはどれか。
- 仰臥位で行う。
- 穿刺時は深呼吸を促す。
- 骨髄液吸引時に痛みが生じる。
- 終了後、当日の入浴は可能である。
Aさん(55歳、男性、会社員)は胃癌の終末期である。
Aさんの訴えのうちスピリチュアルペインの表出はどれか。
- 「腹痛がずっと続いています」
- 「吐き気が続くと思うと不安です」
- 「今後の生活にかかるお金が心配です」
- 「これまでの自分の人生が意味のないものに思えます」
▶午後43
Aさん(63歳、男性)は3年前から肺気腫で定期受診を続けていた。最近、歩行時の息切れが強くなってきたことを自覚し、心配になったため受診した。受診時、呼吸数は34/分で、口唇のチアノーゼがみられた。
Aさんについて正しいのはどれか。
- 1回換気量が増加している。
- 呼気よりも吸気を促すと効果的である。
- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は上昇している。
- 病状が進行すると動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が上昇する。
▶午後44
中心静脈栄養法を受けている患者の看護について適切なのはどれか。
- カテーテルの刺入部は見えないように覆う。
- カテーテル刺入部を定期的に消毒する。
- カテーテルの固定位置を毎日確認する。
- 予防的に抗菌薬の投与を行う。
▶午後45
高尿酸血症で正しいのはどれか。
- 痛風結節は疼痛を伴う。
- 痛風発作は飲酒で誘発される。
- 痛風による関節炎の急性期に尿酸降下薬を投与する。
- 血清尿酸値9.0mg/dL以下を目標にコントロールする。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。
- 空気感染する。
- 無症候期がある。
- DNAウイルスによる。
- 血液中のBリンパ球に感染する。
▶午後47
鼓室形成術を受けた患者の退院指導の内容で正しいのはどれか。
- 水泳は可能である。
- 耳垢はこまめに除去する。
- 鼻を強くかむことを禁じる。
- エレベーターの使用を勧める。
▶午後48
下腿の介達牽引を受けている患者が足背のしびれを訴えている。
看護師が確認すべき項目で優先度が高いのはどれか。
- 下肢の肢位
- 牽引の方向
- 重錘の重さ
- 弾性包帯のずれ
▶午後49
前立腺癌について正しいのはどれか。
- 肺転移の頻度は低い。
- 血清PSA値が高値となる。
- 患者の多くは60歳未満である。
- テストステロン補充療法が行われる。
▶午後50
乳癌の患者に対する抗エストロゲン薬の副作用はどれか。
- 低血糖
- ほてり
- 肺線維症
- 末梢神経障害
▶午後51
高齢者が術後に呼吸器合併症を発症しやすい理由はどれか。
- 1秒率の減少
- 残気量の減少
- 嚥下反射の亢進
- 気道の線毛運動の亢進
▶午後52
加齢に伴う高齢者の循環器系の変化で正しいのはどれか。
- 運動時の心拍出量が増大する。
- 拡張期血圧が上昇する。
- 心室壁が厚くなる。
- 脈圧が狭小化する。
▶午後53
結晶性知能はどれか。
- よく利用するスーパーマーケットから自宅までの近道を考える。
- パソコン教室で操作方法を覚える。
- 携帯電話に電話番号を登録する。
- 外国語の単語を暗記する。
令和4年度(2022年度)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果において、養護者による高齢者虐待に関する説明で正しいのはどれか。
- 夫による虐待が最も多い。
- 被虐待者の9割が女性である。
- 心理的虐待が全体の6割を占めている。
- 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。
退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。
- シルバー人材センター
- 老人福祉センター
- 老人クラブ
- 自治会
▶午後56
高齢者に経口薬の薬効が強く現れる理由はどれか。
- 骨密度の低下
- 胃酸分泌の減少
- 消化管運動の低下
- 血清アルブミンの減少
▶午後57
新生児や乳児が胎児期に母体から受け取った抗体は次のどれか。
- IgA
- IgD
- IgG
- IgM
▶午後58
第二次性徴で正しいのはどれか。
- 女児は乳房の発育から始まる。
- 発現は男児が女児よりも早い。
- 初経の開始後に、第二次発育急進が起こる。
- 精通は11歳の男児のほとんどに認められる。
学童期の肥満で正しいのはどれか。
- Kaup〈カウプ〉指数で評価する。
- 症候性の肥満がほとんどを占める。
- 食事では蛋白質の摂取制限を行う。
- 成人期の生活習慣病のリスク因子である。
▶午後60
生後11か月の男児。ある日の朝、自宅でボタン型電池を飲み込んだ疑いがあり、その日の午前中に外来を受診した。胸部エックス線撮影によって、ボタン型電池が食道下部にあることが確認された。
行われる処置で適切なのはどれか。
- 背部の叩打
- 緩下薬の使用
- 催吐薬の使用
- 緊急摘出術の実施
▶午後61
正常な成長・発達をしている子どもの情緒の分化で、生後6か月ころからみられるのはどれか。
- 恐れ
- 嫉妬
- 喜び
- 恥ずかしさ
▶午後62
性周期とホルモンについて正しいのはどれか。
- 増殖期は基礎体温が上昇する。
- プロラクチンによって排卵が起こる。
- プロゲステロンは子宮内膜の増殖を促進する。
- 排卵直前に黄体形成ホルモン〈LH〉値が高くなる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。
- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。
- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。
- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。
- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。
▶午後64
Aさん(32歳、初産婦)は前置胎盤のため妊娠37週0日の午前10時から帝王切開術を受ける予定である。
手術前日の看護師の対応で適切なのはどれか。
- 浣腸を行う。
- 夕食が禁食となっているか確認する。
- 輸血の準備ができているか確認する。
- 下肢に間欠的空気圧迫装置を装着する。
▶午後65
新生児の呼吸の生理的特徴で適切なのはどれか。
- 成人に比べて肺のガス交換面積が大きい。
- 周期性呼吸がみられる。
- 胸式呼吸が主である。
- 口呼吸が主である。
長期に大量飲酒をした後で、急に断酒した際にみられるのはどれか。
- 病的酩酊
- 振戦せん妄
- アルコール性認知症
- Korsakoff〈コルサコフ〉症候群
▶午後67
母親がAさん(27歳、統合失調症)に対して「親に甘えてはいけない」と言いながら、過度にAさんの世話をすることで、Aさんが混乱していた。
この親子関係を示すのはどれか。
- 共依存
- 同一視
- ネグレクト
- 二重拘束〈ダブルバインド〉
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。
- 家族との面会
- 患者からの信書の発信
- 患者からの退院の請求
- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
▶午後69
感染徴候のない在宅療養者に対する床上での排便の援助において、訪問看護師が行う感染対策で適切なのはどれか。
- 援助時には使い捨てのエプロンを着用する。
- 使用済みのオムツは感染性廃棄物として処分する。
- 使用済みの寝衣は次亜塩素酸ナトリウム液に浸す。
- 陰部洗浄で使用したボトルの洗浄に中性洗剤は用いない。
▶午後70
Aさん(85歳、女性)は1人暮らし。うっ血性心不全で臥床して過ごすことが多い。訪問看護師が訪問すると、Aさんは体温37.6℃、口唇の乾燥はなく、体熱感はあるが手足が冷えると言って羽毛布団を肩まで掛けている。室温30℃、湿度65%、外気温は32℃、冷房設備はあるが使っていない。
このときの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。
- 羽毛布団を取り除く。
- 冷房設備で室温を調整する。
- 頓用の解熱薬を服用してもらう。
- 直ちに経口補水液を飲むよう促す。
▶午後71
Aさん(68歳、男性)は妻(68歳)と2人暮らし。膀胱癌で尿路ストーマを造設している。Aさんはストーマ装具の交換に慣れてきたため、妻と日帰りで近くの温泉地を旅行する計画を立てており、外来看護師に助言を求めた。
外来看護師がAさんに助言する内容で適切なのはどれか。
- 装具の交換に必要な物品一式を2回分持参する。
- 旅行中の水分摂取は1日1,000mL以内に控える。
- 他の入浴客がいなければ装具を外して入浴できる。
- オストメイト対応のトイレがなければ旅行先を変更する。
▶午後72
Aさん(76歳、女性)は1人暮らし。脳血管疾患で右半身麻痺があり、障害高齢者の日常生活自立度判定基準はB-2である。週に2回の訪問看護を利用している。食事の準備と介助および食後の口腔ケアのため訪問介護を利用することになった。訪問介護の担当者は、Aさんのケアについて訪問看護師に助言を求めた。
訪問看護師が訪問介護の担当者に助言する内容で正しいのはどれか。
- 健側に頸部を回旋させ食事の介助をする。
- 野菜は繊維に対し垂直に切って調理する。
- 歯肉出血がみられたら口腔ケアは中止する。
- 食事中はAさんの好きなテレビ番組を見せる。
機能別看護方式の説明で正しいのはどれか。
- 勤務帯ごとに各看護師が担当する患者を決めて受け持つ。
- 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。
- 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つ。
- 患者を複数のグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ。
看護におけるクリニカルラダーについて正しいのはどれか。
- 病院に導入が義務付けられている。
- ワーク・ライフ・バランスを目指すものである。
- 臨床実践に必要な能力が段階的に表現されている。
- 全国の病院で共通のクリニカルラダーが使用されている。
災害拠点病院の説明で正しいのはどれか。
- 国が指定する。
- 災害発生時に指定される。
- 広域搬送の体制を備えている。
- 地域災害拠点病院は各都道府県に1か所設置される。
令和4年(2022年)時点での世界の三大感染症に入るのはどれか。
- ポリオ〈急性灰白髄炎〉
- マラリア
- 天然痘
- 麻疹
▶午後77
肩峰があるのはどれか。
- 鎖骨
- 胸骨柄
- 肩甲棘
- 上腕骨
- 烏口突起
▶午後78
股関節を屈曲させるのはどれか。
- 大腿二頭筋
- 大殿筋
- 中殿筋
- 小殿筋
- 腸腰筋
▶午後79
採血時に操作を誤ったため溶血し、採血管内の血漿が暗赤色になってしまった。
この血漿の電解質濃度を測定したときに、本来の値よりも高くなるのはどれか。
- 塩化物イオン
- 重炭酸イオン
- カリウムイオン
- カルシウムイオン
- ナトリウムイオン
▶午後80
糸球体濾過量の推定に用いられる生体内物質はどれか。
- 尿素
- イヌリン
- ビリルビン
- クレアチニン
- パラアミノ馬尿酸
▶午後81
疾病の内因となるのはどれか。
- 免疫複合体
- 栄養素
- 温度
- 細菌
- 薬物
▶午後82
舌癌について正しいのはどれか。
- 癌全体に対する発症頻度は約10%である。
- 発症年齢は20歳代が多い。
- 好発部位は舌尖である。
- 浸潤は起こさない。
- 扁平上皮癌が多い。
▶午後83
Alzheimer〈アルツハイマー〉病で正しいのはどれか。
- 基礎疾患として高血圧症が多い。
- アミロイドβタンパクが蓄積する。
- 初期には記銘力障害はみられない。
- MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。
- 脳血流シンチグラフィ所見では頭頂葉の血流増加がある。
▶午後84
食物の嚥下において喉頭蓋が喉頭口を閉鎖する時期はどれか。
- 先行期
- 準備期
- 口腔期
- 咽頭期
- 食道期
放射性同位元素を用いるのはどれか。
- 脳血管造影
- 膀胱鏡検査
- 頭部CT検査
- 腹部超音波検査
- 骨シンチグラフィ
地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
- 介護保険法
- 健康増進法
- 社会福祉法
- 地域保健法
- 老人福祉法
▶午後87
動脈硬化症の粥腫形成に関与するのはどれか。2つ選べ。
- Langerhans〈ランゲルハンス〉細胞
- メサンギウム細胞
- 血管内皮細胞
- 肥満細胞
- 泡沫細胞
予防接種に生ワクチンが使用される疾患はどれか。2つ選べ。
- ジフテリア
- 日本脳炎
- 破傷風
- 結核
- 麻疹
▶午後89
修正型電気けいれん療法について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 磁気を用いる。
- 局所麻酔下で行う。
- 筋弛緩薬を用いる。
- 発生頻度の高い有害事象は骨折である。
- 薬物治療抵抗性のうつ病は適応になる。
出生体重3,100gの新生児。日齢3の体重は3,000gである。
このときの体重減少率を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答 [①].[②]%
資料 厚生労働省「第108回保健師国家試験、第105回助産師国家試験、第111回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第111回看護師国家試験
令和4年2月13日(日)に実施された第111回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第111回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
労働力調査による労働力人口の令和5年(2023年)平均に最も近いのはどれか。
- 4,900万人
- 5,900万人
- 6,900万人
- 7,900万人
▶午前26
正常な心臓で心拍出量が減少するのはどれか。
- 心拍数の増加
- 大動脈圧の上昇
- 静脈還流量の増加
- 心筋収縮力の上昇
▶午前27
ワクチン接種後の抗体産生について正しいのはどれか。
- ワクチン内の抗原を提示するのは好中球である。
- 抗原に対して最初に産生される抗体はIgAである。
- 抗原に対して血中濃度が最も高くなる抗体はIgMである。
- 同じワクチンを2回接種すると抗原に対する抗体の産生量が増加する。
▶午前28
B細胞が抗原認識によって分化した抗体産生細胞はどれか。
- マクロファージ
- 形質細胞
- 肥満細胞
- T細胞
▶午前29
皮膚筋炎の皮膚症状はどれか。
- 環状紅斑
- 蝶形紅斑
- ディスコイド疹
- ヘリオトロープ疹
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
- 介護休業は分割して取得することはできない。
- 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
- 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
- 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。
- がん対策
- 男女共同参画
- 就労の支援活動
- ボランティア活動
日本の令和4年(2022年)の健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。
- 女性の死因の第2位は老衰である。
- 男性の死因の第2位は肺炎である。
- 女性の平均寿命は89年を超えている。
- 男性の平均寿命は83年を超えている。
労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。
( )に入るのはどれか。
- 健康管理
- 総括管理
- 労務管理
- 出退勤管理
健康を人々の権利として明記したのはどれか。
- 世界保健機関〈WHO〉の健康に関する定義
- ジュネーブ宣言
- ヘルシンキ宣言
- リスボン宣言
地域連携クリニカルパスの目的はどれか。
- 医療機関から在宅までの医療の継続的な提供
- 地域包括支援センターと地域住民との連携
- 地域医療を担う医療専門職の資質向上
- 患者が活用できる社会資源の紹介
集団指導が望ましいのはどれか。
- 胃全摘出術後の患者への退院指導
- Ⅰ型糖尿病の学童を対象とした療養指導
- 子宮頸癌の術後の神経因性膀胱の患者への間欠的自己導尿の指導
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者への生活指導
▶午前37
上肢のフィジカルアセスメントの立位での実施場面の写真を別に示す。
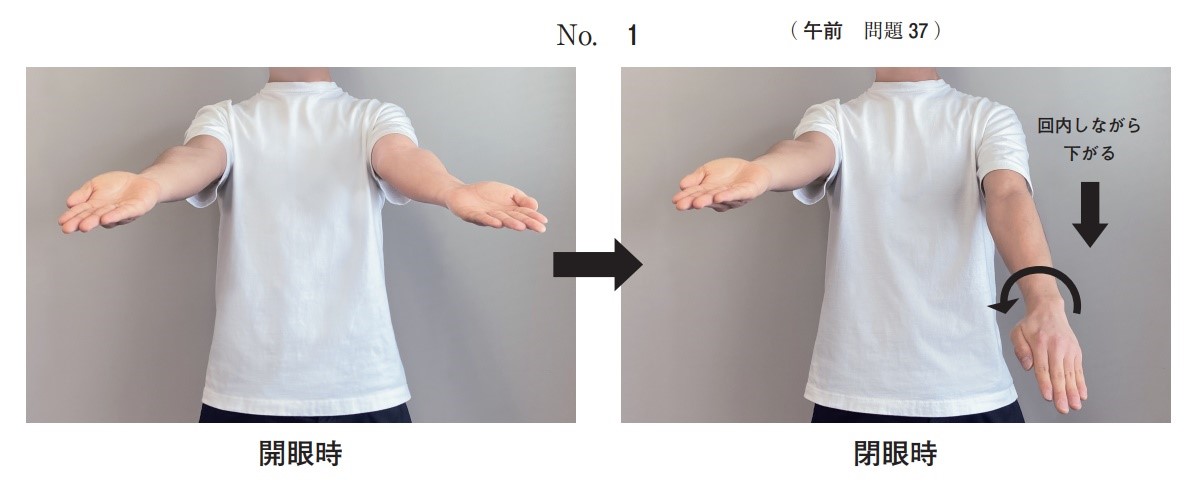
手のひらを上にして、肩の高さで水平に前方に両腕を伸ばしてもらった。その後、閉眼してもらうと、左腕が回内しながら下がっていった。
アセスメントの結果で正しいのはどれか。
- 位置覚の異常
- 錐体路の障害
- 小脳機能の異常
- 関節可動域の障害
▶午前38
臥床患者の体位変換とボディメカニクスの原則との組合せで正しいのはどれか。
- 仰臥位から側臥位――トルクの原理
- 仰臥位から長座位――摩擦力
- ベッドの片側への水平移動――力のモーメント
- ベッドの頭部への水平移動――てこの第1種の原理
▶午前39
Aさん(24歳、男性)は急性虫垂炎の術後1日で、ベッド上で仰臥位になり右前腕から点滴静脈内注射が行われている。Aさんは左利きである。
病室外のトイレまでAさんが移動するための適切な療養環境はどれか。
- 履物はAさんの左手側に置く。
- ベッド柵はAさんの右手側に設置する。
- 輸液スタンドはAさんの左手側に置く。
- ベッドは端座位時にAさんの足底が床につく高さにする。
▶午前40
全介助が必要な臥床患者の口腔ケアで適切なのはどれか。
- スポンジブラシは水を含ませた後、絞って使用する。
- 頸部を後屈した体位で実施する。
- 終了後は口腔内を乾燥させる。
- 舌苔は強くこすって除去する。
▶午前41
術後1日の手術創の正常な治癒過程として正しいのはどれか。
- 創部の浮腫が起こる。
- 肉芽組織が形成される。
- コラーゲンが成熟し瘢痕組織となる。
- 血管内皮細胞が新しい血管を形成する。
令和2年(2020年)の患者調査において医療機関を受診している総患者数が最も多いのはどれか。
- 喘息
- 糖尿病
- 脳血管疾患
- 高血圧性疾患
▶午前43
解離性大動脈瘤の破裂直後に出血性ショックとなった患者の症状として正しいのはどれか。
- 黄疸
- 浮腫
- 顔面紅潮
- 呼吸不全
▶午前44
Aさん(60歳、男性)は大動脈弁置換術を受け、ワルファリンの内服を開始することになった。
Aさんが摂取を避けるべき食品はどれか。
- 海藻
- 牛乳
- 納豆
- グレープフルーツ
▶午前45
慢性膵炎患者の食事療法で制限が必要なのはどれか。
- 蛋白質
- カリウム
- 食物繊維
- アルコール
▶午前46
血中濃度の測定にあたり食事の影響を考慮すべきホルモンはどれか。
- グルカゴン
- メラトニン
- コルチゾール
- バゾプレシン
▶午前47
脳血管造影を行う患者の看護について適切なのはどれか。
- 前日に頭部の剃毛を行う。
- 検査中は患者に話しかけない。
- 穿刺部末梢側の動脈の拍動を確認する。
- 検査30分前まで食事摂取が可能である。
▶午前48
Aさん(32歳、男性)は慢性副鼻腔炎と診断され経過観察をしていたが、症状が改善せず手術を受けることになった。
Aさんへの術後の生活についての説明で適切なのはどれか。
- 咽頭にたまった分泌物は飲み込んでも良い。
- 物が二重に見えるときは看護師に伝える。
- 手術当日から入浴が可能である。
- 臥床時は頭部を低く保つ。
▶午前49
幻肢痛について正しいのはどれか。
- 術前から発症する。
- 抗うつ薬は禁忌である。
- 細菌感染が原因である。
- 切断し喪失した部位に生じる。
▶午前50
乳房超音波検査を受ける女性患者への説明で正しいのはどれか。
- 「検査当日は起床時から飲食をしないでください」
- 「乳房を器具で挟んで検査します」
- 「月経中は検査ができません」
- 「仰向けで検査を行います」
▶午前51
Aさん(54歳、女性)は甲状腺機能亢進症と診断され、放射性ヨウ素内用療法を受けることとなった。
看護師の説明で正しいのはどれか。
- 「治療前1週間は海藻類を摂取しないでください」
- 「治療中は体を固定します」
- 「治療後の副作用に脱毛があります」
- 「治療後1週間は生野菜を摂取しないでください」
▶午前52
老年期の発達課題を引退の危機、身体的健康の危機および死の危機の3つの段階で示したのはどれか。
- エリクソン
- レビンソン
- ペック
- ユング
介護保険制度における施設サービスはどれか。
- 介護医療院サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
▶午前54
30歳を100%とした生理機能と比較して、老年期において機能の残存率の平均値が最も低下するのは次のうちどれか。
- 基礎代謝率
- 最大換気量
- 細胞内水分量
- 神経伝導速度
▶午前55
高齢者の健康障害の特徴で正しいのはどれか。
- 症状の出現は定型である。
- 治療の効果が現れやすい。
- 疾患の発生に心理的要因の影響は少ない。
- 薬物の副作用〈有害事象〉が発生しやすい。
▶午前56
Aさん(83歳)は寝たきり状態で、便意を訴えるが3日間排便がみられない。認知機能に問題はない。昨晩下剤を内服したところ、今朝、紙オムツに水様便が少量付着しており、残便感を訴えている。
このときのAさんの状態で考えられるのはどれか。
- 嵌入便
- 器質性便秘
- 切迫性便失禁
- 非急性感染性下痢
発育と発達に遅れのない生後6か月の男児。BCG接種の翌日に接種部位が赤く腫れ次第に増悪して膿がみられたため、母親は接種後4日目に医療機関に電話で相談し、看護師が対応した。児に発熱はなく、哺乳や機嫌は良好である。
このときの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「通常の反応です」
- 「速やかに来院してください」
- 「1週間後にまた電話をください」
- 「患部をアルコール消毒してください」
▶午前58
新生児の出血性疾患で正しいのはどれか。
- 生後48時間以内には発症しない。
- 母乳栄養児は発症のリスクが高い。
- 予防としてカルシウムを内服する。
- 早期に現われる所見に蕁麻疹がある。
▶午前59
入院中の小児のストレス因子と発達段階の組合せで正しいのはどれか。
- 見慣れない環境――新生児期
- プライバシーの侵害――幼児期
- 病気の予後への不安――学童期
- 母子分離――思春期
▶午前60
A君(小学6年生)は病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫の治療を続けていた。現在、肺転移があり終末期にある。呼吸障害のため鼻腔カニューレで酸素(2L/分)を吸入中である。A君の食事摂取量は減っているが意識は清明である。
1週後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式に出席したい」と話している。
看護師のA君への対応として適切なのはどれか。
- 両親に判断してもらおうと話す。
- 今の状態では出席は難しいと話す。
- 出席できるように準備しようと話す。
- 出席を決める前に体力をつけようと話す。
▶午前61
ジェンダーの定義について正しいのはどれか。
- 生物学的な性
- 社会的文化的な性
- 自己認識している性
- 性的指向の対象となる性
日本の周産期の死亡に関する記述で正しいのはどれか。
- 新生児死亡は生後1週未満の死亡をいう。
- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。
- 妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了後満28日未満の女性の死亡をいう。
- 令和5年(2023年)の人口動態統計では自然死産数が人工死産数よりも多い。
▶午前63
避妊法について適切なのはどれか。
- 経口避妊薬は排卵を抑制する。
- コンドーム法の避妊効果は99%以上である。
- 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。
- 子宮内避妊器具(IUD)は性交のたびに挿入が必要である。
マタニティブルーズについて正しいのはどれか。
- 意欲低下が主症状である。
- 症状は2週間以上持続する。
- 好発時期は産後1か月ころである。
- 産後のホルモンの変動が要因となる。
精神保健における一次予防はどれか。
- 職場でうつ病患者を早期発見する。
- 自殺企図者に精神科医療機関への受療を促す。
- 統合失調症患者の社会参加のための支援を行う。
- ストレスとその対処法に関する知識の啓発活動を行う。
▶午前66
認知行動療法で患者に期待できる効果はどれか。
- 物事の捉え方のゆがみが修正される。
- 自ら催眠状態に導くことができるようになる。
- 過去の自分の態度についての自己洞察が深まる。
- 自分の状態をあるがままに受け入れることができるようになる。
Aさん(22歳、統合失調症)は父親、母親、妹との4人暮らし。高校卒業後、アルバイトをしていたが、症状の悪化によって初めて精神科病院に入院した。退院後に一般企業で働きたいと希望している。
看護師がAさんに提案するサービスで適切なのはどれか。
- 行動援護
- 就労移行支援
- 自立生活援助
- 地域定着支援
Aさん(80歳、女性)は1人暮らし。要介護2の認定を受け、長男(50歳、会社員)、長男妻(45歳、会社員)、孫(大学生、男性)と同居することになった。長男の家の間取りは、洋室5部屋、リビング、台所である。Aさんは同居後に訪問看護を利用する予定である。訪問看護を利用するにあたりAさんの家族から「在宅介護は初めての経験なのでどうすればよいですか」と訪問看護師に相談があった。
訪問看護師の説明で最も適切なのはどれか。
- 「Aさんの介護用ベッドはリビングに置きましょう」
- 「Aさんの介護に家族の生活リズムを合わせましょう」
- 「活用できる在宅サービスをできる限り多く利用しましょう」
- 「特定の同居家族に介護負担が集中しないように家族で話し合いましょう」
▶午前69
Aさん(73歳、男性)は慢性閉塞性肺疾患で在宅酸素療法(HOT)を受けている。
受診時にAさんが「1人でお風呂に入っているが、息切れが強い」と訴えたため、外来看護師は入浴時の具体的な状況を確認した。
外来看護師がAさんに確認した内容で、息切れの原因と考えられるのはどれか。
- 入浴はシャワー浴にしている。
- 椅子に座って更衣を行っている。
- 洗髪時に鼻カニューレを外している。
- 浴室の扉を開けたまま入浴している。
▶午前70
気管切開下で人工呼吸器を装着している利用者に対して、訪問看護事業所が災害に備えて行うことで適切なのはどれか。
- 人工呼吸器の予備の回路を預かる。
- 災害時の個別支援マニュアルを作成する。
- 医療機関から非常用の人工呼吸器を借りる。
- 事業所内に利用者が避難できる場所を確保する。
▶午前71
チューブ型の胃瘻の管理について、介護する家族に看護師が指導する内容で正しいのはどれか。
- 「栄養剤の注入後に白湯を注入してください」
- 「胃瘻のチューブはご家族で交換してください」
- 「胃瘻のチューブは同じ位置に固定してください」
- 「下痢のときは栄養剤の注入速度を速めてください」
▶午前72
病棟で患者の口腔ケア改善に取り組むために担当チームを作った。
これは看護管理のプロセスのどれか。
- 計画
- 指揮
- 統制
- 組織化
多発性骨転移がある終末期の大腸癌患者(53歳、女性)が、外科病棟から緩和ケア病棟に夫に付き添われ転棟してきた。
転棟時の申し送りについて、緩和ケア病棟の看護師が外科病棟の看護師から収集する情報で最も優先すべきなのはどれか。
- 疼痛コントロールの状況
- 自宅の居住環境
- 大腸癌の術式
- 夫の面会頻度
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。
- 看護師等免許保持者の届出
- 特定行為に係る研修
- 教育訓練給付金
- 業務従事者届
災害発生時に行うSTART法によるトリアージで最初に判定を行う項目はどれか。
- 意識
- 呼吸
- 循環
- 歩行
日本の政府開発援助〈ODA〉の実施機関はどれか。
- 世界保健機関〈WHO〉
- 国際協力機構〈JICA〉
- 国連開発計画〈UNDP〉
- 赤十字国際委員会〈ICRC〉
▶午前77
脳の外側面を左右から見た模式図を示す。
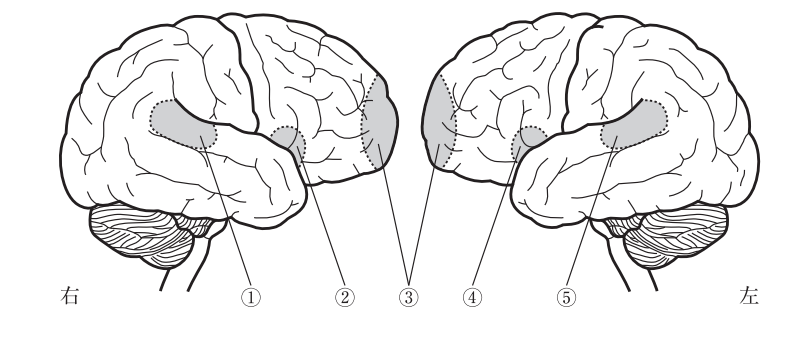
右利きの健常成人のBroca〈ブローカ〉の運動性言語中枢はどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
▶午前78
眼の遠近調節を行う筋はどれか。
- 下斜筋
- 下直筋
- 毛様体筋
- 上眼瞼挙筋
- 瞳孔括約筋
▶午前79
咀嚼運動にかかわる脳神経はどれか。
- 嗅神経
- 滑車神経
- 三叉神経
- 動眼神経
- 内耳神経
▶午前80
射出される精子が通るのはどれか。
- 精囊
- 尿管
- 尿道
- 膀胱
- 前立腺
▶午前81
心電図を別に示す。心電図の記録速度は25mm/秒である。

心電図波形によって計測した心拍数で正しいのはどれか。
- 30/分以上、50/分未満
- 50/分以上、70/分未満
- 70/分以上、90/分未満
- 90/分以上、100/分未満
- 100/分以上、110/分未満
▶午前82
急性大動脈解離において緊急手術を行うかどうかの観点で用いる分類はどれか。
- NYHA分類
- スタンフォード分類
- Killip〈キリップ〉分類
- DeBakey〈ドベーキー〉分類
- Forrester〈フォレスター〉分類
タイムアウトによって予防できるのはどれか。
- 患者の誤認
- 抗癌薬の曝露
- 個人情報の漏洩
- ベッドからの転落
- 血液を媒介とする感染
▶午前84
安静臥床による廃用症候群で生じるのはどれか。
- 1回換気量の増加
- 循環血液量の増加
- 基礎代謝の上昇
- 骨吸収の亢進
- 食欲の増進
▶午前85
Aさんは職場の上司に不満をぶつけたいと考えているが、それができないので、不満をぶつけやすい対象である後輩を叱責している。
Aさんの防衛機制で正しいのはどれか。
- 解離
- 昇華
- 合理化
- 置き換え
- 反動形成
▶午前86
ヘモグロビンA1c(HbA1c)について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 測定値の上限は10%である。
- 赤血球の寿命によって測定値は変動する。
- 過去1、2週間の血糖値管理の指標である。
- グリコアルブミンより短期間の血糖値管理の指標である。
- ヘモグロビンにブドウ糖が結合した糖化蛋白質のことである。
▶午前87
急性胆管炎の代表的な3症状を示すCharcot〈シャルコー〉3徴に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 黄疸
- 嘔吐
- 下痢
- 発熱
- 意識障害
▶午前88
高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA7〉で評価するのはどれか。2つ選べ。
- BMI
- 意欲
- 職業歴
- 新機器の利用
- 日常生活動作〈ADL〉
自閉症スペクトラム障害にみられるのはどれか。2つ選べ。
- 運動性チックが出現する。
- 計算の習得が困難である。
- 不注意による間違いが多い。
- 習慣へのかたくななこだわりがある。
- 非言語的コミュニケーションの障害がある。
▶午前90
100mg/5mLと表記された注射薬を75mg与薬するのに必要な薬液量を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:①.②mL
資料 厚生労働省「第108回保健師国家試験、第105回助産師国家試験、第111回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第111回看護師国家試験
令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午後問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」と合わせてご活用ください。
▼第110回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 状況設定問題
▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。
Aさん(64歳、女性、主婦)は、50歳で高血圧症と診断され、降圧薬を服用している。栄養指導を受け、食事療法も実施している。趣味はサイクリングと海外旅行である。数か月前からサイクリング中に息苦しさやめまいを感じるようになったため、かかりつけ医から紹介された病院を受診した。外来受診時のバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数24/分、脈拍40/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。
▶午後91
Aさんは完全房室ブロックが疑われた。
Aさんに行われる検査で優先されるのはどれか。
- 心臓超音波検査
- 12誘導心電図検査
- 心臓カテーテル検査
- 運動負荷心電図検査
▶午後92
検査の結果、Aさんは完全房室ブロックと診断された。
今後、Aさんに起こりやすいのはどれか。
- 脳虚血
- 肺塞栓症
- 不安定狭心症
- 心タンポナーデ
▶午後93
その後、Aさんにはペースメーカー植込み術が行われ、看護師は退院後の電磁干渉について説明を行った。Aさんからは「生活の中でどのようなことに注意をすれば良いですか」と質問があった。
Aさんが最も注意する必要がある状況はどれか。
- 新幹線への乗車
- パーソナルコンピュータの使用
- 電動アシスト付き自転車での移動
- 電子商品監視装置〈Electronic Article Surveillance:EAS〉の通過
▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。
Aさん(47歳、女性、会社員)は、夫(54歳)と2人暮らし。6か月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子をみていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経腟超音波検査の指示が出され、看護師はAさんに検査について説明することになった。
▶午後94
Aさんへの経腟超音波検査の説明で正しいのはどれか。
- 検査が終了するまで絶飲食にする。
- 検査前に排尿するよう促す。
- 検査は側臥位で行う。
- 検査後1時間は安静にする。
▶午後95
Aさんは、経腟超音波検査で異常所見が認められ、その後の精密検査で子宮体癌と診断されて準広汎子宮全摘出術と両側付属器(卵巣、卵管)切除術を受けた。術後の経過はよく、排尿障害もなく順調に回復していた。術後12日目のバイタルサイン測定時に「身体のほてりがあり、急に汗が出るようになったりして、夜もよく眠れません。そのためかイライラします」と看護師に訴えた。
Aさんに出現している症状の原因はどれか。
- エストロゲンの減少
- プロラクチンの減少
- アンドロゲンの増加
- オキシトシンの増加
- プロゲステロンの増加
▶午後96
Aさんはその後、順調に経過し退院した。退院後、初回の外来受診時に看護師がAさんに心配なことを尋ねると「退院のときも性生活の説明を聞きましたが、子宮がなくなって自分の身体がどう変化しているかわからないし、やっぱり性生活のことが気がかりです。夫も私の身体を気遣ってくれて、今日も一緒に病院に来てくれました」と語った。
Aさんへの性生活の説明で適切なのはどれか。
- 術後1年までは性行為を控える。
- 夫と別々に説明することを提案する。
- 性行為再開後は避妊を続けてもらう。
- 腟の乾燥に対して潤滑ゼリーを用いるとよい。
▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。
Aさん(75歳、女性)は、1人暮らし。高血圧症の内服治療をしているが、その他に既往歴はない。認知機能は問題ない。軽度の円背があるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。簡単な家事は自分で行っており、家の中で過ごすことが多かった。近所に住む長女が時々、Aさんの様子を見に来ていた。ある日、Aさんは自宅の階段を踏み外して転落し、横向きになったまま動けなくなったところを訪問してきた長女に発見され、救急車で病院に運ばれ、右大腿骨頸部骨折と診断された。そのまま入院し、緊急手術を行うことになった。
▶午後97
手術前オリエンテーションの際の看護師の説明内容で適切なのはどれか。
- 「手術はすぐに終わります」
- 「手術後はすぐに水を飲めます」
- 「手術後は両足とも動かしてはいけません」
- 「手術後は背中にクッションを当てます」
▶午後98
手術後14日。Aさんは、回復期リハビリテーション病棟のトイレ付きの個室に移動した。Aさんは歩行訓練を行っているが、立ち上がるときにバランスを崩しやすく「夜トイレに行こうとしてベッドから立ち上がるときに、ふらふらする。また転んでしまうのが怖い」と言っている。
このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。
- ポータブルトイレを置く。
- ベッドに移動介助バーを付ける。
- ベッドの頭部側を45度挙上する。
- 夜間はヒッププロテクターを装着する。
▶午後99
Aさんの退院日が決定した。看護師は、Aさんの退院前の指導を行うことになった。Aさんから「医師から骨がもろくなっていると言われました。これ以上悪くならないように何をすればよいでしょうか」と質問があった。
Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「体操は控えましょう」
- 「炭酸飲料を飲みましょう」
- 「果物を積極的に摂りましょう」
- 「日光を浴びるようにしましょう」
▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。
Aちゃん(生後3週)は、在胎40週、3,070gで出生した。生後5日で退院し、退院時の体重は3,080gであった。完全母乳栄養である。
現病歴:5日前から嘔吐があり、次第に哺乳のたびに噴水状に嘔吐するようになった。今朝も嘔吐があり、吐物は白色である。排尿もないため家族に連れられ来院した。Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症が疑われ入院した。
身体所見:体重3,380g、体温36.7℃。脈拍120/分、整。血圧74/52mmHg。大泉門は陥凹、皮膚のツルゴールは低下、上腹部は軽度膨隆。
検査所見:白血球9,600/μL。Na131mEq/L、K3.4mEq/L、Cl86mEq/L、CRP0.1mg/dL。
▶午後100
Aちゃんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。
- 脱水症は軽度である。
- 非胆汁性嘔吐である。
- 炎症反応の上昇がある。
- 出生後の体重増加は良好である。
▶午後101
検査の結果、Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症と診断された。Aちゃんは直ちに絶飲食となり、経鼻胃管が留置され、持続点滴静脈内注射が開始された。担当医師と家族とが治療方針を話し合った結果、全身状態が安定したあとに手術をする方針になった。
Aちゃんの術前看護で正しいのはどれか。
- 浣腸を1日2回行う。
- 尿量の測定は不要である。
- 経鼻胃管は自然開放とする。
- Aちゃんを抱っこすることは禁忌である。
▶午後102
入院後3日。Aちゃんは全身状態が安定し、全身麻酔下で腹腔鏡を用いた粘膜外幽門筋切開術(Ramstedt〈ラムステッド〉手術)を受けた。
術後の看護で適切なのはどれか。
- 授乳前後の排気
- 人工乳への変更
- 予防接種の計画立案
- 腸管の縫合不全の観察
▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。
Aちゃん(5か月、女児)は、父親(会社員)、母親(主婦)、兄のB君(3歳)と4人家族である。近所に祖父母が住んでいる。Aちゃんは3日前から鼻汁と咳嗽があり、昨日夕方より39℃の発熱がみられ小児科外来を受診した。自宅で哺乳量の低下はなく、1日に1、2回咳嗽とともに嘔吐がみられていた。来院時、体温39.3℃、呼吸数45/分、脈拍142/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であった。診察と検査の結果、RSウイルスによる急性細気管支炎と診断され、去痰薬が処方された。
▶午後103
診察後、家庭でのケアについてAちゃんの母親に指導することになった。
看護師の指導で適切なのはどれか。
- 「1回に飲むミルクの量を多くしてください」
- 「哺乳前に鼻水を器具で吸引してあげてください」
- 「去痰薬は、ミルクを飲んだ後に飲ませてください」
- 「授乳後は仰向けで寝かせてください」
▶午後104
Aちゃんは、発熱が続き、哺乳量が減ってきたため2日後に再度来院した。来院時、体温39.4℃、呼吸数60/分、脈拍154/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)、口唇色と顔色はやや不良であった。胸部エックス線撮影で肺炎像は認められない。Aちゃんは、経口摂取不良と呼吸困難のため、母親が付き添って入院することとなった。酸素吸入と点滴静脈内注射が開始された。
入院前のAちゃんについて母親から収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。
- 去痰薬の内服状況
- 最終排尿の時間
- 皮膚搔痒の有無
- 排便の状況
▶午後105
入院後7日、Aちゃんは症状が軽快し、哺乳量も増加して翌日の金曜日に退院が決定した。母親は「Aはだいぶ元気になりました。でもBが泣いたり、かんしゃくをおこしたりすることが増えているようです。どうしたらいいでしょう」と看護師に相談した。入院中、土曜日、日曜日は父親がB君の世話をしており、平日は祖父母が世話をしているとのことであった。退院時、父親は休暇をとりAちゃんと母親を迎えに来る予定である。
母親への看護師の対応として適切なのはどれか。
- 「B君のかかりつけ医に相談しましょう」
- 「B君の保育所への入所を検討しましょう」
- 「B君に関わる時間をたっぷりとりましょう」
- 「お兄ちゃんだから頑張りなさいと伝えましょう」
▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。
Aさん(30歳、初産婦)は妊娠39週3日で陣痛発来し、4時に入院した。その後、陣痛が増強して順調な分娩進行と診断されて、11時45分の診察で子宮口が8cm開大となった。看護師が12時に昼食を配膳にいくとAさんは額に汗をかいて、側臥位で「陣痛がつらくて何も飲んだり食べたりしたくありません」と言っている。陣痛発作時は強い産痛と努責感を訴え、目を硬く閉じて呼吸を止めて全身に力を入れている。
▶午後106
Aさんへの看護で最も適切なのはどれか。
- 坐位になるよう勧める。
- シャワー浴を勧める。
- 食事摂取を促す。
- 呼吸法を促す。
▶午後107
Aさんは16時15分、3,300gの男児を経腟分娩で出産した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点。胎盤娩出直後から凝血の混じった暗赤色の性器出血が持続している。この時点での出血量は600mL。臍高で柔らかい子宮底を触れた。脈拍90/分、血圧116/76mmHg。意識は清明。Aさんは「赤ちゃんの元気な泣き声を聞いて安心しました」と言っている。
このときの看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 子宮底の輪状マッサージを行う。
- 膀胱留置カテーテルを挿入する。
- 水分摂取を促す。
- 全身清拭を行う。
▶午後108
Aさんの分娩経過は以下のとおりであった。
2時00分 陣痛周期10分
4時00分 入院
15時00分 分娩室入室
15時30分 子宮口全開大
16時00分 自然破水
16時15分 児娩出
16時30分 胎盤娩出
Aさんの分娩所要時間はどれか。
- 12時間30分
- 14時間15分
- 14時間30分
- 16時間30分
▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。
Aさん(32歳、男性)は、仕事上のストレスを抱えていた際に知人から誘われ、覚せい剤を常用するようになり逮捕された。保釈後、薬物依存症の治療を受けることができる精神科病院に入院し、治療プログラムに参加することになった。
▶午後109
入院時のAさんへの看護師の対応として適切なのはどれか。
- 二度と使用しないと約束させる。
- 回復が期待できる病気であることを伝える。
- 使用をやめられなかったことに対する反省を促す。
- 自分で薬物を断ち切る強い意志を持つように伝える。
▶午後110
入院2週後、Aさんは病棟生活のルールを守ることができず、それを注意した看護師に対して攻撃的になることがあった。別の看護師がAさんに理由を尋ねると「指図するような話し方をされると、暴力的だった父親を思い出し、冷静でいられなくなる」と話した。
このときAさんに起こっているのはどれか。
- 転移
- 逆転移
- 躁的防衛
- 反動形成
▶午後111
入院後1か月、Aさんは「正直に言うと、今も覚せい剤を使いたいという気持ちがある。もし誘いがあったら、使いたい気持ちを抑えきれないだろう」と悩みを打ち明けた。
Aさんの状態のアセスメントとして適切なのはどれか。
- 否認
- 共依存
- 身体依存
- 精神依存
- 離脱症状
▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。
Aさん(35歳、男性)は1人暮らし。両親は他県に住んでいる。30歳のときに双極性障害と診断され、これまでに4回の入退院を繰り返している。給料をインターネットゲームの利用料金で度々使い果たし、それが原因で両親と何度も口論になったことがある。仕事では同僚とトラブルを起こすたびに転職を繰り返しており、今回も同僚と口論になり自ら退職した。Aさんは「前の職場の同僚に嫌がらせをしてやる」と母親に電話をかけ、心配した両親が一緒に精神科病院を受診した。診察室では多弁で大きな声を出し、椅子を蹴るなどの行為がみられた。医師の診察の結果、入院して治療することになった。
▶午後112
入院時、AさんのBMIは29.5。この数日は食事をとっていなかった。入院後も興奮状態がおさまらず、壁に頭を打ちつけはじめたため、医師から抗精神病薬の点滴静脈内注射と身体的拘束の指示がでた。
身体的拘束中のAさんの看護で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 水分摂取は最小限にする。
- 肺血栓塞栓症を予防する。
- 頻回に様子を見に来ることを伝える。
- 身体的拘束の原因となった行為を一緒に振り返る。
- 興奮状態が落ち着いたら看護師の判断で身体的拘束を解除する。
▶午後113
入院後1週、身体的拘束は解除された。Aさんは常に動き回り、他の患者への過干渉が続いている。食事中に立ち上がりホールから出ていこうとするため、看護師が止めると強い口調で言い返してくる。Aさんは「ゲーム関連の仕事を探したい。早く退院させろ」と1日に何度も看護師に訴えるが、主治医は退院を許可していない。
Aさんへの対応で適切なのはどれか。
- 休息できる場所へ誘導する。
- 過干渉となる理由を確認する。
- 退院後は家族と暮らすように提案する。
- 仕事に必要なスキルについて話し合う。
▶午後114改題
入院後2か月、Aさんの状態は落ち着き、退院に向けての準備が進められている。Aさんは、「会社で同僚と言い合いになってこれまでも仕事を変わってきた。そのたびに調子が悪くなって、何度も入院した。家族と言い合いをしたぐらいで近所から苦情があって、嫌になって引っ越した」と看護師に訴えた。
Aさんの退院に向けて連携をとる機関はどれか。
- 警察
- 保護観察所
- 地域活動支援センター
▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。
Aさん(37歳、男性)は妻(40歳、会社員)と2人暮らし。筋強直性ジストロフィーで週5回の訪問介護を利用していた。1か月前に傾眠傾向が著明となり入院して精査した結果、睡眠時無呼吸に対して夜間のみフェイスマスクを用いた非侵襲的陽圧換気療法が導入された。Aさんは四肢遠位筋に筋萎縮と筋力低下があるが、室内の移動は電動車椅子を操作して自力で行え、食事も準備すれば妻と同じものを摂取できる。退院後、週1回午後に訪問看護が導入されることになった。
▶午後115
訪問看護と訪問介護の担当者、Aさんと妻を含めた退院前カンファレンスが開催された。妻から「夜間に停電になったらどうすればよいですか」と発言があった。
このときの妻への訪問看護師の対応で適切なのはどれか。
- 電動式でない車椅子を購入するよう勧める。
- 訪問看護事業所が発電機を貸し出すと伝える。
- バッグバルブマスクでの用手換気の指導を行う。
- 停電時にハザードマップを確認するよう提案する。
▶午後116
退院前カンファレンスで、訪問介護の担当者から、これまでと同様に退院後も昼食の準備と後始末、口腔ケア、入浴介助を行う予定と発言があった。訪問看護師は訪問介護の担当者に、Aさんの状態の変化に気付いたら連絡がほしいと協力を求めた。
訪問介護の担当者に説明するAさんの状態の変化で、特に注意が必要なのはどれか。
- 傾眠傾向
- 眼の充血
- 口腔内の乾燥
- 食事摂取量の低下
▶午後117
退院後1週、訪問看護師はAさんの鼻根部の皮膚に発赤があることに気付いた。
訪問看護師の妻への対応で適切なのはどれか。
- 「鼻マスクに変更しましょう」
- 「発赤部位は洗わないようにしましょう」
- 「人工呼吸器の装着時間は短くしましょう」
- 「フェイスマスクのベルトは指が2本入る程度に固定しましょう」
▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。
Aさん(88歳、男性)は、10年前に脳梗塞を発症し左半身麻痺の後遺症がある。杖歩行はでき、要介護2で介護保険サービスを利用中である。Aさんが最近食欲がなく、水分もあまり摂らず、いつもと様子が違うことを心配した妻がAさんに付き添って受診した。
身体所見:呼びかけに対して返答はあるが反応はやや遅い。麻痺の症状に変化はない。
バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数20/分、脈拍100/分、血圧140/60mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。
検査所見:赤血球410万/μL、白血球6,800/μL、Ht50%、総蛋白6.5g/dL、尿素窒素25mg/dL、Na150mEq/L、K3.8mEq/L、血糖値110mg/dL、CRP0.01mg/dL。胸部エックス線写真に異常なし。
▶午後118
Aさんの状態をアセスメントするために、外来看護師が収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。
- 口渇感
- 呼吸音
- 尿比重
- 腹部膨満感
▶午後119
Aさんは入院となり、点滴静脈内注射が開始された。入院当日の夜間、Aさんは「ここはどこか、家に帰る」などと言い、点滴ラインを触ったり杖を使わずにトイレに1人で行こうとしたりして落ち着かず、ほとんど眠っていなかったと夜勤の看護師から日勤の看護師に申し送りがあった。
日勤でAさんを受け持つ看護師の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 時計をAさんから見える場所に置く。
- 主治医にAさんの退院について相談する。
- 日中はAさんにスタッフステーションで過ごしてもらう。
- 点滴ラインがAさんの視界に入らないようにする。
- 日中はAさんの病室の窓のカーテンを閉めておく。
▶午後120
入院から1週が経過し、Aさんのバイタルサインなどは正常となり、食事も摂取できるようになった。Aさんの妻は「先生からそろそろ退院できるといわれましたが、夫はほとんどベッド上で過ごしており、トイレまで歩けそうにありません。これで退院できるか不安です」と看護師に話した。現在のAさんの日常生活動作〈ADL〉は、起立時にふらつきがみられ、歩行は不安定である。ポータブルトイレを使用して排泄している。
現在のAさんの状況から、退院に向けて看護師が連携する者で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 薬剤師
- 民生委員
- 管理栄養士
- 理学療法士
- 介護支援専門員
資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第110回看護師国家試験
令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第110回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後26
生後から20歳になるまでの器官の発育発達を示した曲線(Scammon〈スカモン〉の発育発達曲線)を図に示す。
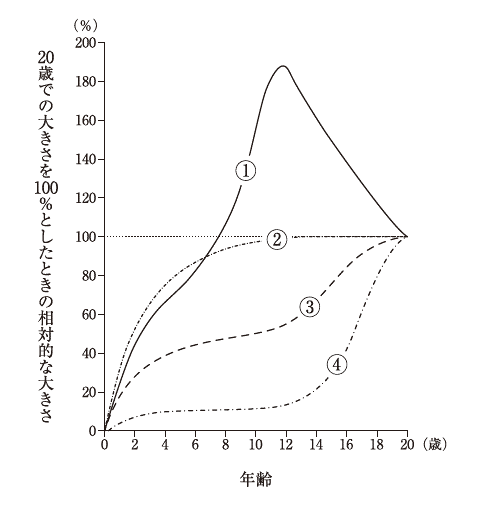
胸腺の成長を示すのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
▶午後27
腸閉塞について正しいのはどれか。
- 仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。
- 経口による水分摂取は少量にする。
- イレウス管を小腸に留置する。
- 抗菌薬の投与は禁忌である。
▶午後28
膀胱癌について正しいのはどれか。
- 女性に多い。
- 尿路上皮癌より腺癌が多い。
- 経尿道的生検によって治療法を決定する。
- 表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。
日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。
- 患者調査
- 国勢調査
- 国民生活基礎調査
- 国民健康・栄養調査
感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。
- 結核――接触感染
- 麻疹――空気感染
- マラリア――飛沫感染
- インフルエンザ――経口感染
▶午後31
診療記録で正しいのはどれか。
- 看護記録が含まれる。
- 開示は保健所長が行う。
- 1年間の保存義務がある。
- 閲覧は患者本人に限られる。
雇用保険法について正しいのはどれか。
- 育児休業給付がある。
- 雇用保険は任意加入である。
- 雇用保険の保険者は市町村である。
- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。
▶午後33
小学校の児童が石けんと流水を用いた手指衛生の手技を習得するために最も適切な学習方法はどれか。
- 動画を視聴する。
- 友人と話し合う。
- 手洗い場で体験する。
- 養護教諭の話を聞く。
▶午後34
呼吸音の変化と原因の組合せで正しいのはどれか。
- 呼気延長――胸水
- 呼吸音の減弱――過換気症候群
- 呼吸音の増強――無気肺
- 肺野での気管支呼吸音の聴取――肺炎
▶午後35
ヒューマンエラーを起こす人間の特性で認知的特性はどれか。
- 同僚への依存
- 睡眠不足による疲労
- 同じ作業の連続による注意力低下
- パワーハラスメントによる心理的圧迫
▶午後36
エアマットレスの使用目的で適切なのはどれか。
- 体圧分散
- 体温管理
- 関節拘縮の予防
- 末梢循環の促進
▶午後37
車椅子による移送で正しいのはどれか。
- 坂を上るときは、背もたれ側から進む。
- 段差を上るときは、小車輪を浮かせる。
- 方向転換をするときは、小車輪を支点にする。
- 乗り降りをするときは、フットレストを下げる。
▶午後38
成人の上腕での触診法による血圧測定で適切なのはどれか。
- ゴム囊中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。
- マンシェットの幅は13〜17cmのものを使用する。
- 加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。
- 動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。
▶午後39
経口薬と食品の関係について、正しいのはどれか。
- テトラサイクリン系抗菌薬は牛乳の摂取によって吸収が高まる。
- 非ステロイド性抗炎症薬は炭酸飲料の摂取によって吸収が早まる。
- 抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。
- キサンチン系気管支拡張薬は納豆の摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。
夜勤帯に看護師が病棟のトイレ内で倒れている患者を発見した。呼びかけても反応がない。
この看護師が最初に実施すべきなのはどれか。
- 脈拍を確認する。
- 胸骨圧迫を開始する。
- トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。
- 自動体外式除細動器〈AED〉を取りに行く。
▶午後41
心原性ショックで現れる症状・徴候はどれか。
- 顔面の紅潮
- 胸部不快感
- 血圧の上昇
- 尿量の増加
▶午後42
脳梗塞による右片麻痺がある成人患者に用いる日常生活動作〈ADL〉の評価として適切なのはどれか。
- NYHA分類
- Borg〈ボルグ〉スケール
- Barthel〈バーセル〉インデックス
- 主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉
▶午後43
現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気がかりや価値観を定期的に話し合って共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。
この内容を示すのはどれか。
- グリーフケア
- 代理意思決定の支援
- アドバンス・ケア・プランニング
- アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援
▶午後44
Aさん(34歳、女性)は、気管支喘息で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。
経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH7.30、HCO3-25 mEq/Lであった。
Aさんの状態で考えられるのはどれか。
- 呼吸性アシドーシス
- 呼吸性アルカローシス
- 代謝性アシドーシス
- 代謝性アルカローシス
脂質異常症の成人患者に対する食事指導の内容で正しいのはどれか。
- 不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。
- コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。
- 高トリグリセリド血症では、アルコールを制限する。
- 高LDLコレステロール血症では、トランス脂肪酸の摂取を促す。
▶午後46
成人患者の甲状腺全摘出術後における合併症とその症状との組合せで正しいのはどれか。
- 乳び漏――嘔気
- 術後出血――ドレーン排液の白濁
- 反回神経麻痺――口唇のしびれ
- 低カルシウム血症――テタニー
▶午後47
Aさんは右側の人工股関節全置換術〈後方アプローチ〉を受けた。
Aさんへの脱臼予防の生活指導で適切なのはどれか。
- 「靴はしゃがんで履いてください」
- 「右側に身体をねじらないでください」
- 「椅子に座るときは足を組んでください」
- 「浴室の椅子は膝の高さより低いものを使ってください」
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- 介護保険法
- 老人福祉法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉
▶午後49
認知症高齢者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。
- 説得するように話す。
- 作話があっても話を聞く。
- 一度に多くの情報を伝える。
- 同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。
令和3年(2021年)の高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査で、高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち割合が最も多いのはどれか。
- 教育・文化
- 子育て支援
- 生産・就業
- 健康・スポーツ
▶午後51
Aさん(73歳、女性)は、既往歴はなく自立した生活を送っていた。最近、尿意を我慢できず尿失禁することがあり、夜間の排尿回数も増えたため、病院を受診した。その結果、過活動膀胱と診断された。
Aさんへの看護師の指導内容で適切なのはどれか。
- 腹筋を鍛える。
- 膀胱訓練を行う。
- 水分摂取を控える。
- 尿意を感じたらすぐトイレに行く。
▶午後52
高齢者のうつ病の症状はどれか。
- 意識障害
- 知能低下
- 歩行障害
- 強い不安感
令和5年度(2023年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。
- 0歳
- 1~4歳
- 5~9歳
- 10~14歳
健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。
- 情緒は快から不快が分化する。
- 発達とともにレム睡眠の割合は増える。
- 体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。
- 身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。
▶午後55
生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。
- 吸啜反射
- Moro〈モロー〉反射
- Landau〈ランドー〉反射
- 探索〈ルーティング〉反射
▶午後56
フォローアップミルクで正しいのはどれか。
- 母乳の代替品である。
- 鉄分が添加されている。
- 離乳食を食べる直前に与える。
- 離乳食開始の時期から与え始める。
▶午後57
受精と着床についての説明で正しいのはどれか。
- 卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。
- 卵管采で受精が起こる。
- 受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。
- 受精卵は桑実胚の段階で着床する。
母体保護法で規定されているのはどれか。
- 育児時間
- 生理休暇
- 受胎調節の実地指導
- 育児中の深夜業の制限
▶午後59
クラウス, M. H.とケネル, J. H.が提唱した絆(ボンディング)について適切なのはどれか。
- 生まれながらのものである。
- 母子間の同調性を意味する。
- 母子相互作用によって促進される。
- 親との間に子どもが築くものである。
早産期の定義はどれか。
- 妊娠21週0日から36週6日
- 妊娠22週0日から36週6日
- 妊娠22週0日から37週6日
- 妊娠23週0日から37週6日
妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
- 母子保健法
- 労働基準法
- 育児介護休業法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
アルコールを多飲する人によくみられ、意識障害、眼球運動障害および歩行障害を特徴とするのはどれか。
- 肝性脳症
- ペラグラ
- Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症
- Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病
精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。
- 知的障害も交付対象である。
- 取得すると住民税の控除対象となる。
- 交付によって生活保護費の支給が開始される。
- 疾病によって障害が永続する人が対象である。
▶午後64
攻撃性の高まった成人患者への対応で正しいのはどれか。
- 患者の正面に立つ。
- アイコンタクトは避ける。
- 身振り手振りは少なくする。
- ボディタッチを積極的に用いる。
▶午後65
Aさん(79歳、男性)は、1人暮らし。要介護2の認定を受け、訪問看護を利用することになった。初回の訪問時、Aさんは敷いたままの布団の上に座っており「便利だから生活に必要なものを手の届くところに置いているんだよ」と話した。
Aさんの生活様式を尊重した訪問看護師のこのときの声かけで適切なのはどれか。
- 「外に出て気分転換しませんか」
- 「昼間は布団をたたみましょう」
- 「介護保険でベッドの貸与を受けましょう」
- 「必要なものを身近に置いているのですね」
▶午後66
Aさん(69歳、女性)は、主治医、訪問看護師とともに、母(91歳)を自宅で看取った。死亡確認の直後、Aさんは涙ぐみながら「母のためにもっとできることがあったのではないかと申し訳なく思います」と話した。
このときに訪問看護師が行うAさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 遺族の会を紹介する。
- 母への思いを傾聴する。
- 遺品を整理することを勧める。
- 新たなことに取りかかるよう促す。
▶午後67
Aさん(82歳、女性)は、脳梗塞の既往があり、要介護2で、夫(85歳)と2人暮らし。訪問看護師の訪問時、Aさんは体温37.0℃、脈拍62/分、血圧100/50mmHg、少し汗をかいており、唇の乾燥がみられた。訪問看護師は、翌日予定されている訪問介護の担当者とAさんの援助の方向性について共有することにした。
共有する内容で適切なのはどれか。
- ポータブルトイレでの排泄に変更する。
- 水分を多めに摂取するよう促す。
- 頻繁に寝衣を交換する。
- 入浴介助を中止する。
介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。
- 重度訪問介護
- 地域活動支援事業
- 小規模多機能型居宅介護
- 特定施設入居者生活介護
成年後見制度で正しいのはどれか。
- 任意後見人は裁判所が決定する。
- 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。
- 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。
- 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。
仙骨部に皮下組織に達する褥瘡がある患者が入院となった。患者は車椅子の利用を主治医に許可されている。
この患者に対する多職種で行う褥瘡ケアにおいて、受け持ち看護師が担う役割で適切なのはどれか。
- 薬剤師に外用薬の処方を依頼する。
- 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。
- 介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。
- 理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。
災害時のトリアージで正しいのはどれか。
- トリアージタッグは衣服に装着する。
- 治療優先度の高さはトリアージ区分のⅠ、Ⅱ、Ⅲの順である。
- トリアージの判定は患者の到着時および到着後30分の2回行う。
- 最優先に治療を必要とする者には、黄色のトリアージタッグを装着する。
国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。
- 国際労働機関〈ILO〉――難民の帰還支援
- 世界保健機関〈WHO〉――保健分野における研究の促進
- 国連人口基金〈UNFPA〉――平和維持活動
- 国連世界食糧計画〈WFP〉――二国間の国際保健医療協力
▶午後73
血漿蛋白質の大部分を合成しているのはどれか。
- 肺
- 肝臓
- 腎臓
- 膵臓
- 脾臓
▶午後74
胸膜腔に存在するのはどれか。
- 滑液
- 空気
- 血液
- 漿液
- 粘液
▶午後75
正常な性周期である健常女性の10週間の基礎体温を図に示す。
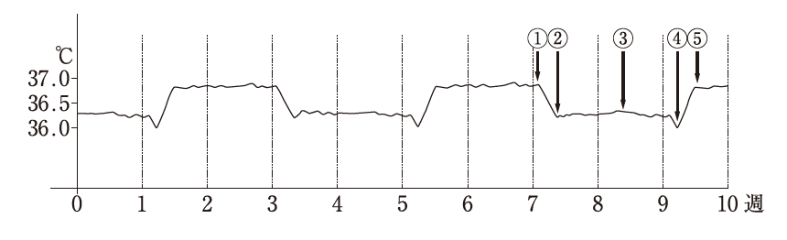
直近の排卵日はどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
▶午後76
閉塞性動脈硬化症〈ASO〉について正しいのはどれか。
- 橈骨動脈に好発する。
- 粥状硬化が原因である。
- 末梢血流量が増加する。
- 歩行によって痛みが改善する。
- 中小動脈の非化膿性炎症で生じる。
関節リウマチで起こる主な炎症はどれか。
- 滑膜炎
- 血管炎
- 骨髄炎
- 骨軟骨炎
- 関節周囲炎
母子保健法に基づく届出はどれか。
- 婚姻届
- 死産届
- 死亡届
- 出生届
- 妊娠届
Aさん(44歳、男性、会社員)は、20年以上の喫煙歴があり、BMI26である。会社の健康診断で脂質異常症と高血圧症を指摘された。
Aさんが発症する危険性が高い疾患はどれか。
- 1型糖尿病
- 潰瘍性大腸炎
- 肺血栓塞栓症
- 労作性狭心症
- 閉塞性血栓血管炎〈TAO〉
▶午後80
Aさん(48歳、男性、会社員)は、大量の飲酒の後、急激な上腹部痛と背部痛を訴え、救急外来を受診し、急性膵炎と診断された。
Aさんの救急外来受診時の血液検査結果で予測されるのはどれか。
- 血小板数の増加
- 血清LDH値の低下
- 血清γ-GTP値の低下
- 血清アミラーゼ値の上昇
- 血清カルシウム値の上昇
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
▶午後82
副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。
- 動眼神経
- 三叉神経
- 内耳神経
- 迷走神経
- 舌下神経
▶午後83
血圧を上昇させるのはどれか。2つ選べ。
- セロトニン
- ヒスタミン
- バソプレシン
- ブラジキニン
- 心房性ナトリウムペプチド
▶午後84
蠕動運動がみられるのはどれか。2つ選べ。
- 腎動脈
- 腎盂
- 尿管
- 膀胱
- 尿道
▶午後85
炎症の4徴候に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 壊疽
- 腫脹
- 膿瘍
- 発赤
- 浮腫
▶午後86
肝硬変におけるChild-Pugh〈チャイルド-ピュー〉分類の判定項目はどれか。2つ選べ。
- プロトロンビン時間
- 血清アルブミン値
- 血中アンモニア値
- 血小板数
- 尿酸値
老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。
- 国
- 市町村
- 都道府県
- 福祉事務所
- 後期高齢者医療広域連合
▶午後88
Aさん(53歳、男性、会社員)は、数日前から耳鳴、めまい、耳閉感が出現し、突発性難聴と診断され入院となった。副腎皮質ステロイド薬の投与で症状が改善したため退院することになった。入院前の生活習慣は、外食2回/週、飲酒(ビール700mL)/日、睡眠6時間/日、入浴1回/日、喫煙20本/日、散歩2回/週。
退院後の生活で、Aさんが控えるべき事項はどれか。2つ選べ。
- 飲酒
- 外食
- 喫煙
- 散歩
- 入浴
▶午後89
神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 過食と嘔吐を繰り返す。
- 腸管で吸収不全がある。
- 男性では性欲が亢進する。
- ボディイメージの歪みがある。
- 第二次性徴の発現前に発症すると初経は遅れる。
▶午後90
6%の次亜塩素酸ナトリウム液を用いて0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を1,000mL作るために必要な6%次亜塩素酸ナトリウム液の量を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②mL
資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第110回看護師国家試験
令和3年2月14日(日)に実施された第110回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第110回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
▶午前26
複数の筋腹が腱で直列につながっている筋はどれか。
- 咬筋
- 上腕二頭筋
- 腹直筋
- 大腿四頭筋
ウイルス性肝炎の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。
- A型肝炎ウイルス
- B型肝炎ウイルス
- C型肝炎ウイルス
- E型肝炎ウイルス
▶午前28
成人の敗血症について正しいのはどれか。
- 徐脈となる。
- 高血圧となる。
- 血管透過性が低下する。
- 全身炎症性反応を認める。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。
- 医療法
- 健康保険法
- 地域保健法
- 個人情報の保護に関する法律
食中毒予防の原則である「中心温度75℃以上1分以上の加熱」が有効なのはどれか。
- フグ毒
- 毒キノコ
- 黄色ブドウ球菌
- サルモネラ属菌
▶午前31
ソーシャルサポートのうち、情緒的サポートはどれか。
- 傾聴する。
- 情報提供する。
- 外出に付き添う。
- 経済的支援をする。
▶午前32
看護過程における情報収集で適切なのはどれか。
- 既往歴は情報に含めない。
- 看護計画立案後も情報収集を継続する。
- 看護問題を特定してから情報収集を開始する。
- 不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。
▶午前33
漸進的筋弛緩法の目的はどれか。
- 気道の確保
- 緊張の緩和
- 麻痺の改善
- 全身麻酔の導入
▶午前34
尿失禁の種類と対応の組合せで正しいのはどれか。
- 溢流性尿失禁――排尿間隔の記録
- 機能性尿失禁――骨盤底筋訓練
- 切迫性尿失禁――下腹部への軽い刺激
- 反射性尿失禁――間欠的自己導尿
▶午前35
成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。
- アドレナリン
- オキシトシン
- 成長ホルモン
- 甲状腺ホルモン
▶午前36
患者の状態と寝衣の特徴との組合せで適切なのはどれか。
- 発熱がある患者――防水性のもの
- 開腹術直後の患者――上着とズボンに分かれたもの
- 意識障害のある患者――前開きのもの
- 下肢に浮腫のある患者――足首にゴムが入っているもの
▶午前37
成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。
- 10〜20度
- 30〜40度
- 50〜60度
- 70〜80度
▶午前38
生体検査はどれか。
- 喀痰検査
- 脳波検査
- 便潜血検査
- 血液培養検査
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。
- 一類感染症
- 二類感染症
- 三類感染症
- 四類感染症
▶午前40
Aさん(63歳、男性)は、右肺癌で化学療法を受けていたが、右腕を動かしたときに上腕から肩にかけて痛みが生じるようになった。検査を行ったところ骨転移が認められ、疼痛の原因と判断された。WHO3段階除痛ラダーに基づいてがん疼痛のコントロールを開始することになった。
この時点でAさんに使用する鎮痛薬で適切なのはどれか。
- 非オピオイド鎮痛薬
- 弱オピオイド鎮痛薬
- 強オピオイド鎮痛薬
- 鎮痛補助薬
▶午前41
Aさん(24歳、男性)は、突然出現した胸痛と呼吸困難があり、外来を受診した。意識は清明。身長180cm、体重51kg、胸郭は扁平である。20歳から40本/日の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分(浅い)、脈拍84/分、血圧122/64mmHgである。 胸部エックス線写真を別に示す。

Aさんの所見から考えられるのはどれか。
- 抗菌薬の投与が必要である。
- 胸腔ドレナージは禁忌である。
- 右肺野の呼吸音は減弱している。
- 胸腔内は腫瘍で占められている。
▶午前42
Aさん(50歳、男性)は肝硬変と診断され、腹水貯留と黄疸がみられる。
Aさんに指導する食事内容で適切なのはどれか。
- 塩分の少ない食事
- 脂肪分の多い食事
- 蛋白質の多い食事
- 食物繊維の少ない食事
▶午前43
Cushing〈クッシング〉症候群の成人女性患者にみられるのはどれか。
- 貧血
- 月経異常
- 体重減少
- 肝機能低下
▶午前44
Aさん(64歳、男性)は、肺炎のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)であった。
Aさんに出現している症状から考えられる病態はどれか。
- 後天性表皮水疱症
- Sjögren〈シェーグレン〉症侯群
- 全身性エリテマトーデス
- Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群
▶午前45
膝関節鏡検査の説明として適切なのはどれか。
- 「外来の処置室で行います」
- 「関節内に空気を入れます」
- 「検査後1日は入浴できません」
- 「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」
▶午前46
高齢者の自立度を手段的日常生活動作〈IADL〉尺度を用いて評価した。
この尺度にある項目はどれか。
- コミュニケーション
- 自分の服薬管理
- トイレ動作
- 階段昇降
▶午前47
加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能はどれか。
- 感覚記憶
- 短期記憶
- 結晶性知能
- 流動性知能
▶午前48
Aさん(80歳、男性)は、1人暮らし。高血圧症で内服治療をしているが健康状態や認知機能に問題はなく、日常生活動作〈ADL〉は自立している。毎朝30分の散歩と買い物を日課とし、週1回は老人クラブでゲートボールをしている。Aさんは受診の際に看護師に「最近、昼食後に居眠りをしてしまう。今は大丈夫だが、このままだと夜眠れなくなるのではないか」と話した。
Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 昼食後にも散歩を促す。
- 主治医に相談するよう勧める。
- 老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。
- 30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。
▶午前49
加齢に伴う血管壁の硬化による血圧への影響はどれか。
- 収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。
- 収縮期血圧は低下し、拡張期血圧は上昇する。
- 収縮期血圧も拡張期血圧も上昇する。
- 収縮期血圧も拡張期血圧も低下する。
▶午前50
加齢によって高齢者に便秘が起こりやすくなる原因で適切なのはどれか。
- 経口摂取量の低下
- 味覚の閾値の低下
- 腸管での水分吸収の低下
- 直腸内圧感受性の閾値の低下
▶午前51
高齢者がMRI検査を受ける前に、看護師が確認する内容で適切なのはどれか。
- 「夜はよく眠れますか」
- 「義歯を装着していますか」
- 「呼吸が苦しいことはありますか」
- 「水を飲むときにむせることはありますか」
養育医療が定められている法律はどれか。
- 児童福祉法
- 母子保健法
- 発達障害者支援法
- 児童虐待の防止等に関する法律
▶午前53
乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。
- 3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。
- 50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。
- 10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。
- 75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。
▶午前54
Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断されステロイド治療の方針となった。
現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。
- 水分摂取を促す。
- 病院内を散歩して良いと伝える。
- 糖分の摂取制限があることを伝える。
- 一時的に満月様顔貌になることを説明する。
▶午前55
子どもの遊びで正しいのはどれか。
- 身体機能の発達を促す。
- 1歳でごっこ遊びが多くみられる。
- 感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。
- テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。
日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。
- 出生10万対で示す。
- 出産後1年までの女性の死亡をいう。
- 令和4年(2022年)の妊産婦死亡率は、10.1である。
- 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。
▶午前57
更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。
- 乳癌
- 骨粗鬆症
- 子宮体癌
- 静脈血栓症
▶午前58
妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。
- 下肢静脈瘤
- 搔痒感
- つわり
- 頻尿
▶午前59
早期新生児の生理的黄疸で正しいのはどれか。
- 生後24時間以内に出現し始める。
- 皮膚の黄染は、腹部から始まる。
- 生後4、5日でピークとなる。
- 便が灰白色になる。
都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。
- ゲートキーパー
- ピアサポーター
- 精神保健福祉相談員
- 退院後生活環境相談員
Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。
Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。
- 療養介護
- 施設入所支援
- 地域移行支援
- 自立訓練としての機能訓練
▶午前62
選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉で正しいのはどれか。
- パニック障害に対して有効である。
- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。
- うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。
- 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。
精神保健指定医について正しいのはどれか。
- 医療法で規定されている。
- 都道府県知事が指定する。
- 障害年金の支給判定を行う。
- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
▶午前64
筋力低下のある在宅療養者の家屋環境において転倒するリスクが最も高いのはどれか。
- 深い浴槽
- 段差がない床
- 整理整頓された部屋
- 足元灯を設置した廊下
▶午前65
Aさん(75歳、男性)は妻(66歳)と2人暮らし。3か月前に認知症の診断を受けた。妻から訪問看護師に「夫は通所介護のときは穏やかに過ごしていると聞いているが、家では興奮することが多く、どう対応すればよいかわからない」と相談があった。
このときの妻に対する訪問看護師の最初の対応で適切なのはどれか。
- 主治医に相談するよう勧める。
- Aさんと散歩に出かけることを勧める。
- 通所介護の頻度を増やすことを提案する。
- Aさんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。
▶午前66
Aさん(83歳、女性)は、1人暮らし。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していた。今回の退院後に、訪問看護が導入されることになり、退院前カンファレンスが行われた。
誤嚥性肺炎の再発を予防するために病棟看護師が訪問看護師に情報提供する内容で優先されるのはどれか。
- 嚥下機能検査の判定結果
- 栄養状態を示す検査データ
- 入院中の日常生活動作〈ADL〉
- 誤嚥性肺炎の治療に用いられた薬剤
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
- 家族の介護能力はアセスメントに含めない。
- 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。
- 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。
- モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。
▶午前68
夜勤帯に、A看護師がスタッフステーションで抗菌薬の点滴静脈内注射を準備しているときに、発汗した患者から寝衣交換の依頼があり、別の患者から口渇で飲水したいという希望があった。直後に患者に装着されている人工呼吸器のアラームが鳴った。他の看護師は別の病室で重症者のケアをしている。
A看護師が最も優先すべきなのはどれか。
- 点滴静脈内注射の準備
- 発汗した患者の寝衣交換
- 飲水を希望する患者への対応
- 人工呼吸器を装着している患者の観察
病院における医療安全文化の醸成につながる行動はどれか。
- 食事介助は30分以内で行うルールを決める。
- 他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。
- 薬剤を間違えても影響がない場合は患者に説明しない。
- 水薬の内服時にこぼれた量が少ない場合はそのままとする。
プリセプターシップの説明で正しいのはどれか。
- 仕事と生活の調和を図ること
- 主体的に自らのキャリアを計画し組み立てること
- チームリーダーのもとに看護ケアを提供すること
- 経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること
大規模災害発生後2か月が経過し、応急仮設住宅で生活を始めた被災地の住民に出現する可能性が高い健康問題はどれか。
- 慢性疾患の悪化
- 消化器感染症の発症
- 深部静脈血栓症の発症
- 急性ストレス障害の発症
国際連合〈UN〉で採択された2016年から2030年までの開発に関する世界的な取り組みはどれか。
- 持続可能な開発目標〈SDGs〉
- ミレニアム開発目標〈MDGs〉
- プライマリヘルスケア
- 政府開発援助〈ODA〉
▶午前73
Aさん(52歳、男性)は、49歳から高血圧症で内服治療と食事や運動に関する生活指導を受けている。2か月間の予定で開発途上国に出張することになり、予防接種を受ける目的で渡航外来を受診した。Aさんから「渡航にあたって何か注意することはありますか」と質問があった。
Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「出張中は、減塩の必要はありません」
- 「出張先では有酸素運動は控えましょう」
- 「現地に到着してから健康診断を受診しましょう」
- 「持参する高血圧症の薬について、かかりつけ医に相談しましょう」
▶午前74
血液中のビリルビンの由来はどれか。
- 核酸
- メラニン
- アルブミン
- グリコゲン
- ヘモグロビン
抗原によって感作されたTリンパ球による細胞性免疫が主体となるのはどれか。
- 花粉症
- 蕁麻疹
- ツベルクリン反応
- アナフィラキシーショック
- インフルエンザの予防接種
▶午前76
後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。
- 二尖弁が多い。
- 弁尖の石灰化による。
- 左室壁は徐々に薄くなる。
- 拡張期に心雑音を聴取する。
- 心筋の酸素需要は減少する。
▶午前77
褐色細胞腫でみられるのはどれか。
- 高血糖
- 中心性肥満
- 満月様顔貌
- 血清カリウム濃度の低下
- 副腎皮質ホルモンの産生の亢進
▶午前78
Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群で正しいのはどれか。
- 若年者に多い。
- 遺伝性疾患である。
- 骨格筋に病因がある。
- 症状に日内変動がある。
- 抗ガングリオシド抗体が出現する。
生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。
( )に入る数字はどれか。
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
▶午前80
カウンセリングの基本的態度で適切なのはどれか。
- 査定
- 指示
- 受容
- 同化
- 評価
▶午前81
成人の人体図を別に示す。
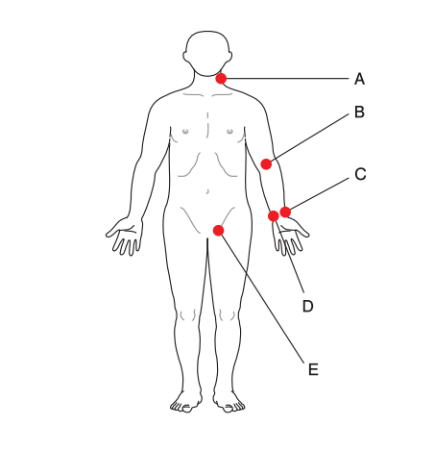
意識清明で不整脈のある成人の脈拍測定時に一般的に使われる部位はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
▶午前82
感染徴候のない創部の治癒を促進する要因はどれか。
- 圧迫
- 痂皮
- 湿潤
- 消毒
- 浮腫
▶午前83
小児期における消化器の特徴で正しいのはどれか。
- 新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。
- 乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。
- ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。
- アミラーゼの活性は12〜13歳で成人と同程度になる。
- 出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。
▶午前84
感覚受容にリンパ液の動きが関与するのはどれか。2つ選べ。
- 嗅覚
- 聴覚
- 味覚
- 振動感覚
- 平衡感覚
▶午前85
血液のpH調節に関わっているのはどれか。2つ選べ。
- 胃
- 肺
- 心臓
- 腎臓
- 膵臓
▶午前86改題
悪性貧血で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 匙状爪が多くみられる。
- 異食症が出現する。
- 小球性の貧血である。
- 胃癌の発症率が高い。
- 自己免疫機序で発症する。
労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 通勤災害時の療養給付
- 失業時の教育訓練給付金
- 災害発生時の超過勤務手当
- 有害業務従事者の健康診断
- 業務上の事故による介護補償給付
▶午前88
尿管結石症の治療で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 尿路変更術
- 血管拡張薬の投与
- カルシウム製剤の投与
- 体外衝撃波砕石術〈ESWL〉
- 非ステロイド系抗炎症薬の投与
Aさん(38歳、女性)は、大腸癌の終末期である。癌性腹膜炎による症状緩和の目的で入院し、鎮痛薬の静脈内注射と高カロリー輸液が開始された。Aさんは自宅で過ごしたいと希望したため、医師と看護師で検討し、症状緩和をしながら自宅退院の方向で退院支援カンファレンスを開催することになった。
退院支援カンファレンスの参加者で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 薬剤師
- 言語聴覚士
- 臨床検査技師
- 介護支援専門員
- ソーシャルワーカー
身体的フレイルの評価基準はどれか。2つ選べ。
- 視力低下
- 体重減少
- 聴力低下
- 歩行速度の低下
- 腸蠕動運動の低下
資料 厚生労働省「第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験、第110回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第110回看護師国家試験
令和2年2月16日(日)に実施された第109回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第109回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後18(必修除外)
過呼吸で正しいのはどれか。
- 吸気時に下顎が動く。
- 1回換気量が増加する。
- 呼吸数が24/分以上になる。
- 呼吸リズムが不規則になる。
▶午後26
成人の骨格で線維軟骨結合があるのはどれか。
- 頭蓋冠
- 脊柱
- 寛骨
- 仙骨
▶午後27
咀嚼筋はどれか。
- 頰筋
- 咬筋
- 口輪筋
- 胸鎖乳突筋
▶午後28
体温のセットポイントが突然高く設定されたときに起こるのはどれか。
- 立毛
- 発汗
- 代謝抑制
- 皮膚血管拡張
▶午後29
二次性高血圧症の原因となるホルモンはどれか。
- アルドステロン
- ソマトスタチン
- グルカゴン
- メラトニン
▶午後30
成人の急性扁桃炎の原因となる菌はどれか。
- 百日咳菌〈Bordetella pertussis〉
- 黄色ブドウ球菌〈Staphylococcus aureus〉
- インフルエンザ菌〈Haemophilus influenzae〉
- ヘリコバクター・ピロリ〈Helicobacter pylori〉
▶午後31
急性骨髄性白血病の検査所見で正しいのはどれか。
- 赤血球数が増加する。
- 血小板数が増加する。
- 白血球分画に白血病裂孔を認める。
- ミエロペルオキシダーゼ反応陽性が3%未満である。
▶午後32
Ménière〈メニエール〉病で正しいのはどれか。
- 伝音性難聴を伴う。
- めまいは回転性である。
- 発作期に外科治療を行う。
- 蝸牛の機能は保たれている。
▶午後33
成人の急性腎盂腎炎で正しいのはどれか。
- 男性に多い。
- 両腎性が多い。
- 初尿を用いて細菌培養を行う。
- 原因菌はGram〈グラム〉陰性桿菌が多い。
国民健康保険で正しいのはどれか。
- 被用者保険である。
- 保険者は国である。
- 高額療養費制度がある。
- 保険料は加入者の年齢で算出する。
高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
- 有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 高齢者生活福祉センター
- サービス付き高齢者向け住宅
母子保健統計の算出方法で出生数を分母としているのはどれか。
- 妊娠満22週以後の死産率
- 周産期死亡率
- 乳児死亡率
- 死産率
健康増進法に基づき実施されるのはどれか。
- 受療行動調査
- 特定保健指導
- アレルギー疾患対策
- 受動喫煙の防止対策
判断能力のある成人患者へのインフォームド・コンセントにおける看護師の対応で適切なのはどれか。
- 患者の疑問には専門用語を用いて回答する。
- 今後の治療に関しては医療者に任せるように話す。
- 治療方針への同意は撤回できないことを説明する。
- 納得ができるまで医師からの説明が受けられることを伝える。
▶午後39
看護過程における情報の分析はどれか。
- 脱水状態である。
- 尿比重は1.030である。
- 痛みは1〜10の尺度で8である。
- 左腓骨骨折によるシーネ固定をしている。
▶午後40
第2〜第4腰髄の障害を確認する方法で適切なのはどれか。
- 輻輳反射
- 膝蓋腱反射
- Barré〈バレー〉徴候
- Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候
▶午後41
成人のセルフケア行動に関する学習を促進するのはどれか。
- 自己効力感
- パターナリズム
- プレパレーション
- ノンコンプライアンス
▶午後42
成人女性に膀胱留置カテーテルを挿入する方法で適切なのはどれか。
- 水溶性の滅菌潤滑剤を用いる。
- カテーテルは外尿道口から15cm挿入する。
- 固定用バルーンを膨らませた後、尿の流出を確認する。
- 固定用バルーンにはクロルヘキシジングルコン酸塩液を注入する。
▶午後43
中心静脈栄養法〈TPN〉で高カロリー輸液を用いる際に、起こりやすい合併症はどれか。
- 高血圧
- 高血糖
- 末梢静脈炎
- 正中神経麻痺
▶午後44
成人に自動体外式除細動器〈AED〉を使用する際の電極パッドの貼付で正しいのはどれか。
- 小児用電極パッドが代用できる。
- 右前胸部に縦に並べて貼付する。
- 貼付部の発汗は貼付前に拭き取る。
- 経皮吸収型テープ剤の上に貼付する。
▶午後45
Braden〈ブレーデン〉スケールの評価項目で正しいのはどれか。
- 湿潤
- 循環
- 体圧
- 年齢
医療施設において、患者の入院から退院までの看護を1人の看護師が継続して責任をもつことを重視した看護体制はどれか。
- 機能別看護方式
- 患者受け持ち方式
- チームナーシングシステム
- プライマリナーシングシステム
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査における成人の生活習慣の特徴で正しいのはどれか。
- 朝食の欠食率は40歳代が最も多い。
- 運動習慣のある人の割合は30歳代が最も多い。
- 1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多い。
- 習慣的に喫煙している人の割合は10年前に比べて増加している。
▶午後48
慢性疾患をもつ成人の自己管理を促進する援助はどれか。
- 行動の習慣化を促す。
- 医療者が患者の目標を設定する。
- 結果を優先して評価することを促す。
- うまくいかない行動に目を向けるよう促す。
▶午後49
気管支鏡検査を受ける成人患者への援助で正しいのはどれか。
- 検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認する。
- 検査の1時間前から飲食しないように指導する。
- 検査中の咳は我慢しなくてよいと指導する。
- 検査後は肺気腫の症状に注意する。
ラテックス製手袋を着用した直後に口唇・手足のしびれと喉頭の違和感を自覚した。
原因となる病態はどれか。
- Ⅰ型アレルギー
- Ⅱ型アレルギー
- Ⅲ型アレルギー
- Ⅳ型アレルギー
▶午後51
Aさん(59歳、女性)は裂孔原性網膜剝離と診断され、硝子体手術の際に硝子体腔中にガス注入を受けた。
手術直後、病室での体位で適切なのはどれか。
- 坐位
- 腹臥位
- 仰臥位
- 側臥位
▶午後52
散瞳薬を用いて眼底検査を受ける成人患者への対応で適切なのはどれか。
- 検査中は室内を明るくする。
- 散瞳薬の点眼は検査直前に行う。
- 検査前に緑内障の有無を確認する。
- 検査後1時間で自動車の運転が可能になると説明する。
▶午後53
関節リウマチで長期にわたりメトトレキサートを服用している患者の副作用〈有害事象〉で適切なのはどれか。
- 便秘
- 不整脈
- 聴力障害
- 間質性肺炎
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、「同居の家族」が占める割合に最も近いのはどれか。
- 6%
- 26%
- 46%
- 66%
▶午後55
老化によって減少または低下するのはどれか。
- 重心の動揺
- 糸球体の数
- 嗅覚の閾値
- 前立腺の重量
高齢者に対するエイジズムの説明で適切なのはどれか。
- 年齢にとらわれないこと
- 加齢に伴う心身機能の変化
- 高齢という理由で不当な扱いをすること
- 老化に関連した遺伝子によって引き起こされる現象
▶午後57
Aさん(90歳、女性)は、認知症で要介護3。デイサービスの送迎の際に、同居している娘から「食事は家族と同じものを食べていたのですが、昨日から下痢が続いています。発熱はなく、元気はあります」と看護師に話があった。デイサービスでは午前中に不消化便が1回あり、おむつ交換の際に、肛門周囲の発赤がみられた。
Aさんへの対応で適切なのはどれか。
- 腹部マッサージを行う。
- 経口補水液の摂取を促す。
- 食物繊維を多く含む食事にする。
- 石けんを使って肛門周囲を洗う。
▶午後58
乳児の安静時におけるバイタルサインで基準値から逸脱しているのはどれか。
- 体温37.0℃
- 呼吸数35/分
- 心拍数60/分
- 血圧88/60mmHg
令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待で正しいのはどれか。
- 主たる虐待者は実父が最も多い。
- 性的虐待件数は身体的虐待件数より多い。
- 児童虐待相談件数は5年間横ばいである。
- 心理的虐待件数は5年前に比べて増加している。
▶午後60
Aちゃん(5歳、女児)は、インフルエンザ脳症の終末期である。Aちゃんに意識はなく、付き添っている母親は「私がもっと早く病院に連れて来ればこんなことにならなかったのに」と病室で泣いている。
Aちゃんの母親への対応で適切なのはどれか。
- 母親に受診が遅くなった状況を聞く。
- 母親がAちゃんに対してできるケアを提案する。
- 病気で亡くなった子どもの親の会を母親に紹介する。
- 母親が泣いている間はAちゃんの病室に居ることができないと母親に説明する。
令和5年(2023年)の人口動態統計における日本の出生で正しいのはどれか。
- 出生数は過去10年で最低である。
- 出生数は80万人を上回っている。
- 合計特殊出生率は1.10を下回っている。
- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳未満である。
▶午後62
エストロゲン低下によって更年期の女性に起こるのはどれか。
- 骨量の低下
- 内臓脂肪の減少
- 脳血流量の増加
- HDLコレステロールの上昇
▶午後63
順調に分娩が進行している産婦から「腟から水っぽいものが流れ、下着が濡れた」と看護師に訴えがあった。流出したものを確認すると、量は少量で、羊水特有の臭いを認めた。
その時の産婦への対応で優先されるのはどれか。
- 更衣を促す。
- 体温を測定する。
- 食事摂取を勧める。
- 胎児心拍数を確認する。
▶午後64
新生児の反応の図を示す。
Moro〈モロー〉反射はどれか。
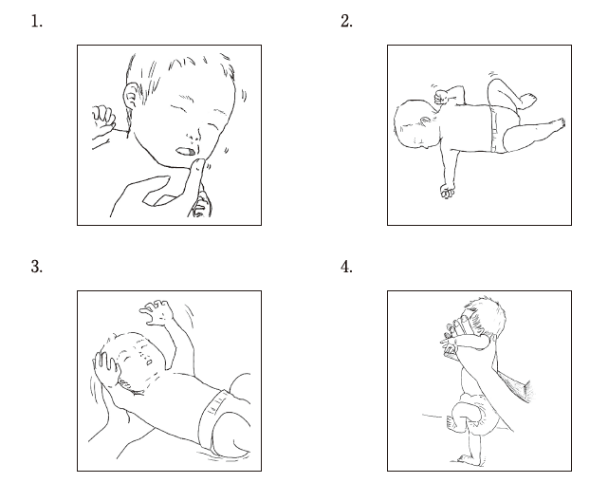
▶午後65
飲酒したい欲求を抑圧した人が、酩酊状態の人の行動を必要以上に非難する防衛機制はどれか。
- 昇華
- 転換
- 合理化
- 反動形成
▶午後66
アギュララ, D. C.が提唱した危機〈クライシス〉を回避する要因で正しいのはどれか。
- 情緒的サポート
- 適切な対処機制
- 問題志向のコーピング
- ソーシャルインクルージョン
精神障害の三次予防の内容で適切なのはどれか。
- うつ病患者の復職支援
- 住民同士のつながりの強化
- 精神保健に関する問題の早期発見
- ストレス関連障害の発症予防に関する知識の提供
▶午後68
成人期早期に、見捨てられることに対する激しい不安、物質乱用や過食などの衝動性、反復する自傷行為、慢性的な空虚感、不適切で激しい怒りがみられ、社会的、職業的に不適応を生じるのはどれか。
- 回避性人格〈パーソナリティ〉障害
- 境界性人格〈パーソナリティ〉障害
- 妄想性人格〈パーソナリティ〉障害
- 反社会性人格〈パーソナリティ〉障害
医療保護入院で正しいのはどれか。
- 入院の期間は72時間に限られる。
- 患者の家族等の同意で入院させることができる。
- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
▶午後70
Aさん(55歳、男性)は、妻と2人暮らし。建築士として主にデスクワークの仕事を行っていた。脊髄損傷のため下半身の不完全麻痺となり、リハビリテーション専門の病院へ転院した。電動車椅子を用いて室内の動作は自立できるようになった。退院調整部門の看護師との面接でAさんから「元の職場に戻りたい」と話があった。
Aさんの自己決定を支援する看護師の助言で適切なのはどれか。
- 「元の職場の仕事を在宅勤務に変更しましょう」
- 「デスクワークなので職場復帰は可能と思います」
- 「職場復帰にあたりAさんが課題と思うことを整理しましょう」
- 「元の職場にこだわらずAさんの障害にあった職場を探しましょう」
訪問看護事業所で正しいのはどれか。
- 24時間対応が義務付けられている。
- 自宅以外への訪問看護は認められない。
- 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。
- 従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。
▶午後72
Aさん(78歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。脳梗塞の既往がある。妻から「最近、夫は食事をむせずに食べることができるが、口の中に食べ物が残っていることが多い。夫の食事について助言が欲しい」と訪問看護師に相談があった。
妻への訪問看護師の助言で適切なのはどれか。
- 「食事にとろみをつけましょう」
- 「自助具を使って食事をしましょう」
- 「口に入れる1回量を少なくしましょう」
- 「食事前に舌の動きを促す運動をしましょう」
▶午後73
皮下埋込みポートを用いた在宅中心静脈栄養法〈HPN〉で適切なのはどれか。
- 抜針して入浴することができる。
- 24時間持続する注入には適さない。
- 同居の家族がいることが必須条件である。
- 外出時に輸液ポンプを使うことはできない。
▶午後74
与薬の事故防止に取り組んでいる病院の医療安全管理者が行う対策で適切なのはどれか。
- 与薬の業務プロセスを見直す。
- 医師に口頭での与薬指示を依頼する。
- 病棟ごとに与薬マニュアルを作成する。
- インシデントを起こした職員の研修会を企画する。
▶午後75
Aさん(55歳、女性)は、1人暮らし。Aさんには視覚障害があり、光と輪郭がぼんやりわかる程度である。食事の準備や室内の移動は自立している。震度6の地震が発生した。Aさんは、避難所に指定されたバリアフリーの公民館に近所のBさんと避難した。公民館には複数の部屋がある。避難所の開設初日に医療救護班として看護師が派遣された。
避難所生活を開始するAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。
- BさんをAさんの介助者とする。
- Aさんの肩に触れてから声をかける。
- Aさんにはトイレに近い部屋を割りあてる。
- 移動するときはAさんの手を引っ張って誘導する。
▶午後76
朝9時に大規模地震が発生した。病棟の患者と職員の安全は確認できた。病棟内の壁や天井に破損はなかったが、病院は、停電によって自家発電装置が作動した。
病棟の看護師長が行う対応で適切なのはどれか。
- 災害対策本部を設置する。
- 災害時マニュアルを整備する。
- 隣接する病棟に支援を要請する。
- スタッフに避難経路の安全確認を指示する。
Aさん(28歳、男性)。海外出張で訪れたアフリカ地域から帰国後1週に39℃の発熱と解熱を繰り返すため外来を受診した。腹部症状は特にない。
予測される感染症はどれか。
- マラリア
- コレラ
- 赤痢
- 破傷風
看護師の特定行為で正しいのはどれか。
- 診療の補助である。
- 医師法に基づいている。
- 手順書は看護師が作成する。
- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。
▶午後79
( )の組織を還流した血液は心臓に戻る前に肝臓を通過する。
( )に入るのはどれか。
- 舌
- 食道
- 小腸
- 腎臓
- 下肢
▶午後80
「安静時呼吸」、「深呼吸」、「徐々に深くなっていく呼吸」に伴う肺容量の変化を図に示す。
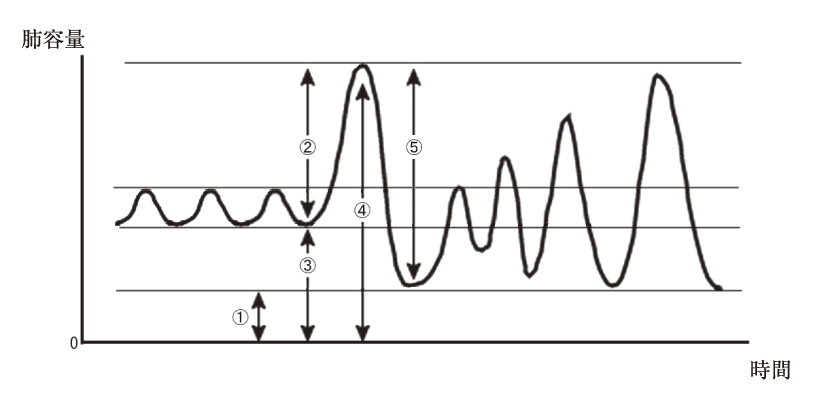
肺活量を示すのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
▶午後81
健常な成人において、血液中のグルコース濃度が低下した時に、グルカゴンの働きでグリコゲンを分解してグルコースを生成し、血液中に放出するのはどれか。
- 肝臓
- 骨格筋
- 脂肪組織
- 心臓
- 膵臓
▶午後82
関節運動はないが筋収縮が認められる場合、徒手筋力テストの結果は( )/5と表記する。
( )に入るのはどれか。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
▶午後83
加齢黄斑変性の症状はどれか。
- 羞明
- 霧視
- 飛蚊症
- 眼圧の亢進
- 中心視野の欠損
▶午後84
高齢者が共同生活をする施設で、感染の拡大予防のために個室への転室などの対応を必要とするのはどれか。
- 白癬
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 角化型疥癬
- 皮膚カンジダ症
▶午後85
3歳児の排泄行動の発達に該当するのはどれか。
- 夜尿をしなくなる。
- 尿意を自覚し始める。
- 排便後の後始末ができる。
- トイレに行くまで排尿を我慢できる。
- 遊びに夢中になっても排尿の失敗がなくなる。
▶午後86
全身性エリテマトーデス〈SLE〉で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 遺伝素因の関与が大きい。
- 発症には男性ホルモンが関与する。
- 中枢神経症状は生命予後に影響する。
- Ⅰ型アレルギーによる免疫異常である。
- 適切に治療しても5年生存率は50%である。
▶午後87
大量の輸液が必要と考えられる救急患者はどれか。2つ選べ。
- 前額部の切創で出血している。
- オートバイ事故で両大腿が変形している。
- プールの飛び込み事故で四肢が動かない。
- デスクワーク中に胸が苦しいと言って倒れている。
- 火事で顔面、胸腹部、背部および両上肢にⅡ度の熱傷を負っている。
▶午後88
胃食道逆流症で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 青年期に多い。
- 高脂肪食の摂取を勧める。
- 食後は左側臥位で休息する。
- 下部食道括約筋の弛緩が関与する。
- H2受容体拮抗薬によって自覚症状が緩和する。
健やか親子21(第2次)の基盤課題Bのうち、学童期・思春期の課題の指標となっているのはどれか。2つ選べ。
- 十代の喫煙率
- 十代の自殺死亡率
- 十代の定期予防接種の接種率
- 児童・生徒における不登校の割合
- 児童・生徒におけるむし歯(う歯)の割合
▶午後90
1,500mLの輸液を朝9時からその日の17時にかけて点滴静脈内注射で実施する。
20滴で1mLの輸液セットを用いた場合の1分間の滴下数を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②滴/分
資料 厚生労働省「第106回保健師国家試験、第103回助産師国家試験、第109回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第109回看護師国家試験
令和2年2月16日(日)に実施された第109回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第109回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
▶午前11(必修除外)
健康な成人の1回換気量はどれか。
- 約150mL
- 約350mL
- 約500mL
- 約1,000mL
▶午前26
固有心筋の特徴はどれか。
- 平滑筋である。
- 骨格筋よりも不応期が短い。
- 活動電位にプラトー相がみられる。
- 筋層は右心室の方が左心室より厚い。
▶午前27
小細胞癌で正しいのはどれか。
- 患者数は非小細胞癌より多い。
- 肺末梢側に発生しやすい。
- 悪性度の低い癌である。
- 治療は化学療法を行う。
▶午前28
脳梗塞を最も早期に検出できる画像検査はどれか。
- シンチグラフィ
- 磁気共鳴画像〈MRI〉
- 磁気共鳴血管画像〈MRA〉
- コンピュータ断層撮影〈CT〉
公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。
- 未熟児の養育医療――医療法
- 結核児童の療養給付――児童福祉法
- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
廃棄する物とその区分との組合せで正しいのはどれか。
- 滅菌パックの袋――産業廃棄物
- エックス線フィルム――一般廃棄物
- 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物
- pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物
▶午前31
患者と看護師の間の専門的な援助関係で適切なのはどれか。
- 自然発生的に成立する。
- 援助方法は看護師に一任される。
- 患者のニーズに焦点がおかれる。
- 日常的な会話を中心に展開する。
▶午前32
細菌の芽胞を死滅させるのはどれか。
- 紫外線
- ポビドンヨード
- 70%アルコール
- 酸化エチレンガス
▶午前33
クロストリジウム・ディフィシレ(ディフィシル)による下痢を発症している患者の陰部洗浄をベッド上で行う際の個人防護具を着用した看護師の写真を別に示す。

適切なのはどれか。
- A
- B
- C
- D
インシデントレポートで適切なのはどれか。
- 責任追及のためには使用されない。
- インシデントの発生から1か月後に提出する。
- 主な記述内容はインシデントの再発防止策である。
- 実施前に発見されたインシデントの報告は不要である。
▶午前35
成人の睡眠で正しいのはどれか。
- レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。
- 入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。
- ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。
- 睡眠周期は90分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。
▶午前36
片麻痺のある成人の臥床患者の患側の良肢位で適切なのはどれか。
- 肩関節は内転10度
- 肘関節は屈曲10度
- 股関節は外転10度
- 足関節は背屈10度
▶午前37
クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する方法で適切なのはどれか。
- 同じ指で24時間連続で測定する。
- マニキュアをしたままで測定する。
- 装着部位に冷感がある場合は温める。
- 指を挟んだプローブはテープで固定する。
▶午前38
熱型を図に示す。
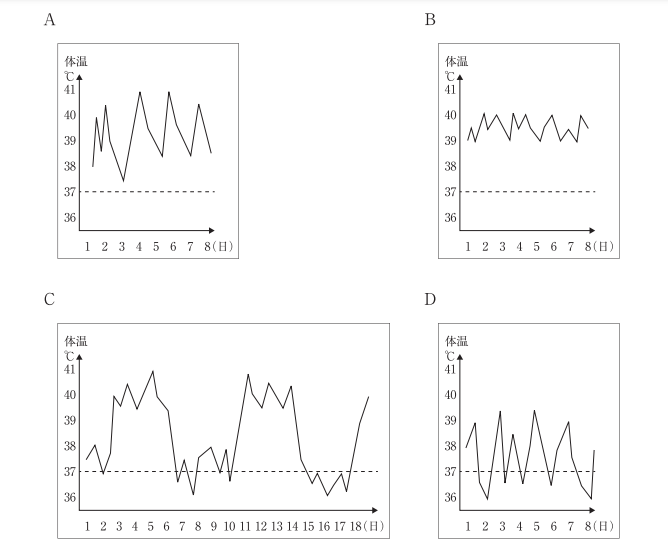
熱型の種類と図の組合せで正しいのはどれか。
- 間欠熱――A
- 稽留熱――B
- 弛張熱――C
- 波状熱――D
▶午前39
薬の内服方法における頓用で正しいのはどれか。
- 週に1回服用する。
- 食事の前に服用する。
- 指定された時間に服用する。
- 症状が現れたときに服用する。
▶午前40
壮年期の身体的特徴で正しいのはどれか。
- 運動耐久力の向上
- 明暗順応の低下
- 持久力の向上
- 臓器の萎縮
▶午前41
急性期患者の生体反応で正しいのはどれか。
- 異化が亢進する。
- 症状の変化は緩やかである。
- サイトカイン分泌が低下する。
- 副腎皮質ホルモンの分泌が低下する。
▶午前42
砕石位による手術で起こりやすい合併症はどれか。
- 猿手
- 尖足
- 下垂手
- 腸骨部の褥瘡
▶午前43
ペースメーカー植込みの有無を事前に確認すべき検査はどれか。
- 超音波検査
- エックス線撮影
- 骨シンチグラフィ
- 磁気共鳴画像〈MRI〉
▶午前44
肝動脈塞栓術〈TAE〉の適応となる疾患はどれか。
- 脂肪肝
- 急性A型肝炎
- 肝細胞癌〈HCC〉
- アメーバ性肝膿瘍
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染している患者で、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の状態にあると判断できる疾患はどれか。
- 季節性インフルエンザ
- ニューモシスチス肺炎
- ノロウイルス性腸炎
- 単純性膀胱炎
細菌性髄膜炎の症状はどれか。
- 羞明
- 羽ばたき振戦
- Raynaud〈レイノー〉現象
- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候
▶午前47
貧血を伴う患者の爪の写真を別に示す。
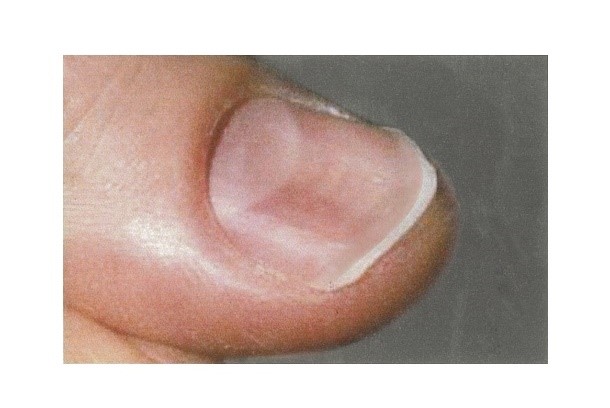
欠乏している栄養素はどれか。
- ビタミンB12
- ビタミンC
- 葉酸
- 鉄
▶午前48
手術後に無排卵になるのはどれか。
- 脳下垂体全摘出術
- 単純子宮摘出術
- 低位前方切除術
- 片側卵巣切除術
▶午前49
被験者が図形を描き写す内容が含まれる認知機能の評価はどれか。
- 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
- Mini-Mental State Examination〈MMSE〉
- 高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA〉
- 改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉
▶午前50
老化による免疫機能の変化はどれか。
- 胸腺の肥大
- T細胞の増加
- 獲得免疫の反応の低下
- 炎症性サイトカインの産生の減少
▶午前51
高齢者の性について正しいのはどれか。
- 女性の性交痛は起こりにくくなる。
- 男性は性ホルモンの分泌量が保たれる。
- 高齢になると異性に対する羞恥心は減退する。
- セクシュアリティの尊重はQOLの維持に影響する。
▶午前52
老化による身体機能の変化と薬物動態への影響との組合せで正しいのはどれか。
- 血中蛋白の低下――薬効の減少
- 腎血流量の低下――薬効の減少
- 肝血流量の低下――薬効の増大
- 消化機能の低下――薬効の増大
▶午前53改題
軽度認知障害で正しいのはどれか。
- 一過性の障害である。
- 認知症である。
- 物忘れを自覚している。
- 日常生活動作〈ADL〉が障害される。
認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、複数の専門職でアセスメントや自立生活の支援を行うのはどれか。
- 成年後見人
- 介護認定審査会
- 認知症対応型通所介護
- 認知症初期集中支援チーム
▶午前55
日本で用いているDENVERⅡ(デンバー発達判定法)で6か月児の90%ができるのはどれか。
- 寝返りをする。
- 積み木をもちかえる。
- 喃語様のおしゃべりをする。
- 自分で食べ物を口へもっていく。
幼児を対象とする定期予防接種はどれか。
- DTワクチン(二種混合)
- ロタウイルスワクチン
- BCGワクチン
- 水痘ワクチン
▶午前57
大泉門の説明で正しいのはどれか。
- 2歳まで増大する。
- 陥没している場合は髄膜炎を疑う。
- 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。
- 頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。
幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。
- 胸骨中央下部を圧迫する。
- 実施者の示指と中指とで行う。
- 1分間に60回を目安に行う。
- 1回の人工呼吸につき3回行う。
▶午前59
配偶子の形成で正しいのはどれか。
- 卵子の形成では減数分裂が起こる。
- 精子の形成では極体の放出が起こる。
- 成熟卵子はXまたはY染色体をもつ。
- 精子は23本の常染色体と1本の性染色体をもつ。
▶午前60
女子の思春期の特徴で正しいのはどれか。
- 9歳で初経が発来する。
- 月経開始後に身長の発育が加速する。
- 陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。
- 性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。
▶午前61
妊娠37週の妊婦の胎児心拍数陣痛図の所見で正常なのはどれか。
- 胎児心拍数基線が110〜160bpmである。
- 胎児心拍数基線細変動を認めない。
- 一過性頻脈を認めない。
- 一過性徐脈を認める。
▶午前62
子宮復古状態を観察する手順で正しいのはどれか。
- 観察は排尿前に行う。
- 褥婦にはFowler〈ファウラー〉位をとってもらう。
- 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。
- 子宮底長は恥骨結合下縁から測定する。
正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。
- 4週後
- 3週後
- 2週後
- 1週後
災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉で正しいのはどれか。
- 厚生労働省が組織する。
- 被災地域の精神科医療機関と連携する。
- 発災1か月後に最初のチームを派遣する。
- 派遣チームの食事は被災自治体が用意する。
平成16年(2004年)に示された精神保健医療福祉の改革ビジョンの内容で正しいのはどれか。
- 地域生活支援の強化
- 任意入院制度の新設
- 医療保護入院の明確化
- 精神障害者の定義の見直し
▶午前66
Aさん(25歳、男性)は、統合失調症と診断された。抗精神病薬の内服を開始した2日後、Aさんはそわそわして落ち着かず「足がムズムズする」と歩き回るようになった。
Aさんにみられている状態はどれか。
- アカシジア
- ジストニア
- ジスキネジア
- ミオクローヌス
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。
- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。
- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。
- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。
- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。
▶午前68
Aさん(82歳、女性)は、要支援2である。
Aさんの屋内での転倒予防と自立の促進のため、自宅で介護する家族への指導で適切なのはどれか。
- 車椅子での移動とする。
- 移動時にスリッパを使用する。
- 手すりがない場所での歩行を避ける。
- 移動の前に立ちくらみの有無を確認する。
Aさん(68歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。
Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。
- 医療保険から給付される。
- 特別訪問看護指示書を受けて実施される。
- 複数の訪問看護事業所の利用はできない。
- 理学療法士による訪問は給付が認められない。
▶午前70
Aさん(85歳、女性)は、要支援1で介護予防通所リハビリテーションを月2回利用している。Aさんから「最近排便が3〜4日に1回しかなくて、お腹が張って困っている」と通所施設の看護師に相談があった。
看護師が行うAさんへの便秘に対する助言で適切なのはどれか。
- 毎日、朝食後に便座に座る。
- 就寝前に水を500mL飲む。
- 1日1万歩を目標に歩く。
- 蛋白質を多めに摂る。
▶午前71
Aさん(88歳、男性)は、長女(60歳、無職)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準ランクC2。仙骨部の褥瘡の治療のため、膀胱留置カテーテルを挿入することになった。
膀胱留置カテーテルを挿入中のAさんを介護する長女に対して、訪問看護師が指導する内容で適切なのはどれか。
- 「褥瘡が治癒するまでおしりは洗浄しないでください」
- 「体位変換ごとに蓄尿バッグを空にしてください」
- 「カテーテルは太ももに固定してください」
- 「尿に浮遊物がないか確認してください」
令和3年(2021年)の介護サービス施設・事業所調査における要介護度別利用者数の構成割合で、要介護5の利用者が最も多いのはどれか。
- 訪問介護
- 訪問看護ステーション
- 居宅介護支援
- 訪問入浴介護
医療法における医療計画で正しいのはどれか。
- 国が策定する。
- 在宅医療が含まれる。
- 3年ごとに見直される。
- 病床の整備は含まれない。
災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。
- 物資の備蓄
- 避難所の設置
- 災害障害見舞金の支給
- 救護班による医療の提供
2021年の経済協力開発機構〈OECD〉の報告書(2019年数値)の日本に関する記述で正しいのはどれか。
- 喫煙率が最も低い。
- 高齢化率が最も高い。
- 人口千人当たりの病床数が最も少ない。
- 国内総生産〈GDP〉に対する医療費の割合が最も高い。
▶午前76
眼球に入る光の量を調節するのはどれか。
- 角膜
- 虹彩
- 瞳孔
- 水晶体
- 毛様体
▶午前77
最終代謝産物に尿酸が含まれるのはどれか。
- 核酸
- リン脂質
- 中性脂肪
- グルコース
- コレステロール
▶午前78
排尿時に収縮するのはどれか。
- 尿管
- 尿道
- 膀胱平滑筋
- 内尿道括約筋
- 外尿道括約筋
▶午前79
重症筋無力症で正しいのはどれか。
- 男性に多い。
- 心肥大を生じる。
- 朝に症状が強くなる。
- 自己免疫疾患である。
- 70歳以上に好発する。
▶午前80
成人の気管内吸引の方法で適切なのはどれか。
- 実施前に咽頭部の分泌物を吸引する。
- 吸引圧は-40kPa(300mmHg)に調整する。
- 気管チューブと同じ内径のカテーテルを用いる。
- カテーテルの挿入開始から終了まで30秒で行う。
- カテーテルは気管分岐部より深い位置まで挿入する。
▶午前81
交感神経の作用はどれか。2つ選べ。
- 散瞳
- 精神性発汗
- 腸蠕動の促進
- 排尿筋の収縮
- グリコーゲン合成の促進
▶午前82
気管で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 軟骨は筒状である。
- 胸骨角の高さで分岐する。
- 交感神経の働きで収縮する。
- 吸息相の気管内圧は陰圧である。
- 頸部では食道の背側に位置する。
▶午前83
食道癌で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 女性に多い。
- 日本では腺癌が多い。
- 放射線感受性は低い。
- 飲酒は危険因子である。
- 胸部中部食道に好発する。
▶午前84
急性膵炎で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 成因はアルコール性より胆石性が多い。
- 重症度判定には造影CTが重要である。
- 血中アミラーゼ値が低下する。
- 鎮痛薬の投与は禁忌である。
- 初発症状は上腹部痛である。
▶午前85改題
もやもや病で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 指定難病ではない。
- 遺伝的要因は関与しない。
- 病変はくも膜下腔にある。
- 進行性の脳血管閉塞症である。
- ウイルス感染によって誘発される。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。
- 子育て世代包括支援センター
- 地域包括ケアシステム
- 子どもの医療費の助成
- 地域生活支援事業
- 地域医療構想
アルコール依存症の一次予防はどれか。2つ選べ。
- 年齢確認による入手経路の制限
- スクリーニングテストの実施
- 精神科デイケアへの参加
- 小学生への健康教育
- 患者会への参加
医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 保健所
- 特定機能病院
- 地方衛生研究所
- 市町村保健センター
- 医療安全支援センター
▶午前89
終末期がん患者にみられる悪液質の徴候はどれか。2つ選べ。
- 末梢神経障害
- リンパ浮腫
- がん疼痛
- 食欲不振
- 体重減少
世界保健機関〈WHO〉の主要な活動はどれか。2つ選べ。
- 児童労働の撲滅
- 保健事業の技術的協力
- 人類の飢餓からの解放
- 感染症の撲滅事業の促進
- 労働者の労働条件の改善
資料 厚生労働省「第106回保健師国家試験、第103回助産師国家試験、第109回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第109回看護師国家試験
平成31年2月17日(日)に実施された第108回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第108回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後26
嗅覚の一次中枢はどれか。
- 嗅球
- 嗅上皮
- 後頭葉
- 上鼻甲介
▶午後27
標的細胞の細胞膜に受容体があるのはどれか。
- 男性ホルモン
- 甲状腺ホルモン
- 糖質コルチコイド
- 甲状腺刺激ホルモン
▶午後28
開心術後の心タンポナーデで正しいのはどれか。
- 徐脈
- 心音増強
- 心拍出量の増加
- 中心静脈圧の上昇
介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。
- 介護保険料は全国同額である。
- 介護保険被保険者証が交付される。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 介護保険給付の利用者負担は一律3割である。
発達障害者支援法で発達障害と定義されているのはどれか。
- 学習障害
- 記憶障害
- 適応障害
- 摂食障害
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
- 自殺総合対策推進センターの設置
- 自殺総合対策大綱の策定
- ゲートキーパーの養成
- 自殺対策計画の策定
▶午後32
ハヴィガースト, R. J.の発達課題に関する説明で適切なのはどれか。
- 成長に伴い発達課題は消失する。
- 各発達段階の発達課題は独立している。
- 身体面の変化と発達課題は無関係である。
- 発達課題の達成は個人の生活と関連する。
風疹の疑いがある入院患者の隔離予防策で適切なのはどれか。
- 標準予防策
- 標準予防策と接触感染予防策
- 標準予防策と飛沫感染予防策
- 標準予防策と空気感染予防策
▶午後34
死後の処置で適切なのはどれか。
- 枕は氷枕にする。
- 義歯を装着する。
- 肛門には青梅綿、脱脂綿の順で詰める。
- 和装の更衣の場合、襟は右前に合わせる。
▶午後35
嚥下障害を評価する改訂水飲みテストで正しいのはどれか。
- 嚥下後10秒間で評価する。
- 嚥下動作の準備期を評価する。
- 嚥下後の呼吸状態を評価する。
- 80mLの水の嚥下状況を評価する。
▶午後36
入浴時に全身の血液循環を促進する作用はどれか。
- 鎮静作用
- 浮力作用
- 抗酸化作用
- 静水圧作用
▶午後37
1回換気量に関係なく吸入酸素濃度を調節できる器具はどれか。
- 鼻カニューレ
- フェイスマスク
- ベンチュリーマスク
- リザーバー付酸素マスク
▶午後38
成人患者への薬剤の投与方法で正しいのはどれか。
- 筋肉内注射は大殿筋に行う。
- 点眼薬は結膜囊に滴下する。
- 皮下注射は前腕内側に行う。
- 食間の指示の経口薬は食事中に服用させる。
▶午後39
永久的止血法に含まれるのはどれか。
- 止血帯法
- タンポン法
- 血管結紮法
- 間接圧迫止血法
▶午後40
成人に行う頭部MRI検査で正しいのはどれか。
- 造影を伴わない場合は検査直前まで飲食してよい。
- 使い捨てカイロは装着したままでよい。
- 検査中は手足を自由に動かしてよい。
- 補聴器は装着したままでよい。
▶午後41
Aさん(48歳、男性)は、仕事中に生じた胸部と右肩の違和感を主訴に来院した。バイタルサインは安定しているが、スタンフォード分類B型の急性大動脈解離と診断され、医師から手術を勧められた。
治療の選択で迷っている様子のAさんへの対応で適切なのはどれか。
- 「医師からの治療のリスクや合併症の説明で、不明な点はありますか」
- 「手術を受けるか受けないか、すぐに決めたほうがよいです」
- 「医師の判断に任せるのが一番よいと思います」
- 「緊急度が高いので、話はあとにしましょう」
▶午後42
Aさん(64歳、男性)は、2年前に前立腺癌と診断され、内分泌療法を受けていた。1か月前から体動時に強い痛みが腰部に生じるようになり、外来を受診したところ腰椎転移と診断された。
Aさんに生じている痛みで最も考えられるのはどれか。
- 関連痛
- 体性痛
- 中枢痛
- 内臓痛
▶午後43
成人患者の気管支喘息の治療で正しいのはどれか。
- テオフィリンの投与中は血中濃度の測定が必要である。
- 副腎皮質ステロイド薬吸入後の含嗽は必要ない。
- インフルエンザワクチン接種は禁忌である。
- 発作時にはβ遮断薬を内服する。
▶午後44
経皮的腎生検を受ける患者への説明で適切なのはどれか。
- 検査中の体位は仰臥位とする。
- 穿刺時にくり返し深呼吸をする。
- 検査後はベッド上安静とする。
- 検査後2日間は禁食にする。
▶午後45
糖質コルチコイドの分泌が長期に過剰となった状態の身体所見で正しいのはどれか。
- 眼球突出
- 甲状腺腫大
- 頻脈
- 満月様顔貌
▶午後46
慢性副鼻腔炎の手術を受けた患者に対する説明で適切なのはどれか。
- 咽頭にたまった分泌物は飲んでも良い。
- 臥床時は頭部を低く保つ。
- 手術当日から入浴が可能である。
- 物が二重に見えるときは看護師に伝える。
▶午後47
サクセスフルエイジングの説明で適切なのはどれか。
- 老化の過程にうまく適応する。
- 権威のある者によって一方的に守られる。
- 生命あるものに共通して起こる現象である。
- 社会的な役割から離脱することで自由になる。
判断能力が不十分な認知症高齢者の権利擁護を目的とするのはどれか。
- 公的年金制度
- 生活保護制度
- 後期高齢者医療制度
- 日常生活自立支援事業
▶午後49
Aさん(76歳、女性)は、ステージ2の慢性腎臓病と診断された。身長146cm、体重50kg。日常生活は自立し、毎日家事をしている。週2回、ビールをグラス1杯程度飲んでいる。
Aさんへの生活指導の内容で優先されるのはどれか。
- 安静
- 禁酒
- 減塩
- 体重の減量
▶午後50
認知症高齢者との対話で適切なのはどれか。
- 表情を見せながら話す。
- 高齢者の横から話しかける。
- 会話の内容を記憶しているか確認する。
- 言葉が出てこない時は思い出すまで待ち続ける。
介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 通所リハビリテーション
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
令和4年(2022年)の人口動態調査で、5~9歳の死因における不慮の事故の原因で最も多いのはどれか。
- 窒息
- 交通事故
- 転倒・転落
- 溺死および溺水
小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。
- 対象は5疾患群である。
- 対象年齢は20歳未満である。
- 医療費の自己負担分の一部を助成する。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。
▶午後54
乳幼児の正常な言語発達で正しいのはどれか。
- 生後1か月で喃語が出始める。
- 生後6か月で意味のある1語が言える。
- 1歳2か月で2語文を話す。
- 4歳で4つの色を正しく言える。
▶午後55
離乳の開始で正しいのはどれか。
- 離乳食は1日2回から開始する。
- 人工乳はフォローアップミルクにする。
- 哺乳反射の減弱が開始時の目安のひとつである。
- 離乳食は歯ぐきでつぶせる硬さのものから始める。
▶午後56
障害のレベルを運動機能と知能指数で区分するのはどれか。
- 大島分類
- NYHA分類
- 国際生活機能分類〈ICF〉
- Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類
▶午後57
人間の性の意義と特質の組合せで適切なのはどれか。
- 快楽性としての性――種の保存
- 生殖性としての性――心理・社会的属性
- 性役割としての性――性的指向
- 連帯性としての性――人間関係の形成
▶午後58
出生前診断を目的とした羊水検査で適切なのはどれか。
- 先天性疾患のほとんどを診断することができる。
- 診断された染色体異常は治療が可能である。
- 合併症として流早産のリスクがある。
- 妊娠22週以降は検査できない。
新生児聴覚スクリーニング検査で正しいのはどれか。
- 空腹時に行う。
- 泣いていない時に行う。
- タンデムマス法で行う。
- 生後24時間以内に行う。
▶午後60
リエゾン精神看護の活動はどれか。
- 行動制限の指示
- 向精神薬の処方
- 他科への転棟指示
- コンサルテーションへの対応
知的障害〈精神遅滞〉の原因となる疾患はどれか。
- 統合失調症
- フェニルケトン尿症
- Alzheimer〈アルツハイマー〉病
- Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病
▶午後62
Aさん(24歳、男性)は、昼間の過剰な眠気を主訴に来院した。半年前に居眠り運転で交通事故を起こした。入眠時の幻視や睡眠と覚醒の移行期に体を動かせなくなることがある。また、笑ったり、怒ったりしたときに脱力してしまうこともある。
最も考えられる疾患はどれか。
- 睡眠時遊行症
- ナルコレプシー
- 睡眠時無呼吸症候群
- 睡眠・覚醒スケジュール障害
現在の日本の精神医療で正しいのはどれか。
- 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。
- 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。
- 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。
- 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。
Aさん(60歳、女性)は、統合失調症で10年間入院していた。来月退院予定となったため、Aさん、医師、看護師でチームを作り、退院支援計画を立てることになった。Aさんは「両親も亡くなってしまい、これからの生活費や住む場所がとても心配だ」と訴えてきた。
退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。
- 薬剤師
- 精神保健福祉士
- ピアサポーター
- 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師等)
訪問看護制度で正しいのはどれか。
- 管理栄養士による訪問は保険請求できる。
- 精神科訪問看護は医療保険から給付される。
- 医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。
- 訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。
▶午後66
Aさん(85歳、女性)は、1人暮らし。日常生活は自立しており、健康のために毎日20〜30分のウォーキングをしている。夜間は、廊下を歩いて1、2回トイレに行く。
Aさんの現時点での家屋環境の整備で最も優先されるのはどれか。
- 便座の高さを高くする。
- 廊下に手すりを設置する。
- トイレの扉を引き戸にする。
- 廊下に足元照明を設置する。
Aさん(52歳、男性、独身)は、銀行員。切除不能の大腸癌と診断され、外来で抗癌薬の点滴静脈内注射を受けることになった。Aさんは「治療を受けながら仕事を続けたいのですが、どうすれば良いか教えてください」と外来看護師に相談した。
外来看護師が行うAさんへの助言で最も適切なのはどれか。
- 「所属部署の変更を上司に申し出ましょう」
- 「副作用が出てから対応を考えましょう」
- 「会社の健康管理部門に相談しましょう」
- 「有給休暇を使って治療を受けましょう」
家族からネグレクトを受けている高齢者について、地域包括支援センターに通報があった。
この通報を受けた地域包括支援センターが行う業務はどれか。
- 権利擁護
- 総合相談支援
- 介護予防ケアマネジメント
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援
▶午後69
病院では、育児中の時短勤務、夜勤専従、非常勤など多様な労働時間や雇用形態の看護師が働いている。
看護管理者が行うマネジメントで最も優先するのはどれか。
- 夜勤専従の看護師の休暇を増やす。
- 育児中の看護師の院内研修を免除する。
- 非常勤看護師は患者の受け持ちを免除する。
- 特定の看護師に仕事が集中しないよう調整する。
▶午後70
診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。
- 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
- 2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
- 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。
医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
- 届出は義務である。
- 届出先は保健所である。
- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
国際社会が抱えるヘルスケアを含む課題に対して、すべての国に適用される普遍的(ユニバーサル)な目標で、2015年の国連サミットで採択されたのはどれか。
- ヘルスフォーオール21(HFA21)
- ミレニアム開発目標(MDGs)
- 持続可能な開発目標(SDGs)
- 国連開発目標(IDGs)
▶午後74
採血の際、血液が凝固するのを防ぐために試験管にクエン酸の結晶を入れておくことがある。
クエン酸によって血液から除かれるのはどれか。
- トロンビン
- プラスミン
- カルシウムイオン
- ナトリウムイオン
- フィブリノーゲン
▶午後75
胃底腺の主細胞の分泌物に由来するタンパク分解酵素はどれか。
- アミラーゼ
- キモトリプシン
- トリプシン
- ペプシン
- リパーゼ
▶午後76
成人で、骨髄が脂肪組織になっているのはどれか。
- 寛骨
- 胸骨
- 大腿骨の骨幹
- 椎骨の椎体
- 肋骨
▶午後77
臓器と産生されるホルモンの組合せで正しいのはどれか。
- 膵臓――グルカゴン
- 副腎――プロラクチン
- 腎臓――アルドステロン
- 脳下垂体――インクレチン
- 視床下部――テストステロン
▶午後78改題
抗甲状腺薬の副作用〈有害事象〉で正しいのはどれか。
- 頻脈
- 肝障害
- 不整脈
- 眼球突出
▶午後79
Barthel〈バーセル〉インデックスで評価するのはどれか。
- 栄養状態
- 疼痛の強さ
- 褥瘡の深さ
- 日常生活動作
- 呼吸困難の程度
▶午後80
急性心筋梗塞患者の合併症を早期に発見するための徴候で正しいのはどれか。
- 皮疹の出現
- 頻脈の出現
- 時間尿の増加
- 腹壁静脈の怒張
- うっ血乳頭の出現
Alzheimer〈アルツハイマー〉型認知症の患者にみられる実行機能障害はどれか。
- シャツを前後反対に着る。
- 調理の手順がわからなくなる。
- 物音がすると食事を中断する。
- 鏡に映った自分の姿に話しかける。
- 歯ブラシで髪の毛をとかそうとする。
▶午後82
副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。
- 嗅神経
- 視神経
- 動眼神経
- 三叉神経
- 迷走神経
糖尿病性腎症の食事療法で制限するのはどれか。2つ選べ。
- 脂質
- 塩分
- 蛋白質
- 炭水化物
- ビタミン
▶午後84
アナフィラキシーショックで正しいのはどれか。2つ選べ。
- 徐脈になる。
- 重症例では死に至る。
- 気道粘膜の浮腫を生じる。
- Ⅲ型アレルギー反応である。
- 副腎皮質ステロイドは禁忌である。
▶午後85
前立腺肥大症で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 進行すると水腎症となる。
- 外科治療は経尿道的前立腺切除術を行う。
- 直腸診で石の様な硬さの前立腺を触知する。
- 前立腺を縮小させるために男性ホルモン薬を用いる。
- 前立腺特異抗原〈prostate specific antigen:PSA〉値が100ng/mL以上となる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく五類感染症はどれか。2つ選べ。
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
- 腸管出血性大腸菌感染症
- つつが虫病
- 日本脳炎
- 梅毒
▶午後87
感覚性失語のある成人患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。2つ選べ。
- 短文で話しかける。
- 身振りを加えて話す。
- 多くの話題を提供する。
- 耳元に近づき大きな声で話す。
- open-ended question〈開かれた質問〉を用いる。
▶午後88
交通事故によって脊髄損傷で入院した下肢に麻痺のある成人患者。職場復帰に向けて、看護師が患者に説明する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 自己導尿は自宅で行う。
- 仕事中は飲水を制限する。
- 車椅子には体圧分散マットを使用する。
- 残業する場合の休憩時間は不要である。
- 職場の担当者に自分の病気について伝える。
▶午後89
人工肛門を造設した患者へのストーマケアの指導内容で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 装具の交換は便が漏れない限り不要である。
- 装具をはがした時は皮膚保護材の溶解の程度を観察する。
- 洗浄後のストーマはドライヤーで乾かす。
- 装具の穴はストーマと同じ大きさにする。
- 装具を貼る時は腹壁のしわを伸ばす。
▶午後90
妊娠36週の妊婦にNST〈non-stress test〉を行うため、分娩監視装置を装着することになった。
妊婦への説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 「胎児の健康状態を判定します」
- 「所要時間は10分です」
- 「排尿を済ませて下さい」
- 「仰向けで行います」
- 「固定用ベルトを1本使用します」
資料 厚生労働省「第105回保健師国家試験、第102回助産師国家試験、第108回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第108回看護師国家試験
平成31年2月17日(日)に実施された第108回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第108回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
▶午前26
三叉神経を求心路として起こるのはどれか。
- 瞬目反射
- 対光反射
- 追跡運動
- 輻輳反射
▶午前27
人工弁置換術の術後合併症で早期離床による予防効果が高いのはどれか。
- 反回神経麻痺
- 術後出血
- 縦隔炎
- 肺炎
▶午前28
成人の鼠径ヘルニアで正しいのはどれか。
- 内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアに分けられる。
- 患者の男女比は約1:3である。
- やせている人に多い。
- 保存的治療を行う。
▶午前29
Aさん(45歳、男性)は、10年ぶりに会った友人から顔貌の変化を指摘された。顔貌変化を図に示す。
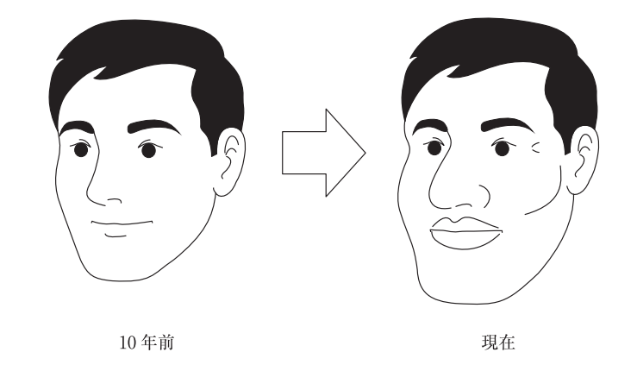
Aさんの顔貌変化を引き起こしたホルモンはどれか。
- 成長ホルモン
- 副甲状腺ホルモン
- 副腎皮質ホルモン
- 甲状腺刺激ホルモン
▶午前30
低血糖時の症状はどれか。
- 発疹
- 徐脈
- 冷汗
- 多幸感
▶午前31
手の写真を別に示す。
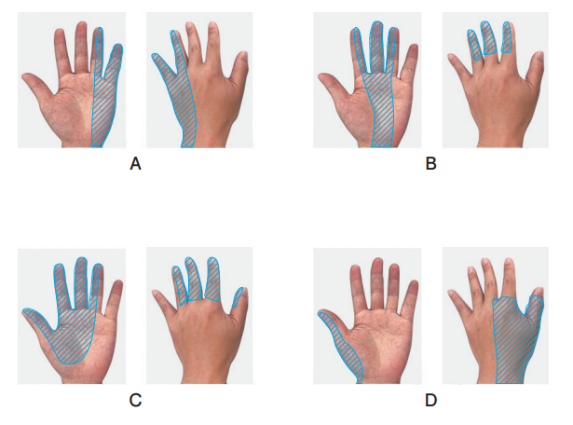
写真の斜線部分で、正中神経の圧迫によって知覚異常を生じる部位を示しているのはどれか。
- A
- B
- C
- D
▶午前32
疫学的因果関係があると判断できるのはどれか。
- 要因と疾病の関係が生物学的研究で得られた事実と異なる。
- 特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。
- 要因と疾病の関係でオッズ比が1である。
- 要因と疾病の関係が散発的である。
令和4年(2022年)の日本の結核対策で増加が問題とされているのはどれか。
- 新登録結核患者数
- 菌喀痰塗抹陽性の肺結核患者数
- 外国生まれの新登録結核患者の割合
- 結核による死亡数
トータル・ヘルスプロモーション・プラン〈THP〉で実施されるのはどれか。
- がん検診
- 健康測定
- 一般健康診断
- 特定健康診査
健康寿命の説明で適切なのはどれか。
- 生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。
- 2019年の健康寿命は2016年よりも短い。
- 2019年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。
- 平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。
▶午前36
指鼻指試験で評価する項目はどれか。
- 小脳機能
- 表在反射
- 深部知覚
- 複合知覚
▶午前37
静脈血採血時に使用する器具の取り扱いで適切なのはどれか。
- 真空採血管で採血する場合は素手で行う。
- 抜針した採血針はキャップをして破棄する。
- 針専用の廃棄容器は実施者の手の届く範囲に置く。
- 針専用の廃棄容器は廃棄物が投入口まで達したら交換する。
▶午前38
便秘を訴えている患者の打診のアセスメント項目で適切なのはどれか。
- 固い腫瘤
- 筋性防御
- 叩打痛
- 鼓腸
▶午前39
夜間の睡眠を促す方法で適切なのはどれか。
- 朝、起床後に日光を浴びる。
- 2時間以上昼寝をする。
- 夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。
- 就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。
▶午前40
歯ブラシを用いたブラッシングで歯周ポケットの清掃に適しているのはどれか。
- バス法
- スクラブ法
- ローリング法
- フォーンズ法
▶午前41
右中葉領域で粗い断続性副雑音〈水泡音〉が聴取された場合の体位ドレナージの体位を図に示す。
適切なのはどれか。
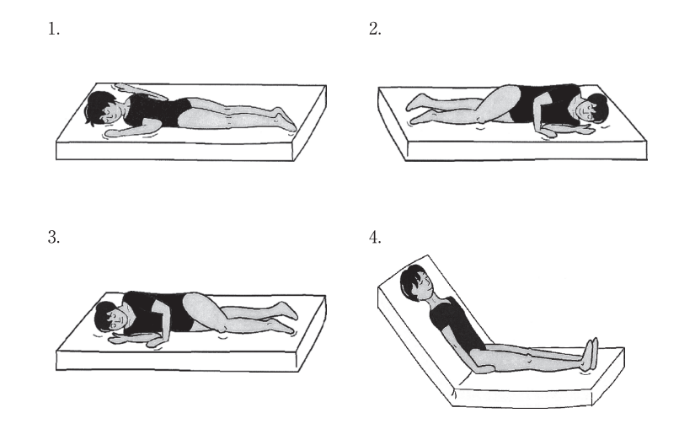
20℃から24℃で保存するのはどれか。
- 全血製剤
- 血漿製剤
- 赤血球液
- 血小板製剤
▶午前43
穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。
- 胸腔穿刺――胸骨体第2肋間
- 腹腔穿刺――剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点
- 腰椎穿刺――第1・2腰椎間
- 骨髄穿刺――後腸骨稜
作業と健康障害の組合せで正しいのはどれか。
- VDT作業――栄養機能障害
- 有機溶剤を扱う作業――呼吸機能障害
- 電離放射線を扱う作業――造血機能障害
- 石綿〈アスベスト〉を扱う作業――排尿機能障害
▶午前45
救急外来を受診した成人患者で、治療の緊急度が最も高いのはどれか。
- 2時間ほど前から右上下肢に力が入らず、ろれつが回らない。
- 3日前にペットの葬儀が終わり、食欲がなく、夜眠れない。
- プールでの日焼けによって背部全体が発赤している。
- 市販の風邪薬を通常の2倍量服用した。
がん診療連携拠点病院に設置されている「がん相談支援センター」の業務はどれか。
- 就労の斡旋
- がん検診の実施
- がんについての情報提供
- セカンドオピニオン外来の開設
▶午前47
胸腔ドレーン挿入中の患者の看護で適切なのはどれか。
- ミルキングは禁忌である。
- 持続的に陽圧となっているか観察する。
- ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。
- ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。
▶午前48
慢性心不全患者の生活指導で、心臓への負担を少なくするのはどれか。
- 肺炎球菌ワクチン接種の回避
- 蛋白質を制限した食事
- 食直後の散歩
- 排泄後の休息
▶午前49
Crohn〈クローン〉病の患者の食事指導で適切なのはどれか。
- 「食物繊維を多く含む食事にしましょう」
- 「蛋白質の多い食事にしましょう」
- 「脂肪分の多い食事にしましょう」
- 「炭水化物を控えましょう」
▶午前50
高カリウム血症の患者でみられるのはどれか。
- Trousseau〈トルソー〉徴候
- 心電図でのT波の増高
- 腸蠕動音の低下
- 四肢の麻痺
▶午前51
開頭術を受けた患者の看護で適切なのはどれか。
- 頭部を水平に保つ。
- 緩下薬は禁忌である。
- 髄膜炎症状の観察を行う。
- 手術後1週間は絶飲食とする。
▶午前52
Aさん(47歳、男性、会社員)は、痛風の既往があり、ほぼ毎日、飲酒を伴う外食をしている。1週前に尿管結石による疝痛発作があり、体外衝撃波結石破砕術〈ESWL〉を受けた。その結果、排出された結石は尿酸結石であることがわかった。
Aさんへの結石の再発予防に対する生活指導で適切なのはどれか。
- 「飲酒量に制限はありません」
- 「負荷の大きい運動をしましょう」
- 「1日2L程度の水分摂取をしましょう」
- 「動物性蛋白質を多く含む食品を摂取しましょう」
▶午前53
高齢者に対する生活史の聴き方で適切なのはどれか。
- 認知機能の評価尺度を用いる。
- 事実と異なる聴取内容を訂正する。
- 話を聴く前に文書による同意を得る。
- 高齢者が話しやすい時代の思い出から聴く。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における高齢者世帯の所得のうち62.8%を占めるものは何か。
- 稼働所得
- 財産所得
- 公的年金・恩給
- 年金以外の社会保障給付金
▶午前55
Aさん(80歳、男性)は、空腹時の胃の痛みが2週間続くため受診し、1週後に胃内視鏡検査を受けることになった。
検査を受けるAさんへの看護で適切なのはどれか。
- 検査前日の夜に下剤を服用することを伝える。
- 検査前に前立腺肥大症の既往の有無を確認する。
- 検査中は仰臥位の姿勢を保持する。
- 検査後はすぐに食事ができることを説明する。
▶午前56
軽度の老人性難聴の特徴はどれか。
- ゆっくり話すと聞き取りにくい。
- 母音よりも子音が聞き分けにくい。
- 高音よりも低音が聞き取りにくい。
- イントネーションが理解しにくい。
▶午前57
Aさん(90歳、男性)は、脳梗塞による軽度の左半身麻痺がある。要介護2。最近、娘(65歳)とその家族と同居を始めた。Aさんの受診に付き添ってきた娘が看護師に「同居を始めてから疲れます」と話した。
この時の娘に対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。
- 心療内科の受診を勧める。
- 娘の幼少期の親子関係を聞く。
- Aさんの介護老人保健施設への入所を勧める。
- 同居後に家族の生活がどのように変化したかを聞く。
Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。
Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。
- 車椅子
- 歩行器
- 電動ベッド
- 入浴用椅子
乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。
- 母子保健法
- 児童福祉法
- 次世代育成支援対策推進法
- 児童虐待の防止等に関する法律
▶午前60
小児の呼吸法が、腹式呼吸から成人と同じ胸式呼吸に変化する時期はどれか。
- 生後6か月
- 3歳
- 7歳
- 12歳
▶午前61
新生児の養育者に対する看護師の指導で正しいのはどれか。
- 「脂漏性湿疹は石けんで洗いましょう」
- 「臍帯はおむつで覆いましょう」
- 「うつぶせ寝にしましょう」
- 「日光浴をしましょう」
▶午前62
先天異常で正しいのはどれか。
- 軟骨無形成症は低身長になる。
- Turner〈ターナー〉症候群は高身長になる。
- Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群は低身長になる。
- Pierre Robin〈ピエール・ロバン〉症候群は巨舌症がある。
▶午前63
平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。
その変更の条件で正しいのはどれか。
- 15歳以上であること
- うつ症状を呈していること
- 現に未成年の子がいないこと
- 両親の同意が得られていること
日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。
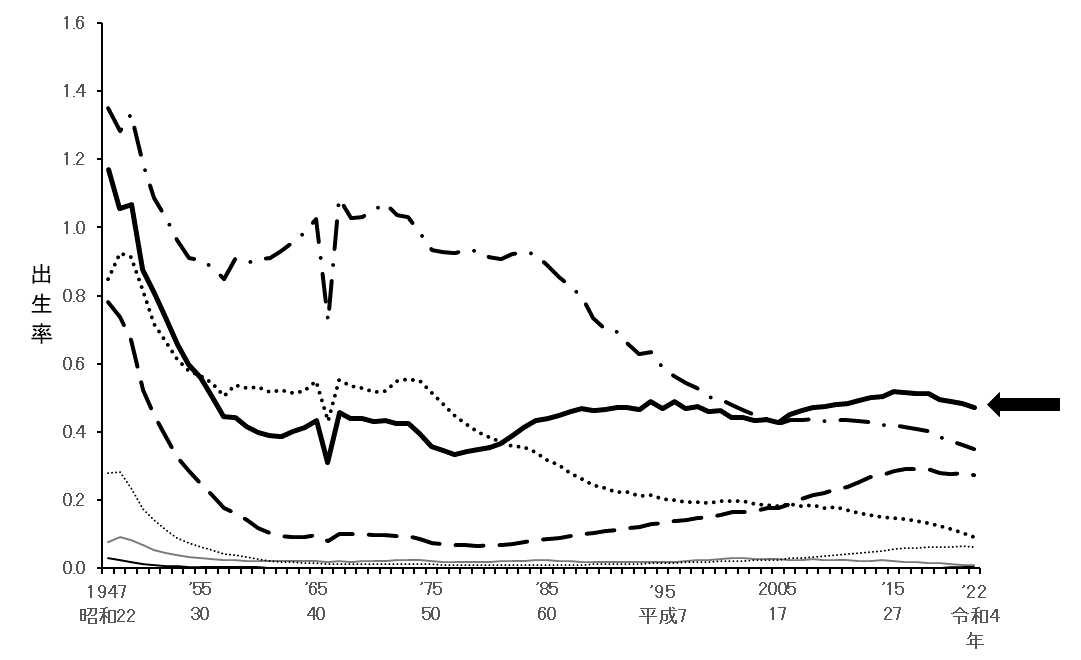
図の矢印で示してある年齢階級はどれか。
- 20~24歳
- 25~29歳
- 30~34歳
- 35~39歳
▶午前65
女性を中心としたケア〈Women centered care〉の概念で適切なのはどれか。
- 父権主義を否定している。
- 周産期にある女性を対象とする。
- 全人的な女性という視点を重視する。
- 女性特有の疾患に関する看護を行う。
▶午前66
入院患者のせん妄に対する予防的介入で適切なのはどれか。
- 可能な限り離床を促す。
- 昼間は部屋を薄暗くする。
- 家族や知人の面会は必要最低限にする。
- 夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。
注意欠如・多動性障害〈ADHD〉の症状はどれか。
- 音声チックが出現する。
- 計算を習得することが困難である。
- 課題や活動に必要なものをしばしば失くしてしまう。
- 読んでいるものの意味を理解することが困難である。
精神医療審査会で審査を行うのはどれか。
- 精神保健指定医の認定
- 入院患者からの退院請求
- 退院後生活環境相談員の選任
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。
- 保護者制度の廃止
- 自立支援医療の新設
- 精神保健指定医制度の導入
- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。
- 性別は女性が多い。
- 続柄は子が最も多い。
- 年齢は50~59歳が最も多い。
- 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。
▶午前71
Aさん(74歳、女性)は、1人暮らし。要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa。頻尿のため、自室からトイレへの移動中に廊下で失禁することが頻繁にある。1日3食の高齢者向け配食サービスを利用している。
現時点でのAさんの日常生活で最も起こりやすいのはどれか。
- 窒息
- 転倒
- 熱傷
- 徘徊
▶午前72
Aさん(77歳、男性)は、脳梗塞による左片麻痺があり、右膝の痛みにより立位が困難である。端坐位で殿部をわずかに持ち上げることはできる。妻(77歳)は小柄で、体格差のある夫の移乗の介助に負担を感じている。
Aさんのベッドから車椅子への移乗の際、妻の介護負担を軽減する福祉用具で適切なのはどれか。
- 歩行器
- ベッド柵
- 電動介助リフト
- トランスファーボード
▶午前73
Aさん(82歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1。日中は車椅子に座っていることが多い。Aさんの仙骨部に発赤があるのを発見したため、訪問看護師は妻にAさんへの介護方法を指導することにした。
妻に指導する内容で正しいのはどれか。
- 「仙骨部をマッサージしましょう」
- 「夜間は2時間毎に体位変換をしましょう」
- 「時々お尻を浮かすよう声をかけましょう」
- 「車椅子に座らせるときは円座を使いましょう」
地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。
- 高齢者が生活保護を受けること
- 住民が定期的に体重測定すること
- 要介護者が介護保険サービスを利用すること
- 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと
医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。
- 医療法
- 医師法
- 健康保険法
- 保健師助産師看護師法
▶午前76
看護師Aが患者Bの点滴ボトルに薬剤を注入しているとき、新人看護師から患者Cについて相談を受けた。看護師Aが作業を中断し新人看護師に対応した後、患者Bの点滴ボトルに患者Cの名前を記入するというヒヤリハットが発生した。
この病棟の看護師長が行う再発防止策で適切なのはどれか。
- 看護師Aに対策を考えさせる。
- 看護師Aを注射の業務から外す。
- 作業中断の対策を病棟チームで検討する。
- 再発防止カンファレンスを1か月後に計画する。
日本における政府開発援助〈ODA〉の実施機関として正しいのはどれか。
- 国際協力機構〈JICA〉
- 世界保健機関〈WHO〉
- 国連児童基金〈UNICEF〉
- 国連世界食糧計画〈WFP〉
▶午前78
災害に関する記述で正しいのはどれか。
- 災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。
- 人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。
- 複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。
- 発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。
▶午前79
血漿の電解質組成を陽イオンと陰イオンに分けたグラフを示す。
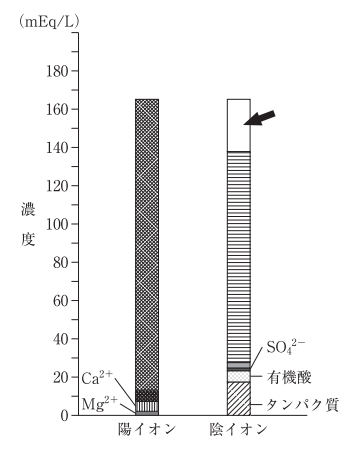
矢印で示すのはどれか。
- ナトリウムイオン
- カリウムイオン
- リン酸イオン
- 塩化物イオン
- 重炭酸イオン
▶午前80
血液中のカルシウムイオン濃度が低下した際に、ホルモン分泌量が増加するのはどれか。
- 膵島
- 甲状腺
- 下垂体
- 副腎皮質
- 副甲状腺
ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。
- 家庭裁判所長
- 児童相談所長
- 保健所長
- 警察署長
- 市町村長
▶午前82
新生児の殿部の写真を別に示す。

考えられるのはどれか。
- ポートワイン母斑
- サーモンパッチ
- ウンナ母斑
- 太田母斑
- 蒙古斑
▶午前83
排便反射の反射弓を構成するのはどれか。2つ選べ。
- 下腸間膜神経節
- 腹腔神経節
- 骨盤神経
- 腰髄
- 仙髄
▶午前84
アセチルコリンで収縮するのはどれか。2つ選べ。
- 心筋
- 排尿筋
- 腓腹筋
- 立毛筋
- 瞳孔散大筋
▶午前85
内臓の痛みを引き起こすのはどれか。2つ選べ。
- 虚血
- 氷水の摂取
- 48℃の白湯の摂取
- 平滑筋の過度の収縮
- 内視鏡によるポリープの切除
▶午前86
心電図検査における肢誘導はどれか。2つ選べ。
- Ⅰ
- V1
- V2
- V3R
- aVR
日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 年金保険
- 雇用保険
- 船員保険
- 組合管掌健康保険
- 労働者災害補償保険
▶午前88
糖尿病末梢神経障害による感覚障害のある患者へのフットケア指導で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 両足部を観察する。
- 熱めの湯をかけて洗う。
- 靴ずれしない靴を選ぶ。
- なるべく素足で過ごす。
- 爪は足趾の先端よりも短く切る。
▶午前89
出生直後の正常新生児に当てはまる特徴はどれか。2つ選べ。
- 生理的に多血である。
- 腸内細菌叢が定着している。
- 噴門部の括約筋は発達している。
- Babinski〈バビンスキー〉反射がみられる。
- 胎盤を通じて母体からIgMが移行している。
身長170cm、体重70kgの成人の体格指数(BMI)を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:① ②
資料 厚生労働省「第105回保健師国家試験、第102回助産師国家試験、第108回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第108回看護師国家試験
平成30年2月18日(日)に実施された第107回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第107回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後5(必修除外)
倫理原則の「正義」はどれか。
- 約束を守る。
- 害を回避する。
- 自己決定を尊重する。
- 公平な資源の配分を行う。
▶午後12(必修除外)
潰瘍性大腸炎によって生じるのはどれか。
- 滲出性下痢
- 分泌性下痢
- 脂肪性下痢
- 浸透圧性下痢
▶午後22(採点除外改題)
静脈血採血の方法で正しいのはどれか。
- 駆血帯を巻いている時間は1分以内とする。
- 針の刃面を下に向けて血管内に刺入する。
- 静脈内に針を刺入したら強く内筒を引く。
- 針を抜いてから1分程度の圧迫止血を行う。
▶午後26
味覚について正しいのはどれか。
- 基本味は5つである。
- 外転神経が支配する。
- 冷たい物ほど味が濃いと感じる。
- 1つの味蕾は1種類の基本味を知覚する。
▶午後27
ビタミンと生理作用の組合せで正しいのはどれか。
- ビタミンA――嗅覚閾値の低下
- ビタミンD――Fe2+吸収の抑制
- ビタミンE――脂質の酸化防止
- ビタミンK――血栓の溶解
▶午後28
呼吸不全について正しいのはどれか。
- 喘息の重積発作によって慢性呼吸不全になる。
- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉で2つの型に分類される。
- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が60mmHg以下をいう。
- Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類は呼吸困難の程度を表す。
▶午後29
薬剤とその副作用〈有害事象〉の組合せで正しいのはどれか。
- 副腎皮質ステロイド――低血糖
- ニューキノロン系抗菌薬――髄膜炎
- アミノグリコシド系抗菌薬――視神経障害
- スタチン〈HMG-CoA還元酵素阻害薬〉――横紋筋融解症
▶午後30
Sjögren〈シェーグレン〉症候群について正しいのはどれか。
- 網膜炎を合併する。
- 男女比は1対1である。
- 主症状は乾燥症状である。
- 抗核抗体の陽性率は30%程度である。
インフォーマルサポートはどれか。
- 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成
- 医師による居宅療養管理指導
- 近隣住民による家事援助
- 民生委員による相談支援
ハイリスクアプローチについて正しいのはどれか。
- 費用対効果が高い。
- 成果が恒久的である。
- 一次予防を目的とする。
- 集団全体の健康状態の向上に貢献する。
▶午後33
フィンク, S. L.の危機モデルの過程で第3段階はどれか。
- 防衛的退行
- 衝撃
- 適応
- 承認
▶午後34
クリティカル・シンキングの思考過程で正しいのはどれか。
- 物事を否定的にみる。
- 主観的情報を重視する。
- 直感的にアプローチをする。
- 根拠に基づいた判断を行う。
学習支援として、集団指導よりも個別指導が望ましいのはどれか。
- 小学生へのインフルエンザ予防の指導
- 塩分摂取量が多い地域住民への食事指導
- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導
- 3〜4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導
感染症の成立過程において、予防接種が影響を与える要素はどれか。
- 病原体
- 感染源
- 感染経路
- 宿主の感受性
▶午後37
Aさん(85歳、女性)。左側の人工股関節置換術後10日である。日中は看護師の援助によって車椅子でトイレまで行くことは可能であるが、夜間はポータブルトイレを使用している。
Aさんの夜間の療養環境を整える上で適切なのはどれか。
- 足側のベッド柵は下げておく。
- 着脱しやすいスリッパを用意する。
- ポータブルトイレはAさんのベッドの右側に置く。
- 移動時につかまれるようにオーバーテーブルを整える。
▶午後38
1948年に、看護教育の現状等に関する大規模な調査報告書「これからの看護〈Nursing for the future〉」を著した人物はどれか。
- リチャーズ, L.
- ブラウン, E. L.
- レイニンガー, M. M.
- ゴールドマーク, J. C.
▶午後39
ノンレム睡眠中の状態で正しいのはどれか。
- 骨格筋が弛緩している。
- 夢をみていることが多い。
- 大脳皮質の活動が低下している。
- 組織の新陳代謝が低下している。
麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。
- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。
- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。
- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。
- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。
成人に対する一次救命処置〈BLS〉において、胸骨圧迫と人工呼吸との回数比で正しいのはどれか。
- 20対1
- 20対2
- 30対1
- 30対2
▶午後42
成人男性に対する全身麻酔下の膵頭十二指腸切除術が時に開始されてから40分間の経過を表に示す。
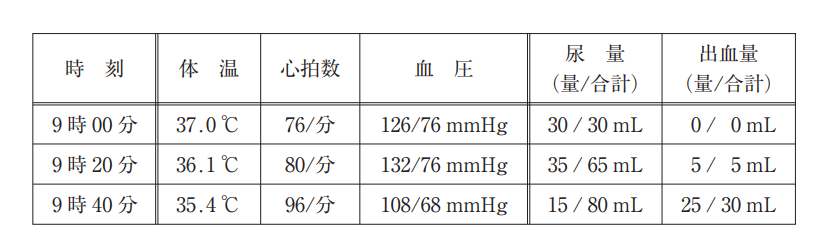
9時40分の時点で、間接介助の看護師が医師に確認の上、実施することとして適切なのはどれか。
- 輸血を準備する。
- 下半身を心臓より高くする。
- 加温マットの設定温度を上げる。
- 次の尿量測定を40分後に実施する。
▶午後43
インスリン製剤について正しいのはどれか。
- 経口投与が可能である。
- 冷凍庫で長期保存できる。
- 皮下注射は同じ部位に行う。
- 飛行機に搭乗する際は手荷物として持ち込む。
▶午後44
廃用症侯群を予防する方法で正しいのはどれか。
- 関節固定後の等張性運動
- ギプス固定後からの等尺性運動
- 下腿の中枢から末梢へのマッサージ
- 足底板の装着による下腿三頭筋の収縮
▶午後45
造影CTの際に最も注意が必要なのはどれか。
- 閉所に対する恐怖がある患者
- 気管支喘息の既往がある患者
- ペースメーカーを装着している患者
- 既往に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者
▶午後46
下垂体腺腫について正しいのはどれか。
- 褐色細胞腫が最も多い。
- トルコ鞍の狭小化を認める。
- 典型的な視野障害として同名半盲がある。
- 代表的な外科治療として経鼻的な経蝶形骨洞法による下垂体切除術がある。
▶午後47
緑内障と診断された患者への説明で適切なのはどれか。
- 「治療すれば視野障害は改善します」
- 「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」
- 「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」
- 「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」
梅毒について正しいのはどれか。
- ウイルス感染症である。
- 感染経路は空気感染である。
- 治療の第一選択薬はステロイド外用薬である。
- 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。
▶午後49
老年期の加齢に伴う生殖器および生殖機能の変化で正しいのはどれか。
- 卵巣が肥大する。
- 腟壁が薄くなる。
- 精液中の精子がなくなる。
- 男性はテストステロンが増加する。
▶午後50
高齢者の薬物動態の特徴で正しいのはどれか。
- 薬物の吸収の亢進
- 薬物の代謝の亢進
- 薬物の排泄の増加
- 血中濃度の半減期の延長
子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。
- 児童憲章の宣言
- 児童福祉法の公布
- 母子保健法の公布
- 児童の権利に関する条約の日本の批准
▶午後52
ピアジェ, J.の認知発達理論において2〜7歳ころの段階はどれか。
- 感覚―運動期
- 具体的操作期
- 形式的操作期
- 前操作期
▶午後53
乳歯について正しいのはどれか。
- 6〜8か月ころから生え始める。
- 5〜7歳ころに生えそろう。
- 全部で28本である。
- う蝕になりにくい。
▶午後54
乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。
- ミルクに混ぜる。
- はちみつに混ぜる。
- 少量の水に溶かす。
- そのまま口に含ませる。
入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。
- 麻疹
- 風疹
- 手足口病
- 流行性耳下腺炎
▶午後56
閉経について正しいのはどれか。
- 月経は永久に停止する。
- 子宮機能の低下で生じる。
- 原発性無月経のことである。
- 月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。
▶午後57
正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。
- 骨盤内嵌入時、胎児の背中は母体の背側にある。
- 胎児の前頭部が先進する。
- 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。
- 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。
母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。
- 育成医療――結核児童
- 養育医療――学齢児童
- 健全母性育成事業――高齢妊婦
- 養育支援訪問事業――特定妊婦
精神保健活動における二次予防に該当するのはどれか。
- 地域の子育てサークルへの支援
- 休職中のうつ病患者への支援
- 企業内でのメンタルヘルス講座の開催
- 学校を長期間欠席している児童への家庭訪問
▶午後60
統合失調症の幻覚や妄想に最も関係する神経伝達物質はどれか。
- ドパミン
- セロトニン
- アセチルコリン
- ノルアドレナリン
精神科デイケアの目的で最も適切なのはどれか。
- 陽性症状を鎮静化する。
- 家族の疾病理解を深める。
- 単身で生活できるようにする。
- 対人関係能力の向上を目指す。
健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。
- サービス対象は75歳以上である。
- 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。
- 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。
- 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。
▶午後63
Aさん(75歳、男性)。1人暮らし。慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉のため、2年前から在宅酸素療法を開始し、週に2回の訪問看護を利用している。訪問看護師はAさんから「最近、洗濯物を干すときに息が苦しくて疲れるが、自分でできることは続けたい」と相談された。
Aさんの労作時の息苦しさを緩和する方法について、訪問看護師が行う指導で適切なのはどれか。
- 労作時は酸素流量を増やす。
- 呼吸は呼気より吸気を長くする。
- 動作に合わせて短速呼吸をする。
- 腕を上げるときは息を吐きながら行う。
▶午後64
Aさん(80歳、男性)は、20年前に大腸癌でストーマを造設し、現在週1回の訪問看護を利用している。訪問看護師は、訪問時にAさんから「2日前から腹痛がある」と相談を受けた。Aさんのバイタルサインは、体温36.4℃、呼吸数24/分、脈拍84/分、血圧138/60mmHgである。
訪問看護師がAさんの腹痛をアセスメントするための情報で最も優先度が高いのはどれか。
- 排便の有無
- 身体活動量
- 食物の摂取状況
- ストーマ周囲の皮膚の状態
▶午後65
Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。脳出血の手術後、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。神経因性膀胱のため、膀胱留置カテーテルを挿入している。要介護2で、退院後は看護小規模多機能型居宅介護を利用する予定である。
退院後にAさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。
- 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。
- カテーテルは大腿の内側に固定する。
- 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。
- カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。
A病院の組織図を図に示す。
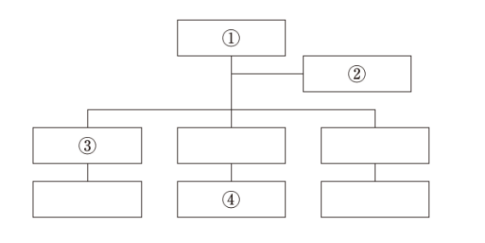
医療安全管理を担う部門が、組織横断的な活動をするのに適切な位置はどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
▶午後67
高速道路で衝突事故が発生し、20人が受傷した。A病院は、5人の重症患者を受け入れ、あわただしい雰囲気となっている。
医療を安全かつ円滑に行うために、救急外来のリーダー看護師に求められる役割として誤っているのはどれか。
- チームで患者情報を共有する。
- スタッフの役割分担を明確にする。
- 患者誤認が生じないように注意喚起する。
- 電話による安否の問い合わせに回答する。
▶午後68
紙カルテと比較したときの電子カルテの特徴として正しいのはどれか。
- データ集計が困難である。
- 診療録の保存期間が短い。
- 多職種間の情報共有が容易になる。
- 個人情報漏えいの危険性がなくなる。
医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。
- 内視鏡室で勤務する看護師
- 精神科病棟で勤務する看護師
- 血管造影室で勤務する看護師
- 一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師
▶午後70
神経伝達物質と効果器の組合せで正しいのはどれか。
- γ-アミノ酪酸〈GABA〉――気管
- アセチルコリン――瞳孔散大筋
- アドレナリン――血管
- セロトニン――心筋
- ドパミン――汗腺
▶午後71
無対の静脈はどれか。
- 鎖骨下静脈
- 総腸骨静脈
- 内頸静脈
- 腕頭静脈
- 門脈
▶午後72
血液中の濃度の変化が膠質浸透圧に影響を与えるのはどれか。
- 血小板
- 赤血球
- アルブミン
- グルコース
- ナトリウムイオン
院内感染の観点から、多剤耐性に注意すべきなのはどれか。
- ジフテリア菌
- 破傷風菌
- 百日咳菌
- コレラ菌
- 緑膿菌
▶午後74
過換気でみられるのはどれか。
- 骨格筋の弛緩
- 血中酸素分圧の低下
- 体循環系の血管の収縮
- 代謝性アルカローシス
- 血中二酸化炭素分圧の上昇
▶午後75
乳癌の検査で侵襲性が高いのはどれか。
- 触診
- 細胞診
- MRI検査
- 超音波検査
- マンモグラフィ
感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。
- 結核――診断後7日以内
- 梅毒――診断後直ちに
- E型肝炎――診断後直ちに
- 腸管出血性大腸菌感染症――診断後7日以内
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉――診断後直ちに
令和3年(2021年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。
①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。
①――②
- 4――4
- 4――5
- 5――5
- 5――6
- 6――6
▶午後78
筋骨格系の加齢に伴う変化が発症の一因となるのはどれか。
- 肺結核
- 骨盤臓器脱
- 前立腺肥大症
- 加齢黄斑変性
- 慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉
令和4年度(2022年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」における養介護施設従事者等による虐待で最も多いのはどれか。
- 性的虐待
- 介護等放棄
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- 経済的虐待
Aさん(66歳、女性)は、4年前に前頭側頭型認知症と診断され、介護老人福祉施設に入所している。時々、隣の席の人のおやつを食べるため、トラブルになることがある。
この状況で考えられるAさんの症状はどれか。
- 脱抑制
- 記憶障害
- 常同行動
- 自発性の低下
- 物盗られ妄想
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。
- 摘便
- 創処置
- 血糖測定
- 喀痰吸引
- インスリン注射
▶午後82
精神障害者のリカバリ〈回復〉について正しいのはどれか。
- ストレングスモデルが適用される。
- 目標に向かう直線的な過程である。
- 精神疾患が寛解した時点から始まる。
- 精神障害者が1人で達成を目指すものである。
- 精神障害者が病識を獲得するまでの過程である。
▶午後83
健常な成人の心臓について、右心室と左心室で等しいのはどれか。2つ選べ。
- 単位時間当たりの収縮の回数
- 拡張時の内圧
- 収縮時の内圧
- 心室壁の厚さ
- 1回拍出量
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
- 申請に基づく特定医療費の支給
- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
▶午後85
急性期の患者の特徴で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 症状の変化が乏しい。
- エネルギー消費量が少ない。
- 身体の恒常性が崩れやすい。
- 生命の危機状態になりやすい。
- セルフマネジメントが必要となる。
▶午後86
甲状腺ホルモンの分泌が亢進した状態の身体所見について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 徐脈
- 便秘
- 眼球突出
- 皮膚乾燥
- 手指振戦
▶午後87
下部尿路症状のうち蓄尿症状はどれか。2つ選べ。
- 尿失禁
- 残尿感
- 腹圧排尿
- 尿線途絶
- 尿意切迫感
▶午後88
妊娠の成立の機序で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 原始卵胞から卵子が排出される。
- 排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。
- 受精は精子と卵子との融合である。
- 受精卵は子宮内で2細胞期になる。
- 着床は排卵後3日目に起こる。
▶午後89
Aさん(65歳、女性)は、5年前に乳癌の左胸筋温存乳房切除術と左腋窩リンパ節郭清術を受けた。1年前に大骨転移のため日常生活動作〈ADL〉に一部介助が必要となり、訪問看護を利用し在宅で療養している。Aさんの左上腕内側の皮膚をつまむと健側より厚みがある。
訪問看護師がAさんに指導する左上腕のケア方法で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 指圧する。
- 皮膚の露出は少なくする。
- 保湿クリームを塗布する。
- ナイロン製タオルで洗う。
- アルカリ性石けんで洗浄する。
出生体重3,200gの新生児。日齢の体重は3,100gである。このときの体重減少率を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:①.②%
資料 厚生労働省「第104回保健師国家試験、第101回助産師国家試験、第107回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第107回看護師国家試験
平成30年2月18日(日)に実施された第107回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第107回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
令和4年(2022年)の病院報告による一般病床の平均在院日数はどれか。
- 6.2日
- 16.2日
- 26.2日
- 36.2日
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。
【 】に入るのはどれか。
- 2
- 3
- 4
- 6
▶午前11(必修除外)
肝臓の機能で正しいのはどれか。
- 胆汁の貯蔵
- 脂肪の吸収
- ホルモンの代謝
- 血漿蛋白質の分解
▶午前26
健常な成人の血液中にみられる細胞のうち、核が無いのはどれか。
- 単球
- 好中球
- 赤血球
- リンパ球
▶午前27
自発呼吸時の胸腔内圧を示す曲線はどれか。
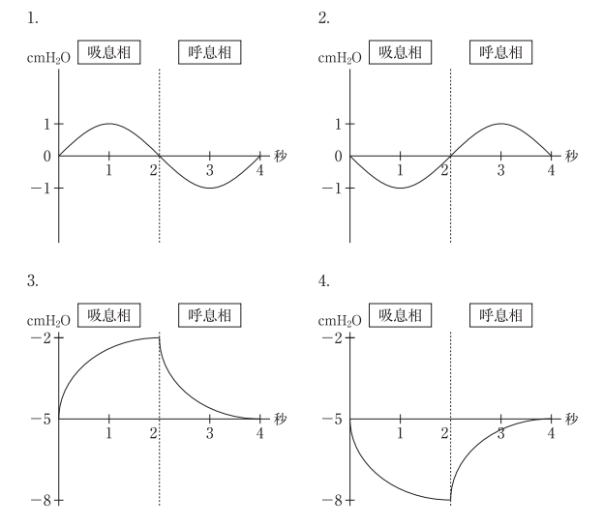
▶午前28
急性大動脈解離について正しいのはどれか。
- 大動脈壁の外膜が解離する。
- 診断には造影剤を用いないCT検査を行う。
- Stanford〈スタンフォード〉分類B型では緊急手術を要する。
- 若年者ではMarfan〈マルファン〉症候群の患者にみられることが多い。
令和3年度(2021年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に並んでいるのはどれか。
- 年金>医療>福祉その他
- 年金>福祉その他>医療
- 医療>年金>福祉その他
- 医療>福祉その他>年金
法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。
- 児童福祉法――受胎調節の実地指導
- 地域保健法――市町村保健センターの設置
- 健康増進法――医療安全支援センターの設置
- 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理
▶午前31
排泄行動が自立している入院中の男性高齢者が、夜間の排尿について「夜は何度もトイレに行きたくなります。そのたびにトイレまで歩くのは疲れます」と訴えている。
この患者の看護で適切なのはどれか。
- おむつの使用
- 夜間の尿器の使用
- 就寝前の水分摂取の制限
- 膀胱留置カテーテルの挿入
良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。
- リスボン宣言
- ヘルシンキ宣言
- ジュネーブ宣言
- ニュルンベルク綱領
▶午前33
看護における問題解決過程で誤っているのはどれか。
- 多面的な情報を分析する。
- 看護問題の優先順位は変化する。
- 家族を含めた看護計画を立てる。
- 看護問題は疾患によって確定される。
▶午前34
検査に用いる器具を別に示す。

Weber〈ウェーバー〉試験に用いるのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
▶午前35
患者と看護師が面談をする際、両者の信頼関係を構築するための看護師の行動で最も適切なのはどれか。
- 患者の正面に座る。
- メモを取ることに集中する。
- 患者と視線の高さを合わせる。
- 事前に用意した文章を読み上げる。
▶午前36
成人に経鼻経管栄養法を行う際の胃管を挿入する方法で適切なのはどれか。
- 体位は仰臥位とする。
- 管が咽頭に達したら頸部を後屈する。
- 咳嗽が生じた場合は直ちに抜去する。
- 嚥下運動よりも速い速度で挿入する。
▶午前37
ボディメカニクスを活用して、看護師が患者を仰臥位から側臥位に体位変換する方法で正しいのはどれか。
- 患者の支持基底面を狭くする。
- 患者の重心を看護師から離す。
- 患者の膝を伸展したままにする。
- 患者の体幹を肩から回転させる。
▶午前38
入浴の際に血圧が低下しやすい状況はどれか。
- 浴槽に入る前に湯を身体にかけたとき
- 浴槽の湯に肩まで浸かったとき
- 浴槽から出たとき
- 浴室から脱衣所に移動したとき
輸血後、数日から数週間経過してから出現する副作用〈有害事象〉はどれか。
- 溶血性反応
- 末梢血管収縮反応
- アナフィラキシー反応
- 輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉
▶午前40
上部消化管内視鏡検査について適切なのはどれか。
- 2時間前から絶飲食とする。
- 前投薬には筋弛緩薬を用いる。
- 体位は左側臥位とする。
- 終了直後から飲食は可能である。
▶午前41
全身麻酔下で食道再建術を受ける患者への術前オリエンテーションで適切なのはどれか。
- 「口から息を吸って鼻から吐く練習をしてください」
- 「手術の直前に下剤を飲んでもらいます」
- 「手術中はコンタクトレンズをつけたままで良いです」
- 「麻酔の際は喉に呼吸用の管を入れます」
生活習慣が発症に関連している疾患はどれか。
- 肺気腫
- 1型糖尿病
- 肥大型心筋症
- 重症筋無力症
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。
- 中皮腫
- C型肝炎
- 慢性腎不全
- 再生不良性貧血
▶午前44
慢性疾患の患者に対する自己管理の支援で最も適切なのはどれか。
- 患者自身の失敗体験をもとに指導する。
- 病気に関する広範囲な知識を提供する。
- 症状に慣れる方法を身につけるように促す。
- 自分の身体徴候を把握するように指導する。
▶午前45
Aさん(56歳、男性)は、化学療法後の血液検査にて好中球数300/mm3であった。
Aさんの状態で正しいのはどれか。
- 入浴を控える必要がある。
- 日和見感染症のリスクが高い。
- 口腔ケアには歯間ブラシを用いる必要がある。
- 化学療法の開始前と比べリンパ球数は増加している。
▶午前46
Aさん(35歳、男性)。身長175cm、体重74kgである。1か月前から腰痛と右下肢のしびれが続くため受診した。腰椎椎間板ヘルニアと診断され、保存的療法で経過をみることになった。
Aさんへの生活指導として適切なのはどれか。
- 「体重を減らしましょう」
- 「痛いときは冷罨法が効果的です」
- 「前かがみの姿勢を控えましょう」
- 「腰の下に枕を入れて寝ると良いですよ」
▶午前47
老年期の心理社会的葛藤を「統合」対「絶望」と表現した人物はどれか。
- ペック, R. C.
- バトラー, R. N.
- エリクソン, E. H.
- ハヴィガースト, R. J.
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における65歳以上の高齢者がいる世帯について正しいのはどれか。
- 単独世帯は1割である。
- 三世代世帯は3割である。
- 夫婦のみの世帯は4割である。
- 親と未婚の子のみの世帯は2割である。
Aさん(66歳、男性)は、Lewy〈レビー〉小体型認知症であるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を初めて利用することとなった。施設の看護師は、同居している家族から「以前、入院したときに、ご飯にかかっているゴマを虫だと言って騒いだことがあったが、自宅ではそのような様子はみられない」と聞いた。
入所当日の夜間の対応で適切なのはどれか。
- 虫はいないと説明する。
- 部屋の照明をつけたままにする。
- 細かい模様のある物は片付ける。
- 窓のカーテンは開けたままにする。
▶午前50
Aさん(70歳、女性)。夫(72歳)と2人暮らし。慢性腎不全のため腹膜透析を行うことになった。認知機能や身体機能の障害はない。腹膜透析について説明を受けた後、Aさんは「私のように高齢でも自分で腹膜透析をできるのか心配です。毎日続けられるでしょうか」と話した。
Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 「誰でも簡単にできます」
- 「ご家族に操作をしてもらいましょう」
- 「訪問看護師に毎日見守ってもらいましょう」
- 「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」
▶午前51
Aさん(80歳、女性)。大腿骨頸部骨折のため人工骨頭置換術を受けた。手術後14日、Aさんの経過は順調で歩行訓練を行っている。歩行による疼痛の訴えはない。
現在のAさんの状態で最も注意すべきなのはどれか。
- せん妄
- 創部感染
- 股関節脱臼
- 深部静脈血栓症
▶午前52
胎生期から小児期の血清免疫グロブリン濃度の年齢による変動を図に示す。
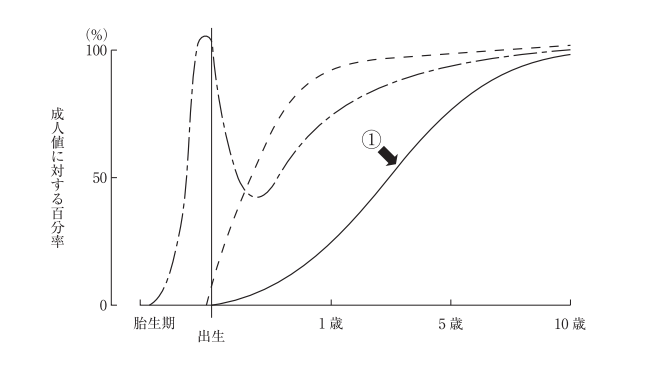
①が示しているのはどれか。
- IgA
- IgD
- IgG
- IgM
▶午前53
Aちゃん(生後4か月、女児)は、嘔吐とけいれんのため病院を受診した。受診時、Aちゃんは傾眠状態で、顔色不良と眼球上転がみられたため入院となった。
受診時の体温は36.8℃であった。四肢は硬直し、数か所の内出血斑があった。大泉門は平坦であったが、次第に膨隆を認めるようになった。このときの頭部CTを別に示す。
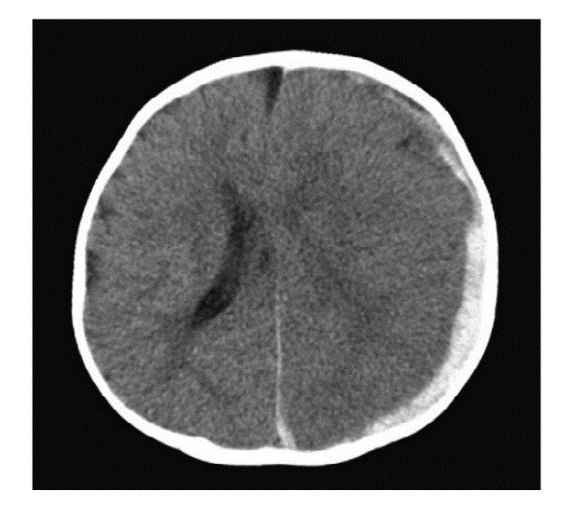
Aちゃんの所見として考えられるのはどれか。
- 急性脳症
- てんかん
- 硬膜下血腫
- 細菌性髄膜炎
▶午前54
性同一性障害〈GID〉/性別違和〈GD〉について正しいのはどれか。
- 出現するのは成人期以降である。
- ホルモン療法の対象にはならない。
- 生物学的性と性の自己認識とが一致しない。
- 生物学的性と同一の性への恋愛感情をもつことである。
▶午前55
ルービン, R.による母親役割獲得過程におけるロールプレイはどれか。
- 友人の出産体験を聞く。
- 人形で沐浴の練習をする。
- 購入する育児用品を考える。
- 看護師が行う児の抱き方を見る。
産科外来を初めて受診した妊婦。夫婦ともに外国籍で、日本の在留資格を取得している。
この妊婦への説明で正しいのはどれか。
- 「母子健康手帳は有料で入手できます」
- 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」
- 「出生届は外務省に提出します」
- 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」
大震災の2日後、避難所にいる成人への心理的援助で適切なのはどれか。
- 宗教の多様性への配慮は後で行う。
- 会話が途切れないように話しかける。
- 確証がなくても安全であると保証する。
- ストレス反応に関する情報提供を行う。
▶午前58
修正型電気けいれん療法について正しいのはどれか。
- 保護室で行う。
- 全身麻酔下で行う。
- 強直間代発作が生じる。
- 発生頻度の高い合併症は骨折である。
自殺念慮を訴える患者で、自殺が最も切迫している状態はどれか。
- 自殺の手段が未定である。
- 自殺する日を決めている。
- 将来の希望について時々話す。
- 普段と変わらない様子で生活している。
養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉に基づき通報する先として正しいのはどれか。
- 市町村
- 警察署
- 消防署
- 訪問看護事業所
▶午前61
Aさん(83歳、男性)は、脳梗塞の後遺症で右片麻痺があり、在宅療養中である。
嚥下障害のため胃瘻を造設している。義歯を装着しているが、自分の歯が数本残っている。
Aさんの口腔ケアについて、介護者への指導で適切なのはどれか。
- 義歯を装着したまま歯を磨く。
- 経管栄養直後に実施する。
- ペースト状の歯磨剤を使用する。
- 歯垢の除去には歯ブラシを用いる。
特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。
- 提供できる頻度は週に3回までである。
- 提供できる期間は最大6か月である。
- 対象に指定難病は含まない。
- 医療保険が適用される。
要介護2と認定された高齢者の在宅療養支援において、支援に関与する者とその役割の組合せで適切なのはどれか。
- 介護支援専門員――家事の援助
- 市町村保健師――居宅サービス計画書の作成
- 訪問看護師――日常生活動作〈ADL〉の向上のための訓練
- 訪問介護員――運動機能の評価
日本の医療保険制度について正しいのはどれか。
- 健康診断は医療保険が適用される。
- 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。
- 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。
- 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。
日本の医療提供施設について正しいのはどれか。
- 病院数は1995年から増加傾向である。
- 2019年の人口対病床数は先進国の中で最も多い。
- 介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。
- 精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
- 医療法
- 労働契約法
- 教育基本法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
災害医療について正しいのはどれか。
- 災害拠点病院は市町村が指定する。
- 医療計画の中に災害医療が含まれる。
- 防災訓練は災害救助法に規定されている。
- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。
▶午前68
小腸で消化吸収される栄養素のうち、胸管を通って輸送されるのはどれか。
- 糖質
- 蛋白質
- 電解質
- 中性脂肪
- 水溶性ビタミン
▶午前69
性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンはどれか。
- アルドステロン
- プロゲステロン
- エストラジオール
- 黄体形成ホルモン〈LH〉
- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉
▶午前70
腹部CTを別に示す。
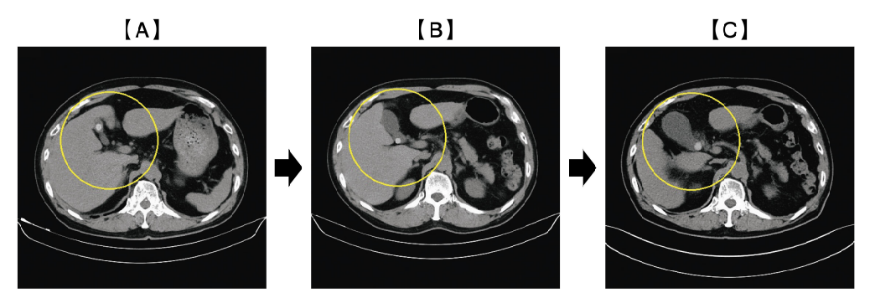
胆石が半年間で胆囊内をAからCまで移動した。
Cの状態を表すのはどれか。
- 嵌頓
- 侵入
- 転位
- 停留
- 迷入
▶午前71
胸腺腫に合併する疾患で多くみられるのはどれか。
- Parkinson〈パーキンソン〉病
- 筋ジストロフィー
- 重症筋無力症
- 多発性硬化症
- 多発性筋炎
▶午前72
頭部CTを別に示す。
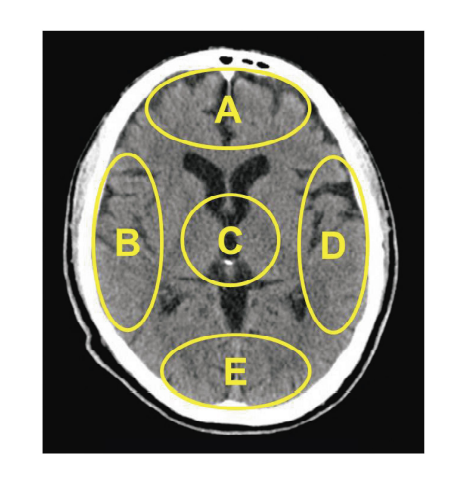
論理的思考を制御する領域はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
糖尿病の合併症のうち、健康日本21(第三次)の目標に含まれるのはどれか。
- 腎症
- 感染症
- 網膜症
- 神経障害
- 血行障害
▶午前74
創傷の治癒過程で炎症期に起こる現象はどれか。
- 創傷周囲の線維芽細胞が活性化する。
- 肉芽の形成が促進される。
- 滲出液が創に溜まる。
- 創の収縮が起こる。
- 上皮化が起こる。
▶午前75
Ménière〈メニエール〉病の患者への指導内容について正しいのはどれか。
- 静かな環境を保持する。
- 発作時は部屋を明るくする。
- めまいがあるときは一点を凝視する。
- 嘔吐を伴う場合は仰臥位安静にする。
- 耳鳴があるときは周囲の音を遮断する。
▶午前76
車椅子での座位の姿勢を別に示す。

このような姿勢を長時間続けることで最も褥瘡が発生しやすい部位はどれか。
- 右肘関節部
- 右大転子部
- 左坐骨結節部
- 左膝関節外側部
- 左足関節外果部
令和5年(2023年)の人口動態統計において、1~4歳の死因で最も多いのはどれか。
- 肺炎
- 心疾患
- 悪性新生物
- 不慮の事故
- 先天奇形、変形及び染色体異常
▶午前78
Aちゃん(8歳、女児)は、白血病の終末期で入院しているが、病状は安定している。両親と姉のBちゃん(10歳)の4人家族である。
Aちゃんの家族へ看護師が伝える内容として適切なのはどれか。
- 「Aちゃんは外出できません」
- 「Bちゃんは面会できません」
- 「Aちゃんが食べたい物を食べて良いです」
- 「Aちゃんよりもご家族の意思を優先します」
- 「Aちゃんに終末期であることは伝えないでください」
Aさん(28歳、女性)は、2歳の子どもを養育しながら働いている。
Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。
- 児童福祉法
- 労働基準法
- 男女共同参画社会基本法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
▶午前80
難病患者が自分の病気について学ぶことで不安を解消しようとする防衛機制はどれか。
- 否認
- 昇華
- 知性化
- 合理化
- 反動形成
▶午前81
新人看護師のAさんは、夜勤の看護師からの引き継ぎが終了した後、日勤で行う業務を書き出した。
Aさんが書き出した以下の業務のうち最も優先して行うのはどれか。
- 頭部の搔痒感を訴える患者の洗髪
- 夜間せん妄のあった患者との散歩
- 午後に入院する患者の診療録の準備
- 翌日に検査を受ける予定の患者への説明
- 人工呼吸器を装着中の患者の状態の確認
▶午前82
車軸関節はどれか。2つ選べ。
- 正中環軸関節
- 腕尺関節
- 上橈尺関節
- 指節間関節
- 顎関節
▶午前84
パルスオキシメータを別に示す。

表示されている数値が示すのはどれか。2つ選べ。
- 脈拍数
- 酸素分圧
- 酸素飽和度
- 重炭酸濃度
- 二酸化炭素濃度
▶午前85
網膜剝離について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 確定診断のために眼底検査を行う。
- 前駆症状として光視症がみられる。
- 初期症状として夜盲がみられる。
- 失明には至らない。
- 若年者に好発する。
労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- 妊娠の届出
- 妊婦の保健指導
- 産前産後の休業
- 配偶者の育児休業
- 妊産婦の時間外労働の制限
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 本人より先に家族に病名を告知する。
- 国内では異性間性的接触による感染が最も多い。
- 適切な対応によって母子感染率を下げることができる。
- 性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。
- HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。
▶午前88
Aさん(63歳、男性)。BMI24。前立腺肥大症のため経尿道的前立腺切除術を受け、手術後3日で膀胱留置カテーテルが抜去された。数日後に退院する予定である。
Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 散歩を控える。
- 水分摂取を促す。
- 長時間の座位を控える。
- 時間をかけて入浴する。
- 排便時に強くいきまないようにする。
精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 行動制限の理由を患者に説明する。
- 原則として2名以上のスタッフで対応する。
- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
- 精神保健指定医による診察は週1回とする。
- 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。
▶午前90
3L/分で酸素療法中の入院患者が、500L酸素ボンベ(14.7MPaで充塡)を用いて移動した。現在の酸素ボンベの圧力計は5MPaを示している。
酸素ボンベの残りの使用可能時間を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②分
資料 厚生労働省「第104回保健師国家試験、第101回助産師国家試験、第107回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第107回看護師国家試験
平成29年2月19日(日)に実施された第106回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第106回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後26
刺激伝導系でないのはどれか。
- 腱索
- 洞房結節
- 房室結節
- Purkinje〈プルキンエ〉線維
▶午後27
アルドステロンで正しいのはどれか。
- 近位尿細管に作用する。
- 副腎髄質から分泌される。
- ナトリウムの再吸収を促進する。
- アンジオテンシンⅠによって分泌が促進される。
▶午後28
慢性閉塞性肺疾患について正しいのはどれか。
- 残気量は減少する。
- %肺活量の低下が著明である。
- 肺コンプライアンスは上昇する。
- 可逆性の気流閉塞が特徴である。
▶午後29
腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。
- 高齢の女性に多発する。
- 診断にはMRIが有用である。
- 好発部位は第1・2腰椎間である。
- 急性期では手術による治療を行う。
配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。
- 一時保護
- 就労の仲介
- 外傷の治療
- 生活資金の給付
施行日が最も新しい法律はどれか。
- 高齢社会対策基本法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
▶午後34
車椅子による移送で適切なのはどれか。
- エレベーターの中で方向転換する。
- 急な下り坂では前向きに車椅子を進める。
- ティッピングレバーを踏み、段差を乗り越える。
- 移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を下げる。
病室環境に適した照度はどれか。
- 100〜200ルクス
- 300〜400ルクス
- 500〜600ルクス
- 700〜800ルクス
▶午後36
検査の目的と採尿方法の組合せで正しいのはどれか。
- 細菌の特定――中間尿
- 腎機能の評価――杯分尿
- 肝機能の評価――24時間尿
- 尿道の病変の推定――早朝尿
職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。
- 労働組合法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働関係調整法
▶午後38
合併症のない全身状態が良好な患者に対して、全身麻酔のための気管挿管を行い用手換気をしたところ、左胸郭の挙上が不良であった。
原因として考えられるのはどれか。
- 無気肺
- 食道挿管
- 片肺挿管
- 換気量不足
▶午後39
脳出血の後遺症で左片麻痺と嚥下障害のある患者の家族に、食事介助の指導を行うときの説明で適切なのはどれか。
- 「食材にこんにゃくを入れると良いですよ」
- 「体を起こしたら、左の脇の下をクッションで支えましょう」
- 「口の左側に食べ物を入れるようにしましょう」
- 「飲み込むときに咳が出なければ誤嚥の心配はありません」
▶午後40
自助具を図に示す。
関節リウマチによって肩関節に痛みがある患者の関節保護のための自助具として最も適切なのはどれか。
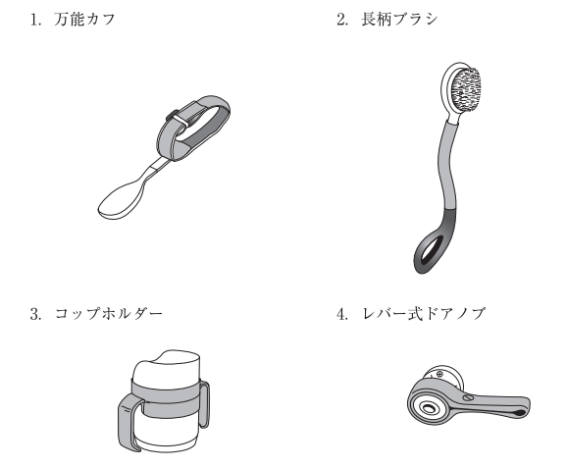
▶午後41
Aさん(59歳、女性)は、半年前に下咽頭癌で放射線治療を受けた。口腔内が乾燥し、水を飲まないと話すことも不自由なことがある。
Aさんに起こりやすいのはどれか。
- う歯
- 顎骨壊死
- 嗅覚障害
- 甲状腺機能亢進症
▶午後42
1型糖尿病と診断された人への説明で適切なのはどれか。
- 自己血糖測定の試験紙の費用は医療保険の対象外である。
- 食事が摂取できないときはインスリン注射を中止する。
- 低血糖症状には振戦などの自律神経症状がある。
- 運動は朝食前が効果的である。
▶午後43
アレルギー性鼻炎について正しいのはどれか。
- 食後に症状が増悪する。
- Ⅳ型アレルギーである。
- スクラッチテストで原因を検索する。
- アレルゲンの除去は症状の抑制に有効である。
▶午後44
他動運動による関節可動域〈ROM〉訓練を行うときの注意点で適切なのはどれか。
- 有酸素運動を取り入れる。
- 等尺性運動を取り入れる。
- 近位の関節を支持して行う。
- 痛みがある場合は速く動かす。
Aさん(80歳、女性)は、要介護となったため長男家族(長男50歳、長男の妻45歳、18歳と16歳の孫)と同居することとなった。在宅介護はこの家族にとって初めての経験である。
Aさんの家族が新たな生活に適応していくための対処方法で最も適切なのはどれか。
- 活用できる在宅サービスをできる限り多く利用する。
- 家族が持つニーズよりもAさんのニーズを優先する。
- 介護の負担が特定の家族に集中しないように家族で話し合う。
- 10代の子どもを持つ家族の発達課題への取り組みを一時保留にする。
令和4年(2022年)の就業構造基本調査における65歳以上75歳未満の高齢者の就業について正しいのはどれか。
- 女性では就業している者の割合は40%以上である。
- 就業していない者よりも就業している者の割合が多い。
- 就業していない者のうち40%以上が就業を希望している。
- 就業している者のうち非正規職員・従業員の割合は成人期より多い。
▶午後47
高齢者施設に入所中のAさん(78歳、女性)は、長期間寝たきり状態で、便秘傾向のため下剤を内服している。下腹部痛と便意を訴えるが3日以上排便がなく、浣腸を行うと短く硬い便塊の後に、多量の軟便が排泄されることが数回続いている。既往歴に、消化管の疾患や痔はない。
Aさんの今後の排便に対する看護として最も適切なのはどれか。
- 直腸の便塊の有無を確認する。
- 止痢薬の処方を医師に依頼する。
- 1日の水分摂取量を800mL程度とする。
- 食物繊維の少ない食事への変更を提案する。
▶午後48
老年期のうつ病に特徴的な症状はどれか。
- 幻覚
- 感情鈍麻
- 心気症状
- 着衣失行
▶午後49
高齢者に術後の呼吸器合併症が発症しやすい理由で正しいのはどれか。
- 残気量の減少
- 肺活量の低下
- 嚥下反射の閾値の低下
- 気道の線毛運動の亢進
学童期の肥満について正しいのはどれか。
- 肥満傾向児は肥満度30%以上と定義される。
- 肥満傾向児は高学年より低学年が多い。
- 肥満傾向児は男子より女子が多い。
- 成人期の肥満に移行しやすい。
▶午後51
外性器異常が疑われた新生児の親への対応として適切なのはどれか。
- 出生直後に性別を伝える。
- 内性器には異常がないことを伝える。
- 出生直後に母児の早期接触を行わない。
- 出生届は性別保留で提出できることを説明する。
▶午後52
受胎のメカニズムで正しいのはどれか。
- 排卵は黄体形成ホルモン〈LH〉の分泌が減少して起こる。
- 卵子の受精能力は排卵後72時間持続する。
- 受精は卵管膨大部で起こることが多い。
- 受精後2日で受精卵は着床を完了する。
▶午後53
成熟期女性の受胎調節について適切なのはどれか。
- 経口避妊薬は女性が主導で使用できる。
- コンドーム法の避妊効果は99%以上である。
- 基礎体温法は月経が不順な女性に有用である。
- 子宮内避妊器具〈IUD〉は経産婦より未産婦に挿入しやすい。
▶午後55
Aさん(65歳、男性)は、胃癌を疑われ検査入院した。入院時、認知機能に問題はなかった。不眠を訴え、入院翌日からベンゾジアゼピン系の睡眠薬の内服が開始された。その日の夜、Aさんは突然ナースステーションに来て、意味不明な内容を叫んでいた。翌朝、Aさんは穏やかに話し意思疎通も取れたが「昨夜のことは覚えていない」と言う。
Aさんの昨夜の行動のアセスメントで最も適切なのはどれか。
- 観念奔逸
- 感情失禁
- 妄想気分
- 夜間せん妄
2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
- 応急入院
- 措置入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
▶午後57
Aさん(65歳、男性)は、肺気腫で在宅酸素療法を受けている。ある日、Aさんの妻(70歳)から「同居している孫がインフルエンザにかかりました。今朝から夫も体が熱く、ぐったりしています」と訪問看護ステーションに電話で連絡があったため緊急訪問した。
訪問看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。
- 喀痰の性状
- 胸痛の有無
- 関節痛の有無
- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉
地域包括ケアシステムについて正しいのはどれか。
- 都道府県を単位として構築することが想定されている。
- 75歳以上の人口が急増する地域に重点が置かれている。
- 本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている。
- 地域特性にかかわらず同じサービスが受けられることを目指している。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。
- 育成医療
- 居宅療養管理指導
- 共同生活援助〈グループホーム〉
- 介護予防通所リハビリテーション
▶午後60
Aさん(55歳、女性)は、夫と2人で暮らしている。進行性の多発性硬化症で在宅療養をしている。脊髄系の症状が主で、両下肢の麻痺、膀胱直腸障害および尿閉がある。最近は座位の保持が難しく、疲れやすくなってきている。排尿はセルフカテーテルを使用してAさんが自己導尿を行い、排便は訪問看護師が浣腸を行っている。夫は仕事のため日中は不在である。
Aさんの身体状態に合わせた療養生活で適切なのはどれか。
- 入浴はシャワー浴とする。
- 介助型の車椅子を利用する。
- ベッドの高さは最低の位置で固定する。
- セルフカテーテルはトイレに保管する。
医療の標準化を目的に活用されているのはどれか。
- コーピング
- クリニカルパス
- エンパワメント
- コンサルテーション
▶午後62
Aさん(27歳、男性)は、地震によって倒壊した建物に下腿を挟まれていたが、2日後に救出された。既往歴に特記すべきことはない。
注意すべき状態はどれか。
- 尿崩症
- 高カリウム血症
- 低ミオグロビン血症
- 代謝性アルカローシス
災害医療におけるトリアージについて正しいのはどれか。
- 傷病者を病名によって分類する。
- 危険区域と安全区域を分けることである。
- 医療資源の効率的な配分のために行われる。
- 救命が困難な患者に対する治療を優先する。
国際保健に関する機関について正しいのはどれか。
- 国際協力機構〈JICA〉は国境なき医師団の派遣を行う。
- 国連開発計画〈UNDP〉は労働者の健康保護の勧告を行う。
- 世界保健機関〈WHO〉は国際疾病分類〈ICD〉を定めている。
- 赤十字国際委員会〈ICRC〉は国際連合〈UN〉の機関の1つである。
▶午後65
女性の骨盤腔内器官について腹側から背側への配列で正しいのはどれか。
- 尿道――肛門管――腟
- 腟――尿道――肛門管
- 肛門管――腟――尿道
- 尿道――腟――肛門管
- 腟――肛門管――尿道
公的年金制度について正しいのはどれか。
- 学生は申請によって納付が免除される。
- 生活保護を受けると支給が停止される。
- 保険料が主要財源である。
- 任意加入である。
- 積立方式である。
健康に影響を及ぼす生活環境とそれを規定している法律の組合せで正しいのはどれか。
- 上水道水質――汚濁防止法
- 飲食店――食品衛生法
- 家庭ごみ――悪臭防止法
- 学校環境――教育基本法
- 住宅用の建築材料――環境基本法
チェーンソーの使用によって生じるのはどれか。
- じん肺
- 視力低下
- 心筋梗塞
- 肘関節の拘縮
- Raynaud〈レイノー〉現象
▶午後69
Aさん(61歳、男性)は、水分が飲み込めないため入院した。高度の狭窄を伴う進行食道癌と診断され、中心静脈栄養が開始された。入院後1週、Aさんは口渇と全身倦怠感を訴えた。意識は清明であり、バイタルサインは脈拍108/分、血圧98/70mmHgであった。尿量は1,600mL/日で、血液検査データは、アルブミン3.5g/dL、AST〈GOT〉45IU/L、ALT〈GPT〉40IU/L、クレアチニン1.1mg/dL、血糖190mg/dL、Hb11.0g/dLであった。
Aさんの口渇と全身倦怠感の要因として最も考えられるのはどれか。
- 貧血
- 低栄養
- 高血糖
- 腎機能障害
- 肝機能障害
▶午後70
病的な老化を示すのはどれか。
- 肝臓の萎縮
- 動脈の粥状硬化
- 毛様体筋の機能低下
- 心筋の弾性線維の減少
- 膀胱の平滑筋の線維化
▶午後71
生後1か月の男児。Hirschsprung〈ヒルシュスプルング〉病と診断され、生後6日、回腸部にストーマ造設術を行った。術後の経過は良好であり、退院に向けてストーマケアに関する指導を行うことになった。
母親に対する指導として適切なのはどれか。
- 「面板をはがした部位はタオルで拭いてください」
- 「ストーマ装具の交換は授乳直後に行ってください」
- 「ストーマから水様の便が出る時は受診してください」
- 「ストーマ装具の交換は滅菌手袋を装着して行ってください」
- 「ストーマ装具は便を捨てる部分が体の外側に向くように貼ってください」
▶午後73
ホメオスタシスに関与するのはどれか。2つ選べ。
- 味蕾
- 筋紡錘
- 痛覚受容器
- 浸透圧受容器
- 中枢化学受容体
▶午後74
眼球内での光の通路に関与するのはどれか。2つ選べ。
- 強膜
- 脈絡膜
- 毛様体
- 硝子体
- 水晶体
▶午後75
排便時の努責で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 直腸平滑筋は弛緩する。
- 呼息位で呼吸が止まる。
- 外肛門括約筋は収縮する。
- 内肛門括約筋は弛緩する。
- 腹腔内圧は安静時より低下する。
▶午後76
急性炎症と比較して慢性炎症に特徴的な所見はどれか。2つ選べ。
- 好中球浸潤
- CRPの上昇
- リンパ球浸潤
- 形質細胞の浸潤
- 血管透過性の亢進
▶午後77
狭心症の治療に用いる薬はどれか。2つ選べ。
- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
- スルホニル尿素薬
- ジギタリス製剤
- 抗血小板薬
- 硝酸薬
▶午後78
出血傾向を把握するために重要なのはどれか。2つ選べ。
- 血糖値
- 血清鉄
- 血小板数
- アルカリフォスファターゼ値
- 活性化部分トロンボプラスチン時間〈APTT〉
▶午後79
胃食道逆流症について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 食道の扁平上皮化生を起こす。
- 上部食道括約筋の弛緩によって生じる。
- 食道炎の程度と症状の強さが一致する。
- プロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法である。
- Barrett〈バレット〉上皮は腺癌の発生リスクが高い。
▶午後80
患者の自立支援で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 不足している知識を補う。
- 発病前の生活習慣を尊重する。
- 支援目標を看護師があらかじめ定める。
- できないことに焦点を当てて行動を修正する。
- 支援者である看護師が上位の関係が望ましい。
▶午後81
腹圧性尿失禁のケアとして適切なのはどれか。2つ選べ。
- 下腹部を保温する。
- 骨盤底筋群訓練を促す。
- 定期的な水分摂取を促す。
- 恥骨上部の圧迫を指導する。
- 尿意を感じたら早めにトイレへ行くことを促す。
▶午後82
手段的日常生活動作〈IADL〉はどれか。2つ選べ。
- 食事
- 洗濯
- 入浴
- 更衣
- 買い物
▶午後83
開放性損傷はどれか。2つ選べ。
- 切創
- 打撲傷
- 擦過創
- 皮下出血
- 内臓損傷
児童憲章について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 児童がよい環境の中で育てられることを定めている。
- 児童の権利に関する条約を受けて制定された。
- 児童が人として尊ばれることを定めている。
- 保護者の責務を定めている。
- 違反すると罰則規定がある。
▶午後85
急性中耳炎で内服薬による治療を受けた5歳の男児および保護者に対して、治癒後に行う生活指導で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 片側ずつ鼻をかむ。
- 耳垢は毎日除去する。
- 入浴時は耳栓を使用する。
- 大声を出させないようにする。
- 発熱時は耳漏の有無を確認する。
▶午後86
Aさん(50歳、女性)は、急に体が熱くなったり汗をかいたりし、夜は眠れなくなり疲れやすさを感じるようになった。月経はこの1年間で2回あった。
Aさんのホルモンで上昇しているのはどれか。2つ選べ。
- エストロゲン
- プロラクチン
- プロゲステロン
- 黄体形成ホルモン〈LH〉
- 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉
▶午後87
医療現場における暴力について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 精神科に特有のものである。
- 病室環境は誘因にならない。
- 目撃者は被害者に含まれない。
- 暴力予防プログラムに合わせて対処する。
- 発生を防止するためには組織的な体制の整備が重要である。
精神医療におけるピアサポーターの活動について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 訪問活動は禁止されている。
- 活動には専門家の同行が条件となる。
- ピアサポーター自身の回復が促進される。
- 精神保健医療福祉サービスの利用を終了していることが条件となる。
- 自分の精神障害の経験を活かして同様の体験をしている人を支援する。
▶午後89
6%A消毒液を用いて、医療器材の消毒用の0.02%A消毒液を1,500mL作るために必要な6%A消毒液の量を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:①.②mL
▶午後90
体重9.6kgの患児に、小児用輸液セットを用いて体重1kg当たり1日100mLの輸液を行う。このときの1分間の滴下数を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②滴/分
資料 厚生労働省「第103回保健師国家試験、第100回助産師国家試験、第106回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第106回看護師国家試験
平成29年2月19日(日)に実施された第106回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第106回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
▶午前10(必修除外)
ヒューマンエラーによる医療事故を防止するための対策で最も適切なのはどれか。
- 性格検査の実施
- 事故発生時の罰則の規定
- 注意力強化のための訓練の実施
- 操作を誤りにくい医療機器の導入
▶午前15(必修除外)
せん妄の誘発因子はどれか。
- 身体拘束
- 心血管障害
- 低栄養状態
- 電解質バランス異常
▶午前26
単層円柱上皮はどれか。
- 表皮
- 腹膜
- 膀胱
- 胃
▶午前27
角加速度を感知するのはどれか。
- 耳管
- 前庭
- 耳小骨
- 半規管
▶午前28
縦隔に含まれるのはどれか。
- 肺
- 胸腺
- 副腎
- 甲状腺
▶午前29
膵液について正しいのはどれか。
- 弱アルカリ性である。
- 糖質分解酵素を含まない。
- セクレチンによって分泌量が減少する。
- Langerhans〈ランゲルハンス〉島のβ細胞から分泌される。
▶午前30
ホルモンと分泌部位の組合せで正しいのはどれか。
- サイロキシン――副甲状腺
- テストステロン――前立腺
- バソプレシン――副腎皮質
- プロラクチン――下垂体前葉
▶午前31
腹部CTを別に示す。
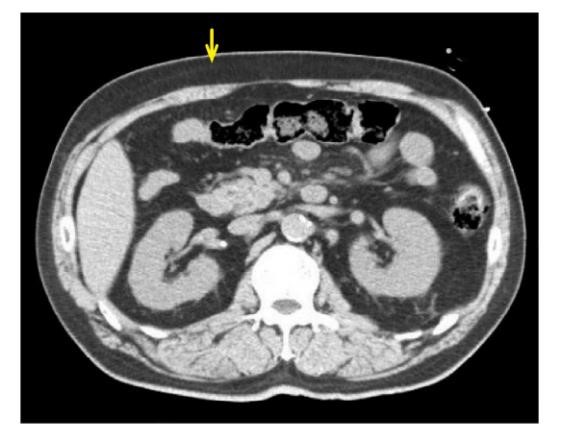
矢印で示す部位について正しいのはどれか。
- 肥満細胞で構成される。
- 厚さはBMIの算出に用いられる。
- 厚い場合は洋梨型の体型の肥満が特徴的である。
- 厚い場合はメタボリックシンドロームと診断される。
▶午前32
放射線療法について正しいのはどれか。
- Gyは吸収線量を表す。
- 主に非電離放射線を用いる。
- 電子線は生体の深部まで到達する。
- 多門照射によって正常組織への線量が増加する。
▶午前33
Alzheimer〈アルツハイマー〉病で正しいのはどれか。
- 基礎疾患として高血圧症が多い。
- 初期には記銘力障害はみられない。
- アミロイドβタンパクが蓄積する。
- MRI所見では前頭葉の萎縮が特徴的である。
▶午前34
ペースメーカー装着患者における右心室ペーシング波形の心電図を別に示す。
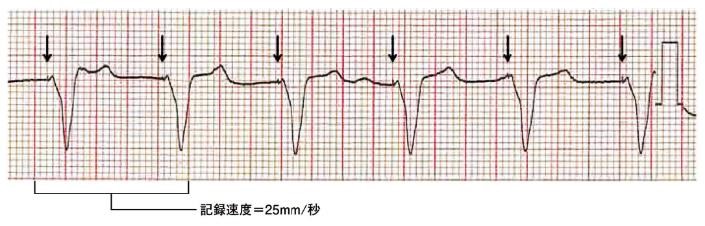
心電図の記録速度は通常の25mm/秒であり、矢印で示した小さなノッチがペースメーカーからの電気刺激が入るタイミングを示している。
心電図波形によって計測した心拍数で正しいのはどれか。
- 30/分以上、50/分未満
- 50/分以上、70/分未満
- 70/分以上、90/分未満
- 90/分以上、99/分以下
労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。
- 失業時の教育訓練給付金
- 災害発生時の超過勤務手当
- 有害業務従事者の健康診断
- 業務上の事故による介護補償給付
高齢者における肺炎の三次予防はどれか。
- 口腔内の衛生管理
- 肺炎球菌ワクチンの接種
- 呼吸リハビリテーション
- 健康診断での胸部エックス線撮影
▶午前37
患者と看護師の関係において、ラポールを意味するのはどれか。
- 侵されたくない個人の空間
- 人間対人間の関係の確立
- 意図的な身体への接触
- 自己開示
▶午前38
看護における情報について正しいのはどれか。
- 尺度で測定された患者の心理状態は主観的情報である。
- 入院費用に関する患者の不安は客観的情報である。
- 観察した食事摂取量は客観的情報である。
- 既往歴は主観的情報である。
▶午前39
Barré〈バレー〉徴候の査定の開始時と判定時の写真を別に示す。
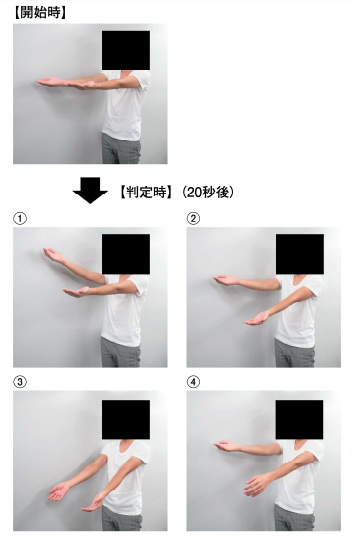
左上肢のBarré〈バレー〉徴候陽性を示すのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
▶午前40
入院中の妻を亡くした直後の夫へのグリーフケアで最も適切なのはどれか。
- 妻の話を夫とすることは避ける。
- 夫の悲嘆が軽減してからケアを開始する。
- 夫が希望する場合は死後の処置を一緒に行う。
- 妻を亡くした夫のためのサポートグループへの参加を促す。
▶午前41
ヨード制限食が提供されるのはどれか。
- 甲状腺シンチグラフィ
- 慢性腎不全の治療
- 肝臓の庇護
- 貧血の治療
▶午前42
体位が身体に与える影響について正しいのはどれか。
- 座位から仰臥位になると楽に呼吸ができる。
- 立位と比較して座位の方が収縮期血圧は低い。
- 仰臥位から急に立位になると脈拍が速くなる。
- 立位からTrendelenburg〈トレンデレンブルグ〉位になると収縮期血圧が下降する。
▶午前43
洗髪を行うときに、患者のエネルギー消費が最も少ない体位はどれか。
- 仰臥位
- 端座位
- 起座位
- Fowler〈ファウラー〉位
▶午前44
前腕部からの動脈性の外出血に対する用手間接圧迫法で血流を遮断するのはどれか。
- 鎖骨下動脈
- 腋窩動脈
- 上腕動脈
- 橈骨動脈
看護師が医療事故を起こした場合の法的責任について正しいのはどれか。
- 罰金以上の刑に処せられた者は行政処分の対象となる。
- 事故の程度にかかわらず業務停止の処分を受ける。
- 民事責任として業務上過失致死傷罪に問われる。
- 刑法に基づき所属施設が使用者責任を問われる。
疾患と原因となる生活習慣の組合せで適切なのはどれか。
- 低血圧症――飲酒
- 心筋梗塞――長時間労働
- 悪性中皮腫――喫煙
- 1型糖尿病――過食
自動体外式除細動器〈AED〉による電気的除細動の適応となるのはどれか。
- 心静止
- 心房細動
- 心室細動
- 房室ブロック
▶午前48
術中の仰臥位の保持によって発生することがある腕神経叢麻痺の原因はどれか。
- 上腕の持続的圧迫
- 前腕の回外の持続
- 肘関節の持続的圧迫
- 上肢の90度以上の外転
▶午前49
点滴静脈内注射によって抗癌薬を投与している患者の看護で適切なのはどれか。
- 悪心は薬で緩和する。
- 留置針は原則として手背に挿入する。
- 血管痛がある場合は直ちに留置針を差し替える。
- 2回目以降の投与では過敏症の症状の確認は必要ない。
▶午前50
Aさん(60歳、男性)は、慢性心不全の終末期で、積極的な治療を行わないことを希望している。現在、入院中で、リザーバーマスク10L/分で酸素を吸入し、水分制限がある。時々息切れがみられるが、Aさんは面会に来た長女との会話を楽しみにしている。バイタルサインは呼吸数28/分、脈拍110/分、血圧76/50mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%であった。
このときの対応で最も適切なのはどれか。
- 面会は制限しない。
- 水分制限を厳しくする。
- Aさんに仰臥位を維持してもらう。
- 面会中は酸素マスクを鼻腔カニューラに変更する。
Aさん(42歳、女性)は、3日前から微熱と強い全身倦怠感を自覚したため病院を受診したところ、肝機能障害が認められ、急性肝炎の診断で入院した。1か月前に生の牡蠣を摂取している。Aさんはこれまで肝臓に異常を指摘されたことはなく、家族で肝臓疾患を罹患した者はいない。
Aさんが罹患した肝炎について正しいのはどれか。
- 細菌感染である。
- 劇症化する危険性がある。
- 慢性肝炎に移行しやすい。
- インターフェロン療法を行う。
▶午前52
ホルモン負荷試験について正しいのはどれか。
- ホルモン分泌異常を生じている部位の推定に用いる。
- 分泌異常が疑われるホルモンを投与する。
- 前日の夕食から禁食にする。
- 入院が必要である。
▶午前53
乳癌の自己検診法の説明で適切なのはどれか。
- 月経前に行う。
- 年に1回実施する。
- 指先を立てて乳房に触る。
- 乳房の皮膚のくぼみの有無を観察する。
▶午前54
高齢者の看護において目標志向型思考を重視する理由で最も適切なのはどれか。
- 疾患の治癒促進
- 老化現象の進行の抑制
- 病態の関連図の作成の効率化
- 生活全体を豊かにするケアの実践
▶午前55
高齢者の活動と休息のリズムの調整について最も適切なのはどれか。
- 午前中に日光を浴びる機会をつくる。
- 昼食後に入浴する。
- 昼寝をしない。
- 就寝前に水分を多く摂る。
▶午前56
加齢による咀嚼・嚥下障害の特徴で正しいのはどれか。
- 咳嗽反射が低下する。
- 口腔内の残渣物が減る。
- 唾液の粘稠度が低下する。
- 食道入口部の開大が円滑になる。
▶午前57
Aさん(85歳、女性)は、両側の感音難聴で「音は聞こえるけれど、話の内容が聞き取れないので困っています」と話した。
Aさんに対する看護師の対応で適切なのはどれか。
- 大きな声で話す。
- 話の内容をより詳しく説明する。
- Aさんが文字盤を使えるようにする。
- 看護師の口の動きが見えるように話す。
Lewy〈レビー〉小体型認知症の初期にみられる症状はどれか。
- 幻視
- 失語
- 脱抑制
- 人格変化
介護保険法で「入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
出産や育児に関する社会資源と法律の組合せで正しいのはどれか。
- 入院助産――児童福祉法
- 出産扶助――母体保護法
- 出産手当金――母子保健法
- 養育医療――児童手当法
▶午前61
Aさん(16歳、女子)。身長160cm、体重40kg。1年で体重が12kg減少した。Aさんは6か月前から月経がみられないため婦人科クリニックを受診し、体重減少性無月経と診断された。
今後、Aさんの無月経が長期間続いた場合、増加することが予想されるのはどれか。
- 血糖値
- 骨吸収
- 体脂肪率
- エストロゲン
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉で正しいのはどれか。
- 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。
- 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。
- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
- 母子健康センターは被害者の保護をする。
妊婦の感染症と児への影響の組合せで正しいのはどれか。
- 風疹――白内障
- 性器ヘルペス――聴力障害
- トキソプラズマ症――先天性心疾患
- 性器クラミジア感染症――小頭症
▶午前64
Aさん(68歳、女性)は、胃癌のため入院した。入院初日に「夫も癌になって、亡くなる前に痛みで苦しんでいました。私も痛みが怖いんです」と言った。看護師は、Aさんが夫のように苦しむことへの恐怖や不安があることが分かり、Aさんとともに対処法について考えた。
この時点での患者―看護師関係の段階はどれか。
- 方向付け
- 同一化
- 開拓利用
- 問題解決
▶午前65
訪問看護の利用者に関する訪問看護と病院の外来看護の連携で適切なのはどれか。
- 訪問看護報告書は外来看護師に提出する。
- 利用者の個人情報の相互共有に利用者の承諾書は不要である。
- 利用者が使用している医療材料の情報を外来看護師と共有する。
- 訪問看護師から外来看護師に利用者の外来診察の予約を依頼する。
▶午前66
Aさん(42歳、女性)は、交通事故による脊髄損傷で入院し、リハビリテーションを受けた。Aさんの排泄の状況は、間欠的導尿による排尿と、坐薬による3日に1回の排便である。同居する夫と実母が導尿の指導を受け、退院することになった。初回の訪問看護は退院後3日目とし、その後は訪問看護を週2回受けることになった。
入院していた医療機関から提供された患者情報のうち、初回訪問のケア計画を立案するのに最も優先度の高い情報はどれか。
- 食事の摂取量
- 1日の導尿回数
- 最終排便の日時
- リハビリテーションの内容
▶午前67
A君(6歳、男児)は、父母と姉との4人で暮らしている。3歳児健康診査で運動機能の発達の遅延を指摘され、5歳のときにDuchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーの確定診断を受けた。現在は、床からの立ち上がり動作に介助が必要である。見守りが必要ではあるが、室内の歩行は自立している。在宅支援サービスは利用していない。A君の外来受診時に母親から「最近、Aの世話をしていると、8歳の姉が私にしがみついて離れないので困ります」と看護師に相談があった。
このときの看護師の対応で最も優先されるのはどれか。
- 姉の小学校の養護教諭に家庭訪問を依頼する。
- 姉にA君の歩行の見守りをさせるよう勧める。
- 短期入所を利用して父母と姉とで旅行するよう勧める。
- 居宅介護を利用して母が姉と関わる時間を確保することを提案する。
▶午前68
在宅で訪問看護師が行う要介護者の入浴に関する援助で適切なのはどれか。
- 入浴前後に水分摂取を促す。
- 浴室の換気は入浴直前に行う。
- 浴槽に入っている間に更衣の準備をする。
- 入浴前の身体状態の観察を家族に依頼する。
▶午前69
Aさん(65歳、女性)は、夫と実父との3人暮らしである。脊柱管狭窄症の術後、地域包括ケア病棟に入院中である。退院後は自宅に戻り室内で車椅子を利用する予定である。Aさんの障害高齢者の日常生活自立度判定基準はB-1である。
看護師による家族への指導で最も適切なのはどれか。
- 家族の生活習慣を中心に屋内環境を整備する。
- 夜間の車椅子によるトイレへの移動は制限する。
- 退院後の生活の課題に応じて福祉用具を選定する。
- ベッドから車椅子への移動介助にリフトの導入を勧める。
特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。
- 特定行為は診療の補助行為である。
- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。
- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。
▶午前71
ある組織では、リーダーの支援の下でグループ討議を経て方針を決定している。
このリーダーシップスタイルはどれか。
- 委任的リーダーシップ
- 参加的リーダーシップ
- 教示的リーダーシップ
- カリスマ的リーダーシップ
▶午前72
Aさん(32歳、女性)は小児専門の病院に勤務していたが、国際保健医療協力プログラムで中央アフリカ地域の州事務所に母子保健担当の看護師として派遣された。この地域は長く紛争が続き、母子の健康状態が不良と聞いた。
Aさんが現地で最初に行う業務はどれか。
- 経口補水液の配布
- 乳幼児の栄養状態の把握
- 女性の識字率向上の支援
- 病院における母子看護業務の把握
▶午前73
最も順応しにくいのはどれか。
- 視覚
- 嗅覚
- 味覚
- 触覚
- 痛覚
▶午前74
起立性低血圧について正しいのはどれか。
- 脱水との関連はない。
- 高齢者には起こりにくい。
- 塩分の過剰摂取によって起こる。
- 脳血流の一時的な増加によって生じる。
- 自律神経障害を起こす疾患で生じやすい。
令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。
- 23.7歳
- 25.7歳
- 27.7歳
- 29.7歳
- 31.7歳
人獣共通感染症で蚊が媒介するのはどれか。
- Q熱
- 黄熱
- 狂犬病
- オウム病
- 重症熱性血小板減少症候群〈SFTS〉
医療職や介護職の業務で法律に規定されているのはどれか。
- 介護福祉士は訪問看護ができる。
- 薬剤師は薬を処方することができる。
- 臨床検査技師は肘静脈から採血ができる。
- 看護師は病院の管理者となることができる。
- 診療放射線技師はエックス線写真に基づく診断ができる。
▶午前78
思春期に、親や家族との関係が依存的な関係から対等な関係に変化し、精神的に自立することを示すのはどれか。
- 自我同一性の獲得
- 心理的離乳
- 愛着形成
- 探索行動
- 母子分離
▶午前79
排泄が自立していない男児の一般尿を採尿バッグを用いて採取する方法で正しいのはどれか。
- 採尿バッグに空気が入らないようにする。
- 採尿口の下縁を陰茎の根元の位置に貼付する。
- 採尿バッグを貼付している間は座位とする。
- 採取できるまで1時間ごとに貼り替える。
- 採取後は貼付部位をアルコール綿で清拭する。
▶午前80
Aちゃん(6歳、女児)は、左上腕骨顆上骨折と診断され、牽引治療のために入院した。医師からAちゃんと家族に対し、牽引と安静臥床の必要性を説明した後、弾性包帯を用いて左上肢の介達牽引を開始した。
Aちゃんに対する看護で適切なのはどれか。
- 食事を全介助する。
- 左手指の熱感を観察する。
- 抑制ジャケットを装着する。
- 1日1回は弾性包帯を巻き直す。
- 痛みに応じて牽引の重錘の重さを変更する。
精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。
当日の看護師の対応で適切なのはどれか。
- 患者に渡さず破棄する。
- 患者による開封に立ち会う。
- 開封せず患者の家族に転送する。
- 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。
- 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。
▶午前82
潰瘍性大腸炎の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 遺伝性である。
- 直腸に好発する。
- 縦走潰瘍が特徴である。
- 大腸癌の危険因子である。
- 大量の水様性下痢が特徴である。
児童相談所について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国が設置する。
- 児童福祉司が配置されている。
- 母親を一時保護する機能を持つ。
- 知的障害に関する相談を受ける。
- 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。
国際生活機能分類〈ICF〉の構成要素はどれか。2つ選べ。
- 参加
- 休息
- 社会的不利
- 生活関連動作
- 心身機能・構造
▶午前85
Aさん(48歳、男性)は、右眼の視野に見えにくい部位があることに気付き眼科を受診した。暗い部屋で見えにくいことはない。頭痛や悪心はない。
Aさんの疾患を診断するのに必要な検査はどれか。2つ選べ。
- 脳波検査
- 色覚検査
- 眼圧測定
- 眼底検査
- 眼球運動検査
麻疹に関して正しいのはどれか。2つ選べ。
- 合併症として脳炎がある。
- 感染力は発疹期が最も強い。
- 効果的な抗ウイルス薬がある。
- 2回のワクチン定期接種が行われている。
- エンテロウイルスの感染によって発症する。
▶午前87
Aさん(30歳、女性)。月経周期は28日型で規則的である。5日間月経があり、現在、月経終了後14日が経過した。
この時期のAさんの状態で推定されるのはどれか。2つ選べ。
- 排卵後である。
- 乳房緊満感がある。
- 子宮内膜は増殖期である。
- 基礎体温は低温相である。
- 子宮頸管の粘液量が増加する。
▶午前88
入院集団精神療法において、看護師が担うリーダーの役割で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 患者間の発言量を均等にする。
- 沈黙も意味があると受け止める。
- メンバーの座る位置を固定する。
- 患者の非言語的サインに注目する。
- 話題が変わった場合はすぐに戻す。
精神保健医療福祉に関する法律について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。
- 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。
- 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。
- 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。
- 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。
災害拠点病院について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 広域災害医療に対応する。
- 災害発生時に指定される。
- 医療救護班の派遣機能を持つ。
- 免震構造であることが指定要件である。
- 救急救命士の配置が義務付けられている。
資料 厚生労働省「第103回保健師国家試験、第100回助産師国家試験、第106回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第106回看護師国家試験
平成28年2月14日(日)に実施された第105回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第105回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後26
耳の感覚器と刺激との組合せで正しいのはどれか。
- 蝸牛管――頭部の回転
- 球形囊――頭部の傾き
- 半規管――鼓膜の振動
- 卵形囊――骨の振動
▶午後27
血液型で正しいのはどれか。
- 日本人の15%はRh(-)である。
- A型のヒトの血漿には抗B抗体がある。
- B型のヒトの赤血球膜表面にはA抗原がある。
- Coombs〈クームス〉試験でABO式の血液型の判定を行う。
▶午後28
胃酸の分泌を抑制するのはどれか。
- アセチルコリン
- ガストリン
- セクレチン
- ヒスタミン
▶午後29
腎臓について正しいのはどれか。
- 腹腔内にある。
- 左右の腎臓は同じ高さにある。
- 腎静脈は下大静脈に合流する。
- 腎動脈は腹腔動脈から分かれる。
▶午後30
アポトーシスで正しいのはどれか。
- 群発的に発現する。
- 壊死のことである。
- 炎症反応が関与する。
- プログラムされた細胞死である。
▶午後31
感染性因子とその構成成分の組合せで正しいのはどれか。
- 細菌――核膜
- 真菌――細胞壁
- プリオン――核酸
- ウイルス――細胞膜
日本の世帯構造の平成4年(1992年)から30年間の変化で正しいのはどれか。
- 単独世帯数は増加している。
- 平均世帯人数は増加している。
- ひとり親と未婚の子のみの世帯数は3倍になっている。
- 65歳以上の者のいる夫婦のみの世帯数は2倍になっている。
食品衛生法に定められていないのはどれか。
- 残留農薬の規制
- 食品添加物の規制
- 食品安全委員会の設置
- ポジティブリスト制度の導入
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 受動喫煙のない職場を実現する。
- がんによる死亡者の減少を目標とする。
- 都道府県がん対策推進計画を策定する。
- がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
▶午後35
患者と看護師との協働について適切なのはどれか。
- 患者が目標達成できるよう支援する。
- 治療に関する情報は看護師が占有する。
- 看護計画は看護師の視点を中心に立案する。
- ケアは看護師の業務予定に基づき実施する。
Aさん(56歳、男性)は、脳梗塞の後遺症のためにリハビリテーションをしている。食事中に箸がうまく使えずイライラしている。
この状況で看護師が最も連携すべき専門職はどれか。
- 精神保健福祉士
- 社会福祉士
- 理学療法士
- 作業療法士
▶午後37
Aさん(80歳、女性)は、肺炎で入院して持続点滴中である。消灯時、訪室すると「体がだるくて眠れない」と訴えている。
Aさんへの入眠に向けた援助で最も適切なのはどれか。
- テレビをつける。
- 足浴を実施する。
- そのまま様子をみる。
- 睡眠薬を処方してもらう。
▶午後38
ベッド上での排便の介助時に使用した手袋を手から取り外すタイミングで適切なのはどれか。
- 肛門周囲の便を拭き取った後
- 排便後の患者の寝衣を整えた後
- ベッド周囲のカーテンを開けた後
- 使用した物品を汚物処理室で片づけた後
▶午後39
臥床患者の安楽な体位への援助として適切なのはどれか。
- 同一体位を5時間程度保持する。
- 仰臥位では膝の下に枕を入れる。
- 側臥位では両腕を胸の前で組む。
- 腹臥位では下腿を挙上する。
▶午後40
嚥下障害のある患者の食事の開始に適しているのはどれか。
- 白湯
- 味噌汁
- ゼリー
- 煮魚
▶午後41改題
病棟での医薬品の管理で正しいのはどれか。
- 生ワクチンは常温で保存する。
- 溶解した薬剤は冷凍保存する。
- 向精神薬は施錠できる場所に保管する。
- アンプルに残った麻薬注射液は廃棄する。
▶午後42
不安の強い入院患者に対し問題中心の対処を促す方法で適切なのはどれか。
- 読書をして気分転換を促す。
- 原因に気付くように支援する。
- 平常な気持ちを保つように助言する。
- 家族に不満を聞いてもらうことを勧める。
▶午後43
セルフケア行動を継続するための支援で適切なのはどれか。
- 看護師が患者の目標を設定する。
- 目標は達成が容易でない水準にする。
- 行動の習慣化が重要であることを伝える。
- これまでの経験は忘れて新たな方法で取り組むよう促す。
▶午後44
Aさん(43歳、男性)は、胆道狭窄のため内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉検査を受けた。検査後に心窩部痛が出現したため、禁食、抗菌薬および蛋白分解酵素阻害薬による治療が行われている。
翌日実施した血液検査の項目でAさんに生じている合併症を判断できるのはどれか。
- アミラーゼ
- アルブミン
- クレアチニン
- クレアチンキナーゼ
▶午後45
維持血液透析中の看護で適切なのはどれか。
- シャント肢を抑制する。
- 室温を18℃に設定する。
- 筋肉のけいれんの出現に注意する。
- 患者が吐き気を感じたら座位にする。
▶午後46
Aさん(37歳、女性)は、月経異常で病院を受診し、糖尿病および高血圧症と診断された。また、満月様顔貌や中心性肥満の身体所見がみられたため検査が行われ、ホルモン分泌異常と診断された。
原因となるホルモンを分泌している臓器はどれか。
- 副甲状腺
- 甲状腺
- 副腎
- 卵巣
日本の令和4年(2022年)の国民生活基礎調査において高齢者世帯の所得で、1世帯当たり平均所得金額の構成割合が最も高いのはどれか。
- 稼働所得
- 財産所得
- 公的年金・恩給
- 仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得
認知症の高齢者に対するノーマライゼーションで正しいのはどれか。
- 散歩を勧める。
- 決められた服を着るよう勧める。
- 重度の場合は精神科病棟に入院を勧める。
- 食べこぼしのあるときに箸を使用しないよう勧める。
▶午後49
Aさん(80歳、男性)は、脳梗塞の治療のために入院した。Aさんは多弁であり「めがねをとってください」のことを「めとねをとってください」などと話す様子が観察される。
Aさんの症状で正しいのはどれか。
- 錯語
- 感情失禁
- 喚語困難
- 運動性失語
▶午後50
便秘の原因となる加齢に伴う身体的変化で誤っているのはどれか。
- 大腸粘膜の萎縮
- 骨盤底筋群の筋力低下
- 直腸内圧の閾値の低下
- 大腸の内括約筋の緊張の低下
▶午後51
Aさん(75歳、女性)は、終末期のがんの夫を自宅で介護している。Aさんと夫は自宅での看取りを希望している。
Aさんへのケアで最も適切なのはどれか。
- 臨死期に起こる身体徴候について説明しておく。
- 自宅で看取る意思が揺らぐことがないように支援する。
- 配偶者を亡くした家族の会への参加を生前から勧める。
- 夫が元気だったころの思い出を話題にしないように勧める。
▶午後52
乳児が1日に必要とする体重1kg当たりの水分量はどれか。
- 80mL
- 100mL
- 150mL
- 180mL
日本の令和5年(2023年)における周産期死亡率(出産千対)について正しいのはどれか。
- 1.3
- 3.3
- 5.3
- 7.3
▶午後54
性的対象とその性的指向の分類との組合せで正しいのはどれか。
- 同性――トランスセクシュアル
- 異性――ヘテロセクシュアル
- 両性――ホモセクシュアル
- なし――バイセクシュアル
▶午後55
更年期障害の女性にみられる特徴的な症状はどれか。
- 異常発汗
- 低血圧
- 妄想
- 便秘
産後うつ病について正しいのはどれか。
- 一過性に涙もろくなる。
- スクリーニング調査票がある。
- 日本における発症頻度は約40%である。
- 産後10日ころまでに発症することが多い。
こころのバリアフリー宣言の目的で正しいのはどれか。
- 身体障害者の人格の尊重
- 高齢者の社会的な孤立の予防
- 精神疾患に対する正しい理解の促進
- 精神科に入院している患者の行動制限の最小化
▶午後58
向精神薬と副作用〈有害事象〉の組合せで正しいのはどれか。
- 抗精神病薬――多毛
- 抗認知症薬――依存性
- 抗てんかん薬――急性ジストニア
- 抗うつ薬――セロトニン症候群
Aさん(40歳、男性)は、5年前に勤めていた会社が倒産し再就職ができず、うつ病になった。その後、治療を受けて回復してきたため、一般企業への再就職を希望している。
Aさんが就労を目指して利用できる社会資源はどれか。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 自立訓練〈生活訓練〉
精神保健指定医を指定するのはどれか。
- 保健所長
- 都道府県知事
- 厚生労働大臣
- 精神保健福祉センター長
日本の平成24年(2012年)の高齢者の健康に関する意識調査において最期を迎える場に関する希望で最も多いのはどれか。
- 自宅
- 医療施設
- 福祉施設
- 高齢者向けのケア付き住宅
レスパイトケアの主な目的について適切なのはどれか。
- 高度な治療を集中的に行う。
- 家族へ介護方法の指導を行う。
- 居宅サービス料金を補助する。
- 介護を行う家族のリフレッシュを図る。
訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。
- 主治医の意見書が必要である。
- 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
- サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
- 主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
▶午後64
看護基準の目的で最も適切なのはどれか。
- 看護の質の保証
- 個別的な看護の促進
- 看護業務の負担の軽減
- 高度な看護技術の提供
▶午後65
新生児標識について正しいのはどれか。
- 沐浴時には児の標識を外す。
- 標識は1個装着すればよい。
- 装着する時期は母児同室を開始する直前である。
- 母親に児を引き渡すときは母子の標識を照合する。
▶午後66
山村部で地震による家屋倒壊と死者が出た災害が発生し、3週が経過した。避難所では、自宅の半壊や全壊の被害にあった高齢者を中心に10世帯が過ごしている。
高齢者の心のケアとして最も適切なのはどれか。
- 認知行動療法を行う。
- 自分が助かったことを喜ぶよう説明する。
- 地震発生時の状況について詳しく聞き取る。
- 長年親しんだものの喪失について話せる場をつくる。
2国間の国際保健医療協力を行うのはどれか。
- 国際協力機構〈JICA〉
- 国際看護師協会〈ICN〉
- 国連開発計画〈UNDP〉
- 国連食糧農業機関〈FAO〉
▶午後68
体温に影響しないのはどれか。
- 運動
- 食事
- ふるえ
- 不感蒸泄
- 精神性発汗
▶午後69
貪食能を有する細胞はどれか。
- 好酸球
- Bリンパ球
- 線維芽細胞
- 血管内皮細胞
- マクロファージ
流行性角結膜炎の原因はどれか。
- 淋菌
- 緑膿菌
- クラミジア
- アデノウイルス
- ヘルペスウイルス
▶午後71
ビタミンの欠乏とその病態との組合せで正しいのはどれか。
- ビタミンA――壊血病
- ビタミンB1――代謝性アシドーシス
- ビタミンC――脚気
- ビタミンD――悪性貧血
- ビタミンE――出血傾向
日本人の食事摂取基準(2020年版)で、身体活動レベルⅠ、75歳以上の男性の1日の推定エネルギー必要量はどれか。
- 1,400kcal
- 1,800kcal
- 1,950kcal
- 2,150kcal
- 2,450kcal
▶午後73
触診法による血圧測定で適切なのはどれか。
- 血圧計は患者の心臓の高さに置く。
- マンシェットの幅は上腕全体を覆うサイズを選ぶ。
- 150mmHgまで加圧して減圧を開始する。
- 加圧後に1拍動当たり2〜4mmHgずつ減圧する。
- 減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値を拡張期血圧とする。
▶午後74
待機的に行う食道静脈瘤硬化療法について正しいのはどれか。
- 全身麻酔下で行う。
- 前日に下剤を内服する。
- 治療後48時間の安静が必要である。
- 治療翌日の朝から常食を開始する。
- 治療後に胸部痛が出現する可能性がある。
▶午後75
老人性白内障の症状で正しいのはどれか。
- 涙が流れ出る状態が続く。
- 小さい虫が飛んでいるように見える。
- 明るい場所ではまぶしくてよく見えない。
- 遠見視力は良好であるが近見視力は低下する。
- 暗い部屋に入ると目が慣れるのに時間がかかる。
臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。
- 1歳
- 6歳
- 15歳
- 20歳
- 年齢制限なし
乳児の髄膜炎などを抑制するため、平成25年(2013年)に定期接種に導入されたのはどれか。
- 日本脳炎ワクチン
- ロタウイルスワクチン
- インフルエンザワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
- Hibワクチン
▶午後78
生後1、2か月のDown〈ダウン〉症候群の乳児にみられる特徴はどれか。
- 活気があり機嫌が良い。
- 体重増加は良好である。
- 筋緊張が強く抱っこしにくい。
- 舌が小さく吸啜が困難である。
- 哺乳の途中で眠ってしまうことが多い。
▶午後79
在胎40週0日、体重3,011gで出生した男児。出生後1分、呼吸数60/分、心拍数140/分であった。四肢を屈曲させ、刺激に対して啼泣している。体幹はピンク色、四肢にはチアノーゼがみられる。
この男児の1分後のApgar〈アプガー〉スコアはどれか。
- 1点
- 3点
- 5点
- 7点
- 9点
▶午後80
関節リウマチで療養している人への日常生活指導で適切なのはどれか。
- 床に座って靴下を履く。
- 2階にある部屋を寝室にする。
- 水道の蛇口をレバー式にする。
- ボタンで着脱する衣服を選択する。
- 寝具はやわらかいマットレスにする。
食事摂取基準に耐容上限量が示されているビタミンはどれか。2つ選べ。
- ビタミンA
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンC
- ビタミンD
▶午後82
水腎症の原因で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 前立腺癌
- 陰囊水腫
- ループス腎炎
- 神経因性膀胱
- 腎アミロイドーシス
児童相談所の業務はどれか。2つ選べ。
- 児童の一時保護
- 自立支援給付の決定
- 不登校に関する相談
- 身体障害者手帳の交付
- 放課後児童健全育成事業の実施
▶午後84
前腕の内側中央部に創部がある患者で、創部のガーゼがずれないよう固定をする必要がある。
伸縮性のある巻軸包帯を使う場合に適切なのはどれか。2つ選べ。
- 創の部位から巻き始める。
- 包帯を伸ばした状態で巻く。
- 前腕部の巻き方は螺旋帯とする。
- 手関節から肘関節まで巻く。
- 巻き終わりは環行帯とする。
▶午後85
壮年期の特徴はどれか。2つ選べ。
- 骨密度の増加
- 味覚の感度の向上
- 総合的判断力の向上
- 早朝覚醒による睡眠障害
- 水晶体の弾力性の低下による視機能の低下
▶午後86
Aさん(63歳、男性)は、胃癌にて胃亜全摘出術後3か月目に誤嚥性肺炎で緊急入院した。食物の通過や排便は問題なかったが、食事摂取量が少なく、術前より体重が10kg減少した。総義歯が外れやすく歯科を受診予定であった。
Aさんの肺炎の原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。
- 消化管内容物の逆流
- 義歯の不適合
- 消化吸収障害
- 吻合部狭窄
- 腸閉塞
▶午後87
眼底検査が必要なのはどれか。2つ選べ。
- 中耳炎
- 糖尿病
- 麦粒腫
- 高血圧症
- 筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉
▶午後88
加齢に伴う心血管系の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 心拍数の増加
- 左室壁の肥厚
- 収縮期血圧の上昇
- 圧受容機能の亢進
- 刺激伝導系の細胞数の増加
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 介護予防サービスである。
- 24時間を通じて行われる。
- 地域密着型サービスである。
- 重症心身障害児を対象とする。
- 施設サービス計画の作成を行う。
▶午後90
車椅子で日常生活を送る在宅療養者の住宅改修で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 床を畳に変える。
- 玄関を引き戸にする。
- 廊下と部屋との段差をなくす。
- トイレに和式便器を設置する。
- 廊下の幅は車椅子の幅と同じにする。
資料 厚生労働省「第102回保健師国家試験、第99回助産師国家試験、第105回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第105回看護師国家試験
平成28年2月14日(日)に実施された第105回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第105回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
▶午前26
筋収縮で正しいのはどれか。
- 筋収縮はミオシンの短縮である。
- アクチンにATP分解酵素が存在する。
- α運動ニューロンは筋紡錘を興奮させる。
- 筋小胞体からカルシウムイオンが放出される。
▶午前27
血管に吻合がないのはどれか。
- 皮静脈
- 冠動脈
- 膝窩動脈
- 腸絨毛の毛細血管
▶午前28
一次脱水でみられるのはどれか。
- 尿量の減少
- 血漿浸透圧の低下
- バソプレシンの分泌の抑制
- 血漿ナトリウムイオン濃度の低下
▶午前29
膵臓から分泌されるのはどれか。
- ガストリン
- カルシトニン
- アルドステロン
- ソマトスタチン
▶午前30
男性生殖器について正しいのはどれか。
- 精巣は腹腔内にある。
- 精囊は精子を貯留する。
- 前立腺は直腸の前面に位置する。
- 右精巣静脈は腎静脈に流入する。
▶午前31
腹部の検査の画像を別に示す。
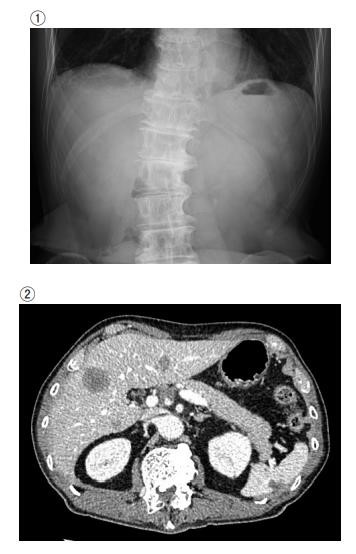
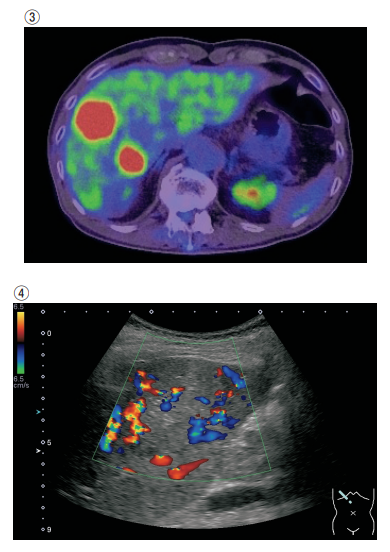
生体の代謝を利用した検査はどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
医療保険について正しいのはどれか。
- 医療給付には一部負担がある。
- 高額療養費の受給には年齢制限がある。
- 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。
- 後期高齢者医療における公費負担は8割である。
日本の令和3年度(2021年度)の国民医療費について正しいのはどれか。
- 総額は約30兆円である。
- 財源の約半分は保険料である。
- 国民総生産に対する比率は5%台である。
- 人口1人当たりでは65歳以上が65歳未満の約2倍である。
学校保健について正しいのはどれか。
- 学校医は健康相談を実施する。
- 校長は学校医を置くことができる。
- 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。
- 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。
▶午前36
高齢者が趣味の絵画を地区の展覧会に発表したいという欲求はどれか。
- 自尊の欲求
- 所属の欲求
- 安全の欲求
- 生理的欲求
▶午前37
根拠に基づいた看護〈EBN〉で最も適切なのはどれか。
- 患者の好みは参考にしない。
- 先輩看護師の行動を模倣する。
- 研究論文の有用性を検討する。
- 既存の看護業務基準を遵守する。
▶午前38
患者の状態と看護師のコミュニケーションの方法との組合せで正しいのはどれか。
- 構音障害――発音を促す
- 聴力障害――後方から声をかける
- 認知症――患者のペースに合わせて話す
- 失語――言葉の誤りを繰り返し訂正する
▶午前39
フィジカルアセスメントにおいて触診で判断するのはどれか。
- 腱反射の有無
- 瞬目反射の有無
- 腸蠕動運動の有無
- リンパ節の腫脹の有無
▶午前40
針刺し事故対策で最も適切なのはどれか。
- 針刺し部位を消毒液に浸す。
- 注射針のリキャップを習慣化する。
- 事故の当事者を対象にした研修を行う。
- 使用済みの針は専用容器に廃棄することを徹底する。
▶午前41
片麻痺のある患者の歩行介助で正しいのはどれか。
- 患者の患側に立つ。
- 靴底は摩擦が少ないものを準備する。
- 杖を使用する場合は杖を持つ側で介助する。
- 階段を昇る場合は患側下肢から昇るように指導する。
▶午前43
胃洗浄を行うときの体位で最も適切なのはどれか。
- 仰臥位
- 腹臥位
- 左側臥位
- 右側臥位
▶午前44
Aさん(59歳、男性)は、糖尿病で内服治療中、血糖コントロールの悪化を契機に膵癌と診断され手術予定である。HbA1c7.0%のため、手術の日前に入院し、食事療法、内服薬およびインスリンの皮下注射で血糖をコントロールしている。Aさんは、空腹感とインスリンを使うことの不安とで、怒りやすくなっている。
Aさんに対する説明で適切なのはどれか。
- 「手術によって糖尿病は軽快します」
- 「術後はインスリンを使用しません」
- 「少量であれば間食をしても大丈夫です」
- 「血糖のコントロールは術後の合併症を予防するために必要です」
▶午前45
冠動脈バイパス術〈CABG〉後5時間が経過したとき、心囊ドレーンからの排液が減少し、血圧低下と脈圧の狭小化とがあり、「息苦しい」と患者が訴えた。
最も考えられるのはどれか。
- 肺梗塞
- 不整脈
- 心筋虚血
- 心タンポナーデ
▶午前46
Aさん(48歳、男性)は、直腸癌のため全身麻酔下で手術中、出血量が多く輸血が行われていたところ、41℃に体温が上昇し、頻脈となり、血圧が低下した。麻酔科医は下顎から頸部の筋肉の硬直を確認した。既往歴に特記すべきことはない。
この状況の原因として考えられるのはどれか。
- アナフィラキシー
- 悪性高熱症
- 菌血症
- 貧血
▶午前47
慢性副鼻腔炎についての説明で適切なのはどれか。
- 1週間の内服で症状が軽減すれば受診の必要はない。
- 発症後1週は空気感染の危険性がある。
- 眼窩内感染を起こす危険性がある。
- 透明の鼻汁が特徴的である。
▶午前48
過活動膀胱の説明で正しいのはどれか。
- 尿意切迫感がある。
- 失禁することはない。
- 水分を制限して治療する。
- 50歳台の有病率が最も高い。
▶午前49
ハヴィガースト, R. J.による発達課題のうち、老年期の発達課題はどれか。
- 健康の衰退に適応する。
- 大人の余暇活動を充実する。
- 個人としての自立を達成する。
- 大人の社会的な責任を果たす。
エイジズムを示す発言はどれか。
- 「介護を要する高齢者を社会で支えるべきだ」
- 「後期高齢者は車の運転免許証を返納するべきだ」
- 「認知症の患者の治療方針は医療従事者が決めるべきだ」
- 「高齢者が潜在的に持つ力を発揮できるような環境を整えるべきだ」
▶午前51
高齢者の栄養管理について栄養サポートチーム〈NST〉と連携するときに、病棟看護師が行う看護活動で最も適切なのはどれか。
- 同時期に他のサポートチームが介入しないようにする。
- 栄養管理が不十分な高齢者のケアについて助言を得る。
- 家族にも栄養サポートチーム〈NST〉の一員になるよう勧める。
- 経管栄養法を行っている高齢者数を減らす方法を一緒に考える。
▶午前52
Aさん(102歳、女性)は、重度の廃用症候群のために5年前から発語が少なく体を動かすことができない。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返し、終末期である。同居している家族は積極的な治療をしないことを希望し、自宅でAさんを看取ることを決めた。
Aさんの家族への退院時の指導で最も適切なのはどれか。
- 「24時間付き添ってあげましょう」
- 「おむつの重さで尿量を測定しましょう」
- 「苦しそうになったら救急車を呼びましょう」
- 「Aさんが食べたければ食べさせてあげましょう」
▶午前53
Aちゃん(生後10か月、男児)は、先天性心疾患のため手術を受けた。Aちゃんの体重の変化を図に示す。
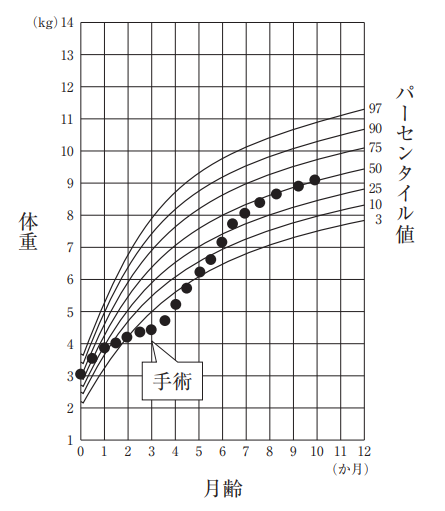
手術後から現在までの体重の変化に対する評価で適切なのはどれか。
- 体重増加の不良
- 過度な体重増加
- 標準的な体重増加
- キャッチアップ現象
▶午前54
小児の骨折の特徴で正しいのはどれか。
- 不全骨折しやすい。
- 圧迫骨折しやすい。
- 骨折部が変形しやすい。
- 骨癒合不全を起こしやすい。
就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。
- 時差出勤――母子保健法
- 産前産後の休業――児童福祉法
- 軽易業務への転換――母体保護法
- 危険有害業務の制限――労働基準法
▶午前56
低用量経口避妊薬について正しいのはどれか。
- 血栓症のリスクは増加しない。
- 1日飲み忘れたときは中止する。
- 授乳期間を通じて内服は可能である。
- 副効用に月経前症候群〈PMS〉の軽減がある。
▶午前57
常位胎盤早期剝離のリスク因子はどれか。
- 肥満
- 妊娠糖尿病
- 帝王切開術の既往
- 妊娠高血圧症候群
地域精神保健活動における二次予防はどれか。
- 精神科病院で統合失調症患者に作業療法を行う。
- 精神疾患患者に再燃を予防するための教育を行う。
- 地域の住民を対象にストレスマネジメントの講演会を行う。
- 会社の健康診断でうつ傾向があると判定された人に面接を行う。
▶午前59
疾患と確定診断のために用いられる検査との組合せで最も適切なのはどれか。
- 脳炎――脳脊髄液検査
- パニック障害――脳波検査
- 特発性てんかん――頭部MRI
- パーソナリティ障害――頭部CT
▶午前60
生活技能訓練〈SST〉について正しいのはどれか。
- 退院支援プログラムの1つである。
- 診断を確定する目的で実施される。
- セルフヘルプグループの一種である。
- 精神分析の考え方を応用したプログラムである。
精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律への改正で行われたのはどれか。
- 私宅監置の廃止
- 任意入院の新設
- 通院医療公費負担制度の導入
- 精神障害者保健福祉手帳制度の創設
介護保険被保険者で介護保険による訪問看護が提供されるのはどれか。
- 脳血管疾患
- 末期の結腸癌
- 脊髄小脳変性症
- 進行性筋ジストロフィー
訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。
- 事務所を設置する必要はない。
- 訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。
- 利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。
- 利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。
医療安全と関連する方法の組合せで誤っているのはどれか。
- 院内感染対策――プライマリナーシング
- 事故防止対策――インシデントレポート
- 医療の質の保証――クリニカルパス
- 手術時の安全対策――タイムアウト
▶午前65
診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
- 死亡した患者の情報は対象にならない。
- 個人情報の利用目的を特定する必要はない。
- 特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
- 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。
国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。
- 国連難民高等弁務官事務所〈UNHCR〉――有償資金協力
- 国連教育科学文化機関〈UNESCO〉――児童の健康改善
- 世界保健機関〈WHO〉――感染症対策
- 国際労働機関〈ILO〉――平和維持活動
▶午前68
頭部CTを別に示す。
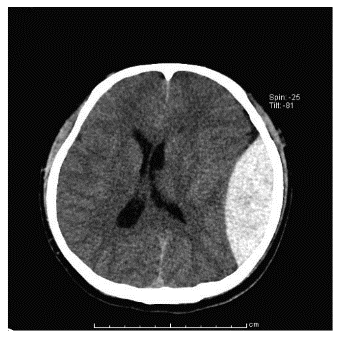
出血部位について正しいのはどれか。
- 皮下組織
- 硬膜外腔
- くも膜下腔
- 脳実質内
- 脳室内
▶午前69
動脈硬化を直視して評価できる血管はどれか。
- 冠動脈
- 眼底動脈
- 大腿動脈
- 腹部大動脈
- 中大脳動脈
接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応で正しいのはどれか。
- Ⅰ型
- Ⅱ型
- Ⅲ型
- Ⅳ型
- Ⅴ型
▶午前71
膀胱留置カテーテルの写真を別に示す。
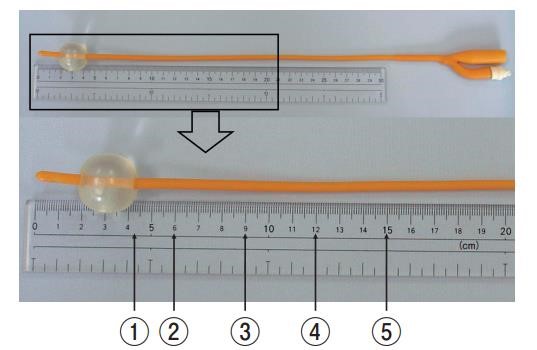
成人女性に膀胱留置カテーテルが挿入されている場合、体内に留置されている長さで最も適切なのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
▶午前72
Aさん(60歳、男性)は、胃癌の手術目的で入院した。大動脈弁置換術を受けた既往があり、内服していたワルファリンをヘパリンに変更することになった。
確認すべきAさんの検査データはどれか。
- PT-INR
- 赤血球数
- 白血球数
- 出血時間
- ヘモグロビン値
▶午前73
膀胱癌のため尿路ストーマを造設する予定の患者への説明で適切なのはどれか。
- 「尿道の一部を体外に出して排泄口を造ります」
- 「尿意を感じたらトイレで尿を捨てます」
- 「ストーマの装具は毎日貼り替えます」
- 「ストーマに装具を付けて入浴します」
- 「水分の摂りすぎに注意が必要です」
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)で正しいのはどれか。
- 光熱費は自己負担である。
- 12人を1つのユニットとしている。
- 看護師の配置が義務付けられている。
- 介護保険制度の施設サービスである。
- 臨死期は提携している病院に入院する。
Aちゃん(3歳、女児)は、病室で朝食を食べていた。そこに、医師が訪室して採血を行いたいと話したところ、Aちゃんは何も答えず下を向いて泣き始めた。その様子を見ていた看護師は、Aちゃんは朝食を中断して採血されるのは嫌だと思っているようなので、朝食後に採血して欲しいと医師に話した。
この看護師の対応の根拠となる概念はどれか。
- アセント
- コンセント
- アドボカシー
- ノーマライゼーション
- ノンコンプライアンス
▶午前76
3か月の乳児の親に対する問診で適切でないのはどれか。
- 「寝返りをしますか」
- 「あやすとよく笑いますか」
- 「物を見て上下左右に目で追いますか」
- 「アーアー、ウーウーなど声を出しますか」
- 「腹ばいにすると腕で体を支えて頭を持ち上げますか」
▶午前77
萎縮性腟炎に伴う状態について正しいのはどれか。
- 性交痛
- 白色の帯下
- 腟壁の肥厚化
- 腟の自浄作用の亢進
- エストロゲン分泌の増加
▶午前78
うつ病で入院している患者が「自分は重大な過ちで皆に迷惑をかけてしまいました。死んでおわびします」という妄想を訴えた。
この患者にみられるのはどれか。
- 罪業妄想
- 心気妄想
- 追跡妄想
- 被毒妄想
- 貧困妄想
▶午前79
訪問看護師が人工肛門を造設して退院した在宅療養者を訪問すると「便が漏れるため外出ができない」と相談を受けた。観察すると、ストーマパウチの面板が皮膚に密着していない。
看護師の対応で適切なのはどれか。
- 無菌操作で交換する。
- 頻回に交換するよう説明する。
- 面板を温めて皮膚に貼付する。
- 面板を人工肛門より小さめに切る。
- 腹壁の皮膚を寄せて面板を貼付する。
トリアージタグを装着する部位の優先順位で適切なのはどれか。
- 頸部→右手→左手→右足→左足
- 頸部→左手→左足→右手→右足
- 右手→右足→左手→左足→頸部
- 右手→左手→右足→左足→頸部
- 左手→右手→左足→右足→頸部
▶午前81
立ち直り反射に関与するのはどれか。2つ選べ。
- 視細胞
- コルチ器
- 圧受容器
- 化学受容器
- 頸筋の筋紡錘
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉の感染経路で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 感染者の嘔吐物との接触
- 感染者の咳による曝露
- 感染者の糞便との接触
- 感染者からの輸血
- 感染者との性行為
▶午前83
慢性腎不全によって起こるのはどれか。2つ選べ。
- 低血圧
- 低リン血症
- 低カリウム血症
- 低カルシウム血症
- 代謝性アシドーシス
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。
- 離婚調停の支援
- 成年後見制度の利用
- 保健所による自立支援
- 婦人相談員による相談
- 裁判所による接近禁止命令
▶午前85
パルスオキシメータによる経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の測定に適した部位はどれか。2つ選べ。
- 背部
- 上腕
- 指先
- 耳たぶ
- 大部
▶午前86
Aさん(60歳、男性)は、転倒して第5頸椎レベルの脊髄を損傷した。肩を上げることはできるが、上肢はわずかに指先を動かせる程度である。呼吸数22/分、脈拍86/分、血圧100/70mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%であった。Aさんは「息がしづらい」と言っている。
Aさんの状態で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 低酸素血症がある。
- 胸郭運動がみられる。
- 無気肺を起こしやすい。
- 腹式呼吸を行っている。
- 閉塞性換気障害を起こしている。
▶午前87
Aさん(35歳、女性、会社員)は、動悸、手指の震え及び体重減少があり、受診したところ、頻脈と眼球突出とを指摘され抗甲状腺薬の内服を開始した。Aさんは看護師に「仕事のストレスは寝る前にビールを飲むことで解消するようにしているが、ちょっとしたことでイライラして眠れない」と話した。
Aさんへの説明で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 「仕事を休みましょう」
- 「禁酒する必要があります」
- 「積極的に運動しましょう」
- 「発熱したときは受診してください」
- 「病気が原因でイライラしやすくなります」
▶午前88
Aさん(42歳、女性)は、2週前から腰痛と坐骨神経痛とを発症し整形外科で処方された鎮痛薬を内服している。帯下が増えて臭いもあるため婦人科を受診し、子宮頸癌と診断された。
進行期を決めるためにAさんに行われる検査で適切なのはどれか。2つ選べ。
- ヒトパピローマウイルス検査
- 小腸内視鏡検査
- 腎盂尿管造影
- 脊髄造影
- CT
▶午前89
児の免疫に関する説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 胎児期は胎盤を通じて母体からIgGを受け取る。
- 出生後は母乳からIgMを受け取る。
- 生後3か月ころに免疫グロブリンが最も少なくなる。
- 1歳ころから抗体の産生が盛んになる。
- 3歳ころにIgAが成人と同じレベルに達する。
▶午前90
500mLの輸液を50滴/分の速度で成人用輸液セットを用いて順調に滴下し、現在80分が経過した。
このときの輸液の残量を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②③mL
資料 厚生労働省「第102回保健師国家試験、第99回助産師国家試験、第105回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第105回看護師国家試験
平成27年2月22日(日)に実施された第104回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第104回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後26
内臓痛が生じるのはどれか。
- 臓器の切開
- 管腔臓器の受動的な過伸展
- 細胞内カリウムイオン濃度の上昇
- 細胞外ナトリウムイオン濃度の上昇
▶午後27
蛋白質で正しいのはどれか。
- アミノ酸で構成される。
- 唾液により分解される。
- 摂取するとそのままの形で体内に吸収される。
- 生体を構成する成分で最も多くの重量を占める。
▶午後28
膀胱で正しいのはどれか。
- 漿膜で覆われている。
- 直腸の後方に存在する。
- 粘膜は移行上皮である。
- 筋層は2層構造である。
▶午後29
ホルモンとその産生部位の組合せで正しいのはどれか。
- エリスロポエチン――膵臓
- アドレナリン――副腎皮質
- 成長ホルモン――視床下部
- レニン――腎臓
▶午後30
糖尿病神経障害で正しいのはどれか。
- 運動神経は温存される。
- 感覚障害は中枢側から起こる。
- 三大合併症の中では晩期に発症する。
- 自律神経障害は無自覚性低血糖に関与する。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。
- 経皮感染する
- 無症候期がある。
- DNAウイルスによる。
- 血液中のB細胞に感染する。
▶午後32
気胸について正しいのはどれか。
- 外傷は原因の1つである。
- 自然気胸は若い女性に多い。
- 原因となるブラは肺底部に多い。
- 治療として人工呼吸器による陽圧換気が行われる。
▶午後33
心電図でT波の上昇の原因となるのはどれか。
- 高カリウム血症
- 低カリウム血症
- 高カルシウム血症
- 低カルシウム血症
▶午後34
前立腺癌の治療薬はどれか。
- インターフェロン
- a交感神経遮断薬
- 抗アンドロゲン薬
- 抗エストロゲン薬
日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
- 国民の平等性
- 国民の生存権
- 国民の教育を受ける権利
- 国及び公共団体の賠償責任
社会福祉協議会の活動で正しいのはどれか。
- ボランティア活動を推進する。
- 就労の支援活動を推進する。
- 男女共同参画を推進する。
- がん対策を推進する。
▶午後37
疾病の発生要因と疫学要因の組合せで正しいのはどれか。
- 食事――宿主要因
- 職業――宿主要因
- 細胞免疫――環境要因
- 媒介動物――環境要因
職場における疾病予防の対策のうち三次予防はどれか。
- 健康教育の実施
- 人間ドックの受診勧奨
- じん肺健康診断の実施
- 職場復帰後の適正配置
看護師の業務で正しいのはどれか。
- グリセリン浣腸液の処方
- 褥婦への療養上の世話
- 酸素吸入の流量の決定
- 血液検査の実施の決定
▶午後40
サーカディアンリズムを整えるための援助で適切なのはどれか。
- 毎朝同じ時刻に起床するよう促す。
- 日中はカーテンを閉めておくよう促す。
- 昼寝の時間を2〜3時間程度とるよう促す。
- 就寝前に温かいコーヒーを摂取するよう促す。
▶午後41
仰臥位の患者の良肢位について正しいのはどれか。
- 肩関節外転90度
- 肘関節屈曲0度
- 膝関節屈曲90度
- 足関節底屈0度
▶午後42
抗癌薬の点滴静脈内注射中の患者が刺入部の腫脹と軽い痛みを訴え、看護師が確認した。
直ちに行うのはどれか。
- 刺入部を温める。
- 注入を中止する。
- 注入速度を遅くする。
- 点滴チューブ内の血液の逆流を確認する。
▶午後43
死後の処置について最も適切なのはどれか。
- 体内に挿入したチューブ類の除去は家族同席で行う。
- 枕の高さを低くし開口を防ぐ。
- 死亡後2時間以内に行う。
- 口腔内は吸引しない。
▶午後44
グリセリン浣腸の効果で正しいのはどれか。
- 腸管の蠕動を促進する。
- 腸管内の炎症を和らげる。
- 腸壁の水分吸収を促進する。
- 腸管内のガスの吸収を促進する。
▶午後45
皮膚の構造と機能について正しいのはどれか。
- 皮膚表面は弱酸性である。
- 粘膜は細菌が繁殖しにくい。
- 皮脂の分泌量は老年期に増加する。
- アポクリン汗腺は全身に分布している。
▶午後46
与薬方法で正しいのはどれか。
- 筋肉内注射は大殿筋に行う。
- 点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。
- バッカル錠は、かんでから飲み込むよう促す。
- 口腔内に溜まった吸入薬は飲み込むよう促す。
▶午後47
全血の検体を25℃の室内に放置すると低下するのはどれか。
- 血糖
- 乳酸
- 遊離脂肪酸
- アンモニア
看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
- 医療法
- 労働基準法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
▶午後49
放射線治療による放射線宿酔について正しいのはどれか。
- 晩期合併症である。
- 食欲不振が出現する。
- 皮膚の発赤が特徴的である。
- 症状は1か月程度持続する。
▶午後50
呼吸困難を訴えて来院した患者の動脈血液ガス分析は、pH7.32、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉72Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉50Torr、HCO3-26.0mEq/Lであった。
このときのアセスメントで適切なのはどれか。
- 肺胞低換気
- 過換気症候群
- 代謝性アシドーシス
- 呼吸性アルカローシス
▶午後51
Aさん(50歳、男性)は、上腹部痛が突然出現したため、冷や汗をかき腹部を押さえながら家族と来院した。Aさんは十二指腸潰瘍の既往がある。
このときに観察する徴候として最も適切なのはどれか。
- Romberg〈ロンベルグ〉徴候
- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候
- Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候
- Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候
▶午後52
Aさん(48歳、女性)は、卵巣癌の腹膜播種性転移で亜イレウス状態になった。栄養療法のために、右鎖骨下静脈から中心静脈カテーテルの挿入が行われたが、鎖骨下動脈を穿刺したため中止された。処置直後の胸部エックス線撮影で異常はなかったが、4時間後、Aさんは胸痛と軽い呼吸困難を訴えた。
最も考えられるのはどれか。
- 血胸
- 肺炎
- 肺転移
- 胸膜炎
▶午後53
Aさん(42歳、男性、会社員)は、1人で暮らしている。毎日、たばこを20本吸い、缶ビールを3本飲んでいた。Aさんは週末にラグビーをした後、帰りに焼肉を食べるのを楽しみにしている。高尿酸血症で治療を受けることになり、尿酸排泄促進薬が処方された。缶ビールを1本に減らしたが、尿酸値が高い状態が続いている。身長172cm、体重67kg。その他の血液検査データに異常はない。
Aさんへの生活指導で最も適切なのはどれか。
- 禁煙
- 体重の減量
- 過度な運動の回避
- 蛋白質摂取の禁止
▶午後54
Raynaud〈レイノー〉現象のある患者への指導で正しいのはどれか。
- 頻繁に含嗽をする。
- 日傘で紫外線を防止する。
- 洗顔のときは温水を使用する。
- 筋力を維持するトレーニングを行う。
▶午後55
脳血管造影を行う患者の看護について最も適切なのはどれか。
- 前日に側頭部の剃毛を行う。
- 検査30分前まで食事摂取が可能である。
- 検査中は患者に話しかけない。
- 穿刺部の末梢側の動脈の拍動を確認する。
▶午後56
Aさん(59歳、男性)は、経尿道的前立腺切除術後1日で、強い尿意を訴えているが腹部超音波検査で膀胱に尿は貯留していない。Aさんは、体温36.9℃、脈拍88/分、血圧128/86mmHgであった。尿は淡血性で混濁はなく蓄尿バッグ内に3時間で350mL貯留している。
この状態で考えられるのはどれか。
- 尿道狭窄
- 尿路感染症
- 膀胱刺激症状
- 膀胱タンポナーデ
日本の令和4年(2022年)の養護者による高齢者虐待の種類で最も多いのはどれか。
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- 介護等放棄
- 性的虐待
▶午後58
高齢者の総合機能評価〈CGA〉について正しいのはどれか。
- 介護者の介護負担は含まない。
- 多職種チームで結果を共有する。
- 疾患の改善を目指すことが目的である。
- 主な対象者は重度の要介護高齢者である。
▶午後59
Aさん(70歳、女性)は、夫のBさんと死別し、軽費老人ホームに入居している。Aさんは「今、再婚をしたいと思う好きな人ができたのに、70歳で再婚なんて恥ずかしいよと息子に叱られました。とても悲しいです」と話した。
Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 「息子さんの気持ちは理解できます」
- 「他の職員の考えを聞いてみましょう」
- 「好きな人ができることは素敵なことですね」
- 「亡くなったBさんのことは忘れてしまったのですか」
▶午後60
軽度の嚥下障害がある患者への誤嚥性肺炎の予防法で正しいのはどれか。
- 流動食にする。
- 軽く下顎を挙上して飲み込んでもらう。
- 食後は10分程度の座位を保持する。
- 口腔内を吸引しながらブラッシングする。
▶午後61
Parkinson〈パーキンソン〉病の症状について正しいのはどれか。
- 満月様顔貌になる。
- 腕を振らずに歩く。
- 後ろに反り返って歩く。
- 頭を左右に大きく振る。
▶午後62
A君(5歳、男児)は、先天性水頭症で脳室−腹腔〈V-P〉シャントが挿入されている。
定期受診の際、看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。
- 頭囲
- 聴力
- 微細運動
- 便秘の有無
▶午後63
二分脊椎の子どもに特徴的な症状はどれか。
- 排泄障害
- 体重増加不良
- 言語発達の遅延
- 上半身の運動障害
▶午後64
セクシュアリティの意義と関連する事項の組合せで正しいのはどれか。
- 生殖性の性――ジェンダー
- 性別としての性――常染色体
- 連帯性としての性――種の保存
- 性役割としての性――社会的規範
▶午後65
正常な月経周期に伴う変化で正しいのはどれか。
- 排卵期には頸管粘液が増量する。
- 月経の直後は浮腫が生じやすい。
- 黄体から黄体形成ホルモン〈LH〉が分泌される。
- 基礎体温は月経終了後から徐々に上昇して高温相になる。
Aさん(38歳、女性、パート勤務)は、腹痛のため、姉に付き添われて救急外来を受診した。診察時、身体には殴られてできたとみられる複数の打撲痕が確認された。腹痛の原因は夫から蹴られたことであった。Aさんは「家に帰るのが怖い。姉には夫の暴力について話したくない」と泣いている。
外来での看護師の対応で適切なのはどれか。
- 打撲痕を姉に見てもらう。
- 配偶者暴力相談支援センターに通報する。
- 暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。
- Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。
▶午後67
プロセスレコードについて正しいのはどれか。
- 看護過程の1つの段階である。
- 患者と家族間の言動を記述する。
- 看護師の対人関係技術の向上に活用する。
- 患者の精神症状をアセスメントする方法である。
▶午後68
集団精神療法の効果が最も期待できるのはどれか。
- 過眠症
- 躁状態
- 薬物依存症
- 小児自閉症
▶午後69
Aさん(80歳、女性)は、1人で暮らしている。内科と整形外科とを受診しているが、2週前から内服薬の飲み間違いがあり、主治医から訪問看護師に服薬管理の依頼があった。
Aさんがセルフケアを維持して内服するための訪問看護師の服薬管理の支援で最も適切なのはどれか。
- 内服薬は薬局から訪問看護師が受け取る。
- 自宅での内服薬の保管場所を分散する。
- 内服指導を診療科ごとに依頼する。
- 内服薬を1回分ごとにまとめる。
▶午後70
Aさん(70歳、男性)は、1人で暮らしている。慢性閉塞性肺疾患のため1週前から在宅酸素療法(0.5L/分、24時間持続)が開始された。Aさんは階段の昇降時に息切れがみられる。
自宅での入浴の方法に関する訪問看護師の説明で最も適切なのはどれか。
- 脱衣は看護師が全介助する。
- 浴槽に入ることは禁止する。
- 身体を洗うときはシャワーチェアを使う。
- 入浴中は携帯用酸素ボンベを利用できない。
▶午後71
Aさん(60歳、男性)は、1年前に膵癌と診断されて自宅で療養中である。疼痛管理はレスキューとして追加注入ができるシリンジポンプを使用し、オピオイドを持続的に皮下注射している。
訪問看護師のAさんへの疼痛管理の指導で適切なのはどれか。
- シリンジの交換はAさんが実施する。
- 疼痛がないときには持続的な注入をやめてもよい。
- レスキューとしてのオピオイドの追加注入はAさんが行う。
- レスキューとして用いるオピオイドの1回量に制限はない。
▶午後72
医療における安全管理のシステム設計の原則で正しいのはどれか。
- 個人の反省を促す。
- 人の記憶力を重視する。
- 作業のプロセスを標準化する。
- いくつかの業務を同時に実施する。
▶午後73
Aさん(79歳、女性)は、癌の化学療法を受けていたが、脳出血を起こし意識不明の状態になった。Aさんの家族は回復する見込みはないと医師から説明を受けた。家族はAさんの延命を望んでおり、医師と今後の治療方針を決定する前に看護師に相談した。
Aさんの家族への対応で最も適切なのはどれか。
- 医師に方針を決めてもらうよう伝える。
- 病院の倫理委員会に判断を依頼するよう伝える。
- Aさんのアドバンスディレクティブ〈事前指示〉を確認するよう伝える。
- 経管栄養法を開始することでAさんの身体の状態は維持できると伝える。
▶午後74
災害急性期における精神障害者への看護師の対応で最も適切なのはどれか。
- 名札の着用を指示する。
- 災害の状況については説明しない。
- 不眠が続いても一時的な変化と判断する。
- 服薬している薬剤を中断しないように支援する。
▶午後75
災害発生後、避難先の体育館で生活を始めた高齢者への対応で最も適切なのはどれか。
- トイレに近い場所を確保する。
- 持参薬を回収して被災者に分ける。
- 区画された範囲内で過ごすよう促す。
- 私語を控えて館内の静穏が保てるように指導する。
▶午後76
自己管理を行う上で自己効力感を高める支援として最も適切なのはどれか。
- 自己管理の目標はできるだけ高くする。
- 必要な知識をできるだけ多く提供する。
- 自己管理の方法で不適切な点はそのたびに指摘する。
- 自己管理で改善できた点が少しでもあればそれを評価する。
- 対象者が自己管理できない理由を話したときは話題を変える。
1歳0か月の幼児の標準的な身長と体重の組合せで正しいのはどれか。
身長――体重
- 55cm――6kg
- 75cm――6kg
- 75cm――9kg
- 100cm――9kg
- 100cm――12kg
▶午後78
Aさん(28歳、初産婦)は、妊娠11週である。身長160cm、体重52kg(非妊時体重50kg)である。現在は身体活動レベルⅠ(非妊時は身体活動レベルⅡ)で妊娠経過は順調である。
現時点で非妊時と比べて食事に付加することが望ましいのはどれか。
- 糖質
- 葉酸
- 蛋白質
- カリウム
- カルシウム
▶午後79
Aさん(60歳、男性)は、統合失調症で20年前から抗精神病薬を服用している。常に口を動かしているため、何か食べていないか看護師が口の中を確認するが、何も口には入っていない。Aさんは「勝手に口と舌が動いてしまう」と言う。
Aさんに現れている症状はどれか。
- 被害妄想
- 作為体験
- カタレプシー
- 遅発性ジスキネジア
- 静座不能〈アカシジア〉
小児医療に関する課題とその対応の組合せで正しいのはどれか。
- 低出生体重児の増加――人工乳による哺育の推進
- 育児不安が強い親の増加――子どもの自立支援
- 障害児の在宅医療のニーズの増加――レスパイトケアの充実
- 小児救急医療を受診する子どもの増加――ドクターカーの充実
- 成人になった小児慢性疾患患者の増加――親の意思決定の支援
▶午後81
小脳の機能はどれか。2つ選べ。
- 関節角度の知覚
- 振動感覚の中継
- 姿勢反射の調節
- 随意運動の制御
- 下行性の疼痛抑制
▶午後82
白血球減少症で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 好塩基球数は増加する。
- EBウイルス感染によって起こる。
- 白血球数が3,000/μL以下をいう。
- 好中球減少症では細菌に感染しやすくなる。
- 無顆粒球症は単球がなくなった病態をいう。
▶午後83
下垂体ホルモンの分泌低下により生じるのはどれか。2つ選べ。
- 性早熟症
- 低身長症
- 先端巨大症
- Sheehan〈シーハン〉症候群
- Cushing〈クッシング〉症候群
▶午後84
抗コリン薬の投与が禁忌の疾患はどれか。2つ選べ。
- 疥癬
- 緑内障
- 大腿骨骨折
- 前立腺肥大症
- 前頭側頭型認知症
▶午後85
新生児の養育に関する親への指導で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 「体温37.0℃で受診させましょう」
- 「沐浴は児が満腹のときに行いましょう」
- 「授乳後は顔を横に向けて寝かせましょう」
- 「衣類は大人よりも1枚少なくしましょう」
- 「オムツはおなかを締めつけないように当てましょう」
▶午後86
一般的な思春期の発育の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 骨端線が閉鎖する。
- 性的成熟は男子の方が女子より早く始まる。
- 成長ホルモンが性腺に作用して第二次性徴が起こる。
- 男子では身長増加のピークの前に精巣の発育が始まる。
- 女子では身長増加のピークの前に乳房の発育が終わる。
▶午後87
前頭葉の障害に伴う症状で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 人格の変化
- 感覚性失語
- 自発性の欠乏
- 平衡機能障害
- 左右識別障害
精神科病棟における身体拘束時の看護で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1時間ごとに訪室する。
- 拘束の理由を説明する。
- 水分摂取は最小限にする。
- 患者の手紙の受け取りを制限する。
- 早期の解除を目指すための看護計画を立てる。
▶午後89
Aさん(72歳、女性)は、1人で暮らしており、要介護1で訪問看護を利用している。昨日の訪問時、看護師は高級な羽毛布団を見かけ、Aさんに尋ねると購入の覚えがないと話した。別居している長男は、週1回電話でAさんの様子を確認している。
看護師の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 長男への連絡
- 羽毛布団の返品
- 成年後見人の選任
- 近隣住民への聞き取り
- Aさんの判断能力の評価
▶午後90
5%のクロルヘキシジングルコン酸塩を用いて0.2%希釈液2,000mLをつくるのに必要な薬液量を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②mL
資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第104回看護師国家試験
平成27年2月22日(日)に実施された第104回看護師国家試験について、午前問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第104回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 一般問題
▶午前26
胸管で正しいのはどれか。
- 弁がない。
- 静脈角に合流する。
- 癌細胞は流入しない。
- 主に蛋白質を輸送する。
▶午前27
ホルモンとその作用の組合せで正しいのはどれか。
- バソプレシン――利尿の促進
- オキシトシン――乳汁産生の促進
- テストステロン――タンパク合成の促進
- アルドステロン――ナトリウムイオン排泄の促進
▶午前28
低体温からの回復に伴う生体の反応はどれか。
- 廃用
- 発汗
- ふるえ
- 乳酸の蓄積
▶午前29
胸部エックス線写真を別に示す。

心胸郭比について正しいのはどれか。
- 小さい。
- 正常である。
- 大きい。
- 測定できない。
▶午前30
乳癌について正しいのはどれか。
- 乳房の内側に多い。
- 有痛性の腫瘤が特徴である。
- エストロゲン補充療法を行う。
- センチネルリンパ節生検により郭清する範囲を決める。
日本の令和4年(2022年)における女性の年齢階級別労働力率の推移を示すグラフの特徴はどれか。
- 20歳代をピークとする山型
- 40歳代をピークとする山型
- 20歳代と40歳代をピークとするM字型
- 20歳代から50歳代にかけての逆U字型
生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。
- 保健センター
- 福祉事務所
- 保健所
- 病院
環境要因と健康への影響の組合せで正しいのはどれか。
- 高温――難聴
- ヒ素――イタイイタイ病
- オゾンホール――赤外線障害
- 光化学オキシダント――粘膜刺激
大気汚染に関する環境基準が定められている物質はどれか。
- 二酸化炭素
- 一酸化窒素
- フッ化水素
- 微小粒子状物質
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。
- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限
▶午前36
看護師と患者の信頼関係の構築において最も考慮すべき要素はどれか。
- 病院の方針
- 看護師の思い
- 患者の価値観
- 家族の経済状況
▶午前37
終末期の患者の妻は患者の死期が近いことを受け入れがたい状態である。
妻の気持ちを受容する看護師の言動として最も適切なのはどれか。
- 「今がつらいときですね」
- 「死を受け入れるしかないと思いますよ」
- 「最期にしてあげたいことを考えましょう」
- 「亡くなった後の準備をすぐに始めましょう」
▶午前38改題
成人の立位の腹部エックス線写真を別に示す。
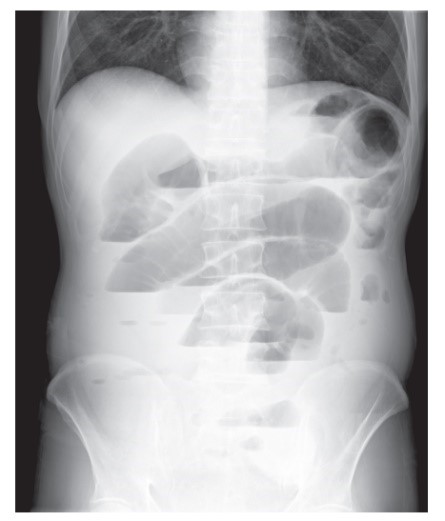
この所見から最も考えられる疾患はどれか。
- 胆石症
- 腸閉塞
- 潰瘍性大腸炎
- 十二指腸潰瘍
血液の付着した注射針を廃棄する容器はどれか。
- 黄色バイオハザードマーク付きの容器
- 橙色バイオハザードマーク付きの容器
- 赤色バイオハザードマーク付きの容器
- 非感染性廃棄物用の容器
▶午前40
臥床している患者に対して看護師が手袋を装着して口腔ケアを実施した。
口腔ケア後の看護師の行動で適切なのはどれか。
- 手袋を外し、すぐに新しい手袋を装着して別の患者のケアを行う。
- 使用した手袋を装着したまま患者の寝衣を交換する。
- 手袋を装着したまま患者の歯ブラシを洗浄する。
- 使用した手袋は一般廃棄物の容器に捨てる。
▶午前41
慢性膵炎の患者の食事療法で制限が必要なのはどれか。
- 糖質
- 脂質
- 蛋白質
- 脂溶性ビタミン
▶午前42
肺血流量が最も減少する体位はどれか。
- 立位
- 座位
- 仰臥位
- Fowler〈ファウラー〉位
▶午前43
ベンチュリーマスクによる酸素吸入で正しいのはどれか。
- 最適な酸素流量は18L/分である。
- 酸素流量に関係なく加湿器が必要である。
- 24〜50%の安定した吸入酸素濃度が得られる。
- マスクに空気を溜めることのできるバッグがある。
成人の心臓マッサージ法の圧迫部位を図に示す。
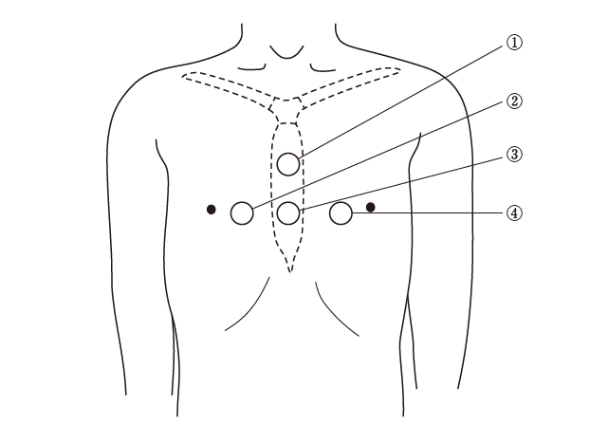
正しいのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
▶午前45
生体検査はどれか。
- 尿検査
- 血液検査
- 心電図検査
- 脳脊髄液検査
日本の最近10年の成人を取り巻く社会状況で正しいのはどれか。
- 生産年齢人口の占める割合の増加
- 単独世帯の占める割合の増加
- 非正規雇用者の比率の低下
- 平均初婚年齢の低下
▶午前47
廃用症候群の説明で適切なのはどれか。
- 二次的に低カルシウム血症を発症する。
- 加齢とともに症状の進行は遅くなる。
- 二次的に起立性低血圧を発症する。
- 癌患者ではみられない。
▶午前48
鮮紅色の底面をした水疱を形成し、痛みが強い熱傷創の回復に要する期間はどれか。
- 2〜3日
- 1〜2週
- 3〜4週
- 2〜3か月
▶午前49
フローボリューム曲線を図に示す。
慢性閉塞性肺疾患の患者の結果はどれか。
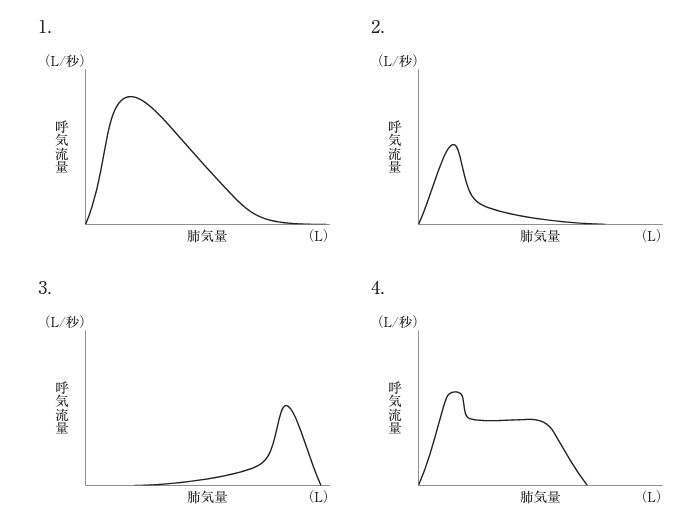
▶午前50
Aさん(39歳、男性、会社員)は、最近口渇が強く、飲水量が増えた。毎日5L以上の水のような薄い排尿があり、夜間に何回も排尿に起きるようになったため病院を受診しホルモン分泌異常を指摘された。
原因と考えられるホルモンが分泌される部位はどれか。
- 視床下部
- 下垂体後葉
- 甲状腺
- 副腎皮質
▶午前51
眼底検査の前処置で散瞳薬を点眼する際の看護で適切なのはどれか。
- 白内障の既往の有無を確認する。
- 羞明が強くなると説明する。
- 散瞳薬による症状は30分程度で消失すると説明する。
- 眼を閉じた状態で検査室に誘導する。
▶午前52
脊髄造影について正しいのはどれか。
- 検査前の食事制限はない。
- 造影剤を硬膜外腔に注入する。
- 検査中のけいれん発作に注意する。
- 検査後は水平仰臥位で安静を保つ。
▶午前53
Aさん(52歳、女性)は、子宮頸癌で広汎子宮全摘術後に排尿障害を発症した。退院に向けて自己導尿の練習を開始したが、39.0℃の発熱と右背部の叩打痛が出現した。
Aさんの症状の原因として考えられるのはどれか。
- 膀胱炎
- 虫垂炎
- 腎盂腎炎
- 骨盤内膿瘍
▶午前54
流動性知能はどれか。
- 新聞を読む。
- 町内会の役員を務める。
- 結婚式のマナーを知っている。
- 携帯電話に電話番号を登録する。
▶午前55
Aさん(66歳、男性)は、尿管結石症で入院し、鎮痛薬の投与と点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。日常生活は自立している。輸液開始の1時間後、Aさんの病室で大きな音がしたので看護師が駆けつけると、Aさんはベッドサイドに座り込んでいた。「トイレに行こうとベッドから立ち上がろうとして、点滴のスタンドをつかんだら滑った」と話した。転倒後の診察の結果に異常はなかった。
Aさんが再び転倒しないための対応で最も適切なのはどれか。
- 床上排泄にする。
- 誰の過失か明らかにする。
- 転倒の原因を一緒に考える。
- 夜間は家族に付き添いを依頼する。
▶午前56
Aさん(88歳、女性)は、中等度の認知症である。介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を利用している。Aさんに入浴を勧めるとAさんは「風呂なんて嫌だ」と強い口調で言い、理由を聞いても話さない。
このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。
- 全身清拭する。
- 入浴の必要性を説明する。
- 石けんとタオルを見せる。
- 気持ちが落ち着いてから再び入浴を勧める。
▶午前57
Aさん(75歳、女性)は、自立した生活を送っている。尿失禁があるため、尿失禁用パッドを使用している。大腿内側部と外陰部の掻痒感を訴え、皮膚科を受診し、外陰部掻痒症と診断された。
このときの指導内容で適切なのはどれか。
- 水分摂取を控える。
- 間欠的自己導尿を行う。
- 尿失禁用パッドの交換頻度を増やす。
- 搔痒感のある部位をアルコール綿で清拭する。
▶午前58
手指の巧緻性が低下している高齢者が操作しやすい補聴器の種類はどれか。
- 骨導補聴器
- 耳あな型補聴器
- 耳かけ型補聴器
- ポケット型補聴器
▶午前59
インフルエンザが流行しているが、小規模多機能型居宅介護を行う事業所では罹患者はいない。
この事業所で看護師が行う罹患予防の対策で最も適切なのはどれか。
- 宿泊の利用を断る。
- 湿度を10%以下に保つ。
- 利用者に手洗いを勧める。
- 利用者に予防的に抗インフルエンザ薬を与薬する。
▶午前60
A君(8歳、男児)は、先天性内反足の手術後、両下腿のギプス固定を行う予定である。手術前にA君に対してギプス固定後の日常生活に関する説明をすることになった。
A君に対する看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「シャワー浴はやめておきましょう」
- 「ギプスの部分を高くしておきましょう」
- 「足のゆびを動かさないようにしましょう」
- 「ギプスを外すまでベッド上で過ごしましょう」
▶午前61
肺高血圧が長期に持続し、肺血管抵抗が上昇することにより、短絡血流が主に左右短絡から右左短絡になった状態はどれか。
- 拡張型心筋症
- 総肺静脈還流異常症
- Fallo〈ファロー〉四徴症
- Eisenmenger〈アイゼンメンジャー〉症候群
出生前診断について正しいのはどれか。
- 遺伝相談は勧めない。
- 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。
- 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。
- 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。
妊娠中の母体の要因が胎児に及ぼす影響について正しいのはどれか。
- 飲酒の習慣による巨大児
- 喫煙による神経管形成障害
- 妊娠初期の風疹の罹患による先天性心疾患
- ビタミンAの過剰摂取による低出生体重児
▶午前64
高齢女性に生じやすい疾患と原因の組合せで正しいのはどれか。
- 腟炎――腟分泌物の酸性化
- 外陰炎――プロゲステロンの減少
- 子宮脱――骨盤底筋群の筋力低下
- 子宮体癌――プロラクチンの増加
▶午前65
在胎38週に正常分娩で出生した児で、体重2,400gの児が体重3,000gの児に比べて起こしやすい症状はどれか。
- 高血糖
- 心雑音
- 低体温
- 無呼吸
▶午前66
神経伝達物質と精神疾患の組合せで最も関連が強いのはどれか。
- ドパミン――脳血管性認知症
- セロトニン――うつ病
- ヒスタミン――Alzheimer〈アルツハイマー〉病
- アセチルコリン――統合失調症
▶午前67
Aさんの母親は過干渉で、Aさんが反論すると厳しい口調でいつまでもAさんを批判し続けるため、Aさんは母親との関係に悩んできた。その母親と同年代で体格が似ている担当看護師に対し、Aさんは常に反抗的な態度をとり、強い拒絶を示している。
Aさんにみられるのはどれか。
- 投影
- 逆転移
- 反動形成
- 陰性転移
精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。
- 保健所
- 地方裁判所
- 精神医療審査会
- 地方精神保健福祉審議会
▶午前69
訪問看護師の関わりで最も適切なのはどれか。
- 看護師の判断で訪問時間を延長する。
- 療養者のライフスタイルを尊重する。
- 1人暮らしの療養者では家族のことは考慮しない。
- 訪問時間以外での療養者との個人的な付き合いを大切にする。
▶午前70
Aさん(59歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。Parkinson〈パーキンソン〉病で、Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類ステージⅢであり、嚥下に困難がある。要介護2の認定を受けている。
食事の見守りを行う妻への訪問看護師による指導で適切なのはどれか。
- 「食事はきざみ食にしましょう」
- 「食事は決まった時間にしましょう」
- 「食事中はテレビをつけておきましょう」
- 「食べ物を飲み込んだことを確認しましょう」
▶午前71
Aさん(52歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。妻は末期の肺癌で、今朝自宅で亡くなった。
主治医が死亡診断を行った後のAさんへの訪問看護師の対応で最も適切なのはどれか。
- 葬儀を手配するよう勧める。
- 医療機器は早急に片づけるよう勧める。
- Aさんの希望に沿って、死後の処置を行う。
- 本日中に死亡診断書を役所に提出するよう説明する。
▶午前72
在宅中心静脈栄養法〈HPN〉について適切なのはどれか。
- 輸液ポンプは外出時には使えない。
- 24時間持続する注入には適さない。
- 輸液の調剤は薬局の薬剤師に依頼できる。
- 家族が管理できることが適用の必須条件である。
▶午前73
看護サービスの質の評価は、①ストラクチャー(看護サービス提供のための仕組み)、②プロセス(提供される看護サービス)、③アウトカム(看護サービスの成果)に分類される。
アウトカムはどれか。
- 患者の満足度
- 退院指導の実施
- 看護手順の整備の有無
- 看護師1人当たりの患者数
医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。
- 医療安全管理者の配置
- 厚生労働省へのインシデント報告
- 患者・家族への医療安全指導の実施
- 医療安全支援センターへの医療事故報告
災害発生後の時期と災害看護活動の組合せで最も適切なのはどれか。
- 災害発生直後〜数時間――食中毒予防
- 災害発生後3日〜1週――外傷後ストレス障害〈PTSD〉への対応
- 災害発生後1週〜1か月――廃用症候群の予防
- 災害発生後1か月以降――救命処置
令和4年(2022年)の国連エイズ合同計画〈UNAIDS〉の報告において、ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉陽性者が最も多い地域はどれか。
- 東欧・中央アジア
- 西欧・中欧・北アメリカ
- アジア太平洋
- 東部・南部アフリカ
▶午前77
タンパク合成が行われる細胞内小器官はどれか。
- 核
- リボソーム
- リソソーム
- ミトコンドリア
- Golgi〈ゴルジ〉装置
▶午前78
閉眼に関与する神経はどれか。
- 動眼神経
- 滑車神経
- 三叉神経
- 外転神経
- 顔面神経
▶午前79
血管造影写真を別に示す。
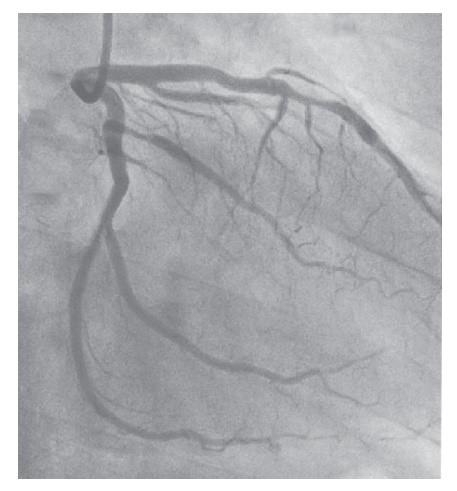
造影部位で正しいのはどれか。
- 脳動脈
- 冠動脈
- 肺動脈
- 肝動脈
- 腎動脈
▶午前80
健常な幼児の基本的生活習慣の獲得で正しいのはどれか。
- 1歳6か月でうがいができるようになる。
- 2歳6か月で靴を履けるようになる。
- 3歳でコップを使って飲めるようになる。
- 4歳で手を洗って拭くようになる。
- 5歳で昼寝は1日1回になる。
▶午前81改題
不妊症について正しいのはどれか。
- 6か月間避妊せずに性交渉があっても妊娠しない状態である。
- 頻度は妊娠を希望し避妊しないカップル10組に3組である。
- 体外受精に要する費用は保険適用される。
- 女性の年齢と不妊症の治療効果は関係しない。
- 男性側の原因は7割程度である。
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
- スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。
- アセスメントで利用者の疾患を診断する。
- 利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。
- ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。
- ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。
▶午前83
伸張反射の構成要素はどれか。2つ選べ。
- 骨膜
- 筋紡錘
- 腱紡錘
- 脊髄側角
- 運動神経
▶午前84
吸息時に収縮する筋はどれか。2つ選べ。
- 腹直筋
- 腹横筋
- 横隔膜
- 外肋間筋
- 内肋間筋
▶午前85
多発性硬化症で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 脱髄病変が多発する。
- 髄液中のIgGは低下する。
- 視力低下は網脈絡膜炎による。
- MRIは病変の検出に有用である。
- 末梢神経が障害されることが多い。
▶午前86
食道癌について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 頸部食道に好発する。
- 放射線感受性は低い。
- アルコール飲料は危険因子である。
- 日本では扁平上皮癌に比べて腺癌が多い。
- ヨードを用いた内視鏡検査は早期診断に有用である。
▶午前87
心電図を別に示す。
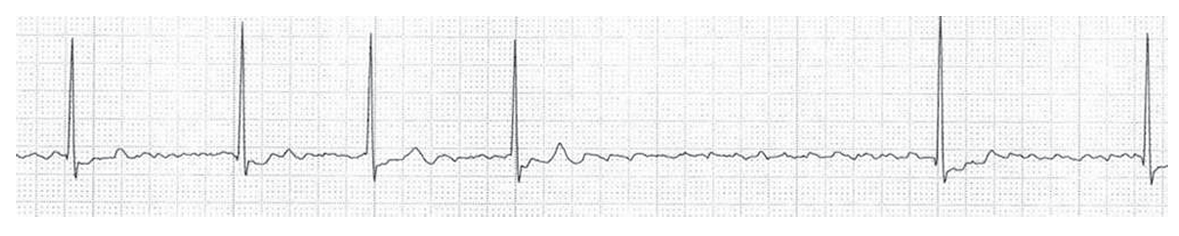
所見として正しいのはどれか。2つ選べ。
- R-R間隔の不整
- 細動波の出現
- QRS波の消失
- STの上昇
- 陰性T波
▶午前88
喉頭摘出および気管孔造設術を受けた患者でみられるのはどれか。2つ選べ。
- 誤嚥をしやすい。
- 咀嚼がしにくい。
- においが分かりづらい。
- 高い音が聞こえにくい。
- 飲み込んだ食物が鼻に逆流しやすい。
▶午前89
改訂版デンバー式発達スクリーニング検査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 4領域について判定を行う。
- 適応年齢は0〜6歳である。
- 判定結果は数値で示される。
- 知能指数の判定が可能である。
- 1領域に10の検査項目がある。
▶午前90
精神障害者のリカバリ〈回復〉の考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 患者に役割をもたせない。
- 薬物療法を主体に展開する。
- 患者の主体的な選択を支援する。
- 患者のストレングス〈強み・力〉に着目する。
- リカバリ〈回復〉とは病気が治癒したことである。
資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第104回看護師国家試験
平成26年2月16日(日)に実施された第103回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第103回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後26
食道について正しいのはどれか。
- 厚く強い外膜で覆われる。
- 粘膜は重層扁平上皮である。
- 胸部では心臓の腹側を通る。
- 成人では全長約50cmである。
▶午後27
遺伝子について正しいのはどれか。
- DNAは体細胞分裂の前に複製される。
- DNAは1本のポリヌクレオチド鎖である。
- DNAの遺伝子情報からmRNAが作られることを翻訳という。
- RNAの塩基配列に基づきアミノ酸がつながることを転写という。
▶午後28
活動電位について正しいのはどれか。
- 脱分極が閾値以上に達すると発生する。
- 細胞内が一過性に負〈マイナス〉の逆転電位となる。
- 脱分極期には細胞膜のカリウム透過性が高くなる。
- 有髄神経ではPurkinje〈プルキンエ〉細胞間隙を跳躍伝導する。
▶午後29
脳神経とその機能の組合せで正しいのはどれか。
- 顔面神経――顔の感覚
- 舌下神経――舌の運動
- 動眼神経――眼球の外転
- 三叉神経――額のしわ寄せ
▶午後30
白血球について正しいのはどれか。
- 酸素を運搬する。
- 貪食作用がある。
- 骨髄で破壊される。
- 血液1μL中に10万~20万個含まれる。
▶午後31
降圧利尿薬により血中濃度が低下するのはどれか。
- ナトリウム
- 中性脂肪
- 尿酸
- 血糖
▶午後32
肺癌について正しいのはどれか。
- 腺癌は小細胞癌より多い。
- 女性の肺癌は扁平上皮癌が多い。
- 腺癌は肺門部の太い気管支に好発する。
- 扁平上皮癌の腫瘍マーカーとしてCEAが用いられる。
▶午後33
急性左心不全の症状はどれか。
- 肝腫大
- 呼吸困難
- 下腿浮腫
- 頸静脈怒張
関節リウマチで起こる主な炎症はどれか。
- 滑膜炎
- 骨髄炎
- 骨軟骨炎
- 関節周囲炎
▶午後35
重症筋無力症について正しいのはどれか。
- 筋肉の障害に起因する。
- 手術療法は甲状腺摘出である。
- 特徴的な症状は眼瞼下垂である。
- クリーゼが発症した時は抗コリンエステラーゼ薬を投与する。
障害者基本法で正しいのはどれか。
- 目的は障害者の保護である。
- 障害者の日が規定されている。
- 身体障害と知的障害の2つが対象である。
- 公共的施設のバリアフリー化の計画的推進を図ることとされている。
外来で患者の血液が付着したガーゼを処理する取り扱いで正しいのはどれか。
- 産業廃棄物
- 一般廃棄物
- 感染性産業廃棄物
- 感染性一般廃棄物
社会福祉に関係する職種とその業務についての組合せで正しいのはどれか。
- 精神保健福祉士――精神障害者保健福祉手帳の発行
- 介護支援専門員――居宅サービス計画の作成
- 介護福祉士――生活保護の認定
- 社会福祉士――要介護度の認定
▶午後39
がんの告知を受けた患者の態度と防衛機制の組合せで正しいのはどれか。
- がんのことは考えないようにする――投射
- がんになったのは家族のせいだと言う――抑圧
- 親ががんで亡くなったので自分も同じだと話す――代償
- 通院日に来院せず、家でゲームをしていたと話す――逃避
▶午後40
カウンセリングの基本的態度で適切なのはどれか。
- 同情
- 指導
- 受容
- 評価
▶午後41
学習の特徴について誤っているのはどれか。
- 環境の影響を受ける。
- 報酬によって強化される。
- 永続的な行動の変容である。
- 情報の一時的な獲得である。
▶午後42
異常な呼吸音とその原因の組合せで正しいのはどれか。
- 連続性副雑音――気道の狭窄
- 断続性副雑音――胸膜での炎症
- 胸膜摩擦音――肺胞の伸展性の低下
- 捻髪音――気道での分泌物貯留
▶午後43
経鼻経管栄養法の実施方法とその目的の組合せで正しいのはどれか。
- 注入前に胃内容物を吸引する――消化の促進
- 注入中はFowler〈ファウラー〉位にする――逆流の防止
- 注入終了後に微温湯を流す――誤嚥の予防
- 注入終了後はチューブを閉鎖する――嘔吐の予防
▶午後44
気管内挿管中の患者の体位ドレナージの実施について適切なのはどれか。
- 実施前後に気管内吸引を行う。
- 体位ドレナージ後に吸入療法を行う。
- 自分で体位変換できる患者には行わない。
- 創部ドレーンが挿入されている場合は禁忌である。
▶午後45
赤血球濃厚液の輸血について正しいのはどれか。
- 専用の輸血セットを使用する。
- 使用直前まで振盪させて使用する。
- 使用直前に冷蔵庫から取り出して使用する。
- 呼吸困難出現時は滴下数を減らして続行する。
地域連携クリニカルパスについて正しいのはどれか。
- 診療報酬の評価の対象ではない。
- 市町村を単位とした連携である。
- 記載内容は医師の治療計画である。
- 医療機関から在宅まで継続した医療を提供する。
▶午後47
Aさん(26歳、男性)は、大量服薬による急性中毒が疑われ、午後9時30分に救急搬送された。呼吸状態と循環動態に異常はないが、意識は低下している。付き添って来たAさんの母親は「午後8時に夕食を終えて息子は部屋に戻りました。午後9時にお風呂へ入るよう声をかけに部屋に行ったら、倒れていたんです。息子はうつ病で通院中でしたが、最近は症状が落ち着いていました」と話す。
このときの対応で適切なのはどれか。
- 気管内挿管を行う。
- 咽頭を刺激して吐かせる。
- 胃酸分泌抑制薬を投与する。
- Aさんの母親にどんな薬を内服していたかを尋ねる。
▶午後48
Aさん(56歳、男性)は、進行結腸癌の術後に両側の多発肺転移が進行し、終末期で在宅療養中であったが呼吸困難が増悪したため入院した。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は95%であるが、安静時でも呼吸困難を訴え、浅い頻呼吸となっている。 発熱はなく、咳嗽はあるが肺炎の併発はない。
Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 仰臥位を保つ。
- 酸素投与は行わない。
- モルヒネ塩酸塩の投与を検討する。
- 安静を保つため訪室は最低限とする。
▶午後49
Aさん(58歳、女性)は、10年前に肺気腫を指摘されたが喫煙を続け、体動時に軽い息切れを自覚していた。Aさんは、肺炎で救急病院に入院し経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉86%でフェイスマスクによる酸素投与(4L/分)が開始された。抗菌薬投与後6日、鼻腔カニューラによる酸素投与(2L/分)でAさんの経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉が94%まで回復した。夜間Aさんは眠れているようだが、早朝に頭痛を訴え、日中も傾眠傾向になった。
Aさんへの対応で適切なのはどれか。
- 抗菌薬の変更
- 酸素投与量の増加
- 動脈血液ガス分析の実施
- 胸部エックス線撮影の実施
B型肝炎と比べたC型肝炎の特徴について正しいのはどれか。
- 劇症化しやすい。
- 性行為による感染が多い。
- 無症状のまま慢性化しやすい。
- ワクチン接種による感染予防対策がある。
▶午後51
頭蓋内圧亢進を助長するのはどれか。
- 便秘
- 酸素療法
- 浸透圧利尿薬
- Fowler〈ファウラー〉位
▶午後52
Aさん(42歳、男性)は、血尿を主訴に泌尿器科を受診した。診察の結果、Aさんは膀胱鏡検査を受けることになった。
Aさんへの検査についての説明で適切なのはどれか。
- 「入院が必要です」
- 「前日は夕食を食べないでください」
- 「局所麻酔で行います」
- 「終了後は水分の摂取を控えてください」
▶午後53
Aさん(85歳、男性)は、認知症である。Aさんは肺炎で入院し、病状が改善したため、主治医は退院を許可した。Aさんは「家に帰りたい」と繰り返し言っているが、同居していた長男夫婦は高齢者施設への入所を希望している。
このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。
- 主治医に退院後の療養場所を決定してもらう。
- 長男夫婦にAさんの希望を尊重するよう話す。
- 長男夫婦に入所が可能な高齢者施設の情報を提供する。
- 長男夫婦がAさんの施設への入所を希望している理由を確認する。
▶午後54
高齢者の蛋白質・エネルギー低栄養状態〈protein-energy malnutrition:PEM〉について正しいのはどれか。
- 体脂肪の消耗はみられない。
- 要介護度が高いほどPEMの発症率は高い。
- PEMの発症率は心疾患によるものが最も高い。
- 栄養指標は血清アルブミン3.7g/dL以下である。
▶午後55
加齢による視覚の変化とその原因の組合せで正しいのはどれか。
- 老視――毛様体筋の萎縮
- 色覚異常――眼圧の亢進
- 視野狭窄――散瞳反応時間の延長
- 明暗順応の低下――水晶体の硬化
▶午後56
Aさん(80歳、男性)は、肺炎と高血圧症で入院している。入院日の夜からAさんにはせん妄の症状がみられる。Aさんの家族は「しっかりした人だったのに急におかしくなってしまった」と動揺している。
せん妄についてAさんの家族への説明で正しいのはどれか。
- 「認知症の一種です」
- 「昼間に起こりやすいです」
- 「一度起こると治りません」
- 「環境の変化で起こることがあります」
▶午後57
大腿骨転子部骨折のため人工骨頭置換術を行った。
術後の腓骨神経麻痺予防のための看護で適切なのはどれか。
- 大腿四頭筋訓練を実施する。
- 患側下肢を外旋位に固定する。
- 患側下肢に弾性ストッキングを着用する。
- 患側下肢の母趾と第2趾間の知覚異常の有無を観察する。
小規模多機能型居宅介護で正しいのはどれか。
- 都道府県が事業者を指定する。
- 介護給付の施設サービスの1つである。
- 1日あたりの利用定員は19人以下である。
- 要介護者の状態に応じて短期間の宿泊が可能である。
▶午後59
Aちゃん(3歳、女児)は母親とともに小児科外来を受診した。診察の結果、Aちゃんは血液検査が必要と判断され、処置室で採血を行うことになった。
看護師の対応で適切なのはどれか。
- 処置前、母親ひとりに採血の説明をする。
- 坐位で行うか仰臥位で行うかをAちゃんに選ばせる。
- 注射器に血液の逆流が見られた時に「終わったよ」とAちゃんに伝える。
- 処置後、Aちゃんと採血について話さないようにする。
▶午後60
正常に発達している小児が2歳0か月ころ、新たに獲得する言語で正しいのはどれか。
- 「おちゃ、ちょうだい」
- 「おかしがないの」
- 「これ、なあに」
- 「まんま」
▶午後61
Aちゃん(3歳0か月)は、午後から38.0℃の発熱があったが、食事は摂取でき活気があった。夜間になり、3回嘔吐したため救急外来を受診した。来院時、Aちゃんは傾眠傾向にあった。診察の結果、髄膜炎が疑われ、点滴静脈内注射を開始し入院した。入院時、Aちゃんは、体温38.5℃、呼吸数30/分、心拍数120/分、血圧102/60mmHgであった。
入院時のAちゃんへの対応で最も優先度が高いのはどれか。
- 冷罨法を行う。
- 水平仰臥位を保つ。
- 意識レベルを観察する。
- 大泉門の状態を観察する。
▶午後62
食物アレルギーのある8歳の児童がアナフィラキシーショックを発症した場合の対応として適切なのはどれか。
- 水分の補給
- 抗ヒスタミン薬の内服
- 副腎皮質ステロイドの吸入
- アドレナリンの筋肉内注射
▶午後63
A君(15歳、男子)は、病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫に対する治療を続けていた。現在、肺に転移しており終末期にある。呼吸困難があり、鼻腔カニュ-ラで酸素(2L/分)を投与中である。A君の食事の摂取量は徐々に減っているが、意識は清明である。1週間後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式は出席したい」と話している。
看護師のA君への対応として最も適切なのはどれか。
- 今の状態では出席は難しいと話す。
- 出席できるように準備しようと話す。
- 出席を決める前に体力をつけようと話す。
- 卒業式の前日に出席するかどうか決めようと話す。
▶午後64
妊娠中期から末期の便秘について適切なのはどれか。
- 妊娠中期は妊娠末期と比較して生じやすい。
- エストロゲンの作用が影響している。
- 子宮による腸の圧迫が影響している。
- けいれん性の便秘を生じやすい。
▶午後65
正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。
- 分娩開始時、胎児の背中は母体の背側にある。
- 後頭部が先進する。
- 胎児の顔は母体の腹側を向いて娩出される。
- 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。
▶午後66
新生児室の環境で適切なのはどれか。
- 無菌室
- 湿度は50~60%
- 温度は27~28℃
- コット間の距離は60cm
▶午後67
Aさん(50歳、男性)は、アルコール依存症のために断酒目的で入院した。入院前日の夜まで毎日飲酒をしていたと話している。
入院当日に優先的に行うのはどれか。
- 抗酒薬の説明を行う。
- 断酒会への参加を促す。
- 振戦の有無を確認する。
- ストレス対処行動を分析する。
▶午後68
Aさん(23歳、女性)は、トラックの横転事故に巻き込まれて一緒に歩いていた友人が死亡し、自分も軽度の外傷で入院している。看護師がAさんに「大変でしたね」と声をかけると、笑顔で「大丈夫ですよ。何のことですか」と言うだけで、事故のことは話さない。Aさんは検査の結果、軽度の外傷以外に身体的な異常や記憶の障害はない。
この現象はどれか。
- 解離
- 昇華
- 合理化
- 反動形成
▶午後69
精神疾患患者の家族の感情表出〈expressed emotion:EE〉について正しいのはどれか。
- 家族の訴えが明確になる。
- 認知行動療法の技法である。
- 統合失調症の再発に関連がある。
- 家族のストレス対処として効果的である。
▶午後70
Aさん(21歳、男性)は、統合失調症と診断され、入院してハロペリドールの投与が開始された。入院後3日、39.5℃の急激な発熱、発汗、筋固縮および意識障害を認めた。
Aさんの状態で考えられるのはどれか。
- 昏迷
- 悪性症候群
- てんかん発作
- 静座不能〈アカシジア〉
▶午後71
訪問看護師が、在宅医療に移行する患者の退院調整のために医療機関の看護師から得る情報で、優先度が高いのはどれか。
- 医療処置の指導内容
- 経済的な問題への対応
- 介護サービス利用の有無
- 訪問看護指示書の記載内容
健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。
- サービス対象は65歳以上である。
- 介護支援専門員がケアプランを作成する。
- 末期の悪性腫瘍の療養者への訪問回数に制限はない。
- 特定医療費(指定難病)受給者証を持っている者は自己負担額1割である。
▶午後73
Aさんは、1人で暮らしている。血管性認知症があり、降圧薬を内服している。要介護1で、週3回の訪問介護と週1回の訪問看護を利用している。最近では、Aさんは日中眠っていることが多く、週1回訪ねてくる長男に暴言を吐くようになっている。
Aさんの長男の話を傾聴した上で、訪問看護師の長男への対応で最も適切なのはどれか。
- デイサービスの利用を提案する。
- Aさんを怒らせないように助言する。
- Aさん宅に行かないように助言する。
- 薬の内服介助をするように提案する。
▶午後74
在宅酸素療法(1L/分24時間)を行っている療養者の居住地域で2週間後に日中3時間の停電が予定されている。
停電への対応で最も適切なのはどれか。
- 事前の呼吸訓練
- 医療機関への入院
- 自家発電器の購入
- 携帯用酸素ボンベの準備
病院における医療安全管理体制で正しいのはどれか。
- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 医療安全管理のために必要な研修を3年に1度行う。
- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない。
大規模災害時のトリアージで緊急度が最も高いと判断されるのはどれか。
- 下腿に創傷があるが補助があれば歩行できる。
- 自発呼吸はあるが橈骨動脈は触知できない。
- 気道確保しても自発呼吸がない。
- 開眼・閉眼の指示に応じる。
▶午後77
災害の慢性期(復興期)における避難所内の看護師の役割で最も適切なのはどれか。
- 住宅支援
- 感染予防
- 安全な避難と誘導
- 居住スペースの確保
▶午後78改題
国際連合児童基金〈UNICEF〉の報告による5歳未満児の死亡率(2019年)が最も高い地域はどれか。
- サハラ以南のアフリカ
- 南アジア
- 北アメリカ
- ヨーロッパ・中央アジア
▶午後79
Aさんは、3年前に来日した外国人でネフローゼ症候群のため入院した。Aさんは日本語を話し日常会話には支障はない。Aさんの食事について、文化的に特定の食品を食べてはいけないなどの制限があるがどうしたらよいかと、担当看護師が看護師長に相談した。
担当看護師に対する看護師長の助言で最も適切なのはどれか。
- 日本の病院なので文化的制限には配慮できないと話す。
- 文化的制限は理解できるが治療が最優先されると話す。
- Aさんの友人から文化的制限に配慮した食事を差し入れてもらうよう話す。
- 文化的制限に配慮した食事の提供が可能か栄養管理部に相談するよう話す。
▶午後80
血液検査で抗凝固剤が入っている採血管を使用するのはどれか。
- 血球数
- 電解質
- 中性脂肪
- 梅毒抗体
- 交差適合試験
市町村の業務でないのはどれか。
- 妊娠届の受理
- 母子健康手帳の交付
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 3歳児健康診査
- 小児慢性特定疾患公費負担医療給付
▶午後82
糖尿病神経障害のある患者へのフットケアの説明で適切なのはどれか。
- 「靴は大きめのサイズがよいです」
- 「靴下を履くようにしてください」
- 「1週間に1回は足の観察をしてください」
- 「足の傷は痛くなったら受診してください」
- 「外出後は足をアルコールで消毒しましょう」
Ⅳ型(遅延型)アレルギー反応について正しいのはどれか。2つ選べ。
- IgE抗体が関与する。
- 肥満細胞が関与する。
- Tリンパ球が関与する。
- ヒスタミンが放出される。
- ツベルクリン反応でみられる。
▶午後84
肝硬変でみられる検査所見はどれか。2つ選べ。
- 血小板増多
- 尿酸値上昇
- 血清アルブミン値低下
- 血中アンモニア値上昇
- プロトロンビン時間短縮
▶午後85
膀胱留置カテーテル挿入中のシャワー浴について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 実施前に蓄尿バッグを空にする。
- シャワー中はカテーテルを閉鎖する。
- 蓄尿バッグは腰より高い位置にかける。
- 終了後は挿入部をエタノールで消毒する。
- 終了後はカテーテルを固定するテープの位置を変える。
▶午後86
潰瘍性大腸炎と比べたCrohn〈クローン〉病の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 悪性化の頻度は低い。
- 瘻孔を併発しやすい。
- 初発症状は粘血便である。
- 炎症は大腸に限局している。
- 好発年齢は50歳以上である。
▶午後87
抗甲状腺ホルモン薬の副作用はどれか。2つ選べ。
- 多毛
- 眼球突出
- 中心性肥満
- 肝機能障害
- 無顆粒球症
▶午後88
胎児と胎児付属物について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 妊娠4週では、Doppler〈ドプラ〉法で胎児心音が聴取できる。
- 妊娠12週では、胎盤が完成している。
- 妊娠24週では、胎児の呼吸様運動がみられる。
- 妊娠26週では、胎児の胎位は固定している。
- 妊娠36週では、肺胞内に十分な肺表面活性物質が分泌されている。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、病院の管理者が精神科病院に入院中の者に対して制限できるのはどれか。2つ選べ。
- 手紙の発信
- 弁護士との面会
- 任意入院患者の開放処遇
- 信書の中の異物の受け渡し
- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
▶午後90
「フロセミド注15mgを静脈内注射」の指示を受けた。注射薬のラベルに「20mg/2mL」と表示されていた。
注射量を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:①.②mL
資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第103回看護師国家試験
平成25年2月17日(日)に実施された第102回看護師国家試験について、午後問題のうち一般問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2025/2026」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第102回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2025.8.26 定価:3,740円(税込) 416頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午後 一般問題
▶午後26
血中カルシウム濃度を上昇させるホルモンを分泌する器官はどれか。
- 副甲状腺
- 甲状腺
- 下垂体
- 副腎
▶午後27
ヒトの精子細胞における染色体の数はどれか。
- 22本
- 23本
- 44本
- 46本
低値によって脂質異常症と診断される検査項目はどれか。
- トリグリセリド
- 総コレステロール
- 低比重リポ蛋白コレステロール〈LDL-C〉
- 高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉
▶午後29
麻痺すると猿手を生じるのはどれか。
- 総腓骨神経
- 橈骨神経
- 尺骨神経
- 正中神経
労働基準法において、就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。
- 産前6週間の就業禁止
- 産後6週間の就業禁止
- 深夜業の就業禁止
- 育児時間の確保
ノーマライゼーションに基づくのはどれか。
- 救急搬送体制を整備すること
- 医療機関にいつでも受診ができること
- 公共交通機関をバリアフリー化すること
- 障害者に介護施設への入所を勧めること
日本の令和5年(2023年)の人口動態統計における悪性新生物〈腫瘍〉に関する記述で正しいのはどれか。
- 死因別順位は第2位である。
- 年間死亡者数は約80万人である。
- 部位別にみた年齢調整死亡率は、男性では胃が最も高い。
- 部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。
▶午後33
聴覚障害のある患者とのコミュニケーションで正しいのはどれか。
- 補聴器の使用中は低音で話す。
- 手話のときは口元を動かさない。
- 音の反響が強い場所を選択する。
- 感音性難聴の場合は大きな声で話す。
結核菌の消毒に効果があるのはどれか。
- エタノール
- アクリノール
- ベンザルコニウム
- クロルヘキシジン
▶午後35
四肢に障害がない患者を仰臥位から側臥位に体位変換するときの姿勢を図に示す。
適切なのはどれか。
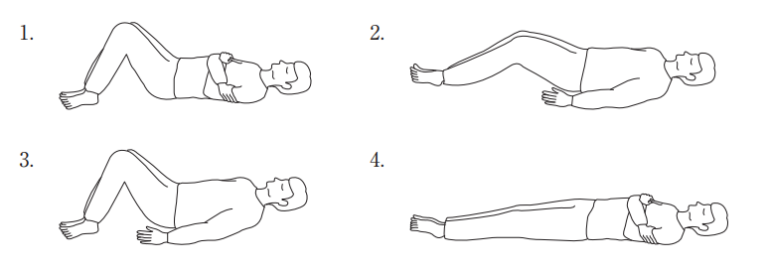
インシデントレポートについて正しいのはどれか。
- 警察への届出義務がある。
- 法令で書式が統一されている
- 事故が発生するまで報告しない。
- 異なる職種間で内容を共有する。
▶午後37
口腔ケアの効果として正しいのはどれか。
- プラークの形成
- 唾液分泌の促進
- 口腔内のpHの酸性化
- バイオフィルムの形成
▶午後38
薬とその副作用の組合せで正しいのはどれか。
- 抗ヒスタミン薬――難聴
- スルホニル尿素薬――咳嗽
- 中枢性麻薬性鎮咳薬――便秘
- アミノグリコシド系薬――骨粗鬆症
▶午後39
成人の腸骨の骨髄穿刺で適切なのはどれか。
- 穿刺前6時間は絶食とする。
- 穿刺は仰臥位で行う。
- 穿刺時は深呼吸を促す。
- 穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。
食の支援に関わる職種とその役割の組合せで適切なのはどれか。
- 歯科衛生士――義歯の作成
- 管理栄養士――経腸栄養の処方
- 言語聴覚士――嚥下機能の評価
- 薬剤師――摂食行動の評価
▶午後41
人工呼吸器による陽圧換気によって生じるのはどれか。
- 肺水腫
- 脳内出血
- 胃液分泌の低下
- 心拍出量の低下
▶午後42
手術中に下肢に弾性ストッキングを着用する主な目的はどれか。
- 浮腫の軽減
- 筋力の維持
- 体温低下の予防
- 深部静脈血栓形成の予防
▶午後43
外傷性脳損傷によって軽度記憶障害のある患者への認知リハビリテーションで適切なのはどれか。
- 簡単な計算を取り入れる。
- 毎日新しい行動を試みる。
- 暗記の練習のときはメモを取る。
- 視覚的なイメージより言葉のほうが記憶しやすい。
▶午後44
腰椎転移のある食道癌の患者。癌性疼痛にフェンタニル貼付剤を使用しているが、右下肢に神経因性疼痛が頻発している。1日に4〜6回レスキューとしてのモルヒネ注射薬を使用しており、入眠すると15秒程度の無呼吸がみられる。
緩和ケアチームで検討すべき対応はどれか。
- 酸素吸入
- 鎮痛補助薬の使用
- モルヒネ注射薬の増量
- フェンタニル貼付剤の増量
▶午後45
慢性腎不全で透析導入を判断するときの指標となる検査はどれか。
- 尿酸〈UA〉値
- 糸球体濾過値〈GFR〉
- 点滴静注腎盂造影〈DIP〉
- PSP〈フェノールスルホンフタレイン〉15分値
▶午後46
1年前にハチに刺された人が再びハチに刺された。
起こる可能性のあるアレルギー反応はどれか。
- Ⅰ型アレルギー
- Ⅱ型アレルギー
- Ⅲ型アレルギー
- Ⅳ型アレルギー
▶午後47
電動のこぎりの操作ミスで、左第2指と3指とも近位指節間〈PIP〉関節と遠位指節間〈DIP〉関節の間で切断した患者が、手指の再接着術を受けた。他に外傷はない。
術後1日の観察で適切なのはどれか。
- Volkmann〈フォルクマン〉拘縮の有無
- 中手指節〈MP〉関節の関節可動域
- 遠位部の血液循環の状態
- 接着部の瘢痕化
▶午後48
スパイロメトリーの結果による換気機能診断図を示す。
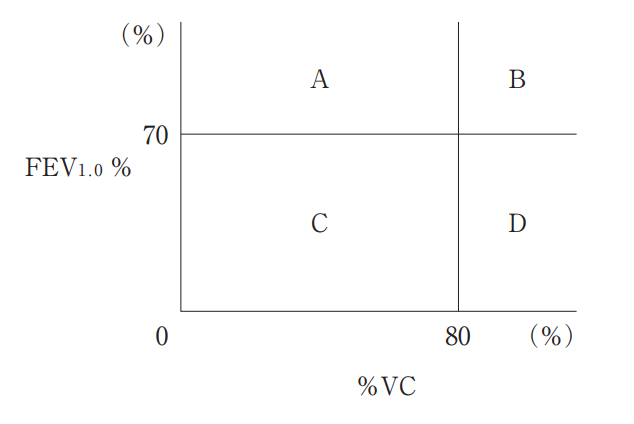
閉塞性換気障害と診断される分類はどれか。
- A
- B
- C
- D
▶午後49
精神看護に関連する理論と理論家の組合せで正しいのはどれか。
- 現存在分析――フロイト, S.
- ストレス理論――シュナイダー, K.
- 精神発達理論――オレム, D.
- 患者-看護師関係――ペプロウ, E.
▶午後50
選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉について正しいのはどれか。
- パニック障害に対する効果はない。
- 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも弱い。
- うつ状態が改善したら直ちに使用を中止する。
- 抗うつ効果の評価は投与開始後3日以内に行う。
▶午後51
リエゾン精神看護に関する説明で正しいのはどれか。
- 直接ケアは含まれない。
- 精神疾患の既往のある患者は対象とならない。
- 看護師は必要に応じて精神病床への移動を指示できる。
- 身体疾患と精神的問題とを併せ持つ患者を対象とする。
精神科病院に入院中の患者の法的処遇について正しいのはどれか。
- 患者は退院を請求できる。
- 看護師は面会を制限できる。
- 家族等は外出の可否を判断できる。
- 精神保健指定医は手紙の発信を制限できる。
▶午後53
Aさん(19歳、女性)は、境界性人格〈パーソナリティ〉障害で入院している。病棟では、安全管理のため、個人用の爪切りをナースステーションで管理している。Aさんが自分の爪切りを使用した後、看護師が返却を求めると「主治医の先生は自分で持っていてもいいって言ったのよ」と攻撃的な口調で抵抗した。この日、主治医は不在であった。
Aさんへの対応として最も適切なのはどれか。
- 「先生はそのようなことは言わないと思います」
- 「先生は不在なので、私の指示に従ってください」
- 「病棟の安全が守れないので退院していただきます」
- 「先生に確認がとれるまで、こちらでお預かりします」
▶午後54
Aさん(78歳)は、妻(76歳)と2人で暮らしている。糖尿病と診断されている。認知症ではない。主治医の指示で、インスリン自己注射を指導するために訪問看護が導入された。Aさんは「針が怖いから、看護師さんが注射をしてください」と言う。
Aさんへの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。
- 「針は細いので怖くないです」
- 「一緒に少しずつやっていきましょう」
- 「注射ができないと家での療養は難しくなります」
- 「そうですね。Aさんも奥さんもしなくていいです」
介護保険法施行令において特定疾病に指定されているのはどれか。
- 脊髄損傷
- Crohn〈クローン〉病
- 脳血管疾患
- 大腿骨頸部骨折
▶午後56
Aさん(68歳)は要介護1で、1人で暮らしている。間質性肺炎のために在宅酸素療法が開始された。
Aさんのサービス担当者会議で訪問看護師が行う提案で適切なのはどれか。
- 炊事の禁止
- 毎日の体温測定
- 1人での外出禁止
- 訪問入浴サービスの導入
▶午後57
Aさんは、要介護2で在宅療養をしている。仙骨部に2cm×3cmの水疱を形成した。この1週間、臥床していることが多くなり、食事摂取量も減ってきている。
訪問看護師がAさんの家族に行う提案として適切なのはどれか。
- 体圧分散マットの使用
- 膀胱留置カテーテルの留置
- 夜間の時間ごとの体位変換
- 訪問介護への褥瘡処置の依頼
▶午後58
高齢者から生活史を聴取する方法として適切なのはどれか。
- 家族の承諾を必須とする。
- 認知機能の評価尺度を用いる。
- 事実とは異なる部分を修正する。
- 高齢者自身の生きてきた時代背景を聴く。
平成3年(1991年)に国際連合総会〈国連総会〉で決議された「高齢者のための国連原則」でないのはどれか。
- 公平の原則
- 参加の原則
- 尊厳の原則
- 自己実現の原則
▶午後60
介護老人福祉施設に入居中の高齢者。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、四肢の麻痺はない。
衣類の選択について最も適切なのはどれか。
- 材質選びは本人に任せる。
- ボタンでとめる上着を選ぶ。
- 夜間就寝時には寝衣に着替える。
- 皮膚の瘙痒感があれば、つなぎ服を着用させる。
▶午後61
Aさん(80歳、女性)は、脳血管性認知症、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点で施設に入所している。看護師が「お風呂に入りますよ」と声をかけると、Aさんは「男の人は入っていないか」と尋ねる。看護師が「男の人はいませんよ」と説明するが、Aさんは「本当にいないのか」と繰り返し、なかなか納得しない。
Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。
- 「男の人はいないから行きましょう」
- 「お風呂に入ったら気持ちよくなりますよ」
- 「遅くなるとお風呂に入れなくなりますよ」
- 「男の人がいないことを一緒に確認してみましょうか」
▶午後62
加齢による身体生理機能の変化とそれによって影響を受ける薬物動態の組合せで正しいのはどれか。
- 体内水分量の減少――代謝
- 体内脂肪量の増加――排泄
- 血清アルブミンの減少――分布
- 糸球体濾過値〈GFR〉の低下――吸収
介護保険サービスについて正しいのはどれか。
- 福祉用具の貸与は無償で受けられる。
- 要支援の高齢者は介護老人保健施設に入所できる。
- 小規模多機能型居宅介護では泊まり(ショートステイ)は提供しない。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。
乳児健康診査を規定している法律はどれか。
- 母体保護法
- 母子保健法
- 児童福祉法
- 児童虐待の防止等に関する法律
▶午後65
正常に経過している分娩第1期の産婦への説明で適切なのはどれか。
- 「食事は摂らないようにしてください」
- 「ベッド上で安静にしていてください」
- 「2、3時間に1回は排尿をしてください」
- 「眠気を感じても眠らないようにしてください」
▶午後67
Aさんは妊娠37週0日に骨盤位のため予定帝王切開術となった。術後の経過は母児ともに順調である。
Aさんへの看護として適切なのはどれか。
- 手術室で出生児と対面する。
- 産褥2日に初回歩行をする。
- 産褥3日に初回授乳をする。
- 産褥4日以降に弾性ストッキングを履く。
▶午後68
子どもの運動機能の発達について正しいのはどれか。
- 身体の下部から頭部の方向に進む。
- 全身的な動きから細かな動きへ進む。
- 新生児期には遺伝より環境の影響を受ける。
- 反射運動は乳児期後期から幼児期にかけて活発になる。
▶午後69
乳児の事故防止として正しいのはどれか。
- 直径25mmの玩具で遊ばせる。
- ベッドにいるときはベッド柵を上げる。
- うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。
- 屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。
▶午後70
A君(14歳、男子)は、心室中隔欠損症のために通院している。母親とともに外来を受診しているが、母親がトイレに行った際に、A君は「自分の心臓のことはよく理解しているし、もう1人で受診したいけど、母さんが心配だから一緒に行くってうるさくて」と看護師に話した。
看護師の最初の対応として適切なのはどれか。
- 母親にA君への関わりが過保護だと伝える。
- 母親の心配を理解してあげなさいとA君に話す。
- 次回からは1人で受診してもよいとA君に話す。
- 母親がいない場でA君の気持ちを聴く機会をもつ。
▶午後71
A君(11歳、男児)。喘息発作のため救急外来に来院した。喘鳴が著明で、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%(room air)、ピークフロー値45%である。
まず行うべきA君への対応で適切なのはどれか。
- 起坐位を保つ。
- 水分摂取を促す。
- 胸式呼吸を促す。
- 発作の状況を尋ねる。
水溶性ビタミンはどれか。
- ビタミンA
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビタミンK
▶午後73
血清に含まれないのはどれか。
- インスリン
- アルブミン
- γ-グロブリン
- β-グロブリン
- フィブリノゲン
▶午後74
出血が止まりにくくなる服用薬はどれか。
- β遮断薬
- ジギタリス
- ワルファリン
- ループ利尿薬
- サイアザイド系利尿薬
▶午後75
老視の原因はどれか。
- 瞳孔括約筋の筋力低下
- 水晶体の弾力低下
- 網膜の色素変性
- 硝子体の混濁
- 水晶体の混濁
▶午後76
脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。
- 心房細動
- WPW症候群
- 心房性期外収縮
- 心室性期外収縮
- 完全房室ブロック
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉が感染する細胞はどれか。
- 好中球
- 形質細胞
- Bリンパ球
- ヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球
- 細胞傷害性〈CD8陽性〉Tリンパ球
生活保護法で扶助として定められていないのはどれか。
- 教育
- 医療
- 授産
- 住宅
- 葬祭
▶午後79
内服薬の初回通過効果が主に起こる部位はどれか。
- 口
- 肝臓
- 胆囊
- 膵臓
- 腎臓
放射線被ばく後、新たな発症について長期の観察が必要な障害はどれか。
- 胃炎
- 食道炎
- 甲状腺癌
- 高尿酸血症
- 皮膚のびらん
▶午後81
副交感神経の作用はどれか。2つ選べ。
- 瞳孔の散大
- 発汗の促進
- 心拍数の低下
- 気管支の拡張
- 消化液の分泌亢進
▶午後82
小腸からそのまま吸収されるのはどれか。2つ選べ。
- グルコース
- スクロース
- マルトース
- ラクトース
- フルクトース
▶午後83
鉄欠乏性貧血の症状または所見として考えられるのはどれか。2つ選べ。
- 動悸
- 匙状爪
- ほてり感
- 運動失調
- 皮膚の紅潮
▶午後84
大腸内視鏡検査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 検査前日の朝から絶食とする。
- 腸管洗浄液は6時間かけて内服する。
- 迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。
- 検査後に嚥下障害を生じる可能性がある。
- 検査後に下血の有無を観察する。
▶午後85
意識障害はどれか。2つ選べ。
- 昏睡
- 制止
- せん妄
- 途絶
- フラッシュバック
▶午後86
加齢によって高齢者に脱水が起こりやすくなる理由はどれか。2つ選べ。
- 骨量の減少
- 筋肉量の減少
- 末梢血管抵抗の増強
- 渇中枢の感受性の低下
- 腎臓のナトリウム保持機能の亢進
▶午後87
妊娠の成立について正しいのはどれか。2つ選べ。
- プロラクチンの急増によって排卵が促される。
- 排卵後、卵子が受精能を有するのは通常24時間である。
- 射精後、精子が受精能を有するのは通常80時間である。
- 着床は受精後7日前後である。
- 受精後、プロゲステロンの分泌がなくなる。
▶午後88
乳児の心拍測定について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 心拍数110/分は正常である。
- 聴診ではⅠ音とⅡ音で心拍となる。
- バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。
- 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。
- 聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。
身長160cm、体重64kgである成人のBMIを求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:① ②
▶午後90
酸素を3L/分で吸入している患者。移送時に使用する500L酸素ボンベ(14.7MPa充塡)の内圧計は4.4MPaを示している。
使用可能時間(分)を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②分
資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第102回看護師国家試験